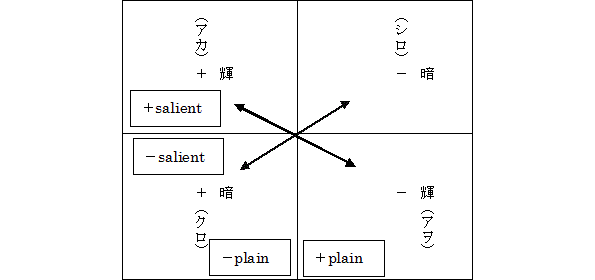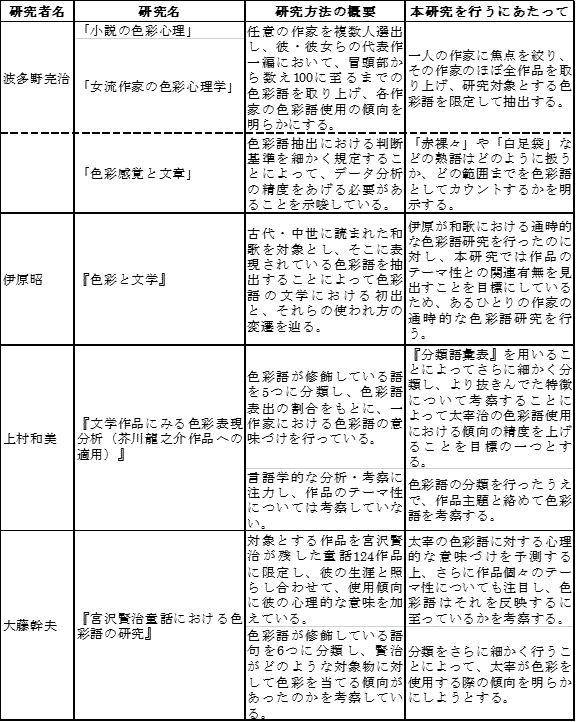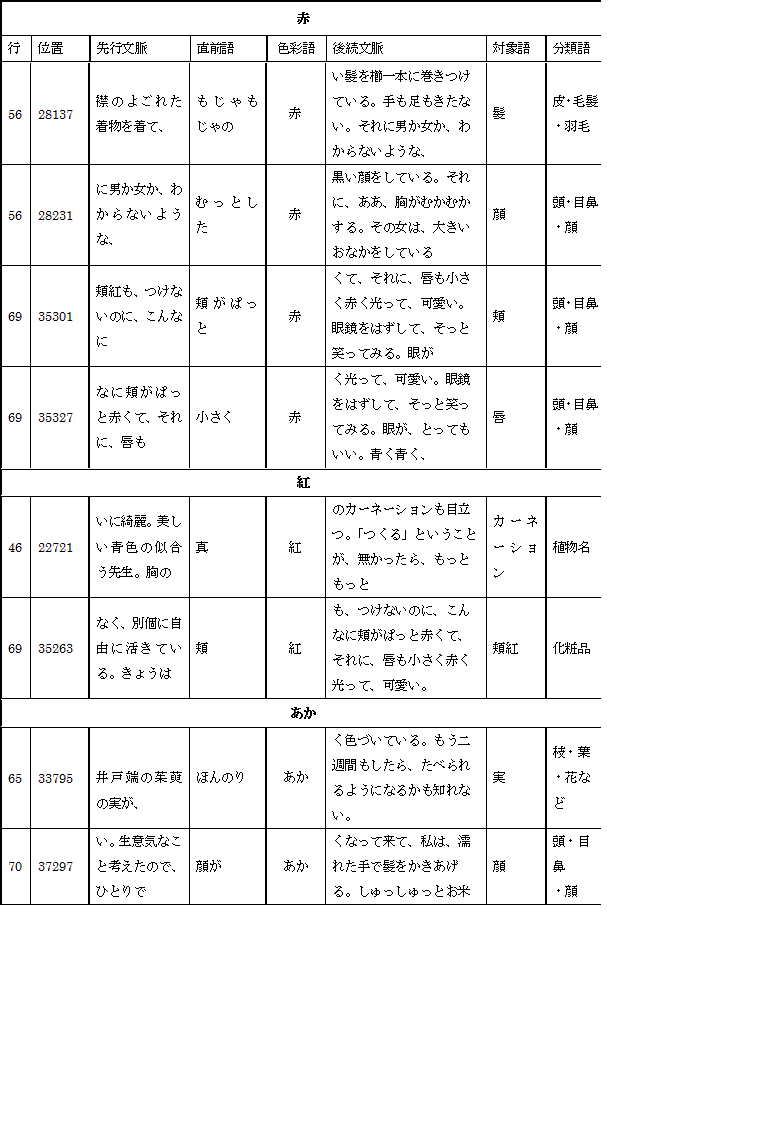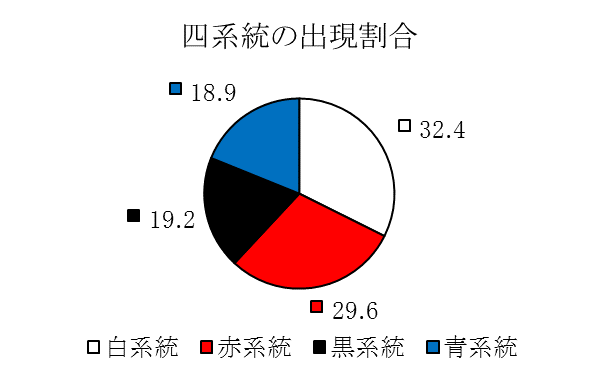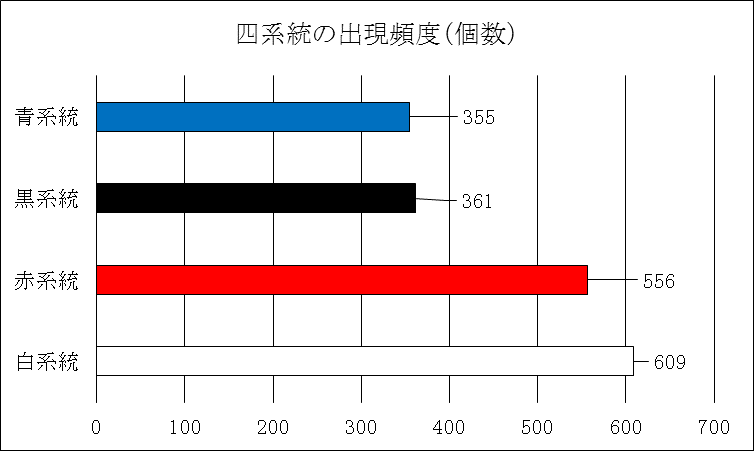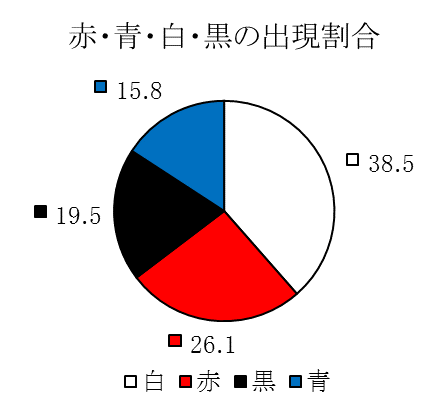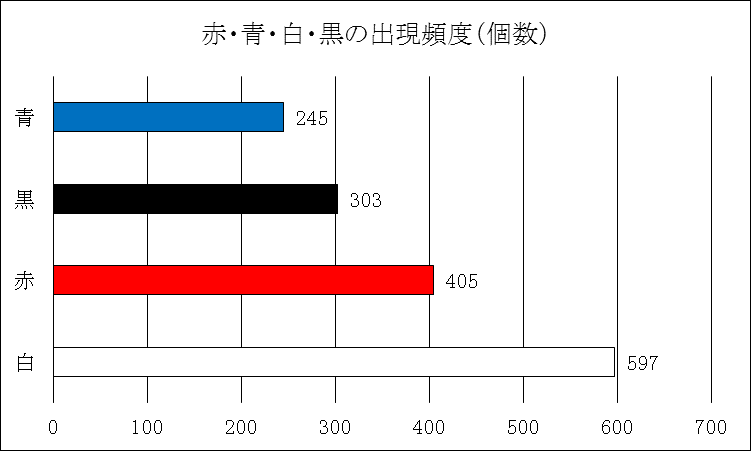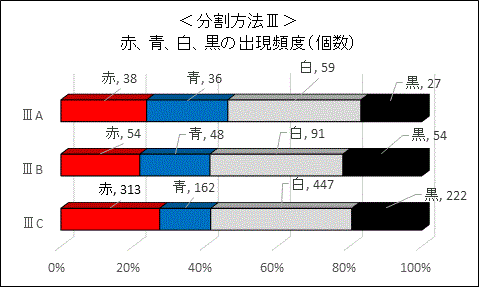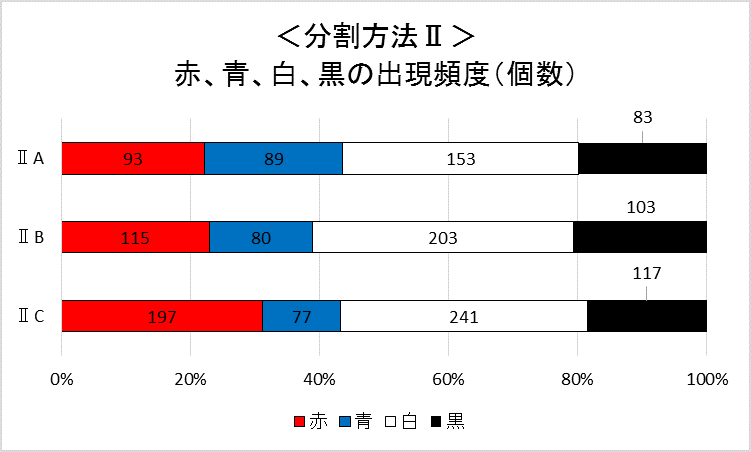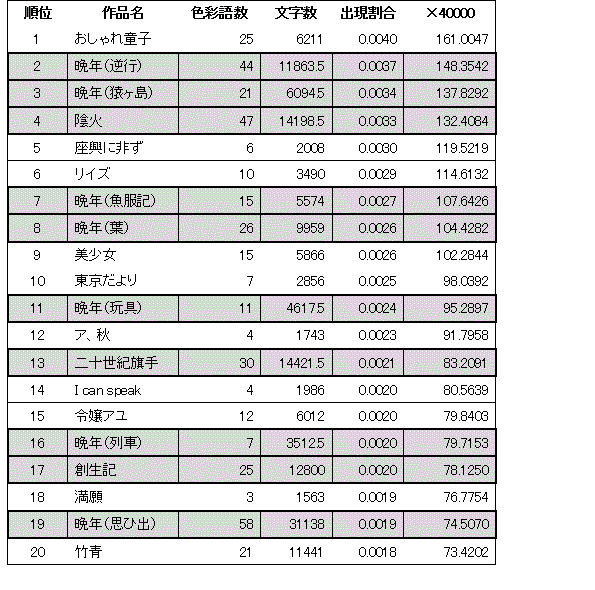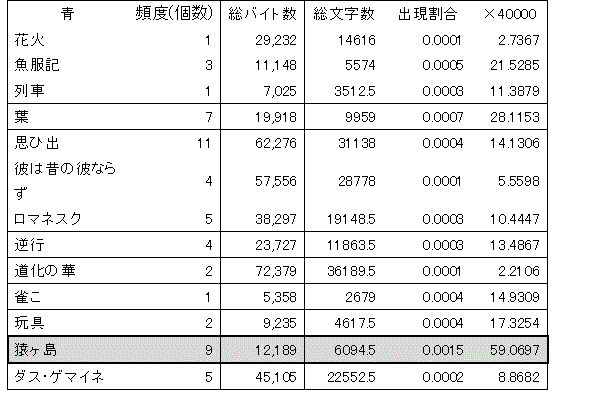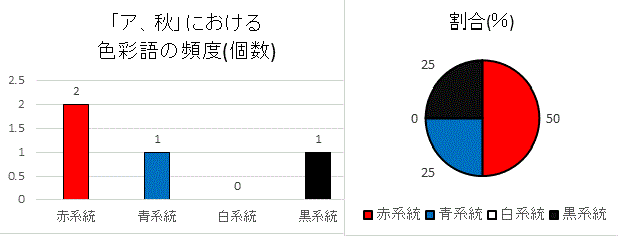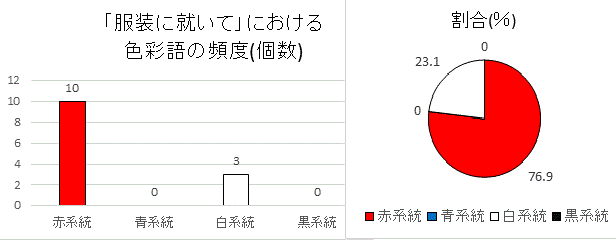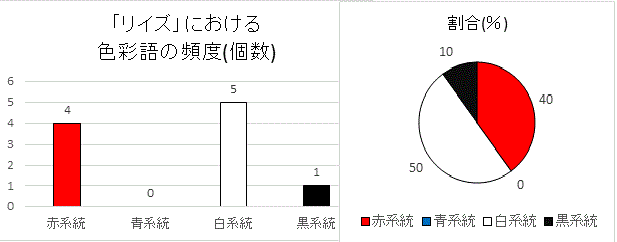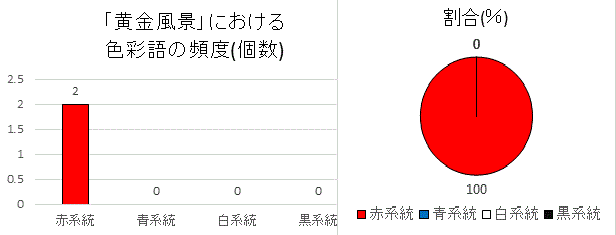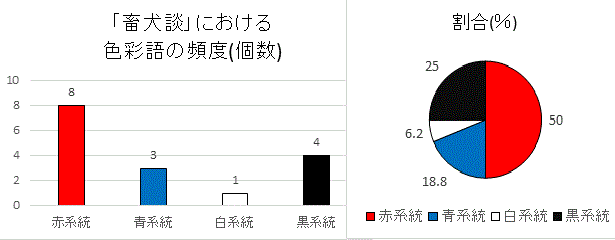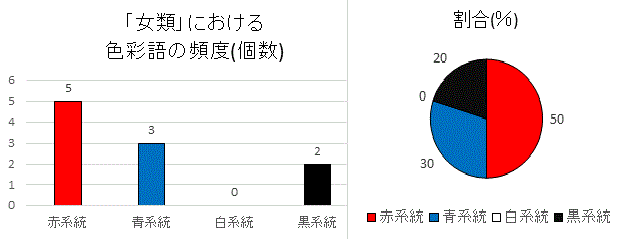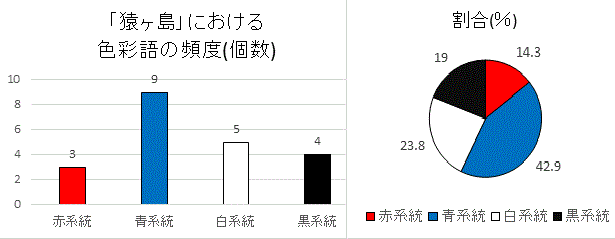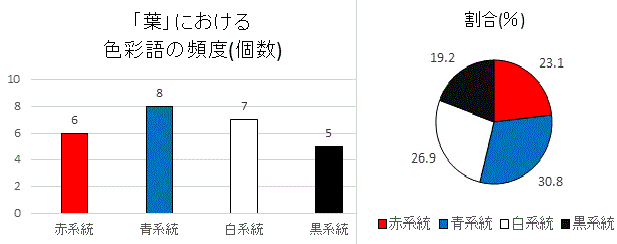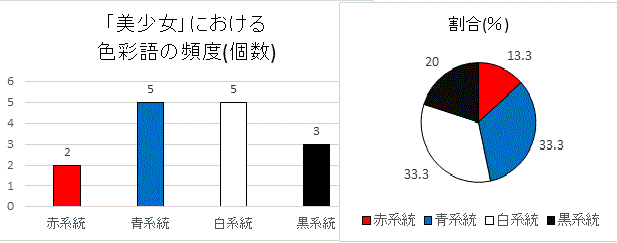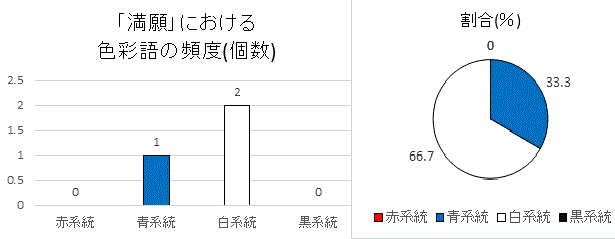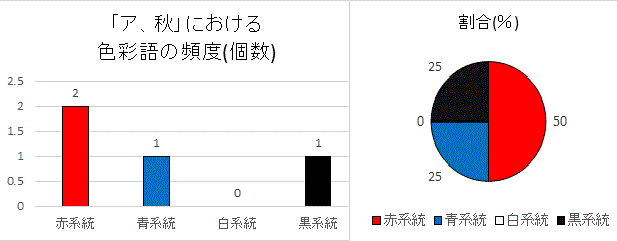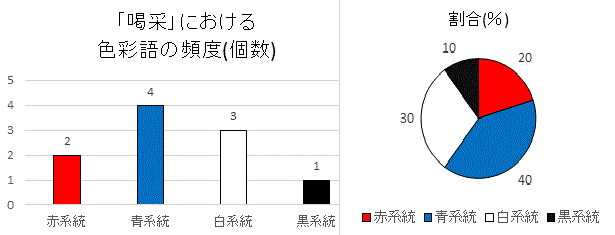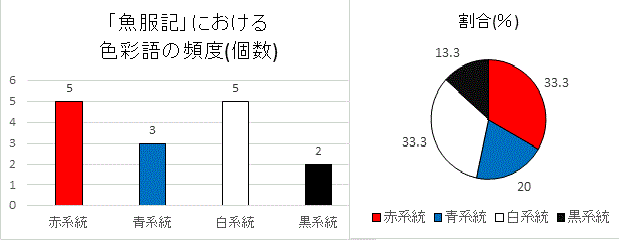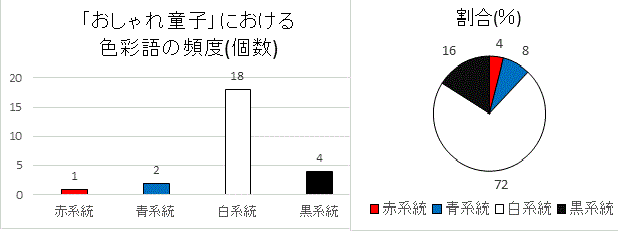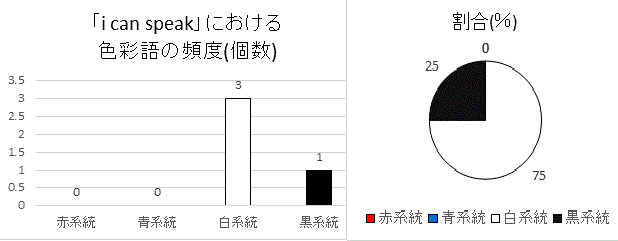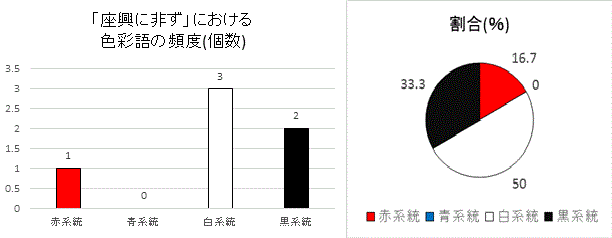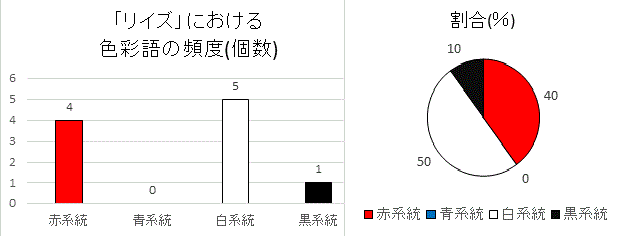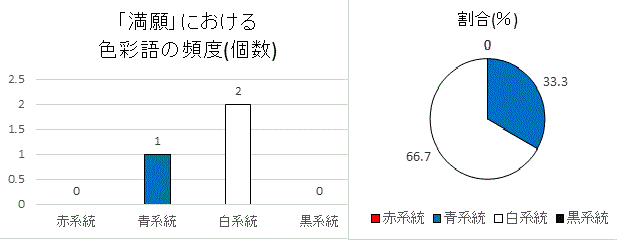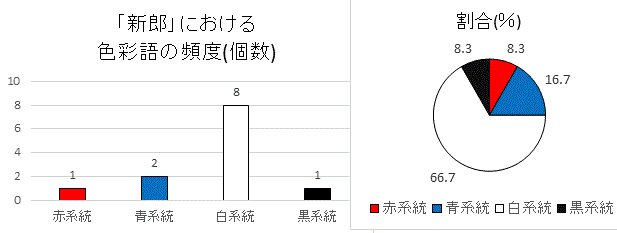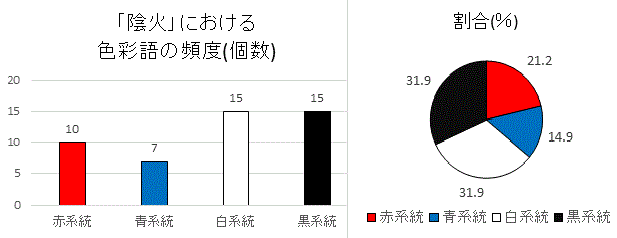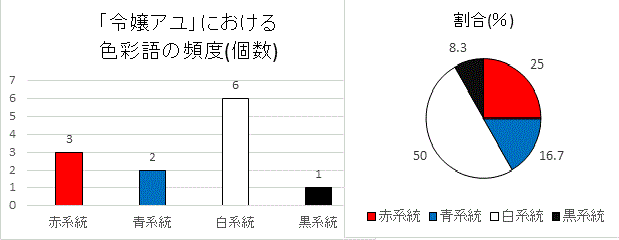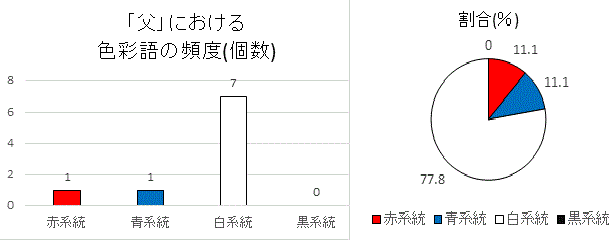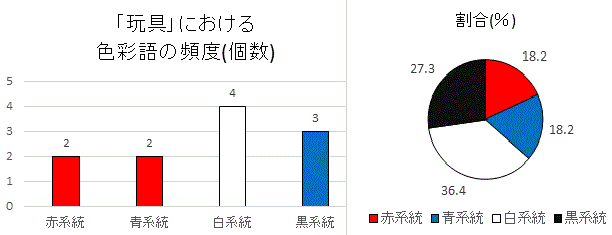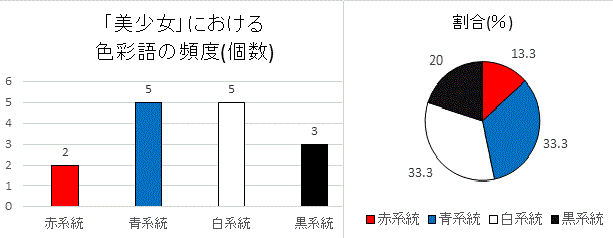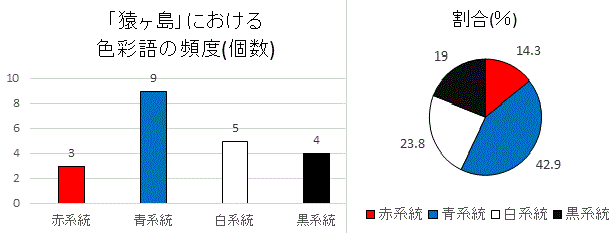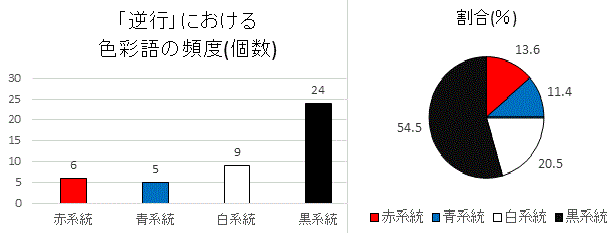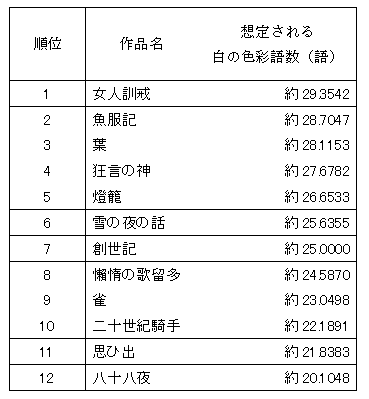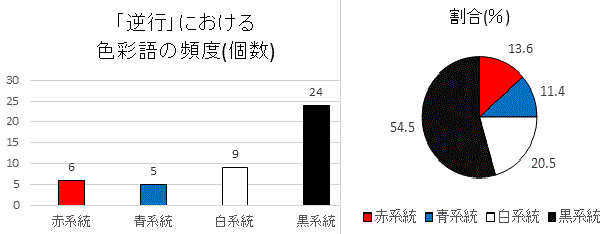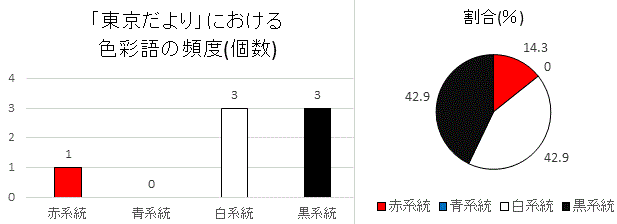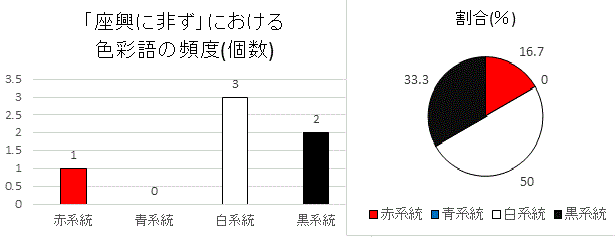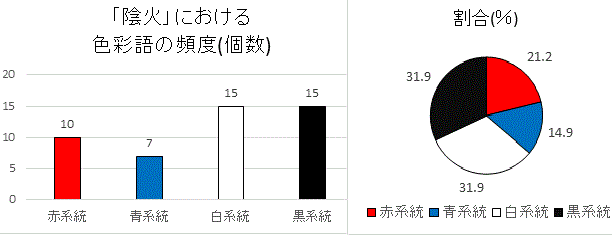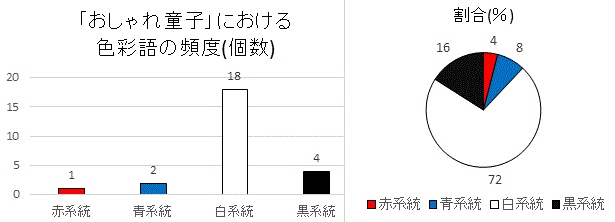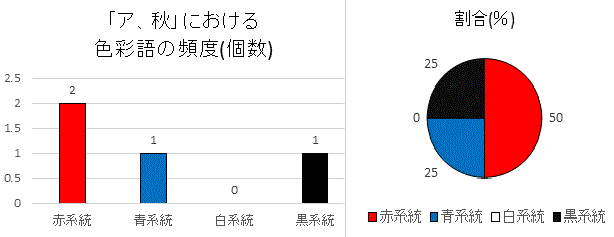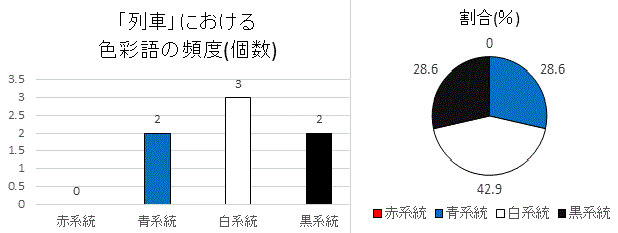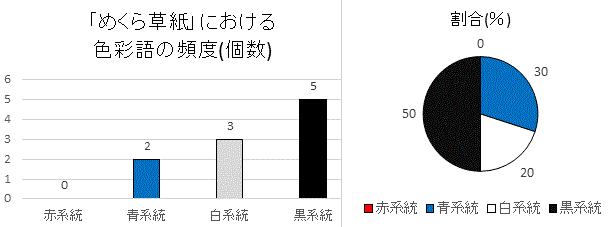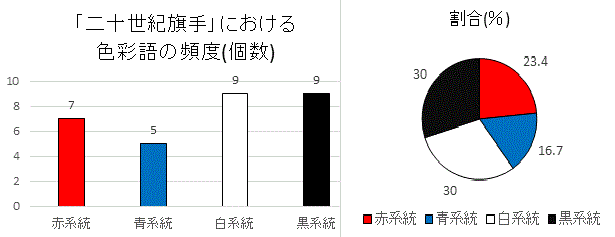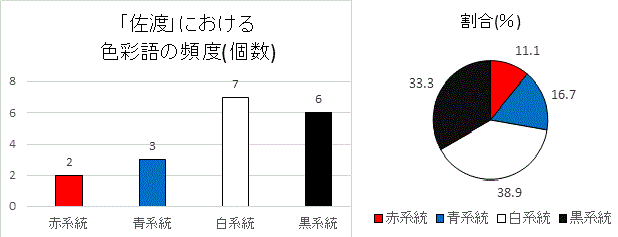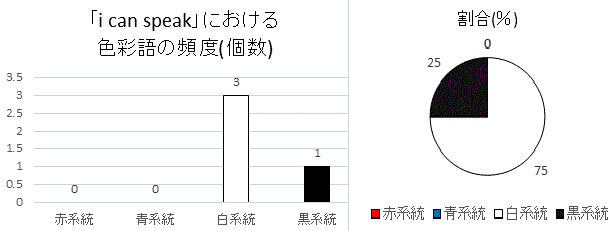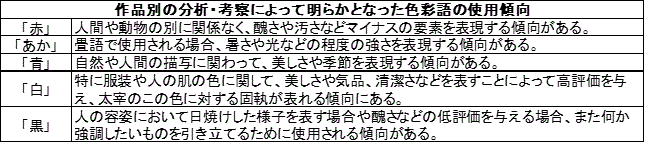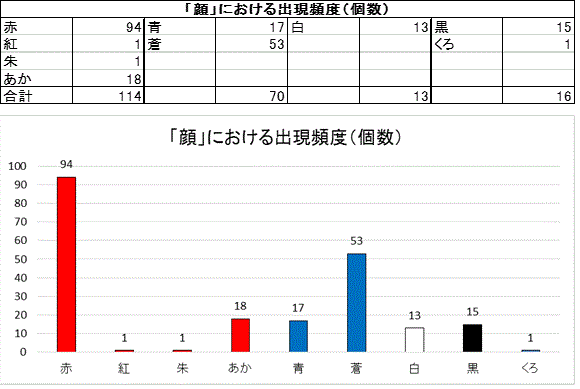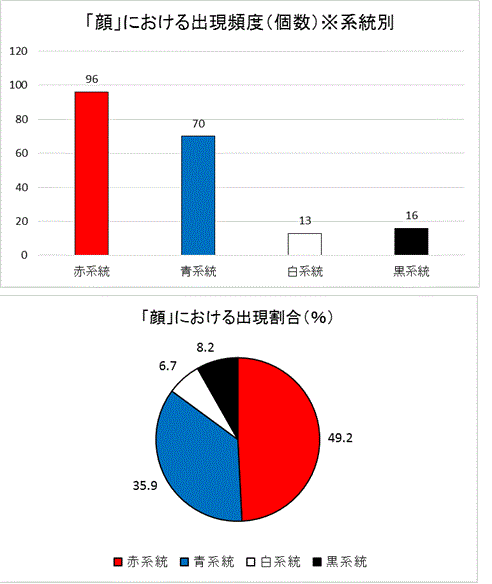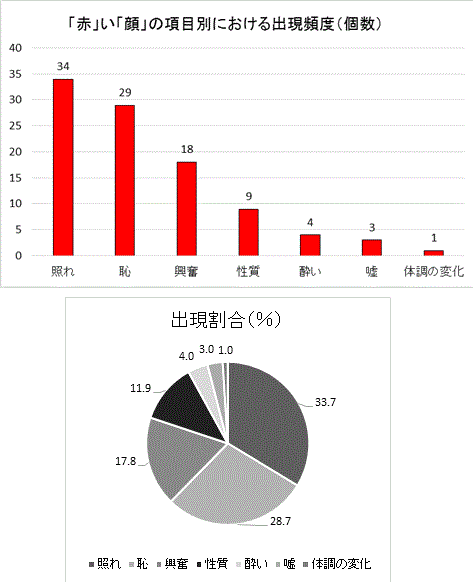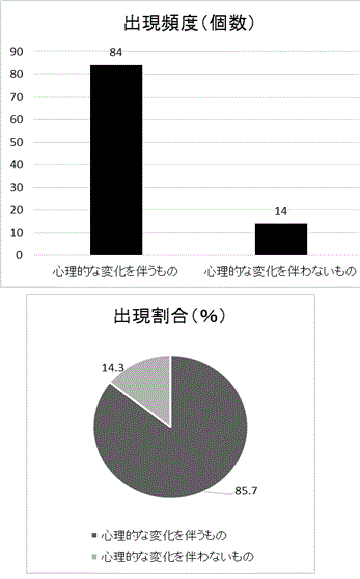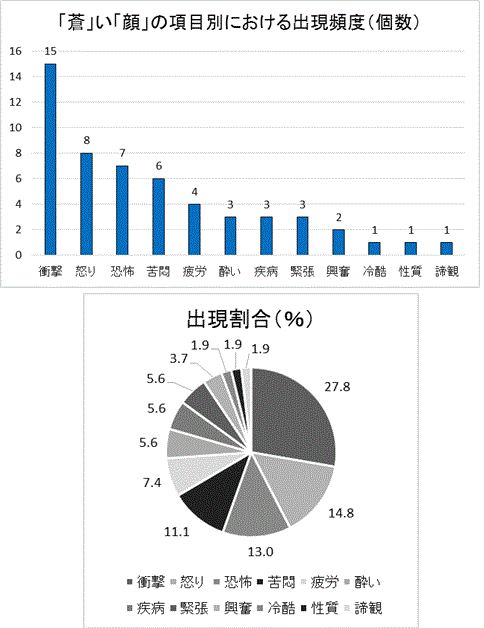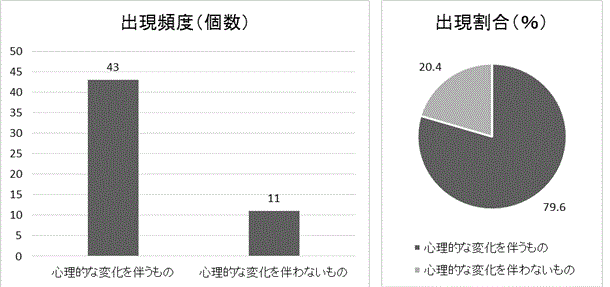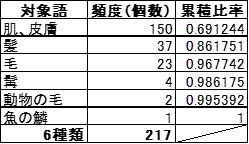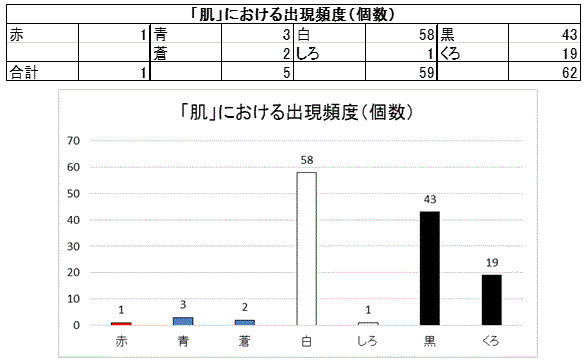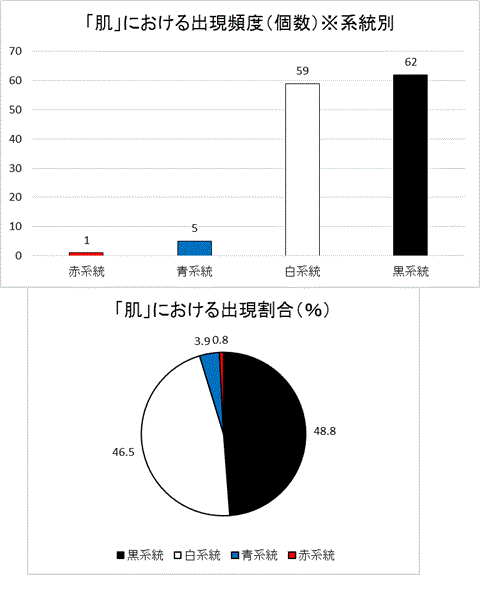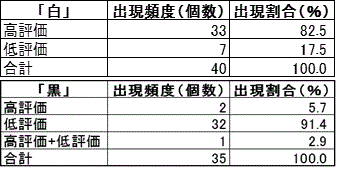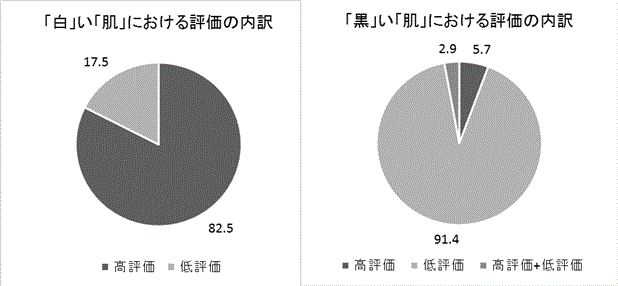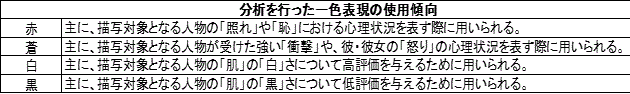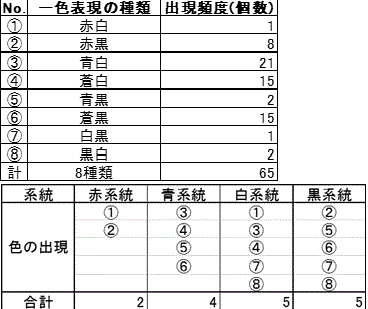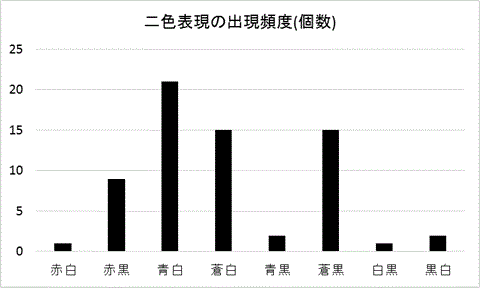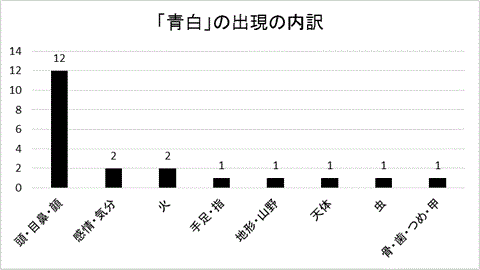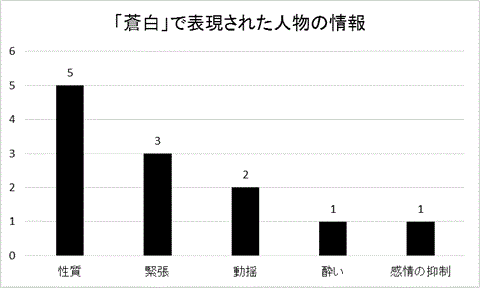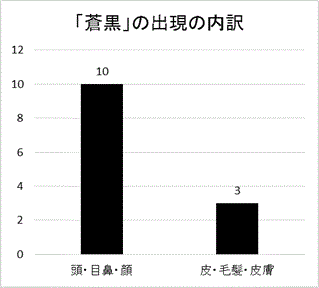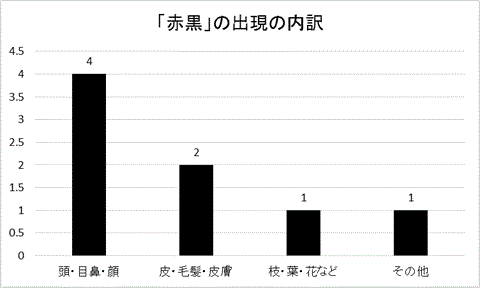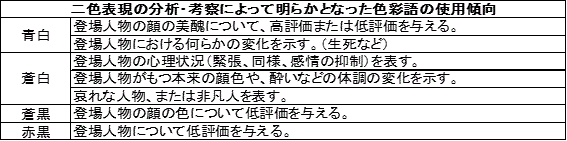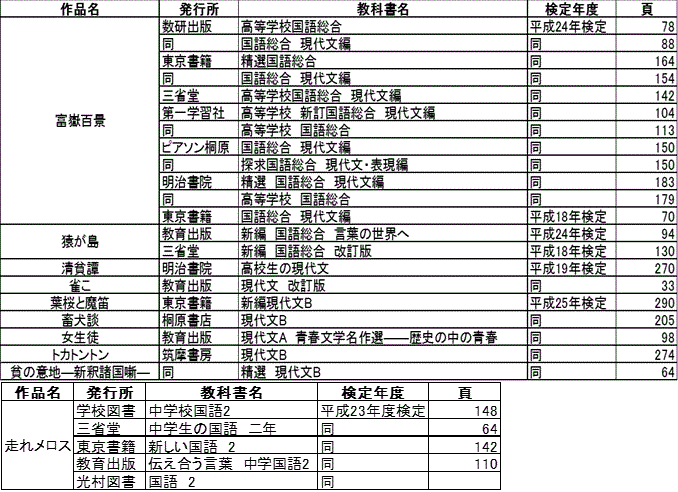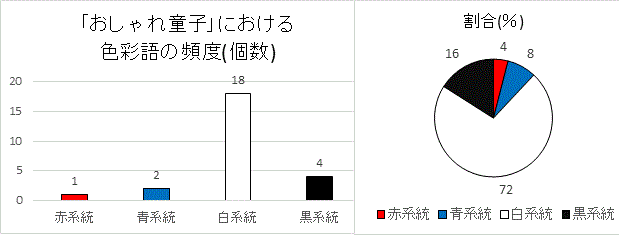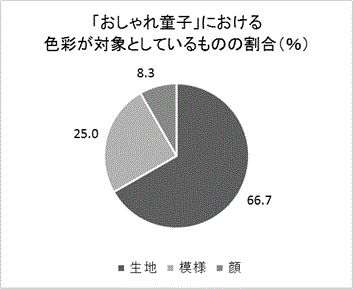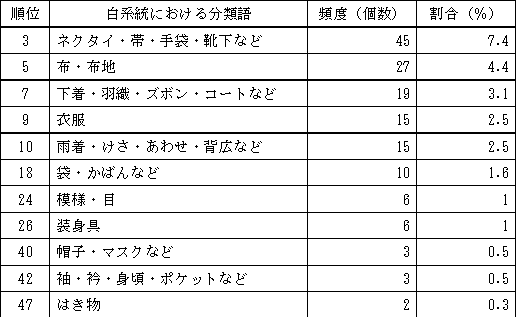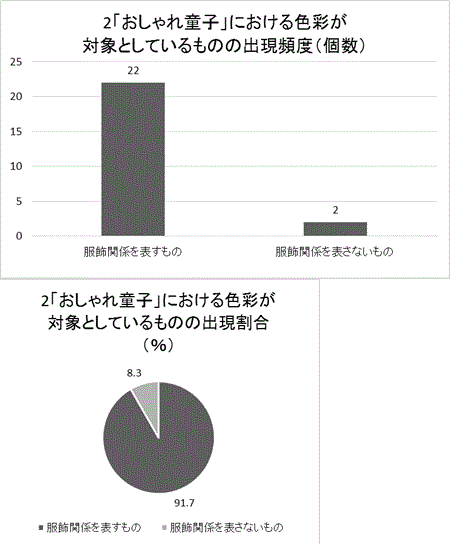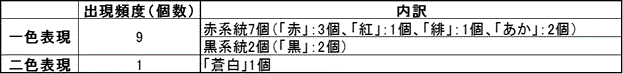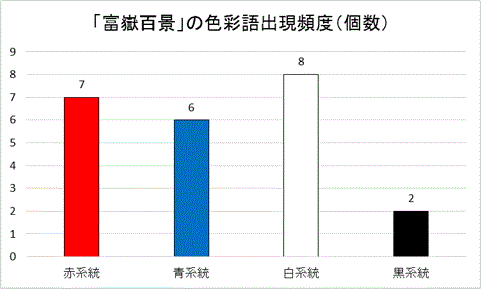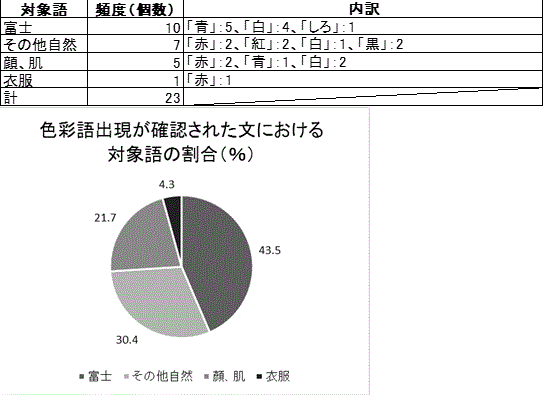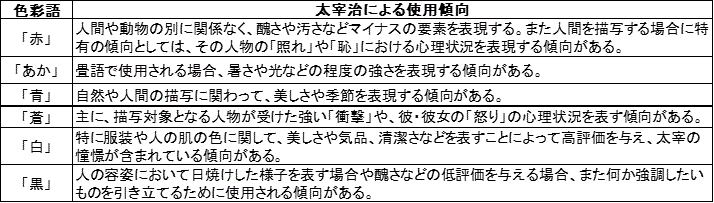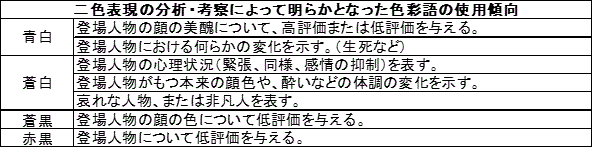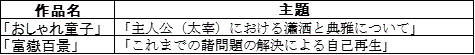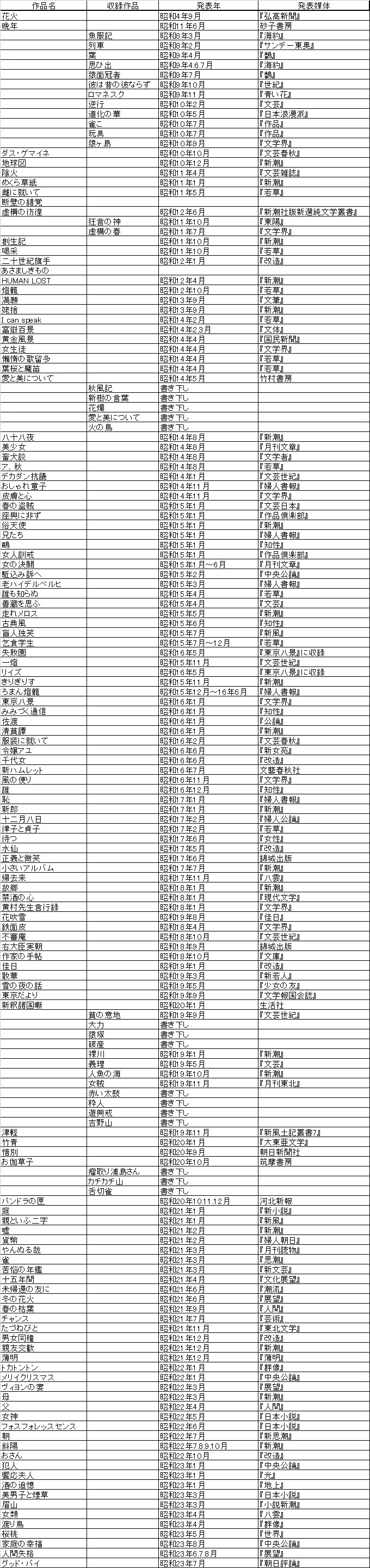平成26年度 修士論文 提出日:平成27年1月14日
平成26年度 修士論文
太宰治作品における色彩語の研究
指導教員 野浪正隆先生
目次
↑目次へ
はじめに
本修士論文は「文学作品における色彩語表現―太宰治作品を用いて―」と題目を設定し、文章表現中における色彩語の表現特性を研究するものである。文学作品の中でも小説に焦点化して分析・考察を行うことにより、色彩語が小説を解釈する上で有効な手段の一つとなりえるかを明らかにする。
↑目次へ
序章 研究課題と研究目的
本研究の目的は、文学作品の中でも小説に注目し、そこに確認される色彩語の出現、またその出現の様相について分析・考察を行うとともに、色彩語の観点が作品を解釈する方法として機能するのか否かを明らかにすることである。研究対象とする作品をひとつひとつ取り上げ、指定した色彩語を抽出し、それらを分析・考察するとともに作品主題と比較することによって、色彩語が作品主題を構築する役割の一端を担うものとして機能しているのかをみていく。これに関して執筆者は、現段階では作品主題と色彩語の関係を読み取ることが、色彩語を用いて作者が作り上げた作品世界を読み取る(解釈する)ことにつながると考えている。
↑目次へ
第一章 先行研究
先にも述べたように、これまでの色彩語に関する研究は依然模索段階であると考えられる。この章では、これまでの研究がどのような変遷を辿って来たのかを実際の研究法を例にとりながら整理していく。第一節 波多野完治における色彩語の研究
波多野の色彩語研究は、後の研究の基盤となるものであり、「文学作品における色彩語」という研究の着眼点を広く示したという点で大きく貢献している。
作家名 存命期間 作品名 作品発表年 田山花袋 1871-1930(明治4-昭和5) 『田舎教師』 明治42 島崎藤村 1872-1943(明治5-昭和18) 『破戒』 明治39 夏目漱石 1867-1916(慶応3-大正5) 『門』 明治43 志賀直哉 1883-1971(明治16-昭和46) 『暗夜行路』 大正10 谷崎潤一郎 1886-1965(明治19-昭和40) 『細雪』 昭和18 川端康成 1899-1972(明治37-昭和28) 『雪国』 昭和10 堀辰雄 1904-1953(明治37-昭和28) 短編 作品不特定のため未定 井上靖 1907-1991(明治40-平成3) 『氷壁』 昭和32
作家名 存命期間 作品名 作品発表年 野上弥生子 1903-1951(明治36-昭和26) 『真知子』 昭和5 岡本かの子 1889-1939(明治22-昭和14) 『母子叙情』 昭和12 林芙美子 1885-1985(明治18-昭和60) 『放浪記』 昭和5 宇野千代 1883-1971(明治30-平成8) 『色ざんげ』 昭和10 宮本百合子 1899-1951(明治32-昭和26) 『伸子』 大正15
↑目次へ
第二節 伊原昭における色彩語の研究
では次に、伊原昭の色彩語研究について取り上げる。
↑目次へ
第三節 上村和美における色彩語の研究
次に上村和美の『文学作品にみる色彩表現分析(芥川龍之介作品への適用)』(双文社 平成11年)について、その研究方法を考察する。彼女は「芥川の小説149編のテキストデータベースを使用し、その中から、色彩表現を抽出し、芥川の色彩観を数量的に考察し」ている。(―上村和美『文学作品にみる色彩表現分析』31頁―)なお、彼女の研究方法の手順は本研究方法に一番近しいものである。
↑目次へ
第四節 大藤幹夫における色彩語の研究
最後に、大藤幹夫の研究について取り上げる。大藤は、宮沢賢治の童話を研究対象として色彩語研究を行った人物である。彼はそれまで色彩語研究があまり着手されていなかった原因として、文学は作家の主観的表現の上に成り立っており、それを形式的に数量化すれば必ず諸々の問題が生じる可能性が高いということ、また研究者の主観的判断に委ねなければならない部分が往々にして存在すること、最後に研究方法の違いによって全く異なった結果が現れる場合があることを挙げている。この研究方法の違いに関しては本研究でも丁寧に扱わなければならない項目である。大藤は波多野完治の研究と安本美典の研究を例に挙げ、色彩語研究が抱える問題点について以下のように論を進めている。
↑目次へ
第二章 研究概要
第一節 研究対象
第一項 対象とする色彩語
ここでは色彩語の定義づけを行うとともに、対象とする色彩語の限定について述べる。
↑目次へ
第二項 太宰治略歴
今回扱う研究対象は太宰治作品である。以下に、彼の略歴を整理して述べることとする。なお、これは太宰の執筆活動期間を前期・中期・後期で分割する方法や作品主題の分析等に影響すると考えられる事柄をおもに注目しながら取り上げたものである。
↑目次へ
第三項 対象作品
本研究において研究対象とする具体的な太宰治の作品名は、本論の後に付することとする。作品数は154作品である。
↑目次へ
第二節 研究方法
研究方法は、上記に挙げた作品をそれぞれテキストデータ化し、KWIC Finderを使用することで各色における出現を確認した。このソフトは検索ワードを指定し、検索を行うとテキストデータ内すべてからその語を抽出することが可能になるものである。次にその中から色彩を表していないと考えてよい結果を取り除き、各色にデータをまとめることで分析を行っている。なお、ここでいう「色彩を表していないと考えてよい結果」とは人物名や地名、その他の語を指し、例としては「黒田先生」(「正義と微笑」)、「青森」(「トカトントン」)、「赤ちゃん」(「雪の夜の話」)「面白い」(「パンドラの匣」)などが挙げられる。なお「白足袋」など色彩と名詞(物)が合わさったものについては、分析の対象として適宜処理した。また、「青白」や「赤黒」などのこれら四色のうちいずれかが混ざった表現については、それぞれ「青」と「白」、「赤」と「黒」に分割して抽出したものと、「青白」や「赤黒」として抽出したものの双方を用意した。考察には「赤」のように単色で出現したものを「一色表現」と呼称し、「赤黒」など色彩が複数同時に使用されて出現したものを「二色表現」と呼称している。先に挙げた柴田武は「あかぐろい」などという形容の仕方は存在しないと述べているが、本研究では太宰が実際に使用している箇所が見られため、あくまでも基本色名四色を限定する際に彼の論を支持したのであって、色彩語の分析としては加えていることをここで明言しておく。
↑目次へ
第三章 色彩語分析結果
第一節 色彩語の出現頻度(個数)と割合(%)
第一項 全体傾向
ここでは本研究において対象とした全154作品の、それぞれ四系統(赤系統、青系統、白系統、黒系統)における全体の出現の割合を考察する。以下は先述した抽出の注意点に従って色彩語として認めたものの結果である。
頻度(個数) 割合(%) 白系統 609 32.4 赤系統 556 29.6 黒系統 361 19.2 青系統 355 18.9 合計 1881 約100
頻度(個数) 割合(%) 白 597 38.5 赤 405 26.1 黒 303 19.5 青 245 15.8 合計 1550 約100 第二項 三つの分割方法による分析
<分割方法Ⅰ> 前期・中期・後期について
自殺年 実年齢 同伴女性 場所 備考 1929(昭和4)年 20歳 町の娘 郊外 カルモチン自殺(両者未遂) 1930(昭和5)年 21歳 田辺シメ子 鎌倉 薬物心中(田辺のみ死亡) 1935(昭和10)年 25歳 なし 鎌倉 縊首(未遂) 1937(昭和12)年 28歳 小山初代 群馬 カルモチン自殺(両者未遂) 1948(昭和23)年 39歳 山崎富栄 玉川 入水(両者完遂) 作品数 バイト数 総文字数 色彩語数 ⅠA 27 769,779 384,889.5 553 ⅠB 89 3,053,508 1,526,754.0 1,052 ⅠC 38 1,204,746 602,373.0 276 合計 154 5,028,033 2,514,016.5 1,881 一作品当たりの色彩語数 ⅠA 20.5 ⅠB 11.8 ⅠC 7.3 全作品 12.2 色彩語一語当たりの必要文字数 ⅠA 602.3 ⅠB 1,409.7 ⅠC 2,128.5 全作品 1,253.9 作品数 バイト数 総文字数 色彩語数 ⅡA 26 757,773 378,886.5 543 ⅡB 50 1,473,829 736,914.5 595 ⅡC 78 2,796,431 1,398,215.5 743 合計 154 5,028,033 2,514,016.5 1,881 一作品当たりの色彩語数 ⅡA 20.9 ⅡB 11.9 ⅡC 9.5 全作品 12.2 色彩語一語当たりの必要文字数 ⅡA 602.4 ⅡB 1,198.2 ⅡC 1,837.3 全作品 1,253.9 作品数 バイト数 総文字数 色彩語数 ⅢA 9 279,213 139,606.5 222 ⅢB 16 453,015 226,507.5 309 ⅢC 129 4,295,805 2,147,902.5 1,350 合計 154 5,028,033 2,514,016.5 1,881 一作品当たりの色彩語数 ⅢA 24.7 ⅢB 19.3 ⅢC 10.5 全作品 12.2 色彩語一語当たりの必要文字数 ⅢA 502.9 ⅢB 649.0 ⅢC 1,547.5 全作品 1,253.9 第三項 四系統において色彩語が見られなかった作品の分析・考察
今回研究対象とした154作品の内、色彩語が見られなかった作品は「あさましきもの」「誰も知らぬ」「一燈」「庭」「やんぬる哉」「苦悩の年鑑」の6作品であった。これは全作品中約4.5%を占めるものである。またこの6作品の総バイト数は59,120バイトであり、全体のバイト数5,028,033からその割合を求めると約1.2%でしかないことがわかった。バイト数は文字数の二倍として反映しているから、これは文字数に関しても同様のことがいえる。
第二節 太宰治作品における色彩語の意味づけ
第一項 系統別にみる色彩語の出現傾向
↑目次へ
第二項 分類語からみる一色表現の傾向と意味づけ
ここでは「第二章 研究概要」の「第二節 研究方法」で述べた操作と同様、各色が修飾している語を、『分類語彙表』(国立国語研究所)を用いて分類したものを扱う。(以下「分類語」と呼称する。)これに関して何度その分類語が出現したかを算出し(頻度(個数))、その累積比率(%)等を求めることによってその傾向をみていく。なお、以降「対象語」と呼称しているものは、色彩語が文脈上修飾していると判断できる被修飾語を指す。また「分類語」と呼称しているものは、前述したとおり『分類語彙表』(国立国語研究所)を参考にし、分類のための見出しとして使用した語を指す。よって本論では、「分類語」は「対象語」の上位語として捉えることができる。
↑目次へ
第三項 二色表現の出現傾向と意味づけ
これまでは一色表現の色彩傾向を分析し、考察を行った。ここでは2つの色が組み合わされて出現しているものを「二色表現」と呼称し、それらの使用傾向について考察したい。
本論で対象とした色彩は赤系統・青系統・白系統・黒系統である。これらに含まれる色彩語を組み合わせ、対象とした全作品に検索をかけて出現を確認したところ、赤系統と白系統、赤系統と黒系統、青系統と白系統、青系統と黒系統、白系統と黒系統の二色表現の色彩が8種類見つかった。以下はその結果を表したものである。
↑目次へ
第三節 作品主題と色彩語の関係性
ここでは、第三章第一節と第二節で述べた分析と考察をもとに、太宰治作品で使用されていた色彩語が、各作品の主題と関連性をもつのかということについて検証する。ここでまず初めに、本論で使用する「主題」という概念について整理する。
↑目次へ
第一項 「おしゃれ童子」の主題と色彩語
ここでは、「おしゃれ童子」における色彩語と、その作品主題の関係性について考察を行うこととする。「おしゃれ童子」は昭和14年11月号の「婦人画報」に発表された作品であり、これは太宰の活動期間の中では比較的明るい作風が多く輩出されたと言われる中期に当てはまる。この中期に関しては後述で詳しく整理することとするが、作品内容は、主人公が幼少期から服装について強く関心を抱きながら成長していく過程を語り手の目線から述べられるというものである。太宰自身、学生時代は周囲とは一風異なった独自の服装をしていたというエピソードが残されていて、「服装に就いて」という作品の内容も同様、主人公は太宰自身であると捉えられやすいようである。
↑目次へ
第二項 「走れメロス」の主題と色彩語
「走れメロス」は、太宰の執筆時代を前期・中期・後期で分けるならば中期に該当する作品である。このころに執筆されたものは数々の研究書において「明るい作風」が展開された時期であると述べられている。太宰の作風が前期の「暗黒」から中期にかけてこのように変化した原因を、奥野健男は以下のように述べている。
↑目次へ
第三項 「富嶽百景」の主題と色彩語
「富嶽百景」は昭和14年2-3月号の「文体」に分けて連載された中期の代表的短編である。太宰はこの作品を山梨県川口村御坂峠の天下茶屋で執筆し、それまで(前期)の退廃的な生活から立ち直ろうとした。彼はこの作品「富嶽百景」を書くときに、「思ひをあらたにする覚悟」(「富嶽百景」)をもって取り組んでいる。先に述べた「おしゃれ童子」は昭和14年11月号の「婦人画報」に発表され、「走れメロス」は昭和15年5月号の「新潮」において発表されているということから、「富嶽百景」がこれらの作品よりも以前に発表されたものであり、中期の始まりである「満願」(昭和13年9月号「文筆」)、「姥捨」(昭和13年10月号「新潮」)「I can speak」(昭和14年2月号「若草」)に次ぐ作品であるため、「走れメロス」などと比較すると未だ前期からの回復を試みている段階であるということがわかる。現代においてもこの作品は「走れメロス」同様、教科書教材として使用されている。
↑目次へ
終章 太宰治が使用する色彩語と作品解釈の有効性
○太宰治によって使用される色彩語に内包されている意味
↑目次へ
おわりに
本論は太宰治作品のほぼ全ての文章表現から色彩語を抽出した上でその使用傾向を調査し、内包される意味について考察を行い、色彩語が太宰作品の内容解釈に有効な手立てとなるかを研究したものであった。しかし実際に調査できた色彩語は「赤」「蒼」「白」「黒」の4つの一色表現と、「青白」「蒼白」「蒼黒」「赤黒」の4つの二色表現にとどまり、色彩を連想する表現(「血」「牛乳」など)への考究までには至っていない。さらに全作品における色彩語の出現状況に関して分析は行えたものの、その機能に関しては「おしゃれ童子」「走れメロス」「富嶽百景」のみを明らかにしたまでであり、よって信憑性に関しては未だ不十分であることをここで指摘しておく。しかし太宰治作品における数々の先行研究がある中、これまで彼の全作品を通した色彩語研究がなされていなかったという点に本論は光を当てたものとなり、今後彼の作品における研究に新たな分野として視点を広げることができたのではないだろうか。またそれと同時に、色彩語研究における新たな方法を提案することへもつながったのではないかと考えている。
研究対象作品、参考資料・文献
研究対象作品
岡崎晃一「近代文学の色彩感覚」『解釈10月号(第43巻)』教育出版センター 平成9年
岡崎晃一「近代作家の色彩感覚」『解釈4月号(第44巻)』教育出版センター 平成10年
池川敬司「大藤先生のこと ―私的アプローチあれこれ―」
波多野完治「作家の色彩感覚-文体論的研究-」『国語・国文 第七巻第三号』星野書店 昭和12年
大國眞希「太宰作品が描き出す色彩のスペクトル―「駈込み訴へ」の鳥の声の問題とともに―」『文学・語学 第210号』平成26年
何 資宜「太宰治研究 ―その方法意識と同時代言説との関連を中心に―」広島大学大学院総合科研究科 国立国語研究所『国立国語研究所資料集6 分類語彙表』秀英出版 昭和39年
波多野完治『最近の文章心理学』大日本図書株式会社 昭和40年
波多野完治『文章心理学の理論』大日本図書株式会社 昭和41年
日本文学研究資料刊行会『日本文学研究資料叢書 太宰治』有精堂 昭和45年
日本文学研究資料刊行会『日本文学研究資料叢書 太宰治Ⅱ』有精堂 昭和45年
伊原昭『色彩と文芸美 ―古典における―』笠間書院 昭和46年
武井邦彦『日本色彩辞典』笠間書院 昭和48年
日本大辞典刊行会『日本国語大辞典』昭和49年
東郷克美、渡部芳紀『作品論 太宰治』双文社 昭和49年
西郷竹彦『西郷竹彦文芸教育著作集 第18巻 文芸学講座(Ⅱ) 人物像と性格』 明治図書 昭和50年
奥野健男『奥野健男作家論集1』泰流社 昭和52年
奥野健男『奥野健男作家論集3』泰流社 昭和52年
浅井清、佐藤勝他『研究資料現代日本文学 第一巻 小説・戯曲Ⅰ』明治書院 昭和55年
饗庭孝男『鑑賞 日本現代文学 第21巻 太宰治』角川書店 昭和56年
三好行雄『太宰治必携』學燈社 昭和56年
伊原昭『平安朝の文学と色彩』中央公論社 昭和57年
千々岩英彰『色彩学』福村出版 昭和58年
長崎盛輝『譜説 日本傳統色彩考 その色名と色調』京都書院 昭和59年
小田切進『日本近代文学大辞典』講談社 昭和59年
小野正文『太宰治 その風土』洋々社 昭和61年
週刊朝日『値段史年表 明治・大正・昭和』朝日新聞社 昭和63年
波多野完治『小学館創造選書106 文章心理学入門<新版>』小学館 平成元年
佐藤嗣男、橘豊『表現学体系 各論篇第一三巻 近代小説の表現 五』教育出版センター 平成2年
長谷部出雄・他『群像 日本の作家17 太宰治』小学館 平成3年
国語教育研究所『国語教育大辞典』明治図書 平成3年
大山正『色彩心理学入門』中央公論新社 平成4年
大藤幹夫『宮沢賢治童話における色彩語の研究』日本図書センター 平成5年
鶴谷憲三『Spirit 太宰治 作家と作品』有精堂 平成6年
大熊利夫『色彩文学論 色彩表現から見直す近代文学』五月書房 平成7年
奥野健男『太宰治』文藝春秋 平成10年
細谷博『太宰治』岩波書店 平成10年
上村和美『文学作品にみる色彩表現分析(芥川龍之介作品への適用)』双文社 平成11年
吉岡幸雄『日本の色辞典』紫紅社 平成12年
壇一雄『小説太宰治』岩波書店 平成12年
山内祥史『太宰治『走れメロス』作品論集 近代文学作品論集成8』クレス出版 平成13年
安藤宏『太宰治 弱さを演じるということ』筑摩書房 平成14年
山内祥史『太宰治研究 13』和泉書院 平成17年
山内祥史『太宰治研究 14』和泉書院 平成18年
甲賀忠一、制作部委員会『物価の文化史事典』展望社 平成20年
宮地裕・甲斐睦朗『「日本語学」特集テーマ別ファイル 普及版 意味4』明治書院 平成20年
太田治子『明るい方へ――父・太宰治と母・太田静子』朝日新聞出版 平成21年
湯原公治『別冊太陽 日本のこころ159 太宰治』平凡社 平成21年
山川健一『幻冬舎新書152 太宰治の女たち』幻冬舎 平成21年
増田美子『日本衣服史』吉川弘文館 平成22年
佐々木行宏『キルケゴールの<イロニー論>について 附・太宰治について』丸善出版 平成22年
濱田信義『日本の伝統色』パイ インターナショナル 平成23年
ドナルド・キーン『ドナルド・キーン著作集 第四巻 思い出の作家たち』新潮社 平成24年
福田邦夫『新版 色の名前507』主婦の友社 平成24年
斎藤利彦『作家太宰治の誕生――「天皇」「帝大」からの解放』岩波書店 平成26年
↑目次へ