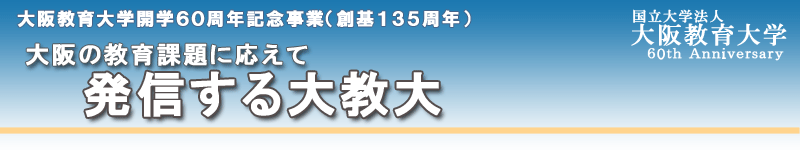
| 学長挨拶 |
| 大阪教育大学開学60周年記念事業 「大阪の教育を考える -学力・授業力・学校力-」収録要旨 |
||||
|
<主催・後援> |
||||
| (全体前文) 大阪教育大学の開学60周年(創基135周年)記念事業の第1弾となる、第1回シンポジウム「大阪の教育を考える―学力・授業力・学校力」が4月25日、大阪市天王寺区の国際交流センター大ホールで開かれ、約700人が参加しました。大阪における今日的な教育課題を5つのテーマに分け、それぞれがつながりをもつテーマについて1年をとおして討論を繰り広げるもので、今後、第2弾の「クラスマネジメント」(6月27日)、第3弾「発達障害と特別支援教育」(9月26日)、第4弾「テクノロジーを学校に」(10月3日)、そして集約点となる第5弾「大阪教育大学への期待」(11月7日)へとテーマが引き継がれます。 以下に、当日の収録(要旨)を掲載します。 <長尾学長冒頭あいさつ>
<久保審議官来賓あいさつ>
本日は、急速に変化する社会、複雑化・多様化する学校教育への課題が山積する中で、教育に求められる改革の方向性を「学力・授業力・学校力」をテーマにシンポジウムを開催されることとなりました。大阪から全国へ発信しようとする教員養成大学としての大阪教育大学のこの取り組みに、文部科学省といたしましても大いに期待をしているところです。創造的で活力ある社会を築くためには、一人ひとりの子どもの個性を伸ばし、生きる力、多彩な能力をはぐくむ視点に立った学校教育を推進できる実践的指導力を身につけた教員を養成することが、極めて重要です。大学に対する期待や社会的な要請に的確に応え、ますます教育研究の実を上げられますよう切に希望しています。 <向山氏講演>
<講演要旨> 子どもの力を引き出す技能を
発達障害の子どもの多くは、短期記憶、ワーキング・メモリーが1つだけに集中するのです。2つとか3つ、入らないのです。「教科書を出して25ページの3番」というと3つ入っているのです。だから、子どもはわからないのです。区切ってやらなければ。 わたしの著書『授業の腕をあげる法則』で一時に一事、1つのときに1つの原理をしなさいという法則を出しました。発達障害、特にADHDの世界的な研究者、アメリカ・マサチューセッツ医科大学のバークレー教授が出した12の指導指針の中に全く同じことが書いてあります。「区切りなさい」と。これは教師なら知っておかなくてはいけない指針です。 実際の教室ではもっと複雑な指示を先生方は出していませんでしょうか。「教科書を出して25ページの3番をやりなさいね。できたらお隣同士と答え合わせをして、間違ったところはノートにもう1回やるのですよ。2人とも全部できたら先生のところへ持ってきて。先生、それを見たら判こを押してやるから。そしたら、本を読んでいいからね」と。 これは、今言った子には何を言っているか全くわからないのです。全くわからない状態ですから、子どもはきょろきょろしたり、先生のところへ行ったりしますが、「席に着きなさい」とかなんとか言っていているうちに、教室は荒れていきます。人権の教育というのは、歴史的な制度に対する克服も極めて重要ですが、子どもたちがもっている力を引き出すことを保障するといった点でも重要です。そのために、教師は専門職としての力量、教える技能を習得しなくてはいけないと思います。原因をわかり、対応方法を知り、それらを克服できる授業ができなかったとすると、その子どもたちはドロップアウトをしていく可能性が極めて大だからです。 優しい笑顔は教師の表芸TOSSの中では、教師のみなさんの授業の力量を上げていただくために、TOSS授業技量検定というライセンスシステムを作っています。その中に、「温かい表情ができる」「子どもとちゃんと向かい合って笑顔ができる」というものがあります。 最近買った本の中でそのことがありました。林先生という世界的に著名な、脳外科のドクターがいることを知りました。死につながるような重い脳出血を奇跡的に生き返らせることのできる、世界トップクラスの医学チームをつくりました。その中に、教師の世界と同じではないかと思ったところがありました。それは、林先生が何十人といるチームのメンバーに要求したことなのです。その4項目の中に、「笑顔がちゃんとできる」というのがあるのです。 これはきっと学校づくりでも、自分たちの仲間をつくるのでも同じことだと思うのですが、教師が、笑顔ができるというのは当然です。子どもたちの前に立って、優しい穏やかな笑顔ができる。それ、いいねとほめられる。それは教師の表芸です。それは訓練しなくてはできません。しかめっ面で子どもたちに授業をしてはいけません。そういったことが、TOSSの技量検定の一番初歩的な段階にあるのです。さらには、言葉を削りなさいなどもありますけども、どのぐらい削るかというと、わたしは90%と言います。教師というのは、しゃべればしゃべるほどわからなくなるのです。 知識の部分と技能の部分は全く別です。教師あるいは医者といった職業の人たちには、技能を身につけなくてはいけない要素があるのです。検定は、そのための一つの試案としてつくったものです。 教師の指導で、子どもたちをいくらでも成長させることができます。しかし、教師自身が学び、かつ技能を身につけるということを抜きにしては無理です。もちろん、それはTOSSでなくてもいいし、いろいろな立派な先生方に学んでもいいのです。 子どもたちは、大切な日本の宝ですし、大阪の宝です。大阪教育大学の学生の皆さんは、子どもたち一人ひとりに目を向け、育んでいくことができる教師になるために、大学時代の4年間を送っていただきたいと思います。 <市川氏講演>
「教えて考えさせる授業」とは
「教えて考えさせる授業」ということをわたし自身が言い出したのは、2001年ごろからです。授業がわからないという子どもたちが非常に多い。当初は学校で詰め込み授業を受けているからだろうと思っていました。そのために子どもたちは消化不良になって授業がわからないと言い出すのではないかと。 子どもたちに「何で授業、わからないの?」と聞くと、「先生が教えてくれないから」という。「授業で何をやっているの?」と聞くと、先生から「さあ、自分で考えてみましょう」「みんなで考えを出し合って話し合いをしましょう」、こういうことで多くの時間がとられているというのです。 実際に学校の研究授業をみると、先生がいきなり子どもたちに問題を投げかける。教科書は閉じましょう、考えを出し合いましょうと。こんな授業がいい授業だと1990年代に言われ過ぎたと思います。何が問題かというと、塾で習ったり予習をしたりした子どもは授業が退屈だと言い出す。一方で、学力の低い子は討論に入ることすらできません。 授業記録だけ見ていると非常にいい授業のように見えます。子どもたちが次々に発言して、「わかった、わかった」と気づいていくという。ところが、実際の授業を見ていますと、半分ぐらいの子どもたちがわからなそうな、つまらなそうな顔をしている。 問題解決学習をめざしているのに、問題解決学習になってない。知っている子にとっては、塾で教わっただけで別に問題解決したわけではない。知らない子、わからない子、考えられない子は次第に考えることをあきらめてしまいます。これでは問題解決とは言えません。 「教えて考えさせる授業」では、新しい学習事項は、教師が丁寧に説明する。教科書も最初から開く。予習を求める場合もあります。家でざっと読んできましょうと。先生がどんどん説明を繰り返してしまったら詰め込み授業になりますが、教えたことがわかったかどうかの理解確認課題というのを入れます。 わかったかどうかの一つの目安は、人に説明できるかどうかです。子ども同士で習ったことを説明させ、グループのみんながわからなかったら、先生が入っていく。こうして理解の確認を行ってから、問題解決的な探究の授業に向かうのです。 授業の最後に、自己評価をしてもらいます。何がわかったのか、自分にとって大事なことだったのか、あいまいだったことは何かと、できるだけ自分の言葉でノートに書いてもらう。先生はそれを集めて、次回の授業に生かします。 学校での学力を社会で生かせる人間力に授業の主人公は子ども。しかし、習得の授業では、シナリオライターは先生だと思います。監督も先生です。その中で子どもが主役として授業に参加していく。先生が授業を組み立て、知識や技能をしっかり身につけさせ、探究の授業につなげる。それによって、その目標となっている知識や技能をしっかり身につけていくものだろうと思います。 人間力を育てる教育ということを考えると、基礎学力の習得だけで教育の役割が終わるのではありません。どういう大人になりたいかということを見据えた教育、学校だけではできない、市民生活の例えば暗い面も生きていくためには必要ですという教育。世の中の犯罪・非行とか、悪徳勧誘はどんな手口でやってくるかとかいう消費者教育とか、学校外の人々と接する地域教育をもっと活性化することが大切です。 学力というのは学校での学習の力と一般に思われていますけれども、それは決して学校だけで閉じているものではなくて、社会人と学ぶ中で例えばコミュニケーションをとる、その中で自分が何か役割を果たす、そういうときに使われる力なのだということを子どもたちにも実感してほしいと思っています。 ボランティアや文化的な活動、スポーツ、職業体験などさまざまな活動があります。子どもたちが学校で得た力は、大人の社会人とかかわる中で、何かの役割を果たす、コミュニケーションを取る、といったときに使われる力だと思います。学校での学力をつけ、それが人間力という形で社会に出て生かせる力となっていくのだということを、子どもたちには知ってもらいたいと思います。 <パネルディスカッション>(敬称略) 教師の授業力、学力、学校力について
【長尾】 【向山】 2つ目は学校が近代的なシステムになってない。毎年、職員会議で同じ議論をする。サッカーは放課後にやっていいのですかと。例えばそういったことが基本的なルールの学校の教育計画の中に明記されていれば、わざわざ議論をやる必要ないのに、そういったことがきちんとされてない。それから、会議そのものも10分で済む会議を1時間半も2時間もやる。それがいいという風潮もある。その結果として多くの先生方が疲れてしまう。近代的な運営システムがつくられれば、学校の中がすごく変わっていくのではないかと思います。 【長尾】 確かに技術の問題は一方であるのですが、それと同時に学力のあり方とか、あるいは学習そのものの捉え方、こういうものとは切り離して考えられない。 そこで、市川先生のおっしゃっている習得サイクルと探究サイクルをクロスさせながら、しかも人間力につないでいくという授業論が戦後の歴史の中でどのように位置づくのかというようなことを教えていただきたいと思います。 【市川】 ところが、それだけでいいのかということになると、家や地域、社会で何か役割を果たすという意識が弱く、家での手伝いなどをする時間は世界の中でも最低レベル。社会に出て自分はどんな役割を果たすのかという意識、これもどんどん弱くなっていっている。自分のオリジナルな発想をすることについても、奨励されてなかった。日本の学生が大学生として留学すると、日本の学生はよく物を知っていますけど、レポートに全然自分の考えが書かれていませんね。これは昔から言われていることです。 そこで、新しい学力観や自己教育力が出てきたことは、非常に大事だと思いますが、今度は基礎学力をしっかりつけるという点がおろそかにされてしまっている。両方大事なことなのに、教育界が往々にして揺れ動いてしまう、そこが問題だったと思います。 【長尾】 【市川】 こういう技術を開発することはものすごく大事だと思います。ただ、最終的に技術というものになって、それが共有財産化されて、それを学校の先生がプロとして身につけるとならないといけないと思うのです。しかし、どちらかというと向山先生は、理論とか理念というものをあまり表に出さずに、とにかくこういうやり方、発問や指示を出すと、これくらいの子どもがうまくいったと、そういう手続とその結果をみんなで出し合って、そして追試もできるような形にして確かな法則にしていこうというやり方を行われた。 この考え方というのは、心理学でいうと行動主義的な考え方なのです。けれども、もっと認識的なことでも、例えば百玉のそろばんだとなぜうまくいくのかという理論的なところにわたしは興味があるので、学校の先生がとりあえずは技術を蓄積していくというのであれば、われわれはそれがなぜうまくいくのかとかいう理論化を考えて、またさらにその理論を新しい技術の開発に生かすというようなことが一緒にできれば、これはすばらしいことではないかなと、期待していました。 【長尾】 【向山】 一つの学級の中に、現在、発達障害の子が約1割、境界知能の子が14%、ざっと数えて4分の1いるといわれています。そういった子どもたちに対して、間違った指導をやったらとんでもない話になってくる。一生自立していけなくなる。その本人も不幸だけども家族も不幸です。その自立していく芽のとき、具体的には小学校4年生までの読み書き算ができること、それを保障していくというのは教師の仕事です。それぞれの子どもたちがもっている障害、困難がわかっていなくてはいけません。それは教師だけがやっている仕事だと思っているのです。 その意味で、わたしは例えば百ます計算に反対です。さきほど短期記憶が1つに集中すると言いました。百ますは縦と横とやりますから2つ入ります。発達障害の子にできるわけがないのです。わたしたちは全国で1、000校ぐらい、百ます計算をやっているところを調べました。発達障害の子は、みんなでたらめを書いています。でも、テレビやマスコミは、あれはいいと言いました。ちっともよくないですよ。でたらめを書いて教室の中で、そういった形の指導法がいいなんてはずがないです。 わたしは、スキルも必要だし、ドリルも必要だし、練習も必要だと思っています。でも、それはそれぞれの子どもたちがうけている障害、困難、そういったことがわかっていなくちゃいけない。これがわたしの出発点なのです。 【長尾】 【市川】 ところが、問題は、ご指摘のとおり授業だといろいろな子どもがいるということです。いろいろな子どもがいる中で、では、どうしようかと。だれかにとっていい方法をやると、だれかよくないという子どもが出てくる。システム全体としてどうすればいいかというのを考えるのが、多分、学校の先生の一番の悩みでもあるし、そこをどうするかというのが問題だと思います。 例えば、4分の3の子どもは百ます計算を喜んでやっているし、学力もつくし、すごい効果が出ていると。それがいいという先生は、ものすごくそれを宣伝するのです。こんなに多くの子どもが伸びましたというようなことを言う。しかし、今の向山先生のお話だと4分の1の子はむしろ害になるというわけでしょう。これをどこでどういう形でやるのか、そこのシステムづくりということをわたしは考えるべきで、一概に何々は悪いとは言いにくくなってくると思うのです。 教師の専門性について【長尾】 さて、大阪の子どもの学力が低いといわれますが、教師の授業力さえ高まれば上がるのかといったらそうではない側面があるのです。大阪的に言えば、家のしんどい子は学力もしんどいという現状がある。そう考えていくと、これは人権教育がずっと提起してきた視点ですが、やはり学校の問題を、教師の専門性の問題を超えた視点、つまり市川先生の言葉を借りるならば、さまざまな学習環境の中に落とし込んでみるということが必要であって、学校教育と地域教育と申しますか、そういう中で教師の専門性を見直してみなければならないと思うのです。 【市川】 ところが、それだけではない、子どものもっと例えば自分は社会の中でどう生きていきたいとか、これはやっぱりいろんな社会人と接することというのはすごく大事だと思うのです。社会の中でいろんな仕事をやっている、あるいはボランティア活動をしているとか、とにかくいろんな生き方をしている人がいます。文化やスポーツの面で、一生それなりに、俳句の会とか、オーケストラとか、アマチュアだけども楽しんでいる人の姿を見る。そういう姿を見て、子どもたちが、自分もああなりたいというような機会を社会の中でもってほしい。 このように、先生は子どもがいろいろな社会人と接する機会を奨励するなど側面からサポートしてあげてほしい。さらに、教師は一市民として市民活動の企画者、運営者としての役割も期待されています。例えば、環境教育をする市民がいますが、子どもにどう教えていいかわからないとおっしゃる。教える専門性を生かしてほしいですね。 【長尾】 【向山】 【長尾】 ラーニングの問題、エラーレス・ラーニングというようにおっしゃったときに、市川先生はどうお考えですか。探究と習得の結びつきの学習、授業の場合、エラーレスというようなことはどういうふうに文脈的に続くでしょうか。 【市川】 ところが、ある程度の年齢になると、やっているレベルも高くなって、そして難しくなってきたときに、間違いは絶対やっぱり起こってしまうというのもあります。これはスポーツでもそうですけど、かなりレベルが高くなってくれば負けることは必ずあると。 ここでわたしたちが見ている、多分年齢の違いもあると思うのですけど、どちらかというと小学校の思春期以降、5、6年から中学生、高校生ぐらいでは間違いは絶対あるのです。テストになれば満点ばかりはあり得ないと。そのときに、間違えたときに何をするかという対処方法を身につけることが自信につながると思うのです。 例えば、数学でもテストをやれば間違いが出ます。ふだん問題集でもやっています。多くの子どもは何をやっているかというと、合っていればマル、問題集の答えを見て間違っていればバツをつける。これくらいで止まってしまう子が多いのです。せいぜいまじめな子は、バツだったら正しい答えを書き込む。これでいつまでたっても力がつきませんと言っているわけです。 それは、むしろなぜ間違えたのかを考えて、それをメモで書きとめておく。わたしたちはこれを、「教訓を間違えたところから引き出す教訓帰納」といっているのですけど、個別学習相談で中学生や高校生にはこれがものすごく大事だと思います。これがどの学習でも次に同じ間違いを犯さないようになるといい。自分はこういう点で賢くなったということで、むしろ間違えることによって賢くなるという感覚をつかんでほしいのです。 教訓を引き出さずに間違えてばっかりだと無力感に陥るのですが、むしろ多くの子ども、学力の低い子が、最初は間違いを犯さないようにしようでいいと思います。教材もそういうように間違えないようにする。ある程度になったら必ず間違いが出てくるので、間違えたときにはどう対処するかということを教訓として引き出す方法、そういう学習方法を教え、身につけてもらうということのほうが、わたしは多分強い学習者になれるのではないかと思います。やっぱり見ている学年も違うし、例えば障害をうけた子どもに最初からそんなことをやったら、これはやる気を失うに決まっています。 【向山】 間違いは必ず起こるというのは市川先生がおっしゃるとおりなのですが、そうしたら3倍ほめろというのです。叱る場合もある。もちろんそういった場合も、叱らざるを得ない場合、3倍はほめてやれと。そのように考えていきますと、随分わたしたち教師の姿勢が変わってくると思うのです。 ところが、日常の教室では普通、1回もほめないで10回ぐらい叱ったり、怒鳴っています。そういった点では市川先生の言われる、後になっていずれ間違える、その場を越えさせていく、もちろんそれは重要な教育の場であると思っていますが、わたしは一番出発点のところでこだわっています。 【市川】 わたしが一番自分でもよく出会う子どもはその中間にいて、この子たちは間違えると、力がある程度はあるにもかかわらず、ただ間違えて自信をなくすということを繰り返している。間違いから何か教訓を引き出すというようなことがあまり念頭にない。その子たちには、そういう学習方法を教えてあげることによって、「ああ、そうなんだ、克服できるんだ」というようなことをやっぱり伝えたい。 【向山】 【長尾】 【向山】 【市川】 【長尾】 |
||||
|
|
||||
|
|
|
|
||
国立大学法人大阪教育大学 総務課
Tel:072-978-3212 E-mail:somuka@bur.osaka-kyoiku.ac.jp
 「教科書を出して25ページの3番をやりなさい」と言った瞬間、「先生、何やるの」と言う子がいませんか? 普通の先生は、そこで叱ります。「ちゃんと聞いてないんだから」と。このような子どもは、どの教室にも1割から2割います。
「教科書を出して25ページの3番をやりなさい」と言った瞬間、「先生、何やるの」と言う子がいませんか? 普通の先生は、そこで叱ります。「ちゃんと聞いてないんだから」と。このような子どもは、どの教室にも1割から2割います。 基礎学力をどう保障するのか。学校にとっても、基礎学力は非常に大事な問題です。学校でのふだんの授業において「教えて考えさせる授業」の取り組みについて考えてみたい。
基礎学力をどう保障するのか。学校にとっても、基礎学力は非常に大事な問題です。学校でのふだんの授業において「教えて考えさせる授業」の取り組みについて考えてみたい。
 教える力が衰退する中で、向山先生は、斎藤喜博先生に惹かれ、その技術的な側面を徹底して追究されたと思います。わたしも斎藤喜博先生の授業は何度か見せていただきました。斎藤先生の場合は必ずしもスキルの側面ではなくて、かなりイデー(理念)的なものや、教材論にもかなり踏み込んでいく。それで、当時の状況からいいますと、民間教育研究団体の多くはその授業技術と同時にかなり教育内容に踏み込んでいった。教科研の国語部会だとか日本作文の会とかいうときは、確かに一定の授業技術を提起しながらも、常に教育内容というか、そこまで視野に入れようとした。それで、いわばかなりイデーの側面も含めたように思います。それゆえに技術としての体系はできなかったということでもあるのかなと思いますが、向山先生は教育界の中にあったさまざまな潮流の中でスキルの側面、技術の側面をこそ今の日本の教師たちは必要だというように、今の法則化運動をつくられていったのではないか。そのあたりはいかがでしょうか。
教える力が衰退する中で、向山先生は、斎藤喜博先生に惹かれ、その技術的な側面を徹底して追究されたと思います。わたしも斎藤喜博先生の授業は何度か見せていただきました。斎藤先生の場合は必ずしもスキルの側面ではなくて、かなりイデー(理念)的なものや、教材論にもかなり踏み込んでいく。それで、当時の状況からいいますと、民間教育研究団体の多くはその授業技術と同時にかなり教育内容に踏み込んでいった。教科研の国語部会だとか日本作文の会とかいうときは、確かに一定の授業技術を提起しながらも、常に教育内容というか、そこまで視野に入れようとした。それで、いわばかなりイデーの側面も含めたように思います。それゆえに技術としての体系はできなかったということでもあるのかなと思いますが、向山先生は教育界の中にあったさまざまな潮流の中でスキルの側面、技術の側面をこそ今の日本の教師たちは必要だというように、今の法則化運動をつくられていったのではないか。そのあたりはいかがでしょうか。  教師の専門性の中心を構成するのは教科教育だと思います。つまり、教科というものをよく理解して、それを教える技術をもっているということ。また教科の学習を通じて人間力的なこと、これは学級経営にしてもそうですし、子どもたち一人ひとりを見る中で、つき合う中で人間力的な力もつけていく。この教科学習を中心に据えた人間力形成ということをまず期待したいのです。
教師の専門性の中心を構成するのは教科教育だと思います。つまり、教科というものをよく理解して、それを教える技術をもっているということ。また教科の学習を通じて人間力的なこと、これは学級経営にしてもそうですし、子どもたち一人ひとりを見る中で、つき合う中で人間力的な力もつけていく。この教科学習を中心に据えた人間力形成ということをまず期待したいのです。 わたしも言いたいことは市川先生と同じです。例えばスポーツでいうならば県大会代表、あるいは一定の力があった人たちは、それは間違いの中からたくさん学んできた。わたしがさらに強く言いたいのは、勉強できない子、発達障害の子、その他の小さい子、そういった子にはエラーレスの形でやるべきだと考えます。
わたしも言いたいことは市川先生と同じです。例えばスポーツでいうならば県大会代表、あるいは一定の力があった人たちは、それは間違いの中からたくさん学んできた。わたしがさらに強く言いたいのは、勉強できない子、発達障害の子、その他の小さい子、そういった子にはエラーレスの形でやるべきだと考えます。