@¶|ìiÍ·×ÄiAU¶AYÈÈÇWÌ¢©ñðâí¸j éêèÌ_ð}îƵÄ\»³êĢܷBµ½ªÁÄSÄ̶|ìiÍ_ð}îÆ·é±ÆȵÉͳµ[»êðÇÝÆé±ÆÍūܹñB
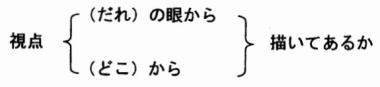
½¬16Nx@Cm_¶
ñoúF½¬17N114ú
½¬16Nx@Cm_¶
Cm_¶èÚ
\\_ÌzÆq@ÆðĪ©èƵÄ\\
åã³çåw@åw@
³çw¤È@ê³çêU
êwêC@ìQ³²¤º
ûüc@vk
Í@¤Tv
@æPß@¤Ûè
@æQß@¤ÎÛ
@@æP@¤ÎÛ
@@æQ@ªÍÎÛƵ½ìiÌTvÆ»ÌR
@æRß@¤û@
æPÍ@æs¤
@æPß@uê¼ÆÌæs¤
@æQß@__Ìæs¤
@æRß@qªÍÌæs¤
æQÍ@úìi̪ÍÆl@
@æPß@w½é©xɨ¯é_ÌzÆq@
@@æ1@w½é©xÌæs¤
@@æQ@w½é©xɨ¯éêÊ\¬
@@æR@q̪ުÍÌÚ
@@æS@w½é©xÌq̪ުÍÉæél@
@@æT@w½é©xɨ¯éÁ¥IÈqÉ¢ÄÌl@
@@æU@w½é©xɨ¯é_ÌzÆq@
@æQß@wÔÜÅxɨ¯é_ÌzÆq@
@@æP@wÔÜÅxÌæs¤
@@æQ@wÔÜÅxɨ¯éêÊ\¬
@@æR@q̪ުÍÌÚ
@@æS@wÔÜÅxÌq̪ުÍÉæél@
@@æTß@wÔÜÅxɨ¯éÁ¥IÈqÉ¢ÄÌl@
@@æU@wÔÜÅxɨ¯é_ÌzÆq@
@æRß@wäxɨ¯é_ÌzÆq@
@@æP@wäxÌæs¤
@@æQ@wäxɨ¯éêÊ\¬
@@æR@q̪ުÍÌÚ
@@æS@wäxÌq̪ުÍÉæél@
@@æT@wäxɨ¯éÁ¥IÈqÉ¢ÄÌl@
@@æU@wäxɨ¯é_ÌzÆq@
æRÍ@OÂÌúìiÌärl@
@æPß@OÂÌúìiɨ¯é_ÌzÌär
@@æP@OÂÌúìiɨ¯é_ÌzÌ·Ù_
@@æQ@OÂÌúìiɨ¯é_Ìz̤Ê_
@æQß@OÂÌúìiɨ¯éq@Ìär
@@æP@OÂÌúìiɨ¯éq@Ì·Ù_
@@æQ@OÂÌúìiɨ¯éq@̤Ê_
IÍ@_
¨íèÉ
Ql¶£
±Ìy[WÉ¢Ä
@{¤ÍAuê¼ÆÌúìiɨ¯é¶Í\»ÌÁ¥ð¾ç©É·é±ÆðÚIÆ·éBïÌIÈìiÉ¢ÄA»ÌÐÆÂÐÆÂÌqðשªÍµA»Ì_ÌzÆq@É
Ú·é±ÆÅAuê¼ÆÌúìi̶Í\»Á«ðl¦éB
@_ÌzÆq@ÆÍAÊXÌâèÅÍÈ¢BDZ©çi é¢ÍN©çj©Ä¢éÌ©ADZðiNðj©Ä¢éÌ©AÇÌæ¤É©Ä¢éÌ©i é¢Í©æ¤ÆµÄ¢éÌ©jÆ¢Á½Aìiɨ¢ÄÇÌæ¤É_ªz³êÄ¢éÌ©AÆ¢¤âèÆAÇÌæ¤Éq·é©i é¢ÍµÈ¢Ì©jÆ¢Á½±ÆÆÊXÉØ裵Äâ¤×«âèÅÍÈ¢B_ÌzÆq@ÆðÖA³¹Äl¦é±ÆÅAæè§ÌIŸmȪÍEl@ªÂ\ÆÈéÆl¦éB
@uê¼Æ̶Í\»ðl¦éÛA»ÌÏ»âÏeÆ¢Á½ÊIÈ·Ù_E¤Ê_ÅÍÈA½í½lÈìi𵤱ÆÉæèA¤IÈ·Ù_E¤Ê_É
Ú·éB éöxÌÀè³ê½úÌìið¡ªÍEl@·é±ÆÉæÁÄAúɨ¯éuê¼Æ̶Í\»Á«ð¾ç©É·éB
@_ÌzÆq@ÆÉ
ÚµAuê¼Æ̶Í\»Á«ð¾ç©É·é±ÆÍAPÉ\»_¤â¶w¤Auê¼Æ¤¾¯ÌâèÅÍÈ¢Bê³çÌêɨ¢ÄA{¤ÅÎÛÆ·éúìiâAuê¼ÆÌìið³ÞƵÄà¿¢éêÌîbIȤÉàÈë¤B
@{¤Ì¤ÎÛÍAuê¼ÆÌúìiÆ·éBuúìivÆÍAå³3Ni1914NjÈOÉ\³ê½ìiQðw·àÌÆ·éBuê¼ÆÍAwðÞbxðå³3N4Éwxæ5ªæ4É\ãA¨¨æ»3NÔìið\µÈ©Á½BæÁÄAwðÞbxÜÅÉ\³ê½ìiðuúìivƵÄA»êÈãÌìiÆæʵĵ¤±ÆÉ·éB
@úìiÉÍAÆßðèÞɵ½ìiâA¼Æ©gÌ̱âo±ðèÞɵ½ìiÈÇAÀ±IŽlÈìiª½\³êÄ¢éB»Ì½ßAìi̤IȤʫE·Ù«ðÝéÉÍKµ½ìiQÅ éÆl¦½BªÍÎÛÆ·éÌÍAïÌIÉͺÌOÂÌìii\NjÅ éB
| w½é©x | i\å³7N3j |
| wÔÜÅx | i\¾¡43N4j |
| wäx | i\¾¡43N6j |
@ªÍEl@ÌÎÛƵ½±êçOÂÌìiÉ¢Ä̬§ÉÖ·éTvÆAÎÛƵ½RÉ¢ÄÍAÉྷéB
@æQÅÍA¤ÎÛÆ·éeìi̬§ÉÖ·éTvÆAuê¼Æ©gÌìiÉηé¾yð°Ä¢éB·MA¬§ÉÖ·éàÌÍAwuê¼ÆSWæêªxiâgX1998NjÉæÁ½Buê¼Æ̾yÍAºa3N6Éãª{SW̪Éunì]kvƵÄû^³ê½àÌÌ©çAeìi̪ðøpµÄ¢éB
y\z
w¶wxå³7N3i1918Nj
y·Mz
¾¡41N114ú@cÌ@Ìúi1908Nj
yunì]kvɨ¯éw½é©xÖ̾yz
u½é©vÍñ\µÎ̳\OúScÌOñõÌßãA»Ì©Ìoð¢½àÌÅA±êðÌìÆ¢ÂÄࢢ©àmêÈ¢BÍ»êÜÅà¬àðnI©¤ÆµÄAêxàÜÆÜçȩ½BØÍoÄîÄàAÆàÌÉÈçÈ¢BêCÉÆΩèÌrÂÛ¢àÌÉÈèAäÂèÆàòÈ¿ÉMªèAÜÆÜçȩ½BªAu½é©vÍàeàÈPÈàÌÅÍ éªAÄOyÉMªèAßĬય½Æ¢Óâ¤ÈCªµ½B»êªñ\µÎ̾©çA¡vÖÎxêÄî½à̾B±ñÈàÌ©ç½v̪ª©ÂĽB
iºa3N6Éãª{SW̪Éunì]kvƵÄû^³ê½àÌB
øpÍwuê¼ÆSW@æZªxiâgX1999N5jj
@ÈãÌæ¤ÉAw½é©xª\³ê½ÌÍå³7NÅ èA{¤ÅuúìivÆèß½úæèãÉ\³ê½ìiÅ éBÂÜèAw½é©xÍAßÄ·M³ê½Æ«©ç\³êéÉéÜÅA10NÈãÌu½èª é±ÆÉÈéB³çÉA·M³ê½iKÌeuñ¬àAcêvª©³êĢȢ½ßA»sÌw½é©xÆÌ·ÙðÎÆ·é±ÆàÅ«È¢B»Ì½ßAuê¼Æ©gªêéæ¤ÉuìvƵÄÊuïéÉÍTdÉÈéKvª éBªÌæÍoÈ¢ªAeuñ¬àAcêvÌ·MÆA®¬ew½é©xÌ\ÆÌÔIu½èðl¦éÆA¨»çeiKÌuñ¬àAcêvÆAãÉ\³ê½w½é©xÆÍAå«áÁÄ¢éÂ\«ª¢Æl¦çêéB
@µ©µA±±Å¸¦ÄuúìivƵÄw½é©xðIñ¾ÌÍAâÍè©gªuìvƵĦéÙÇAìÆEuê¼ÆÉÆÁÄå«ÈÓ¡ðÁÄ¢é½ßÅ éB_Ìzâq@ðl¦é¤¦ÅAußĬય½Æ¢Óâ¤ÈCªµ½vƾÁÄ¢éӡͬ³È¢BuúìivƵÄÀÕÉÜßĵܤ±ÆÍÅ«È¢ªAtÉuúìivðÎÛÆ·éÈãAâÍè³Å«È¢ìiÅ éBæÁÄA±Ìw½é©xÍáOIÉuúìivƵĵ¤±Æɵ½B
@ȨAãÌunì]kvÉÍAuñ\µÎ̳\OúScÌOñõÌßãA»Ì©Ìoð¢½àÌvÆ éªAuê¼ÆÌúLÉæêÎAñ\ZÎÌÅ èAw½é©xÌOgÅ éuñ¬àAcêvª©ê½ÌÍA@ÌúÅ é±ÆªL³êÄ¢éBæÁÄA±êÍuê¼Æ̨á¢Å éÂ\«ª¢B
@w½é©xÌàeÉ¢ľ¦ÎA±ÌìiÍAuM¾YvðSƵ½Ol̬àÅ éBܽAãÌøpÉà éƨèA±ÌìiÍuê¼ÆªÀÛÉ̱µ½oðîɵ½ìiÅ éB
y·Mz
¾¡41N8i1908Nj
iå³7N3ÉVªÐ©ç§s³ê½¯lÌìiWwÌXxÉû^³ê½ÛAui¾¡41N8jvÆ·MNªL³ê½Bj
y\z
wxæ1ª1in§j@¾¡43N4i1910Nj
yunì]kvɨ¯éwÔÜÅxÖ̾yz
uÔÜÅvͽküðêlÅAÂÄéñÔÌÅAOÉæèµÄî½Æ»Ìq©çAèÉzµÄ¬àÉ¢½àÌÅ éB±êÍé¶wÉÐðu¢Äî½ÖW©çué¶wvÉeµ½ªAv³ê½B´e̪«½È¢×Š½©àmêÈ¢B
iºa3N6Éãª{SW̪Éunì]kvƵÄû^³ê½àÌB
øpÍwuê¼ÆSWæZªxiâgX1999N5jj
@wÔÜÅxÍAuê¼ÆÌìiÌÅÅÉ\³ê½uìvÅ éBw½é©xÆÍá¢A¾¡41NÉ·M³êAññNã̾¡43NÉ\³êÄ¢éBâÍèuê¼ÆÌuìvÌêÂÅ é±ÆàAÎÛƵ½RÌêÂÅ éB
@wÔÜÅxÍAu©ªvðSl¨Æ·éêl̬àÅ éB©gÌ̱ƼÚIÉÖíéìiÅÍÈ¢ªAuOÉæèµÄî½Æ»Ìq©çAèÉzµÄ¬àÉ¢½àÌvÆ é±Æ©çAèÞÍ»Ì̱ÉæéàÌÅ éƾ¦éB»ÌÓ¡ÅA©gÌ̱Éîâ½ñÂÌìiƵÄAOl̬àÌw½é©xÆêl̬àÌwÔÜÅxÆ¢¤¤Ê«Æ·Ù«ðàÁ½ìiÅ éBêlÌ©OlÌ©AÆ¢¤¬àÌlÌ̽l«ðÝé±ÆªÅ«éÆl¦½½ßAwÔÜÅxðªÍÎÛƵ½B
@wäx̬§¨æÑAuê¼ÆÌìiÉηé¾yÍÌÊèÅ éBwäxÍ\É Æª«ÆµÄuuävÌãÉvÆ¢¤¶ÍðÚ¹çê½B»Ì½ßA»êà í¹ÄøpµÄ¨B
y·Mz
¾¡42N930ú·MÌútulÔÌs×vi1909Nj
¾¡42N1013ú·MÌútuElvi1909Nj
¾¡43N424ú©ç¯N57úÜÅüe³ê½±ÆªúLÉ éBi1919Nj
y\z
¾¡43N6sÌwxæ1ª3É\Bi1910Nj
i»ÌãAw¯xiz°å³2N1i1913NjjÉû^AêüeBj
yuê¼Æ©g̾yz
uuävÌãÉv
uävÍNÌHAÔÌôGÉoµ½à̾ªÉ»êðo·Éµ½ÌÅlñ\lúÌө缵ĩ½BúÌÓà»êÉïµÄFOYÆ¢ÓjªäÅáÒÌôðØéOÜŢĽB\ñ߬¾Â½BOÉÍE·V[ͩȩ½ª¡xÍ´V[ð¢ÄIç¹éɵ½BRµÇ¤ànbLµ½õiªÎÈ¢B©µ ©çñOÔ©©ÂÄǤ©A©¤©«ã°½B»ÌúÍñ\ZúÅ éB
@©ªÌÆÍzOÍä¬ÅAë©ç_êdÌ×ƪå¹\îÌîÅ éB
ñ\µúÌV·Éå¹Ojª¼mäÅ©Eµ½Æ]ÓLªoĽAÔÍñ\ZúÌßOñ²ëÅ éA©ªª¶¤¢ÓV[ðzµÂÂÄÔàÈÌÅ éBÆÌlª»êð©³ê½Ì͵ ¾Æ¢Ä ½B´ªA©ªÍ×èÅOé̱«ð¢Äî½ÌÅ éB
@ôRÈãÌàÌÆM¸éÍoÈ¢¯êÇàA»êɵÄàsvcÈôRÅ éB
i¾¡43i1910jN6sÌwxæ1ª3É\B
øpÍwuê¼ÆSWæêªxiâgX1998N12jj
unì]kv
@uäv°®Å°çN઴¸é¾ç¤ÏO©çìèã°½à̾B½Þ¿ÌªrAY[É éÆ¢ÓbðãÉ·¢½B
@¬àð¢ÄîéAéA\ñ߬ÄAxFOYÆ]ÓålöªáÒÌôðØéOÜÅ¢ÄQÄA©Aµ ©ñOÔ©©ÂÄAãð«ã°½ªA´ÓA\ª«Â ½©AQĩ穪çÈ¢ªA_êd×èÌlªA¼mäÅôðØÂÄ©EµÄî½BÈôRª éà̾Æv½B
iºa3N6Éãª{SW̪Éunì]kvƵÄû^³ê½àÌB
øpÍwuê¼ÆSWæZªxiâgX1999N5jj
@wäxÉ¢ÄÌuê¼Æ̾yÉÍAwäxªGwxÉfÚ³ê½Æ«ÉuuävÌãÉvÆ¢¤ ƪ«ª¯¶ÉfÚ³ê½B±±Åͱêð í¹ÄøpµÄ¨¢½B
@wäxÍOÂÌeª èA®¬eÉÁÄ¢éBuê¼Æ̾yÉà éæ¤ÉAwäxÍA©gÌ̱ÉîÃàÌÅÍÈAnì«Ì¢ìiÆÈÁÄ¢éBRè³i1998juuê¼Æ_iñj\\gÆ߬àhðß®ÁÄ\\viwåâqåw¶Ñxæ491998N3jÍA±ÌwäxðAÆßðµÁ½ìiƵÄAwäÌÆßxAwN[fBAXÌúLxAwðÞbxÈÇÆÆàÉAuÆ߬àvƵÄÊuïĢéBìl¨uFOYvðSƵ½Ol̬àÅ èAlÌÍw½é©xƤʵĢéBµ©µAw½é©xEwÔÜÅxÆÍá¢A©gÌ̱ɼÚèÞð¾Ä¢È¢Æ¢¤_ÅA½l«ðÝé±ÆªÅ«é¾ë¤Æl¦ÄAÎÛƵ½BܽAuElvðµÁ½uÆ߬àvÅ é±Æ©çàAw½é©xEwÔÜÅxÆÍÙ¿ÈìiÅ éB
@ÈãÌOÂÌìiðªÍEl@·é±ÆÅAuê¼ÆÌúìi̶Í\»Á«ð¾ç©Éµ½¢B
@¤û@ÍAyOÌuqwvÆ¢¤l¦ÉîâÄAq̪ުÍð¨±È¤B±Ìû@É¢ÄÌÚ×âyÉæéïÌáÍ{eæPÍæRßÅ®·éBªÞÚÉ¢ÄÍAàeâlÌAìl¨ÈÇðl¶µ½¤¦ÅA»ÌìiɦµÄìi²ÆÉÝè·éB
@eìiɦµ½ÚÉ]ÁĨ±ÈÁ½ªÞªÍÉîëA_ÌzÆq@É¢Äl@·éBqðÐÆÂÐƪުͷé±ÆÅAÈÉðÇÌæ¤Éq³êÄ¢éÌ©i é¢ÍÈɪq³ê¸ÉB³êÄ¢éÌ©jAïÌIÉl@·é±ÆªÂ\ÆÈéB»ÌÅàÁ¥IÈqÉ¢ÄÍAÊÉÆè °Ä³çÉÚ×ɪÍEl@·é±ÆÉ·éBuåèvu\¬i\zjvÆÌÖAÌÈ©ÅqÌ è©½ðl¦A»êçɺx¦³ê½q@ð¾ç©Éµ½¢B
@_¶Ì\¬ÍAͶßÌÚÉLµ½Æ¨èÅ éBवڵ¯ÎÌæ¤ÉÈéBÍÅÍA¤ÌTvÉ¢Äq×½BæPÍÅÍAæs¤ð®·éBæPßÅÍuê¼Æ̶Íâ\»É¢ľyµÄ¢éàÌAæQßÅÍ__É¢ÄÌàÌAæRßÅÍ{e̤û@Å éq̪ުÍ̺nÅ éyOÌuqwvÆ¢¤ªÍû@É¢ÄAÝÄ¢BæQßÅÍA__Ìæs¤ð®·éÆÆàÉA{eɨ¯é_ÉÖ·épêEpêðè`ïéB
@æQÍÅÍAÎÛƵ½OÂÌúìiÉ¢Ä̪ÍEl@ðÀÛɨ±È¤BªÍEl@·éÍAw½é©xiæPßjAwÔÜÅxiæQßjAwäxiæRßjÆ·éBªÍEl@ÌèÍAܸeìiÌæs¤ðÝéBæQÅÍA»ê¼êÌìiÉ¢ÄÌêÊ\¬ðl¦éBÌæRÅÍAq̪ުÍÌÚðAìiɦµÄè·éBæSÅA»ÌªÍðàÆɵ½l@ð¨±È¢AæTÅÍA»ÌÅàìiÌåèÉ©©íéæ¤ÈAÁ¥IÈqÉ¢Äl@ð[ßéBæUÅA»ê¼êÌìiɨ¯é_ÌzÆq@É¢ÄAÜÆßÆ¢¤©½¿Ål@Êð®·éB
@æRÍÅÍAæQÍÌl@ÊðàÆɵÄAOÂÌúìiɨ¯é_ÌzÆq@É¢ÄÌärl@ð¨±È¤B»±ÅAOÂÌìiÌ·Ù_ÆA¤Ê_ð¾ç©Éµ½¢BIÍÅÍ{eÌuê¼ÆÌúìiÉ¢ÄÌ_ðÜÆßéBQl¶£ÌêÍ»ÌãÉñµÄ¢éB
@¿ÍAw½é©xAwÔÜÅxAwäxÌ{¶ÆAæQÍŨ±ÈÁ½eìi̪ުÍÌ}\ðYtµ½B»ê¼êÌìiÌ{¶ÍAûücªwuê¼ÆSWæêªxiâgX1998N12jðàÆÉA»ê¼êÌìiɶÔi1A2A3cjƪÔiiajAibjAicjcjðtµ½àÌÅ éBT_Í´¶Ç¨ètµ½B´¶É Á½rÍA·×Ä͸µÄ¢éBfíèªÈ¢ÀèA{eɨ¯éìiÌøpÍA±êƯ¶àÌðøpµÄ¢éB½¾µAeìiÌæs¤É¨¯é{¶ÌøpÍA¶ÔEªÔÆàÉtµÄ¢È¢àÌðøpµ½iæQÍÌeßæPjB
@±ÌæPÍ
ÅÍAæPßÅuê¼Æ̶ÍÉÖ·éæs¤AæQßÅ__ÉÖ·éæs¤A»µÄæRßÅÍA{e̤û@Æ[ÖíéqwªÍÉ¢ÄÌæs¤ðÉÝÄ¢BȨA¤ÎÛƵ½w½é©xwÔÜÅxwäxÌ»ê¼êÌæs¤É¢ÄÍAæQÍÌìiªÍÌAeßÌæPÅ®·éB
@æPÍæPßÅÍAuê¼Æ̶ÍÉÖ·éæs¤ðÝÄ¢±ÆÉ·éB±êÜÅuê¼Æ̶ÍÉ¢ÄÍA½Ì¤ÒâìÆÈǪlXÉwEµÄ«½B»êçÌSÄðæèã°é±Æ͹¸ÉA{¤ÉÖíéwEÌÝðæèã°é±ÆÉ·éB
@¬Ñpvi1944ju¶Ì©çݽuê¼Æviwuê¼Æ¤xÍo[1944N8jÅÍAuê¼Æ̶ÍÉ¢ÄÌæ¤ÉwE·éB
@í½µÍ_éå`ð±ÌÜÈ¢µAܽ»êÍྩçÌêí̦ð¾Æl¦éÌÅAu¸_ÌYvÆ¢¤±ÆÎàAÈñç©ÌÊÌA^WuȱÆÎÉu«©¦ÄðߵȢÅÍ¢çêÈ¢B
@í½µÌl¦ð¢¦ÎAuêÌ¢¤u¸_ÌYvÆÍA`ǨèÉðµÄAìÒªÎÛÆæÁgÝÁÄ¢éƫ̸_Ì٣ƢÁ½A¸_¨IÈàÌÆÍvíÈ¢BÞµëìÒÌÏ@·éÎÛ»ê©ÌÌàÂYÅ éBÆ¢ÁÄàìƪ`©Ê³«ÉAܽͩéܦÉAÎÛ»ê©Ìª±ëªÁÄ¢éí¯ÅÍÈ¢©çA©êª`×·éµãñ©ñÌAÎÛÌàÂYÅ éBiªj¨Ìd\\AeÌê¹IÈÓ¡¢É¨¢ÄAuêÍܳÉAXgÅ ë¤Bà¿ëñ±±É¢¤¨ÆÍA Ȫ¿dÊÌ éAvÊÂ\̨IÎÛðÓ¡·éÌÅÍÈ¢BÏ@Î۽马èÌASÌ®«à»êÉÓÜêéÌÅ éB
@±ÌÓ¡ÅAí½µÍuêÌ¢íäéu¸_ÌYvðÊ̤¦©çÍÜéŽÎÈAu¨ÌYvÆ¢¤±ÆÎÉA¢¢©¦³µÄà碽¢B
@±ÌAu¨ÌYvðd·é±Æ©çµÄAuê̶ÍÌe|ªè³êéÌÅ éB
iºüøpÒBȺ¯¶B
¬Ñpvi1944ju¶Ì©çݽuê¼Ævwuê¼Æ¤x
øpÍw¬ÑpvìWW@¶Ì_IìÆìi_xiOzÐA1976N11jj
uê¼Æ̶ÍÌÁ¥ÆµÄAu¨ÌYvðwEµÄ¢éB»ÌuYvÆÍAu©êª`×·éµãñ©ñÌAÎÛÌàÂYvƵĢéBÉA¬Ñpvi1944jÅÍAÌæ¤ÈÀ±ð¨±ÈÁÄ¢éB
@±±ëÝÉí½µÍAuêÌZÑu°ÎvðÆèA±êðêZ¼Ìåw¶ÌܦÅAí½µÌKµÌA²Ó¤ÌÍâ³ÅANǵÄݽBñꪩ©Á½Bgm[ÅÊÁ½í¯ÅÍÈ¢ÌÅA³mÈð °éÌͳӡŠé©çAåÌ̱Æð¢¤ÉÆÇßé¯êÇALøÈðȵ½êl¼Ì¤¿Aí½µÌÇÝ©½Ì¬xðÂÆ·éàÌêZ¼AÍâ·¬½Æ]·éàÌl¼A¨»·¬½Æ·éàÌÍF³Å Á½BXPb`Ó¤ÌìiÅA×ÂɱÝüÁ½Ì¶¶éí¯ÅàÈ¢©çAÍâÇñÅàðð³µÄW°é±ÆÍȢŠ뤪A¡í¤½ßÉÍAष±µäÁèÇޱƪKvÅ Á½Bí½µÌ¬xÍf[gç¢Å Á½ë¤©çAA_WIÜÅ¢©¸ÆàA¹ßÄA_eÙÇÉ·êÎæ©Á½Ì©àµêÈ¢B
i„pvi1944jj
±Ìæ¤ÈNÇÌÀ±ðÝA±Ìåw¶ªuÍâ·¬½vÆ]¿µ½à̪l¼¢½Éà©©íç¸Au¨»·¬½vƵ½à̪¢È©Á½Êðño·éB±ÌÊ©çuê¼Æ̶ÍÉ¢ÄAÌæ¤ÈwEðµÄ¢éB
uê̶ÍÉ ÁÄÍAO̶Æã̶ÆÌ\í·Ó¡ªAWJÈÂȪèðàÁĢȢ±Æª½¢B¼ÒÌ ¢¾ÉÍ^ónѪ ÁÄAÇÞÒÍO¶©çã¶ÖÚéÆ«ÉA»ÌÔðzÍðàÁÄA¤ßÄ¢©ÈÄÍÈçÈ¢B±ÌwÍÌvªe|𨻩çµßAܽ¶Í̤í·×èðÓ¹¬AêX̶Éd³ðཹAÂȬÌê̶ÝðàYê³¹éÌÅ éB
i„pvi1944jj
uO̶Æã̶ÆÌ\í·Ó¡ªAWJÈÂȪèðàÁĢȢ±Æª½¢vÆ¢¤uê¼Æ̶ÍÌÁ¥ðÆç¦ÄA»Ì½ßAåw¶ÖÌNÇÌÀ±É¨¢ÄAuÍâ·¬½vÆ]¿µ½à̪¢½ÌÉεÄAu¨»·¬½vÆ]¿µ½à̪¢È©Á½Æ¢¤Êª¤Üê½ÌÅ éÆྵĢéB
@g½ì®¡i1953juìÆ̶ÍS\\JèêYÆuê¼Æ\\viw¶ÍSwüåxVªÐ1953N1jÅÍAJèêY̶ÍÆärµÄAuê¼Æ̶ÍÉ¢ÄAl@µÄ¢éBÌwEÍA¼Ò̶Íɨ¯éê¶Ì·Zðärµ½¤¦ÅÌàÌÅ éBJè̶ÍÉä×ÄAuê̶ÍÍ궪Z¢±Æðݽ¤¦ÅA
¬àÆÍ¢ÂÅà©È̶ÍðʶĽ©Ìj AXðo»¤Æw͵ĢéÌÅ ÁÄAÁÉuê̶ÍÉÍAOÌÇÌìÆÉà©çêÈ¢±Ü©¢j AXªæoÄ¢é±ÆðFßÈ¢àÌÍ éÜ¢B]ÁÄ·¢¶ð©Z¢¶ð©©ÍA¬àƪ¾tÌÂj AX𨳦ÄA»Ì¨³¦é±ÆÉæÁÄA©¦ÁľtÌàeÆÈÁÄ¢é¨Ìj AXð çíɵæ¤Æ·é©É©ÁÄ¢éB
@uÏOI«iv̶ÍiÏOͶÍɨ¢Ä;tÅ é©çj;tÌÂj AXðàÁÄo龯±Ü©»ÀÌÄ»ðú·éɽµu¦¨I«iv̶Í;tðKmɵÄAääÌSð¼ÚɨÉÞ¯³¹A¨Ìj AXð¶©ÉäXÉóÛ³¹éû@ðÆéBÏOI«i̶Íɨ¢ÄÍA¨Ìj AXÌOÉA¾tÌj AXÉå«ÈÓª¥íêÄ¢éªA±êɽµÄA¦¨I«iɨ¢Ä;tÌàÂj AXªÓ¯IÉ}§³êéB
iºüøpÒB
g½ì®¡i1953juìÆ̶ÍS\\JèêYÆuê¼Æ\\v
w¶ÍSwüåxVªÐ
iøpÍw_Wú{ê¤W@¶ÍE¶ÌxL¸°1979N4jj
ÆwE·éBuÏOI«iv̶ÍÆÍAJèêYÌàÌÅ èAu¦¨I«iv̶ÍÆÍuê¼ÆÌàÌÅ éB¬Ñpvi1944jÅÍu¨ÌYvÆ]µÄ¢½ªAg½ì®¡i1953jÅÍu¦¨I«ivÆwE·éBJèêY̶ͪu¨Ìj
AXÌOÉA¾tÌj
AXÉå«ÈÓª¥íêÄ¢évÌÉεÄAuê¼Æ̶ÍÍAu¦¨I«iɨ¢Ä;tÌàÂj
AXªÓ¯IÉ}§³êv½¶ÍÅ éÆ¢¤B
@³çÉAg½ì®¡i1965juJèEuê¼Ì¶ÍÌ`ÔIáviw¶ÍSwÌnP@¶ÍSwVexåú{}1965N9jÅÍAæèÚ×ɪ͵ĢéBg½ì®¡i1965jàAJèÆuê̶ÍÆÌärðSÉl@ð¨±ÈÁÄ¢éBܸAJèêYÌwåb xÆuê¼ÆÌwR`xÆðärµÄÌæ¤ÉAwE·éB
Jèɨ¢ÄÍܽͨÌqªA ÜÅà¾êðåÌƵÄA¾êªåðÆÈÁÄ©½çêÄ¢éB±êɽµÄAuêɨ¢ÄÍ é¢Í¨Í±ÆÎÉæÁÄ©½çêÄ¢ÄàA±Ìê±ÆÎͽ¾}îð·é¾¯ÅAåÉÈéàÌͨ»ÌàÌA»ÌàÌÅ éB±ÆÎÍðæ·éÉÆÇÜèA·×ĩ̪¼Úñ¦³êéBµ½ªÁÄA±ÆÎÌ𾯢¦ÎAãÒ̾êgpÍ¢¿¶éµÛ¥IÉÈéB¾êÍÇÒªiFðSÛ»·é½ßÌhÈÌÅ é©çB
iºüøpÒBȺ¯¶B
g½ì®¡i1965juJèEuê¼Ì¶ÍÌ`ÔIáv
w¶ÍSwÌnP@¶ÍSwVexj
u±ÆÎvªuåðÆÈÁÄ©½çêÄ¢évJèêY̶ÍÉεÄAuê¼Æ̶ÍÍu¨vuvÉd«ª¨©êÄ¢éÆ¢¤B³çɼÒÌûü«É¢ÄAÌæ¤ÉwE·éB
JèÌÙ¤ÍA¾êªOÊÉÅÄ«Ä¢éAÆ¢¤©¬èɨ¢ÄA©ÈÌÙ£ÌnðÐïIÈ©½¿ÅASXIÈ\»`®ðÆÁÄ¢ÌÅ éªAuêÌÙ¤ÍA»Ì¶ÍÌuüªÐïIBÓÌÙ¤ÖÞ©í¸ÉAu¨vÌÙ¤ÖÞ©ÁÄ¢éBOÒÍqð¢©ÉÐï»·é©AÆ¢¤ûüÉÞ©¢AãÒÍqð¢©Éu¨vÉÀÉ·é©AÆ¢¤ûüÉÞ©¤B
ig½ì®¡i1965jj
±Ìæ¤ÉAuê¼Æ̶ÍÌÁ¥ÍAuqð¢©Éu¨vÉÀÉ·é©vÆ¢¤ûü«ðàÁÄ¢é±ÆÅ éƵĢéB
@uê̶ͪA©©éZIIȶÍnì©çé½Ïö·ÌåƱÆÈé±ÆÍA̶ÍÌOÌ«¿©ç½¾¿É»¾·éªA½Ïö·ª½¾¿Éu¨ÖÌÖSvð¦·àÌÅÈ¢±ÆÍӵĨ¢Äæ¢B
ig½ì®¡i1965jj
¾ªA»Ìuê¼Æ̶ÍÌûü«Æ¢¤ÌàA¨ÉÖSªü¯çêÄ¢éàÌÅÍÈ¢±ÆðmFµÄ¢éB¶ÍÌÁ¥ÆµÄAu±ÆÎvâu¾êvÅÍÈu¨vÉÀÉq·é©AÆ¢¤ûü«ÈÌÅ éB
uêÍA¶Ôñ̪ÌÉ é\ÛðA¨É¦µÄªßµÄ¢B¨»ÌàÌÍPÈéu¶Ý»fvi~NVbqAu^[mjÆl¦Äæ¢BuêÍܸ¨ð¨ÆµÄ¾ê»·éB»¤µÄ¨Ìªßi¨Ì»ÛÏ»jðA»ÌÜܾê̪ßÉÏ`·éBµ½ªÁÄ»±ÅͶݻfÌA±ªÝçêéí¯ÉÈéBêå¶ÌA±ÆÍv·éÉA¨ÌªßðA»ÌÜܾêÉ çíµ½©çÉÙ©ÈçÈ¢B
ig½ì®¡i1965jj
@±¢ÄAJèêYÌwàÆâxÆuê¼ÆÌwJ^xɨ¯é»ê¼êÌi̽Çâäg\»ÈÇÉ
ڵļÒÌá¢É¢ijçÉl@ð··ßÄ¢éBܸA¼Ò̼̽ÇÉ
ÚµA
JèÉäµÄAuê̶ÍÉÍ¢¿¶éµ¼ª½¢BãÒÍOÒæèñÜÙǼª½¢ÌÅ éiuêÍçÉêZZËAJèÍêêµÂjB
ig½ì®¡i1965jj
Æ¢¤°Èá¢ðwE·éB³çÉAJèêYÌwàÆâxɨ¢ÄÍA궪·çÉ\µÌ¶µ©È¢ÌÉεAuê¼ÆÌwJ^xɨ¢ÄÍA궪ZçÉO\̶ª éÆ¢¤BÉà©©íç¸A¼ÒÌ®ÌÍS\OiJèjAS\ñiuêjÆÙÚ¯¶Å é±Æð¾ç©Éµ½¤¦ÅA±êçÌá¢ðAJè̶Íðup¾^̶ÍvAuê¼Æ̶Íðu̾^̶ÍvÆæÑæÊ·éB
@»µÄ±Ìup¾^vÆu̾^v̶ÍÌ·ÙÉ¢ÄÌæ¤ÉÜÆßÄ¢éB
@±Ì̾^̶ÍÆAp¾^̶ÍƪâÍèu¨ÖÌûüvÆAuÐïÖÌûüvÆ¢¤S«Ìî{ûüÌêÂÌ çíêÅ é±Æͽ¾¿ÉªÅ«æ¤Bêûͨðw¦µÄA¨Ì¼Ï»ÌàÌ©çAêíÌÙ£ÌnðæѨ±»¤Æ·éB±êɽµÄAp¾^̶ÍÅÍ̾ÆÆàÉA»Ì̾ÌlóÔðū龯u¾êIvÉq·éBlÉí©ç¹éÉÍA±ÆÎðµÄApÓüÉq·éKvª éBiªj»¤µÄAà¾ÌåÌÍ©¬çêÄ¢éÌÅ é©çA¼ÍÈA¼É¢ÄÌḻÆÎi·Èí¿p¾jª½Èéí¯Å éBuê̶ÍͱêÆͽÎÉA¨»ÌàÌɦµæ¤Æ·éB¨ðí©ç¹æ¤Æ·éæèàÇÒª¨ÌÖÆѱޱÆðv·éB±ÆÎÍæÆè¾·¯ÉÆÇÜèA»Ì±Ü²Üµ½à¾Í·×ÄÇÒÌzÉÜ©¹çêéB
ig½ì®¡i1965jj
@³çÉA¬Ñpvi1944jƯ¶æ¤ÉA¶Æ¶ÆÌ_IÈÂȪèªóÅ é±ÆÉàGêÄ¢éB
Ʊëªuê̶ÍA©©éÓ¡ÅÍsIhÍSRÈ¢Bɨ¢ÄÍA½Æ¦ªZ½¶Ì·¶Å ÁÄàlÂܽÍÜÂ̶ªA½¾ù¢Ìæ¤ÉÂÝ©³ÈÁÄ¢éÉ·¬È¢©çAñíÉucucµ½¢ÂàÌsIhªAêÂ̶ÉÓÜêéí¯Å éB
ig½ì®¡i1965jj
±¤µ½¶Æ¶ÆÌÂȪèÌó³ÉÁ¦ÄAuê¼Æ̶ÍÉÍȪª½¢±ÆðwEµAÌæ¤É»Ìà¾ð·éB
@uê̶ÌàÂeÍͱ¤¢¤É[È黃 éƨà¤BlÍȪ³ê½±ÆÉæÁÄA¶Í©ç¶ÍÖ¤Âé³¢Éòôðo±·éA±±ÅAeÍÌæêÌ´¶ªÅÄéBÉAlÍȪÌÓðA³Ó¯É¨¬È¤wÍð·éBÇ̳¢©æ¤È\®IÔxªAÇÒÉÇ꾯®ÍIȴ𠽦é©ÍzÉ Üè éBæOÉAÌȢ̾~âAÌ~ÌI~ÉæÁÄAå«Èâ~Ì´¶ð¤¯A»êªÖ¤Â鳢̥ØÂÉÈéB±±ÉܽY\\JèÌæ¤ÉêåÌA©çéYÅÈAष±µÙ©ÌY̶Üêé]nª éB
ig½ì®¡i1965jj
±ÌwEÍAȪ̽¢uê¼Æ̶ÍÉ¢ÄÌ྾¯ÅÍÈA¬Ñpvi1944jÅåw¶ðÎÛƵ½NÇÌÀ±ÊðàྵĢéƾ¦éBÂÜèAulÍȪÌÓðA³Ó¯É¨¬È¤wÍvðv·éàÌÅ é½ßANÇÉεÄuÍâ¢vÆ´¶é±ÆÍ ÁÄàAu¨»¢vÆ¢¤]¿Í¾çêÈ¢ÌÅ éB
@»µÄA±Ìuष±µÙ©ÌYvÉ¢ÄÍAÌæ¤ÉྷéB
@v·éÉAuê̶ÍÌY´ÍA»Ìå¼ðA]ɨ¤Ä¢é±Æªí©éB±ÆΪA©©êA¢íêÄ¢éƱë©çÅÈÄA±ÆÎƱÆÎÆÌ ¢¾Ì¢Æ±ëA¾t̹çêÈ¢uÔvªAÉxÉp³êÄ¢éÌÅ éB
ig½ì®¡i1965jj
ÂÜèAuê¼Æ̶Íɨ¢ÄÍAȪ³ê½Æ±ëiÇÝèªâíȯêÎÈçÈ¢uÔvjÆA±ÆÎÆÈÁÄ¢éƱëƪuYvƵÄp³êÄ¢éÌÅ éB±êçÌÁ¥ÉÁ¦ÄAg½ì®¡i1965jÅÍAJèêY̶ÍÆuê¼Æ̶ÍÆÅÍA`eip.190jâA¼g\»ª{ÙÇᤱÆàwEµÄ¢éip.195|200jBuê¼Æ̶ÍÌ»êÍAJèêYÌàÌÉä×ÄA»ê¼êñ¼ªÅ Á½Æ¢¤ÌÅ éB±êç½ÇàAuÐï«v©u¨v©Æ¢¤ûü«Ìá¢ð¦µÄ¢éàÌÅ éÆ¢¤B
@Éò³üi1960juuê¼ÆÌAYviwªåwJw\üNLO_¶Wx1960N2jÅÍAuê¼Æ̶ÍÍuAYvÅ éƵÄAÌæ¤ÉwE·éB
ZÑɵÄà{¿ÍPÉ×̳m³Æ¢¤àÌÉÆUÜéàÌÅÍÈ¢Bl¶Ì½éfÊð¦·ÉͪªSÌ̪ƵÄÌÓ¡ð¦·×«Å éB¼ÆÌZÑÉ»êÉߢà̪F³Æ¢¤í¯ÅÍÈ¢ªA½Í©ÈÌÀ¶É§Úµ½ìÒÌuáv̨¦½¢EÅ éB»Ì¢EÍ×ÉĶ«^_µ½oI[Àð¦·B
@»êÍPÉÎÛÌÊ^IÄ»ÅÍÈ¢±Æ;¤àÈ¢B
iºüøpÒBȺ¯¶B
Éò³üi1960juuê¼ÆÌAYvwªåwJw\üNLO_¶Wx
øpÍwú{¶w¤¿W@uê¼ÆxiL¸°1970N6jj
±Ìæ¤ÉAuê¼ÆÌuávÌs³ðu×ÉĶ«^_µ½oI[Àð¦·v¢Eð¨¦éÆwE·éBܽAuê¼ÆÌã\ìÅ éwéÌèÉÄxÌ`ÊÉ¢ÄAÌæ¤ÉwE·éB
iªj»êçÌ`Êͽêà¼ÆÌuávª×ɨ¯éÎÛÌÊ^IÄ»ÅÍÈåÌÉ Ã¯ç꽶«½ÊÀÅ é±Æð¦·Bµ©µ»ÌÊÀª×ÉÀè³êÈ¢ÅA»ÀÌíXÆlÔÝÌÖWðʶÄæèÌ¢EÉs«¾éƱëÜÅ\ªÉè¾È©Â½±Æ;¢¾éÅ ë¤B
iÉò³üi1960jj
uoI[Àvð¦µÈªçàA»êªu¼ÆÌuávvªÆ禽àÌÅ é½ßAuåÌÉ Ã¯ç꽶«½ÊÀvÅ éÆÆàÉAulÔÝÌÖWðʶÄæèÌ¢EÉs«¾éƱëÜÅ\ªÉè¾È©Â½vÆ]·éÌÅ éB»µÄA»êªuê¼ÆÐÆèÌuávÅÆç¦çê½àÌÅ é½ßAÌæ¤Èuê¼Æ̶ÍÌuãȽ_vðàwEµÄ¢éB
¼ÆÌAYª{\I¼ÏIÅåÌIÈ¢Yª èA¯ÉÏIŠ辽Ƣ¤±ÆÍßãú{̶wMdÈàÌÅ éªA»ÌAYªmoIÈ[ÀÉW³êÄAÎÛÌS~Ìc¬Æ¢¤_ÅãȽ_ÍFß´éð¾È¢B±Ì_ð¼Æ̬à̬à«Æ¢¤px©çêûIÉÓßÄA¬àSÛèÆ¢¤å£ÌÝÅͼÆðæèz¦é±ÆÍoÈ¢Æv¤B
iÉò³üi1960jj
umoIÈ[Àvð¦·àÌÅ éªä¦ÉAuÎÛÌS~Ìc¬Æ¢¤_ÅãȽvƵÄAuê¼ÆÌuAYvÌ·ZÉ¢ÄwE·éB
@ܽAràPYi1977ju¼ÆÌAYviwßã¶wS@島wÌxiODsYE|·VY^ÒjLãt1977N9jÅàAuê¼Æ̶ÍðuAYvƵÄÌæ¤ÉwEµÄ¢éB
uê¼ÆÌAYÍêûɾ¤ÈçAuåÏIAYvÆÅྤ׫Š뤩BiªjuêÌû@Í©äâåϪOÊÉo³êAµ©à»Ì©äâåϳ¦àªÆç¦çêé׫ÎÛƵÄqÏIÉ`©êéAÆ¢Á½àÌÅ éB
iràPYi1977ju¼ÆÌAYv
wßã¶wS@島wÌxj
âÍèAu©äâåϪOÊÉo³êAµ©à»Ì©äâåϳ¦àªÆç¦çêé׫ÎÛƵÄqÏIÉ`©êévÆ¢¤uê¼Æ̶ÍÉηé]¿ÍAÉò³üi1960jƨ¨æ»¯¶]¿Å éƾ¦éB
@êûA¿Jsli1972ju¬à̼`«\\uê¼ÆÆúé½viwG§|pxæ23@ukÐ@1972N10jÅÍAuqÏ«vÆuåÏ«vÆð¯ÉËõ¦½Æ³êéuê¼Æ̶ÍÉ¢ÄAuê¼Æ̽Ììiɨ¢ÄµÎµÎdvÆÈéuCªvÆÖíç¹Ä_¶Ä¢éB
ÙÆñÇ·×ÄÌìiªOªOöuålöÌCv é¢ÍuCªvÅÂçÊ©êÄ¢éÌÅ éB޵뱤¢¤×«ÅÍÈ¢¾ë¤©AålöÌuCªvª©êÄ¢éÌÅÍÈAuCªvªålöÈ̾AÆB
@±ê;tÌ»ÅÍÈ¢BÀÛÉuê¼Æ̬àÅÍAuCªvªåÌÈÌÅ éB»±ÅÍuCªvͽµ©ÉÌuCªvÅÍ éªAªL·éàÌÅÍÈADZ©ç©âÁÄ«Äð¢éàÌÅ éB±¤¢¦ÎA¬àÆÍðàÌÅ èGSZgbNżÒð@µ½¢E¾Æ¢¤èàÉw½·éæ¤Éݦé©àµêÈ¢Buê¼ÆÌ¢EÅÍA¾ç©Éu¼ÒvªµÄ¢éªAuvàܽµÄ¢éÌÅA½¾uCªvª·×ÄðxzµÄ¢éÆ¢¤ÜÅÅ éB
iºüøpÒBȺ¯¶B
¿Jsli1972ju¬à̼`«\\uê¼ÆÆúé½v
wG§|pxæ23j
uê¼ÆÌìiɨ¢ÄAuvÆ»êÉγ·éu¼ÒvÆ¢¤Î§ÈA½¾uCªvª 龯¾Æ¢¤B³çÉA»ÌuCªvÌuõvusõvÉ¢ÄÍAÌæ¤ÉྷéB
uêÌusõv;¯ÅÈ çäéàÌÉü¯çêÄ¢éBµ©à»êÍÎÛâ¼ÒÉÓCÍÈAܽuê©gÉàÓCªÈ¢BdvȱÆÍAuêɨ¯éusõvª½ñÈé´îÅÍÈA¢íÎuNÅÈ¢vÆ¢¤¶Ý«ÆÑ¢Ģé±Æ¾Busõvɨ»íê½Æ«AÞÍu©ªÅ é±Ævªë¤ÈÁÄ¢éÌð´¶éBußãlƵÄÌ©äÌm§vÈÇÆ¢¤âèÍA±¤¢¤ë@Éä×êνàÌÅàÈ¢BuvÆÍAÞÌÀ¶ð¨Ñ⩵k¬³¹éàÌÌ\ÛÅ ÁÄAÀÛÌeÆͽñÉεĢ龯ŠéB
i¿Jsli1972jj
v·éÉAuê¼ÆÉÆÁÄuCªvÍâÌâ½ÌàÌÅ èA¼ÒðE·©³àȯêΩÈðE·©Æ¢¤æ¤È{¿ðàÁÄ¢éÌÅ éB
i¿Jsli1972jj
@uê¼ÆÉÆÁÄAuCªvÍu¶Ý«vÆÑ¢½uâÌâ½ÌàÌvÅ éÆ·éB»Ì½ßAuCªvÌuõvusõv¾¯ªAuvÌs®îÅ èA»±ÉÍ¢íäéuåövƵÄÌuvͶݵȢƢ¤ÌÅ éB»êÍuê¼Æ̶ÍÉ¢Äà©©íé±ÆÅ éB
@uê¼ÆÌìiÍ·×ÄuCªvðx[XɵĩêÄ¢éªA»êÍÞÌÓI´îÉõßÊ©êÄ¢éÆ¢¤±ÆðÓ¡µÈ¢B¨»çuê¼ÆÉÍÓ«Í è¦È¢ÌÅ éB¼lÉÆÁÄǤݦæ¤ÆAÞ©gÉÆÁÄuCªvÍÓÅÍÈ¢BÂÜèAíêíêÍuCªvÆu´îvðæʷ׫ŠéBÞÌuCªvÍÂËÉÏI»fðÓñÅ¢éΩèÅÈAÏI»f»ÌàÌÈ̾B
i¿Jsli1972jj
uêÌuCªvÍ»ÌÜÜÏI»fÅ éªA±±ÉÍÇñÈÓ«àåÏ«àÈ¢BuCªvÍÏIÈâΫðÑÑÄ¢éBµ©µAÞ̵¢D«Ì\oÍAIÈåÏIÈâΫðÓ¡µÄ¢éÌÅÍÈA»ÌtÉÞ©gɨ¢ÄÍÞµëu³vðÓ¡µÄ¢éÌÅ éB
@ÅÉAÍuêͼÒð¢Ä¢é¾¯ÅÈð¢Ä¢é̾AÆq×½B½Æ¦Î«Í¼ÒӯŠéBuêÌusõvÉͼҪ¢È¢BusõvªæÉ«ÌÚÁÄé̾BuêÌõEsõÌ\oÍAÓIÈ»fÅÍÈA¢ÂàDZ©ç©âÁÄéàÌÅ éBÞÍ Æ©ç»ÌRðl¦é©àµêÈ¢ªA»êͼÒiÎÛjÉàÞ©gÉ]ŵ¦È¢àÌÈÌÅ éBusõvÆ´¶½Æ«AÞ©gÉà»ÌÓ¡ªí©ÁĢȩÁ½Æ¢¤×«¾ë¤BÀAÞÍusõvÌRÍÙÆñǢĢȢB»Ì©íèAusõvÆ¢¤êêÉAÞÌS¶ÝIÈ»fª±ßçêÄ¢½ÌÅ éBުꩩÈâÎIÅ èȪçA»ÌàÀɨ¢Äu³vÅ Á½Æ¢¤tàÍAܳɱ±É éB
i¿Jsli1972jj
±Ìæ¤ÉAuê¼Æ̶ÍÍAâÎIÈÏI»fƵÄÌuCªvª èA»Ì½ßAuvÌÓ«AåÏ«©çÆêÄ¢éÆ¢¤ÌÅ éB³çÉoÆuCªvÉ¢ÄàAÌæ¤ÉྷéB
¢¢©¦êÎAuê¼ÆÌuAYvÍAið¾É`Ê·éƱëÉàSà¸×ÉLq·éƱëÉà è͵ȢB¨ÆÌÔÉ éuCªvª¾mÉ`Û»³êé̾B»±ÉÓ«ÍÈ¢Bóz̬¶è±Þ]nÍÈ¢B
@Íuêɨ¢ÄuCªvÆIðE»fEs×Ív·éÆq×½ªA¯¶æ¤ÉuCªvÆÞÌoÍv·éÆ¢ÁÄæ¢BÞͯÁµÄ]vÈàÌÍÈ¢ÌÅ éBȺÈçAÞÍ ê±êðÓIÉéÌÅÍÈA¢çêÄé©ç¾BuCªvÉæéÞÌsתÓIÅ éDZë©âÌâ½Å Á½æ¤ÉA»Ìoà¢íÎâÌâ½ÈÌÅ éB
i¿Jsli1972jj
»µÄAuqÏvâuåÏvÆ¢Á½uê¼ÆªuAYvÅ éÆ]³êéÈðÌæ¤ÉAwE·éB
@ÞçÌ©È®«ÍA»Ìu¢Evª¢½KRÅ éBÞçÍ»Ìu¢EvðO¤©çÝéáðà½È©Á½BtÉ¢¦ÎAO¤©çÝé±ÆÉæé¬EBE\áÔðÞçÍÅ©çÜʪêÄ¢½ÌÅ éB»êͽñÉÞçªum¯lvÅÈ©Á½Æ¢¤±ÆÅÍÈ¢BÞçÍÓ¯ª¶Ý¾·è]ÉÖSð¥¤ÉÍA ÜèɾÄȧIÈàÌÉÆçíêÄ¢½Ì¾Biªj
@ÞçÍuv𢽪A»ÌuvÍu¢Evɶ±ßçê½àÌÅ èA»±ÉÍÓ«ª è¦È¢BÁ׫±ÆÍAÞçªÉ¢ľ¯«ÈªçAÓ«ðÜʪêÄ¢½Æ¢¤±Æ¾B©Èðqϵ¢EðqÏIÉÎÛ»µæ¤Æ·é¸_ÍAK¸Ó«iåÏ«jÉÂܸ©´éð¦È¢BqÏ«ÆÍêÂÌ_bÅ èAíêíêÍu¢Evð¢EÆÆè¿ªÄ ¢éÉ·¬È¢B
i¿Jsli1972jj
±±ÅuÞçvÆÍAuê¼ÆÆúé½ÆðwµÄ¢éBuê¼ÆªÓ«ðÆê½ÌÍAuCªvÉæéàÌÅ é©çÆwE·éBuê¼ÆÉÆÁÄAuÏIÈ»fvÅà èâÌâ½Å éA±ÌuCªvÌxz³ê½ìiÉÍAÓ«Í è¾È¢Æ¢¤ÌÅ éB
@ÅãÉJûßqi1977juu½é©vÉݦéuê¶wÌ´^viwÉì¶xæ11@1977N3jðæèã°éBJûßqi1977jÅÍAuê¼Æ©gªuìvÆÊuïĢéw½é©xÉ¢ÄÌæ¤É]·éB
@±±ÉÍ©½àÌÈO]vÈàÌÍêØÈ©êÄ¢éÌÅ é©çA»Ìs¢JbgÉæèc³ê½àÌA¦¿`«o³ê½àÌÍÀÉm©É»µÄNâ©ÉÚÉ©ÑA»Ì`ÛðʵÄålöÌSÌÚªóÛïçêéÌÅ éB±ÌêÑÉ©½àÌð©½ÊèɶXµÄ»·éuê¼ÆÌVÌ˪»êÄ¢éÆvíêéB
iºüøpÒBȺ¯¶B
Jûßqi1977juu½é©vÉݦéuê¶wÌ´^v
wÉì¶xæ11j
±Ìæ¤ÉAw½é©xÉuê¼ÆÌuVÌËvð©oµ½Ì¿Auê¼Æ̶ÍÉ¢ÄÌæ¤ÉàwE·éB
@µ©µåØÈÍ»ÌuávÉx¦çê½uê¶wÍPÉoIvfÌZ¢ÀĻ̶wÉInµÄ¢éÌÅÍÈA»ÌãÉSÄÌÛðåÏÌ´îÉïÝüêSî»·éAܽ»¤o¾é´îÌשȮ«ªíɢĢéÆ¢¤Å éB·¾·êÎÞÌuávͨ𶫶«Æ³mɨ¦éΩèÅÈA»êƤɻÌXÌC¿ª çäéÖA«ðÑÑĨ¦çêÄ¢éÌÅ éB±ÌC¿ÉæÁÄÂXÌoIfªêÂÉÈéÉÂȪêAÇÒÉ¿lðÑÑÄèAàu¶wvÆæÎêéàÌÉßçêéÌÅ éBÞµëA»Ìæ¤ÈC¿Ì«ÉæÁı»A»êçÌofª¶©³êÄ¢éƾÁÄàß¾ÅÍÈ¢B½Í©ÈÌÀ¶É§ µ½ìÒÌuáv̨¦½¢EÍA×ÉĶ«¶«µ½oÌ[À𦷪A»êçÌ`ÊÍÎÛÌPÈéÊ^IÄ»ÅÍÈåÏÌ¢½¶«½ÊÀ Å éB±Ìuê¼ÆÉÆÁÄÍAu©évÆ¢¤oI®ìͦul¦évÆ¢¤vlI®ìÉÂȪéBÂÜ袩Éæu©v½Ûðo¦Ä¢é©A»ÌmÀ³Í»ÌÌSIàeÌm©³Å èA©½àÌÆ»ÌÌSÌóÔƪsªÈàÌƵĶݷéí¯Å éB
iT_´¶BȺ¯¶B
Jûßqi1977jj
uê¼Æ̶Íɨ¢ÄAu©½àÌð©½ÊèɶXµÄ»·évÆ¢¤uáv̳m³ÍAu»êƤɻÌXÌC¿ª çäéÖA«ðÑÑĨ¦çêÄ¢évÆ¢¤B»êÍ·Èí¿Auê¼ÆÉÆÁÄAuu©évÆ¢¤oI®ìͦul¦évÆ¢¤vlI®ìÉÂȪév½ßAu©évÆul¦évƪsªÈàÌÅ éÆl@·éB»µÄÌæ¤ÉàwE·éB
ÂÜèAuz¤vÆ¢¤´îÆu×·vÆ¢¤s®ÆÍêÌÆÈÁÄ¢éÌÅ èAÞÌu©ävªà´îEs®êÌÆ̳궫éȪ±±É éBÌìiÉÍuCªvuC¿vÈÇÆ¢¤¾tÅ©ÈÌuÀ´vð\»·éÆ¢¤±ÆªÉßÄpÉÉÝçê骻êÍ»ÌÜÜuê¶wðzãÌåØÈè@̪{Å éÆv¦éB
iJûßqi1977jj
±Ìæ¤ÉAuz¤vÆu×·vƪêÌÆÈÁÄ¢éƱëÉAuê¼Æ̶Íɨ¯éuè@̪{vÅ éÆ¢¤B»êä¦Aw½é©xðͶßÆ·éuê¼ÆÌìiÍAuålöÌ´îvÌݪ`©êÄ¢é̾Æ_t¯éB
æOÒIÉ©ç«IAqÏIÉèð©ÂßÂÂ`Æ¢¤Íuê¶wÆͳÈÌÅ éBÌÉu½é©vÌcêà«ÂßêÎÞ̼gÅ éÆྦæ¤BÞÌìiÌoêl¨ÍSÄålöæ謳AƧµ½liðàÁĶݷéð³êĢȢÌÅ éBÉIÉÍAÞ̶wÉÍuê¼ÆÆ¢¤êÂl̴`©êĨç¸A¼Ìl¨ÍƧ«A©å«ð½¸ÉålöÌ´îÆuõv é¢Íusõvðà½ç·}ÌƵĵ©`©êĢȢÆl¦çêæ¤BM¾Yª°èɾñÅ¢¼Ìõ´ðjQ·écêÌÄÑ©¯A±êðKvƵĢé»ÀÌlqÉ¢Äͽ¾ÞÌ´îðG·éðƵÄÌÓ¡ðÂÉ·¬¸A¼Ì»À»ÌàÌÉ¢ÄÍwñÇÞÌÓ¯ÉfÁıȢÌÅ éB
iJûßqi1977jj
@¿Jsli1972jÅÍAuCªvÌݪåÌ«ðàÂâÌâ½ÌàÌÅ é½ßAu©È®«vðÛ¿AÓ«©çÆê½Æ¢¤wEÉεÄAJûßqi1977jÅÍAuìiÌoêl¨ÍSÄålöæ謳AƧµ½liðàÁĶݷéð³êÄv¨ç¸AìiS̪Auê¼ÆðééƳ¹éuålövÌuvlI®ìvÌÝÅxz³êÄ¢éÆ¢¤ÌÅ éB
@ÈãÌæ¤ÉAuê¼Æ̶ÍÉ¢ÄÌæs¤ðÝÄ«½B¬Ñpvi1944jÅÍAuê¼Æ̶ÍÍu¨ÌYvÅ èAuWJÈÂȪèvðà½È¢±Æ©çAÇÝèÍA¶Æ¶ÆÌu^ónÑvðßÄ¢Kvª éÆwEµÄ¢½B
@ܽg½ì®¡i1953jA¯i1965jÅÍAJèêY̶ÍÆärµÄAu¦¨I«ivðà¿A¾tÌj
AXÅÍÈu¨vâu¨vuvÉ»Ìûü«ª éƳêÄ¢½B»µÄA¼ª½AZ¶Å èA`eâ¼g\»ªµÈ¢±ÆðªÍÊƵÄñ¦µAu̾^̶ÍvÅ èAu¨ÖÌûüvÆ¢¤î{ûüð¦µÄ¢éÆྵĢ½B±êÍAu¨ÌYvÆ]·é¬Ñpvi1944jƤʷé_ª½¢àÌÅ Á½B
@êûAÉò³üi1960jÅÍAuAYvÅ éuê¼Æ̶ÍÍAuê¼Æ©gªÆ禽uávÉæÁÄAu×ÉĶ«^_µ½oI[Àv𦷶ÍÅ éÆwEµÄ¢½B»êƯÉAu»ÌAYªmoIÈ[ÀÉW³êÄAÎÛÌS~Ìc¬Æ¢¤_ÅãȽ_ÍFß´éð¾È¢vÆ¢¤uê¼Æ̶ÍÌuãȽ_vðàwE·éàÌÅ Á½BràPYi1977jÅÍAuê¼ÆÌuAYvÍAu©äâåϪOÊÉo³êAµ©à»Ì©äâåϳ¦àªÆç¦çêé׫ÎÛƵÄqÏIÉ`©êévÆ¢¤uåÏIÈAYvÅ éƵĢ½B
@¿Jsli1972jÅÍA±¤µ½uåÏvuqÏvÆ¢¤ñΧÅÍÈAuCªv©çuê¼Æ̶Íðl@µÄ¢½BuâÌâ½v³ðàÁ½uCªvªålöÆÈèAÏIÈ»fðºµAuIðE»fEs×vA»µÄ»êÍuovÆàv·éàÌÅ éÆ·éB»Ì½ßu³vª¬§µAu¢Evɶ±ßçê½uvÍAuvÆ¢¤Ó«©çÆêÄ¢½Æ_ïéB
@Jûßqi1977jÅÍAuÞÌuávͨ𶫶«Æ³mɨ¦éΩèÅÈA»êƤɻÌXÌC¿ª çäéÖA«ðÑÑĨ¦çêÄ¢évƱëÉAìÆEuê¼ÆÌÁ¥ðÆç¦æ¤Æ·éBuu©évÆ¢¤oI®ìͦul¦évÆ¢¤vlI®ìÉÂȪévÌÅ èAuuz¤vÆ¢¤´îÆu×·vÆ¢¤s®ÆÍêÌÆÈÁÄ¢évÆ¢¤ê«ðwEµÄ¢½B»±ÉÍAu¼Òvª¶Ý¹¸Auê¼Æêl̴`©êȢƵĢ½B
@¾ªA±ÌJûßqi1977jÌwEÍA\»Å é¬àêÊÉ ÄÍÜé±ÆÅÍÈ¢¾ë¤©B¬àªA«èÉÓ}³ê½\»Å éÈãASÄ̬àÉ¢ÄAu`ÊÍÎÛÌPÈéÊ^IÄ»ÅÍÈåÏÌ¢½¶«½
@ÅÍA»Ìæ¤Èuê¼ÆÌìiÌÁ¥ÆÍAÇÌæ¤ÈàÌÈÌŠ뤩B{¤ÅÍA±Ìuu©évÆ¢¤oI®ìͦul¦évÆ¢¤vlI®ìÉÂȪévÆ¢¤uê¼ÆÌìiÌÁ¥É¢ÄAuê¼ÆÌ_Ìzâq@Æ¢Á½\»Ì¤Ê©çªÍEl@·é±ÆÅA¾ç©Éµ½¢B
@ܽA¬Ñpvi1944jâAg½ì®¡i1965jÈÇÅwE³êÄ¢½u¨ÌYvâu¦¨I«iv̶ÍÆÍAêÌÇÌæ¤È¶ÍÅ éÌ©AìiÌàe\åèâ\¬Aq\ÉÖíç¹Äl¦éKvª é¾ë¤BæQÍÌOÂÌìiªÍðʵÄA±êçæs¤ÌwEÉ¢ÄïÌIÉl@µÄ¢B
æQßæPÅÍA__É¢ÄÌæs¤ð®·éB
@ܸAFmÈw̪ìɨ¯éæs¤ÆµÄ{è´FEãì¼÷i1985jwFmÈwI@_xiåwoÅï1985N10jðÝéBÉê³çɨ¯é__ƵÄA¼½|FÌ__ðÝéB»µÄÅãÉA{eÌu_ÌzvÆ¢¤l¦ÌàÆÅà é¡ä¶jÌ__ðAuz_vÆ¢¤l¦ûðSÉ®·é±ÆÆ·éB
@»ÌãAæQƵÄ{eɨ¯é¾tÌè`ð·éÆ¢¤\¬ðÆéB
@{è´FEãì¼÷i1985jiwFmÈwI@_xåwoÅï1985N10jÍAñ\¬ÉÈÁÄ¢éBuTD_̵ÝvƵÄAlÔª¨ð©éÆÍǤ¢¤Í½ç«ð¢¤Ì©AÆ¢¤lÔÌFm¨¯é_É¢Äl@µÄ¢éB»µÄuUD_Ì«\æè[¢ðÖü¯ÄvƵÄA¶wìiɨ¢ÄA©éÆÍǤ¢¤«Å éÌ©AÇÞÆÍǤ¢¤±Æ©AÆ¢Á½±ÆðFmÈwÌÏ_©çl@µÄ¢éBTÍãì¼÷ªAUÍ{è´Fª»ê¼ê·MµÄ¢éB
@ܸT©çÝÄ¢B
úí¶ÌÅÍA½¿Í¨ðæ©æ¤ÆµÄA½¦¸ñðX¯½èAgÌðÚ®³¹é±ÆÉæÁÄ_𮩵ÂïĢéÌÅ éB
@}NÌxÅ_𮩷±ÆÉæÁÄ©¦éàÌÍAâÍèXibvVbgÌæ¤ÈàÌÅÍÈAÏ»â¬êÌp^Æ¢Á½àÌÅ ë¤BÂÜèA~NÌxÌÝÈç¸A}NÌxÅàA½¿ÍAÏ»ð©éÅAÎÛªÇÌæ¤ÈàÌ©ÁèµÄäÌÅ éB
i{è´FEãì¼÷i1985jwFmÈwI@_x@p.9j
@±Ìæ¤ÉAu©évÆ¢¤±ÆÍA éàÌÌâ~µ½óÔÅÍÈAÇÌæ¤ÉÏ»·éÌ©AÆ¢¤©éÎÛÆA©éåÌÆÌÚ®âÏ»ÌlÉæÁÄAuÎÛªÇÌæ¤ÈàÌ©ÁèµÄävÆ¢¤B»µÄA©¦Ä¢½Rª©¦ÈÈéÆ¢¤Ï»É¢ÄAÌæ¤ÉྷéB
µ©µA©¦ÈÈÁ½RÍA»±É¶ÝµÈÈÁ½RÆ;ç©ÉÙÈÁ½àÌƵÄmo³êéÌÅ éB_𮩷±ÆÉæÁÄA»ÌRª©¦ÈÈÁ½Æ¢¤±ÆÍAPÉ»ÌRªÔ©çÁ¦½Æ¢¤±ÆƯ¶ÅÍÈ¢B¡ÜÅ©¦Ä¢½ÎÛÌ©¦ÈÈèû A é¢Í»êª©¦ÈÈÁ½±Æ ÍA»êÍ»êŧhÈîñÅ èAPÉZXEf[^ª¶ÝµÈÈÁ½Æ¢¤±ÆÅÍÈ¢ÌÅ éB
@©é±ÆÍAXibvVbgð©éÆ¢¤±ÆÈÌÅÍÈA©¦BêÌvZXð©éÆ¢¤±ÆÈÌÅ éB é¢ÍAE©çÁ¦é»ÌÁ¦ûð©éÆ¢¤±ÆÈÌÅ éB
iT_´¶BȺ¯¶B
{è´FEãì¼÷i1985j@p.28j
@ÎÛª©¦ÈÈéAÆ¢¤±ÆÍAPÉÎÛªE©çÈÈÁ½Æ¢¤ÌÅÍÈAu¡ÜÅ©¦Ä¢½ÎÛÌ©¦ÈÈè
@{è´FEãì¼÷i1985jÅÍAlÔªÎÛðFm·éÆ«Ìu_vðñÂÌ_ª éÆ¢¤B»êªu®IÈ_vÆuÃIÈ_vÆ¢¤ñÂÌu_vÅ éB
@®I_ÆÍA¶ÊèA®«Â é_̱ÆÅ éB©éÆ¢¤±ÆÍAî{IÉÍ®I_Ì®ÉÙ©ÈçÈ¢B¯¶±ÆÍTOIÈðÉÖµÄྦé¾ë¤B®I_ª©éàÌÍAÎÛÌÇÌ_©çÌ©¦ÆàA é¢ÍAÇÌæ¤ÈÂÊIÈáÆàεȢB±±Å©çêéàÌÍAè`iformjÅÍÈA_𮩷±Æɺ¤sè`È©¦ÌÏ»ÌvZXÆ¢Á½àÌÅ ë¤B
i{è´FEãì¼÷i1985j@p.53|54j
@êûAÃIÈ_ÆÍA ÜÅ®IÈ_ÌrãɶݷéàÌÅ éBÂÜèAÃIÈ_ÆÍA®¢Ä¢érŧ¿~ÜÁ½Æ¢¤óÔÉÙ©ÈçÈ¢Bµ½ªÁÄA½Æ¦ÃIÈ_©ç©éÆ¢¤Æ«Å³¦AXibvVbgEf̾¤æ¤È`iformjð©Ä¢éÌÅÍÈA½ç©ÌÏ»âÏ`Ìrãð©Ä¢éÌÅ éB é¢ÍArãƵÄÌg`hð©Ä¢éÌÅ éB
i{è´FEãì¼÷i1985j@p.54j
»µÄA±êçÌ_ðÌæ¤ÉÜÆßÄ¢éB
ÜÆßľ¤ÈçA®I_Ͷ¬IÅ èAêûÃI_Í®I_Ì®ÉæÁĶÝo³êéÂÊIÈA é¢ÍáIÈ_¾Æ¢¤±ÆàÂ\Å ë¤BÂÜèA®I_ÍA_Ìϻɺ¤ÎÛÌ©¦ÌÏ»Ì èûð©éÌÉεAÃI_ÍA»¤µ½A±IÈÏ»ÌrãÉ éÎÛÌêÂÌ©¦ûÌáðȪßéÆ¢¤í¯Å éB
i{è´FEãì¼÷i1985j@p.55j
@±¢ÄAU̶wìiðÇÞÆ«Éͽçu_vÉ¢ÄÌl@ðÝÄ¢B{è´FEãì¼÷i1985j¶wìiðÇÞAÆ¢¤s×ÍAȺÌå«ñÂÌ«ÉæéàÌÅ éÆྷéB{è´FEãì¼÷i1985jÅÍA¼ÒÅ é¶wìiÌìl¨ÉεÄA¤´IÉð·é±ÆðAu¼zI©Èðh·évÆÄÑȪçྵĢéB
@g©éh«ÆgÈÁÄhÝé«ÌñÂðêIÉÆç¦éÉÍAÌæ¤Él¦ÄÝéÆí©èâ·¢¾ë¤Bg©éh«ÍA¢íμzI©ÈÌgáhÌ«Å éB±êÉεÄA¼ÒÉgÈÁÄhÝé«ÍA¼zI©ÈÌà¤Ì«Å éB±Ì¢¢ûðg¦ÎA½Æ¦Î éÚIðàÁ½¼ÒÉ_ðÝè·éÆÍA±Ì¼Òɽ¢µÄ¼zI©ÈðhµA»Ìà¤É¼ÒÌÚI𶬵ÄÝéÆ¢¤±ÆÅ éB
@±Ìæ¤Ég©éh«ÆgÈéh«ª¯¶¼zI©ÈÌ«¾Æ·êÎA±ÌQÂÌ«ª¯É¨±èAÝ¢Ée¿µ ¤Ô̶Ýà\z³êéB½Æ¦ÎA éÚIðàÁ½¼ÒÉ_ðÝè·éêðl¦ÄÝæ¤B±ÌÆ«A»Ì¼ÒÌàÁÄ¢éÚIâÓ}ðªµA¼zI©ÈÌà¤É¶¬·é±ÆÉæÁĻ̼ÒÉgÈÁÄhÝÄA»êÉæÁijçɻ̼ÒÌgáhÅ¢Eðg©ÄhÝéA±±Å½¿Ìpêðg¦ÎA¼ÒÌ©Ä¢éq©¦r𶬷éAÆ¢¤ßöª è¤é¾ë¤B
i{è´FEãì¼÷i1985j@p.133j
±Ìæ¤ÉAìl¨ðu©év«ÆAìl¨ÉuÈév«ÉæÁÄAlͶwìiðÇÞÆ¢¤ÌÅ éBlÔªA¼lÌ¢½àÌÅ é¶wìiÌÌAìl¨ÌC¿ÉÈÁÄÇÞÆ¢¤ÌÍAu©év«ÆAuÈév«ÉæéàÌÅ éÆ¢¤Bµ©µAPÉuÈévÆ¢¤¾¯Åìl¨ÌSîÉuÈévÆ¢¤ÌÅÍÈ¢ÆྷéB
@¾ª±±ÅÍA¢ë¢ëÈû@Ì©çA_Ìg©éh«Æà§ÚÉÖAµ½PÂÌðûªÉÅ_ð ÄA»êÉ¢Äl¦Ä¢±Æɵæ¤B»êÍA¼ÒÌSîðð·éÉ ½ÁÄAܸ»Ì¼ÒªÞÌÜíèÌ¢EÉ¢ÄàÁÄ¢éÅ ë¤Þ©ç©½q©¦r𶬵ÄÝéAÆ¢¤âèûÅ éB±êðq©¦ræsûªÆæÔ±Æɵæ¤B
i{è´FEãì¼÷i1985j@p.139j
uÈév«ÍAPÉ»Ìuìl¨ÌC¿ÉÈévAÆ¢¤ÌÅÍÈA»Ììl¨ª»ÌüèðÇÌæ¤É©Ä¢éÌ©AÆ¢¤±Æðu©év±ÆÉæÁÄ»ÌàÊðð·éÌÅ éÆ¢¤B±êðuq©¦ræsûªvÆÄÑA¶wìiÌìl¨ÌSâSîðÇÞ¤¦ÅAdvÈu_vÌ«ÌêÂÅ éÆ·éB
@±Ìæ¤ÉÎÛª¯¶Å ÁÄàA»ÌÆ«ÌSîɶĩ¦ª·ÙðàÂÈçÎA¼Òððµæ¤Æ·éÆ«A½¿ªÞ̩Ģ驦Ìà·ÙðmèA»Ì©¦ð¶¬Å«êÎA»±©çÞÌSîÌ èûÉ¢ĪµÄ¢±ÆªÅ«é¾ë¤BÂÜèA±Ì©¦Ìà·٪ASîÉÖ·é_ÁèîñÉÈéÌÅ éB
i{è´FEãì¼÷i1985j@p.152|153j
ÎÛÌ©¦ûÌá¢ðð·é±ÆÉæÁÄAìl¨ÌSîÜÅð·éiª·éj±ÆÉÂȪéÌÅ éwE·éB»êÍAÌæ¤ÈàÌÅ éB
@½¾±±ÅdvȱÆÍA±ÌöÊIÈ_ÁèîñÌÝðàÁ½©¦ð¶¬·é¾¯ÅÍA[¢¼ÒðÉB·é±ÆªÅ«È¢êªÙÆñÇÅ éÆ¢¤±Æ¾B¼ÒÉe¿ð^¦Ä¢é¨AoðÁèÅ«êÎA¼Òðª\ªÂ\Å éæ¤Éê©Ý¦éÔÅàA»Ì¨Aoª¼ÒÉæÁÄÇÌæ¤É©¦Ä¢é©ðmçȯêÎA[¢¼ÒðÍÅ«È¢ÌÅ éB
i{è´FEãì¼÷i1985j@p.155j
±Ìæ¤È¶wìiɨ¯éìl¨ÌðÌvZXðAVFCNXsAÌwnbgxðáÉÆÁÄÌæ¤ÉྵĢéB
@½Æ¦ÎnbgÌáÅ¢¤ÈçÎA»ÌðßöͱñÈàÌÅ ë¤Bܸ½¿ÍYÈðÇÞÅA½ÆàTO»³ê½nbgÌSîðð·éB»µÄ»êÉàÆâÄÞªàŠ뤩¦ðAÆÉà©ÉඬµÄÝéB»µÄ³çÉ»êðîµÄAïÌIAÀ´IÈSîÉÖ·ém¯ð³ªµA»êðgÁÄnbgÌSîðïÌIɵĢB»µÄ»ÌSîÉàÆâÄA©¦ð³çÉôûµAæèKØÈàÌƵĶ¬³êÄ¢B±Ìæ¤È©¦ÆSîÆÌÔÌ^®ðƨµA©¦ÍæèKØÈàÌÉÈèASîàæèÀ´IÉÈÁÄ¢ÌÅ éB
@±êðæèêÊIÉ¢¦ÎAKØÈ©¦ª¶¬Â\ÈêÂÌOñðÍAq©¦ræsûªªÜ¸®àøÈ©¦ð¶¬µA»±©çSîðð·éÆ¢Á½êûüIÈàÌÅÍÈA»êªoûüIÈàÌÅ éÆ¢¤±Æ¾BoûüIÈßöªs³êéÅASîªïÌIAÀ´IÉÈ龯ÅÍÈA©¦àæèKØÈàÌðß´µÄÏíÁÄ¢ÌÅ éB
i{è´FEãì¼÷i1985j@p.172|173j
@êûA¼½|FÌ__É¢ÄÍA¼½|Fi1975jw¼½|F¶|³çìW17@¶|wuÀiTj_E`ÛE\¢xi¾¡}oÅ1975N9jªÚµ¢B¼½|Fi1975jÅÍAu¶|ìivɨ¯é_ðÌæ¤ÉKèµÄ¢éB
_Æͽ©
@¶|ìiÍ·×ÄiAU¶AYÈÈÇWÌ¢©ñðâí¸j éêèÌ_ð}îƵÄ\»³êĢܷBµ½ªÁÄSÄ̶|ìiÍ_ð}îÆ·é±ÆȵÉͳµ[»êðÇÝÆé±ÆÍūܹñB
iÌÍ´¶ÉæéBȺ¯¶B
¼½|Fi1975jw¼½|F¶|³çìW17
¶|wuÀiTj_E`ÛE\¢x@p.338j
±Ìæ¤ÉKèµA¼½|Fi1975jž¤u_vÆÍu¾êÌá©çvuDZ©çv`¢Ä¢éÌ©AÆ¢¤âèÅ éÆ·éBµ©µA»Ìu_vÆÍAPÉìiྯÌâèÅÍÈA»ÌìÒƧÚÉÖíéàÌÅ é±ÆàmFµÄ¢éB
Ï_Æ_
@Ù©ÈçÊ»Ì_©ç¦çÎê½Æ¢¤±ÆÍlÔɽ¢·éA¢Eɽ¢·éìÒÌlÔÏAl¶ÏA¢EÏAܽ|pÏÈÇAÂÜèìÒÌÏ_ÉàÆÃàÌÅ·Bµ½ªÁÄAÇÒÍ»ÌìiÌ_Ì è©½ÉæÁÄìÒÌÏ_ðÆç¦é±ÆàÂ\ÆÈèÜ·B
@Èw̶ÍA é¢Íê³çÅ¢¤Æ±ëÌྶÍAqÏIÈ_iàµÍ³lÌÌ_jðÆéàÌÅåÏðr·éƱëÉÆÁÈ«iª èÜ·B
¶|̶ÍÍi¶|Ì`ÛÍj_ÌÝèÉæÁÄAìÒÌåÏÆqϪÙØ@IÉ~gê³ê½àÌÅ·B
iºüøpÒBȺ¯¶B
¼½|Fi1975j@p.339j
_ÌÝè
@ìÒÍÎÛð\»·éÆ«ÉA¬Ìæ¤È_ðÝèµÜ·B
@êlÌÌ_ÌÎ ¢A»ÌlÌ̱ðq×éàÌÆAÍÐîÒAbÒƵÄA¼ÒÌ̱ðÇÒÉêè`¦éÆ¢¤àÌÆ èÜ·B
@ñlÌÌ_ÍAêÊIÉÍܾìi»³êĢܹñªÅßtXÈÇÅ»ÌݪȳêĢܷB
@OlÌÌ_ÉÍÎÛðOªí©çÜÁ½qÏIÉ`Ê·éqÏÌ_ÆAìÌ éÁèÌl¨Ì_Æêv³¹½ÀèÌ_ª èA³çÉAÎÛðO©çAܽà©ç©ÝÉiÆ¢¤±ÆͽʫíßÄ ¢Ü¢ÉÆ¢¤±ÆÅà èÜ·ªj`«¾·SmÌ_ƪ èÜ·BiªjOlÌSmÌ_Í´zÒÌ_A_Ì_Æà¢íêÜ·B
i¼½|Fi1975j@p.339j
u¶|ìivɨ¯éAu_vÍAuêlÌvÆuOlÌvÆÉܸñª³êAuOlÌvÍuSmvuÀèvuqÏvÆ¢¤Oíª éÆ·éBuêlÌ_vÆÍAêlÌÌêèèÉæÁÄêçêéìiÅ éBuvâulvu©ªvÆ¢Á½êlÌÌìl¨ÆµÄìiàÉoê·éàÌÆAìl¨ÆµÄÅÍÈPÉêèèƵÄÌÝoê·éàÌƪ éÆ¢¤B
@uSmvÆÍA¢íäéu_Ì_vÅ èA·×ÄÌìl¨ÌàÊð©Ê·u_vÅ éBuÀèvÆÍAêÌÁèÌìl¨ÌàÊ©çÌÝ`©êé_ðw·BuqÏvÆÍAìl¨ÌàÊ©çÍ`©¸ÉASÄìl¨ÌOÊ©ç`Æ¢¤ìiÅ éB
à©çÌ_AO©çÌ_
@·×ÄÌ_ðÍA±ÌñÂÌ_ÉæÁĪ޵ܷB½Æ¦ÎêlÌÌ_ÌêÍAÈél¨ÌáðƨµÄ¢EðȪßéàÌÅAµ½ªÁÄAÈél¨ÌàÊð®Á½A é¢ÍÌåÏÉÊçê½¢EÆ¢¦Ü·ªA±ÌÎ ¢Ì_ðà©çÌ_ é¢ÍªµÄáàÌÚâƼïܷBOlÌqÏÌ_ÍO©çÌ_ é¢ÍªµÄáOÌÚâƼïܷBOlÌÀèÌ_ÍÁèÌl¨ÌàÊðƨ·ÆÆàÉ»Ìl¨ðO©çà`_Å ÁÄA½Æ¦Ä¢¦ÎOlÌÌqÏÆåϪê³êÄ¢é_Å·B±ÌÎ ¢áàÌÚâÆáOÌÚ⪩³ÈÁ½àÌÆ¢¦Ü·BOlÌSmÌ_ÍÁèÌl¨¾¯ÅÈ·×ÄÌoêl¨ÌuàÆOvðÆç¦é_Å·Bµ©à»êÍáàÌÚâÆáOÌÚâªA éÆ«ÍuæÊv³êA éÆ«Íu©³ÈèvAܽ½ÌÎ ¢u ¢Ü¢vÆÈèÜ·B
i¼½|Fi1975j@p.339|340j
±Ìæ¤ÉAuàÌÚvÆuOÌÚvÆ¢¤ñÂÌ_ÉæÁÄAu¶|ìivðÇÞÆ¢¤B¼½|FÌ__ÅÍA±ÌuàÌÚvÅu¶|ìivð̱·é±ÆðAu¯»Ì±vÆæÑAuOÌÚvÅ̱·é±Æðuٻ̱vÆÄÔBu¶|ìivÌÙÆñÇÍA±ÌñÂÌÚiu_vjªÝÉÖíè ¤±ÆÉæÁÄAÇÝ··ßÄ¢±ÆÉÈéB±ÌñÂÌÚªÖíèȪçu¶|ìivð̱·é±ÆðAu¤Ì±vi é¢Íu¶|̱vjÆÄÔB
@±Ìu¯»Ì±vAuٻ̱vÆ¢¤æÊÍA{è´FEãì¼÷i1985jÅuÈév«ÆAu©év«ÆÉæÁÄìiðÇÞÆ¢¤wEƤʷéàÌÅ éƾ¦éB·Èí¿A¨¨æ»ÈºÌæ¤È¤Ê_Å éB
| ¼½|FÌ__ | {è´FEãì¼÷i1985j | |
| ¯»Ì±iuàÌÚvÉæé̱j | cc | u¼zI©ÈvÌuÈév«Éæéð |
| ٻ̱iuOÌÚvÉæé̱j | cc | u¼zI©ÈvÌu©év«Éæéð |
@{è´FEãì¼÷i1985jÅàA¼½|FÌ__Åà¤ÊµÄ¢éÌÍAìl¨ÌàÊiSASîAC¿ÈÇjð`±ÆªuÈév«AuàÌÚvÉæéu¯»Ì±vÈÌÅÍÈAàÊ©ç`±ÆªuÈév«Éæéìl¨ÌðÅ èAu¯»Ì±v·éÆ¢¤±ÆÆྵĢé_Å éBu½ðv`¢Ä¢é©Æ¢¤âèÅÍÈAuN©çv é¢ÍuDZ©çv`¢Ä¢éÌ©AÆ¢¤u_vÌâèðdµÄ¢éÌÅ éB·¾·êÎA©çêéÎÛÅÍÈA©éå̪__ÅÍdvÅ éÆ¢¤±ÆÅ éB
_l¨
@_ðÝè³ê½l¨ð_l¨Æ¼Ã¯æ¤BiêlÌÌ_É ÁÄÍqr ª_l¨Å·B¨êÉ ÁÄÍbÒª_l¨ÆÈèÜ·Bj
_l¨Ìð
@_l¨É¦çÎêél¨ÍAìÒÌÏ_AÂÜèÍìiÌåèÆvzð`Û»·é½ßÉKvÈððà½ËÎÈçÈ¢BðÆÍA_l¨Ì«iA¶AvzA§êÈÇÅ·B
@_l¨ÌáiåÏjðƨµÄ©çê½l¨iÎÛl¨A é¢ÍÅ_l¨Æ¢¤jâ¢EÍAµ½ªÁÄ_l¨ÌðÉæÁÄKè³êéàÌÅ·B±Ì±ÆÍA_l¨ÌåÏÉæÁĽf³ê½qÏÌ¢EÆ¢¤±ÆÅ·BiåÏÆqÏÌÙØ@I~gêƵÄ̶|`Ûji_ðvYƵÄÆç¦çê½A\»³ê½AqÏI»ÀÌåÏI½fj
i¼½|Fi1975j@p.341j
»µÄAu_vªu©ê½ìl¨ðu_l¨vÆÄÑA»êÈOÌl¨ÆæʵĵÁÄ¢éB±Ìu_l¨vðʵÄAìiÌâoðu¤Ì±v·é±ÆÉÈéÌÅ éB³çÉA©éu_l¨vÆA»Ìl¨É©çêéuÎÛl¨vÆÌÖWðÌæ¤É¦µÄ¢éB
_l¨ÆÎÛl¨iÅ_l¨j
@_l¨ÉæÁÄ©çêÄ¢é̪íÌl¨ðÎÛl¨iÆÉ»ÌSÆÈél¨ðÅ_l¨jÆ¢¢Ü·B_l¨ÆÎÛl¨Í»Ì`ÊE\»ÌãŬÌæ¤È¿ª¢ª èÜ·B
@_l¨É½¢µÄÎÛl¨ðålöƼïé_Òª éªëèÅ·BìiÉæÁÄ_l¨ªålöÅ éÎ ¢AÎÛl¨ªålöÅ éÎ ¢A é¢Í¼ÒÆàÉ¡IÉålöÆl¦çêéÎ ¢ÈÇA³Ü´ÜÅ·Biªj
@ÎÛl¨ÌàÊðImÉ`«¾·½ßÉÍA»Ìl¨ð_l¨ÆµÄ]·i«è©¦j·éû@ª èÜ·BÂÜè©éªíÆ©çêéªíÌÖWðt]·éû@Å·Biªj
@_l¨Ìði«iEvzB§êccjÌÏ»EWÉÆàÈÁÄBÎÛÌÆ禩½ªÏ»EW·é±ÆÍà¿ëñÅ·BÂÜèAÎÛl¨âÎÛÆÈé`ÛÆÈé©RÈÇÌ`Ûª¿ªÁ½àÌÆÈÁÄ«Ü·B
i¼½|Fi1975j@p.341|342j
±Ìæ¤ÉAu_l¨vÌàÊÍæ`©êéêûÅAOÊÍÆç¦ÉAuÎÛl¨vÌOÊÍæ`©êéêûÅAàÊÍÆç¦É¢AƵĢéB
@±Ìæ¤É¼½|FÌ__ÅÍAu¶|ìivðð·éêÌdvÈvfƵÄA»Ì¶â¶ÍªÇ±©çiN©çjAÆç¦çê½i`©ê½jàÌÈÌ©AÆ¢¤u_vÉÚµ½àÌÅ éB
@¡ä¶ji1975jw¶Í\»@åvxi}Ô@1975N4jÅÍA¶Í\»ð¨±È¤\»·éßöƵÄAu_vªÖíÁÄ¢éÆ·éBܸAu\»vÉ¢ÄÌæ¤É®·éB
@½©ð½©Å çí·±Æðu\»·évÆ¢¤Bu½©ðvÆÍA©½±ÆA·¢½±ÆA´¶½±ÆAl¦½±ÆXð³·B»êðu½©Åv çí·ÌÅ éB¹y͹Šçíµ½àÌÅ èAGæÍüâFÅ çíµ½àÌÅ éBu çí·vÆÍAÍÁ«èí©éæ¤ÉOÉÅ¿o·±ÆÅ éBOÉÅ¿o³ê½àÌÍu©½¿vðàÂB
@±Ì±ÆðÊ̱ÆÎÅ¢¢©¦éÆA¬Ìæ¤ÉÈéBu½©ðvª\»ÎÛAu½©Åvª\»èiAu çí·vª\»s×AOÉÅ¿o³ê½u©½¿vªìiAìiðÅ¿o·å̪\»åÌÅ éB\»åÌÍÓuðàÁ½¶ÝÅ èA»ÌÓuª\»É çíêéÆ«A\»Ó}ÆæÎêéB çäé\»Í\»åÌÌÓ}ȵɬ§³êéB
i¡ä¶ji1975jw¶Í\»@åvx@p.1j
@Ìæ¤ÉAlÔiu\»åÌvjª éu\»Ó}vðÁĶÍð\»·éÆ«A©Èç¸utvÆ¢¤Í½ç«ÉæÁÄAuÐçßv̾ÆྷéB
@ çäé\»Íêɨ¢ÄȳêéBêðà½È¢\»ÍÈ¢B±êÍ\»åÌiêÊIÉ¢¦ÎlÔjªêÌÈ©ÅïÌIɶݵĨèA\»ÎÛà¯lȶÝÅ èAµ©à\»å̪»ÌêÅ\»ÎÛÉuü·é±Æ©çéB
@±ÆÎÍA»¤¢¤êÌÈ©ÅAÎÛðÝÂßéåÌ̪ðʵÄÐçß«oéB±ÌÐçß«ÍA½ÈiReflexionjÉæÁĨ±éB½ÈÆ¢ÁÄàÏIÈTOð³·ÌÅÍÈ¢BÎÛð±ÆÎÉÐ骦·A»Ìæ¤Èͽç«ð³µÄ¢¤ÌÅ éB
i¡ä¶ji1975j@p.16j
±ÌutvÆ¢¤Í½ç«É¢ÄA¡ä¶ji1968jw\»w¼àxi@¥¶»Ð1968N12jÅÍAÌæ¤ÉÜÂÌiKÉí¯ÄླêÄ¢éB
@ܸAÚÌOÉ{Ìu»¨vª éƵæ¤B÷ÌãÉ»Ìu»¨vª éÌÅ éBæPÌtÍA»Ìu»¨vðu{vÆ¢¤êÅã\³¹é±ÆÅ éB±ÌêAu{vÆ¢¤êªA[ÔIiKâÞIiKÅÈAÛ¥IiKÅ éƵÄàA±Ì±ÆÍ ÄÍÜéBêͨƼÆð³¹éàÌÅÍÈ¢©çÅ éBu{vÆ¢¤êÍu»¨v»ÌàÌÅÍÈ¢BêÆ»¨ÆÌÔÉÍf⪠éBÉà©©íç¸êÍ»¨ðã\·é@\ðàÁÄ¢éBµ½ªÁÄ»Ìfâð±¦é½ßÉÓ¯Ít¹´éð¦È¢ÌÅ éB¢¢©¦êÎAã\³¹¤éÌÍtÌͽç«Å éB
@æQÍA»Ìu»¨vÅ éu{vð¢ë¢ëÉS]·µÄêƵÄ©ÝÆéêÅ éBu»¨vSÌÌàÁÄ¢é\îªAúÄAu¾Á¿åi¾Á½ÐÆjª¾©¢Ä¢évæ¤Éݦ½èA{Ì嫳ª×·Ä¢Æ«ÍAu⵪ÁÄ¢évæ¤Éݦ½è·éêieImojà±±ÉÓßéB»ê©çu»¨vª¹Å Á½è·êÎA»êðuíª¸_ÌÆvÆÝé±ÆàÅ«é©çA»ÌêÍAu{vÅ é±ÆƯÉu¸_ÌÆvÆÈé±ÆªñdÉÈÁÄF¯³êé±ÆÉÈéB
i¡ä¶ji1968jw\»w¼àx@p.67j
@æRÍA»fÉæéÓ¯ÌtÅ éBu»¨vðu{v¾ÆFèµAܽuüµ¢vXÆ»f·éÆ«AuíêvÌÓ¯ÍǤ®©Å éB±±ÉàêIÓ¯ÆñIÓ¯Ìtª Á½BæPÌêÅàAæQÌêÅà±êÍͽç¢Ä¢éÆÝÈÄÍÈçÈ¢B
@æSÍAê»ê©Ìɨ¯étÅ éBꪨƼð³¹éàÌÅÍÈA»ê©Ìªu»¨vÆÍÊÌ̧ŠèAêÔªLÆ\LÌt\¢ðà¿A±Ìä¦ÉuÓ¡Ìvð࿤é±ÆÅ éB
@æTÍAæP©çæSÜÅÌP[XÌãɧÁÄA»êçÌàÌð\»Ì@\̤¿É®·é@\ƵÄÌtÅ éB»êÍdwIÉȪßçêÄ¢éÉ·¬È¢B»êÉOãydð¯Äês\¢ÉÜÅàÁÄä½ßÉÍtªÍ½ç©ÈÄÍÈçÊB¾©çA\»»ÌàÌÉͽçtÆ¢¤±ÆªÅ«æ¤BêƵÄt³ê½àÌðÏÝ °i³¹jĶƳ¹Aܽ»êç̶ðÏÝ©³ËĶÍÆ·éÆ«ÉͽçtÅ éB
i¡ä¶ji1968j@p.68j
±Ìæ¤ÉA\»åÌƵÄÌlÔªA»¨Å émERgðF¯µA»êð¾tƵÄês\¢ÆµÄÌqÉ·éÛAÈãÌæ¤ÈÜÂÌutvªÍ½çÆ¢¤ButvÆ¢¤¾tÌaóƵÄAÌæ¤ÉàྷéB
@tÌêðg¢½È¯êÎA½ÈEàÈEÔÆE½ÆÈÇÌóêÉÇÝ©¦ÄàAÈñ̳µÂ©¦à¨±çÈ¢B
i¡ä¶ji1975j@p.17j
¡ä¶jÌ__ÅÍA»Ìutv·éͽç«ÆA\»åÌÆÌÖW«ðÌæ¤Éu_vÆ¢¤±ÆÎÅྷéÌÅ éB
@t·éͽ竪\»åÌÉæéÌÍRÅ éªA»ÌåÌÌàÆàÆÁÄ¢é_ð´_Æ·éÆArefAaAbAcð¶Þ»ê¼ê¿ªÁ½_ÍA´_©çª¯çê½àÌA·Èí¿Az_ƵÄÈÄÍÈéÜ¢Bi_ð´_©çz·é±ÆÌÅ«éÌàA¶ÂÍtÌͽç«ÉæéBj
@z_Æ¢¤ÌÍAâ³µ¢¦ÎAuªûÉÚðÎévÈÇÆ¢¤Æ«ÌAÎçê½Ú̱ÆÅ éBfæÅÐÆĄ̂ðÊ·ÌÉ¢ë¢ëÆJÌÊuð©¦Ä»ÌSÌÌ^Àðʵo»¤Æ·éªA»ÌÆ«ÌA©¦çê½JÌô©ÌÊuðl¦ÄÝÄàæ¢B
@´_Íoriginal¾©çSoAz_Í´_©çallotiè Äj³ê½à̾©çASaÆ»·éB
i¡ä¶ji1975j@p.18j
\»å̪AÇÌæ¤É¾tƵÄ\»·é©AÆ¢¤Æ«Éu´_v©çuzvµ½u_vÉæÁÄutvµAüð«ðàÂqƵÄêsÉutv·é±ÆÅA¶ÍƵÄu©½¿v·Èí¿ìiƵĬ§³¹éAÆ¢¤ÌÅ éBÂÜèA¡ä¶jÌ__ÍA\»ßöð©Êµ½A\»_ƵÄÌ__ÈÌÅ éB
@_ÉÍ¢ë¢ë éB\»åÌÌoriginalÉàÁÄ¢é_ð´_iSojA»ê©çÎçêé_ðz_iSajÆ·é±ÆÍùqÌÊèÅ éBz_ªÍ½çÆ¢¤ÌÍA½Æ¦Î¬Ìæ¤È±Æðl¦ í¹êÎæ¢B é¨ðÐîµæ¤Æ¢¤êAÒÍHàeÍHïÕÍHÈÇÆ©Ä¢ªA»ÌÒÍHàeÍHïÕÍHÈÇÆ¢¤â¤_ÍAÊXÆ¢íÈÄÍÈçÈ¢Bµ©à»ÌÊXÌ_ÍA é¨ðÐîµæ¤Æ·éåÌÌÚi´_@Soj©çí¯çê½àÌÅ éBtÉ¢¦ÎA±Ìæ¤É_ð¢Â©ÉÎé±ÆȵÉÍAÎÛð¢ë¢ëÌpx©ç©é±ÆªÅ«È¢BÒÍHàeÍHïÕÍHÈÇ¢¤ÌÍA»Ì_AÎçê½_A·Èí¿z_Å éÆ¢ÁÄæ¢B
@µ©µz·éÆ¢ÁÄàiKÍ éBiKIÉÎçêÈÄÍF¯Í[ÜçÈ¢B½Æ¦ÎAïÕÍHÆâ¤êAêÊü«ÆµÄ¾¯ÅÍÈAZ¶Þ«ÉÍǤ©Aåw¶Þ«ÉÍǤ©AÆâ¤êÍA³çÉz_ðí¯ÄÝèµÄ¢éÆ¢ÁÄ¢¢¾ë¤B
i¡ä¶ji1975jp.44|45j
u\»åÌÌoriginalÉàÁÄ¢é_ð´_iSojvÆÍAu\»åÌvÌL¢Ó¡ÅÌu\»Ó}vƵľ¢·¦ªÂ\Å éB é¶ÍðA¶ÍƵÄìiɵ½¢Æl¦½u\»Ó}vÅ éB»Ìu´_vðAÇÌæ¤ÉB¬³¹é©AÇÌæ¤É±ÆÎƵÄA¶ÍìiƵÄu©½¿vÉ·é©AÆ¢¤iKðuz_vªSÁÄ¢éÌÅ éBãÌøpÌêAu±Ì{ðÐî·é±Ævªu\»åÌvÌu_vu´_vÆÈèA»êðÇÌæ¤È
@¡äÍu_vÆu¶ÍvÆÌÖWÉ¢ÄAÌæ¤ÉàwE·éB
©ñ½ñÉ¢¦ÎA¶ÍÆÍA_Ì©ÄÜí誻ÌÉ©êÄ¢éàÌAÆÝȵÄæ¢B_ª©ÄÜíéÆ¢¤s®ÉæÁĶÍÍÅ« ªÁÄ¢éÌÅ éB
i¡ä¶ji1975jp.59j
±Ìæ¤ÉA¶Í\»ð¨±ÈÁÄ¢¤¦ÅÌ\»ßöÌÉu_vÆ¢¤TOð±üµà¾µÄ¢éB»ÌÓ¡ÅA{è´FEãì¼÷i1985jâA¼½|FÌ__ÆÍáÁ½u_vÌTOÅ éÆ¢¦éB
@{è´FEãì¼÷i1985jÅÍAFmÈwÆ¢¤Ï_©çAulªmð©éÆÍǤ¢¤±Æ©vAu©½¿ðÆç¦éÆÍǤ¢¤±Æ©vÆ¢¤»À¢EÌu_vÌ è©½ÆÆàÉAulª¶wìiðÇÝA»Ììl¨ÌSîðð·éÆÍǤ¢¤±Æ©vÆ¢¤¶wìiðÇÞÉ ½ÁÄÌu_vÉ¢Äl@µÄ¢½B»ÌÈ©ÅÍAlªmðoÉæÁÄFm·éÆ¢¤±ÆÍAÎÛÌu©½¿vÌÏ»Ìlð©é±ÆÅ èAu®I_vÆuÃI_vƪ éƵĢ½BܽA¶wìiðÇÞÛÉÍAuÈévÆu©évÆ¢¤ñÂÌ«ÉæÁÄAu¼zI©Èðh·év̾ƵĢ½Bìl¨ÌSî»ÌàÌðð·éÌÅÍÈA»Ìl¨Ìuávðl¾·é±ÆÅA»Ìl¨ÉÈÁÄìiÌ¢EàÌmð©éB¶wìiɨ¢ÄÇÝèÍAu©évÆÆàÉAuÈévÆ¢¤oûüIÈðÉæÁÄAìl¨ÌSîð¤´IÉð·éƵĢ½B
@¼½|Fi1975jÍAu¶|ìivɨ¢ÄAu_vÆÍu¾êÌá©çvAuDZ©çv`¢Ä¢éÌ©AÆ¢¤âèÅ éƵĢ½B»êÍAuêlÌvÈÌ©uOlÌvÈÌ©AÆ¢¤ìiSÌðÇÌæ¤É`Ì©AÆ¢¤âèÅ éBܽAìl¨ÌuàÌÚv©ç`Ì©AuOÌÚv©ç`Ì©AÆ¢¤âèÅà éBl¨ÌàÊ©ç`±ÆÅÇÝèÍu¯»Ì±vðµAOÊ©ç`±ÆÉæÁÄuٻ̱vð·éƵĢ½B»Ìu¯»vÆuÙ»vðJèÔ·±ÆÅAu¶|ìivðÇÞA·Èí¿u¤Ì±v·éÆ¢¤B
@êûA¡ä¶jÌ__ÍA{è´FEãì¼÷i1985jA¼½|Fi1975jÌ__ÆÍá¢AÇÌæ¤É\»ÍȳêĢ̩AÆ¢¤\»ßöÌÅÌu_vð\zµÄ¢½B·Èí¿Au\»åÌvÌu\»Ó}vðÇÌæ¤É·êÎA¶Íi±ÆÎjƵĬ§³¹¤é©AÆ¢¤âèðu_vÆ¢¤±ÆÎÅྷéÌÅ éBRð\»µæ¤Æ¢¤u´_v©çAu_vðuzv·é±ÆÅutvµA½xàutv·é±ÆÉæèAqÆ¢¤ês\¢ÆµÄ¬§³¹éÌÅ éÆ·éBæÁÄA¡äÌ__ÍAÇÌæ¤É\»·éÌ©Au\»Ó}vðÇÌæ¤ÉìiƵĬ§³¹éÌ©AÆ¢¤\»_É©©íéàÌÅ éBÇÌæ¤É\»·éÌ©AÆ¢¤u_vÌuzvÆ¢¤__ÍA¼½|FÌ__ɨ¯éuDZiNj©ç`©êÄ¢é©vÆ¢¤âèðàÜß½àÌÅ éÆ¢¦æ¤B
@{eÅÍA±Ì¡ä¶jÌ__ɨ¯éuzvÆ¢¤l¦ðQƵAuê¼ÆÌúìiðl¦éĪ©èƵ½¢BæQÅÍA¡ä¶jÌ__Ƽ½|FÌ__ðÖA³¹½©½¿ÅA{eɨ¯éu_vÉ¢ÄÌpêEpêÌè`ð¨±È¤±ÆÉ·éB
@æQÅÍAæPÅÝÄ«½__É¢ÄÌæs¤ÉîâÄ{eɨ¯éu_vÉÖ·é±ÆÎÌè`ð¨±È¤B
@{eÍA_¶Ì\èÉà éæ¤É¡ä¶ji1968jA¯i1975jÌ__ɨ¯éu_ÌzvÆ¢¤l¦ûÉÖA³¹ÄA¶Íìiɨ¯éu_vðl¦Ä¢±ÆÉ·éB{eÅp¢éÛÌu_v¨æÑu_vÉÖ·é±ÆÎðAÌæ¤Ép¢éæ¤è`·éB
| u´_vccccc | @\»åÌÌuRð\»µ½¢vÆ¢¤Æ«ÌA\»ÎÛÉηé_Å éBìiɨ¯éuåèvÆAu\»åÌvÌu\»Ó}vÅ éu´_vƪ¬¯³êé°êª é½ßA{eÅÍuåèvÆ·éBuåèvðAÇÌæ¤É¶ÍƵĬ§³¹é©Æ¢¤âèðAuz_vªS¤±ÆÉÈéB |
| uz_vcccc iu_ðz·évj |
@DZA¾êÉ_ð¨«AÇÌÔÅ\¬µAÇÌæ¤Éq·é©BDZAN©çÝé©AÆ¢¤±ÆâÇÌæ¤É¶âêåðIð·é©AÆ¢¤q̵©½A³ê©½Éà©©íézçêé_Å éBDZ©çiN©çj©éÌ©ADZÉ_ðu«`©êÄ¢é©AÆ¢¤¼½|FÌ__ðQlɵȪçAìiÌ\¬Éà©©íéAÇÌæ¤ÉìiƵÄìi½çµßÄ¢é©AÆ¢¤_Ìͽç«Å éB @_ðz·éÆ¢¤Æ«ÍA»Ì®`Å èAuÇÌæ¤É_ðzÁÄ¢éÌ©vÆ¢¤±ÆÅ éB |
| u_ðuvccc | @¼½|FÌ__ÅâèɳêÄ¢½AuDZ©çvuN©çv`Ì©AÆ¢¤âèðl¦éÆ«Au_Ìzvâuz_vÆ¢¤±ÆÎÅÍÈAu_ðuvu_ªu©êévÆuuvÆ¢¤±ÆÎ𩤱ÆÆ·éBu_l¨vÍN©AÆ¢Á½âèÅ éB |
±¤µ½_ÌzÌâèðAq@ÆÌ©©íèÌÈ©Ål@µÄ¢Bìiɨ¯é_ÌzðªÍEl@·é±ÆÅA¶Íð¬è§½¹Ä¢éuåèvu\¬i\zjvuqvðl¦é±ÆÉÈë¤B
@q@ðl@·éĪ©èƵÄAyOªñÄ·éuqwªÍvÆ¢¤û@ðQlÉAq̪ުÍð¨±È¤BuqwªÍvÉ¢ÄÍAæRßÅÚµÆè °é±ÆÉ·éB
@æRßÅÍAq̪ުÍÌQlƵÄAyOÌuqwvÆ¢¤l¦ðÝé±ÆÉ·éB¶ÍÍAÐÆÂÐÆÂÌqªÇÌæ¤ÉÜèdÈèAê̽é¶ÍƵÄuwvðȵĢé©AÆ¢¤±Æð¾ç©É·é±ÆðÚIƵ½l¦ûÅ éB
@yOi1986ju¾êóÔÌdgÝ\¶Í\»ÌqwÆ\¬\viw\»wån_Ñæêª@\»wÌ_ÆWJx³çoÅZ^[1986N3jÌÅA¶Íªu¢©É¬§µÄ¢é©vÆ¢¤âè©çA¶Íɨ¯éqªÇÌæ¤Éuq×çêÄ¢é©vÆ¢¤âèð¾ç©É·é½ßÉAqÌuwvðÆç¦é±ÆªKvÅ éÆwE·éB
@¶Í¬§i«¿j_ÌÛèuóÔISÌÆÔISÌvÍA¶Í\¬_ÌÛèu\ƶ¬vÉЫpªêA³çÉA»êÍA¶Íl_ÌÛèuqÌwvÉÂȪéB¶Í\»ÍAq³êÄA¶ÍìiƵĬè½ÂB»Ìæ¤ÈudgÜꩽvÍA»Ìæ¤Èuq×çꩽvÉæÁĶÍìiÉè µÄ¢éB»Ìæ¤Èuà̲Ævâ»ÌuÆ禩½vÌ èæ¤ÍA»Ìæ¤ÈuLqE`Êvâuà¾E]ßvÌ èæ¤ÉæÁÄAqÊÉuwvðȵİ»³êÄ¢éB
iyOi1986ju¾êóÔÌdgÝ\\¶Í\»ÌqwÆ\¬\\v
w\»wån_Ñæêª@\»wÌ_ÆWJxj
»µÄAqÍÌæ¤ÉÌnðȵĢéÆ·éBÌøpÍAyOi1995ju¬à\»É¨¯éqwÌdw\¢viw¶wxæ73Ö¼åw¶wï1995N2jÉæéàÌÅ éB
\»åÌÍA éuà̲Ævð éuÆ禩½vÅÆç¦Ä\»·éªAuà̲ÆvÌ èæ¤É¦µÄ\»·éêÆAuÆ禩½vÌ èæ¤É¦µÄ\»·éêƪA©ª¯çêéBuqvÍA»Ìæ¤È\»û@ɦµÄAuà̲Æv{ÊÌuÎÛ\»vÅ éiêjuiL`jLqvÆAuÆ禩½v{ÊÌuqÒ\»vÅ éiñjuiL`jà¾vÆÉAñåʳêA»ê¼êÍ\Ìæ¤Éת³êéB
@iêjuiL`jLqvÍAuÔvià̲ÆjðÂÊIEקIÉÚq·éi1ju`ÊvÆAÔðêÊIETīɪq·éi2jui·`jLqvÆÉA¯Ê³êéB¬àâ|pIMÌåvªÍi1ju`ÊvÅ èAV·ÐïÊLÌåvªÍi2jui·`jLqvÅ éBܽAiñjuiL`jà¾vÍAuÔvià̲ÆjðªÍEµÄàÌvfðÝÖWÉæÁÄÊuï½èA»ÌÔðOÌÔÆÖWt¯½è·é±ÆÉæÁÄAuÔv̶§îðuð¾v·éAÆ¢¤i3jui·`jà¾vÆAÔðqÏIEåmIÉuðßvµÄӡï½èAÔðåÏIEåîIÉu]¿vµÄӡï½è·é±ÆÉæÁÄAuvðu¾vµAu©ðvðu\¾v·éAÆ¢¤i4ju]ßvÆÉA¯Ê³êéBuྶvuðà¶vÌåvªÍi3jui·`jà¾vÅ èAu_à¶vu]_¶vÌSªÍi4ju]ßvÅ éB
iyOi1995ju¬à\»É¨¯éqwÌdw\¢vw¶wxæ73j
±±ÉÉ éu\vÆÍAEÌ}\ðwµÄ¢éiyOi1995jæèøpjB³çɬàðͶßÆ·éu|pI¶ÍvÉ¢ÄÍÌæ¤É檳êéÆ¢¤B
@êûAu¨ê¶vu¬à¶vÈÇÌu|pI¶ÍvÍAul¨i«ijvu«iwijvuis®jvÈÇÉæÁÄ\¬³êéBÊíAubèvðS¤ul¨v·Èí¿ålöâålöÌs®EóÔªubèvÌuÔvƵÄÝu³êA»ÌuÔvÉηéuà¾vâu]ßvªzu³êéBµ½ªÁÄAuÎÛ\»vªãwiã\¢jÉÊuµAuqÒ\»vªºwiº\¢jÉÊu·éBÊíul¨`ÊiLqjvu¨`ÊiLqjvuà¾vu]ßvÆ¢¤uqwvÉæÁÄ\¬³êéBת·êÎAåvªÌul¨`ÊiLqjvÍukb`ÊiLqjE®Ô`ÊiLqjEÃÔ`ÊiLqjES`ÊiLqjvÆ¢¤æ¤ÉAà̲Æ{ÊÌ`ÊiLqjÙÇAæèãwÉÊuµÄAlªiªªj³êéB¯lÉAu¨`ÊiLqjvàAu®Ô`ÊiLqjEÃÔ`ÊiLqjvÆ¢¤æ¤Éñªilªj³êéB
iyOi1995jj
@±Ìæ¤Éqðת»µAu|pI¶ÍvÆu_I¶ÍvÆÌqÌuwvÌ è©½ªAuÎÛ\»vuqÒ\»vªt]µÄÝçêéƵĢéB
@ÉA»ÌªÍû@É¢ÄAïÌáð °Ä¨±¤BÌøpÍAÅÉøpµ½yOi1986jÅ éBªÍÌïÌáƵĺÌHì´VîÌwxðÆè °Ä¢éBìiwx¶¶Ìøpª·ø«ÉÈÁĵܤªAyi1986j̪ÍƺÌ{¶ÆðØ裵Äøp·é±ÆÍAïÌáÌÐîƵÄÓ¡ð¬³È¢½ßAHì´VîÌìiÌ´TÉÍæç¸ÉAyOi1986jÌàÌð»ÌÜÜøpµ½B
T@@âÉÈÁ½HÌyªAu ̲ Ìæ¤É£¢Ä¢éBAâµ¢RÔ̬¾©çAHÉÍÎò àÈÈ¢BB¼¤ÉÍⱯç ÌƪÐÁ»èÆúõðÑÄ¢éB
U@ClñlÌw¶ÍA»ÌH𹩹©ãÁÄ¢Á½BD·éÆAÔñVðwÁ½ªêlAZ¢eð«àÆÉƵȪçAÃ©É âðºÁÄ«½BEÍA³ÌÜê½ èÉAsÌ·¢ 𩴵ĢéBF½ÌשÆvÁ½çA»êÍA^ÄÌúõªA·â·âQüÁ½ÔñVÌçÖ½çÊ×ÌÅ Á½BGlñlÍ·êá¤ÉA»ÁÆ÷Îðð·µ½BHªAÍ»êàmçÈ¢ æ¤ÉAâÍèéÉÊè·¬½B
V@I©·©ÉjªúÉį½ålÌ羿 ÌÅ éBJ»Ì窢¾ÉǤ©·éÆÍÁ«èL¯É©Ô±Æª éBiHì´Vîuvj
iyOi1986jj
@{¶É«ÜêÄ¢é¶Ôi@AAABcjAOí̺üAT_ErÍASÄyOi1986jÉæéàÌÅ éBÈãÌæ¤Éìiƻ̪Í}\ÉæÁÄAÌæ¤Éìiðl@µÄ¢éB
uâµ¢RÔ̬vÌuÃÔ`ÊvðwiɵÄAìÒ̪gÅ éuÚiçjvi_l¨jÉ»ÁÆu÷Îvðð·³¹½AbèÌl¨uvÌu®Ô`ÊvuÃÔ`ÊvªDèȳêAꬪWJ³êéB»µÄA»ÌãÉAuvÌçªu¢¾ÉÍÁ«èL¯É©ÔvÆ¢¤ãúkªtÁ³êéB
iªj
@¨ê¶E¬à¶É¨¢ÄÍA¢íäéuålövªAbèÌl¨ÆµÄuèÚvðS¤Î ¢ª½¢BålöÌuvÌu®Ô`ÊvwuÃÔ`ÊvwÌDEHðAê¶Éû©·êÎi1juªAÔñVÖð©´µÄAéÉâðÊè·¬½BvÆÈéŠ뤩BƱëªAi1jÍubè¶vÅÍ ÁÄàAuåè¶vÆÍÝÆßçêȢŠë¤Bi1jÅÍAìÒªÔð»Ìæ¤Èv¢ÅÆç¦i´¶ÆèjA[óÛïçêÄ¢½Å ë¤à̪AÙÆñÇÌÛ³êĵÜÁÄ¢éB»êðqÊÉÐ骦µÄAi1jðqµÈ¨·AÆ·êÎAi2juªièÚjAÔñVÖð©´µÄAéÉâðÊè·¬éÌð©ÄiàqjAÙÌÚÌÆS·ÜéàÌifpųSȤîj𴶽iïÓjBvÆÈéŠ뤩B
@uÙÌÚÌS·ÜéàÌifpųSȤîjvÆ¢¤ÌÍAìÒ̪gÅ éuÚiçjvÌu÷ÎvðUÁ½ÔñVÖÌv¢ð¢Å¢é®Ô`ÊEÃÔ`Êvɨ¯éu«îIÓ¡vðAû©µiTO»µjÄAqµÈ¨µ½àÌÅ éB\èi^CgjÌuvÍB»Ìæ¤ÈuïÓvÌۥŠë¤B
iyOi1986jj
±Ìæ¤ÉAuqwv̪ÍÆÍAqªÇÌæ¤ÉL@IÉwÆÈÁĶÍ𬧳¹Ä¢é©AÆ¢¤±Æð¾ç©É·é½ß̪ÍÅ èA}\Å éƾ¦éB±ÌuqwvÌÈ轿ð©é±ÆÅAìiÌåèâ\¬Æ¢Á½âèðàÜñ¾ªÍªÂ\ÆÈéB±ÌuqwªÍvªDêÄ¢éà¤êÂÌ_ÍAÎÛìiâ¤ÚIɦµÄp³¹é±ÆªÅ«é_Å éBªÍÎÛƵ½ìi̽ð¾ç©É·éÌ©AÆ¢¤ÚIɶÄAq̺ÊæªðÄl·é±ÆªÅ«éÆ¢¤¬®«ÆÂ\«ðàÁ½ªÍû@Åà éB
@{eÅÍA±ÌyOÌuqwvÆ¢¤l¦ûÉîëAq̪ުÍð¨±È¤±ÆÅAuê¼ÆÌúìiɨ¯éq@ðl¦éĪ©èƵ½¢B»ÌÛAìiÌàeɦµ½ªÞÚðl¦Aìi²ÆÉáÁ½Úð§Äé±ÆÉ·éB
@ȨAyOi1986jÅÍAc«ÅA}\Ì¡²ÉqÌ檪A}\Ìc²ÉqÌWJi¶jªzu³êAqªE©ç¶ÖÆWJ·éæ¤ÉÈÁÄ¢éB±êÍAu|pI¶Ívɨ¯éqðuã\¢vuÎÛ\»vAuº\¢vuqÒ\»vÆ\¬³êÄ¢éOñÉæéàÌÅ éBµ©µA{eÅÍA¡«ÅA}\Ì¡²iñjÉq̪ÞÚðA}\Ìc²isjɵÄAã©çºÖÆqªWJ·éæ¤Ézu·éB±êÍADui2001juvñÞ^Æåè¶^\\Hì´VîwsAmxð´¶ÍƵÄ\\viwê\»¤xæ91996N3jű±ëÝçêÄ¢éHì´VîÌwsAmxðªÍµ½qwÌ}\ðQlɵ½àÌÅ éB
@±êçæPÍÅ®µÄ«½æs¤ð¥Ü¦ÄA±æQÍɨ¢ÄÀÛÉuê¼ÆÌúìi̪Íð¨±È¤±ÆÉ·éB
@w½é©x̪ÍEl@ð¨±È¤OÉAܸw½é©xÉ¢ÄÌæs¤ðÝÄ¢±ÆÉ·éB»Ì ÆAæ2ÅÍ»êçÌæs¤ð¥Ü¦½¤¦ÅAw½é©xÌ[TAêÊ\¬É¢Į·éBæ3ÅÍAæPAæQÌàeð¥Ü¦ÄAq̪ުÍÌÚðè·éB»µÄæSÅA»ÌªÍÊðàÆɵ½l@ð¨±È¢AæTÅAl@ÊðàÆÉw½é©xÁ¥IÈqÉ¢Äl@µÄ¢«AÅãÌæUÅìiɨ¯é_ÌzÆq@ðÜÆßéAÆ¢¤èð¥Þ±ÆÉ·éB±ÌÍAæQßwÔÜÅxAæRßwäx̪ÍEl@Åà¯lÅ éB
@ÔØri1944ju¬àìÆƵÄÌuê¼Æviwuê¼Æ¤xÍo[1944N6jÅÍAuê¼ÆÌìiɤʷélÂÌiKðuìvÅ éw½é©xÉ©oµÄ¢éB
@w½é©xɨ¢ÄA½xàN±µÉéucêvÉεÄÌAuM¾YvÌu§ vÆ¢¤´îªAìiÌ_@ÆÈÁÄ¢é±Æ©çA±êðu½vÆÄÔB»µÄAucêvÆûÜÉÈèA°ÌÅucêvðSz³¹ÄA¢ç¹æ¤ÆvÄ·éiKðu¡vÆ·éB»µÄucêvÆÌâèÆèÉæÁÄÜð¬·iKªuaðvBÅãÉí
½¿Ì®Åïbððí·iKªAu²avÅ éBw½é©xɨ¯é±êçÌliKª é±Æð¥Ü¦½¤¦ÅAÌæ¤ÉwE·éB
Èã̲ƽA¡AaðA²aÆ¢ÓliKÌßöðzè·é±Æ©çA¬àìÆƵÄÌuê¼ÆÌ{¿ðÆ«Ù®·½ßÌè|©èª¦çêéÌÅÍ éÜ¢©Bà¿ëñA{¿Æ¢ÂÄàAÃ~¹éàÌÅÍÈA¬·µÏ»·é®IÈàÌÅ éB éÆ«Í¡Ìvfªå«ÈèA éÆ«ÍaðÌvfªÈèAܽ٩ÌÆ«ÉͲaÌädª¢¿¶éµ¦éƢ½ïÉA»ê¼êÌúɨ¯é¤Âè©ÍèÍ éɵÄàA±ÌliKÌßöªA»ê¼êÌdûÅAÂXÌìiðÂçÊ¢ÄîéÌÅ éB
iÔØri1944ju¬àìÆƵÄÌuê¼Ævwuê¼Æ¤x
i{¼Íur³lvB
øpÍuú{¶w¤¿p@uê¼ÆvL¸°oÅ1970N6jj
³çÉA±ÌlÂÌiKªuê¼ÆÌìiÌOúɨ¯éu¬àvÌT^Å èAìÆEuê¼ÆͱÌL³ÉæÁÄOãúÅå«ñª³êéÆ¢¤B
«ÍßÄå«TµÄA½A¡AaðA²aÆ¢ÓßöÌÈ©ÉuvÌ¢Eð¢ÆÈñÅî½±êÜÅÌúðA¢Ü©èÉOúÆæÔ±Æɵæ¤B±êɽµÄAãúÍAÅãÌiK½é²aÌ٩ͱêðìiÌ»ÆÖÇúµÄµÜÐA³¤·é±ÆÉæÂĦçê½S«ðuvÌjSÉïæ¤ÆÂÆßéúÅ éBOÒª{Ìӡɨ¯é¬àÅ éÆ·êÎAãÒÍA»êªÏeµÄS«¬àÉÈÂÄîé̾ƢÖæ¤B
iÔØri1944jj
»µÄAw½é©xÆ·ÒÌwÃésHxÆÉÌæ¤ÈÖW«ð©oµÄ¢éB
»ÌÏû©ç·êÎAêÍÙáÆlÖ½uÃésHvÍAu½é©vÌ´^ªÉÀÉÜÅgåµ½àÌÅ ÂÄA»ÌߢÓÈÇÍA±ÌúÌ{¿Æ§ÚÉÂȪéàÌÅ éB
iÔØri1944jj
Æà·êÎAÍ_ð±Ìú̲aÌÊɨ¢½¤ÖÅA¬àìÆuê¼Æª]X³êª¿È̾ªAí½µÍA»êðS«¬àƵÄA{̬àÌð̻۾ÆlÖéB»êÌA¬àìÆƵÄÌuê¼Æðf`·éÉ ½ÂÄÍA½Æ¡ðÂæµ¾µ½OúÌȬàðÆÉdéB¤¯Â®×«¸_ÍÞµë»ÌÈ©É éÌÅÍÈ¢©B
iÔØri1944jj
ÈãÌæ¤ÉA±Ìu½vu¡vuaðvu²avÆ¢¤liKªAu¬àìÆuê¼Ævðl¦é¤¦ÅdvÅ éƵĢéB
@¬chi1972,cjuuê¼Æ̶w`¬liOj\\OìÌØ\\viw¶wx40ª3âgX1972N3jÅÍAw½é©xª®¬ÉéoÜðl@µAìÆEuê¼ÆÆÖíç¹Ä_¶Ä¢éB
uñ¬àAcêvÍu¨k³ñÆÌÜvðµ¢ÈªçAè¼Ì¦·@A»ÌoßÌàÉAuêªØÀÉ´¾µ½cêÖ̤îð`[tÆ·éBcêðålöƵAuvuꪤðêÁ½àÌÅ ë¤BuêÌ©ÌQN«Ì«³AäÔèðß®ÁÄA¶Ó·écêƽR·é·ÆÌû_©çȨèÜÅðQwIÉ`AuÜvÍAuêÆàÅÅàÔÉÈè¾é¼ÒÔÌAeìÈ´î̶ÉÜ©¹½AqÏIÉͳӡȡŠéBµ©µA±Ì¡Í³Ó¡ä¦ÉAÞ«oµÌ´îð sµÄàA³íâ©È´Á´ðª©¿¦é«¿ðÂB
i¬chi1972,cjuuê¼Æ̶w`¬liOj\\OìÌØ\\v
w¶wx40ª3j
±Ìæ¤ÉAw½é©xÍAuê¼Æ©gªuØÀÉ´¾µ½cêÖ̤îð`[tvƵĢé±ÆðwE·éBܽA»êª©gÌÆëàÅÌoð`¢½ìiÅ é½ßAuqÏIÉͳӡȡvÅ éªä¦ÉAuÞ«oµÌ´îð sµÄàA³íâ©È´Á´ðª©¿¦é«¿ðÂvÆwEµÄ¢éB
@w½é©xÌ`ªÅAucêvÆuM¾YvÆÌΧªA·ÅɼÒÌΧð\´³¹éàÌÅ é±ÆðmFµA©ð}¦½ñlÌâèÆèÉ¢ÄÌæ¤ÉwE·éB
@c¼¹Ì@vðcÞúÌ©AZÉålöÍcêÉN±³êéBôxÆÈQºÉÄAM¾Yɺð©¯ÄÍZµoÄ¢cêÉÍA¢©Éà@êØÌÉÌÒ½épªèèµ¢BñAO\ªÌÔÉOx®ðoüè·écêÆAålöÆÌÎÍ©Èj}Ìæ~²ðàÁÄis·éB
i¬chi1972,cjj
±Ìuj}Ìæ~²vðàÁ½âèÆèÌÈ©ÉAuM¾YvÌí
½¿ÌâèÆèª`©êÄ¢é±ÆÉ¢ÄAÌæ¤ÉªÍ·éB
µ©µAMOÆFqÆÌÓ´¯¤¾tÍAN«ëN«È¢Æu½Õ௶ðJèÔµv¾¢Á½M¾YÌê¢àSðA½Ø·éÌÉøÊIÅ éBí ½¿ÍàSðÆ緾ŠèAcêÍålöÌOeðf·¾Å éBålöÍcê©ç温çêA¶Ó³êAíÉógɽ¢ÍãèÉÈÁĽ·éBuêÌ©ÈÃÌJjYªA±êÅ éBñÊ̾Éfµo³ê½M¾YÍAÂÜçÊÓnƨð£ÁÄ¢éªAàSͬSÈFsÒÅ éB
i¬chi1972,cjj
±Ìí
½¿ÌâèÆèªAucêvÆuM¾YvÆÌâèÆèð½Ø·éàÌƵÄÊuïçêÄ¢éÆ¢¤B»µÄAÔØri1944j̾¤uaðvª¬§µ½ãÌAìiÌÅã̪É¢ÄAÌæ¤Él@·éB
@ÅãÉAM¾YÍQ®ðoÄA×ÌqB\OfÌAålöÌusÀvð~«§Ä½í _iÆÍÎÆIÉ`©êé\ÉüÁÄAðY·éÉn¯ÞBuêÌÆ°¤ÖÌñA·éSîûüÍmèIÅ éBiªj\ua¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YvÍAuêÌñîÈ©Èéçoµ½©æÅ éBÇÆðÛÁÄAàÉúOÆOÉÃæ²aðYí¹Ä¢épÅ éBÆ°IbÌóÔªAìÆÌðXÆ©o³êA©Èð¥µAÇÆðßéSî©ç¶Ýo³ê½àÌÅ éB¢íÎAaðã¼Îðo½uêÌ»µÉÒÁ½èÆdÈè¤B
i¬chi1972,cjj
±Ìua¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YvÆ¢¤uàÉúOÆOÉÃæ²aðYí¹Ä¢épvÉAuaðã¼Îðo½uêÌ»µvð©oµÄ¢éBä¦ÉA±Ìw½é©xð®¬ÍAuñ¬àAcêvª©ê½úi¾¡41N114úi1908NjjÅÍÈAw½é©xƵÄ\³ê½úiå³7N3i1918NjjÅ éƪµÄ¢éB
@{¡¼Yi1976jwßã̶w@uê¼Æ̶wiVÅjxi÷Ð@1976N6jÅÍAw½é©xÉ¢ÄÚ×Él@ð±±ëÝÄ¢éBܸAw½é©xɨ¯élÌÌâèÉ¢ÄÌæ¤ÉmF·éB
@±Ì¬ÍAǤ¢¤¤ÊðåƵÄ`¬³êÄ¢é©BÂNÉÍM¾YÆ¢¤¼ª^¦çêAêAOlÌÌ`ÉÈÁÄ¢éªAÀ¿I´Á©ç¢¦ÎêlÌÅ èAìÒ©gÅ ÁÄA±ÌM¾YÌ©½è´¶½èµ½àÌƵÄcêÌðªµé³êéB
i{¡¼Yi1976jwßã̶w@uê¼Æ̶wiVÅjx@p.20j
³çÉAuê¼ÆÌìiÉÍuìÒ̶ÌâÎIÈÏvª¶Ý·é±ÆðwEµA»êªuê¼ÆÌìiÉÍuê¼Æ©gðèÞɵ½à̪½¢ÌÅ éÆྷéB
@uê¶wÌîêɶ®µÍ¶ß½lÔÍAìÒ©g̶«é´Å èA±ÌìÒÌâÎIÈÏÅ éBà¿ëñìÒªAÀ¶Ì çäéuÔÉA±ÌlÔÌÅÌóÔðÀ»µÄ¢éÈÇÆ¢¤ÌÅÍÈ¢Bµ©µ±ÌÅóÔÖÌuüðíÉà µAÉÕñűÌÅÌóÔðÀ»µAìÒ໤¢¤©ªÌóÔðmèµÄ^íȢƢ¤Ó¡ÅA±ÌìÒ̶ÌâÎIÈÏÈÌÅ éB±ÌlÔÏð µA»Ì¢¿lðöµÄ¶«éÌÍAÁÉìÒ©gÅ é©çAuê¶wÅÍAìÒ©gð`±Æªî{IÈûüÉÈéB
i{¡¼Yi1976j@p.23j
@vñµÄ¢¦ÎA»Ìo±ðà¤êx¶«é±Æɨ¢Ä`ÌÅ éBà¿ëñAL¯³ê½óÛðA»ÝÌ©ªÆÍ£ê½àÌƵÄéÉÏƵÂÂ`Æ¢¤æ¤ÈAuê¶wÆÍáÁ½s«ûÌ`Êɨ¢ÄàA»ÌL¯³ê½o±ðA½ç©ÌöxA½ç©ÌdûÅà¤êxs«¼·Æ¢¤_@ª¢Ä¢È¯êÎA»êͬ觽ȢBµ©µAuê¶wÌêÉÍA»¤¢¤êÊIÈAÈÜâ³µ¢öxÅÍÈÄA¶Ç¨èà¤êx¶«¼·ÌÅ éB©êéo±ªA´îAs®êÌƵÄAóAɶ«é±Æð´^Æ·éàÌÅ é©çA¶«¼·ÌàA»Ìæ¤È¶ð¶«éÌÅ éB»êÍà¿ëñA´epÉêê«iÝÂÂSÌŶ«éÌÅ éªA¾©çÆ¢ÁÄA»À̶æèeª¢Æ¢¤æ¤ÈàÌÅÍÈ¢Buê¶wÆÍÀç¸AÇÌ|pÆÅàA»Àɶ«éêæèàA»êð\»µÂ éêÌSÌ̶ÍAeªÈéDZë©A»A»³êAæèxÉÃWµÄ¢é͸ŠÁÄA»êÅ ÁÄͶßÄ|pìi𻳹é±ÆªÅ«éB
i{¡¼Yi1976j@p.24j
±Ìæ¤ÉAuê¼ÆÌìiÍAuê¼Æ©gÌ̱µ½oðu¶Ç¨èà¤êx¶«¼·v±ÆÉæÁÄìiƵĬ§·é̾Ƣ¤B
ìÒ©gÌo±ðÌÅÍÈÄA¼lÌo±µ½ÀâAẕƪçðêÅàAnìå̪êl¨ÉüèÝA¢«¢«µ½´îAs®êÌƵĶ«é±ÆɦµÄA»êð`¬·éêAìl¨ÍAìÒ©ç¢ÁÄÌêlÌIÀ¿ÌàÌÉÈ調Šë¤BܵÄAìÒ©gªA´îAs®êÌƵĶ«½o±ðAEÌæ¤ÈnìåÌƵĵé¹ÎAM¾YAåÃgÈÇÆOlÌ絼ïçêÄ¢ÄàAìÒ©ç¢ÁÄÌêlÌIÀ¿ðõ¦Aì̼Ìl¨ÍA±ÌêlÌIl¨Ì¶ÉüÁÄéÀèɨ¢Ä`©êAÎÌiŶݷéàÌƵÄÍ`©êɢƢ¤±ÆÉÈéB
i{¡¼Yi1976j@p.36j
u¶Ç¨èà¤êx¶«¼·v±ÆÅìi𬧳¹é½ßA½Æ¦Ol̬àÅ ÁÄàAuêlÌIÀ¿vð»È¦½ìiÉÈéÆ¢¤B
»ÌM¾Y̶ÍAìÒ©ç©ÄÌêlÌIÀ¿Ì´îAs®êÌƵÄWJ³êÄ¢éªAÅã̪ŻÌ_ªÏíÁÄ¢éA»êÍwa¢¾ARµµÒµ¢ÎçŧÂĽM¾YªAu¼½²·ÉEÍÈ¢ævÆ]½BxÆ¢¤ÓÅ éB¾ç©ÉM¾YÍAM¾Y©ç£ê½ìÒÉæÁÄAO©çȪßçêÄ¢éçÌ\îª`©êÄi»êàuÒµ¢vÆ¢¤`uM¾YvàA»êÜÅÌêlÌIÀ¿©çOlÌIÀ¿ÉÏíÁÄAí ½¿Æ¯ñÉÈçñÅ¢éeÈÇðgÁÄjAB±ÌÏ»ÍA½Æ¦ÎìÒª¤Á©èµÄA±Ìæ¤ÉsêÉÈÁ½Æ¢¤æ¤ÈàÌÅÍÈ¢B±ÌìÒÌnìåÌÌ{¿©ç©Ä©RÈAKRIÈÏ»ÈÌÅ éB
i{¡¼Yi1976j@p.37j
w½é©xÌÅãÌua¢¾ARµµÒµ¢ÎçŧÂĽM¾YªAvÆ¢¤ê¶ªAuO©çȪßçêÄ¢éçÌ\îª`©êÄv¢é±ÆÉ
ÚµÄAu»êÜÅÌêlÌIÀ¿©çOlÌIÀ¿ÉÏíÁÄAí
½¿Æ¯ñÉÈçñÅ¢évÆ¢¤B±Ìæ¤Éu²avª¬§µ½±ÆðAuêlÌIÀ¿©çOlÌIÀ¿vÖÆ¢¤lÌÌÏ»ÉÝÄ¢éÌÅ éB
@{ì¿i1989juuê¼Æ̶Íviw\»wÌne_Ñæêêª@ßã¬àÌ\»Ox³çoÅZ^[1989N1jÍAw½é©xÉ¢ÄAìiÌ`ªÆÉ
ÚµÄ_¶Ä¢éB
@cÌOñõÌ@Ì éOÌÓAM¾YÍQ°Å¬àðÇñÅéÆAÀñÅQÄécêªA
@u¾úV³ñ̨¢ÅȳéÌͪ¼Å·¼vÆ]½B
iw½é©xwuê¼ÆSWæêªxâgX1998N12j
w½é©xÌ`ªæ1¶ªAucêªvu]½vÉà©©íç¸AuM¾YÍvÆq³êÄ¢é±ÆÉ¢ÄAÌæ¤ÉwE·éB
@ìÒ©gÅà éuvªAìÒÌÓ¯ÌÅùÉêÊÉoêµÄ¢él¨ÆµÄæèµíêÄ¢éƱëÉuñ¬àAcêv̼cðFßÄàæ¢Å ë¤Bu½é©vÌålöÉÍêuM¾YvÆ¢¤ÅL¼ð^¦Ä¢éìÒ©gÆØ裻¤ÆµÄ¢éªAÞÍÀèÈuvÉߢl¨Å éB
@ÇÒð¢«Èè¬àêÊÌ^¼ÉAêÞ½ßÉAVµoê·él¨ðuÍvÅàÁÄ\¦·éû@ªÌçêé±Æª éªAu½é©vɨ¯é»êÍA»¤¢¤øÊð_Á½Ó¯IÈqÆÍvíêÈ¢B
i{ì¿i1989juuê¼Æ̶Ív
w\»wÌne_Ñæêêª@ßã¬àÌ\»Oxj
{¡¼Yi1976jÅàuêlÌIÀ¿vðõ¦Ä¢éÆwEµÄ¢½ªA{ì¿i1989jÅ௶æ¤ÉuM¾YvÍuÀèÈuvÉߢl¨vƵĢéBêûAìiÌÌuM¾YvÉ¢ÄÌ`ÊÅAua¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YªAvÆÈÁÄ¢é_É¢ÄAÌæ¤ÉwE·éB
iªjM¾YÍAË@ƵĩéåÌ©ç©çêéÎÛÖÆÊuðϦéB±±ÅÍAM¾YÍí BƯñÉz³êAÞÌeñ¾âèæèÉÁíÁÄ¢él¨ÖÆޢĢéB±ÌªÍÞµëuM¾YÍvÆ é׫ƱëªAuM¾YªvÆ ç½ßÄ\¦µ¼µÄAÞðí BƯɩéìÒ̶Ýð¾ç©ÉµÄ¢éÌÅ éBM¾YÆcêÆ̬³ÈΧÌèðÐîµ½êÒÌtɨ¢ÄÍAålöÆìÒÆÌü ðI泹Ģ½ªAIÇɨ¢ÄÍAÙÆñÇÓ¯IƾÁÄ¢¢ÙÇÉAìÒÍålöÆÌÔÉ£ðݯAË«úµÄ¢éB±ÌêÊÍAu½é©vÅÍd¢Ó¡ð±ÆÉÈéB
i{ì¿i1989jj
±ÌøpÅAuM¾YÆcêÆ̬³ÈΧÌèðÐîµ½êÒÌtɨ¢ÄÍAålöÆìÒÆÌü
ðI泹Ģ½vÆÍA`ªæ1¶ªuM¾YÍvÆÈÁÄ¢é±ÆðwµÄ¢éB`ªÌæ1¶ÆÎƵÄAuM¾YªvÆÈÁÄ¢é±Æ©çAuÞðí
BƯɩéìÒ̶Ýð¾ç©ÉµÄ¢évÆ¢¤Ï»ðwE·éB»êÜÅuM¾YvÌàÊÉu©êÄ¢½_ªA±Ìê¶ÉæèA¼Ììl¨ÆuìÒvÌÊuÜÅã޵ĢéÆ¢¤±ÆÅ ë¤B³çɱÌ_ÌÏ»ðÌæ¤ÉӡïéB
@¶ÆSÌ©Rðæèßµ½M¾YªÂ¶½¢E©çL¢¢EÖoéƯÉλ³êAgåµÄfµo³ê½Ó¯ÌàÍêCÉÁµçêéB»êÜÅAhÉηé½Æ¢¤`ÅOEð໵±¯Ä¢½ÌðA©ÈÌOÝ»ÖÆ}]³¹ÄIíéBM¾YªOEÉú½êéƯÉÇÒàðú³êéB
i{ì¿i1989jj
±Ìæ¤ÉAu¶½¢E©çL¢¢EÖoév±Æð¦·Ï»Å éÆ·éBw½é©xÉ¢ÄÍAÌæ¤ÉÜÆßÄ¢éB
@u½é©vÍAäÌ¢êÂNÌC¿Ìð`¢½àÌÆ¢¤Ó¤ÉvñÅ«æ¤Bµ©µA»ÌC¿ÌÍA¶âSÌ©RÉ]ÁĶ«æ¤Æ·é¶Ì\¢ÌãÉA»êªjQ³ê½ÌsõÈCªðUIÈûüÖƳ¹æ¤Æ·éÓ¯Ììpð©Ô¹½ñd\¢ðÁÄ¢éÌÅ éB
@ìÒuê¼ÆÍA é©Ì¼Æ©g̼Ú̱ÉÞðæéɽÁÄAPÊ̱»ÌàÌðʶIÉq·éÌÅÍÈÄAÓ¯ÌàðÎÛ»µÄAC¿Ìà½çµ½oðܳɽçµßæ¤ÆµÄ¢éÌÅ éB¼ÆÍBsõ´â{èÆ¢Á½ÌGlM[ÌÁ¬xIȪAVµ¢s®ÌGlM[É]»µA»ÌuÔɶÌ[ÀðÀ´Å«é±ÆðæmÁÄ¢½Bu½é©vÍ»¤¢¤©ÈÌÎÛ»ðÝæ¤Æµ½ìiÅ Á½B
i{ì¿i1989jj
±Ìæ¤ÉA{ì¿i1989jÅÍAw½é©xÌåèÍAuäÌ¢êÂNÌC¿Ìð`¢½àÌvÅ èA»ÌuÂNvÌSÌϻƢ¤àÌÍAu»êÜÅAhÉηé½Æ¢¤`ÅOEð໵±¯Ä¢½ÌðA©ÈÌOÝ»ÖÆ}]³¹véÆ¢¤Ï»Å éÆA_t¯Ä¢éÌÅ éB
@ܽAæÌæPÍæPßuê¼ÆÌæs¤Åàæèã°½AJûßqi1977juu½é©vÉݦéuê¶wÌ´^viwÉì¶xæ11@1977N3jÅàA{ì¿i1989jƯlÌl@ð±±ëÝÄ¢éB{ì¿i1989jÆÍA_¶Ì\N̪OãµÄµÜÁ½ªAÅãÉøpµÄmFµÄ¨B
¾ç©ÉM¾YìÒ©gÅÈÈèAM¾Y©çª£µ½ìÒÉæÁÄM¾YÌçÌ\îª`©êA¡ÜÅÌêlÌI¶Ý©çOlÌI¶ÝÉÏíÁÄí Ư¶Êuɨ©êÄ¢éÌÅ éB
iJûßqi1977juu½é©vÉݦéuê¶wÌ´^v
wÉì¶xæ11j
ãÌwEÍAua¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YªAvÆ¢¤ìiÌÉ¢Ä̾yÅ éB»ÌϻɢÄAÌæ¤ÉwE·éB
u½vªIíèuaðvu²avÌæÉB·éÆA´îEs®êÌƵÄÌ©äðѶàÃÜèAƯÉnìåÌÌ«àÃÜèuÃvÌ«nÉüéB»¤ÈêÎM¾YͳÌOlÌI¶ÝÉßéÌÅ èAìÒÍ éêèÌ£ð¨¢ÄM¾YÌ¢EðÝé±ÆÉÈéB
iJûßqi1977jj
±Ìæ¤ÉAuu½vªIíèuaðvu²avÌæÉB·éÆA´îEs®êÌƵÄÌ©äðѶàÃÜèAƯÉnìåÌÌ«àÃÜèuÃvÌ«nÉüvÁ½±ÆÉæÁÄAua¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YªAvÆ¢¤uOlÌI¶ÝÉßévÆ¢¤B±ÌJûßqi1977jɨ¯éAw½é©xÌÌl@ÍA{¡¼Yi1976jâA{ì¿i1989jƤÊ_ðàÁÄ¢éƾ¦æ¤B
@ÈãÌæ¤ÉAw½é©xÉ¢ÄÌæs¤ðÝÄ«½BÔØri1944jÅÍAw½é©xÌuM¾Yvª½ÇéSðlÂÌiKðAu½vAu¡vAuaðvAu²avƵÄAuê¼ÆÌìiɤʷéßöðÆç¦Ä¢½B»±Éu¬àìÆvƵÄÌuê¼Æð©oµÄ¢½B
@¬chi1972,cjÅÍAucêvÆuM¾YvÆÌâèÆèÆÆàÉAí
½¿Ì`ʪuM¾YvÌuàSðÆç·¾vÅ èAuÂÜçÊÓnƨð£ÁÄ¢éªAàSͬSÈFsÒÅ évÆ¢¤uM¾YvÌl¨ðwEµ½B»µÄAua¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YvÆ¢¤`Ê©çAuàÉúOÆOÉÃæ²aðYí¹Ä¢épvð©oµAw½é©x̬§ðªµÄ¢½B
@{¡¼Yi1976jÅÍAuM¾YvÆ¢¤OlÌÅÄ̳êȪçAuÀ¿I´Á©ç¢¦ÎêlÌvÅ éÆmF·éB¾ªAua¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YªAvÆ¢¤qÉæÁÄAuêlÌIÀ¿©çOlÌIÀ¿ÉÏívéƵÄA»±Éu²avª¬§µ½ð©oµÄ¢½B
@ܽA{ì¿i1989jÅÍA`ªÌæ1¶ªuM¾YÍvÆA\¶ãs©RÅ éÌÉεAÌua¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YªAvÆ¢¤qÍuM¾YªAvÆÈÁÄ¢é±ÆÉ
Ú·éB»µÄA»ÌÏ»ÆÍAu¶½¢E©çL¢¢EÖoévÆ¢¤Q°Ì é®ðoé±ÆÆAÓ¯ªuOEð໵±¯Ä¢½ÌðA©ÈÌOÝ»ÖÆ}]v·éÆ¢¤Ï»Å éÆྵĢ½BܽAJûßqi1977jÅàA¯¶qÉ¢ÄAuu½vªIíèuaðvu²avÌæÉB·éÆA´îEs®êÌƵÄÌ©äðѶàÃÜèAƯÉnìåÌÌ«àÃÜèuÃvÌ«nÉüévÆ¢¤Ï»ð©oµÄ¢½B
@ÈãÌæ¤ÉAæs¤ÅÍAw½é©xɨ¢ÄuM¾YvÌàÊÌßöªdvÅ èAìiÌåèƧÚÉ©©íéàÌÅ éÆ¢¤_ͤʵĢ½Æ¢¦éB»ÌêûÅAua¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YªAvÆ¢¤qªAìiðl¦é¤¦ÅÇÌæ¤ÈÓ¡ª éÌ©AÆ¢¤_ðdvµÄ¢½B±êçÉ¢ÄAæSÈ~ÅÀÛɪÍEl@µÄ¢B
@Ìæ2ÅÍA»ÌOiKƵÄAæs¤ð¥Ü¦½¤¦ÅÌw½é©xÌ[TAêÊ\¬É¢Į·é±ÆÉ·éB
@qªÍ̪ÞÚðè·éOÉAw½é©xÌ[TÆêÊ\¬É¢Äl¦Ä¨«½¢BªÞÚÍAìi̽ð¾ç©É·éÌ©AìiÌåèÍÇÌæ¤ÈàÌ©AÆ¢Á½âèÉ©©íÁÄ¢éBq̪ÞÆ¢ÁÄàAìiɦµ½ªÞÚÅȯêÎAìiÌåèð¾ç©É·é±ÆÉÂȪçÈ¢B»±ÅæQÅÍAOÅݽæs¤ð¥Ü¦ÈªçAìį¨Ü©È¬êÆAêÊÌ\¬É¢ĮµÄ¨Kvª ë¤B»ÌãAæRÅAÀÛÉq̪ÞÚÉ¢ÄAè·é±ÆÉ·éB
@uM¾YvÍcÌ@ÌOÌÓA¬àðÇñÅ¢éÆucêvÉQéæ¤É£³êéBuM¾YvÍ»êÉ©Üí¸Çݱ¯éBucêvªQĵܢAuM¾Yvà°Cð´¶é̪AéÌê߬¾Á½BuM¾YvÍQ°èÉÂiêÊTjB
@©i@újAuM¾YvªQÄ¢éÆAucêvªN«éæ¤É£·BuM¾YvÍ°CÌ ÜèA¶Ôð·éªÜ½°èÉÂBÄÑucêvªN±µÉéÆuM¾YvÍ·®ÉN«éæ¤ÈfUèðݹÄucêvðÇ¢Ô·BOxÚÉucêvªN±µÉéÆAuM¾YvÍ ð§ÄÄAuí«ÖÄ»¤®Ã^_]Ó©çA®N«çêÈÈéñ¾vÆucêvɾ¢úÂBuM¾YvͱÌâèÆèÉæÁÄAáªoßĵܤªA¡xÍucêvÉ ð§ÄAN«ãªë¤ÆµÈ¢BucêvªN±µÉȯêÎN«ãªë¤©AvÄ·éiêÊUjB
@uM¾YvÍ×̮ɢéí
½¿ÌºÉ¨ðX¯éB¢ÂàÍQVÌuMOvÍA
½¿Æ½x௶âèÆèðµÄVñÅ¢éiêÊVjB
@ÄÑucêvªN±µÉéBµ©µAuM¾YvÍN±³êé±ÆÉæÁÄA]vÉN«çêÈÈéBuM¾YvÉè`í¹æ¤ÆA®Åzcð½½Ýnß½ucêv¾Á½ªAuM¾YvÍÙÁÄ©Ä¢éB½Üè©Ë½ucêvÍAusFÒvÆ{ÂéBµ©µuM¾YvàuNñÌ]ÐÈèúèÉÈé̪FsÈçA»ñÈFsÍ^½¾vƾ¤B»Ì¾tÅucêvͫȪç®ðoÄsBà¤N±µÉé±ÆÍÈ¢ÆvÁ½uM¾YvÍAQN«ãªéB
ª¦ÈªçuM¾YvÍA³çÉucêvð¢ç¹æ¤ÆzKÉXP[gÉs±Æðv¢ÂB»ñȱÆðl¦Ä¢éÆA¡ÜÅÌâèÆèðYê½æ¤ÈçðµÄucêvªÄÑ®ÉüÁÄéBV³ñÉ¢Äà礲k̽ßÌMðTµÉ½Æ¢¤BuM¾YvÍA©ªÌÁĽMÅÍÈAeÌMðg¤æ¤É¾¤BucêvÍA¾íêéªÜÜÉ®ðoÄsBuM¾YvÍ}ÉÂεÈèAzcð½½ÝȪçÜð¬·B»µÄ·ª·ªµ¢CªÉÈéiêÊWjB
@®ðo½uM¾YvÍA×̮ɢ½uMOv½¿Öua¢¾ARµµÒµ¢Îçvð©¹éiêÊXjB
@ÈãÌæ¤Évñ·é±ÆªÅ«éw½é©xͺÌæ¤ÉTÂÌêÊÉæØé±ÆªÅ«éB\à̶ÔÆÍA¿ÆµÄYtµ½w½é©x{¶Ì¶ÔðwµÄ¢éiì¬ÍûücjB
| êÊÔ | ¶Ô | êÊ | êÊÌ[T |
|---|---|---|---|
| êÊT | 1`12 | OÌÓÌâèÆè | ucÌOñõÌ@Ì éOÌÓvAucêvÆuM¾Yvª×¯mÅQÄ¢éBucêvªA¬àðÇñÅ¢éuM¾YvÉQéæ¤É£·B |
| êÊU | 13`49 | ucêvÆÌâèÆè@ | @ª é©iu¾¡l\êN³\OúvjAuM¾YvªucêvÉN±³êéBOxucêvªNµÉéªuM¾YvÍN«æ¤ÆµÈ¢B |
| êÊV | 50`53 | ×Ì®Ìlq | uM¾YvªQÄ¢é×Ì®ÅÌñlÌí ªÍµá¢Å¢élqB¯¶æ¤ÈâèÆèðJèԵĢéB |
| êÊW | 54`122 | ucêvÆÌâèÆèA | ÄÑucêvªuM¾YvðNµÉéBâªÄucêvÍuM¾YvÉ{éªAucêvÆ̽CÈ¢âèÆèÉAuM¾YvÍÜð¬µað·éB |
| êÊX | 122`131 | ×Ì®ÅÌí ½¿ÆÌâèÆè | N«½uM¾Yvª®ðoÄA×Ì®ÖÆsBuM¾YvÍA×Ì®ÌuMOvçí ÆâèÆè·éB |
@±Ìæ¤É®·éÆAw½é©xÌåªÍAuM¾YvÆucêvÆÌâèÆèªWJ³êé±Æª¾ÄÉÈë¤BuM¾YvªucêvÆÌâèÆèÉæÁÄAN«ãªè®ðoéÜÅÌ÷ÈSÌßöð`¢Ä¢éƾ¦éBÔØri1944jÅÍAw½é©xÌuM¾YvÌSÉAu½vu¡vuaðvu²avÆ¢¤uê¼ÆÌìiɤʵ½SÌßöð©oµÄ¢½Bw½é©xðl¦é¤¦ÅAuM¾YvÌSÏ»Ìßöðl¦È¢í¯ÉÍ¢©È¢BtÉ¢¦ÎAêxucêvɽµ½uM¾YvªÇÌæ¤ÉµÄ®ðoéÉéÌ©AÆ¢¤SÌßöð©é±ÆªAìið¾ç©É·é±ÆÉÈéÆ¢¦é¾ë¤B
@ê¾ÅuSvÆ¢ÁÄàAw½é©xÌuM¾YvÌàÊÍAêlÅÍÈ¢BàÆàÆ°½¢¾¯¾Á½uM¾YvÌN«çêÈ¢RÍA½xàN±µÉé±ÆÅucêvÖÌu½vÉÏíéBucêvðÇ¢oµzc©çN«ãªÁ½ ÆàAuM¾YvÍucêvð¢©É¢ç¹é©Æl¦éB»µÄucêvÆÌâèÆèÉæÁÄAêCÉuaðvÖÆÏ»µÄ¢ÌÅ éB±êçÌoßÍAPÉàÊÌÏ»¾¯ÅÍÈAàÊÌ¿IÈÏ»àN±ÁÄ¢éB¦¿A¶IÈ~Å é°CAucêvÉεÄ̽A¢©É¢ç¹æ¤©Æ¢¤vlAÆ¢Á½Ï»Å éB
@qðªÍ·éêɨ¢ÄàA±¤µ½uM¾YvÌSÌÏ»ðÆç¦é½ßÉÍAàÊÌ¿IÈÏ»ðàÆç¦éKvª éB
@±êç̱Æð¥Ü¦ÄAÉq̪޷é½ßÌÚðl¦éB
@æPÍæRßÅݽæ¤ÉAyOi1986jű±ëÝçêÄ¢éqwªÍÌû@ðQlɵÄAw½é©xðªÍEl@·é½ßÉLøȪÞÚðè·éBȨA_¶\¬ãÍAãIÉÚðè·éæ¤ÈÉÈÁÄ¢éªAÀÛÉÚðl¦éÛÍA½xàÚð§ÄÄÍÚðÄl·éAÆ¢¤ìiɦµ½A[IÈÉæÁÄèµ½B
@ܸAuqÒvɦµ½uqÒvÌåÏ«ðº¤qÆAÎÛɦµ½AæèqÏIÈqÆð¯ÊµA»ê¼êðuqÒ\»vÆuÎÛ\»vÆÉñÊ·éB
@³çÉuqÒ\»vÉÍAæèqÏIÅuÎÛ\»vÌâ«à¾ÆµÄq³êéuà¾vÆAæèuqÒvÌåÏ«ðÑѽuðßvA»µÄuqÒv©çÌåÏIÈu]¿vÆɺÊ檳ê¤éBµ©µAw½é©xÉÍAuqÒ\»v»Ìà̪ÈAìiðl¦é¤¦ÅºÊ檷éKvÍȢƻfµAuà¾E]ßvƵÄêµ½B
@uÎÛ\»vÍAl¨É¢Ä`ʳê½ul¨`ÊvÆA¨É¢Ä`ʵ½u¨`ÊvÆɺÊ檳ê¤éB¾ªAw½é©xÉ¢ÄÍAªÍµ½Êu¨`ÊvÉ·éqªÈ¢½ßAݯȢBµ©µAêÊÌ
@ul¨`ÊvÍAìiÌSÆÈéìl¨ÌuM¾YvÆA»êÈOÌucêvâí
½¿Ìul¨`ÊvÆðæʵ½Bul¨`ÊvÌ»ê¼ê̺ÊÉÍukb`ÊvEus®`ÊvEuóÔ`ÊvEuS`Êvðݯ½Bukb`ÊvÍA¼Úb@iêd®ÊiguhgvhjjÉæél¨ÌïbÌ`ÊÅ éBus®`ÊvÆÍAl¨Ì®ÔIÈs®â®«ª`ʳê½àÌÅ éB»Ìl¨ÌÓ¯IÈs®¾¯ÅÍÈAl¨Ì®ìÉÖ·éàÌÍ·×ıÌqÆÈéBuóÔ`ÊvÆÍAl¨ÌÃÔIÈlqâepª`ʳê½àÌÅ éBÈÇÌ`ÊÍuóÔ`ÊvÅ éBuS`ÊvÆÍAl¨ÌàÊð`ʵ½àÌÅ éiuS`ÊvjB
@w½é©xɨ¢ÄAuM¾YvÌàÊÌßöªåèÆÖíédvÈàÌÅ é½ßAuM¾YvÌuS`ÊvÉ¢ÄÍA³çÉu´ovEuSîvEuvlvÆ¢¤OÂɺÊ檷éBu´ovÆÍAuM¾YvÌÜ´ðͶßƵ½gÌ´oÉæÁÄFm³ê½±Æð`ʵ½qÅ éBuSîvÆÍAuM¾YvÌñ¾êIÅÛIÈ´îð`ʵ½qÅ éBuvlvÆÍAuM¾Yv̾êIÅïÌIÈmð`ʵ½qÅ éB
@Èã̪ÍÚðÓð«ÉÜÆßéÆÌæ¤ÉÈéBiájƵ½àÌÍAw½é©xɨ¯éA»ÌÚÌqÌïÌáÅ éB¶ÔAªÔÍYtµ½¿Ì{¶Æ¯lÌàÌÅ éiì¬ÍûücjBºüª éàÌÍA»ÌºüÌݪ»ÌqÅ éiºüÍûücjB´¶É érÍOµ½B
| uqÒ\»vc | uqÒvɦµ½åÏIÈ\»B |
| uà¾E]ßvc | uqÒvÉæéæèqÏIÈuà¾vu]ßvÌqB iáj24¨Ê^Æ]ÓÌÍ´®Ì°ÌÔÉ|¯Ä éCMæÌÑÅAM¾YªwÌ KÁ½æw̳tÉcÌSȽA`¢Äá½àÌÅ éB |
| @ | |
| uÎÛ\»vcc | q³êé±Æªçɦµ½AæèqÏIÈ\»B |
| uêÊÝèvcc | êÊÌ¢ÜE±±ðÝè·éqB iáj13iaj©i¾¡l\êN³\OújibjM¾YÍcê̺Åáðoµ½B |
| ukb`Êvcc | ¼Úb@ÉæÁIJ«o³ê½eìl¨ÌïbÌ`ÊB iáju5»êɷ©èxxðµÄu̾©çA¡ÓÍà¤Ë½ç¢¢Å¹¤v |
| us®`Êvcc | l¨Ì®ÔIÈ®ìA®«Ì`ÊB iáj18³¤]ÂÄcêÍ®ðoÄs½B |
| uóÔ`Êvcc | l¨ÌÃÔIÈlqAepÌ`ÊB iáj25ÙÂÄ¢éÞðu³ A¼®vÆcêÍ£µ½B |
| uS`Êvcc | u»Ì¼Ìl¨vÉ¢ÄÌàÊÌ`ÊBuM¾YvÌuS`ÊvÍA·×ÄȺÌOÂɺÊæªÉ·éB iáj73cêÍM¾YªN«Äè`Ó¾ë¤ÆvÂÄéB |
| u´ovcc | uM¾YvÌuS`ÊvBuM¾YvÌÜ´ðͶßƵ½gÌ´oÉæÁÄFm³ê½±Æð`ʵ½qBFm³ê½àe»ÌàÌÅÍÈ¢B iáj118¨ª©¦ÈȽB |
| uSîvcc | uM¾YvÌuS`ÊvBuM¾YvÌñ¾êIÅAÛIÈ´îð`ʵ½qB iáj83ÞàÞÂƵ½B |
| uvlvcc | @uM¾YvÌuS`ÊvBuM¾Yv̾êIÅïÌIÈmð`ʵ½qB iáj48व±¤µÄÄNµÉȩ½çA»êÉƶÄN«Äâç¤A³¤vÂÄ¢éB |
@±êçÌÚðAc²iñjɨ«A¶ð¡²isjɨ¢½B}\Ì^CgsÍÌæ¤ÉÈéB
| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l¨`Ê | ྠE ]ß | ||||||||||
| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||
@¶[ɶÔð¨«AuÎÛ\»vAuqÒ\»vÆÈç×½BuÎÛ\»vͶ©çuêÊÝèvAul¨`ÊvƵÄAȺuM¾YvAu»Ì¼Ììl¨vÌul¨`ÊvðÎä³¹çêéæ¤Èç×½Bul¨`Êv̺ÊÚÍA¶¤É¢ÙÇOIÈ`ÊAE¤É¢ÙÇl¨ÌàÊÉ©©íé`ÊÉÈéæ¤zuµ½B
@á¦ÎAukb`ÊvÍAèðµÈÄà®oÅÆ禤éªAus®`ÊvÍ«¿ñÆèð©éKvª éBuóÔ`ÊvÉÈéÆAæèÓ¯IÉ©é±ÆªKvÆÈéBܽAu´ovÍlqðÓ[Ï@·é±ÆÅ éöxµÊé±ÆªÅ«éªAïÌIÈuvlvÌàeðmé±ÆÍïµ¢BuSîvÍ»ÌÔÅ éBÂÜèA¾¢·¦êÎA»ÌÎÛðÆç¦é¢ï³ÉæÁÄAÀ×Ä¢éÆ¢¤±ÆÅ éB
@ªÍÍê¶ð»ÌÜÜêÂÌÚɪ޷éÌÅÍÈAqªªIɪ¯çêéêÍAª¯Ä¢éB¶ÔÈOÉàAªÔªKvÈÌͻ̽ßÅ éBܽAá¦ÎÌæ¤È¶ÌêÍA¶SÌÅucêvÌus®`ÊvƵĪ޳êA»ÌÉuM¾YvÌuS`ÊvªÜÜêÄ¢éÆl¦çêéB
iaj·éÆibj°ÂÄîéÆv½icjcꪯ¶ð]½B@
iw½é©xæ3¶j
@»Ì½ßAiaju·éÆvÍAicjucꪯ¶ð]½BvÉÂȪéqÅ éÆl¦AucêvÌus®`ÊvƵĪ޷éB
@ªÍÍêʲÆɨ±È¢A}\ɵÄA{e̪ɿƵÄYt·éÆÆàÉAæSÈ~Ìl@ÅàA¾yµÄ¢éªÌªÍ}\ð²«oµ½BȨA{eɲ«oµ½}\ÍAȪ»·é½ßukb`ÊvAus®`ÊvccðA»ê¼êukbvAus®vccƪLµÄ¢éB
@\LÉ¢ÄÍAÌæ¤Éµ½BYtµ½ªÍ}\Ì¿ÍAêʲÆɨ±ÈÁ½àÌÅ éB}\É«ÞÌÍA´¥ÆµÄA¶Ôi1A2A3cjƪÔiiajAibjAicjcjÌÝÅ éB±Ì¶ÔÍA{e̪ɿƵÄYtµ½w½é©xÌ{¶ÆεĢéBuêÊÝèvÌqÍA¶ÔÈOɼÚ\É«Á¦Ä¢éBܽAæTÅÚµl@·é¡«Ì éqƵġÌÚɪͳê½qÉ¢ÄÍA»Ì¶ð궲«oµ\É«Á¦Ä¢éB
@ÈãÌæ¤ÉAqðªÍµ½Êð³ÉAæSÅïÌIÉw½é©xÉ¢Äl@ð¨±ÈÁÄ¢±ÆÉ·éB
@ÉAq̪ުÍÌ}\ð³ÉAqɦµ½ìiÌl@ðsȤB±±Å
Ú·é±ÆÍAuM¾YvÌSÌßöªÇÌæ¤É`©êÄ¢é©AÆ¢¤±ÆÅ éBȨAêÂÌqª¡ÌÚɪ޳êÄ¢éqª éªA»êÉ¢ÄÍÈ~žy·é±ÆÉ·éB
@{Åøp·éw½é©x{¶ÌT_ÍA´¶ÉæéB¶ÔAªÔÍøpÒÉæéB
yêÊTz
@1iajcÌOñõÌ@Ì éOÌÓAibjM¾YÍQ°Å¬àðÇñÅéÆAicjÀñÅQÄécêªA
@uidj¾úV³ñ̨¢ÅȳéÌͪ¼Å·¼viejÆ]½B
@2bµ½B3iaj·éÆibj°ÂÄîéÆv½icjcꪯ¶ð]½B4ÞÍ¡xÍÔðµÈ©Â½B
@u5»êɷ©èxxðµÄu̾©çA¡ÓÍà¤Ë½ç¢¢Å¹¤v
@u6í©ÂÄÜ·v
@7iajÔàÈibjcêÍ°ÂĹ½B
@8iajÇ꾯©ibjo½B9M¾Yà°È½B10vð©½B11êªß¬Ä½B12ÞÍvðÁµÄAQÔèðµÄA»µÄé ÌÝÉçðß½B
| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||
| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||
| 1 | 1iaj | @ | @ | 1ibj | @ | @ | @ | 1idj | 1icjiej | @ | @ | @ |
| 2 | 2 | @@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 3 | @ | @ | @ | @ | @ | @@ | 3ibj | @ | 3iajicj | @ | @ | @ |
| 4 | @ | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | @ |
| 6 | @ | 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 7 | 7iajÔàÈ | @ | @ | @ | 7iajiÔàÈj | @ | @ | @ | 7ibjcêÍ°ÂĹ½B | @ | @ | @ |
| 8 | 8iajÇ꾯© ibjo½B |
@ | @ | @ | 8iajiÇ꾯©j | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 9 | @ | @ | @ | @ | 9 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 10 | @ | @ | 10 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 11 | 11iêªß¬Ä½j | @@ | @ | @@ | 11êªß¬Ä½B | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 12 | @ | @ | 12 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@±êÍìiÌ`ªÅ éBìiÌåvÈÔÅ éu½é©vÌOÌÓɨ¯éAuM¾YvÆucêvÆâèÆèð`¢½êÊÅ éB
@æP¶iajucÌOñõÌ@Ì éOÌÓvÆ¢¤ÁèÌúªAuêÊÝèvÌqÉæÁÄÝè³êéBæ1¶ÍAuM¾Yvªu¬àðÇñÅév±ÆÆAicjidjiejÆucêvÌus®`ÊvÌukb`ÊvªAê¶ÆµÄq³êÄ¢é±ÆªÁ¥IÅ ë¤BêÊÌÝèÆAuM¾YvÌóµAucêvÌs®ªê¶Å çí³êÄ¢éB3¶©ç6¶ÜÅÌqÉæÁÄA@ª éÌÅQÄÙµ¢Æl¦éucêvÉεÄAuM¾YvÍ»êÉÍ©Üí¸¬àðÇÞ±ÆÉMSÉÈÁÄ¢éÆ¢¤¼ÒÌl¦Ìᢪ¦³êÄ¢éB7¶ÅucêvÍu°ÂĹv¤ªAuM¾YvͬàðÇݱ¯éBuM¾YvÍuêªß¬v½Æ±ëÅæ¤â°Cð´¶A°èÉÂB
@2¶ibjÌu°ÂÄîéÆv½vÆ¢¤uS`ÊvÌuvlvA9¶ÉuM¾Yà°È½vÆ¢¤uS`ÊvÌu´ovª èAuM¾YvÌàÊÉ_ªu©êq³êÄ¢éB
@êÊTÅÍAuM¾YvÆucêvÆ̾ç©ÈΧͶÜêĢȢàÌÌAl¦ÌᢪùɶÜêÄ¢éB¾ªA¯ÉñlªuÀñÅQÄév±Æ©çAÓ¾ñ̼ÒÌlÔÖWÍA¯«ÈGηéæ¤ÈÖWÉÍÈ¢±Æà¯É¦³êÄ¢éB
yêÊUz@
13iaj©i¾¡l\êN³\OújibjM¾YÍcê̺Åáðoµ½B
@u14Z߬ܵ½¼v15iajÁ©·Ü¢Æibj¨Ìí«ÅéÉ]ÂÄéB
@u16iaj¡N«Ü·vibjÆÞͦ½B
@u17¼®Å·¼v18³¤]ÂÄcêÍ®ðoÄs½B19ÞÍAéâ¤É°ÂĹ½B
| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||
| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||
| 13 | 13iaj | @ | 13ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 14 | 14iZ߬j | @ | @ | @@ | @ | @ | @ | 14 | @ | @ | @ | @ |
| 15 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 15ibj | @ | 15iaj | @ |
| 16 | @ | 16iaj | 16ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 17 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 17 | @ | @ | @ | @ |
| 18 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 18 | @ | @ | @ |
| 19 | @ | @ | 19 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@u©vÉÈèAucvÌ@Ì©ð}¦éBucêvÍQÄ¢éuM¾YvðN±µÉéBµ©µAuM¾YvÍ°¢½ßAÄÑ°ÁĵܤB
@uM¾YvÍ©ÉÈÁÄAucêv̺ÅÚðoÜ·BuM¾YvÍA16¶Åu¡N«Ü·vƦéÆAܽuAéâ¤Évi19¶jQüÁĵܤBuAéæ¤ÉvÆ èA±Ì_ÌuM¾YvÉÆÁÄÍA°é±Æª©RÅ èAÚoßéi é¢ÍN±³êéj±ÆÍAs©RÈóÔÅ éæ¤Éq³êÄ¢éBucêvÉηés@â½IÈ´îÅÍÈA°è½¢Æ¢¤¶IÈ~ÉæÁÄÄÑ°ÁĵܤÌÅ éB
@15¶iajuÁ©·Ü¢ÆvÆucêvÌuS`Êvª éªA13¶ibjÅuM¾YvÌàÊÉ_ªu©êÄ¢é±Æ©çA±êÍibjÌu¨Ìí«ÅéÉ]ÂÄévÆ¢¤ucêvÌû²©çuM¾YvªucêvÌSðµÊÁ½àÌÅ èAucêvÌàÊÉ_ªu©êÄ¢éÆÜÅ;¦È¢BêÊTɱ«AêÊUàuM¾YvÌàÊÉu©ê½_©çq³êÄ¢éB
@20Acê̺Åáªoß½B
@u21¼®N«Ü·v22iajÞÍibjCÀßÉAicjXèȪçé ©çñÌrÜÅoµÄAidjÌÑðµÄ©¹½B
@u23¨Ê^Éà¨Ö·é̾©ç¼®N«Ä¨àêv
@24¨Ê^Æ]ÓÌÍ´®Ì°ÌÔÉ|¯Ä éCMæÌÑÅAM¾YªwÌ KÁ½æw̳tÉcÌSȽA`¢Äá½àÌÅ éB
@25iajÙÂÄ¢éÞðibju³ A¼®vicjÆcêÍ£µ½B
@u26åävA¼®N«Ü·B27\\ÞûÖsÂÄľ³¢B28¼®N«é©çv29iaj³¤]ÂÄÞÍibj¡ÉàN«³¤ÈlqðµÄ©¹½B
@30cêÍÄÑoÄs½B31ÞÍ°èɾñÅs½B
| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||
| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||
| 20 | @ | @ | @ | @ | 20 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 21 | @ | 21 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 22 | @ | @ | 22iajÞÍ icjXèȪçé ©çñÌrÜÅoµÄA idjÌÑðµÄ©¹½B |
@ | @ | @ | 22ibjiCÀßÉAj idjiÌÑðµÄ©¹½Bj |
@ | @ | @ | @ | @ |
| 23 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 23 | @ | @ | @ | @ |
| 24 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 24 |
| 25 | @ | @ | @ | 25iaj | @ | @ | @ | 25ibj | 25icj | @ | @ | @ |
| 26 | @ | 26 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 27 | @ | 27 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 28 | @ | 28 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 29 | @ | @ | 29iaj³¤]ÂÄÞÍ ibj¡ÉàN«³¤ÈlqðµÄ©¹½B |
@ | @ | @ | 29ibji¡ÉàN«³¤ÈlqðµÄ©¹½Bj | @ | @ | @ | @ | @ |
| 30 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 30 | @ | @ | @ |
| 31 | @ | @ | 31 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@uM¾YvªN«È¢½ßucêvªÄÑN±µÉéB
@21¶A22¶É éæ¤ÉAuM¾YvÍ°¢½ßN«éCÍÈ¢ªAucêvðÇ¢¥¨¤Æ·éBηéucêvͽƩN«Äà稤Æ23¶u¨Ê^Éà¨Ö·é̾©ç¼®N«Ä¨àêvÆuM¾YvªN«ãªçȯêÎÈçÈ¢Rðño·éBuM¾YvÍ26`28¶Ìæ¤ÉεA30¶ÅucêvªoÄsÁ½ãA31¶ÅÄÑQüÁĵܤB
@uM¾YvÍucêvðྷé½ßÉA¡ÉàN«é¾ë¤Æ¢¤Zð©¹éBêxÚÍÔð·é¾¯¾Á½uM¾YvÍAÓ}IÉèðÇ¢¥¨¤ÆµÄ¨èAoÁµÍ¶ßÄ¢éB
@22¶A29¶Éu©¹½vÆ èA_ªuM¾YvÌàÊÉu©êÄ¢éB
@u32³ ^_B33Ǥµ½ñ¾Â³v34iaj¡xÍibjpÌ éºicj¾B35M¾YÍÜp¾ñÅsA¢¾´êÉBµÈ¢ð}ÉÄÑÔ³êésùõ©ç ð§Ä½B
@u36N«éÆ]ÖÎN«Ü·æv37iaj¡xÍÞàx¹ðïÄibjN«éÆ]ÓlqàµÈ©Â½B
@u38{ɵĨàêB39नVàFoÄÜ·¼v
@u40í«ÖÄ»¤®Ã^_]Ó©çA®N«çêÈÈéñ¾v
@u41 Ü̶âIv42iajcêÍibj{ÂÄicjoÄs½B43M¾YàरÍÈȽB44N«Äࢢ̾ªA]èN«ë^_Æ]Íê½ÌÅÀÛN«ÉÈÂĽB45iajÞÍ{Æ°ÌÔÌÑð©ÈªçAibj»êÅàà¤NµÉé©^_Æ¢¤sÀð´¶Ä½B46N«Äâ뤩ÈÆvÓB47Rµà¤µÆvÓB48व±¤µÄÄNµÉȩ½çA»êÉƶÄN«Äâç¤A³¤vÂÄ¢éB49ÞÍå«ÈáðJ¢Ä¢¾¡ÉÈÂĽB
| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||
| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||
| 32 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 32 | @ | @ | @ | @ |
| 33 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 33 | @ | @ | @ | @ |
| 34 | @ | @ | @ | @ | 34iaj icj |
@ | @ | @ | @ | 34ibj | @ | @ |
| 35 | @ | @ | @ | @ | @ | 35 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 36 | @ | 36 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 37 | @ | @ | @ | 37iaj ibj |
@ | 37ibj | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 38 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 38 | @ | @ | @ | @ |
| 39 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 39 | @ | @ | @ | @ |
| 40 | @ | 40 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 41 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 41 | @ | @ | @ | @ |
| 42 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 42iaj icj |
@ | 42ibj | @ |
| 43 | @ | @ | @ | @ | @ | 43 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 44 | @ | @ | @ | @ | @ | 44 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 45 | @ | @ | 45iaj | @ | @ | 45ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 46 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 46 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 47 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 47 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 48 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 48 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 49 | @ | @ | 49 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@@OxucêvÍN±µÉéBuM¾YvªucêvðÇÈè¯é±ÆÅAucêvÍoÄsªAuM¾YvàáªoßĵܤB
@È©È©N«È¢uM¾YvÉεÄucêvÍA34¶upÌ éºvÅb·BηéuM¾YvàA35¶uÜp¾ñÅsA¢¾´êÉBµÈ¢ð}ÉÄÑÔ³êésùõ©ç ð§ÄvéB»µÄA40¶uí«ÖÄ»¤®Ã^_]Ó©çA®N«çêÈÈéñ¾vƾ¢ú±ÆÅAucêvðÇ¢¥ÁĵܤBucêvƾ¢¢ÉÈÁ½±ÆÅAuM¾YvÍ®SÉoÁµÄµÜ¤Bµ©µAÚÍoß½àÌÌA44¶u]èN«ë^_Æ]Íê½ÌÅÀÛN«ÉvÈèAN«ãªë¤Æ͵ȢB»µÄ48¶uव±¤µÄÄNµÉȩ½çA»êÉƶÄN«Äâç¤vÆl¦éB
@±±ÉÁÄAuM¾YvͶIÈ°CÅÍÈAucêvÉηé¸_IÈsÀi45¶u»êÅàà¤NµÉé©^_Æ¢¤sÀð´¶Ä½vjÆA{èi48¶uव±¤µÄÄNµÉȩ½çA»êÉƶÄN«Äâç¤vjÉæÁÄN«ãªçÈ¢A é¢ÍN«ãªé±ÆªÅ«ÈÈéBN«ãªçÈ¢RªA©gÅÍÈAÎucêvÉÈéÌÅ éB
@±êÜÅàAuM¾YvÌuS`ÊvÉÍuvlvɪ޳êéqªFßç꽪A44`48¶ÍïÌIÈuvlvÅ é±ÆÉÚ³êéB32¶ÈOÜÅÍA©ªª°è±¯é½ßÉucêvðÇ¢¥¨¤ÆµÄ¢½Bµ©µA±Ì32¶©çÌøpÅucêvÉOxN±³êé±ÆÉæÁÄAuM¾YvÍA©gªN«ãªèÉ¢óµð©oµi44¶jAN«ãªé½ßÌððl¦i48¶jA»µÄ»êªB¬³êéÜÅÍN«ãªçÈ¢ÆßéÌÅ éi48¶jB±êÍAuM¾Yvª®SÉoÁµAïÌIÉuvlvµÄ¢é±Æð\íµÄ¢éBqÌ¿ÌÏ»ÉæÁÄàAuM¾YvÌN«ãªêÈ¢RªÏ»µÄ¢é±Æª¦³êÄ¢éÌÅ éB
@34¶Íu¡xÍpÌ éº¾BvÆ]¿IÈ»fð\í·qÉÈÁÄ¢éªA±êÍuqÒv©çuqÒ\»vÅÍÈAuM¾YvÌ»fÉæéàÌÅ èAuM¾YvÌàÊÉu©ê½_©çÌuM¾YvÌuS`Êvu´ovÅ ë¤B
@42¶Éibju{ÁÄvÆucêvÌuS`Êvª éªA±êÍ_ªNÉu©êÄ¢é©Æ¢¤âèÉ©©íéàÌÅÍÈA15¶iajuÁ©·Ü¢ÆvƯ¶æ¤ÉAû²âdÈÇÌOIÈÁ¥Å ë¤BêÊUàAuM¾YvÌàÊÉ_ªu©êÄ¢éB
@±Ìæ¤ÉêÊUÅÍAucvÌOñõÌ©ÉÈèAucêvªN«æ¤ÆµÈ¢uM¾YvðOxN±µÉéBOxÚÉN±³êéÆAuM¾YvÍ°CÅÍÈucêvÖÌ{èÉæÁÄAN±µÉéÀèN«ãªçÈ¢±ÆðßéBêÊUÍAuM¾YvÌN«éRªÏ»·éêÊÆÈÁÄ¢éB
yêÊVz
@50¢ÂàÞɯȢQVÌMOªA¡úÍN«ðµÄA×̮ŠÌFqÆ¢ÅéB
@u51iaj¨èÊBìÊAåÊA¬ÊvibjÆ»ñÈðêÉ©ñÅéB52iaj»µÄêiºð£èã°ÄA
@uibj´àå«¢ÌÍFq¿âñÌáÊvicjÆêlª]ÓÆAêlªidjuMO³ñÌ ½ÜviejÆ{½B53ñlͽÕ௶ðJèԵĽB
| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||
| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||
| 50 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 50 | @ | @ | @ |
| 51 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 51iaj | 51ibj | @ | @ | @ |
| 52 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 52ibj idj |
52iaj icj iej |
@ | @ | @ |
| 53 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 53 |
@@uM¾YvÍA©ªÌQ°ª 鮩çAu×Ì®vÅÌlqðf¤B×Ì®ÅÍAíÌuMOvÆ
ÌuFqvƪ¯¶ðJèÔµÄVñÅ¢éB
@Q°ðoé±ÆªÅ«È¢uM¾YvÍA×Ì®ÌlqðA®o©çÌîñÉæÁÄfÁÄ¢éB51¶â52¶ÅAukb`Êvâus®`ÊvÌå̪uêÉvAuêlªvÆÈÁÄ¢éÌÍANÌukb`ÊvÅ éÌ©Q°É¢éuM¾YvÉÍ»ÊÅ«È¢©çÅ éBæÁÄA±ÌêÊVɨ¯é×Ì®ÌlqàAuM¾YvÌàÊÉu©ê½_ÉæÁÄuM¾Yv̨©çÌFm³ê½±Æªçªq³êÄ¢éÌÅ éB
yêÊWz
@54AcêªüÁĽB55M¾YÍN«çêÈȽB
@u56वÉÈèܵ½æv57iajcêÍibj±í¢çðµÄ½ÂÄJÉicj]½B58M¾Y͵̤ÍÈ¢Æv½B59ÞÍ̺ÉèñÅéùvðoµ½B60iaj»µÄA
@uibj¢¾ñ\ª évicjÆ]½B
@u61ǤµÄ©¤â´ ¾©ccv62cêͧð¢½B
iT_´¶BȺ¯¶Bj
| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||
| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||
| 54 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 54 | @ | @ | @ |
| 55 | @ | @ | @ | 55 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 56 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 56 | @ | @ | @ | @ |
| 57 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 57iaj icj |
57ibj | @ | @ |
| 58 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 58 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 59 | @ | @ | 59 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 60 | @ | 60ibj | 60iaj icj |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 61 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 61 | @ | @ | @ | @ |
| 62 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 62 | @ | @ | @ |
@êÊWÌ`ªBÄÑucêvªN±µÉéÆAuM¾YvÍucêvÉηé´îÉæÁÄAÄÑN«çêÈÈéB
@ucêvÉη齩çAuM¾YvÍN«ãªè½ÈÈéÌÅÍÈA55¶uN«çêÈÈvéB»µÄAN«ãªçÈ¢½ßÉAucêv̾tɽ·éB55¶ÍuM¾YvÌuóÔ`ÊvŦ³êéB±êÍAuM¾YvÌÓvÆÍÖíèÈAN«ãªé±ÆªÅ«È¢Æ¢¤óÔÅ éÆ¢¤±ÆÅ éBucêvÉη齪AuM¾YvÌs®ÉìpµÄ¢éÌÅ éB
@u63êÉËÄAZ¼ÉN«êÎÜÔ¼¾B64â´ÅÈÄàÜÔ¼Àâ °¢Å¹¤v
@u65ªÉ½xËëÆ]ÂÄàø«àµÈ¢Åccv
@66M¾YÍÙÂĽB
@u67¼®¨N«B68¨Â¯g¬©çN©é¾ç¤µAV³ñàनoÅÈ³é ¾v
@69êͱñÈð¾ÐȪçA©gÌQ°ð½½Ýnß½B70cê͵\O¾B71æ¹Î¢¢ÌÉÆM¾YÍvÂÄ¢éB
@@72cêÍÌÉ~rÌçð½½ñÅ©çAå«¢~zcð½½Ü¤ÆµÄ§ð͸ܹÄéB73cêÍM¾YªN«Äè`Ó¾ë¤ÆvÂÄéB74iajªM¾YÍibj´èðH͸ÉÌÓÉicjâ©ÈçðµÄ¡ÉȽÜÜ©Ä¢½B75iaj½¤Æ¤ibjcêÍ{èoµ½B
@u76iajsFÒvibjÆ]Á½B
| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||
| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||
| 63 | @ | 63 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 64 | @ | 64 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 65 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 65 | @ | @ | @ | @ |
| 66 | @ | @ | 66 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 67 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 67 | @ | @ | @ | @ |
| 68 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 68 | @ | @ | @ | @ |
| 69 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 69 | @ | @ | @ |
| 70 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 70 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 71 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 71 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 72 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 72 | @ | @ | @ |
| 73 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 73 | @ |
| 74 | @ | @ | 74iaj icj |
@ | @ | @ | 74ibj | @ | @ | @ | @ | @ |
| 75 | @ | @ | @ | @ | 75iaji½¤Æ¤j | @ | @ | @ | @ | @ | 75iaj½¤Æ¤ ibjcêÍ{èoµ½B |
@ |
| 76 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 76iaj | 76ibj | @ | @ | @ |
@uM¾YvÆucêvƪN«é©N«È¢©ðß®ÁÄAâèÆèðJèÔ·ÓÅ éB
@½x¾tÅ£µÄàN«È¢½ßAucêvÍAuM¾YvÉè`í¹é±ÆÅN«ãªç¹æ¤ÆA©gÌQ°ð½½ÝnßéBµ©µAuM¾YvÍ74¶Au´èðH͸ÉÌÓÉâ©ÈçðµÄ¡ÉȽÜÜvÅ éB
@70¶ucê͵\O¾BvÍuqÒv©çÌà¾IÈuqÒ\»vÆ¢¤©½¿Å éªA34¶Ìu¡xÍpÌ éº¾BvƯlÉA±êÍuM¾YvÌuS`ÊvuvlvÌqÅ ë¤B
@73¶ucêÍM¾YªN«Äè`Ó¾ë¤ÆvÂÄéBvÆucêvÌuS`Êvª éªA±êÍæÙÇÜÅƯ¶æ¤ÉAuM¾YvªucêvÌìíð©jÁÄ¢éÌÅ èAucêvÌàÊÉ_ªu©ê½àÌÅÍÈ¢Æl¦çêéBucêvÆÌâèÆèÅN«ãªêÈÈÁ½uM¾YvÉÆÁÄA»ÌÓvªeÕÉÇÝÆêéucêv̾®ÅÍAN«ãªé«Á©¯ÉÍÈè¾È¢BȺÈçA»Ìæ¤ÈucêvÌ©¦§¢½ìíÍAuM¾YvÉÆÁÄA±êÜÅƯ¶æ¤É¼ÚuN«ëvƾíêÄ¢éÌƯ¶Å é©çÅ éBucêvɽµÄ¢éuM¾YvÍAuâ©ÈçðµÄ¡ÉȽÜÜ©Ä¢vé±Æµ©µÈ¢ÌÅ éB
@»±Å75¶AucêvÍ{èo·B±êà73¶¯lÉAuM¾YvÉu©ê½_©çÌucêvÌlqÅ ë¤B76¶Ìû²©çAu{èoµ½v±ÆðFmµ½ÌÅ éB
@u77NñÌ]ÐÈèúèÉÈé̪FsÈçA»ñÈFsÍ^½¾v78Þ௸Æ]½B79iajÞÍàÂÆÅXµ¢ª]н©Â½ªAibj¸ô½B80¶åà·ß¬½B81iajRµibjcêð©ÂƳ·icjÉÍ»êÅ\ñª¾Â½B82cêͽ½Ý©¯ð´ÖÍÓèo·ÆAÜð@«ÈªçAóµð ¯½Ä µÄoÄs½B
| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||
| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||
| 77 | @ | 77 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 78 | @ | @ | 78iaj icj |
@ | @ | 78ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 79 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 79 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 80 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 80 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 81 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 81ibj | 81iaj icj |
| 82 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 82 | @ | @ | @ |
@uM¾YvÍ{èoµ½ucêvÉεÄA¾¢Ô·B»êð·¢½ucêvͫȪç®ðoÄsB
@usFÒvÆ¢¤ucêv̱ÆÎÉAuM¾YvàÎRµÄ77¶uNñÌ]ÐÈèúèÉÈé̪FsÈçA»ñÈFsÍ^½¾vƾ¢úÂBµ©µA»êÍucêvÌusFÒvÆ¢¤±ÆÎÆäµÄAÅXµ³ª«è¸A79¶ibju¸ô½vA80¶u¶åà·ß¬½vàÌÅ Á½BÊIÉÍAucêvð©¹ÄoÄs©¹éÙÇÌøÊðöµ½ªAuM¾YvÍÅë«èÈ¢ÌÅ éB
@78¶uÞ௸ÆvÆ¢¤us®`Êv©çAuM¾YvÉηé{èÍA¾mÉucêvÖü¯çê½àÌÅ èA©ªÌ¾Á½±ÆΪucêvÌàÌÆärµÄ¢éÆ¢¤±ÆÅàA»êª¦³êÄ¢éB
@83ÞàÞÂƵ½B84iajRµà¤NµÉÜ¢ÆvÓÆibjyXN«éCÉÈê½B
@85ÞÍ©Ìâ¤É©gÌQ°ð½½Ýoµ½B86iajåé ©çÌé A»ê©ç¬é ð½½Ü¤Æ·éAÞÍsÓÉibju¦¦vÆvÂÄAicj¡cꪴÉÍÓ½æ¤É©ªÌ´¬é ðÍÓ½B
@87Þͳɵ¦Ä ½ ¨É ª¦½B
@88 µ½©çê·sðµÄâ礩µçB89zKÖXèÉsÂÄâ礩µçB90zKÈçAÔOlÌw¶ª¿Äñ¾B91cêÍV·Å®¢Äî餾©çA©ªªsÂÄîéÔÆàSz·é¾ç¤B
| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||
| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||
| 83 | @ | @ | @ | @ | @ | 83 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 84 | @ | @ | @ | @ | @ | 84ibj | 84iaj | @ | @ | @ | @ | @ |
| 85 | @ | @ | 85 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 86 | @ | @ | 86iaj icj |
@ | @ | 86ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 87 | @ | @@ | 87 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 88 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 88 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 89 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 89 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 90 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 90 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 91 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 91 | @ | @ | @ | @ | @ |
@ucêvð{ç¹Auà¤NµÉÜ¢vÆvÁ½uM¾YvÍAN«ãªèAucêvð¢ç¹éû@ðvÄ·éB
@ucêvÉ«ÔðÔ¯é±ÆÅÇ¢oµ½uM¾YvÍAæ¤âN«ãªé±ÆªÅ«éæ¤ÉÈéB84¶uyXN«éCÉÈê½vÆ é±Æ©çàAuM¾YvÍ©çÌÓuÉæÁÄN«ãªë¤ÆµÈ©Á½ÌÅÍÈA½©ÔÁ½C¿ÉæÁÄA»êÜÅN«é±ÆªÅ«È©Á½±Æªí©éB¾ªAuM¾YvÌ{èͻ꾯ÅÍûÜçÈ¢B86¶ibjuu¦¦vÆvÂÄvÆ èA{èÍܾ®SÉ¥@µ«êĢȢB
@»µÄA88`91¶uS`ÊvuvlvÅAú©ç·sÉo|¯æ¤©ÆvÄ·élqª¦³êéBN«ãªé«Á©¯ªAuyXN«éCÉÈê½vÆ©çÌÓuÆͳÖWÈqÅ Á½ÌÉεA¢ç¹æ¤Æ·éuM¾YvÌàÊÍAuS`ÊvuvlvŦ³êéÌÅ éB
@92iajüêÌOÅÑð÷ßȪçibj±ñÈðlÖÄéÆAicjcêªüÂĽB93cêÍÈé×ûð©È¢â¤ÉµÄGÉµÄ ééïÌÜÍèðñÁÄüêðJ¯É½B94Þ͵ǢÄâ½B95»µÄéïÌRÉðºëµÄ«Üðú¢Ä½B
@96cêÍüêÌÌpMy©ç¬³¢Mðñ{oµ½B97ÜZNOM¾YªÉÛ©çÂĽ©RØÌâ´ ÈMÅ éB
@u98±êÅ@½¾ç¤v99iajcêÍ¡ÌðYê½æ¤ÈçðibjÌÓƵÄicj]½B
@u100½É·éñÅ·v101M¾YÌûÍÌÓÆ¢¾µÞ ƵÄîéB
@u102V³ñɨkð¢Ä¸Ì³v
@u103ÊÚ³B104»ñÈ×¢ñůéàñÅ·©B105¨³ñÌûɧhÈ̪ èÜ·æv
@u106¨c³ñÌàôÂÄ Â½Â¯ªA½ÖÂĹ½©ccv107³¤]ÐȪçcêÍ´×¢MðÁÄ®ðoÄs©¤Æµ½B
@u108iaj»ñÈÌðÂÄs½ÂÄÊÚÅ·ævibjÆÞÍ]½B
@u109³¤©v110iajcêÍibjf¼ÉicjàÇÂĽB111»µÄJÉ»êð³ÌÉdÂÄoÄs½B
| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||
| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||
| 92 | @ | @ | 92iaj | @ | @ | @ | 92ibj | @ | 92icj | @ | @ | @ |
| 93 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 93 | @ | @ | @ |
| 94 | @ | @ | 94Þ͵ǢÄâ½B | @ | @ | 94iÞ͵ǢÄâ½Bj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 95 | @ | @ | 95 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 96 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 96 | @ | @ | @ |
| 97 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 97 |
| 98 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 98 | @ | @ | @ | @ |
| 99 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 99iaj icj |
@ | 99ibj | @ |
| 100 | @ | 100 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 101 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 101 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 102 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 102 | @ | @ | @ | @ |
| 103 | @ | 103 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 104 | @ | 104 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 105 | @ | 105 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 106 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 106 | @ | @ | @ | @ |
| 107 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 107 | @ | @ | @ |
| 108 | @ | 108iaj | 108ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 109 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 109 | @ | @ | @ | @ |
| 110 | @ | @ | @ | @ | 110ibjif¼Éj | @ | @ | @ | 110iajcêÍ ibjf¼É icjàÇÂĽB |
@ | @ | @ |
| 111 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 111 | @ | @ | @ |
@«ÈªçoÄ¢Á½ucêvÍAÄÑuM¾YvÌQ°Ì é®ÉâÁÄéB¼Òªïbððí·±ÆÅAuM¾YvÍí¾©ÜèðXð³¹éA»Ì¼ÚIÈ«Á©¯ÆÈéÓÅ éB
@uM¾Yvªucêvð¢©É¢ç¹æ¤©ÆvĵĢéƱëÉAÄÑucêvª®ÉüÁÄéBüê©çMðæèoµ½ucêvÍ99¶u¡ÌðYê½æ¤ÈçðÌÓƵÄvuM¾YvÉbµ©¯éBR{ÁÄ¢é͸ÌucêvªA©RÉbµ©¯é±Æªs©RÅ Á½½ßA99¶ibjuÌÓƵÄvÆuM¾YvÍucêvÌÓ}ðÇÝæë¤Æ·éB±±ÅàAucêvÉ_ªu©êÄ¢éÌÅÍÈAuM¾Yvª»ÌÓ}𩧩µÄ¢éi é¢Í©§©»¤ÆµÄ¢éjÆl¦çêéB»Ì½ßAuM¾YvàucêvÉεÄ101¶uÌÓÆ¢¾µÞÂƵÄîévlqÅηéÌÅ éB
@102`109¶ÅÍAw½é©xÅͶßÄucêvÆuM¾Yvªïbçµ¢ïbððí·BZÅ éÆí©èÂÂàAÝ¢ÉZÌïbððí·±Æª«Á©¯ÆÈèuM¾YvÍucêvÆÌí¾©ÜèððÁ·é±ÆÉÈéBuÌÓÆvÅ èȪçàAðí·ïbÌÔÉuM¾YvÌuS`ÊvªÈ¢B±êÍAuM¾YvÉÆÁÄA»êÜÅl¦Ä¢½A¢©Éucêvð¢ç¹é©AÆ¢¤vf©çÅÍÈA[¢ÅZàȵÉïbððíµÄ¢éÆ¢¤±ÆÅ éB
@112M¾YÍ}ÉÂεȽB113·sàâß ¾Æv½B114ÞÍ΢ȪçA´ÉêXXÉµÄ Â½¬é ðæèã°Ä½½ñ¾B115~zcàB116iaj»ê©çcêÌཽñÅ¢éÆibjÞÉÍÂε¢É½¾©«½¢â¤ÈCªNÂĽB117ܪ©RÉoĽB118¨ª©¦ÈȽB119»êª|^_jֿĽB120iajÞÍibj©¦È¢ÔÉicjüêðJ¯ÄcêÌ੪Ìà³Åɵñ¾B121ÔàÈÜÍ~½B122Þ͹̷ª^_µ³ð´¶½B
| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||
| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||
| 112 | @ | @ | @ | @ | @ | 112 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 113 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 113 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 114 | @ | @ | 114 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 115 | @ | @ | 115 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 116 | @ | @ | 116iaj | @ | @ | 116ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 117 | @ | @ | 117 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 118 | @ | @ | @ | @ | 118 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 119 | @ | @ | 119 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 120 | @ | @ | 120iaj icj |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 121 | @ | @ | 121 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 122 | @ | @ | @ | @ | 122 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@±ÌøpÍAucêvÆÌâèÆèÉæÁÄAuM¾Yv̽ªXð·éÓÅ éB±±ÅAuM¾YvÍÜð¬µAucêvÖÌí¾©ÜèððB
@112¶u}ÉÂεȽvuM¾YvÍA¬é
ð½½ñŢ餿ÉA116¶ibjuÂε¢É½¾©«½¢â¤ÈCªNÂÄvéB»µÄA117¶u©RÉܪoĽvÆ èAus®`Êv³êéB±118¶u¨ª©¦ÈȽvA119¶u»êª|^_jֿĽvA121¶uÔàÈÜÍ~½vA122¶uÞ͹̷ª^_µ³ð´¶½vÆ èA·×ÄÌqªuS`ÊvÌu´ovÆus®`ÊvÆÈÁÄ¢éB
@uM¾Yvªucêvð¢ç¹æ¤Æl¦Ä¢½Æ«ÍAuS`ÊvÌuvlvŦ³êÄ¢½uM¾YvÌàʪAucêvÆÌí¾©Üèªð©êéÛÉÍA©RÉN±Á½Ï»ÆµÄq³êÄ¢é±ÆÉÚ³êéBN«ãªé±ÆªÅ«È¢lqƯ¶æ¤ÉAucêvÆÌí¾©Üèªð©êélqàAuM¾YvÌÓuÆÍ©©íèÌÈ¢qŦ³êéÆ¢¤±ÆÅ éBN«çêÈÈéóµ\\¦¿AucêvÆÌí¾©Ü誤Üêéóµ\\ÖÌ«Á©¯àAucêvÆÌí¾©Üèªð©êéóµÖÌ«Á©¯àAuM¾YvÉÆÁÄA©çÌÓuÆÍ©©íèÌȢƱëÅN±Á½Ï»ÆµÄq³êÄ¢éÌÅ éB
yêÊXz
@123ÞÍ®ðo½B124ãÌ ÆñÔÚÌ ÌFqƪ×Ì®ÌàxàÉ ½ÂĽB125MO¾¯àxàEÌãÉ˧¼B126iajMOÍÞð©éÆ}ÉñªðµÄVäÌêûð©ã°ÄA
@uibjº¾vicjÆÍñÅ©¹½B127iajãÌ ªA
@uibj³¤]ÖÎMOͪªå«¢©ç{ɼ½³ñÌ⤾ívicjÆ]½B128iajMO;ÓÉÈÂÄA
@uibjÌ¢Èvicjƺð£ÂÄEðÐËé^ðµ½B129iaja¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YªA
@uibj¼½²·ÉEÍÈ¢ævicjÆ]½B130iaj ñlªAibjuí[¢vicjÆÍâµ½B131iajMOÍA
@uibjµÜ½IvicjÆidj¢âÉܹ½ ûiejð«¢ÄAEðòѺèéÆA¢«ÈèêÂÅñ®èÔµðµÄA¨Ç¯½çðifjÌÓÆigjFÌûÖü¯Ä©¹½B
| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||
| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||
| 123 | @ | @ | 123 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 124 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 124 | @ | @ | @ |
| 125 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 125 | @ | @ | @ |
| 126 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 126ibj | 126iaj icj |
@ | @ | @ |
| 127 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 127ibj | 127iaj icj |
@ | @ | @ |
| 128 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 128ibj | 128icj | @ | 128iaj | @ |
| 129 | @ | 129ibj | 129iaj icj |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @@ | @ | @ |
| 130 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 130ibj | 130iaj icj |
@ | @ | @ |
| 131 | @ | @ | @ | @ | 131idji¢âÉܹ½ûj | @ | @ | 131ibjuµÜ½Iv | 131iajMOÍA icjÆ idj¢âÉܹ½û iejð«¢ÄAEðòѺèéÆA¢«ÈèêÂÅñ®èÔµðµÄA¨Ç¯½çð ifjFÌûÖü¯Ä©¹½B |
@ | 131iejÌÓÆ | @ |
@êÊWÅucêvÆaððʽµ½uM¾YvÍæ¤âuMOv½¿Ì¢é×Ì®ÖÆü©¤ìiÌÅãÌÓÅ éB
@®ðo½uM¾YvÍAÓ´¯ ÁÄ¢éí
½¿Æçð í¹éBuMOvªuM¾Yvð©ÄÓ´¯Ä126¶ibjuº¾vÆ¢¦ÎAuãÌ
vÍ127¶ibju¼½³ñÌ⤾ívƨ¾ÄéBuMOv;ӰÉÈÁÄA128¶ibjuÌ¢Èvƾ¤B»êÉuM¾YvàQÁµÄA129¶ibju¼½²·ÉEÍÈ¢ævƾ¤B
@»êÜÅ×Ì®Ålqðf¤¾¯Å Á½uM¾YvÍAucêvÆÌí¾©ÜèððÁµ½±ÆÅAí
½¿ÌVÑÉQÁ·éæ¤ÉÈéB
@128¶iajuMO;ÓÉÈÂÄAvÍAqƵÄÍuS`Êvɪ޳êéàÌÌA±ê¾¯ðàÁļ¿ÉuMOvÌàÊÉ_ªu©êÄ¢éÆÜÅ;¦¸AuM¾YvÉu©ê½_©çÌqÅ ë¤B
@129¶iajua¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YªAvÉ¢ÄAæPÅàøpµ½ªA{ì¿i1989jÍAÌæ¤Éq×Ä¢½B
iªjM¾YÍAË@ƵĩéåÌ©ç©çêéÎÛÖÆÊuðϦéB±±ÅÍAM¾YÍí BƯñÉz³êAÞÌeñ¾âèæèÉÁíÁÄ¢él¨ÖÆޢĢéB±ÌªÍÞµëuM¾YÍvÆ é׫ƱëªAuM¾YªvÆ ç½ßÄ\¦µ¼µÄAÞðí BƯɩéìÒ̶Ýð¾ç©ÉµÄ¢éÌÅ éB
i{ì¿i1989juuê¼Æ̶Ívw\»wÌn@e_Ñæêêª@ßã¬àÌ\»Oxj
@¾ªA`ªÌæ1¶uM¾YÍvÆ¢¤qÆA±ÌuM¾YªvÆ¢¤qÆÌÝðĪ©èƵÄA_ªu©êél¨ªÏ»µÄ¢éÆÆç¦éÌÍA}ÅÍÈ¢¾ë¤©B
@êÊXÉÁÄàAËRƵÄuM¾YvÌàÊÉ_ªu©êÄ¢éÆ¢¤±ÆÍA131¶icju¢âÉ
@±êÜÅAæRAæSÅÍAq̪ުÍÉ¢ÄÌl@ð[ßÄ«½Bq̪ÞÚÍAyOi1986jÈÇðàÆɵ½àÌÅ èA´¥ÆµÄA éqÍÇê©ÌêÂÌÚªÞ³êéàÌÅ éBµ©µAw½é©xðªÍµ½êAêÂÌÚɪ޵ĵܤÆA¼ÌÚɪ޳ê¤éÂ\«ð©¦µÄµÜ¤æ¤ÈAñÂÈãÌÚɪ޳ê¤éqª éB±êçÍAñÂÈãÌÚɪ޳ê¤éæ¤È¡«ðàÁ½qÅ éB»êçÌñÂÈãÌÚɪ޳ê¤éqÉ¢ÄAïÌIÉáð°ÄA»Ì¡«É¢Äl¦éB
@ºÌøpÍAêxNµÉ½Éà©©íç¸SN«æ¤ÆµÈ¢uM¾YvÉεAÄÑucêvªNµÉéÆ¢¤ÓÅ éB
@u21¼®N«Ü·v22iajÞÍibjCÀßÉAicjXèȪçé ©çñÌrÜÅoµÄAidjÌÑðµÄ©¹½B
@u23¨Ê^Éà¨Ö·é̾©ç¼®N«Ä¨àêv
@24¨Ê^Æ]ÓÌÍ´®Ì°ÌÔÉ|¯Ä éCMæÌÑÅAM¾YªwÌ KÁ½æw̳tÉcÌSȽA`¢Äá½àÌÅ éB
@25iajÙÂÄ¢éÞðibju³ A¼®vicjÆcêÍ£µ½B
@u26åävA¼®N«Ü·B27\\ÞûÖsÂÄľ³¢B28¼®N«é©çv29iaj³¤]ÂÄÞÍibj¡ÉàN«³¤ÈlqðµÄ©¹½B
@±±ÅÍAuM¾YvÌܾQÄ¢½¢½ßÉA½Æ©ucêvð[¾³¹ÄN±·Ìðâß³¹æ¤Æ·és®ª¦³êÄ¢éB±ÌÓðæRŧĽÚÉ]ÁĪ޷éÆ·êÎAÌæ¤ÉÈë¤B
@21¶ÍAN±µÉ½ucêvÉεÄÌuM¾YvÌukb`ÊvÅ éB22¶Íê¶SÌÍuÞiM¾YjvÌuÌÑðµÄ©¹½vÆ¢¤us®`ÊvÅ éB»Ìus®`ÊvÉAucêvð[¾³¹é½ßÌibjuCxßÉAvÆ¢¤uS`ÊvuvlvªÜÜêÄ¢éB23¶ÍAN«éæ¤É£·ucêvÌukb`ÊvB24¶ÍuÊ^vÉ¢ÄÌuqÒvÉæéuqÒ\»vuà¾vA25¶ÌiajÍuM¾YvÌuóÔ`ÊvAibjÍucêvÌukb`ÊvAicjÍucêvÌus®`ÊvÅ éB26A27A28¶Í·×ÄuM¾YvÌukb`ÊvÅ éB29¶ÍASÌÅuM¾YvÌus®`ÊvÆÈéB
@»êð}\É·éÆÌæ¤ÉÈéB
| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||
| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||
| 21 | @ | 21 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 22 | @ | @ | 22iajÞÍ icjXèȪçé ©çñÌrÜÅoµÄA idjÌÑðµÄ©¹½B |
@ | @ | @ | 22ibjiCÀßÉAj | @ | @ | @ | @ | @ |
| 23 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 23 | @ | @ | @ | @ |
| 24 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 24 |
| 25 | @ | @ | @ | 25iaj | @ | @ | @ | 25ibj | 25icj | @ | @ | @ |
| 26 | @ | 26 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 27 | @ | 27 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 28 | @ | 28 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 29 | @ | 29iaj³¤]ÂÄÞÍ ibj¡ÉàN«³¤ÈlqðµÄ©¹½B |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@µ©µA±Ì}\ÅÍq̪ުÍÌàÌƵÄÍs\ªÅ éBȺÈçA±êÅÍuM¾YvÌàʪ23¶ÌibjuCxßÉAvÆ¢¤qÉæÁÄÌݦ³êÄ¢éÆ¢¤±ÆÉÈé©çÅ éBµ©µAÀÛÉÍuM¾YvÌàʪ23¶idjuÌÑðµÄ©¹½vA29¶ibju¡ÉàN«³¤ÈlqðµÄ©¹½vÆ¢¤qÉæÁÄ঳êÄ¢éB±ÌñÂÌqÍuS`ÊvÅÍÈ¢Bucêvð[¾³¹é½ßÉA·®ÉÅàN«»¤Èu©¹évÆ¢¤OIÅ®ÔIÈus®`ÊvÅ éBµ©µA±Ìu©¹½vÆ¢¤qÉÍA»êêêÅuM¾YvÌuS`Êvð঵ĢéqÆÈÁÄ¢éB»êÍÇÝ誢íäésÔð⤱ÆÅÇÝæêéuM¾YvÌàÊÅÍÈ¢B
@±¤µ½qðªÍ}\ɽf·é½ßÉÌæ¤ÈªÍ}\ɵÄA¡«Ì éqð©Ñãªç¹éæ¤È}\É·éKvª ë¤B
| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||
| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||
| 21 | @ | 21 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 22 | @ | @ | 22iajÞÍ icjXèȪçé ©çñÌrÜÅoµÄA idjÌÑðµÄ©¹½B |
@ | @ | @ | 22ibjiCÀßÉAj idjiÌÑðµÄ©¹½Bj |
@ | @ | @ | @ | @ |
| 23 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 23 | @ | @ | @ | @ |
| 24 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 24 |
| 25 | @ | @ | @ | 25iaj | @ | @ | @ | 25ibj | 25icj | @ | @ | @ |
| 26 | @ | 26 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 27 | @ | 27 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 28 | @ | 28 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 29 | @ | 29iaj³¤]ÂÄÞÍ ibj¡ÉàN«³¤ÈlqðµÄ©¹½B |
@ | @ | @ | @ | 29ibji¡ÉàN«³¤ÈlqðµÄ©¹½Bj | @ | @ | @ | @ | @ |
@±Ìæ¤ÉA꾯ɵ©ªÞÅ«È¢æ¤È}\ÅÍÈAñÂÈãɪ޳êéæ¤É¬®«Ì éàÌÉ·éB±¤·é±ÆÉæÁÄAqƵÄñÂÈãÌÚɪ޳êéæ¤È¡«Ì éqÉ¢Ä̪ͪÂ\ÆÈéB¡«Ì éqÉ¢ÄÍA¼Ú\É«Á¦é±ÆÉæÁÄA
ڵⷢæ¤Éz¶µ½B±êçÌqÉ
Ú·é±ÆÉæÁÄAuM¾YvÌàÊÌAæè¡GŧÌIÈßöð½Çé±ÆªÅ«æ¤B»êÉæÁÄAêÊXÌ129iajua¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YªAvÆ¢¤qÉ¢ÄÌl@ð[ßéĪ©èÉàÈë¤B
@ÅÍA±¢Äw½é©xɨ¯éA±¤µ½¡«Ì éqi}\ÌÔ|¯ªjÉ¢Äl@ð··ßéB»ÌãA»Ìl@ÌÊðĪ©èƵÄAw½é©xɨ¢ÄAdvÅ éÆl¦çêéÁ¥IÈ\»É¢ÄÌl@ðí¹ÄsȤ±ÆÆ·éB
yêÊTz
@1iajcÌOñõÌ@Ì éOÌÓAibjM¾YÍQ°Å¬àðÇñÅéÆAicjÀñÅQÄécêªA
@uidj¾úV³ñ̨¢ÅȳéÌͪ¼Å·¼viejÆ]½B
@2bµ½B3iaj·éÆibj°ÂÄîéÆv½icjcꪯ¶ð]½B4ÞÍ¡xÍÔðµÈ©Â½B
@u5»êɷ©èxxðµÄu̾©çA¡ÓÍà¤Ë½ç¢¢Å¹¤v
@u6í©ÂÄÜ·v
@7iajÔàÈibjcêÍ°ÂĹ½B
@8iajÇ꾯©ibjo½B9M¾Yà°È½B10vð©½B11êªß¬Ä½B12ÞÍvðÁµÄAQÔèðµÄA»µÄé ÌÝÉçðß½B
iºüøpÒBȺ¯¶j
| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||
| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||
| 1 | 1iaj | @ | @ | 1ibj | @ | @ | @ | 1idj | 1icj iej |
@ | @ | @ |
| 2 | 2 | @@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 3 | @ | @ | @ | @ | @ | @@ | 3ibj | @ | 3iaj icj |
@ | @ | @ |
| 4 | @ | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | @ |
| 6 | @ | 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 7 | 7iajÔàÈ | @ | @ | @ | 7iajiÔàÈj | @ | @ | @ | 7ibjcêÍ°ÂĹ½B | @ | @ | @ |
| 8 | 8iajÇ꾯© ibjo½B |
@@ | @ | @ | 8iajiÇ꾯©j | @ | @ | @ | @@ | @@ | @@ | @@ |
| 9 | @ | @ | @ | @ | 9 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 10 | @ | @ | 10 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 11 | 11iêªß¬Ä½j | @@ | @ | @@ | 11êªß¬Ä½B | @ | @ | @ | @ | @ | @@ | @ |
| 12 | @ | @ | 12 | @ | @ | @@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@æÉàøpµ½AìiÌ`ªÅ éBOñõÌOÌÓÌAuM¾YvÆucêvÆÌâèÆèð`¢½ÓÅ éB
@3¶â9¶Ìq©çAuM¾YvÌàÊÉ_ªu©êÄ¢é±ÆÍùÉmFµ½B±±ÅâèÉ·éÌÍAºüðø¢½7¶iajuÔàÈvA8iajuÇ꾯©vÅ éB±êçÌqÍÔÌoßð¦µÄ¢é½ßAuêÊÝèvÌÚɪ޳êéqÉ ½éBµ©µA_l¨ÆµÄÝè³êÄ¢éuM¾YvÌàÊÆ[¢©©íèÌ éqÅ é½ßAPÉuêÊÝèvÌqƵĪ޹¸ÉA¡«Ì éqƵÄAªÞµÈ¯êÎuM¾YvÌàÊð¸mÉÆç¦é±ÆÍÅ«È¢B±±ÅÍAuM¾YvÌÔoßÌu´ovª½f³ê½qÅ éB
@7¶iajuÔàÈvucêvÍ°ÁĵܤªA»êÉεÄuM¾YvÍ8iajuÇ꾯©vÆAÔÌoßðYêéÙǬàðÇñÅ¢éÆ¢¤±Æª¦³êÄ¢éBucêvÆuM¾YvƪÎä³êÄ¢éÌÅ éB5¶Ìu»êɷ©èxxðµÄu̾©çA¡ÓÍà¤Ë½ç¢¢Å¹¤vÆ¢¤ucêvÌukb`ÊvÍAucêvÉÆÁÄuM¾YvðSz·é ÜèA°ë¤ÆµÄ¢éƱëð¸¦Äºð©¯A°éæ¤É£µÄ¢éB¾©çAuÔàÈv°ÁĵܤÌÅ éB
@»êÉεÄAuM¾YvÍA¾ú½ÉN«È¯êÎÈçÈ¢©AÆ¢¤±ÆÅÍÈA¬àðÇÝÓ¯èAæ¤â°ÈÁ½Æ«É10¶uvð©vÄAÔðmF·éB8¶uÇ꾯©vÆ¢¤ÌÍAuM¾YvªÔðYêéÙÇA¬àÉÇÝÓ¯ÁÄ¢éÆ¢¤pðA©Ñãªç¹éBuM¾YvÉÆÁÄuÇ꾯©vÆ¢¤Ó¯ÈÌÅ èAPÉuêÊÝèvÌqƵĪ޷龯ÅÍA»ÌàÊÉ éÓ¯ðÆ禫êÈ¢B
@OñõÌOÌÓɨ¯éucêvÆuM¾YvÆÌÓ¯Ìá¢ðuM¾YvÌuÔàÈvÆuÇ꾯©vÆÌÎäÉæÁÄq³êÄ¢éÌÅ éB
yêÊUz
@20Acê̺Åáªoß½B
@u21¼®N«Ü·v22iajÞÍibjCÀßÉAicjXèȪçé ©çñÌrÜÅoµÄAidjÌÑðµÄ©¹½B
@u23¨Ê^Éà¨Ö·é̾©ç¼®N«Ä¨àêv
@24¨Ê^Æ]ÓÌÍ´®Ì°ÌÔÉ|¯Ä éCMæÌÑÅAM¾YªwÌ KÁ½æw̳tÉcÌSȽA`¢Äá½àÌÅ éB
@25ÙÂÄ¢éÞðu³ A¼®vÆcêÍ£µ½B
@u26åävA¼®N«Ü·B27\\ÞûÖsÂÄľ³¢B28¼®N«é©çv29iaj³¤]ÂÄÞÍibj¡ÉàN«³¤ÈlqðµÄ©¹½B
@30cêÍÄÑoÄs½B31ÞÍ°èɾñÅs½B
| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||
| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||
| 20 | @ | @ | @ | @ | 20 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 21 | @ | 21 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 22 | @ | @ | 22iajÞÍ icjXèȪçé ©çñÌrÜÅoµÄA idjÌÑðµÄ©¹½B |
@ | @ | @ | 22ibjiCÀßÉAj idjiÌÑðµÄ©¹½Bj |
@ | @ | @ | @ | @ |
| 23 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 23 | @ | @ | @ | @ |
| 24 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 24 |
| 25 | @ | @ | @ | 25iaj | @ | @ | @ | 25ibj | 25icj | @ | @ | @ |
| 26 | @ | 26 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 27 | @ | 27 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 28 | @ | 28 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 29 | @ | @ | 29iaj³¤]ÂÄÞÍ ibj¡ÉàN«³¤ÈlqðµÄ©¹½B |
@ | @ | @ | 29ibji¡ÉàN«³¤ÈlqðµÄ©¹½Bj | @ | @ | @ | @ | @ |
| 30 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 30 | @ | @ | @ |
| 31 | @ | @ | 31 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@øpµ½ÌÍAêxN±³ê½uM¾YvªAÄÑucêvÉN±³êéÓÅ éB
@22¶idjuÌÑðµÄ©¹½vA29ibju¡ÉàN«³¤ÈlqðµÄ©¹½vÆ¢¤qª¡«ðàÂqÅ éBÇ¿çàAucêvð[¾³¹é½ßÉAuM¾YvªN«»¤ÈZð·éBêxÚÉucêvªN±µÉ«½Æ«ÍAuM¾YvͶÔð·é¾¯¾Á½ªAñxÚÉN±µÉéÆAÔ¾¯ÅÍÈs®ÉæÁÄucêvð[¾³¹æ¤ÆN«éfUèð©¹éÌÅ éB
@22¶idjuÌÑðµÄ©¹½vA29ibju¡ÉàN«³¤ÈlqðµÄ©¹½vÍAuM¾YvÌus®`Êvɪ޳êéªAu©¹évÆ¢¤qÉÍuM¾YvÌàʪ½f³êÄ¢éB¦¿AuM¾Yvªucêvð[¾³¹ÄAÈñÆ©±ÌêÍǢԵवQæ¤AÆ¢¤Ó}Å éB±Ìqðus®`ÊvƷ龯ÅÍA»ÌàÊðÆç¦é±ÆªÅ«È¢B
@èð[¾³¹æ¤Æ¢¤uS`ÊvuvlvªÜÜê½us®`Êv¾ªA±êð±ÌÜÜus®`ÊvÆuS`ÊvÆɪ¯Äqµ½Æ·éÆAuM¾YvªÜ¾°AoÁµØêĢȢlq𦷱ƪūÈÈéBtɾ¦ÎAuS`ÊviuvlvjµÄµÜ¤ÆAuM¾YvÍ
@±Ì26¶Æ29¶ÆÍAuM¾YvÌs®ÆAuM¾Yv̶IÈóÔÆvfÆðÆç¦é½ßÉÍdvÈqÅ éB
yêÊWz
@72cêÍÌÉ~rÌçð½½ñÅ©çAå«¢~zcð½½Ü¤ÆµÄ§ð͸ܹÄéB73cêÍM¾YªN«Äè`Ó¾ë¤ÆvÂÄéB74iajªM¾YÍibj´èðH͸ÉÌÓÉicjâ©ÈçðµÄ¡ÉȽÜÜ©Ä¢½B75iaj½¤Æ¤ibjcêÍ{èoµ½B
| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||
| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||
| 72 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 72 | @ | @ | @ |
| 73 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 73 | @ |
| 74 | @ | @ | 74iaj icj |
@ | @ | @ | 74ibj | @ | @ | @ | @ | @ |
| 75 | @ | @ | @ | @ | 75iaji½¤Æ¤j | @ | @ | @ | @ | @ | 75iaj½¤Æ¤ ibjcêÍ{èoµ½B |
@ |
®SÉoÁµ½ãAÄÑucêvª®ÉàÇÁÄéªAuM¾YvÍN«È¢BãÌøpÍA»±ÅAucêvªzcð½½ÝͶßA»êðuM¾Yvª©ÂßéÆ¢¤ÓÅ éB
@uM¾YvªucêvÌs®ÌÓ}ðÇÝæèAuâ©ÈçvÅ©ÂßÄ¢éÆA75¶iajuƤ½¤vucêvð{ç¹ÄµÜ¤B±±ÅàAu½¤Æ¤vÆ¢¤ªuM¾YvÌàÊðÜñ¾¡«Ì éqÉÈÁÄ¢éB75¶SÌÍAæÉàq×½æ¤ÉAuM¾YvÌ_©çAucêvÌOIÈÁ¥ðÆ禽¤¦ÅÌuS`Êvɪ޳ê¤éBµ©µA75¶iajÌu½¤Æ¤vÌqÍAuM¾YvÌàÊðÜݱñ¾qÆl¦çêéB
@uM¾YvÍAucêvª¢Â©{èo·©àµêÈ¢AÆ éöx\zð§ÄȪçAucêvð74¶u©Ä¢½vÌÅ éBuM¾Yv©gAucêvð{ç¹Ä¢és®ðµÄ¢é±ÆðA©oµÄ¢éA»ÌãÅu©Ä¢½vÆ¢¤±ÆÅ éBuƤ½¤vÉÍAuM¾YvÌAष®{èo·©àµêÈ¢AÅ੪Íè`¤CÍȢƢ¤ucêvÉηéå«È½ªN±ÁÄ¢éÆ¢¤±ÆÅ éBæÁÄA±Ìu½¤Æ¤vªuM¾YvÌàÊð½fµ½qÅ é©çAËRƵÄuM¾YvÌàÊÉ_ªu©êÄ¢éÆ»fÅ«éÌÅ éB
@uM¾YvÌ\zÆࢦé±Ìu½¤Æ¤vÍAâÍèucêvÌuS`ÊvƷ龯ÅÍs\ªÈ¡«Ì éqÈÌÅ éB
@92iajüêÌOÅÑð÷ßȪçibj±ñÈðlÖÄéÆAicjcêªüÂĽB93cêÍÈé×ûð©È¢â¤ÉµÄGÉµÄ ééïÌÜÍèðñÁÄüêðJ¯É½B94Þ͵ǢÄâ½B95»µÄéïÌRÉðºëµÄ«Üðú¢Ä½B
| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||
| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||
| 92 | @ | @ | 92iaj | @ | @ | @ | 92ibj | @ | 92icj | @ | @ | @ |
| 93 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 93 | @ | @ | @ |
| 94 | @ | @ | 94Þ͵ǢÄâ½B | @ | @ | 94iÞ͵ǢÄâ½Bj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 95 | @ | @ | 95 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@ucêvƵ¾¢Á½ ÆAuM¾YvªN«ãªÁÄ
ª¦Ä¢éÆAÄÑucêvªuM¾YvÌQ°Ì é®ÉâÁÄéB
@±±ÅàA94¶ª¡«Ì éqÆÈÁÄ¢éBµ¾¢ÁÄucêvðÇ¢oµ½uM¾Yv¾Á½ªA»êÅàí¾©ÜèÍðÁ³ê¸ÉAucêvð¢ç¹éû@ðvÄ·éB»±Öucêvª®ÉüÁÄéBRuM¾YvÍAucêvÉËRƵĽµÄ¢éB»Ì½ßAüÁÄ«½ucêvÉεÄAuµv¾¯Þ±ÆÉÈéB94¶ÍAuM¾YvÌus®`ÊvÅ éBµ©µAuM¾YvÌËRƵÄucêvÉεÄ{èð´¶Ä¢éàÊðàÜݱñ¾us®`ÊvÆÈÁÄ¢éÌÅ éBuµÇ¢Äâ½vÆ¢¤ÌÍAuM¾YvÌ®¢½¨IÈ£¾¯ÅÍÈAuM¾YvÌucêvÖÌuSîvªÜÜêÄ¢éB
@»êÍAus®`Êv©çÇÝÆçêéÇÝèÌðßÆ¢Á½âèÅÍÈAqƵÄuS`ÊvªÜÜêÄ¢éÌÅ éBus®`ÊvƵľ¯ÈçAuµÇ¢½vâAuÇ¢½vƵÄà·µx¦È©Á½Í¸Å éÉà©©íç¸A±±ÅÍuµÇ¢Äâ½vÆÈÁÄ¢éBuM¾YvªucêvÉεÄÌuSîvªÜÜêÄ¢é©ç±»A®¢½£ªuµvÅ èAuÇ¢Äâ½vÆÈéÌÅ éB
@÷ÈSÅÍ éàÌÌAuM¾YvÌàÊðÆç¦é½ßÉͩƵÄÍÈçÈ¢dvÈ¡«Ì éuS`ÊvðÜñ¾us®`ÊvÅ éB
@
u98±êÅ@½¾ç¤v99iajcêÍ¡ÌðYê½æ¤ÈçðibjÌÓƵÄicj]½B
@u100½É·éñÅ·v101M¾YÌûÍÌÓÆ¢¾µÞÂƵÄîéB
@u102V³ñɨkð¢Ä¸Ì³v
@u103ÊÚ³B104»ñÈ×¢ñůéàñÅ·©B105¨³ñÌûɧhÈ̪ èÜ·æv
@u106¨c³ñÌàôÂÄ Â½Â¯ªA½ÖÂĹ½©ccv107³¤]ÐȪçcêÍ´×¢MðÁÄ®ðoÄs©¤Æµ½B
@u108iaj»ñÈÌðÂÄs½ÂÄÊÚÅ·ævibjÆÞÍ]½B
@u109³¤©v110iajcêÍibjf¼ÉicjàÇÂĽB111»µÄJÉ»êð³ÌÉdÂÄoÄs½B
| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||
| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||
| 98 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 98 | @ | @ | @ | @ |
| 99 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 99iaj icj |
@ | 99ibj | @ |
| 100 | @ | 100 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 101 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 101 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 102 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 102 | @ | @ | @ | @ |
| 103 | @ | 103 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 104 | @ | 104 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 105 | @ | 105 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 106 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 106 | @ | @ | @ | @ |
| 107 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 107 | @ | @ | @ |
| 108 | @ | 108iaj | 108ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 109 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 109 | @ | @ | @ | @ |
| 110 | @ | @ | @ | @ | 110ibjif¼Éj | @ | @ | @ | 110iajcêÍ ibjf¼É icjàÇÂĽB |
@ | @ | @ |
| 111 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 111 | @ | @ | @ |
@95¶É±AuM¾YvÆucêvƪïbððí·êÊÅ éB
@±±Å
Úµ½¢ÌÍA110¶ÌucêÍf¼ÉàÇÂĽvÆ¢¤qÅ éB±Ìºüibjuf¼ÉvÆ¢¤qà¡«Ì éàÌÉÈÁÄ¢éBæÉøpµ½92¶Åucêvª®ÉüÁÄéÜÅAucêvÆuM¾Yv͵¢¾¢¢ðJèԵĢ½BÉà©©íç¸A108¶ÌuM¾YvÌñ¾ÉεÄAucêvÍ109¶u³¤©vƽ·é±ÆÈ®ÉßÁÄéB
@±±ÅÍA»êÜž¢¢Î§µÄ¢½uM¾YvÉÆÁÄAucêvÌs®ÍÁ׫ÙÇuf¼ÉvuM¾YÌv¾¤±Æð·¢½ÌÅ éBâÍè±ÌqàAPÈéus®`ÊvÌlqðqµ½àÌÅÍÈAuS`ÊvÌu´ovªqƵÄÜÜêAuM¾YvÌàÊð½fµ½qÅ éƾ¦éB
yêÊXz
@123ÞÍ®ðo½B124ãÌ ÆñÔÚÌ ÌFqƪ×Ì®ÌàxàÉ ½ÂĽB125MO¾¯àxàEÌãÉ˧¼B126iajMOÍÞð©éÆ}ÉñªðµÄVäÌêûð©ã°ÄA
@uibjº¾vicjÆÍñÅ©¹½B127iajãÌ ªA
@uibj³¤]ÖÎMOͪªå«¢©ç{ɼ½³ñÌ⤾ívicjÆ]½B128iajMO;ÓÉÈÂÄA
@uibjÌ¢Èvicjƺð£ÂÄEðÐËé^ðµ½B129iaja¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YªA
@uibj¼½²·ÉEÍÈ¢ævicjÆ]½B130iaj ñlªAibjuí[¢vicjÆÍâµ½B131iajMOÍA
@uibjµÜ½IvicjÆidj¢âÉܹ½ ûiejð«¢ÄAEðòѺèéÆA¢«ÈèêÂÅñ®èÔµðµÄA¨Ç¯½çðifjÌÓÆigjFÌûÖü¯Ä©¹½B
| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||
| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||
| 123 | @ | @ | 123 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 124 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 124 | @ | @ | @ |
| 125 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 125 | @ | @ | @ |
| 126 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 126ibj | 126iaj icj |
@ | @ | @ |
| 127 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 127ibj | 127iaj icj |
@ | @ | @ |
| 128 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 128ibj | 128icj | @ | 128iaj | @ |
| 129 | @ | 129ibj | 129iaj icj |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @@ | @ | @ |
| 130 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 130ibj | 130iaj icj |
@ | @ | @ |
| 131 | @ | @ | @ | @ | 131idji¢âÉܹ½ûj | @ | @ | 131ibjuµÜ½Iv | 131iajMOÍA icjÆ idj¢âÉ iejð«¢ÄAEðòѺèéÆA¢«ÈèêÂÅñ®èÔµðµÄA¨Ç¯½çð ifjFÌûÖü¯Ä©¹½B |
@ | 131iejÌÓÆ | @ |
@ucêvÆaððʽµ½uM¾YvÍAæ¤â×Ì®Éü©¤B
@131¶idjÌu¢âÉ
@Å éÈçÎAâÍèêÊWÜÅ_l¨ÆµÄ_ªu©êÄ¢½uM¾YvÉÆÁÄAu¢âÉܹ½vû²¾Á½Æl¦é̪ÃÅÍÈ¢¾ë¤©BuMOvÌû²ªu¢âÉܹ½væ¤É·¦½ÌÍAuM¾Yv̱êÜÅ̾®ðÈÝÄÆç¦çê½uMOvÌû²ÌóÛÈÌÅ ë¤BuMOvÌû²ðu¢âÉ
@±Ìæ¤Él¦éÆA{i1989jÅwE³êÄ¢½129¶iajua¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YªAvÆ¢¤qÍAâÍèuM¾YÍí
BƯñÉz³êAÞÌeñ¾âèæèÉÁíÁÄ¢él¨ÖÆޢĢévÆ¢¤_ÌÏ»ÍFßçꪽ¢B129¶¾¯ÅÍÈAêÊXÍËRƵÄAuM¾YvÉ_ªu©êÄ¢éÌÅ éBÅÍAuM¾Yvªu¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽvÆ©gðÆç¦Ä¢éÌÍAȺ¾ë¤©B
@±ÌqÍAuM¾YvÌÓ¯ÌÏ»ÈÌÅ éB»ÌÓ¯ÌÏ»ÆÍA»êÜÅucêvð©ÂßAucêvÆΧµ±¯Ä¢½uM¾Yvª©ªÍÇÌæ¤È\îðµÄ¢éÌ©AÓ¯·éæ¤ÉÈÁ½Æ¢¤±ÆÅ éBucêvɽ·é±ÆÉÓ¯ªü¢Ä¢½uM¾YvÉÆÁÄAÇñÈ\îðµÄ¢é©Æ¢¤Ó¯ðl¾·éÉÍAuMOvðͶßÆ·éí
½¿Æïbððí·Kvª Á½ÌÅ éB»êÍAÆ°ÌÒÅ ÁÄà¼ÒðÓ¯·éÆ¢¤Ó¡É¨¢ÄdvÈϻŠë¤B
@129¶iajua¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YªAvÆ¢¤qàA131¶u¢âÉ
@129¶iajua¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YªAvÆ¢¤qðAuM¾YvÌÓ¯ÌϻŠèAuM¾Yvª©gðÆ禽©ç±»Au¢âÉܹ½ûvÆ¢¤uM¾YvÌuS`Êvu´ovðÜñ¾qÉÈÁÄ¢éÌÅ éB
@±Ìæ¤ÉA¡«Ì éqÉ¢Äl@µÄ¢ÆAw½é©xɨ¯éåèðl¦éãÅĪ©èð¾é±ÆªÅ«éB±êçÌ¡«Ì éqɨ¨ÞˤʵĢé±ÆÍAuµvu½¤Æ¤vu¢âÉvÈÇAuqÒvÌåÏIÈ]¿«ðàÁ½Pꪽ¢Æ¢¤±ÆÅ éBuåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêvÆÍA`eA`e®AAAÌÈÇÌiðͶßƵ½AqÒÌåÏÉæé]¿ªtÁ³ê½Pê̱ÆÅ éBw½é©xɨ¢ÄAìiÌSƵÄl¦çêéuM¾YvÌSÌßöðÆç¦æ¤Æµ½êA±¤µ½åÏIÈ]¿«ðàÁ½PêªAdvÈððʽµÄ¢éÌÅÍÈ¢¾ë¤©B
@»±ÅA¡IÈqƵĪ޳êÈ©Á½ªAÁ¥IȱêçÌåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêÉ¢ı¢Äl@µÄ¢±¤B
@u40í«ÖÄ»¤®Ã^_]Ó©çA®N«çêÈÈéñ¾v
@u41 Ü̶âIv42iajcêÍibj{ÂÄicjoÄs½B43M¾YàरÍÈȽB44N«Äࢢ̾ªA]èN«ë^_Æ]Íê½ÌÅÀÛN«ÉÈÂĽB45iajÞÍ{Æ°ÌÔÌÑð©ÈªçAibj»êÅàà¤NµÉé©^_Æ¢¤sÀð´¶Ä½B46N«Äâ뤩ÈÆvÓB47Rµà¤µÆvÓB48व±¤µÄÄNµÉȩ½çA»êÉƶÄN«Äâç¤A³¤vÂÄ¢éB49ÞÍå«ÈáðJ¢Ä¢¾¡ÉÈÂĽB
@êÊUÌÅãAÈ©È©N«È¢uM¾YvÍAuí«ÖÄ»¤®Ã^_]Ó©çA®N«çêÈÈéñ¾vƾ¢ú¿AucêvðÇ¢oµÄµÜ¤B
@±±Å
Úµ½¢ÌÍA44¶uÀÛvÆ49¶uå«ÈávÆ¢¤qÅ éB44¶ÌuÀÛvÍA40¶uí«ÖÄ»¤®Ã^_]Ó©çA®N«çêÈÈéñ¾vÆ¢¤uM¾YvÌukb`ÊvÉεÄÌucêvÌ41¶u Ü̶âIvÆ¢¤ukb`ÊvÉ¢Äó¯½àÌÅ ë¤Buí«ÖÄ»¤®Ã^_]Ó©çA®N«çêÈÈév±ÆÍAu Ü̶âvÅ éÌÍÜ_¾ªAuM¾YvƵÄÍuÀÛvN«çêÈÈÁÄ¢½AÆ¢¤±ÆÅ éBuÀÛvÆ é±ÆÅAuM¾Yv©gAu Ü̶âvÅ é±ÆÍðµÄ¢éàÌÌA»êÅàN«ÉÈÁÄ¢éÆ¢¤üܵ½àÊð`ʵĢéB¡«Ì éqÅÍÈAuS`Êvɪ޳êéqÅ éªAuM¾YvÌàÊðl¦é¤¦ÅdvÈqÅ éB
@49¶uå«ÈávðJ¢Ä¢éuM¾YvÍAçÌOIÈÁ¥ð\íµÄ¢éÌÅÍÈAùÉ®SÉoÁµÄµÜÁÄ¢é±Æð\íµÄ¢éBOxN±³êAucêvÉ ð§ÄÄ¢éuM¾YvÍAïÌIÉ45`48¶É éæ¤ÉvĵĢéBuM¾YvÌàÊɨ¢ÄdvÈqÅÍÈ¢ªAuM¾YvªoÁµÄ¢é±Æð@ÀɦµÄ¢éqÆ¢¤_ɨ¢ÄdvÅ ë¤B
@97cêÍüêÌÌpMy©ç¬³¢Mðñ{oµ½B96ÜZNOM¾YªÉÛ©çÂĽ©RØÌâ´ ÈMÅ éB
@u98±êÅ@½¾ç¤v99iajcêÍ¡ÌðYê½æ¤ÈçðibjÌÓƵÄicj]½B
@u100½É·éñÅ·v101M¾YÌûÍÌÓÆ¢¾µÞÂƵÄîéB
@êÊWÅA{ÁÄoÄsÁ½ucêvªÄÑ®ÉüÁÄAuM¾YvÌMðæèÉéÓÅ éB
@±±ÅAucêvÍA97¶u¬³¢vA96¶uÜZNOM¾YªÉÛ©çÂĽ©RØÌâ´ÈMvð¿o»¤Æ·éB96¶A97¶ÌºüÍAuM¾YvªÁĽƢ¤uMvÉ¢ÄÌ`eÅ éB±êÍuM¾YvÌàÊÅÍÈAucêvÌàÊð\íµÄ¢é±ÆÅÚ³êéBãÌ99¶Éà éæ¤ÉuÌÓÆvuM¾YvÌg¦È¢MðæèÉéB·Å éuM¾YvÆað·é½ßɱÌæ¤Ès®Éoé̾ªA96¶97¶Åu¬³¢vuâ´ÈMvÆ`eÆ`e®Å]¿ðº·±ÆÉæÁÄA»ÌÓ}ª¦³êé±ÆÉÈéBuM¾YvÌàÊðÆç¦é½ßÌqÅÍÈ¢ªAaðÌ«Á©¯ÆÈéucêvÌÓ}ðÆç¦é½ßÉÍÚ³êéqÅ ë¤B
@±Ìæ¤ÉAw½é©xɨ¯é±êçÌåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêÍA¡«Ì éqðÜßÄl¦éÆAuM¾YvÌàÊðÆç¦é½ßÉdvÈððàÁÄ¢éƾ¦éB³_AìiÌåÏIÈ]¿«Ì éPê·×ĪuM¾YvÌàÊðFZ½fµ½àÌÆÍ¢¦È¢Bµ©µAÈÆàA±êçÌ]¿«ðàÁ½PêÉ
Ú·é±ÆÅAuM¾YvÌSÌßöªæè¾ÄÉÆç¦çêé±ÆÍmF³êæ¤B
@»µÄA±êÜÅÝÄ«½q@ÌÁ¥ÍAq@ÌÝÌâèÉÆÇÜéÌÅÍÈA_ÌzÉà©©íé±ÆÅ éB
@ÌæUÅAÈãÜÅÌl@ÉæÁľç©ÆÈÁ½Aw½é©xɨ¯é_ÌzÆq@É¢ÄAÜÆßé±ÆÉ·éB
@æQÍæPßÅÍAw½é©xɨ¯é_ÌzÆq@ðĪ©èƵÄAw½é©xÉ¢ĪÍEl@ð¨±ÈÁÄ«½B»ÌÊAw½é©xÍÌæ¤ÉÜÆßçêæ¤B
@uM¾YvÍA½xàN±µÉéucêvÉεÄA»êÜÅÌ°½¢Æ¢¤¶IÈ~ÅÍÈAucêvÉηés@ÉæÁÄN«çêÈÈéBucêvªN±µÉ±È¯êÎN«Äâë¤AÆl¦éuM¾YvÌ®ÉAucêvÍN±µÉéªAuM¾YvÍN«ãªë¤ÆµÈ¢BƤƤ{è¾µÄ{ÂéucêvÉεÄAuM¾YvྡྷԷBucêv𩹽uM¾Yvªæ¤âN«ãªè
ª¦Ä¢éƱëÉAucêvª½¶ð¢®ÉâÁÄ«ÄA¼ÒͱÌúͶßÄïbçµ¢ïbððí·Bucêvª®ð£êéÆAuM¾YvÍÜð¬µA·ª·ªµ¢CªÉÈéB®ðo½uM¾YvÍAí
½¿Éa碾ⵢÎçð©¹éB
@»µÄAw½é©xÌåèÍÌæ¤ÉÈë¤BucêvÉN±³êé±ÆÅs@ÉÈÁ½uM¾YvªA½CÈ¢âèÆèÉæÁÄucêvÉηé{èððÁ³¹éAÆ¢¤o±ÉæÁÄA»êÜÅ꺩ç¼ÒðÝÂß龯ŠÁ½uM¾YvÉA¼ÒÉü©¤©ÈÆ¢¤Ó¯ªè¶¦éB
@åèÉ©©íéw½é©xɨ¯éA_ÌzÆq@É¢ÄÍAÌæ¤ÉÜÆßçêæ¤B
@@ÈãÌæ¤ÉA±êÜÅl@µÄ«½ÊðàÆÉw½é©xɨ¯é_ÌzÌÁ¥É¢ĮµÄ¨B
@w½é©xÍAæSɨ¯éªÍEl@ÉæÁÄAìiíÉA_ÍuM¾YvÌàÊÉu©êé±Æª¾ç©ÆÈÁ½BuM¾YvêlÉ_ªu©êé±ÆÉæÁÄAucêvÉηé´îÌNÆ¢¤AuM¾YvÌàʪ©Ñ ªé±ÆÉÈéB
@@ÌOÌÓÅ éÉà©©íç¸Aucêv̾tàÓÉÉAuM¾YvÍ°ÈéÜŬàðÇÝÓ¯éB»±ÉͬàðÇݽ¢Æ¢¤v¢ÆA°ÈÁ½©ç°éÆ¢¤©ª©gÌ©ªèÆྦé~ÌÜÜÉU¤l¨ÆµÄÌuM¾Yvð`«o·B
@©A@ÌpÅZµ®«ñÁÄ¢éÅ ë¤ucêvÍAuM¾YvðN±µÉéB¾ªAuM¾YvÍÔð·é¾¯ÅN«È¢B°¢ÈªçàAucêvðÇ¢Ô»¤ÆN«édÜÅ·éBOxÚżÒ̽ªå«ÈèAuM¾YvÍáªoßĵܤÉà©©íç¸AucêvªN±µÉé±ÆÅN«ãªé±ÆªÅ«ÈÈéBoÁ©çAN«çêÈÈéÜÅÌßöªuS`ÊvÌL³ÆA»Ì¿ÌÏ»ÉæÁĦ³êéB
@»µÄuM¾YvÍA¡ÉÈÁ½ÜÜuMOvçí
Ìlqð®o©çf¤BêÊVÍAuM¾YvÉu©ê½_©çÌqÅ é½ßAukb`Êvâus®`ÊvÌå̪uêlªvÆ¢¤qŦ³êéBuM¾YvÍÐÆ让çOEð©·«·éÆ¢¤óÔªAí
½¿Ìlqðf¤êÊVð}ü·é±ÆÉæÁÄA¦ß³êéÌÅ éB±êÍAêÊXÉ×Ì®ÉsÆ¢¤Ï»ð©Ñãªç¹éB
@N«ãªçÈ¢uM¾Yv̳ÖÄÑucêvªé±ÆÅAuM¾YvÍÜ·Ü·N«ãªé±ÆªÅ«ÈÈéBzcâ¬é
ð½½Ýnß½ucêvÌÓ}ÜũʵÄAuM¾YvÍâââ©É©ÂßéBucêvÌuS`Êvª³êé±ÆÅAuM¾YvÆucêvÆÌâèÆ誦³êéB»ÌÔxÉ{èoµ½ucêvƾ¢¢ÉÈé±ÆÅAucêv𩹽uM¾YvÍAN±µÉ±È¢¾ë¤Æl¦æ¤âN«ãªéB»êÅà{誨³Üç¸ÉAXP[gÉsÁÄSz³¹æ¤©ÆuS`Êviuvlvj³êéB»±ÖÄÑâÁÄ«½ucêvÍA»êÜÅ̱ÆðY꽩Ìæ¤Ébµ©¯éB»êªuÌÓÆvÅ é±ÆðåÁ½uM¾YvÍA©çàuÌÓÆvÞÁƵ½ÔxŶéBµ©µA»ÌïbÉAuS`ÊvÌuvlvÌqŦ³êéæ¤ÈÅZÍÈ¢BucêvªÁÄ¢Á½ ÆAuM¾YvÍÜð¬µA¹Ì·ª·ªµ³ðo¦éÌÅ éB±êçÌqÍ·×ÄuM¾YvÉÆÁÄ©RÅÓ}µÈ¢Ï»ÆµÄ¦³êéB
@®ðoÄí
ÌàÆÉpð©¹éuM¾YvÍA©gÌ\îðua¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄv¢é±ÆÉÓ¯ðü¯AuMOvÌu¢âÉ
@±Ì¡«Ì éqðºx¦·é_ÌzÍAìl¨iuM¾YvjÌàÊÉ_ðu©A é¢ÍOÉuÌ©AÆ¢Á½ñΧIÈàÌÅÍÈA»Ì¼Òðê·é_ÌzÅ éB é¢ÍàÊð©ÊµÈªçAOÊð`AÆ¢¤_ÌzÈÌÅ éB
@w½é©xÍAuM¾YvÌàÊÉu©ê½_ÉæÁÄAàÊð`¾¯ÅÍÈA çäéÎÛÍuM¾YvÌàÊ©çÆç¦çêq³êé±ÆÉÈéBå«OÂɪ¯çê¤éuS`ÊvÉæÁÄA¡GÅ÷ÈuM¾YvÌàÊÌßöª§ÌIÉ`©êéB»ÌOÂÆÍAê´ÉæéFmðqµ½uS`ÊvÌu´ovAÛIÅñ¾êIÈàÊðqµ½uS`ÊvÌuSîvAæèïÌIžêIÈuS`ÊvÌuvlvÅ éB±êçÌA¿ðÙɵ½uS`ÊvÉæÁÄAuM¾YvÌoÁóÔâASóÔAïÌIÈvlàeÈǪA§ÌIɦ³êéÌÅ éB
@³çÉA½lÈuS`ÊvÉÁ¦ÄA¡«Ì éqÉæÁÄàuM¾YvÌàʪ`©êéB¡«Ì éqÆÍAuM¾YvucêvÉ©©íç¸Aus®`ÊvÌqÉuS`ÊvàÜÜêÄ¢éÆ¢¤qÅ éB»êÍAus®`Êv©çìl¨ÌàʪÇÝÆêéAÆ¢Á½àÌÅÍÈAqƵÄuS`ÊvªÜÜêÄ¢éÆ¢¤±ÆÅ éBܽA¡«Ì éq¾¯ÅÍÈAåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêàuM¾YvÌàÊð½fµ½qÅ Á½B±êÍ¡«Ì éqÅÍÈAqƵÄÍus®`ÊvÅ Á½èAuqÒ\»vÅ Á½è·éªAuM¾YvÌàÊÌßöð½Ç餦ųūȢqÆÈÁÄ¢½B
@±¤µ½A½í½lÈqÉæÁÄAuM¾YvÌàÊÌßöª`o³êéBucêvÉN±³ês@ÉÈèAuaðvðʽ·AÆ¢¤PȨêÅ éªA»ÌàÊð`«o·qÍ¡G³ðàÁÄ¢éBw½é©xð¸mÉImÉÆç¦é½ßÉÍA±¤µ½q@ÆA»êðºx¦µÄ¢é_Ìzðl¦é±ÆÍLøÅ ë¤B
@±¢ÄæQßÅÍAwÔÜÅxÉ¢ĪÍEl@·é±ÆÉ·éB
@ܸwÔÜÅx̪ÍEl@ð··ßéÉ ½ÁÄA±êÜÅÌwÔÜÅxÉ¢ÄÌæs¤ðÝĨ«½¢B»ÌÌ¿A»êçÌæs¤ð¥Ü¦ÄAæQÈ~ÅÀÛÉ_ÌzEq@Æ¢¤Ï_©ç̪ÍEl@ð¨±ÈÁÄ¢B
@¬chi1972,bjuuê¼Æ̶w`¬liñj\\OìÌØ\\viw¶wxæ40ª2@âgX1972N2jÅÍAuÔÜÅvÆ¢¤\èÆAuFs{vÌFlÉï¢ÉsÆ¢¤`ªÌÝèÉ¢ÄAÌæ¤ÉwE·éB
@ìiÍAFs{ÌFlðUÁÄúõ©¨És¬·s\\ÂÜèãìwÅæÔµAFs{wÅͺԵȯêÎÈçÊÔ̱ÆÉAæ¸Ýè·éB{uFs{ÜÅvÆè³êÄæ¢ìiÅ éB±ÌÝèÍAÀÉIÅ éBãìwEÔEFs{wÌÚ·éOÂÌêÊÅ»ê¼êålöÌêqÆÌo¢EðÂEÊêðÚ¹éÆ¢¤®³ê½\¬ðÁÄ¢éBêÂ̪A`ªÉ¨¢ÄuÊêvÅàÁÄ·éàÌÆAvZ³êÄ¢é̾B
i¬chi1972,bjuuê¼Æ̶w`¬liñj\\OìÌØ\\v
w¶wxæ40ª2j
uÔÜÅvÆ¢¤\èÉà©©íç¸A`ªÅÌuFs{vÌFlÉï¢ÉsÆ¢¤ÝèÅ é±ÆÉæÁÄAuêÂ̪A`ªÉ¨¢ÄuÊêvÅàÁÄ·éàÌÆAvZ³êÄ¢évÆ·éB»µÄAìl¨ÌujÌqvÆuê¼ÆÌÖWðÌæ¤ÉwE·éB
qðæèÞÆ·éuêÅ éªAá¦ÎwÀsxEwaðxEw½é©xEwqlèxÈÇÉoê·éq½¿ÍA¢¸êàL©ÈîÆALÑâ©ÈÍÉ¿Aqçµ¢f¼³ðÁÄ`©êéBÞçÍ éâÎqÌƵĶݵAìÒ©çßçêA`ʳêéOiÈÌÅ éBwªìÌL¯xi»wÃésHxÉ ½éjÉ`©êéNÍA±ÌujÌqvÉߢ«îÌ¿åÅ éBßq«A¢áÈA éη«ðÑÑÄ¢éBªìNÌ«îÍuê̬ðª¯AujÌqv̼\ÉÍAuêÌ©ÈeªÈ³êÄ¢é̾B
i¬chi1972,bjj
¾ªA±ÌuujÌqv̼\ÉÍAuêÌ©ÈeªÈ³êÄ¢évÆ¢¤wEÍAPÈé¼Ò̤ʫÉÆÆÇÜé±ÆÅÍÈAwÔÜÅxÌìiÖÌe¿ðàwE·éB
ålöÍujÌqvÉG³êÄAêeÌ^½â»ÌvÌ«öð³Ü´ÜÉA\\ÀÍúÉzµÄÝéªAuzvàeª ½©àÀÅ é©Ì@tBbgµAmŽévoreB[ðÛصĢéÌÍAuêàålöà¤ÉujÌqvÌÉüÁÄA©ÝÉìµÄ¢é©çÅ éBOÒÉƧ«ÍÈ¢BÂNÌñ¹éêqÖÌÌßèÝ ÍASõ³êé±ÆÈA¼į̂àÞÜÜɱ¯çêéBuê©gÉ滦Ģ^µ½u©ªvÆujÌqvƪA\\»ÌujÌqv©ç[ðµAúËIÉ`ålöÌuzvÉAÀÍuêÌuèÉzvµ½àeÉA¢AeBð^¦é̾B
i¬chi1972,bjj
u©ªvªèÉzµ½Í¸ÌuêeÌ^½â»ÌvÌ«övªAÀÅ é©Ìæ¤ÈWR«ðàÁÄ¢éÌÍAuuê©gÉ滦Ģ^µ½u©ªvÆujÌqvÆvÉæÁÄAu¢AeBð^¦év̾Ƣ¤B»µÄAWR«Ì¢±ÌuzvªAuvÉÜÅB·é±ÆÉ
Ú·éB
ålöÌuzvªuvÉBµÄ¢é±ÆÍÓ³êËÎÈçÈ¢BålöªÊêÉðõ³ê½AM«Ìu¼¶Í¤ÉÅAêÂÍAêÂÍj¼vÌͪ«ªÛ¥IÅ éBóælª¼eAZío AeÊ©A½¢ÍFlÅ é©ÍA ÜèâèÅÍÈ¢B±ÌKÈuñ\ZAµÌFÌ¢A¯ÌÑÌ¢ÌlvªAh¤¶Ä¶«Ä½æ·ªÆྦéujvAæ·ª ÆàÈÁÄ¢½uvɶĽu[vÍA\\»¢Ö̽éÊðÓ¡·éBwÔÜÅxÆ¢¤è¼ÍA´^ìÈ࿱µ½àÌɹæAoìÌ_ÅÍA»ÌÓ¡ð^î«Ìæè¢àÌÉϦĢéB\\uÌlvÌÃàW½éßÁÌl¶ðæ·éAÆB
iºüøpÒB¬chi1972,bjj
¾ªAuuÌlvÌÃàW½éßÁÌl¶ðæ·évÜÅàæµ½u[vðu©ªvÍÅãÜÅÇÞ±ÆÍÈ¢B»±ÉìÆEuê¼ÆÌua¶vð©oµÄ¢éB»ÌÓ¡ÅAuê¼ÆÌìiÌÅàAuÅàuìvÌ«iðõ¦Ä¢évÆ¢¤ÌÅ éB
ålöÍêíÌâÅ éu[vðñîÉàÇÜÈ¢BuêÌ¿ª^îIÈàÌƵľÄÉ©¾³êA©È~ÏÌåäå`ªÍÁ«è壳êÄ¢é̾B\\uê¶wÌua¶vÅ éB
iºüøpÒB¬chi1972,bjj
ÂÜèA¬chi1972,bjÅÍAuzvªuvÉB·é±Æ𨳦ȪçA»êÅàuêíÌâÅ éu[vvðÇÜÈ¢uñîv³A»±ÉìÆEuê¼ÆƵÄÌu©È~ÏÌåäå`vÌ壪 é̾ÆwEµÄ¢éÌÅ éB
@¬ÑKvi1985juuÔÜÅv_\\q¶«çêéÔrÌj]ÆBÁ\\viwìVw@qZúåwIvx91985N12jÅÍAu©ªvªuÌlvÉøuGXvªdvÅ éÆ¢¤ÇÝðño·éBܸ¬ÑKvi1985jÍu»ÀÌvÆu\ÌvÆðÌæ¤É¾mÉæÊ·éB
iªj¬àÌÉ»O·éA±êðq»ÀÌrÆÄÔ±ÆÉ·éB¬àÌ»ÀÌÉÀÝ·éÅ éB»±©ç¼ØÈÝÆêéÌÍAR½ésFÌC[WÅ ë¤B»êÍARAjÉAÉηéÛIÈF¯AÍáeâT^öxÌF¯µ©à½ç³êÈ¢B»êÉεÄA»ÌÛIȽéF¯ÉA̬ªÆÊÁ½ïÌIÈÖsð^¦é̪Oqµ½jÌqFmÖÌzÍrÆ¢¤í¯Å éB
i¬ÑKvi1985juuÔÜÅv_\\q¶«çêéÔrÌj]ÆBÁ\\v
wìVw@qZúåwIvx9
iøpÍwFmÖÌzÍ@uê¼Æ_xo¶Ð2004N3jj
»µÄA±Ìu©ªvÌuFmÖÌzÍvÉæÁÄ`¬³ê½u\ÌvÆAu¬àÌÉ»O·évÅ éu»ÀÌvÆÌÖWðÌæ¤ÉwE·éB
dvȱÆÍA±Ì̪q»ÀÌrÆdÈéÛØÍDZÉàȢƢ¤±ÆÅ éB»Ìӡɨ¢ÄA±ÌÌÍAq\ÌrÆÄÔÉÓ³íµ¢Bjɨ¢Äq»ÀÌrÍqFmÖÌzÍrÌàÆÉq\ÌrƵĬnµ½ÌÅ éB
@ƱëÅADèã°çê½^sXg[ÉÍq·×«rÌàóª³ê½BßÌáXµ³ÆØâ¬ð¾Å³¹ÈªçAÔÜÅÁ¬xð¯ÄëµÄäÅ éB±±ÉßÌqCͬ§µ½BjÌSð¯îƤ´ÉU¢Þ£f̬§Å éB{ÈçÎAF¯ÌsÀèÉ«ð^¦AF¯s×ðâ~³¹é͸ÌqFmÖÌzÍrª±ÌjÌêÉÀÁÄÍnÌnÆÈÁ½Bq·×«rÆ¢¤fðÅãÉF¯sתIðݽ̾ªA»ÌF¯Ì¬§Æ¯ÉAßÌ«ð©çè~¤±ÆàÂ\ÈA¢íäéq[[ÌüèÞ]nÌ éóÔª¬§µÄµÜÁ½ÌÅ éBµ©àA±ÌóÔ̬§ÉÔ¯ðüê¸ÉDÔÍFs{wÉ·×èÝAâÔÔÌÔÉjÌqð¬pÉÂêÄ䱤ƷéÆÌÔÉâèÆèªÅ«ÄµÜ¤ÌÅ é©çAÞÍ»ÀÆóÔÆÌÙÊð·éÔàÈA©çÌìèã°½óÔÅq\ÌrÆε½ÜÜ»ÀÌÉúèo³ê½±ÆÉÈéB
iºüøpÒBȺ¯¶B¬ÑKvi1985jj
@uzvÌY¨Å éu\ÌvªAuvÜÅuzv³êé±ÆÉæÁÄAu·×«vƵÄÌußÌqCvª¬§·éÆ¢¤B»µÄ»êÍA±ÌußÌqCvðAuq[[vÅ éu©ªvª¯éÆ¢¤uóÔv̬§ðàÓ¡·éÆ¢¤ÌÅ éB
iªjFs{ÆÍAjªqCbNÈCªÅßé±ÆÌÅ«éóÔAjÌZðÛØ·éóÔÈÌÅ éBjͱ±ÅAq»ÀÌrðA©çÌqFmÖÌzÍrªìÁ½q\ÌrÆ·è·¦Äs׵ĢéÌÅ èA»ÌëFÌÅßÌð©çè~¢Ìèð·µL×éDµ¢q[[ð¶Ä¢éÌÅ éB
i„Kvi1985jj
ܽA»ÌuÌlvÆÌâèÆèÆÍAuq[[vÅ éu©ªvÌêûüIÈàÌÅÍÈAuÌlvàܽAu éµ é¢Íeàtð±ßī𰩯æ¤Æµ½Svð¦·æ¤ÈoûüIÈàÌÅ éÆ¢¤B
tðù©ço»¤ÆµÄg·é¨ÌªÍAÔðwÁ½Ñª¹ÌƱëÅ\ÉÈÁĵÜÁÄ¢½Æ¢¤¨IðÉæÁÄ¢é̾ªAjÌqÌAêeÌs×ðéßéæ¤ÈûÔèÆAÌüÍÔèÆðí¹Äl¦êÎAª éµ é¢Íeàtð±ßī𰩯æ¤Æµ½SÌg³\\ãµpð¦µÄ¢éÆl¦Äæ¢ÆvíêéB
i„Kvi1985jj
»µÄAu[vðÇÞ±ÆÉ¢ÄÍÌæ¤É¾y·éB
õ³ê½t̶ÊðÇÞ±ÆA»êÍïÌIÉ̶̽ªµ©ðmÁĵܤ±ÆÅ éB±ÌªÉÖµÄjÌÏ«ðÇÝÆèA¼l̶ðÝ©éºò³ÉϦ½Æ¾¤±ÆàÅ«éB½µ©É»¤¢¤êÊà Á½ë¤BÔàɨ¢ÄàjÍKvÈãÉ̶ɥÝñŢȢBµ©µA»êÈãÉjÍ éÏÉIÈ~É¡ø³êÄ¢½Æ©çêéBÆ¢¤ÌÍAtðÇÞ±ÆÉæÁÄA©ªªìèã°½q\ÌrÌðâ·é±Æà è¾é½ÊA»ÌªÏXð]VȳêAjó³êéÂ\«à¢©ç¾BàµãÒÅ Á½êÉÍA¹Á©Ìð´ÌGXà³ÉAµÄµÜ¤BjÍ©ªÌìèã°½ßÌöóð°ê½B©ªÌÍÌj]ð°ê½BÞªDïS̵ÀðKÉ}¦Äß½ÌÍAßÌäŶçê½eaóÔÌBÁÅ éBÇÒÌک群ÈçÎAjªÆìèã°½ÆvÁ½ea«ÌÛÅ éB©çªÆ¤Éq¶«çê½ÔrÌ·¶Å éB±êÉæÁÄÞÍiÉð´ÌGXðÂȬÆßAÆea³ê½óð¤É¶«½Æ¢¤[À´ðèÉüê½ÌÅ éB
@µ©µAtðÇÜÈ©Á½Æ¢¤±ÆÍAà¤êûɨ¢ÄAjªÇÍózÆÆ¢¤TÏÒÅ èA»ÀÆÅÍȢƢ¤±Æð\IµÄ¢éBÞÍA¢íÎTÏÒƵÄÌöoÌqCYÈ¢µÍiVVYÉÁÄ¢éÉ·¬È¢ÌÅ ÁÄA±Ì¬àªÅIIÉ\o³¹Ä¢éàÌÍAÎÛÆÆð¯ê·é±ÆÉæÁÄTÏÒª¾½A¤¶´Æ¢¤öoÌGSCYɼÈçÈ¢B»Àæèà©ÈÌzÌûÉè²½¦ð´¶ÄäjÌa¶A±êªuÔÜÅvÌÅL«Å éB
i„Kvi1985jj
u©ªvªu[vðÇÜÈ©Á½ÌÍAutðÇÞ±ÆÉæÁÄA©ªªìèã°½q\ÌrÌðâ·é±Æà è¾é½ÊA»ÌªÏXð]VȳêAjó³êéÂ\«à¢©çvÅ èAu©ªvª»êÜÅnèã°Ä«½u\ÌvÆá¤u»ÀÌvÌîñðFmµÈ¢½ßÅ éÆྷéB©gÌzðu[v©çÌîñÅó³È©Á½±ÆÉæÁÄAuiÉð´ÌGXðÂȬÆßAÆea³ê½óð¤É¶«½Æ¢¤[À´ðèÉüêvéÆ¢¤B¾ªA»Ì½ßÉAuTÏÒƵÄÌöoÌqCYÈ¢µÍiVVYÉÁÄ¢éÉ·¬È¢vÆ¢¤¤Êð©Ñãªç¹é±ÆÉÈÁ½ÆwE·éB
@±Ìæ¤É¬ÑKvi1985jÅÍAu©ªvªÍ©Èu»ÀÌvÅ éuÌlv©ç¾½îñÉæèAu\ÌvÆ¢¤zðìèo·ÆྷéB»µÄ»ÌzÍuÌlvðußÌqCvÉd§Äã°Au©ªvðuq[[vƵÄA¼ÒÌuóÔv𬧳¹éB»±Å¾çê½uð´ÌGXvðiÉÛ·é½ßÉAu[vðÇܸɵĵܤƢ¤AuöoÌqCYÈ¢µÍiVVYvð©o·ÌÅ éB
@IØÇ÷i1985juuê¼ÆEmÆÏOÌwü«\\úìiÌâèÉ¢Ä\\viwÂRw@qZúåwIvxæ391985N11jÅÍAwÔÜÅxðw½é©xƯ¶æ¤ÉAu´îÌNvÌuzÂv̨êÅ éÆÊuïéB
@uêÌìiðÇñÅ¢ÄCñÆÌêÂÉAoêl¨Ì´îÌN̵³ªA«Åͳ¦æ¤àȦ«ãªèø¢ÄäA»Ìzª½ÇçêéBµ¢Ü ªN«êλÌÎÉÉK¸að ª éB÷eÉηé檩êéÆ·êÎA»ÌÎÉɵi ª©êéBßxÌsõ´ ª½ÇçêéÆ·êÎA»ÌÎÉÉßxÌõ´ ª½ÇçêéÆ¢Á½Ó¤Å éBuÔÜÅvÌålöÌàà»ÌHü©çµà¸êĢȢBqÌlrÉηéßx̯î àµÍõ´ ÍA»ÌÎÉÉqjÌqrÆÞÌ·É éÆ©çêé»ÌqrEÞÌqvrÖÌpÌ«´ àµÍsõ´ ðÄÑoܵĢéBiªjålöÍA»Ìæ¤È´îÌÉÆÉɧ¿ÈªçAêqêsÌßÆ»ÝÆ¢ðAS©ªÌáÌàÉWµæ¤ÆµÄ¢éÌÅ éB
iT_´¶BȺ¯¶B
IØÇ÷i1985juuê¼ÆEmÆÏOÌwü«\\úìiÌâèÉ¢Ä\\v
wÂRw@qZúåwIvxæ39
iøpÍwú{¶w¤å¬uê¼Æx§sï1992N10jj
uÌlvðu¯îvuõ´vðÄÑN±·àÌÅ èA»ÌÎÉÉujÌqvâuvvªu«´vusõ´vðÄÑN±·àÌÅ éÆÊuïéB»µÄA¼ÒÌÖW«ðÌæ¤ÉྷéB
@ålöÌáÌàÉÊÁ½êÆqÌÎƪA±Ìæ¤ÉµÄA½¿Ç±ëɯîS Æsõ´ Ép^[»³êA±Ì´îÌp^[ª±Ì¨ê𮩷îêÆÈéB
@µ©µA±Ì´îÌÎÆÍAålöªqÌlrÖ̯îÌ´öÉÈÁÄ¢éqjÌqrÌíªÜÜÔèA»ÌíªÜÜÔèðÁßé±ÆÉæèAålöÍàÁÆqÌlrÉßñƪÂ\ÉÈé̾B
iIØÇ÷i1985jj
¾ªA±Ìu¨ê𮩷îêvÍAu©ªvªujÌqvÌeðz·éÓÉÈÁÄAÏ»·éÆ¢¤B
@uê¼ÆÌ\»·élÔƵÄÌqwü«rªAqjÌqrðvƵÄÞÌêÆÞÌÌq^½rðqÌ»A´@A\¾·éƱëÜÅiñÅäB±ÌÀèɨ¢ÄAålöÍwDZ̬àðuê©gƯ¶Êuɧ¿nßÄ¢éB\»ÒƵÄÌuê¼ÆÌ®«ªZÝoµ½lÉA±ÌålöÍÞÌÆÌ^½ð°XÆ´@E\©µÄ¢éÌÅ éBuÔÜÅvJªÌålöÍA¯îSÆsõ´É¶E³êéPÈé´îÌl Å Á½ªA±±ÅÍÙÚ®àøÉF¯Ò E\¾Ò ÌÊuɧÁÄ¢éB·Èí¿AÞÌÆ°Sõð©gÌàÉW³¹½F¯Ìí Ƶı±É§ÁÄ¢éB
iºüøpÒBIØÇ÷i1985jj
±ÌøpÍAujÌqvÌeðz·éÓÉ¢ÄwEµÄ¢éB±ÌzÉæÁÄu©ªvÍA»êÜÅu¯îSÆsõ´É¶E³êéPÈé
iªjuê¼ÆÌqmâÏOrÌqwü«rÍAuê©gÌgßÈ̱©ç¶¶½êlÌålöðA®©µæ¤ÌÈ¢êÂÌ¢Eɶ߽ÌÅ éB±ÌålöÍA¯îÒ Å Á½©ªÌ^½A»µÄqÌlrÌ^½AÞÌêÆÌ^½ð»Ì]¡ÌXN[ÉÄ«t¯ÄA»êðSðß̱ÆƵÄAÞÆoï¤ÈOÌ¢EÉßÁ½ÌÅ éB»êÍêlÌ\»ÒÌa¶ðÓ¡µAålöÌqwü«rÌêÂÌðàÓ¡µÄ¢éB
iIØÇ÷i1985jj
uß̱ÆƵÄAÞÆoï¤ÈOÌ¢EÉßÁ½vÆ¢¤ÌÍAuÌlvÉo·æ¤ÉÜê½u[vðAÇܸɷé±ÆÌà¾Å éBPÈéu¯îÒvu´îÌlvÅ Á½u©ªvªAu\»ÒvƵÄu
@ÅãÉAäøÀ³üi1992jueNXgÌóeƶ¬\\uÔÜÅvÆ¢¤qór\\viw궤xæ92kC¹åw1992N12jÅÍAwÔÜÅxÆ¢¤ìiªAueNXgvÌuóvðßéæ¤Év·éàÌÅ éÆ壷éB
@ÆÜ껤µ½uÌlvÌËÉεAu©ªvÍuwæ¤äÀ¢Ü·xvÆuõv¾¤ÌÅ éB»êÍܳÉu©ªvªuÌlvðÆʸȢàÌƵĵ©©Ä¢È¢©çÅ éBÂÜèu©ªvÍA»¤¢¤uÌlv©çËð³êA»êð³moé±ÆªAuõv¢ÌÅ éB»¤µ½»Ìuõv³±»ªAu©ªvªwÔÜÅxðêé®@ ÌêÂÈ̾B
ir´¶B
äøÀ³üi1992jueNXgÌóeƶ¬\\uÔÜÅvÆ¢¤qór\\v
w궤xæ92j
±Ìæ¤ÉAu©ªvÉÆÁÄÌÝÌuuõv³vðAwÔÜÅxɨ¯éu
»à»àu[vÆÍA¶ÊÌöJ³ê½ÈÅ éBÂÜè»êÍAíɼÌN©ÉÇÜêé±ÆªOñƳ꽮ÈÌÅ éB»ê¾¯ÉuÌlvªu©ªvÉð˵½ÌÍAu©ªvÉεêXÈÏÏðúҵĢ½©çÅÍÈAÞµë»Ìu[vª½Æ¦ÇÜê½ÆµÄà·µáèÌÈ¢AÊèêÕÌàÌÅ Á½©ç¾Æ¢ÁÄàæ¢B
iäøÀ³üi1992jj
¬ÑKvi1985jÅÍAuÌlvÉÜê½u[vð¸¦ÄÇà¤ÆµÈ¢ÌÍA©gÅnèã°½u\Ìvðóµ½È©Á½©ç¾AÆ¢¤à¾µÄ¢½Bµ©µAäøÀ³üi1992jÅÍA±Ìu[vÆ¢¤Á«É
ÚµAu½Æ¦ÇÜê½ÆµÄà·µáèÌÈ¢AÊèêÕÌàÌÅ Á½vÆwE·éB»µÄAu©ªvÆuÌlvêqOlƪÊêéÛAuáXvÆ¢¤ÄÌðp¢çêé±ÆÉÖµÄÍAÌæ¤ÉwE·éB
µ©µ±±ÅÓð¥íȯêÎÈçÈ¢ÌÍAuáXvÆ¢¤\»ªAu©ªvÆuÌlvÆÉæÁÄIð³ê½àÌÅÍÈA ÜÅu©ªv̤ÌIðð¾¢\µ½à̾Ƣ¤±Æ¾BÂÜè±êÜÅ©ÄĪ©éÊèAuÌlvÉÆÁÄÂXÌoÍAµÄu©ªvÆÌÖWÉuáXvÆ¢¤êÌIðð±«o·æ¤ÈàÌÅÍÈ©Á½B»¤¢¤uÌlvÌ»ÀÉεAu©ªvªuáXvÆ¢¤êÅñlÌÖWð¨¦é±ÆÍAtÉuÌlvÌ»ÀðÜÁ½aOµÄ¢é±ÆÉÈé̾B
iäøÀ³üi1992jj
±Ìæ¤ÉA±ÌuáXvÆ¢¤ÄÌÍA ÜÅàu©ªvÉÆÁÄÌuÌlvÆÌÖW«ð çíµ½àÌÅ é±ÆðmF·éB¾ªAäøÀ³üi1992jÅ_¶çêÄ¢é±ÆÍAPɬÑKvi1985jÌá»ÅÍÈ¢BwÔÜÅxÆ¢¤ìi¶½¢ÉA¬ÑKvi1985jÅwE³êÄ¢½æ¤ÈuGXvÆ¢Á½ÇÝûðv·éuóvª éÆ¢¤Bìi`ªÌA
@Fs{ÌFÉAuúõÌArÉÍ¥ñ¨×·évÆ]ÂÄâ½çAuUÂÄàêAlàs©çvÆ]ÓÔðó¯æ½B
@»êͪࢪÌÅA©ªÍÁÉßãlñ\ªÌDÔðIñÅAeÉp»ÌFÌÜÅsɵ½B
iwÔÜÅxwuê¼ÆSWæêªx1998N12j
Æ¢¤ÔÝèÉæÁÄAuu©ªvÉæÁÄêçêÄ¢éßÌÔvu»µÄ»êðu©ªvªêÁÄ¢éÔvuÇÒƵĽ¿ª±ÌeNXgðHÁÄ¢éÔvÆ¢¤uOdÌÔ\¢vðà±ÆÉÈé±ÆðmF·éBµ©µA»êªÌæ¤ÉAuu©ªvÉæÁÄêçêÄ¢éßÌÔv¾¯ªuOi»v³êéÆ¢¤B
iªjZ¶ÅAµ©à»ÌêÌ®«âÜ ðôÝ|¯éæ¤ÉĶ·é±ÆÅAêèè©Éàܽ½¿ÉàA ½©à»êªáOÌêÊÅ é©Ìæ¤ÉÓ¯³êÄ¢B»êÉæÁÄu©ªvÌ̱µ½ßÌÔªAeNXgàÌAÈ»Ý ÆµÄOi»³êAêèèâÇÒƵÄÌÔÍAwiƵÄÞ¯çêÄ¢ÌÅ éB
@Ʊ못ÌÔÉATôªüéª éB»êªuFs{ÜÅÇñÈÉêÍ¢ç³ê½ç¤BvÆ¢¤¾qÅ éB±êÍRp[ggÌÔÉ]¤ÈçÎAuFs{ÜÅÇñÈÉêÍ¢ç³êé¾ë¤ Bvƾ¤×«Å éB»êÉεu¢ç³ê½ç¤vÆ¢¤¾qÍAu©ªvª»êÜÅÌRp[ggÌÔ\¢©çíEµAêèèƵĨêðêé»Ý ɧ¿ßÁÄêçêÄ¢éB
iT_´¶BäøÀ³üi1992jj
wÔÜÅxÌã¼ÌuFs{ÜÅÇñÈÉêÍ¢ç³ê½ç¤BvÆ¢¤qÉ
ÚµA±ÌqÉæÁÄAuu©ªvª»êÜÅÌRp[ggÌÔ\¢©çíEµAêèèƵĨêðêé
@u©ªvªRp[ggÌ»Ý ©çíE·éÆ¢¤±ÆÍAñÔÌæqÅ é±ÆðâßAêèèƵÄÌ»Ý É§¿ßé±ÆÅ éB»êÉæÁĽ¿àܽA¯æÒƵÄÌ»Ý Éø«ß³êé±ÆÉÈéB±ÌâèÈÌÍAu©ªvƽ¿ÆÌq»Ý rÌ¿IáÅÍÈAu©ªvÍ ÜÅ»ÌêÌêJðæmÁÄ¢ÄA½¿ÍS»êðmçȢƢ¤±Æ¾BÂÜèuÇñÈÉêÍ¢ç³ê½ç¤BvÆ¢¤¾qÅA»ÌêJÉ¢ÄÌqórðø¦ñŵܤÌÍAu©ªvÅÍȽ¿ÌûÈÌÅ éB»Ìæ¤ÉµÄêèèÍA½¿É»ÌqórðïÌ»·é±Æ\\±Æ \\ðßÄ¢éÌÅ éB
@»ÌÓ¡ÅwÔÜÅxÌêèèªÓ¯IÅ Á½à¤êÂ̱ÆÍA½¿ÇÒÉηéÄÑ|¯É¦é±ÆÍA½¿ÌÇÞ±Æ ðAeNXgÌ_b\\©çðú·é±ÆÅà éB
iäøÀ³üi1992jj
wÔÜÅxÌuêèèÍA½¿É»ÌqórðïÌ»·é±Æ\\
@ÈãÌæ¤ÉwÔÜÅxÉ¢ÄÌæs¤ÌwEðÝÄ«½B¬chi1972,bjÅÍAujÌqvÌeðuzvµA»ÌuzvªÉB·éàÌÅ é±ÆðmFµA»êÅàuêíÌâÅ éu[vvðÇÜÈ¢u©ªvÌuñîv³ÉAu©È~ÏÌåäå`vÆ¢¤å£ðwEµÄ¢½B
@¬ÑKvi1985jÅÍAwÔÜÅxÉAußÌqCvÅ éÆ©§Ä½uÌlvÆA»êð~¢o·uqCbNÈCªvÌu©ªvƪAuð´ÌGXvðø¨êÅ éÆ¢¤åèð©o·Bu[vðÇÜÈ¢ÌÍA»ÌußÌqCvÅ éu\Ìvðó³È¢½ßÅ éÆl@µÄ¢½B
@êûAIØÇ÷i1985jÍAwÔÜÅxÍA»ÌÙ©Ìuê¼ÆÌìiƤʷéu´îÌNvÌuzÂvð½ÇéÆ¢¤uîêvðàÂÆmF·éB¾ªAujÌqvðz·éÛA»êÜÅu´îÌlvÅ Á½u©ªvÍAuF¯ÌívÆÈèAuÞÌÆ°Sõð©gÌàÉW³¹vÄ¢Æl@µÄ¢½B»µÄA»êÍAìÆEuê¼ÆÌumâÏOvÌuwü«vð¦·àÌÅ éÆwEµÄ¢½B
@ÅãÉAäøÀ³üi1992jÅÍAu©ªvÆuÌlvÆÌâèÆèªAu©ªvÌÝÌuuõv³vÉ·¬¸A»Ìuuõv³vªìiÌu
@±êçÌæs¤ð¥Ü¦ÄAÌæQÅwÔÜÅxÌ[TÆêÊ\¬É¢Į·é±ÆÉ·éB
@æQÅÍAOßÌw½é©x̪ÍÅà±±ëàݽæ¤ÉAªÍÚðl¦é誩èƵÄAìiSÌÌåÜ©È[TÆêÊ\¬Æð®·éBæPÌæs¤ð¥Ü¦ÈªçAwÔÜÅxÉ¢Äl¦Ä¢B
@ÄÌ¢úÌ[ûAuFs{vÌFlÉï¢És½ßAu©ªvÍuãìvw©çuÂXsvÌDÔÉæèÞB¢ÂàÊè̪µ¢æqðæ»ÚÉAu©ªvͬGªð¯çêéêÔOÌÔ¼ÌêÔãëÌêÔÉæèÞ±ÆÉ·éB»±ÉAoÔÛÉÈÁÄAñ\ZµÎÌuÌlvªñlÌcqðÂêÄAu©ªvÌ¢éêÔÉæÔµÄéB»µÄDÔªoéBiêÊTj
@DÔªoéÆAuÌlvÍu©ªvÌü©¢¤ÌAúªéêÉÈðÆéBúªé굩Ȣ±ÆÉ¢Á½lqÌuÌlvÉεÄAAêçê½ujÌqvÍ°ëµ¢çðµÄ¦éBuÌlvÌ¢ÁÄ¢élqð©©Ë½u©ªvÍAujÌqvÉÈðä¸ÁÄâéBµ©µAujÌqvͳ¤zÈÜÜÅ éBÎÌçÈ¢êÉȪó«uÌlvª»±ÉÚ®·éÆAÔÁÄ¢½uÔvªáðoܵīoµÄµÜ¤BuÌlvª â·ªAuÔv̨µßªGêÄ¢é±ÆÉCëAÄÑujÌqvÌÀéêªÈÈÁĵܤB»êð©Ä¢½u©ªvÍAÄÑujÌqvÉÈð÷ÁÄâéBujÌqvªÈÉßéÆAu©ªvÍêqÌs«æðqËéBkC¹ÌuÔvÜÅsÆ·¢½u©ªvÍA ÜèÉóÛÌá¤êqÌÚ³ªÄ¢é±ÆÉCëAujÌqvÌeðzµnßéBiêÊUj
@u©ªvÍAuÌlvÌbÆAÈÇ©çAÌÌØâ©Èéçµðz·éBµ©µAvÌïЪ¤Üs©ÈÈÁÄACïµ¢jÉÈÁĵÜÁ½Ì¾ë¤Æv¢ðß®ç¹éBiêÊVj
@u©ªvªñlÌqÌeðzµÄ¢éÆAujÌqvª¬Öði¦éBµ©µADÔÉÍÖªÈAwvÍuFs{vÜŬÖð·éԪȢƢ¤BKÉä·éæ¤É£·uÌlv¾Á½ªAuÔvÜÅà«oµÄµÜ¤BñlÌqÇàÉ¢ç³êélqðÝÄAu©ªvÍuÌlvªâªÄñŵܤÌÅÍÈ¢©AÆl¦éBuFs{vÉÂÆAuÌlvÉÔñVðÝĨ¢ÄêAÆÜêAu©ªvÍõø·éBµ©µAêeª£êæ¤Æ·éÆuÔvÍ«oµÄµÜ¤BdûÈw¤±Æɵ½uÌlvÍAu©ªvª±ÌuFs{vÅ~èéÆ°éÆÁBtH[Åà¢Ä¢éÆAuÌlvÍu©ªvÉtðo·æ¤ÉÞBµ©µA»ÌtªÈ©È©æèo¹¸É¢éÆAu©ªvÍAuÌlv̨ÌnJ`ªÍ¾¯éÌðÝÄA»ê𼻤Æèð·µL×éB»µÄu©ªvÆOlÌêqÍÊêéBiêÊWj
@wÅtðo»¤Æ·éÆ«Au©ªvÍ»Ìàeð©é©©Ü¢©À¤Bµ©µAÇ©¸É·éBiêÊXj
@wÔÜÅxÌ[TðÜÆßéÆÈãÌæ¤ÉÈéBêÊ\¬ÍÌæ¤Éª¯çêéÅ ë¤BȨAw½é©xƯlÉA\Ìu¶ÔvÍA{eɿƵÄYtµÄ¢éwÔÜÅx{¶iì¬Ícj̶ÔÉηéàÌÅ éB
| êÊÔ | ¶Ô | êÊ | êÊÌ[T |
|---|---|---|---|
| êÊT | 1`12 | æÔEÔ | ìiÌ`ªBu©ªvªÂXsÌDÔÉæè±ÝAñlÌqðÂê½Ìlªu©ªvÌæéÔ¼ÉæèñÅéBDÔªÔ·éÜÅB |
| êÊU | 13`129 | êqÆÌâèÆè@ | »ÌãÌu©ªvÆêqÆÌâèÆèªWJ³êéBu©ªvÍujÌqvð×ÉÀç¹éBuÌlvÌÚInªuÔvÅ é±ÆðméB |
| êÊV | 130`153 | eivjÌz | u©ªvªêqÌpð©ÈªçA©ÂÄ̯¶ðv¢©×A»Ìeðz·éB |
| êÊW | 154`197 | êqÆÌâèÆèA | ÄÑAêqÆÌâèÆèªWJ³êéBujÌqvª¬Ö𵽢ƾ¢o·BFs{źԵAêqÆÊêéÜÅB |
| êÊX | 198`204 | èÌ | êqÆÊê½ ÆAÜê½èð·éB |
@wÔÜÅxÅÍAu©ªvÆDÔÌÅoïÁ½uÌlvÆÌð¬ªSIÈìiÉÈÁÄ¢éBæs¤ÅÍAu©ªvªuÌlvÖuGXvð´¶é±ÆªAìiÌåèÅ éÆwE³êÄ¢½i¬ÑKvi1985jjBµ©µAl@ÌOñƵÄA»ÌuGXvðl¦éÌÅÍÈAu©ªvª¢©ÉuÌlvÉÖSðø«ASIÈ£ðßïĢ©AÆ¢¤_É
Ú·é±ÆÉ·éBuGXvð´¶Ä¢½©Û©A é¢Íu©ªvªuÌlvÉεÄÇÌæ¤È´îðø¢Ä¢½Ì©AÆ¢¤_ÍìiSÌðê·éåèÉ©©íéâèÅ éBwÔÜÅxɨ¯éåèªAïÌIÉÇÌæ¤ÈàÌÅ é©AÆ¢¤±ÆÉ¢ÄÍAÈ~Åq@â_Ìz̪ÍEl@ðʵÄA¾ç©Éµ½¢B
@»ÌSIÈ£ªßÃÆ¢¤±Æðl¦é½ßÌĪ©èƵÄAuÌlvÆA»ÌqÇàÅ éujÌqvâuÔvÆ¢Á½»Ì¼Ììl¨½¿ÆªAÇÌæ¤ÉÎäIÉ`©êĢ̩AÆ¢¤_ðêÂÌÏ_ƵĪÍEl@ðißÄ¢BêÊWÌIíèÅAu©ªvÆuÌlvçªAuáXvÆ¢¤êêÅÄ̳êéB»êÜÅu©ªvÆuÌlvAuêevƾmɪ¯çêÄ¢½Ä̪AêÂÌêÅÄ̳êéæ¤ÉÈéÆ¢¤±ÆÍA»ê¾¯u©ªvÆuÌlvÆÌSIÈ£ªßâ½Æ¢¤±ÆÅ ë¤Bu©ªvÍAôRDÔÅæèí¹½uÌlvÉεÄAuáXvÆÄ̳êéÙÇÉSIÈ£ªßïĢA»Ìßöðl¦é±ÆªAìiÌåèðl¦éĪ©èÉÈéB
@æRÅÍA±êç̱Æð¥Ü¦ÄAÀÛÉÇÌæ¤ÈªÞÌÚðݯéÌ©ðè·é±ÆÉ·éB
@wÔÜÅxÌq̪ުÍÌÚðè·éBOßÅà±±ëݽæ¤ÉAyOi1986jâw½é©xŪ͵½Úð¥Ü¦ÈªçAwÔÜÅxÌàeɦµ½Úðè·éBwÔÜÅxɨ¢ÄàA±êç̪ÞÚÍAìiɦµ½àÌÉ·é½ßA½xàÄlµA[@IÉèµ½àÌÅ éB
@w½é©xƯ¶æ¤ÉAuqÒ\»vÆuÎÛ\»vÉñª³êéBuqÒ\»vÍAw½é©xɨ¯é»êÙÇÈÈ¢½ßAºÊæªÆµÄAuqÒvÉæéAæèqÏIÈâ«à¾Ìquà¾vÆAæèåÏIÈuðßE]¿vðºÊæªÆµÄݯéB
@uÎÛ\»vÍAul¨`ÊvAu¨`ÊvÉñʳêéBwÔÜÅxÅÍAu¨`ÊvÌqª é½ß±êðݯé±ÆÉ·éBu¨`ÊvÍA¨Ì®«â®ìð\í·u®Ô`ÊvÆA¨ÌlqâóÔðqµ½uÃÔ`ÊvÆÉñª³êéBܽAuêÊÝèvÌqªÝÆßçêé½ßA±êàul¨`ÊvEu¨`ÊvÉÁ¦é±ÆÉ·éB
@wÔÜÅxÍAæPÌæs¤âAæQÌêÊ\¬Ì®Åݽæ¤ÉAêlÌu©ªvªuÌlvÉSIÈ£ðßïĢAÆ¢¤¨êÅ éB»±ÅSIÈìl¨ÆÈéu©ªvðul¨`ÊvÅæʵĵ¤±ÆÉ·éBܽAuÌlvÆAujÌqvðͶßÆ·é¼Ììl¨ÆÌ`«í¯ªdvÈÓ¡ðàÂàÌÆl¦½½ßAuÌlvàÊɪ޷é±Æɵ½B¼ê¼êÌul¨`ÊvÉÍukb`ÊvEus®`ÊvEuóÔ`ÊvEuS`ÊvÆ¢¤lÂ̺Êæªð·éBwÔÜÅxɨ¢ÄÍAuS`ÊvɺÊæªðݯȢB
@±êç̪ÞÚðÓð«É®µÈ¨·ÆȺÌæ¤ÉÈéBiájƵ½àÌÍAwÔÜÅxɨ¯éA»ÌÚÌqÌïÌáÅ éB¶ÔAªÔÍYtµ½¿ÌwÔÜÅx{¶Æ¯lÌàÌÅ éiì¬ÍûücjBºüª éàÌÍA»ÌºüÌݪ»ÌqÅ éiºüÍûücjB´¶É érÍOµ½B
| uqÒ\»vc | uqÒvɦµ½åÏIÈ\»B |
| uà¾vcccc | uqÒvÉæéæèqÏIÈâ«à¾Ìuà¾vÌqB iáj24´µ©ó¢ÄÈ©Á½ÌÅB |
| uðßE]¿vc | uqÒvÉæéæèåÏIÅ]¿ªÁíÁ½uðßvAu]¿vÌqB iáj52×Æ¢ÂÄàAÌMºÜÆC~ïªê¾¯¾B |
| @ | @ |
| uÎÛ\»vcc | q³êé±Æªçɦµ½AæèqÏIÈ\»B |
| uêÊÝèvcc | êÊÌ¢ÜE±±ðÝè·éqB iáj2iaj»êͪࢪÌÅAibj©ªÍÁÉßãlñ\ªÌDÔðIñÅAeÉp»ÌFÌÜÅsɵ½B |
| ukb`Êvcc | ¼Úb@ÉæÁIJ«o³ê½eìl¨ÌïbÌ`ÊB iáju25iajê³ñAÇ¢ÆêævibjƵÂèÌjÌqªûÌÔɵíðñ¹Ä¢ÓB |
| us®`Êvcc | l¨Ì®ÔIÈ®ìA®«Ì`ÊB iáj46©ªÍjÌqÌèðæÂÄ©ªÌTÉ¿ç¹½B |
| uóÔ`Êvcc | l¨ÌÃÔIÈlqAepÌ`ÊB iáj42qͨÆ@ÆÉÈðÂ߼B |
| uS`Êvcc | u»Ì¼Ìl¨vÉ¢ÄÌàÊÌ`ÊB iáj40çFÌ«¢AªÌ«ÌJ¢½AÈq¾Æv½B |
| u¨`Êvcc | l¨ÅÍÈ¢Aâ¨É¢ÄÌqBȺÌñÂÌqɺÊ檳êéB |
| u®Ô`Êvcc | ¨É¢ÄÌ®IÈ`ÊB¨Ì®«âA®ìÆ¢Á½ÔIÈÏ»ð`ʵ½qB iáj6éªÂÂÄAüDûªJ©ê½B |
| uÃÔ`Êvcc | ¨É¢ÄÌÃIÈ`ÊB¨ÌlqâAóÔÆ¢Á½óÔIÈ`Êð`ʵ½qB iáj16»êÅ൪µ©üÂÄÈ¢B |
@±êçÌÚðAc²iñjɨ«A¶ð¡²isjɨ¢½B}\Ì^CgsÍÌæ¤ÉÈéB
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||||
| u©ªv | uÌlv | »Ì¼Ììl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | ||||||
@eÚÌqÍAwÔÜÅxɨ¢ÄàAOßÌw½é©xƯ¶æ¤Ézuµ½B¶[ɶÔð¨«AuÎÛ\»vuqÒ\»vÆÈç×½BuÎÛ\»vͶ©çuêÊÝèvul¨`ÊvƵÄAȺu©ªvuÌlvu»Ì¼Ììl¨vÌul¨`ÊvðÎä³¹çêéæ¤Èç×½Bul¨`Êv̺ÊÚÍA¶¤É¢ÙÇOIÈ`ÊAE¤É¢ÙÇl¨ÌàÊÉ©©íé`ÊÉÈéæ¤zuµ½B
@ªÞªÍÍAê¶ð»ÌÜÜêÂÌÚɪ޷éÌÅÍÈAqªªIɪ¯çêéêÍAª¯Ä¢éB¶ÔÈOÉàAªÔªKvÈÌͻ̽ßÅ éB±êç̱Æàw½é©xŨ±ÈÁ½ªÞªÍɶĢéB
@ªÍÍêʲÆɨ±È¢A}\ƵĿƵÄYtµÄ¢éBeêÊÅSÝçêÈ©Á½ÚÉ¢ÄÍA}\ðȪ»·é½ßíµÄ¢éBêÊUɨ¯éul¨`ÊvÌuÌlvÌuS`ÊvÈǪ»êÅ éBܽAæSÈ~Ìl@ÅàQƵⷢæ¤ÉA¾yµÄ¢éªÌªÍ}\ð²«oµ½BȨA{eÌɲ«oµ½}\ÍAȪ»·é½ßukb`ÊvAus®`ÊvccðA»ê¼êukbvAus®vccƪLµÄ¢éB
@\LÉ¢ÄÍAÌæ¤Éµ½BYtµ½ªÍ}\Ì¿ÍAêʲÆɨ±ÈÁ½àÌÅ éB}\É«ÞÌÍA´¥ÆµÄA¶Ôi1A2A3cjƪÔiiajAibjAicjcjÌÝÅ éB±Ì¶ÔÍA¿ÉYtµ½wÔÜÅxÌ{¶ÆεĢéBuêÊÝèvÌqÍA¶ÔÈOɼÚ}\É«Á¦Ä¢éB
@ÈãÌæ¤ÉAqðªÍµ½Êð³ÉAæSÅïÌIÉwÔÜÅxÉ¢Äl@ð¨±ÈÁÄ¢±ÆÉ·éB
@OßÌw½é©x̪ÍƯ¶æ¤ÉAq̪ުÍÉæèAwÔÜÅxÌl@ð··ßéB±±Å
ڷ׫_ÍAuÌlvÆujÌqvðͶßÆ·é»Ì¼Ìl¨Æª¢©ÉÎäIÉ`©êÄ¢é©AÆ¢¤_Å éB»ÌÎäÆÍAuÌlvÆujÌqvâuÔvçƪ³½ÎÉ éÌÅÍÈAu©ªvªuÌlvÉÖSð¿A¯î·éêÂÌvöƵÄAujÌqvâuÔvÌóÛIÈ`ʪ éÆ¢¤±ÆÅ éB
@ÂÜèA¢©Éu©ªvªuÌlvÉÖSðà¿A¯î·é©AÆ¢¤_ðl¦é¤¦ÅÌĪ©èƵÄA¼ÒÌÎäðq©çl@µÄ¢Æ¢¤è±«ÉÈéB
@wÔÜÅxɨ¢Ä_ªu©êÄ¢éÌÍAw½é©xÆÍá¢Aêl̬àÅ é½ßAêlÌÌu©ªvÅ éBȺÌl@àAu©ªvÉ_ªu©êÄ¢é±ÆðOñƵķ·ßÄ¢±ÆÆ·éB
@{Åøp·éwÔÜÅx{¶ÌT_ÍA´¶Éæéiwuê¼ÆSWæêªxâgX1998N12jB¶ÔAªÔÍøpÒÉæéB
yêÊTz
@1Fs{ÌFÉAuúõÌArÉÍ¥ñ¨×·évÆ]ÂÄâ½çAuUÂÄàêAlàs©çvÆ]ÓÔðó¯æ½B
@2iaj»êͪࢪÌÅAibj©ªÍÁÉßãlñ\ªÌDÔðIñÅAeÉp»ÌFÌÜÅsɵ½B3DÔÍÂXsÅ éB4iaj©ªªãìÖ ¢½ibjÉÍAà¤å¨ÌlªüDûÖWÂĽB5©ªà¼®´ÔÖüÂħ½B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||
| u©ªv | uÌlv | »Ì¼Ììl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||
| s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | ||||||
| 1 | 1Fs{ÌFÉAiªj]ÓÔðó¯æ½B | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 2 | 2iaj»êͪࢪÌÅA | @@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2ibj | @ |
| 3 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | @ |
| 4 | @ | 4iaj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 4ibj | @ | @ | @ | |
| 5 | @ | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
@
@@±ÌøpÍwÔÜÅxÌ`ªÉ ½éBu©ªvªuFs{vÉsRªñ¦³êAïÌIÈÔÆóÔÌÝ誳êAu©ªvÍuÂXsvÌDÔª éuãìvÌwÉ
B
@æ1¶ÌiKÅÍAu]ÂÄâ½çvÆ¢¤å̪NÅ éÌ©As¾Å éB±Ìu]ÂÄâ½çvÆ¢¤qÍus®`Êvɪ޳ê¤éªAu]ÓÔðó¯æ½vÆ é±ÆÆAuFvÆÌâèÆèªïÌIÈêÊɨ¢Äq³êÄ¢éí¯ÅÍÈ¢±ÆÆ©çA±ÌqÍAèÈÇÅÌâèÆèÆl¦çêé½ßuêÊÝèvÌqƵĪ޵½B
@±2¶A3¶ÌqàAuêÊÝèvÆuqÒ\»vÌuà¾vÅ éB±Ì`ª3¶ÜÅÅڷ׫±ÆÍAæs¤ÅwE³êÄ¢½æ¤ÉAìiÌ\èªuÔÜÅvÅ éÌÉεAu©ªvÌÚInªuFs{vÅ é±Æª¾©³êé_Å éB±Ì`ªÌ_ÅÍAuÌlv̶Ý;ç©É³êÈ¢ªAÇÝèÍáa´ð±ÆÉÈë¤BìiÌ\èªuÔÜÅvÅ éÌÉεAu©ªvÌÚInÍuFs{vÅ èAH¢áÁÄ¢éB±Ì\èÆ`ªÌH¢á¢ÍAâªÄKêéuÌlvÆÌoAÊêðOñÆ·éàÌÅ éÆ¢¤±Æª¦³êÄ¢éBÇ꾯SIÉßâ½ÆµÄàu©ªvÍuÌlvÆÊêéÆ¢¤ðæµÄ¢éÌÅ éB
@ܽA±Ì`ªÍ¯ÉAu©ªvÉÆÁÄÍAuãìv©çuúõvÖÆ¢¤óÔIÈÚ®ðº¤s®Å êAúíÌoÅ é±Æ঳êÄ¢éB
@6éªÂÂÄAüDûªJ©ê½B7lXÍêxÉÇæß«§Â½B8iajçõ̹ªÉ·¦o·B9üDûÌè Ö©ֽèרðûðcßÄøÂÏélâA{¬©çHÝoµÄ³ÉAÒç¤Æ·élâA»êðüêܢƷélâAibj¢ÂàÌÊè̬GÅ éB10¸ª}Èá«ÅüDlÌwã©çqÌêlXXð©ÄéB11iajðh¤¶Äo½lXÍvbgtH[ð¬èÉ}¢ÅAwvÌibjuæªó¢Ä¢Ü·Aæªó¢Ä¢Ü·vicjÆ©ÔÌà·©¸ÉAáêæ«ÆèZÈqÔÉü轪éB12iaj©ªÍêÔæÌqÔÉæéÂàèÅibj}¢¾B
@13iajæÌqÔÍibjÄÌèicj·¢Äî½B14©ªÍêÔæÌÔÌêÔãÌê ÄÔÉü½B15ãûÌqÔÉæêȩ½AªÇXÜÅàµñ¹Ä½B16»êÅ൪µ©üÂÄÈ¢B17Ô̪¹Ü½B18ßËð½Äé¹A»Ì¨³Öàð|¯é¹ÈǪ·¦éB19iaj©ªÌéÔÌËð¡Âßæ¤Æµ½XÉÔ¢Ø𪢽wõªèð°ÄA
@uibjûÖ¢çµâ¢B20iaj±¿çÖvibjÆËðJ¯ÄÒÂÄéB21iajÖAibjñ\ZµÌFÌ¢A¯ÌÑÌ¢icjÌlªAêlð¨ÔÐAêlÌèðg¢ÄüÂĽB22DÔͼ®o½B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||
| u©ªv | uÌlv | »Ì¼Ììl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||
| s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | ||||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 6 | @ | @ | @ |
| 7 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 7 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 8 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 8 | @ | @ | @ |
| 9 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 9iaj | @ | @ | @ | 9ibj |
| 10 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 10 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 11 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 11ibj | 11iaj icj |
@ | @ | @ | @ | @ |
| 12 | @ | 12ibj | @ | 12iaj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 13 | @ | @ | @ | 13ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 13iaj icj |
@ | @ |
| 14 | @ | 14 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 15 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 15 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 16 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 16 | @ | @ |
| 17 | 17Ô̪¹Ü½B | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 18 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 18 | @ | @ |
| 19 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 19ibj | 19iaj | @ | @ | @ | @ | @ |
| 20 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 20iaj | 20ibj | @ | @ | @ | @ | @ |
| 21 | @ | @ | @ | @ | 21iaj icj |
21ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 22 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 22 | @ | @ | @ |
@uãìvÌwÉ¢½u©ªvÍAæªÌDÔÌAêÔãÌêÔÉæÔ·éB»µÄAÔÔÛÌDÔÉAu©ªvÌæéêÔÉñlÌcqðÂê½uÌlvªæÔµADÔÍÔ·éB
@wÉ
µ½u©ªvÍG¥ðð¯ÄA¬GÌÈ¢æªÌÔ¼ÌAêÔãÌêÔÉæÔ·éB±±ÅAڷ׫±ÆÍAu©ªvÆ»êÈO̬G·élXƪÎä³êÄ¢é±ÆÅ éB9¶uüDûÌè Ö©ֽèרðûðcßÄøÂÏélâA{¬©çHÝoµÄ³ÉAÒç¤Æ·élâA»êðüêܢƷélv½¿ÌAu¢ÂàÊèvÌlXÆAu©ªvÆÍùÉêüðæ·éæ¤É`©êÄ¢éB11¶u©ÔÌà·©¸ÉAáêæ«ÆèZÈqÔÉü轪évÆ èAu©ªvÍlXðâÃÉÆç¦Ä¢éB³çÉA12¶u©ªÍêÔæÌqÔÉæéÂàèÅ}¢¾vÆ éæ¤ÉAu©ªvƻ̼ÌæqƪÎäIÉ`©êÄ¢éB[¢ÖSƯîðX¯é±ÆÉÈéuÌlvÆoï¤OÉAêÊqÆÍAêüðæ·éu©ªvÆ¢¤l¨ÆA»ÌÓ¯ª`©êÄ¢éÆ¢¤±ÆÅ éB
@ܽAu©ªvÉÖµÄà¤ÐÆÂÌÚ³êéÌÍAúíIÉDÔðpµÄ¢él¨Å éÆ¢¤_Å éBu¢ÂàÊèvÆ·éæqâA¬Gð©zµÄͶߩçæªÌÔ¼ÉæèÞu©ªvÉÆÁÄADÔÉæé±Æ»ÌàÌÍA»êÙÇÁÊȱÆÅÍÈ¢ÌÅ éB
@»Ìæ¤È¬GÌAñlÌqÇàðÂê½uÌlvªAu©ªvƯ¶êÔÉâÁÄéBæ21¶É éæ¤ÉAuÌlvÍA»êÜÅ̻̼Ìl¨½¿ÆÍá¢Auñ\ZµÌFÌ¢A¯ÌÑÌ¢vÆש¢uóÔ`Êvª³êÄ¢é±Æ©çA©©¯½_Å·ÅÉ»¡ðÁÄ¢é±Æðfí¹éB
@±Ìæ¤ÉêÊTÅÍAu©ªvͼÌêÊÌæqÆÍá¤Ó¯ðàÁÄ¢él¨Å é±Æª¦³êÄ¢éBܽA»Ìu©ªvÍADÔÌð 究ßßÄ¢½èA¬Gð©zµÄæéÔ¼ÉÚ¯ð¯Ģélq©çADÔÉæé±ÆªúíIȶÌÉ él¨Åà éB»Ìu©ªvÍAâÃżÌlÔÆÍá¤Ó¯ðÁ½l¨ÆµÄ`©êÄ¢éBâªÄuÌlvÉ¢ÖSÆ[¢¯îðàÂæ¤ÉÈéªA»êÅàuÌlvÌl¶É§¿üë¤ÆµÈ¢ÌÍA±ÌâÃÉ©gƼlÆÌá¢ð©Âßél¨ÆµÄÝè³êÄ¢é©çÅ éB
yêÊUz
@23Ìlͼú̳·©ªÆͽΤÌÌTÉÈðæ½B24´µ©ó¢ÄÈ©Á½ÌÅB
@u25iajê³ñAÇ¢ÆêævibjƵÂèÌjÌqªûÌÔɵíðñ¹Ä¢ÓB
@u26iaj±±Í²´ñ·ævibjÆêÍwÌÔðºëµÈªçéÉ]½B
@u27½ÁÄ¢¢æv
@u28úÌ ½éÖéÆA¨ÂÞ ªÉÝÜ·æv
@u29iaj¢¢Â½çvibjÆqÍ°ëµ¢çðµÄêðÉçñ¾B
@u30iajê³ñvibjÆéÉçðñ¹ÄAuicj±ê©çËA¢ÜÅsñÅ·©çËB31áµrÅA¨O³ñ̨ÂÞ ÅàÉÝo·ÆAê³ñÍ{É«½¢Ê¢éñÅ·©çËB32ËA¢¢¾©çê³ñÌ]Óðm¢Ä¸ÕB33»êÉËA¢ÜÉúÌ ½çÈ¢û̪ ©çA³¤µ½ç¼®¢çµâ¢ËB34ðèܵÄHv
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| u©ªv | uÌlv | »Ì¼Ììl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | ||||||
| 23 | @ | @ | @ | @ | @ | 23 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 24 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 24 | @ |
| 25 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 25iaj | 25ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 26 | @ | @ | @ | @ | 26iaj | 26ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 27 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 27 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 28 | @ | @ | @ | @ | 28 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 29 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 29iaj | 29ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 30 | @ | @ | @ | @ | 30iaj icj |
30ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 31 | @ | @ | @ | @ | 31 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 32 | @ | @ | @ | @ | 32 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 33 | @ | @ | @ | @ | 33 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 34 | @ | @ | @ | @ | 34 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@±êÍAêÊUÉÈèuÌlvÆujÌqvƪâèÆèð試·Ìðu©ªvª©ÂßéÓÅ éB
@±±ÅÍAu©ªvÉ¢ÄÌus®`ÊvâuS`ÊvÈǪÝçêÈ¢BȺÈçA±ÌÓÍAñlÌeqÌâèÆèðA¼lÅ éu©ªvª©ÂßÄ¢éÌÝÅ èAu©ªvÍ»ÌeqÉͼÚÖ^µÄ¢È¢©çÅ éB
@±±ÅdvÈÌÍAâÍèuÌlvÆujÌqvÆÌÎäIÈ`©êûÅ éB25¶ujÌqªûÌÔɵíðñ¹Ä¢ÓvÌÉεÄAêeÅ éuÌlvÍ26¶uéÉv]¤BܽA29¶u°ëµ¢çðµÄvÉçÞujÌqvÉεÄAuÌlvÍA30¶uéÉçðñ¹ÄvJÉujÌqvð@·Bu©ªvÍñlÌâèÆèɼÚQÁµÄ͢ȢªA·ÅÉujÌqvÌóÛªu©ªvÉÆÁÄÛèIÈàÌÅ é±ÆªmF³êéBuÌlvujÌqv¼ÒÌ`©êûÍÎäIÅÍ éªA»ÌÎäIÈ`ÊÆ¢¤ÌÍA³½ÎÅÍÈujÌqvÌÈóÛªÛ§Âæ¤É`©êÄ¢éBÂÜèA»Ì¼ÒÌÎä«ÍA»ÌÈóÛðàÂujÌqvªAêeÅ éuÌlvðêµßéÆ¢¤ÎäÈÌÅ éB
@u35iajªÈñÄÉÈèâdȢ½çvibjÆqÍ®P^_µ]У½B36êÍßµ³¤Èçðµ½B
@u37¢éÌ˦v
@38iaj©ªÍËRA
@uibjÖ¨¢Åȳ¢vicjÆÌðêÚè ¯ÄAuidjÈçúªèܹñæviejÆ]½B
@39jÌqÍ}ÈáÅ©ªð©½B40çFÌ«¢AªÌ«ÌJ¢½AÈq¾Æv½B41©ªÍ¢âÈCªµ½B42qͨÆ@ÆÉÈðÂ߼B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| u©ªv | uÌlv | »Ì¼Ììl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | ||||||
| 35 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 35iaj | 35ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 36 | @ | @ | @ | @ | @ | 36 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 37 | @ | @ | @ | @ | 37 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 38 | @ | 38ibj idj |
38iaj icj iej |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 39 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 39 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 40 | @ | @ | @ | 40 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 41 | @ | @ | @ | 41 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 42 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 42 | @ | @ | @ | @ | @ |
@u©ªvÍA¢ÁÄ¢éuÌlvÌlqð©ÄAujÌqvÉÈð÷é±Æð\µoéB
@êqÉÆÁÄ»êÜÅæèí¹½æqÉ·¬È©Á½u©ªvªAÈð÷é±Æð\µoé±ÆÅAêqÆu©ªvÆâèÆèððí·æ¤ÉÈéB38¶uÖ¨¢Åȳ¢vÆAuËRvbµ©¯½u©ªvÉεÄAujÌqvÍu}ÈáÅv©ÂßÔ·Bu©ªvÍA»±Å41¶u©ªÍ¢âÈCªµ½vÆuS`Êv³êAujÌqvÌóÛª«¢±Æª¦³êéB±êÜÅêqÌlqð©Ä¢½¾¯¾Á½u©ªvÉÆÁÄAâèÆèððíµ½_ÅùÉujÌqvÌóÛª«¢Æ¢¤±ÆªAuS`ÊvƵÄÍÁ«èƦ³êéÌÅ éB
@u43Ü AǤà°êüèÜ·v44iajÌlÍßµ¢çÉÎð©×ÄAuibjê³ñAäçð]ÂÄA »±ðqØȳ¢vicjÆqÌwÉèðâÂÄûÖ·â¤É·éB
@u45¢çµâ¢v46©ªÍjÌqÌèðæÂÄ©ªÌTÉ¿ç¹½B47jÌqÍÈá«ÅX©ªÌçð©Ä½ªA¬µÄQOÌiFÉ©ü½B
@u48È齯A´ûΩè©Ä½ÜÖæAÎYkªÚÉüé©çv
@49iaj±ñÈð¢ÂÄàibjjÌqÍÔðdÈ¢B50âªÄYaɽB51iajÅ©ªÆüÐÂÄî½ñlª~è½ÌÅAibjÌlÍ×ÆêÉ´ÖÚ½B52×Æ¢ÂÄàAÌMºÜÆC~ïªê¾¯¾B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| u©ªv | uÌlv | »Ì¼Ììl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | ||||||
| 43 | @ | @ | @ | @ | 43 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 44 | @ | @ | @ | @ | 44ibj | 44iaj icj |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 45 | @ | 45 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 46 | @ | @ | 46 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 47 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 47 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 48 | @ | 48 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 49 | @ | @ | @ | @ | @ | 49iaj | @ | @ | @ | 49ibj | @ | @ | @ | @ | @ |
| 50 | 50âªÄYaɽB | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 51 | @ | @ | @ | @ | @ | 51iaj | @ | @ | 51ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 52 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 52 |
@±¢ÄAu©ªvÌ\µoÉεÄAuÌlvª£·±ÆÅujÌqvÍAÈðÚéB
@u©ªvÌ\µoÉεÄAuÌlvª44¶ußµ¢çÉÎð©×ÄvujÌqvðu©ªvÌÈÖÆ£·Bµ©µA£³ê½ujÌqvÍu©ªvÌeØ©ç̾Éà¨ðݳȢi49¶jBâÍè±±ÅàAu©ªvÉJÈuÌlvÉεÄAujÌqvÍuÔðdÈ¢vÆÎäIÉ`©êÄ¢éBÎä³¹é±ÆÅA³¤zÈujÌqvªAPÉqÇàÅ éÆ¢¤c³©çÌÔxÅÍÈAu©ªvÉÈóÛð^¦él¨ÆµÄ`©êÄ¢éÌÅ éB
@52¶u×Æ¢ÂÄàAÌMºÜÆC~ïªê¾¯¾vÆ¢¤uqÒ\»vÌuðßE]¿vÌqÉÈÁÄ¢éB±êÍAæÌ30¶icjÌuÌlv̾tâA±êÈ~Ì102¶ÌÚInªuÔvÅ é±ÆÆÖíÁÄ¢éqÅ ë¤Buê¾Á½vâuê¾vÆ¢Á½¶ÅÍÈAuqÒvÉu¾¯¾vÆ¢¤u]¿vªº³êéÌÍAu¢ÜÅsvAuÔvÜÅsÉà©©íç¸AרªuÌMºÜÆC~ïªêÂvµ©È¢©çÅ éB
@u53³Aê³ñA±¿çÖä¢Åȳ¢B54Ǥà 誽¤äÀ¢Üµ½v55Ìlͳ¤]ÂĨ«Vðµ½B56®¢½ÌÅ¡ÜÅæ°ÂĽԪáðoµÄ«oµ½B57iajêÍA
@uibjæµ^_vicjÆGÌãÅä·èȪçAidju``JA``JviejÆ â· â¤É]ÓªAifjÔÍ¥½è©ÖÂÄvXBu58iaj¨¨æµ^_vibjƯ¶â¤ÈðµÄA¡xÍAuicj¤ÜAã°æ¤vidjÆÐèÅMºÜ©çuÌIvðêÂoµÄâéB59»êÅàÔÍ«âÜÊB60iají«©çÍA
@uibjê³ñA ½¢ÉÍvicjƳàs½çµ¢çðµÄ]ÓB
@u61iaj©ªÅoµÄA¨ ªñȳ¢vibjÆ¢ÂÄê͹ðJ¯ÄûñðÜܹAÑÌÔ©çæ²ê½¦ÌnP`ðoµÄ©ªÌAÌÖ²ñŽçµAJ¢½¹ðBµ½B
@62iajjÌqÍMºÜÌÖèðüêÄTÂĽªA
@uibj¤¤ñA±êÀâÈ¢ÌvicjÆñðUéB
@u63»êÅÈ¢ÂÄAÇñÈÌHv
@u64ÊÌv
@u65ÊÌÍÈ¢B66 êÍÂÄȩ½Bv
@u67¢â¾ I@68iajÊÌÅÈ¿âA¢âvibjÆ@ºðo·B
@u69´ºÉhbvªüÂÄÜ·©çA»ê𨠪ñȳ¢B70ËA¢¢AhbvÅਢµ¢Ìæv
@71jÌqÍs³XX¤ÈÃB72êÍÐèÅ»êðoµÄqÌèÖl±Î©èA»êð̹½B
@u73iajàÂÆvibjÆjÌqª]ÓB74êÍXÉñ±«µ½B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| u©ªv | uÌlv | »Ì¼Ììl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | ||||||
| 53 | @ | @ | @ | @ | 53 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 54 | @ | @ | @ | @ | 54 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 55 | @ | @ | @ | @ | @ | 55 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 56 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 56 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 57 | @ | @ | @ | @ | 57ibj idj |
57iaj icj iej |
@ | @ | 57ifj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 58 | @ | @ | @ | @ | 58iaj icj |
58ibj idj |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 59 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 59 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 60 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 60ibj | 60iaj icj |
@ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 61 | @ | @ | @ | @ | 61iaj | 61ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 62 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 62ibj | 62iaj icj |
@ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 63 | @ | @ | @ | @ | 63 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 64 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 64 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 65 | @ | @ | @ | @ | 65 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 66 | @ | @ | @ | @ | 66 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 67 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 67 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 68 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 68iaj | 68ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 69 | @ | @ | @ | @ | 69 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 70 | @ | @ | @ | @ | 70 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 71 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 71 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 72 | @ | @ | @ | @ | @ | 72 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 73 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 73iaj | 73ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 74 | @ | @ | @ | @ | @ | 74 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@uÌlvÆø¢Ä¢½ÔñVªAÈðÚ®µ½½ßAÔñVª«oµÄµÜ¤B«~Ü·½ßuÌIvð^¦æ¤Æ·éÆAujÌqv๪ÞÆ¢¤êqÌâèÆèªWJ³êéB
@±ÌÓàAu©ªvÍêqð©ÂßéÏ@ÒÆÈèAêØÌus®`ÊvâuS`ÊvªÈÈéB57¶uÌlvª«oµ½uÔvÉu
@75ûÉ}«½ÔÍAê̯©ç¿½otÌùð¢ÀÂÄAdÉ»êðûÖüêæ¤Æ·éB
@u76iaj¢¯Ü¹ñvibjÆꪴ¬³ÈèðxÖéÆAicjÔÍûðJ¢ÄAçð´ûÖàÂÄsB77ºÌ®«É¬³¢ªñ©¦½B
@u78³A¤Ü^_v79iajGÌãÖ¿½uÌIvðçÌOÖo·ÆAibj [^_Æ]ÂĽÔÍÙÂÄAáÌÊðñ¹Äb©ÂßÄAùðúµÄ»êðæéB80»µÄ¬èÌÜÜûÖüêæ¤Æ·éB81´û³©ç^^_Ƶ ª½ê½B
@82ÌlÍÔðµQ¹Á¸ÉµÄAÒÌÔÖèðâÂÄ©½B83GêĽ絩½B
@u84¨Þ ðXÖܹ¤Ëv85iaj©¤Æ¾Ìâ¤É]ÂÄXÉjÌqÉA
@uibjê³ñAµ»±ðݵĸÕAÔ¿âñ̨Þ ðXÖéñÅ·©çv
@u86iaj¢â¾ÈA\\ê@³ñÍvibjÆjÌqÍicj¢â^_idjNÂB
@u87iajÖ¨|¯È³¢vibjÆ©ªÍÄÑOÉ|¯³¹½êðó¯Äâ½B
@u88°êüèÜ·AǤàCÞéµÄ¢èÜ·v89ÌlÍâµÎ½B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| u©ªv | uÌlv | »Ì¼Ììl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | ||||||
| 75 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 75 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 76 | @ | @ | @ | @ | 76iaj | 76ibj | @ | @ | 76icj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 77 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 77 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 78 | @ | @ | @ | @ | 78 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 79 | @ | @ | @ | @ | @ | 79iaj | @ | @ | 79ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 80 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 80 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 81 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 81 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 82 | @ | @ | @ | @ | @ | 82 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 83 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 83 | @ | @ |
| 84 | @ | @ | @ | @ | 84 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 85 | @ | @ | @ | @ | 85ibj | 85iaj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 86 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 86iaj |
86ibj idj |
86icj | @ | @ | @ | @ | @ |
| 87 | @ | 87iaj | 87ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 88 | @ | @ | @ | @ | 88 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 89 | @ | @ | @ | @ | @ | 89 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@ÔñV̨µßð·¦é½ßAÄÑu©ªvªujÌqvÉÈðó¯ÄâéB
@±ÌÓÅAu©ªvÍÄÑêqÌâèÆèÉÖíéB¾ªA87¶ÅuÖ¨|¯È³¢vÆujÌqvÉ\µoéÜÅÍAâÍèÏ@ÒÅ èAu©ªvÉ¢ÄÌuÎÛ\»vÍÈ¢BܽAññujÌqvÉÈðó¯ÄâéÌÍAññÆàuÌlvª¢Á½lqð©©ËÄÌs®Å éBµ©µA±ÌññÌu©ªvÌs®ÍA\®IÅDÓIÈs®ÅÍ é̾ªA»êÜÅÏ@ÒðÑÔxiêqÆâèÆè·éæ¤ÈAu©ªvÉ¢ÄÌuÎÛ\»vªÈ¢±ÆjâAèiuÌlvjª¢Á½Æ«¾¯Öíë¤ÆµÄ¢é±Æ©çAÏÉIÉÖíë¤Æ͵ĢȢB¯¶êÔÉæèí¹ÄA¢ÁÄ¢élq¾Á½©çÈðó¯½AÆ¢¤öx̱ÆÅ éB
@±±ÅÍA±êÜÅêqÌul¨`ÊvÍAukb`ÊvEus®`ÊvEuóÔ`ÊvªS¾Á½Bµ©µA86¶icju¢â^_vÍAujÌqvÌuS`Êvª³êéB±êÍAu©êé_ªÏ»·éÆ¢¤àÌÅÍÈAujÌqvÌOIÈlqi86¶iajÌukb`ÊvÌû²âAidjÌuNÂvlqÈÇj©çu©ªvªÇÝÆÁ½àÌÅ éB
@u90¨âA@̨«¢¹î à 鏤v
@u91iajäÆVιvibjÆÌlÍãðü¢Äï©ç£¢½¨µß ÆGê½ÌðïÞûÆðoµÈªçA
@uicj»êཱུ©ÉäÀ¢Ü·vidjÆ¢ÓB
@u92½ ©ç¨«¢ñÅ·©v
@u93¥Í¶ê«ÅäÀ¢Ü·ÌB94¨ãÒl̪ͥ]èåðð·é©ç¾ÆÂL¢Ü·ªA@â¨ÍeÉpÂÞè ª«¢ÌÍ»ñÈÅÍÈ¢©Æ¶¶Ü·v
@95|ÉÂü¯É]ª³ê½ÔÍIàȽ©ð©lßÄAè𮩵ÄA [^_ƺðoµÄî½B96iajÔàȨµß ðXÖAGê½ÌðnµÄêÍÔðø«ã°éÆA
@uibj 誽¤äÀ¢Üµ½ccTAê³ñAûÖ¢çµâ¢vicjÆ]½B
@u97iaj©ÜÐܹñAûÖ¨oÅȳ¢vibjÆ]½ªAicjjÌqÍÙÂħÂÄü¤¤Ö©¯éƼ®Öæè©©ÂÄOðȪßnß½B
@u98Ü A¸çÈv99ÌlÍCÌų¤Élð]½B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| u©ªv | uÌlv | »Ì¼Ììl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | ||||||
| 90 | @ | 90 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 91 | @ | @ | @ | @ | 91iaj icj |
91ibj idj |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 92 | @ | 92 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 93 | @ | @ | @ | @ | 93 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 94 | @ | @ | @ | @ | 94 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 95 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 95 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 96 | @ | @ | @ | @ | 96ibj | 96iaj icj |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 97 | @ | 97iaj | 97ibj | @ | @ | @ | @ | @ | 97icj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 98 | @ | @ | @ | @ | 98 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 99 | @ | @ | @ | @ | @ | 99 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@ÄÑujÌqvÉÈðä¸Á½u©ªvÍAÔñV̨µßð·¦Ä¢éÔuÌlvÆïbððí·B
@±±Åu©ªvÍAͶßÄïbçµ¢ïbðuÌlvÆðí·B¨µßðæè·¦½ ÆàAu©ªvÍ97¶u©ÜÐܹñAûÖ¨oÅȳ¢vƾ¤ªAujÌqvÍ»êɶȢB»êÉεÄuÌlvÍA99¶uCÌų¤Élð]v¤B±±ÅàAu©ªvÉÆÁÄAujÌqvÌÔxÍÇ¢àÌÆ;¦È¢B¾ªAâÍè»ÌóÛÌ«³ÍAujÌqvÌc³ÉæéàÌƵÄÅÍÈAujÌqv©gÌu©ªvÉηéÈóÛƵÄ`©êÄ¢éBuÌlvªuCÌų¤vÈÌÍAu©ªvÉÆÁÄujÌqvÌÔxª«¢Æ¢¤±Æð¦µÄ¢éÌÅ éB
@100iaj¬µÄ©ªÍA
@uibjǿ稢ÅÅ·©vicjÆu¢½B
@u101kC¹ÅäÀ¢Ü·B102ÔÆ©\·¾³¤ÅAåÏÄsÖȾ³¤Å·v
@u103½ÌÉÈÂÄÜ·©µçHv
@u104k©¾Æ©\µÜµ½v
@u105»èâåϾB106ÜúÍǤµÄàA©©èܹ¤v
@u107ʵÄQèܵÄàAêTÔ©©é³¤ÅäÀ¢Ü·v
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| u©ªv | uÌlv | »Ì¼Ììl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | ||||||
| 100 | @ | 100ibj | 100iaj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 101 | @ | @ | @ | @ | 101 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 102 | @ | @ | @ | @ | 102 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 103 | @ | 103 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 104 | @ | @ | @ | @ | 104 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 105 | @ | 105 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 106 | @ | 106 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 107 | @ | @ | @ | @ | 107 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@u©ªvÍÄÑuÌlvÉbµ©¯AêqÌÚInðuB
@±±ÅͶßÄu©ªvÍuÌlvÌÚInªuÔvÅ é±ÆðméB±±ÅÍAÙÚu©ªvÌukb`ÊvÆuÌlvÌukb`ÊvÌÝÅq³êéB±êÜÅA½Ñ½ÑÈðó¯½èAbµ©¯½è·é±ÆÅAu©ªvÍuÌlvÉεÄÖSðñ¹ÄÍ¢éBµ©µAu©ªvÌuS`ÊvªÈA»ÌïbÌàeàêÊIÈ¢ÔböxÌàeƾ¦éàÌÅ é±Æ©çAu©ªvÍ[¢Ó}àÈ¢ïbƵÄq³êÄ¢éBÂÜèAuÌlvÖÌÖSâ¯îðàÁÄ¢½ÆµÄàA»êÍ[å«¢àÌÅÍȢƢ¤±ÆÅ éB
@108DÔÍ¡AÔXcÌâÔêðo½B109ßÌX©çå̺ªÇЩ¯éâ¤É·¦éB110úÍü½B111¼¤ÌÛɽlXÍú¯ðJ¯½B112Áµ¢ªüéB113¡µª½AêÉø©ê½ÜÜ°ü½ÔÌê¡èÉѽ¶ÑªÉÌÌ¢ÄéB114ÔÌyJ¢½ûÌ ½èɪñOD¤é³òÑÜÍéB115êÍÀbƽ©lÖĽªAXèÌnP`ÅðÍç½B116¬µÄÌlÍ×ðÐñ¹A´ÖÔðQ©·ÆAMºÜ©ç[ðñOÆMðoµÄ«nß½B117¯êÇàMÍpXiÜȩ½B
@u118ê@³ñv119iajiFÉà}«Ä½ibjjÌqÍAËÞ³¤ÈáðµÄ]½B
@u120ÈÉHv
@u121ܾpXHv
@u122¦¦ApXÅ·©çËA¨ËÞÉȽçê@³ñßè©©ÂÄAËñË È³¢æv
@u123ËÞ©È¢v
@u124³¤AÀâA½©G{Åàäȳ¢Èv
@125jÌqÍÙÂÄñm¢½B126êÍïÌ©çlÜûÌG{ðoµÄâ½B127ÉâobNÈǪL½B128jÌqÍ_µA»êçÌG{ðêÂ^_©nß½B129´©ªÍAãÖßè©©ÂÄAºÚgÐðµÄ{ð©ÄéjÌqÌáÆAî£è¯¶ÚðµÄ[¢ÄéêÌáƪ»Âè¾Æ¢ÓÉS¢½B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| u©ªv | uÌlv | »Ì¼Ììl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | ||||||
| 108 | 108DÔÍiªjðo½B | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 109 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 109 | @ | @ | @ |
| 110 | 110úÍü½B | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 111 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 111 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 112 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 112 | @ | @ | @ |
| 113 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 113 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 114 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 114 | @ | @ | @ |
| 115 | @ | @ | @ | @ | @ | 115 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 116 | 116¬µÄ | @ | @ | @ | @ | 116 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 117 | @ | @ | @ | @ | @ | 117 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 118 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 118 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 119 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 119ibj | @ | 119iaj | @ | @ | @ | @ |
| 120 | @ | @ | @ | @ | 120 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 121 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 121 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 122 | @ | @ | @ | @ | 122 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 123 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 123 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 124 | @ | @ | @ | @ | 124 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 125 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 125 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 126 | @ | @ | @ | @ | @ | 126 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 127 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 127 | @ | @ |
| 128 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 128 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 129 | @ | @ | @ | 129 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@DÔÍiÝAúvÌÔð}¦éBæ¤â¿Â«nß½ñlÌqÇàÌlqð©ÈªçAuÌlvÍ[ð«nßéBujÌqvàAiFÉO«ÄG{ð©nßéB
@ÄÑAu©ªvÍêqð©ÂßéÏ@ÒÆÈéÆAqàu©ªvÉ¢ÄÌ`ÊÍÈÈéBujÌqvÆuÌlvÆÌ»ê¼êÌڪĢé±Æ©çAu©ªvÍqÇཿÌeðzµnßéB
@±ÌêÊUÅÍAu©ªvͽx©êq½¿ÆâèÆèðJèÔ·ªA¨¨ÞËÏ@ÒƵÄêqðÏ@µÄ¢éB¢ÁÄ¢élqð©ÄÍAujÌqvÉÈðó¯ÄâéªAêqAÁÉuÌlvÆu©ªvÆÌÖWÍAÁÊe§Æ¾¦éÙÇÌqÍÈ¢B¼ÌæqÉ¢ÄÌqªÈ¢±Æ©çAÏÉIɱÌOlÌêqðÏ@µÄ¢éÆ;¦éàÌÌAu©ªvÍêqÉÏÉIÉÖíë¤Æ͵ĢȢBÈóÛÌujÌqvÉ¢ç³êÄ¢éuÌlvðñx¯éƵÄàAËRƵÄu©ªvÍA©gƼlÆð¾mÉüø«·éæ¤ÈâÃÈÔxÅ éB
@»ÌÏ@ÒƵÄÌu©ªvÌóÛÉcéÌÍAuÌlvÖ̯îÅÍÈAÞµëujÌqvÖÌÈóÛÅ éBJÅAéÈû²Æ¢¤uÌlvÌ`©êûÉεÄAujÌqvÍAu©ªvÍIÆྦéÙÇ41¶u¢âÈCvªuS`Êv³êéBæÙÇàq×½æ¤ÉA±ÌujÌqvÍAqÇྩçÆ¢¤c³Éæéu©ªvÖ̳¤zÈÔxƵÄÅÍÈAu©ªvÉu¢âÈCvð^¦éÒƵÄ`©êÄ¢éB
@uÌlvÖÌÖSâAujÌqvuÔvÌÈóÛªAuÌlvÖÌ¢ÖSÆ[¢¯îÉÏíéÌÍAêÊVÈ~Å éB±¢ÄAêÊVÌl@ðsȤB
yêÊVz
@130©ªÍêeɺÍê½qð\\áÖÎdÔÅüнêÈÇÉ©éAæà±êç̽ÌÞàÈ¢jÆÆÌOÊÉ°ê½Â«ª¬³ÈêlÌçÈèAgÌ«ÈèÌàÉAµÂÆèƲa³êAêÂÉÈÂÄéà̾Æ]ÓÉÁ©³êéB131ÅAêÆqÆð©r×ÄAæÄéÆvÓB132ÉÆqÆð©r×Äî£èÄéÆvÓB133³¤µÄAÅãÉÆêÆð©r×ÄSÞÌÈ¢Ìð½ÆÈsvcÉvÓª éB
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||
| u©ªv | »Ì¼Ììl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | ||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | ||||||
| 130 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 130 | @ |
| 131 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 131 | @ |
| 132 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 132 | @ |
| 133 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 133 |
ujÌqvÆuÌlvÆÌڪĢé±Æ©çu©ªvÍAñlÌqÇàÌeðzµÍ¶ßéB
@»êÜÅÌu©ªvÌo±ðzNµAu©ªvÍñlÌqÇàÌeðzµÍ¶ßéB»Ì«Á©¯ÌqÍA·×ıêÜÅÌu©ªvÌo±Éîâ½uqÒ\»vÌuà¾vÆÈÁÄ¢éBêÊUÜÅÅAuÌlvÆujÌqvªÎäIÉ`©êA¼Òª³½ÎÆྦéóÛÉà©©íç¸AñlÌÚ³ªÄ¢é±Æð©µAsvcÈv¢ÉìçêéÌÅ éB
@134¡AðvÐoµÄA©ªÍêɶê½q©çA»Ìðz¹¸Éçêȩ½B135³¤µÄ´lÌ¡Ì^½ÜÅàz¹¸ÉçêÈ¢B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||
| u©ªv | »Ì¼Ììl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | ||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | ||||||
| 134 | @ | @ | @ | @ | 134 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 135 | @ | @ | @ | @ | 135 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@dÔÅÌo±ðv¢o·±ÆÉæÁÄAñlÌeqªÄ¢é±ÆÉCâ½u©ªvÍAeðzµ½¢Æ¢¤~ÉìçêéB134¶A135¶ÆàÉAu©ªvÌuS`Êv¾ªAuz¹¸Éçêȩ½vAuz¹¸ÉçêÈ¢vÆA¢Õ®ÉË«®©³êÄ¢é±ÆÉÚ³êéBu©ªvÉÆÁÄóÛÌ«¢ujÌqvÆAJÈÔxÌuÌlvÆÌÎäA³çÉkC¹ÌuÔvÜÅsÆ¢¤wiÆA»Ìe©çAu©ªvÍêqÆ»ÌeivjÉεĢÖSðàÁÄ¢éB»Ì¢ÖSªAuz¹¸ÉçêÈ¢vÆ¢¤uS`ÊvÆÈÁÄ¢éÌÅ éB
@136©ªÍÈãÝz©çÌlÌvÌçâlqð¼®ÉvÐ×éªo½B137©ªª³î½wZÉAÍ»êöáÍȩ½ªNͽµ©ÜÂZÂãÅAÈØÆ¢Óö¨Ø°ª ½B138©ªÍ´jð¯Ðoµ½B139ÞÍåðÆŠ½B140åððµÄÍ¢ÂàAå«Èð]ÂĽB141Á@Ì¢çðµ½Aå¿ÈjÅA×͵àµÈ©Â½B142ñOx±¯ÄæµÄA½¤Æ¤©ªÅÞwµÄ¹Â½ªAúIíãAãB»®ïÐÆ©¢ÓÌÌзƵÄA½©ÌV·Å´¼ð©½¬èA¡ÍǤµÄé©XÉÁ§ð·©È¢B
@143©ªÍs}jðzÐ×ÄA ñÈjÅÍÈ¢©µçÆv½B144RµÞÍå¾sêð·é¾¯ÅÊÉCZµ¢Æ¢ÓjÅÍȩ½B145½©õÅAwELÈ³Ö Â½B146ÞàA»ñÈ«¿Í ÄÉÈçʪ½¢B147@½ÉõÈjÅàxX̸sÉïÖÎCZµàÈéB148ACÉàÈéB149«½È¢ÆÌÅã¢ÈÖèU©µÄAôç©JÐðÍç·Æ]Óâ¤ÈlÔÉàÈéB
@150ÌqÌÍ»ñÈlÅÍÈ¢¾ç¤©B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||
| u©ªv | »Ì¼Ììl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | ||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | ||||||
| 136 | @ | @ | @ | @ | 136 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 137 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 137 | @ |
| 138 | @ | @ | @ | @ | 138 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 139 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 139 | @ |
| 140 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 140 | @ |
| 141 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 141 | @ |
| 142 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 142 | @ |
| 143 | @ | @ | @ | @ | 143 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 144 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 144 | @ |
| 145 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 145 | @ |
| 146 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 146 |
| 147 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 147 |
| 148 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 148 |
| 149 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 149 |
| 150 | @ | @ | @ | @ | 150 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@±±ÅÍA±êÜÅÌo±©çu©ªvÍeðzµnßéBïÌIÉuÈØvÆ¢¤ÅL¼ðoµÄAzðcçܹĢB
@136¶u¼®ÉvÐ×éªo½vA138¶u©ªÍ´jð¯Ðoµ½vA143¶u ñÈjÅÍÈ¢©µçÆv½vA150¶uÌqÌÍ»ñÈlÅÍÈ¢¾ç¤©vÆ¢¤¶ªAu©ªvÌuS`ÊvÉ ½éB±Ìøp·×ĪAu©ªvÌàÊÌ®«ðqµ½àÌÉÍá¢È¢ªA±ÌlÂ̶ª»ÌàʪuS`ÊvƵÄq³êÄ¢éÌÅ éB±êçÌuS`ÊvÍAeðl¦Ä¢ßöÌÔÉ}ü³êAuqÒ\»vÌuà¾vEuðßE]¿vÆAuS`ÊvªðÝÉq³êÄ¢B
@ïÌIÈ él¨ðzµA»Ìoððuà¾vµA143¶u ñÈjÅÍÈ¢©µçvÆv¤B¾ªA144¶uCZµ¢Æ¢ÓjÅÍȩ½v145¶u½©õÅAwELÈ³Ö Â½vÆl¦éBµ©µA»ÌuÈØvÆ¢¤jÌ«iàA146¶u»ñÈ«¿Í ÄÉÈçʪ½¢vÆuqÒ\»vÌuðßE]¿vÉæÁÄÛèµA147¶u@½ÉõÈjÅàxX̸sÉïÖÎCZµàÈévA148¶uACÉàÈévA149¶u«½È¢ÆÌÅã¢ÈÖèU©µÄAôç©JÐðÍç·Æ]Óâ¤ÈlÔÉàÈévÆzð©gÌÅmèIÈàÌƵÄuðßE]¿vÅ»fðºµÈªçA¨¦È¨µÄ¢B»µÄA150¶uÌqÌÍ»ñÈlÅÍÈ¢¾ç¤©vÆ¢¤_ÉéB
@±Ìæ¤ÉA±ÌzÍAêqÌOIÈlqâuÔvÉü©¤Æ¢¤îñ©çAeðzµA©gÌo±ÉîâĻÌ
@151ÌlÍâȪçàkÉÌPßÉä[ËFðµ½ÑðYÄéB152©ªÉÍA»êç©çAÌlÌ¥ÈOâA´ÌØâ©ÈpðvÐ×éªÅ«éB153XÉ´ãÌêJð³ÖlÖéªo½B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||
| u©ªv | »Ì¼Ììl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | ||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | ||||||
| 151 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 151 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 152 | @ | @ | @ | @ | 152 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 153 | @ | @ | @ | @ | 153 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@³çÉAuÌlvÌ©çA»êÜÅÌu©ªvÌzðâ·éB
@uÌlv̪uóÔ`Êv³êAu©ªvÌzªÄÑuS`Êv³êéBuS`Êv̶ªA152¶uÅ«évA153¶uo½vÆÈÁĨèAu©ªvÌÓ¯IÈuS`ÊvÅÍÈA©IÈàÊƵÄuS`Êv³êÄ¢éBu©ªvÌzÅ é͸ÌuÌlvÌf«ªsKÈvðàÁ½«ÆµÄAu©ªvÆÁÄmèIÈ
@êÊVÅÍAu©ªvÍujÌqvÆuÔvÆÌeðz·éB±ÌzÍAu©ªvªAêÊUÜÅÌuÌlvÌOIÈlqÆA©gÌßÌo±ÆðÆçµí¹½ãÅAzðcçܹĢßöªAuS`ÊvAuqÒ\»vÌuà¾v»µÄuðßE]¿vÅq³êÄ¢éB
@Ú³êé׫±ÆÍAâÍèA»êªu©ªvÌàÊÅ®³ê½zÅ èA»êªu©ªvÉÆÁÄAuÌlvÉ¢ÄÌmèIÈ
yêÊWz
@154DÔͬRð߬A¬àäð߬Aδð߬Äiñ¾B155ÌOÍQÃÈÂĽB
@156iajÌlªñ[ð«I½AibjjÌqªA
@uicjê@³ñAµÂ± vidjÆ]Ðoµ½B157qÔÉÍÖª¢ÄîÈ¢B
@u158वäoܹñ©Hv159iajêÍibjfµÄicju¢½B160jÌqÍûªðñ¹Ä¤ÈÃB
@161iajÌlÍAjÌqðøâ¤ÉµÄA ½èð©ôµ½ªibjÊÉlàÈ¢B
@u162iajवAÒÂÄlHvibjÆØèÉȾßéªAicjjÌqÍgÌðä·ÂÄAàçµ³¤¾Æ¢ÓB
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||
| u©ªv | uÌlv | »Ì¼Ììl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | ||||||
| 154 | 154DÔÍ iªj߬Äiñ¾B |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 155 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 155 | @ | @ | @ |
| 156 | @ | @ | @ | @ | @ | 156iaj | @ | 156icj | 156ibj idj |
@ | @ | @ | @ |
| 157 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 157 | @ |
| 158 | @ | @ | @ | @ | 158 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 159 | @ | @ | @ | @ | @ | 159iaj icj |
159ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 160 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 160 | @ | @ | @ | @ |
| 161 | @ | @ | @ | @ | @ | 161iaj | 161ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 162 | @ | @ | @ | @ | 162iaj | 162ibj | @ | @ | @ | 162icj | @ | @ | @ |
@
@øpÍAêÊWADÔÍuδvð߬Äiñ¾Æ±ëÅAujÌqvª¬Öðµ½¢Æi¦éÓÅ éB
@eivjÌzðI¦éÆAujÌqvª156¶uê@³ñA
@±±Åڷ׫qÍA159¶ibjufµÄvA161¶ibjuÊÉlàÈ¢vÆ¢¤qÅ éB±êçÍAuÌlvÌuS`ÊvÅ éBu©ªvÆ¢¤êlÌÉ_ªu©êÄ¢é½ßA±êçÌq¾¯ªuÌlvÌàÊÉ_ªu©êÄ¢éÆÍl¦ÉAuÌlvÌOIÈlqðu©ªvÌÆ禽à̪Aq³ê½ÌÅ ë¤Bµ©µA»êÜÅAêxàuÌlvÌuS`ÊvªÈ©Á½Éà©©íç¸A159¶ibjA161¶ibjªuS`Êv³êÄ¢é±ÆÍAâÍèdvÅ éB
@±êÍAêÊVɨ¢ÄAujÌqvÌeðzµ½±ÆÉæéàÌÅ éBu©ªvÍAuÌlvÌvÆAuÌlvÌ«öðz·é±ÆÅAuÌlvÉηéÖSƯîªÜÁ½½ßAuÌlvÌuS`Êvàq³ê½ÌÅ ë¤Bu©ªvªuÌlvÖÌÖSƯîðß½±ÆÉæÁÄAuÌlvÌOIÈlq¾¯ÅÍÈA»ÌàÊÜÅàÆç¦æ¤ÆµÄ¢éÌÅ éBujÌqvÖÌÈóÛÍA»ÌÜÜuÌlvÖ̯îÖÆÏíÁ½Æྦé¾ë¤B
@163iajÔàÈDÔÍÌ{É ¢½ªAibjÔ¶ÉuÆAicj´ÔÍÈ¢©çÉȳ¢AÆ¢ÓB164ÍFs{ŪªÌâÔð·éB
@165Fs{ÜÅAÇñÈÉêÍ¢ç³ê½ç¤B166´àÉ°ÂĽÔàáðoµ½B167iajêÍ»êÖûñðÜܹȪçAüA
@uibj़®Å·ævicjÆ¢Ó¾tðJèԵĽB168êÍ¡ÌvÉA¢ÀßçêsµÄÊ©Aᵶ«c½ɵÄàɽ©E³ê¸ÉÍÜ¢Æ]Óâ¤ÈlàNéB
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||
| u©ªv | uÌlv | »Ì¼Ììl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | ||||||
| 163 | 163iajiÌ{j | @ | @ | @ | @ | 163ibj | @ | @ | 163icj | 163iaj | @ | @ | @ |
| 164 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 164 | @ |
| 165 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 165 |
| 166 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 166 | @ | @ | @ | @ |
| 167 | @ | @ | @ | @ | 167ibj | 167iaj icj |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 168 | @ | @ | @ | 168 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@DÔÍêUuÌ{vÉ
·éªAuFs{vÜÅpð«·ÔÍȢƢ¤Bu©ªvÍAñlÌqÇàÉÂγÝÉÈÁ½uÌlvÌð\´·éB
@163¶ibjÌuÔ¶ÉuÆAvÆ éÌÍAuÌlvÌus®`ÊvÅ ë¤B165¶uFs{ÜÅAÇñÈÉêÍ¢ç³ê½ç¤BvÆuqÒ\»vÌuðßE]¿vª³êéB±êÍAuFs{vÜÅuÌlvª½xàu¬Öðµ½¢vƹªÞujÌqvÉεÀÛÉ¢Á½Æ¢¤±ÆÆAu©ªvª»êÉ[¢¯îðàÁ½Æ¢¤±Æª¦³êÄ¢éBËR¬Öªµ½¢Æ¾¢oµ½ujÌqvÉA¢fµÄ¢éuÌlvÉεÄA[¢¯îðà¿A168¶Ì\´ÜŸسêéÌÅ éB
@³çÉA±±ÅAu©ªvÍAuÌlvÌðv¢©×éB»ÌuS`ÊvªA168¶uêÍ¡ÌvÉA¢ÀßçêsµÄÊ©Aᵶ«c½ɵÄàɽ©E³ê¸ÉÍÜ¢Æ]Óâ¤ÈlàNévÆq³êÄ¢éBu¡ÌvvªuÌlvðêµßé¶ÝƵÄAùÉmèIÈÀÌæ¤Éu©ªvÍl¦Ä¢éÌÅ éBulàNévÆ¢¤¶ÉÈÁÄ¢é±Æ©çAu©ªvÉÆÁÄ©RÉv¢½Á½l¦ÆµÄq³êÄ¢é±ÆÉàÚ³êéBð\´³¹éÙÇAu©ªvÉÆÁÄuÌlvÌ«öÌzªAâÍèmèIÈ
@169âªÄAS[Eƹð½ÄÄADÔÍvbgtH[ÉY¤ÄâÔêÖü½B170iaj¢¾âçÊà©çA
@uibj³^_vicjÆjÌqÍO±²Ýɺ ð¨³Öéâ¤ÉµÄ¢ÓB
@u171³ As«Ü¹¤v172iajêÍGÌÔð|¯ÉºµAçðñ¹ÄAuibj_µÒÂÄĸÕævicjÆ¢ÐAXÉ©ªÉAuidj°êüèÜ·Aê¡©Äĸ«Ü·v
@u173iajæ¤äÀ¢Ü·vibjÆ©ªÍicjõidj]½B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||
| u©ªv | uÌlv | »Ì¼Ììl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | ||||||
| 169 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 169 | @ | @ | @ |
| 170 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 170ibj | 170ij icj |
@ | @ | @ | @ |
| 171 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 171 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 172 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 172ibj idj |
172iaj icj |
@ | @ | @ | @ |
| 173 | @ | 173iaj | 173ibj idj |
173icj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@
@uFs{vÌvbgtH[ÉDÔª
µAuÌlvÍu©ªvÉÔñVð©Ä¨æ¤ÉÞB
@±ÌÓÅAͶßÄuÌlvɦÍðÜêéƯÉA±êÜÅÏ@ÒÅ Á½u©ªvàܽAͶßÄÏÉIÉuÌlvɦͷéBuFs{vÅ~èéÉà©©íç¸u©ªvÍA173¶icjuõvuÌlvÌ\µoɶéBu©ªvÌuÌlvÖ̯îª[ÈÁÄ¢é±ÆðuS`Êv³êé±ÆŦµÄ¢éB
@174DÔÍâ½B175©ªÍ¼®àðJ¯½B176jÌqͺè½B
@u177iajN¿âñA_µµÄéñÅ·ævibjÆ´ð£êæ¤Æ·éwã©çAicjèð×ÄÔÍÎÌ¢½â¤É«oµ½B
@u178¢éí˦v179iajêÍibj꡽ß罪Aicjï©çAX^_Æ×¢A½ÌqÑðo·ÆAÔ̼Ìãü̺ðʵÄA¼®wͤƵ½ªAåÔ©çØÈÌnP`ðoµÄ©gÌÝñÖ©¯AèЯ¨ñÔɵÄAvbgtH[Öºè§Â½B180iaj©ªàã©çºèÄA
@uibjÀâ AÍźèÜ·©çvicjƢ½B181iajÌlÍÁ¢½â¤ÉA
@uibjÜ A³¤ÅäÀ¢Ü·©ccvicjÆ]½B182iaj»µÄA
@uibjFXA 誽¤äÀ¢Üµ½vicjÆÌlÍØɨ«Vðµ½B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||
| u©ªv | uÌlv | »Ì¼Ììl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | ||||||
| 174 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 174 | @ | @ | @ |
| 175 | @ | @ | 175 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 176 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 176 | @ | @ | @ | @ |
| 177 | @ | @ | @ | @ | 177iaj | 177ibj | @ | @ | 177icj | @ | @ | @ | @ |
| 178 | @ | @ | @ | @ | 178 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 179 | @ | @ | @ | @ | @ | 179iaj icj |
179ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 180 | @ | @ | 180ibj | 180iaj icj |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 181 | @ | @ | @ | @ | 181ibj | 181iaj icj |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 182 | @ | @ | @ | @ | 182ibj | 182iaj icj |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@DÔªÆÜèAêeªÈð£êæ¤Æ·éÆAÔñVÍ«oµÄµÜ¢AuÌlvÍAÔñVðø«©©¦éB
@uÌlvÌ\µoðuõvø«ó¯½u©ªvÍÏ@ÒÅÍÈA»ÌêqÉÏÉIÉ©©íë¤Æ·éB175¶u©ªÍ¼®àðJ¯½vÆ èAêqÉÏÉIɦ͵æ¤ÆµÄ¢é±Æð¦µÄ¢éBܽA179¶ibju꡽ßç½vÆAÄÑuÌlvÌuS`Êvª³êé±ÆÉæÁÄàAu©ªvÉÆÁÄÌuÌlvÆÌSIÈ£ªkÜÁÄ¢é±Æð¦µÄ¢éB
@»êªu©ªvÉÆÁÄÌSIÈ£ÌkÜèÅ é±ÆÍA181¶iajuÌlÍÁ¢½â¤ÉvÆ¢¤uÌlvÌÁ«ª¦µÄ¢éB±ÌwÅ~èé͸ÌlªAȺ©ªÌqÇàð©Ä¨±ÆÉõøµ½Ì©ÆuÌlvÍÁ¢½ÌÅ éBuÌlvªÁÙÇAu©ªvÍuÌlvÉ[¢¯îðæ¹Ä¢éÌÅ éB
@183iajl²ÝÌðÀñÅà«oµ½A
@uibj°ê¢èÜ·ªAǤ©[ðv184iaj©¤¢ÂÄù©ço³¤Æ·éªAibj½ÌѪ¹Å\ÉÈÂÄéÌÅAicjpXo¹È¢B185ÌlÍꡧ¿~½B
@u186iajê@³ñA½µÄñÌvibjÆjÌqªUè©ÖÂĶ¾çµ]½B
@u187ê¡AÒÂÄccv188ÌlÍèóðø¢ÄA³É¹ðÂë°æ¤Æ·éB189Íðüê½ÌÅA¨ÌªªAÔȽB190iaj´A©ªÍibjÝñÌnP`ªwÓqÉæê^_ÉÈÂÄAêų̂ÌɲÜÂÄéicjÌ𩽩çAidj¢AÙÂÄ»ê𼳤iejÆ´¨ÖèðGê½B191ÌlÍÁ¢Äçð°½B
@u192nP`ªAæêÄîÜ·©çccv193©¤]ÐȪ穪ÍçðæÝçß½B
@u194°êüèÜ·v195iajÌlÍibj©ªª»êð¼·ÔAicjabƵĽB
@196iaj©ªªÙÂĨ©çèðø¢½ÉAibjÌlÍuicj°êüèÜ·vidjÆJèÔµ½B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||
| u©ªv | uÌlv | »Ì¼Ììl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | ||||||
| 183 | @ | @ | @ | @ | 183ibj | 183iaj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 184 | @ | @ | @ | @ | @ | 184iaj icj |
@ | @ | @ | @ | @ | 184ibj | @ |
| 185 | @ | @ | @ | @ | @ | 185 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 186 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 186iaj | 186ibj | @ | @ | @ | @ |
| 187 | @ | @ | @ | @ | 187 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 188 | @ | @ | @ | @ | @ | 188 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 189 | @ | @ | @ | @ | @ | 189 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 190 | @ | @ | 190iaj icj iej |
190idj | @ | 190ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 191 | @ | @ | @ | @ | @ | 191 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 192 | @ | 192 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 193 | @ | @ | 193 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 194 | @ | @ | @ | @ | 194 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 195 | @ | @ | 195icj | @ | @ | 195(aj ibj |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 196 | @ | @ | 196iaj | @ | 196icj | 196ibj idj |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@±±ÍAêqOlÆAu©ªvªºÔµà«nßAuÌlvÍ[ðo·æ¤Éu©ªvÉÞÓÅ éB
@uÌlvÍA[ðo»¤Æ·é̾ªA184¶ibju½ÌѪ¹Å\ÉÈÂÄév½ßAo·±ÆªÅ«È¢B³Éo»¤Æµ½Æ«Au©ªvÍA190¶uÝñÌnP`ªwÓqÉæê^_ÉÈÂÄAêų̂ÌɲÜÂÄéÌ𩽩çA¢AÙÂÄ»ê𼳤ƴ¨ÖèðGêvéB[¢¯îðñ¹Ä¢½u©ªvÍAuÌlvÌêµÞlqð©Äu¢vGêĵܤB»Ìu©ªvÌs®ªuÌlvÉÆÁÄsÓÅ Á½±ÆÍA±191¶uÁ¢Äçð°½vÆ¢¤us®`Êv³êÄ¢é±Æª¦µÄ¢éB
@u©ªvÍAuÌlvÉ[¢¯îðø¢Ä¢½½ßAu¢vuÌlv̨ÉGêæ¤Æ·éB193¶ÅuçðæÝçß½vÆ é±Æ©çA±Ìs®ÍAÓ}µ½àÌÅÍÈAܳÉu¢vÅ èu©ªvÌuÌlvÉηé¯îªví¸s®É çíêĵÜÁ½Æ¢¤±ÆÅ éB
@êÊVÅeðz·é±ÆÅuÌlvÖÌÜÁ½ÖSÆA¯îªA¢ÁÄ¢éuÌlvÉηéu©ªvàÓ}µÈ¢s®ÖÆu¢vìè§ÄçêÄ¢B¾ªAu©ªvÉÆÁÄAuÌlvÖÌÖSƯîªÅàå«[ÈéÌÍA±ÌÓÅÍÈ¢B
@197áXÍAvbgtH[ÅA¼à·©¸A·©ê๸ÉAÊê½B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||
| u©ªv | uÌlv | »Ì¼Ììl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | ||||||
| 197 | @ | @ | 197 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@±Ìê¶ÅAͶßÄu©ªvÆOlÌêqª¯¶uáXvÆ¢¤êèÌåêÉæÁÄq³êéBµ§É¾¦ÎA±ÌuáXvÆ¢¤ÄÌÉÍA»ÌêÉ¢éujÌqvEuÔvÆ¢¤ñlÌqÇàÍÜÜêĨç¸AuÌlvÆu©ªvÆðêèÉÄ̵½àÌÅ ë¤Bu©ªÍAccÌlÆÊê½BvÆq³êÄàA¶ÆµÄÍÈñçáa´ÌÈ¢ÓÅ éÉà©©íç¸AuáXvÆêèÉÄ̳êéÌÍAu©ªvÉÆÁÄÌuÌlvÆÌSIÈ£ªßâ½½ßɼÈçÈ¢B
@ܽdvȱÆÍAuÊê½vÆ èAu©ªvÆêqOlªÊêéÛÉuáXvÆÈÁÄ¢é_Å éBuáXvÆ¢¤êèÌåêÅq³êéÌÍAu©ªvÉÆÁÄÌAuÌlvÆÌSIÈ£ªêÔßÃ̪A±ÌÊêéÛ¾©çÈÌÅ éBu©ªvÍuÌlvÉεÄA¢ÖSÆ[¢¯îðàÁÄ¢é½ßAuÌlvÆÊêéÛÉAuáXvÆ¢¤êèÅq³êéÙÇSIÈ£ªßÃÌÅ éBȺÈçu©ªvÉÆÁÄAuÌlvÍAuêÍ¡ÌvÉA¢ÀßçêsµÄÊ©Aᵶ«c½ɵÄàɽ©E³ê¸ÉÍÜ¢vÆ¢¤ßsÈ^½ðwÁ½«¾©çÅ éBu©ªvÍÊê½ ÆÌuÌlvÌsðĶĢéÌÅ éBu©ªvÉÆÁÄAuÌlvƨIÉêÔßÃÌͨÌnJ`𼻤Ʒ龪ASIÉêÔßÃÌÍA±ÌÊêÌÛÈÌÅ éB
@êÊVÅAñlÌqÇàÌeÆuÌlvÌ«öðzµ½±ÆÉæèAêÊWÅÍu©ªvÍuÌlvÉ[¢¯îðæ¹AêqÉÏÉIɦ͵æ¤Æ·éBu©ªvÍuÌlvÌ¢f·élqðÝÄA³¦\´·éBuFs{vÌwÅèðo¹È¢Å¢éuÌlvð©©Ë½u©ªvÍAu¢v¨ÉGêĵܤB»µÄu©ªvÍAuÌlvÌ^½ðv¢Í¹ÈªçAÊêéÌÅ éB
yêÊXz
@198©ªÍ[ð½ÜÜâÔêÌüèûÖ½B199´ÉÌ|Xgª|ÂÄ Â½B200©ªÍ[ðÇñÅ©½¢â¤ÈCªµ½B201ÇñÅà·xÖȢƢÓâ¤ÈCൽB
@202iaj©ªÍê¡À½ªAibjÖæéÆA¼¶ðãɵÄAêûêð°üê½B203üêéƼ®à¤êxoµÄ©½¢Æ¢Óâ¤ÈCൽB204½µëA°Þ¿çèÆ©½¼¶Í¤ÉÅAêÂÍAêÂÍj¼Å ½B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||
| u©ªv | »Ì¼Ììl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | ||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | ||||||
| 198 | @ | @ | 198 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 199 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 199 | @ | @ |
| 200 | @ | @ | @ | @ | 200 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 201 | @ | @ | @ | @ | 201 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 202 | @ | @ | 202ibj | @ | 202iaj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 203 | @ | @ | @ | @ | 203 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 204 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 204 | @ | @ |
@@uÌlvçÆÊê½u©ªvÍAuFs{vÌ|XgÉÜê½[ð·é±ÆÅAwÔÜÅxÍIíéB
@u©ªvÍÜê½[ð200¶u©ªÍ[ðÇñÅ©½¢â¤ÈCªµ½vA201uÇñÅà·xÖȢƢÓâ¤ÈCൽvÆuS`Êv³êAÝé©ÝÜ¢©À¤Bu©ªvÍA±Ì[É»¡ð¦µÈªçAÇܸɵĵܤB±Ìu©ªvÌÀ¢ÍAȺŠ뤩BêÂÉÍA¬ÑKvi1985jÌwEÉ éæ¤Éu©ªvªzµ½±Æðóµ½ÈÁ½Æ¢¤±Æà ë¤BܽAäøÀ³üi1992jÅwE³êÄ¢éæ¤ÉA
»à»àu[vÆÍA¶ÊÌöJ³ê½ÈÅ éBÂÜè»êÍAíɼÌN©ÉÇÜêé±ÆªOñƳ꽮ÈÌÅ éB»ê¾¯ÉuÌlvªu©ªvÉð˵½ÌÍAu©ªvÉεêXÈÏÏðúҵĢ½©çÅÍÈAÞµë»Ìu[vª½Æ¦ÇÜê½ÆµÄà·µáèÌÈ¢AÊèêÕÌàÌÅ Á½©ç¾Æ¢ÁÄàæ¢B
iäøÀ³üi1992jueNXgÌóeƶ¬\\uÔÜÅvÆ¢¤qór\\v
w궤xæ92j
Æ¢¤Au[vÌ«¿©çÌÀ¢Åà ë¤B»êÉÁ¦ÄA½Æ¦·µÁ½îª©êÄ¢½ÆµÄàuÌlvªu©ªvÉõµ½Æ¢¤±ÆÅAu©ªvªuÇñÅà·xÖÈ¢vÆl¦½Ì©àµêÈ¢B
@¾ªdvÈÌÍA»¤µ½±ÆÅÍÈ¢Bu©ªvÍùÉuÌlvÆÊêĨèA©gÌúíiuúõvÖÌ·jÖßè éBuÌlvÖ[¢¯î±»øàÌÌAu©ªvÉÆÁÄÍAêAÌoÍâÍèu¢ÂàÊèvÌúíÌêR}É߬ȢBæÁÄu©ªvÍA¡GÅ ë¤Æ\z³êé±ÌêqÌîÉͧ¿üçÈ¢Bu©ªvÍùÉuÌlvÆ
@±Ìæ¤ÉAwÔÜÅxÍAu©ªvÌúíÌÅoïÁ½uÌlvÉ¢ÖSÆ[¢¯îðøìiÆÈÁÄ¢éB©é©çÉÈóÛÌujÌqvÉ¢ç³éuÌlvð©©ËAÈðó¯Ä¯½±ÆÅA»¡Æ¯î𦵻̯îÍeÌzðoé±ÆÅæè[¢àÌÉÈÁÄ¢Bµ©µAu©ªvÉÆÁĪ{IɼlÅ éuÌlvÉεĻÌsð\´³¹çêÂÂàAÊêéB¯îµÂÂàA»êÅàuÌlvÉ[Öíë¤ÆµÈ¢ÌÍAu©ªvªAæqðâÃÉ©Âßéu©ªvÉ Å¿³ê½A©gƼlÆð¾mÉæÊ·él¨Å é©çÅ éB
@uÌlvÉηéA»Ì[¢¯îÖÌßöÍAXÉå«ÈÁÄ¢ÌÅÍÈAêÊVɨ¯éñlÌqÇàÌeðz·é±Æð«ÉµÄAËRå«ÈéB é¢ÍAêÊUÅ`©êÄ¢½ujÌqvÖÌÈóÛªAuÌlvÖ̯îÖÆÏíéB±¤µ½u©ªvÌÏ»ÍAÇÌæ¤ÈqÌÁ¥ª é̾뤩BwÔÜÅxÉÍAqÉuS`ÊvðÜñ¾us®`ÊvÆ¢Á½AOßw½é©xÉÝç꽡«Ì éqÍFßçêÈ©Á½Bµ©µAw½é©xɤʷéqÌÁ¥ª éæ¤Å éBÅÍA»¤µ½qÌÁ¥É¢ijçÉl@ð[ßé±ÆÆ·éB
@æTÅÍAæSÅq̪ުÍÉæèl@µ½wÔÜÅxɨ¯éAÁ¥IÈqÉ¢Äl@ð[ßé±ÆÆ·éB
@wÔÜÅxÌåèÉAuÌlvÆAujÌqvðͶßÆ·é»Ì¼Ììl¨ÆªAÎäIÉAÎÆIÉ`©êÄ¢é±ÆÍAæSÅl@µ½Æ¨èÅ éB¾ªAÜÂÌêʲÆɪÍEl@µ½ÊA»ÌÎäÍA³½ÎÉÊuïçêéæ¤ÈàÌÅÍÈ¢ÆྦéBujÌqvâ»Ì¼Ììl¨ªu©ªvÉÈóÛð^¦êÎ^¦éÙÇAuÌlvÉÖSðà¿A[¯îµÄ¢Æ¢Á½àÌÅ Á½BܽAêÊUÅÍAujÌqvÆuÔvÌóÛªAu©ªvÉÆÁÄDܵȢàÌÅ Á½ªAuÌlvÖÌÖSE¯îÍ[å«¢àÌÅÍÈ¢±ÆàmFµ½Bu©ªvÍuÌlvÉÏÉIÉÖíë¤Æµ½ÌÅÍÈAuÌlvª¢ÁÄ¢éÉuÈð÷évÆ¢¤s®ÉoéÌÝÅ éB
@u35iajªÈñÄÉÈèâdȢ½çvibjÆqÍ®P^_µ]У½B36êÍßµ³¤Èçðµ½B
@u37¢éÌ˦v
@38iaj©ªÍËRA
@uibjÖ¨¢Åȳ¢vicjÆÌðêÚè ¯ÄAuidjÈçúªèܹñæviejÆ]½B
@39jÌqÍ}ÈáÅ©ªð©½B40çFÌ«¢AªÌ«ÌJ¢½AÈq¾Æv½B41©ªÍ¢âÈCªµ½B42qͨÆ@ÆÉÈðÂ߼B
@u84¨Þ ðXÖܹ¤Ëv85iaj©¤Æ¾Ìâ¤É]ÂÄXÉjÌqÉA
@uibjê³ñAµ»±ðݵĸÕAÔ¿âñ̨Þ ðXÖéñÅ·©çv
@u86iaj¢â¾ÈA\\ê@³ñÍvibjÆjÌqÍicj¢â^_idjNÂB
@u87iajÖ¨|¯È³¢vibjÆ©ªÍÄÑOÉ|¯³¹½êðó¯Äâ½B
@u88°êüèÜ·AǤàCÞéµÄ¢èÜ·v89ÌlÍâµÎ½B
@±Ìæ¤ÉAuÌlvÉεÄAu©ªvÍÁÊÈs®ÉoÄ¢éÆÜÅÍFßçêÈ¢BܽAuÌlvÆïbððí·ªA»êÍå«ÈÖSâ[¢¯îÆ¢Á½ÁÊÈàÌÅÍÈAÈð÷Á½±Æð«Á©¯Éµ½êÊIÈïbÅ éƾ¦éB
@100iaj¬µÄ©ªÍA
@uibjǿ稢ÅÅ·©vicjÆu¢½B
@u101kC¹ÅäÀ¢Ü·B102ÔÆ©\·¾³¤ÅAåÏÄsÖȾ³¤Å·v
@u103½ÌÉÈÂÄÜ·©µçHv
@u104k©¾Æ©\µÜµ½v
@u105»èâåϾB106ÜúÍǤµÄàA©©èܹ¤v
@u107ʵÄQèܵÄàAêTÔ©©é³¤ÅäÀ¢Ü·v
@µ©µA±Ìu©ªvÌÔxÍAêÊWÅÍuÌlvÉÏÉIÉÖíë¤Æ·éæ¤ÉÈéB
@170iaj¢¾âçÊà©çA
@uibj³^_vicjÆjÌqÍO±²Ýɺ ð¨³Öéâ¤ÉµÄ¢ÓB
@u171³ As«Ü¹¤v172iajêÍGÌÔð|¯ÉºµAçðñ¹ÄAuibj_µÒÂÄĸÕævicjÆ¢ÐAXÉ©ªÉAuidj°êüèÜ·Aê¡©Äĸ«Ü·v
@u173iajæ¤äÀ¢Ü·vibjÆ©ªÍicjõidj]½B
@174DÔÍâ½B175©ªÍ¼®àðJ¯½B176jÌqͺè½B
±Ìæ¤ÉuFs{vÅu©ªvàºÔ·éÉà©©íç¸AuõvÔñVÌÊ|ðø«ó¯½èAÏÉIÉu©ªÍ¼®àðJ¯v½è·éÌÅ éB»µÄAÊêéÛÉAuáXÍAvbgtH[ÅA¼à·©¸A·©ê๸ÉAÊê½BvÆ¢¤uÌlvÆu©ªvÆðuáXvÆ¢¤êÂÌÄÌÅêèɳêéÙÇAu©ªvÉÆÁÄÌuÌlvÆÌSIÈ£ªkÜéB
@±Ìæ¤ÉêÊUÆêÊWÆÌu©ªvÌuÌlvÖÌÖSÍA¾ç©Éᢪ éB±êÍAu©ªvªuÌlvÌvÅ èAujÌqvuÔvÌeðz·éêÊVÉæéàÌÅ é±ÆÍA·ÅÉæSÅl@µ½Æ¨èÅ éBµ©µA±ÌuÌlvÖÌÖSÆAujÌqvEuÔvÖÌóÛƪÎä³êÄ¢é±ÆÍAq©çྦé±ÆÅ éB»ÌÎäÍAåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêÉæéàÌÅ éBw½é©xÅàÝçê½æ¤ÉAuåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêvÆÍA`eA`e®AAAÌÈÇÌiðͶßƵ½AuqÒvÌåÏÉæé]¿ªtÁ³ê½Pê̱ÆÅ Á½B
@uÌlvÆAujÌqvuÔvÈǻ̼Ììl¨ÌÎä³êÄ¢éAÁ¥IÈåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêðÝÄ¢±ÆÉ·éB
yêÊTz
@6éªÂÂÄAüDûªJ©ê½B7lXÍêxÉÇæß«§Â½B8iajçõ̹ªÉ·¦o·B9üDûÌè Ö©ֽèרðûðcßÄøÂÏélâA{¬©çHÝoµÄ³ÉAÒç¤Æ·élâA»êðüêܢƷélâAibj¢ÂàÌÊè̬GÅ éB10¸ª}Èá«ÅüDlÌwã©çqÌêlXXð©ÄéB11iajðh¤¶Äo½lXÍvbgtH[ð¬èÉ}¢ÅAwvÌibjuæªó¢Ä¢Ü·Aæªó¢Ä¢Ü·vicjÆ©ÔÌà·©¸ÉAáêæ«ÆèZÈqÔÉü轪éB12iaj©ªÍêÔæÌqÔÉæéÂàèÅibj}¢¾B
iºüøpÒBȺ¯¶j
@êÊTAuãìvwżÌæqðKÚÉAu©ªv¾¯ª¬Gð©zµÄêÔOÌÔ¼Éæèà¤Æ·éÓÅ éB
@ºüªAåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêÅ éB9¶u³ÉvA10¶u}Èá«ÅvA11¶uü轪évÆ¢Á½qªAu©ªÍêÔæÌqÔÉæéÂàèvÅ é±ÆÆAÎä³êÄ¢éB±Ì7¶©çÌÓS̪A 究߬Gð©zµÄuêÔæÌqÔvÉæèà¤ÆµÄ¢éu©ªvÆA»Ì¼Ìuáêæ«ÆèZÈqÔÉü轪évÆ¢¤æqƪÎä³êÄ¢éB¾ªA±êçÌåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêÉæÁÄAæèFZ»ÌÎäªÆç¦çêéæ¤Éq³êÄ¢é±ÆªÁ¥IÅ éB
@±ÌêÊTÅÍAuÌlvÍܾ»êĢȢ½ßAuÌlvÉ¢ÄÌ`ÊÆÎä³êÄ¢éÓÅÍÈ¢Bµ©µAu©ªvªÇ¤¢¤l¨Å é©AÆ¢¤ÝèƵÄdvÈÓÅ éB¼ÌæqÆÍá¤AÆ¢¤Ó¯ðàÁ½u©ªvÍAsKÅ ë¤uÌlvɯîðøÒƵÄAêÊTÅùÉÝè³êÄ¢éÌÅ éB
yêÊUz
@u25iajê³ñAÇ¢ÆêævibjƵÂèÌjÌqªûÌÔɵíðñ¹Ä¢ÓB
@u26iaj±±Í²´ñ·ævibjÆêÍwÌÔðºëµÈªçéÉ]½B
@u27½ÁÄ¢¢æv
@u28úÌ ½éÖéÆA¨ÂÞ ªÉÝÜ·æv
@u29iaj¢¢Â½çvibjÆqÍ°ëµ¢çðµÄêðÉçñ¾B
@u30iajê³ñvibjÆéÉçðñ¹ÄAuicj±ê©çËA¢ÜÅsñÅ·©çËB31áµrÅA¨O³ñ̨ÂÞ ÅàÉÝo·ÆAê³ñÍ{É«½¢Ê¢éñÅ·©çËB32ËA¢¢¾©çê³ñÌ]Óðm¢Ä¸ÕB33»êÉËA¢ÜÉúÌ ½çÈ¢û̪ ©çA³¤µ½ç¼®¢çµâ¢ËB34ðèܵÄHv
@u35iajªÈñÄÉÈèâdȢ½çvibjÆqÍ®P^_µ]У½B36êÍßµ³¤Èçðµ½B
@u37¢éÌ˦v
@êÊUAñlÌqÇàðÂêÄ«½uÌlvÍú̽éêÉÀéB»µÄujÌqvÆïbððíµÄ¢éA»Ìlqðu©ªvÍ©Ä¢éÆ¢¤ÓÅ éB
@±ÌÓÍAu©ªvªÍ¶ßÄêqÌâèÆèð©éƱëÅ éBÎÊÅ éuÌlvÆujÌqvƪùÉÎä³êÄ¢éB25¶uûÌÔɵíðñ¹Ä¢ÓvujÌqvÉεÄAuÌlvÍuéÉv¾¤i26¶jB¾ªAujÌqvÍA29¶u°ëµ¢çvÅêeðÉçÞB»êÅàêeÍ29¶uéÉvA»µÄu±ê©çËA¢ÜÅsñÅ·©çËBccvÆc¢qÇàÉJÉྵĢéi30`34¶jB¾ªA»êÅà35¶u®P^_µv¾¢£éB»ÌæÈÈÔxÉuÌlvÍ36¶ußµ³¤Èv\îð·éBÎÊÅ éÉà©©íç¸AùɼÒÌóÛÍÎäIÉ`©êÄ¢éBÁÉujÌqvÍAIÆྦéÙÇu°ëµ¢vAu®P^_µvÆóÛ«`©êÄ¢éBeqÍu©ªvÌuÎÛ\»vÅÍÈ¢ªAu©ªvÌåÏIÈ]¿ðàÁÄq³êÄ¢éÌÅ éB
@ȺÉAêÊUɨ¯éA±êçÌÁ¥IÈåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêðÜÞqðêɵÄÝéÆAÌæ¤ÉÈéB
| ¶Ô | ]¿³êé ÎÛ |
]¿«ð àÁ½Pê |
q |
|---|---|---|---|
| 26 | uÌlv | uéÉv | u±±Í²´ñ·ævÆêÍwÌÔðºëµÈªçéÉ]½B |
| 29 | ujÌqv | u°ëµ¢çv | u¢¢Â½çvÆqÍ°ëµ¢çðµÄêðÉçñ¾B |
| 30 | uÌlv | uéÉv | uê³ñvÆéÉçðñ¹ÄAu±ê©çËA¢ÜÅsñÅ·©çËBcc |
| 35 | ujÌqv | u®P^_µv | uªÈñÄÉÈèâdȢ½çvÆqÍ®P^_µ]У½B |
| 36 | uÌlv | ußµ³¤Èv | êÍßµ³¤Èçðµ½B |
| 39 | ujÌqv | u}ÈáÅv | jÌqÍ}ÈáÅ©ªð©½B |
| 40 | ujÌqv | uÈqv | çFÌ«¢AªÌ«ÌJ¢½AÈq¾Æv½B |
| 41 | ujÌqv | u¢âÈCv | ©ªÍ¢âÈCªµ½B |
| 44 | uÌlv | ußµ¢çÉv | @ÌlÍßµ¢çÉÎð©×ÄAuê³ñAäçð]ÂÄA »±ðqØȳ¢vÆqÌwÉèðâÂÄûÖ·â¤É·éB |
| 47 | ujÌqv | uÈá«Åv | jÌqÍÈá«ÅX©ªÌçð©Ä½ªA¬µÄQOÌiFÉ©ü½B |
| 57 | uÌlv | u â·â¤Év | @êÍA uæµ^_vÆGÌãÅä·èȪçAu``JA``JvÆ â·â¤É]ÓªAÔÍ¥½è©ÖÂÄvXB |
| uÔv | uvXv | ||
| 60 | ujÌqv | u³às½çµ¢v | @í«©çÍA uê³ñA ½¢ÉÍvƳàs½çµ¢çðµÄ]ÓB |
| 71 | ujÌqv | us³XXv | jÌqÍs³XX¤ÈÃB |
| 86 | ujÌqv | u¢â^_v | @u¢â¾ÈA\\ê@³ñÍvÆjÌqÍ¢â^_NÂB |
| 89 | uÌlv | uâµv | ÌlÍâµÎ½B |
| 99 | uÌlv | uCÌų¤Év | ÌlÍCÌų¤Élð]½B |
@\̶[©çAu¶ÔvAu]¿³êéÎÛvAu]¿«ðàÁ½PêvAuqvƵ½Bu¶ÔvÆÍAåÏIÈ]¿«ðàÁ½qÌPêªÝçêé¶Ì¶ÔÅ éBu]¿³êéÎÛvÆÍAåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêÉæÁÄA]¿³êéÎÛðw·Bu]¿«ðàÁ½PêvÆÍAåÏIÈ]¿«ðàÁ½Pêð²«oµÄ°½BuqvÆÍA»ÌåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêªÝçêéqÌê¶ð²«oµÄ¢éBÎäµâ·¢æ¤ÉuÌlvÉηéàÌÌÝÔ|¯ðµ½B
@±Ìæ¤ÉAêÊUɨ¢ÄÍAuÌlvÉηé]¿æèàAujÌqvuÔvÉηéÛèIÈ]¿«ðàÁ½Pꪽ¢Æ¾¦éBÌlvÉεÄÍA]¿ÅÍÈußµ³¤Èvußµ¢vAuâµ¢vAuCÌų¤ÉvÈÇÆ¢Á½A´îðµÊÁ½à̪½¢BêûAujÌqvEuÔvÍAu°ëµ¢vAu}ÈvAuÈvÆ¢Á½]¿ðº·æ¤ÈPꪽ¢B±êçÌ]¿«Ì¿Ìá¢àAPÉóÛÌD«ÅÍÈA¯îðñ¹éèƵÄÌuÌlvÆA»ÌuÌlvðÇ¢lßéÒƵÄÌujÌqvEuÔvÆ¢¤·Ùª çíêÄ¢éB
@ܽAêÊUɨ¯éu©ªvÌuS`ÊvÍAȺÌO¶ÌÝÅ éB
| 40¶ | çFÌ«¢AªÌ«ÌJ¢½AÈq¾Æv½B |
| 41¶ | ©ªÍ¢âÈCªµ½B |
| 129¶ | ´©ªÍAãÖßè©©ÂÄAºÚgÐðµÄ{ð©ÄéjÌqÌáÆAî£è¯¶ÚðµÄ[¢ÄéêÌáƪ»Âè¾Æ¢ÓÉS¢½B |
êÊUÅÍAu©ªvÌuS`ÊvðÜÞqÍAêZµ¶AO¶µ©È¢ÌÅ éBÅ éÉà©©íç¸A±êçÌÁ¥IÈ]¿«ðàÁ½qÍA½¢Æ¾¦é¾ë¤Bµ©àA»ÌOÂÌuS`Êv̤¿AñÂÌuS`ÊvªAujÌqvÉεÄÌóÛªAåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêðÜñÅ¢éBujÌqvÌÈóÛªAuS`ÊvÉæÁľmɦ³êéÌÅ éB
@u©ªvÌuS`ÊvÍÙÆñÇÝçêÈ¢ãíèÉA±ÌåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêðÜñ¾qÉæÁÄAuÌlvÆujÌqvEuÔvÆðÎäIÉ`©êÄ¢éB»Ì½ßAuÌlvÖÌÖS̳ÆA»êÈãÉA}ÈCɳ¹éujÌqvÌóÛÌ«³Æ¢¤u©ªvÉÆÁÄÌA¼ÒÌóÛÌᢪ¾mÆÈéÌÅ éBuÌlvÆAujÌqvEuÔvÆÌu©ªvÉÆÁÄÌóÛÌá¢ðÆç¦é½ßÉÍA±êçÌåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêªdvÈÌÅ éB
@±¢ÄAêÊUÈ~ɨ¢ÄA±êçåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêðÜÞqªÇÌæ¤ÉÏ»·éÌ©A é¢ÍµÈ¢Ì©ðÝÄ¢B
@êÊVÍu©ªvÉæéeÌzÌêÊÅ é½ßAêqðÎä·éæ¤È`ÊÍ©çêÈ¢BêÊWɨ¯éÁ¥IÈqðl@·éB
yêÊWz
180iaj©ªàã©çºèÄA
@uibjÀâ AÍźèÜ·©çvicjƢ½B181iajÌlÍÁ¢½â¤ÉA
@uibjÜ A³¤ÅäÀ¢Ü·©ccvicjÆ]½B182iaj»µÄA
@uibjFXA 誽¤äÀ¢Üµ½vicjÆÌlÍØɨ«Vðµ½B
@183iajl²ÝÌðÀñÅà«oµ½A
@uibj°ê¢èÜ·ªAǤ©[ðv184iaj©¤¢ÂÄù©ço³¤Æ·éªAibj½ÌѪ¹Å\ÉÈÂÄéÌÅAicjpXo¹È¢B185ÌlÍꡧ¿~½B
@u186iajê@³ñA½µÄñÌvibjÆjÌqªUè©ÖÂĶ¾çµ]½B
@êÊWAu©ªvÌÚInÅ éuFs{vÉDÔª
·éBuÌlvÍA¬Ö𵽢Ƣ¤ujÌqv̽ßÉêºÔ·é±ÆÉÈèAêqOlÆÆàÉAu©ªvàºÔ·éÆ¢¤ÓÅ éB
@u©ªvÉηéçð¾¤uÌlvÌus®`ÊvÌÉA182¶uØÉvÆ¢¤uÌlvÉηéåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêªÜÜêÄ¢éBDÔŢĢ½u[vðo»¤ÆµÄo¹È¢Å¢éuÌlvÉü©ÁÄA¬ÖðäµÄ¢éujÌqvÍ186¶u¶¾çµvbµ©¯éB±Ìu¶¾çµvÆ¢¤qªAåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêÅ éBâÍèêÊWÅàAêÊUƯ¶æ¤ÉA¼ÒðÎäIÉ`½ßÉA±êçÌåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêðÜñ¾us®`ÊvªÝçêéB¾ªAêÊWɨ¯éAåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêÍA±ÌñÂÌÝÅ éBæÁÄAêÊUÙǼÒðÎä³êÄ͢ȢBµ©µAêÊWÅڷ׫±ÆÍAåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêðÜñ¾qª¸Á½Æ¢¤±Æ¾¯ÅÍÈAêÊWÅÍuÌlvÌuS`ÊvªÝçêéÆ¢¤±ÆÆÌÖAɨ¢ÄÅ éB
@êÊUÅÍAuÌlvÉ¢ÄuS`ÊvÍÈ©Á½Bµ©µAêÊWÉÈéÆAuÌlvÌuS`ÊvªÝçêéÌÅ éB
@156iajÌlªñ[ð«I½AibjjÌqªA
@uicjê@³ñAµÂ± vidjÆ]Ðoµ½B157qÔÉÍÖª¢ÄîÈ¢B
@u158वäoܹñ©Hv159iajêÍibjfµÄicju¢½B160jÌqÍûªðñ¹Ä¤ÈÃB
@161iajÌlÍAjÌqðøâ¤ÉµÄA ½èð©ôµ½ªibjÊÉlàÈ¢B
@u162iajवAÒÂÄlHvibjÆØèÉȾßéªAicjjÌqÍgÌðä·ÂÄAàçµ³¤¾Æ¢ÓB
@u177iajN¿âñA_µµÄéñÅ·ævibjÆ´ð£êæ¤Æ·éwã©çAicjèð×ÄÔÍÎÌ¢½â¤É«oµ½B
u178¢éí˦v179iajêÍibj꡽ß罪Aicjï©çAX^_Æ×¢A½ÌqÑðo·ÆAÔ̼Ìãü̺ðʵÄA¼®wͤƵ½ªAåÔ©çØÈÌnP`ðoµÄ©gÌÝñÖ©¯AèЯ¨ñÔɵÄAvbgtH[Öºè§Â½B
@uÌlvÌàʪuS`Êv³êÄ¢éÌÍA159¶ufµÄvA161¶uÊÉlàÈ¢vA179¶u꡽ß罪vÆ¢¤OÂÅ éBæSÌl@ÅàGê½æ¤ÉA±êçÌuS`ÊvÍAuÌlvÌàÊÉ_ªu©êÄ¢é½ßÌàÌÅÍÈ¢B±êçÌuÌlvÉ¢ÄÌuS`ÊvÍAu©ªvªuÌlvÉεÄSIÈ£ðkßÄ¢é±Æð¦µÄ¢éB
@êÊWÅ}ÉuÌlvÌuS`Êvª³êéæ¤ÉÈé±ÆÆAåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêªêÊWÅÍÉ[ÉÈÈÁÄ¢é±ÆÆÍAÖA«ª éBæSÅàwEµ½æ¤ÉAuÌlvªuS`ÊvÅàÊÜÅ`ʳêéÌÍAu©ªvÉÆÁÄASIÈ£ªkÜÁ½±Æð¦µÄ¢éB»êÉÁ¦ÄAåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêªÈÈÁÄ¢éÆ¢¤±ÆàA¯lÉuÌlvÆÌSIÈ£ªkÜÁÄ¢éÆ¢¤±ÆÅ éB
@êÊUÅÍAèðÏ@µÄ¢½u©ªvÉÆÁÄAuÌlvÌ«öðêÊVÅïÌIÉz·é±ÆÉæÁÄA»êçÌzÍ
@ÈãÌæ¤ÉAwÔÜÅxÌåèðl¦æ¤Æ·éÆ«Au©ªvÌuS`Êv¾¯ðÆç¦æ¤ÆµÄàAu©ªvÌàÊðÆ禫é±ÆÍÅ«È¢BåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêðÜñ¾qðl@·é±ÆÅAu©ªvÌuÌlvÖÌÏ»ðÆç¦éĪ©èÆÈéÌÅ éB
@æUÅÍA±êÜÅÌwÔÜÅx̪ÍEl@ðÜÆßé±ÆÆ·éB
@æQÍæQßÅÍAOßɱ¢ÄAwÔÜÅxɨ¯é_ÌzÆq@ðĪ©èƵÄAwÔÜÅx̪ÍEl@ð··ßÄ«½B±êÜÅÌl@Êð¥Ü¦ÄAwÔÜÅxðÜÆßéÆȺÌæ¤ÉÈé¾ë¤B
@uãìv©çuFs{vÜÅsÂàèÅu©ªvÍA¢ÂàÊèRƵĢé¼Ìæqðð¯ÄADÔÉæèÞB¯¶êÔÉæèñÅ«½uÌlvÍAñlÌcqðAêÄ¢½BujÌqvÌÔxÉ¢Á½\îð©¹éuÌlvð©©ËAu©ªvÍ©gÌÈðujÌqvÉ÷ÁÄâéB·¯Î»ÌêqÍuÔvÜÅü©¤Æ¢¤B]èÉàóÛÌá¤uÌlvÆujÌqvÌÚ³ª»ÁèÅ é±ÆÉCâÄA»ÌêÅsÝÅ éeðz·éBâªÄAêqÍAujÌqvª¬Ö𵽢ƾ¢oµAuFs{vźԷé±ÆÉÈéBñlÌqÇàÉ¢f·élqðݽu©ªvÍAuÌlvÌÜÅàz·éBuFs{vÉ~è½uÌlvÍAu©ªvÉu[vð·éæ¤ÉÞªA¹³ÅøÁ©©èu[vðæèo¹È¢BßÌêÉCâ½u©ªvÍAÙÁÄuÌlv̨ÖGêéBu[vðó¯æÁ½u©ªvÍAÊê½ãAÀ¢Èªçààeð©¸ÉµÄµÜ¤B
@wÔÜÅxÌåèÍAu©ªvÌúíÅ©©¯½AKÈgÌãÌuÌlvÉεÄÖSE¯îðøAÆ¢Á½Æ±ëÅ ë¤B³¦zµÈªçàAuÌlvÉεÄÏÉIÈs®ðN±³È¢ÌÍAu©ªvÉÆÁÄ»êªuFs{vÜÅsÆ¢¤úíÅ é©çÅ éBu[vð©È¢ÌàA»Ì½ßÅ ë¤B
@ÉAwÔÜÅxÌ_ÌzÆq@ÌÁ¥É¢ÄAÜÆßĨB
@wÔÜÅxÍAu©ªvÆ¢¤êlÌÉæéêl̬àÅ éBu©ªvÌ©·«µA̱µ½àeªAuãìvw©çuFs{vÜÅÌDÔÌbðSƵÄ`©êÄ¢éBu©êé_àAu©ªvêlÅ éB¼Ììl¨ÉàuS`ÊvªÝçêéªA»êçÍSÄAêlÌu©ªvªèÌàÊðµÊÁ½àÌÅ èA_Íu©ªvÉu©êéB
@u©ªvª¢©ÉuÌlvÉεÄÖSE¯îðø©AÆ¢¤¨êÅ éÉà©©íç¸A¼ÚIÉuS`Êvͳê¸ÉAÏ@·éÎÛ\\uÌlvAujÌqvAuÔvA»Ì¼Ìæq\\ð©Âßé±ÆÅA©gÌàÊð`«o»¤Æ·éBìi`ªÉ ½éêÊTÅAu¢ÂàÊè̬GvÆ]¿·é±Æ©çAu©ªvÍDÔÉæÁÄÚ®·é±ÆÉñúí«ð´¶éæ¤Èl¨ÅÍÈAúíIÉDÔðÚ®èiƵÄpµÄ¢él¨ÆµÄ©Ñãªç¹éB
@½¾Ï@ÒƵÄÌÝAuÌlvÆAujÌqvEuÔvÆÌóÛÌá¢ðq·é¾¯Å Á½u©ªvÌÔxªAuÌlvÖÌ¢ÖSE[¢¯îÆÏíéÌÍAeðz·éÆ¢¤êÊVÉÈÁÄ©çÅ éBêÊVÅÍAu©ªvÌßÌFðv¢o·±ÆÅAuÌlv̱êÜÅ̶¢§¿ÆA»ÌvÉ¢ÄïÌIÉun¢v³êéBêl̬àÅ èAu©ªvêlÉ_ªu©êé±Æà èA±ÌzÍu©ªvÉÆÁÄÀÆÈÁÄ¢B
@êÊWÅÍAeÌzÅuÌlvÌ«öªâ®³êé±ÆÉæÁÄAu©ªvÍêqÉÏÉIÉÖ^µnßéB»êÜÅÌåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêðÜñ¾qÉæÁÄu]¿v³êÄ¢½uÌlvÉεÄA»ÌàÊðuS`Êv³êéÙÇÉASIÈ£ðßïĢB»êÍuáXvÆ¢¤êèÌÄÌÜÅÚß·éB¾ªAu©ªvÉÆÁÄúíÅ éDÔÉæèí¹½uÌlvÉÍAu[vÌàeð©éÙÇÖ^µÈ¢ÌÅ éBuÌlvÉÌÝ»ÌÏ@ÌÚªü¯çêéÌÍAúíÉ¢éu©ªvÉÆÁÄAuÌlvEujÌqvEuÔvÆ¢¤êqOlªÏ@·×«ÙÇñúíÅ Á½ªÌÅ ë¤BêqOlÈOÌæqÍAu©ªvÉÆÁÄPÈéúíÉ߬ȩÁ½ÌÅ éB
@ÈãÌæ¤ÉAwÔÜÅxɨ¢ÄÍAu©ªvÌàÊâAuÌlvÌ`«ûªÏíé±ÆÅAuÌlvÖÌu©ªvÌÖSE¯îð`«o·Æ¢¤_ÌzÌÁ¥ªÝçêéBêl̬àÅA_ªu©êéìl¨ªu©ªv¾¯Å é±Æðl¦êÎAwÔÜÅxɨ¯é_ÌzÍPÈàÌÆ¢¦æ¤Bµ©µAwÔÜÅxÆ¢¤ìiÉÍA»ÌåèðìiƵĬ§³¹é½ßÉAu©ªvÌàÊÌÇ̪ð`©A é¢ÍÇÌæ¤É`©AÆ¢¤¡GÈ_ÌzÉæÁĺx¦³êÄ¢éÌÅ éB
@wÔÜÅxɨ¯éq@ÌÁ¥ÍAu©ªvÌàÊÌ`©êûÅ éBuÌlvÖÌAu©ªvÌSIÈ£ÌÚßðAuS`Êv¾¯ÅÍÈAuÌlvEujÌqvEuÔvÈÇÌìl¨ÉηéóÛÌ·ÙÉæÁÄà`©êéBSÄÌ`ÊÍA_ªu©êÄ¢éu©ªvÉæéàÌÅ éÈãA½ç©Ìàʪ½f³ê½qÅ é±ÆÍA¬àêÊÉà éÁ¥Å ë¤Bµ©µAwÔÜÅxɨ¢ÄÍAåèâ\¬ðl¦é¤¦ÅAÆÉdvÈqƵÄ
Ú³êéÌÅ éB»ÌqÆÍAåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêðÓÞqÅ éB±ÌqÉæÁÄAu©ªvÌàʪ`©ê½uS`ÊvªÈ¢Éà©©íç¸AuÌlvÖÌÖSE¯îª[ÈÁÄ¢ßöª`o³êéÌÅ éB
@ܽAuÌlvÖÌÖSE¯îð¦·àÌƵÄAuÌlvÌuS`Êvª³êéÆ¢¤Ï»àAu©ªvÌàÊÌÏ»ÉæéàÌÅ Á½BèÌSÌàÜÅàAÆçêçêéÙÇAu©ªvÉÆÁÄÌuÌlvÆÌSIÈ£ªßÃÌÅ éB±Ìæ¤ÉwÔÜÅxɨ¢ÄÌq@ÌÁ¥ÍAàÊð¼ÚIÉ`¢½uS`Êv¾¯ÅÍÈA½ðÇÌæ¤É©é©AÆ¢¤u©ªvÌ©éÎÛÌÆ禩½ðàu©ªvÌàÊðl¦é¤¦ÅÌdvÈĪ©èÆÈéÆ¢¤àÌÅ éB
@ÈãÌæ¤ÉwÔÜÅxɨ¯é_ÌzÆq@ðĪ©èɵÄAwÔÜÅxÉ¢Äl@ð¨±ÈÁÄ«½BæRßÅÍAwäxÉ¢Ä̪ÍEl@ð¨±È¤±ÆÉ·éB
@OßÌìiªÍƯlÉAܸæPÅÍwäxÉ¢ÄÌæs¤ð®·éBÈ~ÅA{Å®µ½æs¤ð¥Ü¦ÄAïÌIȪÍEl@ð¨±È¤±ÆÉ·éB
@gìªîi1989juuê¼Æwäxðß®éK\\¶wÖÌðú^¶w©çÌðú\\viwwpxæ461989N3jÅÍAܸìiÌSIÈìl¨Å éuFOYvÉ¢ÄAȺÌæ¤ÉÆç¦È¨µðÝÄ¢éB
±Ìl¨`ÛðuElC¿vÆ©u_o¿vÆ¢Á½A»±Åvlªâ~µÄµÜ¤æ¤ÈC¿IÈ]¿ÅÁÄÍÈçÈ¢B®SðúµÄdÉü©¢Aê_ÌñÌÅ¿ÌÈ¢»Ì®àøȬAÉ©È̯ê«ðmFµAìÑðo¦él¨ÆµÄÆç¦ÄÝæ¤B
iºüÍøpÒBȺ¯¶B
gìªîi1989juuê¼Æwäxðß®éK
\\¶wÖÌðú^¶w©çÌðú\\vwwpxæ46j
±Ìæ¤ÉAuFOYvÌuáÌ¢v«iðAPÉuElC¿vÆ¢Á½«iÅÍÈAdð±È·±ÆÉu©È̯ê«ðmFµAìÑðo¦él¨vƵÄAñÊ«Ì él¨Å é±ÆðmF·éB»ÌãÅwäx{¶ÌA
@ÉßÃÉÂê Äqª½Ä ñŽB¯½½Üµ¢ÉqËÌJ¯ÂÄâAÑöÌø«¸éÌäéñ¾«ÊÌ£¢½â¤È¿ªsȽ_oÉÍs^_GéB
@iwäx{¶ÌøpÍwuê¼ÆSWæ1ªxiâgX1998N12jÉæÁ½B
@Ⱥ¯¶Bj
Æ¢¤ÓðøpµAÌæ¤ÉwE·éB
±±É©çêégÌ´oÌgåÍA{êÂÅ é͸̸_^g̪auóÔÉ é±ÆðÓ¡·éBÓ¯ÍSIÈ´«óÔðL°AÙlɤ¬Ü³êAgÌÍÇxzÌÜÜÈçÊ٨ƵÄaO³êÄ¢BgÌ©çV£µ½Ó¯ªÆç¦é´oÍ©¦ÁÄúíÌ̱æèà¶XµgÌ«ð½fµA»±ÉÍð¸Á½Ó¯ÌöóÔð»o·é̾B
igìªîi1989jj
±Ìæ¤ÉྵAu¸_vÆugÌvƪuauóÔvÉ×ÁÄ¢uFOYvÌàÊðÆç¦Ä¢éB»µÄ±ÌuauóÔvªÉÀÜÅBµ½Æ«AuFOYvÍuáÒv̶½ðDÁĵܤ̾Ƣ¤B»µÄAwäxÆ¢¤ìiÌåèÉ¢ÄÌæ¤ÉÜÆßéB
iªj±Ì¬àª¸_^gÌƵÄÌ©Èӯ̡ðåèIÉ\¬µ½±Æªí©ÁÄéB·Èí¿¸_^gÌÌ}§IêÌãɬè§ÁÄ¢½©È¯ê«Ìë@Æ»ÌÊÄÉN«½gÌ»ÌàÌÌÉIaOÆ¢¤¨êBnÚÌIèÉ éqÄÌ^®Íâ~µ½rÆ¢¤êèèÉæéê¶àA±êª»ÀÌOI¢EðÆ禽ÌÅÍÈAFOYÌӯɦµ½»Û¢EðÆçê½àÌÅ é±Æð¦µÄ¢éÆ[¾³êæ¤B
igìªîi1989jj
@³çÉAwäxÌlÌÆA_ªÇ±Éu©êéÌ©Æ¢Á½âèÉ¢ÄÍAÌæ¤É¾y·éB
@¬àÌ\»ÉÓµÄÝéÈçA`ªÆöÌêèèÉæéà¾Iqð̼ÙÆñÇFOYÌSA´oAzɦµ½`Å_ªÝè³êÄ¢é±Æªí©éBµ©àqFOYrÆ¢¤OlÌð͸µÄêlÌÌqrÉϦ½ÆµÄàA¶@ãAs©RÉ©¦éÌÍÓÉ߬ȢBܳÉÇÒÍFOYÌSI̱ð½Çè¼·æ¤ÈÍð´¶Ä¢BÕ§¿ÌVÔéßöª©RÉ[¾³êéä¦ñÅ éBqrÌ_A·Èí¿±Ì¬àeNXgð·éìÒÌ´«Ì_ɵ½ªÁÄq³ê½±ÆÉÈéB
igìªîi1989jj
±Ìæ¤ÉAwäxS̪AuFOYv̨êÅ èA»êÍuìÒÌ´«Ì_vÉ]ÁÄq³ê½¨êÅ éÆ·éB³çÉA±ÌlÌÆ_ªÇ±Éu©êéÌ©AÆ¢¤âèÍAwäxÌÅãÌÓɧÚÉÖíéàÌƵÄAÌæ¤ÉྷéB
@¬àÌÅãAFOYÌ_ð£êÄÄÑêèèªoêµAqüÆè¾¾¯ªOû©çâââ©Éõið߼rÆÔB±Ìq¾rðʵÄÌü±»A^Àð©ÂßéÜÈ´µÆ¢¤tBNVð¨êéB»ÌqÏ«ÌgUè̺Åл©É²³êéÌÍAOEÆÚGµ½´o̶Xµ¢®«Å èAgÌ«ð[Öíç¹½´«Ì_È̾BgUèÍgUèÌÜÜÅ èAFOYÌ`ÛàAElÆ¢¤_IÈ`[tà»±ÅÍâèÉÈçÈ¢BÉà©©íç¸ÅIIÉñ¦³êéÌÍA çäé_ðÝèɵÄAElÉÜÅ¢½é±¤µ½SgÌ´oðAlÔÉÍXɵı¤µ½sÈÔªN±éÆ¢ÁÄÜÆßĵܤqqÏ«rÈÌÅ éB»±É éÌÍÕ«Ìçðµ½âλ³ê½åÏɼÈçÈ¢B
igìªîi1989jj
ìið÷ßéÅãÌê¶AuüÆè¾¾¯ªOû©çââ©Éõið߼BvÆ¢¤qªA»êÜÅuFOYvÌàÊÉu©ê½_ªAuFOYv©ç£êAuqÏ«vðàÁ½u¾vÉu©êéB±Ì±ÆÉæÁÄAuåÏvÅ é͸Ìu´«Ì_vªuqÏ«vðàÁÄ¢é±ÆðuâλvµÄ¢éÆ¢¤ÌÅ éB
@räÏi2002juuê¼Æuäv_viw¶|Æá]xæ9ª6@2002N11jÅÍAuFOYvÉ¢ÄÌæ¤ÉÆç¦Ä¢éB
ÞÉÆÁÄÌ¿lÆÍA¢©Édð®àøɱȷ©\\Å Á½ë¤BVÑ๸Aº¢½à¹¸A½¾ElƵÄÌrÉASvChð©¯Ä¢½ÆvíêéB»Ìæ¤ÈÞÉÆÁÄAgplÌÑöÍA½¿lðÁ½jƵÄAFOYÉÆÁÄsõÌÎÛÅ Á½BdðÓ¯AVÑÉ^èAXÌàÜÅ©ßéBÂÜèAFOYÉÆÁÄó¯üêé±ÆÌÅ«ÊAÓÄAúAÆßÆ¢Á½A½¿lðA±Æ²ÆÁÄ¢½Ìªgpl̹ö¾Á½Ì¾B
iºüÍøpÒBȺ¯¶B
räÏi2002juuê¼Æuäv_vw¶|Æá]xæ9ª6j
gìi1989jƯ¶æ¤ÉAuFOYvͽ¾uáÌ¢v«iŠ龯ÅÈAuÞÉÆÁÄÌ¿lÆÍA¢©Édð®àøɱȷ©vÅ Á½Æ·éB»êÉεXðÇ¢o³êé¼OÌu¹övÌs®ÍAuFOYÉÆÁÄó¯üêé±ÆÌÅ«ÊAÓÄAúAÆßÆ¢Á½A½¿lðA±Æ²ÆÁÄ¢½vl¨Å é½ßAuFOYvÍu¹övðÇ¢oµ½ÌÅ éÆྷéB³çÉAuFOYvÉ¢ÄAÌæ¤ÉàwE·éB
\\PÈéÆß¾¯ÅÍÈ¢BFOYÉÍARÆÅÍ éªA©ÈÌ¿lÏÆÍíÈ¢àÌÉη齴ª Á½ÆvíêéBÞÉÍA©È©gÉη鵵¢¿lÓ¯ª èA»êÉ͸ê½àÌÍFßçêÈ¢B»±ÉElƵÄÌ·³àæųà éÌÅ éªAܽA»±ÉÍA¼ÌlÉÍÈ¢êO³à é̾B
iräÏi2002jj
±Ìæ¤ÉuFOYvðAu¼ÌlÉÍÈ¢êO³vâu©È©gÉη鵵¢¿lÓ¯vðà¿ÈªçAu©ÈÌ¿lÏÆÍíÈ¢àÌÉη齴vÆ¢¤uElƵÄÌ·³àæųvðàÁÄ¢él¨ÆµÄྷéB
@FOYÆAìÒuê¼ÆÆɤʷéàÌÍA¼ÒÌs®KͪAuCªvÉå«æÁÄ¢éƱëÉ éÆ¢¦é¾ë¤B±ÌuCªvÌõAsõÍAFOYÉÆÁÄ໤ŠÁ½B»µÄA±ÌuCªvÍA¢EÆηéÉAs¢´@ðàÁÄ¢½Æ¢íȯêÎÈçÈ¢B
iräÏi2002jj
@uFOYvÆìÒÅ éuuê¼ÆvÆ̤ʫðuCªvÉæéus®KÍvÉ éÆwEµAÌæ¤ÉwäxÌåèðྷéB
@µ©µA±Ììiɨ¢ÄuêÍA»ÌuCªvªÅàµÄÍÈçÈ¢±Æ\\³çÉÍȹĵܤ±Æ\\ÉÁĵܤßöð`¢½B¢íÎuCªvÉ©RÉÜ©¹Ä»fÉëé±ÆÌÈ©Á½ålöªA¢ÉÍAuCªvð©È©gªäÅ«¸A»êÉЫ¸çêÄElÜÅÁĵܤAuCªvÌskð`¢½Ì¾B
@Ðï©çÌíEðAÅàÁ½ålöªAuCªvÉæÁÄÐï©çAÅåÌíEðµÄµÜ¤A»Ìßöð`¢½BD«Ì»fªP«Ì»fÆÈè¾È¢Aµ©à©ÈŧäÅ«È¢A»Ìskð`¢½B
iräÏi2002jj
±Ìæ¤ÉAwäxðAuuê¼ÆvƤʫðàÂuFOYvªAuCªvÉæÁÄÐï©çElÆ¢¤uÅåÌíEvðµÄµÜ¤ßöð`¢½ìiÅ éÆ·éB»µÄA»ÌíEÆÍAuíÉlðíE³¹ñƵÄUfÌûð ¯ÄÒ¿ó¯Ä¢évàÌÅ èAuÙñÌ¿åÁƵ½íEªAèIÈ}CiXðlÉ^¦év±Æà éAƵÄA±ÌwäxªúíÉN±è¤éuíEvÅ éÆÌæ¤ÉAªÍµÄ¢éB
@FOYÌêÍAElÆ¢¤`ÅAi é¢ÍAƱã߸vÆ¢¤`ÅjÐï©çå«íEµÄµÜÁ½ªA¢ÌÍAíÉlðíE³¹ñƵÄUfÌûð ¯ÄÒ¿ó¯Ä¢éAÆ¢ÁÄàß¾ÅÍÈ¢BÙñÌ¿åÁƵ½íEªAèIÈ}CiXðlÉ^¦éÆ¢¤±Æª éB±ÌFOYÌêàAMª éÌÉAäðƤƵ½±Æ\\ßÍAqÌÌÇð¦®ë¤ÆÈÇÆÍÓ}µÄ͢ȩÁ½\\Æ¢¤Aí¸©ÈíEªAèIÈÊÉÁĵÜÁ½Ì¾B
iräÏi2002jj
@ÅãÉATäç¾i2003juuê¼Æuäv_\\qA`EÆ߬àr\\viwbìqåwåw@_W@¶w¶»¤Òxn§2003N3jÅÍA
m©ÉuävÉεÄFOYðSÉ`©êĨèAÁÉááðN±µCCµÄ¢éƱëâAÅãÌqðEµÄµÜ¤V[ÍÇÝèÉ[¢óÛð^¦éàÌÅ éB»Ì±Æ©çuävÉÍqÆ߬àrÆÌÄ̪³êé±ÆÉÈèAuê¶wɨ¢ÄuävÉͶÜéqÆ߬àrÌnÈéàÌà©o³êé±ÆÍAqÆßrÉ Ú·é±ÆÉÔð©¯é±ÆÉÈÁ½Æ¢¦éB
iTäç¾i2003juuê¼Æuäv_\\qA`EÆ߬àr\\v
wbìqåwåw@_W@¶w¶»¤Òxn§j
Æ]Ìwäx_ÉεÄâèñN·éB³çÉAwäxÅÍìl¨Éu©êé_ªÏíé±ÆðÌæ¤ÉwE·éB
êèèÌ_Í»ÌwñǪFOYÉu«·¦é±ÆªoéàÌÌA¨~âcÉoÌqÉdÈÁÄ¢é±Æà éB±Ìê³êĢȢêèûðÛèIɨ¦éÌÅÍÈA»¤¢Á½êèûª¦·ÌÍÞµëFOY¾¯ÉìiªÅ_»³êé±ÆÌÈ¢àÌÆ¢¦È¢¾ë¤©B
iºüÍøpÒBȺ¯¶B
Täç¾i2003jj
@»µÄ±Ìæ¤ÉAuÆ߬àvƳêéwäxÉ¢ÄAuFOYvÌElÖÌßö¾¯ÉÎ調È_É^âðñoµAÆ©Ì_ðWJ·éBTäi2003jÅÍAuFOYvÌuá̳vÆüèðæèÍÞlXÆÌÖWÉ¢ÄÌæ¤ÉwE·éB
FOYÍíÉááÅüÍÉèUçµÄ¢éí¯ÅÍÈAgplÉεÄæèA¨~ÉεÄÍÈÅ éÆ¢¤ßµ³©çááðN±µÍ·éªA»êàPÉááƾÁĵܦéàÌÅÍÈA»ÌÉÍæÌÔxà©çêéÌÅ éBܽAqÉεÄÍ¢ç«ȪçàA¤ã©çûÉÍo¹È¢Å¢éBæÁıÌæ¤ÈÖW«ÍA¼Ìoêl¨çÆÌÖWÉêêðN±·FOYðêûɾ¢¾ÄµÜ¦éàÌÅÍÈ¢BÞµëAFOYͼÒÆÌÖW«ÌŶݵĢél¨Æ¢¦éÌÅ éB
iTäç¾i2003jj
uFOYvÉ¢ÄAu¨~vÉεÄÍuæÌÔxvð©¹Ä¢éªA»êª¤ÌuqvÉηéÛÍA½Æ¦Õ§Á½ÆµÄàu¤ã©çûÉÍo¹È¢Å¢évÆ¢¤_ÉڵĢéB»µÄAu¼ÒÆÌÖW«ÌŶݵĢél¨vÅ éƵÄA½Æ¦uáÌ¢v«iÌuFOYvÅ Á½ÆµÄàAlÆÌÖíèðà½È¢l¨ÅÍÈ¢ÆྷéB»µÄAwäxÌÅãÌuüÆè¾¾¯ªOû©çââ©Éõið߼BvÆ¢¤qÉ¢ÄAÌæ¤É¾y·éB
µ©µAFOYªìiàɨ¢Ä¼ÒÆÌÖW«ÌŶݷéÆ¢¤±Æð¥Ü¦éA±Ì´îðº¢A[l»³ê½¾ðAFOYÉÆÁÄ̼ÒÆl¦é±ÆªoÈ¢¾ë¤©B
@»Ìæ¤È¾Ì¶Ý𦷼Òð¦·ÌªêèèÅ éBìiɨ¿¦êèÍÙÚFOYÉ_ð ÄĨèAöɼÌoêl¨Ì_ÉàñèY¤±ÆÍæÉq×½Bµ©µÅIIÉ;ÌFOYÌs×ðßéüðÅ¿¾¯éÌÅ éBÂÜèêèèÍAÇ¿ç©Æ¢¦ÎFOYñèÌ©ûð¦µÂÂàAÅãÉͼÒÉá·³êé¶ÝƵÄFOYÌpðÅ¿oµÄ¢éÌÅ éB±Ì©ÝÆྦéêèè±»ªA¼ÒÌÌFOYÌpð©Ñãªç¹A»ÀIóÔÆñúíÆ¢¤Ï¿IÈìióÔðq¢Å¢éB
iTäç¾i2003jj
u¾vÉ_ªu©êé±ÆðÈãÌæ¤ÉྷéBuFOYvÉu©êÄ¢½_ªAu¾vÉu©êé±ÆÉæÁÄA¨ÌÅ éu¾vðuFOYvð©Âßéu¼ÒvÅ éÆ¢¤ÌÅ éB»µÄTäi2003jÅÍAÌæ¤ÉwäxðÊuïéB
@µ©µAÅãÉê誦µÄê½ñúíIÈ¢EÉËRÌ@»ê½¾ÍAPÈé¼ÒÆÄ×È¢ÌÅÍÈ¢©Æàl¦éBà¿ëñuââ©vÈ´îðº¢ÂÂA¼ÒƵÄFOYÌEls×ðßéàÌÌAs×Ì¥ñðâ¤ÄÍ¢éí¯ÅÍÈ¢BÆÈéÆAFOYÌElÍÆßƵĬ§·éàÌŠ뤩BÆßÌ{Ì`ƵÄÍAƵ½ßÅ èAá@s×Æ¢¤æ¤ÈàÌÅ éBuävÍ»À¢EÉʸéæ¤ÈÝèð³êȪçàAÅIIÉͻ̻Àð£ê½ìi¢EÆÈÁÄ¢é±ÆͱêÜÅJèÔµGêÄ«½BÂÜè»Ìæ¤Èñ»ÀI¢EàÅAÐïIÉâíêé±ÆªÈ¢úÆ»³ê½ElÍÆßÆÍ¢¦È¢àÌÅAÞµëElªÆµ½ßƵĬ§·é±ÆÌÈ¢qA`EÆ߬àrƵÄÌuävÌpª©¦ÄéÌÅ éB
iTäç¾i2003jj
Rè³i1998juuê¼Æ_iñj\\
gÆ߬àhðß®ÁÄ\\viwåâqåw¶Ñxæ491998N3jÅuÆ߬àvƵÄÊuïçêÄ«½wäxðAElÆ¢¤uÆßvª¬§³êé±ÆÌÈ¢uA`EÆ߬àvƵÄÆç¦È¨µÄ¢éB
@ÈãÌæ¤ÉAæs¤ðÝÄ«½Bgìªîi1989jÅÍASIÈìl¨Å éuFOYvÉ¢ÄAu®SðúµÄdÉü©¢Aê_ÌñÌÅ¿ÌÈ¢»Ì®àøȬAÉ©È̯ê«ðmFµAìÑðo¦él¨vÆ¢¤ñÊ«Ì é«iðmFµA»ÌuFOYvÌu¸_^gÌÌ}§IêÌãɬè§ÁÄ¢½©È¯ê«Ìë@Æ»ÌÊÄÉN«½gÌ»ÌàÌÌÉIaOÆ¢¤¨êvÆ¢¤åèð±«o·BwäxÌÅãÅAu©êé_ª¨Å éu¾vÉÏíé±ÆÉ
ÚµAu çäé_ðÝèɵÄAElÉÜÅ¢½é±¤µ½SgÌ´oðAlÔÉÍXɵı¤µ½sÈÔªN±éÆ¢ÁÄÜÆßĵܤqqÏ«rvð©oµÄ¢½B
@ܽAräÏi2002jÍAuFOYvÉ¢ÄAuÞÉÆÁÄÌ¿lÆÍA¢©Édð®àøɱȷ©v¾Á½ÆµÄA»Ìu½¿lvÉÊu·é̪êOÉÇ¢oµÄµÜÁ½u¹övÅ Á½Æ·éBuê¼Æ©gÆA±ÌuFOYvªuCªvÉæéus®KÍvðàÂÆ·éB»µÄA»ÌuCªvðu©È©gªäÅ«¸A»êÉЫ¸çêÄElÜÅÁĵܤAuCªvÌskð`¢½Ì¾vÆwäxÌåèðྵĢ½B»ÌuuCªvÌskvÆ¢¤àÌÍAuÙñÌ¿åÁƵ½íEvð´öÆ·éÆàྷéB
@Täç¾i2003jÅÍwäxðA]ÜÅÌuÆ߬àvÆ¢¤Êut¯ÅÍÈAuA`EÆ߬àvƵÄÌÆç¦È¨µðݽàÌÅ Á½B»êÜÅu¼ÒÆÌÖW«ÌŶݵĢél¨vÅ Á½uFOYvªAElðƵĵܤB»Ìõiðʵ¾·ÅãÌu¾vÉ¢ÄAuFOYvÉÆÁÄÌu¼ÒvÆÊuïéBuFOYvÌSÌßöðǤ±Æªæs¤ÌÎÛÅ Á½ÌÉεA»¤ÅÍÈA±Ìu¾vÉ_ªÏíé±ÆÉ
Ú·éB»µÄA±Ìu¨vÅ éu¾vÖÌ_ÌÏ»ÍAuElªÆµ½ßƵĬ§·é±ÆÌÈ¢qA`EÆ߬àrvƵÄÌwäxÌåèð©o·B
@±Ìæ¤ÉAæs¤ÅÍAuFOYvªuáÒvðEµÄµÜ¤ÉéSÌßöðǢȪçAêûÅÍìiÌÅãÌu¾vÖ_ªÏíé±ÆªAìiÌåèð¾ç©É·éĪ©èƵÄÆè °çêÄ¢éB
@±êçÌwEð¥Ü¦ÄÌæQÅÍAq̪ÞÚðl¦éOiKƵÄAwäxÌ[TÆAêÊ\¬É¢Į·é±ÆÉ·éB
@±ÌæQÅÍAOßÜÅƯlÉAªÞªÍÌÚðl¦é½ßÉAܸwäxÌåܩȬêÆA»ÌêÊ\¬ðl¦éBæPÌæs¤ð¥Ü¦½¤¦ÅAwäxÌ[TðÜÆßéÆÌæ¤ÉÈë¤B
@áÌ¢ElC¿ÌuFOYvÍêOÉñlÌElðÇ¢oµÄµÜÁ½½ßAXÉÍèÈ¢ñlÌEl¾¯ÉÈÁĵÜÁÄ¢½BZµ¢·èÌúÉAuFOYvÍ×ÅQñŵܤBÕXµÈªçuFOYvÍQ°Å¡ÉÈÁÄ¢éiêÊTj
@uFOYvªQ°É¢éÔÉXÍæÉZµÈÁÄéBäðu¢ÅêÆA}¬ÌdªüéBQ°©ç»êð·¢Ä¢½uFOYvÍA̲ªßçÈ¢ªó¯ÄµÜ¤BX̽í¢ÌÈ¢bð·¢Ä¢é¤¿ÉACªª¿
¢Ä«½uFOYvÍAd̽ßÉN«ãªë¤Æ·éªA̲ÍܾßÁĨç¸ËÁµÄµÜ¤B»êð©½ÈÌu¨~vÍAdð·éƾ¤vÉÁBu¨~vÍAd¹ïðàÁı¢Æ¾¤uFOYv̾¤Æ¨èɵÄâéªAuFOYvÍ·®ÉÄÑQüÁĵܤBuFOYvªQÄ¢éÔÉA˵½qªäðó¯æÁÄAéBiêÊUj
@áðoܵ½uFOYvÍAuÑövɳÁ«u¢¾äªAu ÜèØêÈ¢vÆ¢¤±ÆÅßÁÄ«½±Æð°çêéBËR̲ªDêÈ¢uFOYv¾Á½ªAÄѯ¶äðQ°Åu¬nßéBuÎÅu¢¾ãAçuÅu²¤Æ·éÆAçuð~ßÄ¢½Bª²¯ÄµÜ¤B»±ÅuFOYvÍAu¨~vªÆßéÌà·©¸ÉAdêÉ~èÄ¢B~èéÆqÍNà¨ç¸Au¨~vÍX¶Ü¢ðµæ¤Æ¾¤ªAuFOYvÍuܾ¢vƽηéB»¤µÄAÄÑuFOYvÍäðu¬±¯éBiêÊVj
@uFOYvªäðu¢Å¢éÆAÂXÔÛÌXÖêlÌuáÒvªEðäÁÄêÆâÁÄéBuFOYvÍAu¨~vª~ßéÌà·©¸ÉAÔÍ÷ÌJÉ]µÄ¢éÓ¤ÌuáÒvÌEðäènßéBµ©µA̲ª«¢ÉÁ¦ÄA ÜèäêÈ¢äÅ é½ßv¤æ¤Éäé±ÆªÅ«È¢BÕXðåç¹éuFOYvÉ\í¸AuáÒvÆuÑövÍQüÁĵܤBu¨~vàÔqð âµÉdêðÍÈêéBÃâªïÞdêÅuFOYvÉäÌÀEªKêéB¶ÜêÄßÄqÌçð¯ĵÜÁ½uFOYvÍAuáÒvðäÅaè¯EµÄµÜ¤BElðƵĵÜÁ½uFOYvÍAlÌæ¤ÉÖqÉÀè±ÞAÆ¢¤õiðu¾vª¤Âµ¾·Æ¢¤`ÊÅIíéBiêÊWj
@T·êÎAwäxͱÌæ¤ÉÜÆßé±ÆªÅ«æ¤BÌ\ÍA»ÌêÊT`WÜÅÌêÊ\¬\Å éB¶ÔÍA{e̪ÉYtµÄ¢é¿Ìwäx{¶iì¬ÍcjÆεĢéB
| êÊÔ | ¶Ô | êÊ | êÊÌ[T |
|---|---|---|---|
| êÊT | 1`22 | uvÈO | @×ðø¢½uFOYvªQÄ¢éBElðÇ¢oµÄµÜÁ½±ÆÈÇA»êÜÅÌXÌóµB |
| êÊU | 23`78 | äðu®@ | @uFOYvÍACªªÇÈèqÌäðu®Bµ©µA·®ÉæJð´¶A°ÁĵܤBu¢¾rÌäðqªÁÄAéB8ÉêxHÆò̽ßÉN±³êéB |
| êÊV | 79`143 | äð¤®A | @uFOYvÍò̽ßÄÑ10߬ÉN±³êéBq©çÔÁÄ«½äðu®ªAÄѤ°¸ÉAdêÌ éyÔÉ~èACªªyÉÈÁ½½ßu¬Í¶ßéB |
| êÊW | 144`235 | áÒÌEäèÆEl | @uáÒvªXÉKêéB̲̫¢uFOYvÍAv¤æ¤Éäê¸ÉuáÒvÌôð¯ĵܢAuáÒvðäÅEµÄµÜ¤B |
@æs¤ÅàwE³êÄ¢½æ¤ÉA±ÌwäxÅÍAElC¿ÌuFOYvªAuáÒvðEµÄµÜ¤Æ¢¤ßöªAåèƧÚÉÖíÁÄ¢éB»ÌßöÆÍAuFOYvªÇÌæ¤ÉÕXðåç¹Ä¢©AÆ¢¤ßöÅ éB
@»êÍAlXÈàÌE±ÆÆuFOYvª²aµ«ê¸ÉuêêvðN±µÄ¢ßöÅà éB»±ÅA{eÅÍAuFOYvÌÓvɽµAÕXðåç¹Ä¢óµðuêêvÆÊ«ÅÄÔ±ÆÉ·éBuFOYvÍA̲ª«¢Éà©©íç¸Aäðu¢¾èAEðäÁ½èµÈ¯êÎÈçÈ¢±ÆÉæÁÄAÕXðåç¹Ä¢BܽAüèÌlXÆÌÓvaʪ®SÅÈ¢½ßA³çÉCªªÕ§ÁÄ¢B{eÅÍAlXÈàÌE±ÆÆAuFOYvƵµÄ¢±¤µ½óÔðêµÄAuêêvÆÄÔ±ÆÉ·éB»ÌuêêvðN±µÄ¢ßöð½Çé±ÆÉæÁÄAuFOYvªElÖìè§ÄçêÄ¢SÌßöðǤB
@ܽA±ÌwäxÆ¢¤ìiÉoê·éäÍAu³yÌRcvÆ¢¤qªu¢ÅÙµ¢Æ¿ñ¾uävê{¾¯Å éiȺA±Ìu³yÌRcvÌäÍÊ«ÅguävhƼÌìl¨Æ¯¶æ¤ÉÅL¼IÉ\L·éB»êÈOÌêÊIÈäðw·êÍAÊȵÌgähÆ\L·é±ÆÉ·éjBu²¤ÆµÄ«Éu°È¢ÌàAuáÒvÌEðäë¤Æ·éÌàAu³yÌRcvÌuävÈÌÅ éB»êÜÅä𵤱ÆÉ©¯Äͼl¾Á½Í¸ÌuFOYvªAê{Ìuävð§äÅ«ÈÈèAuFOYvÌÓvÆͳÖWÉuêêvð¤Ý¾µÄ¢ÌÅ éB±Ìuäv̧äsÂ\É×ÁÄ¢ßöàAElÖÌßöð½Ç餦ÅAdvÈĪ©èÆÈë¤BêûÅÍAElÖÆü©¤uFOYvÌàÊÌßöªADZÉiNÉj_ªu©êq³êĢ̩AÆ¢¤_Éà
Ú·éKvª éB
@»ÌÓ¡ÅAÅIIÉucêvÆaððʽ·w½é©xÆÍAÜÁ½á¤ðà¿ÈªçA»ÌàÊÉ
ڵȯêÎÈçȢƾ¤_ÅA¤Ê_à éBw½é©xEwÔÜÅxÅl¦Ä«½ªÍÚð¥Ü¦ÈªçAÌæ3Å»ÌïÌIȪÍÚðè·é±ÆÉ·éB
@wäxÉ¢ÄÌæs¤ÆêÊ\¬ð¥Ü¦AªÍÚðè·éByOi1986jâAæPßAQßÌw½é©xAwÔÜÅxű±ëݽªÍÚð¥Ü¦AÌæ¤ÉªÞÚðè·éBȨAw½é©xEwÔÜÅxƯlÉAÚÍÄlðJèÔµÄAìiɦ·éæ¤ÉµÄA[IÈèÉæÁľçê½àÌÅ éB
@SÄÌqÍAuqÒ\»vÆuÎÛ\»vÉñª³êéB
@uqÒ\»vÍAæèqÏIÅâ«à¾Ìquà¾vÆAuqÒvÌåÏIÈà¾ÌðßÆAåÏIÈ»fªÁíÁ½]¿ðêµ½uðßE]¿vÆÉ檷éB±êÍAwÔÜÅxƯlÉAuqÒ\»vªÊIɽAuà¾vÆuðßE]ßvÆ¢¤qÌ¿Ìá¢ð¾ç©É·é½ßÅ éB
@uÎÛ\»vÍAu¨`ÊvÆul¨`ÊvÆÉñª·éBwäxÅÍAuêÊÝèvÌqƵÄÅÍÈAu¨`ÊvâuqÒ\»vuà¾vɪ޳êéqÉæÁÄêÊðÝè³êÄ¢é©çÅ éB
@u¨`ÊvÍAu®Ô`ÊvÆuÃÔ`ÊvÆÉñª·éBu®Ô`ÊvÍA¨Ì®ÔIÈϻ⮫A®ìÆ¢Á½qÅ éBuÃÔ`ÊvÍA¨ÌÃÔIÈlqAóÔAÁ¥ÈÇÆ¢Á½qÅ éB
@ul¨`ÊvÍAìiÌSIÈìl¨Å éuFOYvðÊÂÉÆè ¦°Au»Ì¼Ììl¨vÆÎä³¹éB»ê¼êÌul¨`ÊvÍAukb`ÊvEus®`ÊvEuóÔ`ÊvEuS`ÊvÆ¢¤lÂ̺ÊÚðݯéBuFOYvÌÝAuS`ÊvÉw½é©xÌuM¾YvƯlÉAu´ovEuSîvEuvlvÆ¢¤ºÊÚðݯéBwäxɨ¢ÄàAuFOYvÌàʪÇÌæ¤Éq³êÄ¢é©AÆ¢¤âèªAåèƧÚÉ©©íÁÄ¢éÆl¦çêé½ßÅ éBu´ovÆÍAuFOYvÌÜ´ðSƵ½gÌ´oÉæéFm³ê½±Æª¦³êéqÅ éBuSîvÆÍAuFOYvÌÛIÅAñ¾êIÈSð`ʵ½qÅ éBuCªvÉÖ·é`ÊÍ·×ÄuSîvÅêµ½B±êÍA̲̫³ÉæéCªÌ«³ª`ʳê½àÌÅ éÌ©Adð¤Ü±È¹È¢±Æ©çéCªÌ«³ª`ʳê½àÌÈÌ©AæÊ·é̪ﵢ½ßÅ éBܽA±ÌñÂÌCªÌ«³ÍAuFOYvÉÆÁÄÊXÌàÌƵÄÅÍÈAêÌÆÈÁ½àÌÅ éB±êð³ÉæʵĵܤÆA¼ÒÉ©©íéCªÌ«³ðÆç¦é±ÆªïµÈéBæÁÄAuSîvƵÄê·é±Æɵ½BuvlvÆÍAuFOYvÌïÌIA¾êIÈl¦ª`ʳê½qÅ éB
@Èã̪ÍÚðÓð«ÉÜÆßéÆÌæ¤ÉÈéBiájƵ½àÌÍAwäx{¶É¨¯éA»ÌÚÌqÌïÌáÅ éB¶ÔAªÔÍYtµ½¿Ì{¶Æ¯lÌàÌÅ éiì¬ÍûücjBºüª éàÌÍA»ÌºüÌݪ»ÌqÅ éiºüÍûücjBrÍOµÄAT_Í´¶ÌÜÜÅ éB
| uqÒ\»vc | uqÒvɦµ½åÏIÈ\»B |
| uà¾vcccc | uqÒvÉæéæèqÏIÈâ«à¾Ìuà¾vÌqB iáj4FOYÍ´ÈOAN±»êÂñÂÈã¾Â½ªA¹ö⡾öƤÉ̬mŠ½ÌðAOÌ媴äÌrOÉêñÅêlºÉzµA©ªÍ¼®BµÄXðø«nµ½ÌÅ éB |
| uðßE]¿vc | uqÒvÉæéæèåÏIÅ]¿ªÁíÁ½uðßvAu]¿vÌqB iáj7äðgÓÉ©¯ÄÍFOYÍÀɼl¾Â½B |
| @ | @ |
| uÎÛ\»vcc | q³êé±Æªçɦµ½AæèqÏIÈ\»B |
| ukb`Êvcc | ¼Úb@ÉæÁIJ«o³ê½eìl¨ÌïbÌ`ÊB iáju27³yÌRcÅ·ªAUßlª¾úÌÓ©çä·sðVηñÅ·©çA[ûÜűêðu¢Åu¢Äº³¢B28ªæèÉÜ·v |
| us®`Êvcc | l¨Ì®ÔIÈ®ìA®«Ì`ÊB iáj57¨~Í¢½Íéâ¤ÉµÄwãÉô½B |
| uóÔ`Êvcc | l¨ÌÃÔIÈlqAepÌ`ÊB iáj83XÌûàÃÜè©ÖÂÄîéB |
| uS`Êvcc | u»Ì¼Ìl¨vÉ¢ÄÌàÊÌ`ÊBuFOYvÌuS`ÊvÍA·×ÄȺÌOÂɺÊæªÉ·éB iáj75iaj»êÌâ¦ÊàÉH׳¹½¢Æv½ªæêØÂÄ°ÂÄîéàÌðNµÄs@É·éÌàÆlÖAibjT¦Ä½B |
| u´ovcc | uFOYvÌuS`ÊvBuFOYvÌÜ´ðͶßƵ½gÌ´oÉæÁÄFm³ê½±Æð`ʵ½qBFm³ê½ iáj40RµMÉæê½ |
| uSîvcc | uFOYvÌuS`ÊvBuFOYvÌñ¾êIÅAÛIÈ´îð`ʵ½qB iáj45±ñÈbð·¢ÄéàÉA¢ç©¢¢CªÉÈÂĽB |
| uvlvcc | uFOYvÌuS`ÊvBuFOYv̾êIÅïÌIÈmð`ʵ½qB iáj169FOYÉÍAj©©ªçÈ¢â¤ÈºðoµÄîé¬Y®Ì«½È¢ª¼®áÉ©ñ¾B |
| u®Ô`Êvcc | ¨É¢ÄÌ®IÈ`ÊB¨Ì®«âA®ìÆ¢Á½ÔIÈÏ»ð`ʵ½qB iáj113\ªäéÂéB |
| uÃÔ`Êvcc | ¨É¢ÄÌÃIÈ`ÊB¨ÌlqâAóÔÆ¢Á½óÔIÈ`Êð`ʵ½qB iáj42¢£qÉ墪òRÆÜÂĽB |
@±êçÌÚðAc²iñjɨ«A¶ð¡²isjɨ¢½BªÍ}\Ì^CgsÍÌæ¤ÉÈéB
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| uFOYv | »Ì¼Ìl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||||
@ÚÌzuÍAw½é©xwÔÜÅxɶĢéBÄÑJèÔ·ÆA¶[ɶÔð¨«AuÎÛ\»vuqÒ\»vÆÈç×½BuÎÛ\»vͶ©çul¨`Êvu¨`ÊvƵÄAȺuFOYvÆu»Ì¼Ììl¨vÌul¨`ÊvÆðÎä³¹çêéæ¤Èç×½Bul¨`Êv̺ÊÚÍA¶¤É¢ÙÇOIÈ`ÊAE¤É¢ÙÇl¨ÌàÊÉ©©íé`ÊÉÈéæ¤zuµÄ¢éB
@ªÞªÍÍê¶ð»ÌÜÜêÂÌÚɪ޷éÌÅÍÈAqªªIɪ¯çêéêÍAª¯Ä¢éB¶ÔÈOÉàAªÔªKvÈÌͻ̽ßÅ éB»êçÍw½é©xAwÔÜÅxƯlÌû@Å éB
@ªÍÍêʲÆɨ±ÈÁ½BêÊTÍAuFOYvÌ»êÜÅ̼¶ðLqIÉྵ½ÓÅ é½ßAuFOYvÌuS`ÊvɺÊæªðݯéKvÍȢƻfµAuS`ÊvƵĻêçðêµ½BªÍÊÍA}\ƵĿƵÄYt·éÆÆàÉAæSÈ~Ìl@ÅàA¾yµÄ¢éªÌªÍ}\ð²«oµ½BȨA{eɲ«oµ½}\ÍAȪ»·é½ßukb`ÊvAus®`ÊvccðA»ê¼êukbvAus®vccƪLµÄ¢éB
@\LÉ¢ÄÍAÌæ¤Éµ½BYtµ½ªÍ}\Ì¿ÍAêʲÆɨ±ÈÁ½àÌÅ éB}\É«ÞÌÍA´¥ÆµÄA¶Ôi1A2A3cjƪÔiiajAibjAicjcjÌÝÅ éB±Ì¶ÔÍA¿ÉYtµ½w½é©xÌ{¶ÆεĢéB
@ÈãÌæ¤ÉAqðªÍµ½Êð³ÉAæSÅïÌIÉwäxÉ¢Äl@ð¨±ÈÁÄ¢±ÆÉ·éB
@æSÅÍAOßÜÅƯ¶æ¤ÉAwäxÌq̪ުÍÉæél@ð··ßÄ¢B±±Å
Ú·é_ÍAàÆàÆáÌ¢jÅ Á½uFOYvªAüè̼Ììl¨âA©gÌ̲A»µÄ©ªªXɧ½È¯êÎÈçÈ¢óµA§äª¢ïÉÈÁÄ¢uävÈÇÆ¢¤lXÈuêêvð¤Ý¾µAuáÒvðEµÄµÜ¤Æ¢¤ElÖÌßöÅ éB»ÌßöÍA»êçÌuêêvÉæÁĤÜê½ÕXµ¢CªªADZiNjÉü¯çêÄðÁ³êæ¤ÆµÄ¢éÌ©AÆ¢¤ßöÅà éB
@»êçÌElÖÌßöªÇÌæ¤ÈqŦ³êéÌ©Aשl@µÄ¢BܽA±ÌwäxÅÍAw½é©xEwÔÜÅxÅÍÝçêÈ©Á½_ÌÏ»ªÝçêéBàÊÉ_ªu©êél¨ªÇÌæ¤ÉÏ»µÄ¢Ì©A»ÌÏ»Íìiðl¦éêÇÌæ¤ÈÓ¡ð࿤éÌ©AÆ¢¤_à í¹Äl@·éB
@{Åøp·éwäx{¶ÌT_ÍA´¶ÉæéB¶ÔAªÔÍøpÒÉæéB
yêÊTz
@1zZ{ØÌC°ÌFOYÍ×̽߿µ°ÖA¢½B2»êªxHGcìÕÌOÉ©©ÂÄçºàÌdÉZµ¢·è¾Â½B3ÞÍQȪçê ÄOÉÇÐoµ½¹öÆ¡¾öª½çÆlÖ½B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| uFOYv | »Ì¼Ìl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||||
| 1 | @ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 2 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | @ |
| 3 | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@±êÍAwäxÌ`ªÅ éBæ1¶uzZ{ØÌC°ÌFOYÍ×̽߿µ°ÖA¢½vAæ2¶u»êªxHGcìÕÌOÉ©©ÂÄçºàÌdÉZµ¢·è¾Â½vÆ èAïÌIÈêÆÔª¦³êéB±Ì`ªÌñ¶ÅAu×̽߿µ°ÖA¢½vÉà©©íç¸AuºàÌdÉZµ¢·èvÅ èAuFOYvÍ̲ª«¢Éà©©íç¸AXªZµ¢úÅ éÆ¢¤Î§·é±Æªçª¦³êA`ª©çùÉuêêvª¤ÜêÄ¢éB
@»µÄAæ3¶uÞÍQȪçê
ÄOÉÇÐoµ½¹öÆ¡¾öª½çÆlÖ½vÆuS`Êv³êA±4¶È~ÌqªAuFOYvªulÖ½vàeƵĦ³êé±ÆÉÈéB
@±Ìæ3¶ªuS`Êv³êé±ÆÉæÁÄAuFOYvÌàÊÉ_ªu©êÄq³êé±ÆÉÈéB
@4FOYÍ´ÈOAN±»êÂñÂÈã¾Â½ªA¹ö⡾öƤÉ̬mŠ½ÌðAOÌ媴äÌrOÉêñÅêlºÉzµA©ªÍ¼®BµÄXðø«nµ½ÌÅ éB
@5àXºÉCÌ Â½¹öÍÔàÈÉð潪ACÌ¢¢¡¾öÍ¡ÜÅÌuF³ñvðueûvÆÄÑüßÄOÊèæ¢Ä½B6Bµ½eÍ»ê©ç¼NöµÄAêeͼNöµÄñŵܽB
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| uFOYv | »Ì¼Ìl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||||
| 4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | @ |
| 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | @ |
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 6 | @ |
@±4¶©çÍAuFOYvÌXðC¹çêéæ¤ÉÈéÜÅÌoܪ¦³êéB
@æ3¶uê
ÄOÉÇÐoµ½¹öÆ¡¾öª½çÆlÖ½vÆ é±Æ©çA±êÈ~ÌqÍAuFOYvªv¢oµÄ¢éàeÅ éªAqƵÄÍAqqÒrÉæéLqIÈuqÒ\»vuà¾vÅ éB±ÌøpÅAuFOYvͼÌñlÌElƯ¶u¬mvÅ Á½ÌðAuOÌåªvuäÌrOÉêñÅvXðC¹çêé±ÆÉÈÁ½l¨Å é±Æª¦³êéBuFOYvÍAXðC¹çêéÙÇAñíÉŗÂElÅ éB
@7äðgÓÉ©¯ÄÍFOYÍÀɼl¾Â½B8ÁVAáÌ¢jÅAÅĩĵÅà´ç¯ÎÑðê{XXµo·â¤ÉµÄäçËÎCªÏÜȩ½B9»êÅðrç·â¤È͵ÄÈ¢B10qÍFOYÉ ½ÂÄáÓÆêúѪA¿ªÓÆ]½B11»µÄÞÍ\NÔAÔáÐÉàqÌçÉ𯽪ȢƢÓÌð©ÉµÄî½B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| uFOYv | »Ì¼Ìl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||||
| 7 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 7 |
| 8 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 8 | @ |
| 9 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 9 | @ |
| 10 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 10 | @ |
| 11 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 11 | @ |
±êÍAuFOYvÌrÌdzÆAuáÌ¢v«iª¦³êéÓÅ éB
@±±àâÍèuqÒ\»vÌqÅ éBuFOYvÌuS`ÊvƵÄÅÍÈAuqÒ\»vÌuà¾vÆAuðßE]¿vÌqÅ éBÂÜèAuFOYv©g̩ƵÄÅÍÈAÀƵÄuFOYÍÀɼl¾Â½vƵÄqqÒrÉu]¿v³ê¤érÌåÅ Á½Æ¢¤±ÆÅ éB±êÜÅÌuFOYvÍA©¼¤ÉFßçêéÙÇAä̵¢ÉÈê½l¨ÈÌÅ éB
@±±ÅÍAuFOYvª±êÜÅêxàqÌç𯽱ÆÌȢƢ¤rÌdzÆAáÌ¢ElC¿ÅA[¾¢dðµÈ¯êÎCª·ÜȢƢ¤±Æª¦³êéBu©ÉµÄî½vÆ é±Æ©çAuáÌ¢jvÅ éÆÆàÉAÀÛÉñíÉrª§¿A©çà©gÌrÉÖèðàÁÄ¢é±Æ঳êéB¼ÚuFOYvÆuêêvð¤Ý¾·±Æªçͦ³êÈ¢ªA·×ÄÌ´öª±ÌáÌ³É é±ÆÍAmF³êé׫Šë¤B
@12oÄs½¹öÍ´ãñNèµÄÔçèÆÒÂĽB13FOYÍÈOüy¾Â½Dæ©çàlð]ÂÄé¹öðgÍÈ¢í¯És©È©Â½B14Rµ¹öÍ´ñNÔÉ©Èè«ÈÂÄî½B15dÍepÓ¯éB16»µÄ¡¾öðUÐoµÄAଠ½è̺àèÌöµCÈɶÐôéB17dÉÍlÌ¢¢¡¾öð´©µÄXÌàÜÅ©ß³·lÈðµ½B18FOYÍ¡¾öð£zÉvÂÄxXÓ©àµÄ©½B19RµXÌàð¿o·lÉÈÂÄÍAǤ·éàoȩ½B20ÅAÞÍê ÄöOAÉñlðÇ¢oµÄ¹Â½ÌÅ éB
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| uFOYv | »Ì¼Ìl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||||
| 12 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 12 | @ |
| 13 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 13 | @ |
| 14 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 14 |
| 15 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 15 | @ |
| 16 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 16 | @ |
| 17 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 17 | @ |
| 18 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 18 | @ |
| 19 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 19 | @ |
| 20 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 20 | @ |
@¯NãÌu¹övÆu¡¾övÆðX©çÇ¢o³´éð¾È©Á½îª¦³êéB
@±±ÅàA·×ÄÌqªuqÒ\»vÆÈÁÄ¢éBElC¿Å éuFOYvª¯NãÅ Á½ñlÌElðǤµÄàXɨ¢Ä¨¯ÈÈÁ½oܪïÌIɦ³êÄ¢éB±¤µ½êAÌo©çAuFOYvÍuÈOüy¾Â½Dævðdñ¶él¨Å èȪçA»êÅàXðçé½ßÉÍÇ¢oµÄµÜ¤Æ¢¤µµ³ðàÁ½l¨ÆµÄ¦³êéB±ÌªA3¶Ìuê
ÄOÉÇÐoµ½¹öÆ¡¾öª½çvÆ¢¤uFOYvl¦éRÆÈÁÄ¢éÌÅ éB
@21¡îéÌÍYÆ¢Óñ\ÎÉÈéÂÄCÍÌȢ¢çÌjÆAÑöÆ¢Ó\ñOÌA±êͪªãOÉP É·¢qÆÅ éB22ÕúOÌÒ¬ÉñlÅͳÂÏ轪 ©ÊB23ÞÍMÅêµ¢gð¡ÖȪç°ÌÅêlÕXµÄ½B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| uFOYv | »Ì¼Ìl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||||
| 21 | @ | @ | @ | @ | @@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 21 |
| 22 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 22 |
| 23 | @ | @ | @ | @ | 23 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@±±ÍA»ÝuFOYvÌXÉ¢éñlÌElÉ¢Ħ³êéÓÅ éB`ªÌ3¶ÅuFOYvª«ß³¹ÄµÜÁ½Elª¢êÎAÆl¦éÌÍA¡¢éElªXðC¹çêél¨ÅÍÈ¢½ßÅ éB³çÉAuFOYvÍElC¿ÌjÅ é½ßA̲ª«¢©çÆ¢ÁÄXÉC¹çêéÒ̢ȢóÔÅÍQÄ¢çê¸AÕXðåç¹Ä¢BXðC¹çêéElª¢È¢½ßAuFOYvÌ̲ª«¢Éà©©íç¸AXÉoÈÄÍ¢¯È¢Æ¢¤uêêvð¶ñÅ¢éB
@±±ÅÌqàâÍèuqÒ\»vÌuà¾vÅ éB»ÌóµÉÕXðåç¹Ä¢éuFOYvÌàÊÍAuS`ÊvÌuSîvÌqŦ³êéB
@XðC¹çêéÒª¢È¢Éà©©íç¸AñlÌElðÇ¢oµÄµÜÁ½Æ¢¤±ÆÍA»ê¾¯uFOYvªÈªÁ½±Æ̹Ȣl¨Å éÆ¢¤±ÆÅà éB©ªÌrð©·éÆÆàÉAæã©çó¯p¢¾Xðçë¤Æ·éuFOYvÌdÉηél¦ª çíê½Æྦæ¤B
@±ÌêÊTÍA»ÌÙÆñÇÌqªuFOYvªC¹çêéElª¢ÈÈÁĵÜÁ½oܪAuqÒ\»vŦ³êÄ¢é±ÆÉÚ³êéBuFOYvªElÉéÀÛÌoÜÍAêÊUÈ~ÅWJ³êÄ¢±ÆÉÈé±Æà èAuFOYvÌ«iÆ»ÌúÌ̲̫³AÞðæèªóµÆ¢¤uêêvªAåƵÄuqÒ\»vÌuà¾vŦ³êéBuFOYvÍA©ªÌdð®·é±ÆÉÖèðà¿ArÌdzÅXÜÅàC¹çêéæ¤ÉÈÁ½l¨Å é±Æª¦³êéBµ©µA»ÌrÌdzÆÖèÍAáÌ¢jÅà èA[¾·édðµÈ¯êÎCª·ÜȢƢ¤«iÆ¢¤ñÊ«ðËõ¦Äà¢éB
@±Ìæ¤ÉA±ÌêÊTÅÍAáÌ¢«iÌuFOYvðÕX³¹é´öÍA©È¯ê΢¯È¢óµÈÌÉA×̽߯ȢAÆ¢¤uêêvÉæéàÌÅ éB
yêÊUz
@24ÉßÃÉÂê Äqª½Ä ñŽB25iaj¯½½Üµ¢ÉqËÌJ¯ÂÄâAÑöÌø«¸éÌäéñ¾«ÊÌ£¢½â¤È¿ibjªsȽ_oÉÍs^_GéB
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| uFOYv | »Ì¼Ìl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||||
| 24 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 24 | @ | @ | @ |
| 25 | @ | @ | @ | 25ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 25iaj | @ | @ | @ |
@êÊUÉÈèA¢æ¢æqª§ÄñÅéB
@uFOYvÍA°ÉüèȪçàX̪µ¢lqÉÕXðåç¹Ä¢BQÄ¢éuFOYvÍA»ÌXÌlqðQ°©ç®oÉæÁÄméB25¶ªAu¯½½Üµ¢ÉqËÌJ¯ÂÄâAÑöÌø«¸éÌäéñ¾«ÊÌ£¢½â¤È¿vÆ¢¤PÉu¨`ÊvÅÍÈA»êªusȽ_oÉÍs^_GévÆuS`ÊvÌu´ovŦ³êéB±êÍAuFOYvÌ̲ª«¢±ÆÆA̲ª«¢Éà©©íç¸Zµ¢Xðè`¤±ÆªÅ«È¢±ÆÉæÁÄAÕXµÄusȽv½ßÅ éB24¶Íu¨`ÊvÌu®Ô`ÊvÅ éÌÉεA25¶ªuS`ÊvÅ é½ßA»ÌÕ§¿ª¯É¦³êÄ¢éÌÅ éB
@±ÌuS`ÊvÌu´ovÍAuFOYvÌàÊÉ_ªu©êÄq³êÄ¢éB
@26Éq˪J¢½B
@u27³yÌRcÅ·ªAUßlª¾úÌÓ©çä·sðVηñÅ·©çA[ûÜűêðu¢Åu¢Äº³¢B28ªæèÉÜ·v29̺¾B
@u30iaj¡úÍ¿ÂÆ½Ä ñÅéñÅ·ªA¾ú̩̤¿Àâ ¢¯Ü¹ñ©HvibjÆY̺ª·éB
@31iajÍê¡a½lq¾Â½ªA
@uibjÀâ ÔáÐÈËv32iaj©¤¢ÂÄÉqËðÂß½ªA¼®J¯ÄA
@uibjäÊ|ÅàeûÉäèеܷæv
@u33 ÌAeûÍccv34Yª¢ÓB35iaj»êðÕÂÄA
@uibjAâéºIvicjÆFOYÍQ°©ç{½B36s©Â½ªmêĽB37iaj»êÉÍÖ¸A
@uibjæ뵤äÀ¢Ü·vicjÆYÌ]Óidj̪·¦éB38ÍÉqËðÂß½lq¾B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| uFOYv | »Ì¼Ìl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||||
| 26 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 26 | @ | @ | @ |
| 27 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 27 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 28 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 28 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 29 | @ | @ | @ | @ | @ | 29 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 30 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 30iaj | 30ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 31 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 31iaj | @ | 31ibj | @ | @ | @ | @ | @ |
| 32 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 32ibj | 32iaj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 33 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 33 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 34 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 34 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 35 | 35ibj | 35iaj icj |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 36 | @ | @ | 36 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 37 | @ | @ | @ | 37idj | @ | @ | 37ibj | 37iaj icj |
@ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 38 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 38 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@ÉßëAZµÈènß½uC°vÉAuävðu¢ÅÙµ¢Æ¢¤dªüéB
@±Ìu³yÌRcv©çÌdÌËÌlqàAuFOYvÌQ°©çÌFmÉæéqÅ éB29¶u̺¾vÆ¢¤®oÉæé»fðͶßA30¶ibjuY̺ª·évA37¶idju̪·¦évÆ¢¤q©çAuFOYvÌàÊÉ_ªu©êÄ¢é±ÆªmFÅ«éB
@̲ª««ÉXɧ±ÆàÅ«È¢uFOYv¾ªAdð¿¯ÄµÜ¤BáÌ¢«i̽ßA̲ª«¢±ÆÅ©¦ÁÄuFOYvÍdð¿¯ÄµÜ¤ÌÅ éB̲ª«¢Éà©©íç¸AuävðuªÈ¯êÎÈçȢƢ¤uêêvª¤ÜêÄ¢éB
@u39iaj{¶vibjÆFOYͬºÉƾµÄé Ì®ÅÂæ²ê½rðoµÄAbÃÂÆ©l߼B40RµMÉæê½©ç¾ Íïçê½u¨Ìâ¤Éd©Â½B41ÞͤÂÆèµ½áÅVäÌ··¯½¢£qð߼B42¢£qÉ墪òRÆÜÂĽB
@43ÞÍ·ÆàÈXÌbɨðX¯½B44iajºàªñOlAß̬¿®Ìi]©çRàÌÑÌ@½És¡¢©ÈÇðbµÂÄARµ©¤ÁµÈéÆA»êàôç©ÍH×çêĽÈÇ]ÂÄéibj̪·¦éB45±ñÈbð·¢ÄéàÉA¢ç©¢¢CªÉÈÂĽB46bµÄÞÍåV³¤ÉQÔèðµ½B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| uFOYv | »Ì¼Ìl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||||
| 39 | 39iaj | 39ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 40 | @ | @ | @ | 40 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 41 | @ | 41 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 42 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 42 | @ | @ |
| 43 | @ | 43 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 44 | @ | @ | @ | 44ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 44iaj | @ | @ | @ |
| 45 | @ | @ | @ | @ | 45 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 46 | @ | 46 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@̲ª«¢Éà©©íç¸Adð¿¯ÄµÜÁ½uFOYvÍAN«ãªë¤Æ·éBµ©µuFOYvÌgÌÍAËRƵÄ40¶uMÉæ꽩ç¾Íïçê½u¨Ìâ¤Édv¢BdðµÈ¯êÎÈçÈ¢ÆÓ¯·éÆA̲̫³àÓ¯³êéÌÅ éB̲ÆdðµÈ¯êÎÈçÈ¢±ÆªAuFOYvÌàÊÅAuêêvð¤Ý¾µÄ¢éB
@tÉA43¶44¶Ìæ¤Éu·ÆàÈXÌbɨðX¯véÆA45¶u±ñÈbð·¢ÄéàÉA¢ç©¢¢CªÉÈÂÄvéBäðu®±ÆðÓ¯µÈÈéÆAuFOYvÌCªÍ¿
ÌÅ éB
@±ÌÓàAâÍèuFOYvÌuS`Êvu´ovuSîvªSÅ èA»ÌàÊÉ_ªu©êÄ¢éB
@47OôÌü¤Ìèûð˵ÞÂۢܽ[ûÌõÌÉ[̨~ªÔñVð¼Z¨ñÔɵÄ[éMÌxxðµÄéB48iajÞÍibjyȽCªð¡ÐȪçicj»êð©Äî½B
@u49¡ÌàÉâÂÄu©¤v50iajÞÍ©¤vÂÄibjd¢©ç¾ÅcÌãÖN«¼Â½ªAá¿òªµÄbÍÌãÖ˵ĽB
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| uFOYv | »Ì¼Ìl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||||
| 47 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 47 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 48 | @ | 48iaj icj |
@ | @ | 48ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 49 | @ | @ | @ | @ | @ | 49 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 50 | @ | 50ibj | @ | @ | @ | 50iaj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@uFOYvÍAQ°ÉA«ÈªçàCªªÇÈÁÄ«½½ßA¿¯Á½uävðu²¤Æl¦éi49¶A50iajjBµ©µA̲Íܾ«ÌãÉËÁµÄµÜ¤i50¶ibjjB±±ÅàAFOYÌdðµæ¤Æ¢¤ÓvÆÍtÉA̲ªßç¸Auêêvð¤Ý¾µÄ¢éB47¶Åu¨~vÌpð©Ä¢éÆA48¶CªÍuyÈvéªAâÍèdÉæègà¤Æ·éÆA̲̫³ðÓ¯·éÌÅ éB
@±ÌÓàAu¨~vÌlqªuFOYvÌàÊÉ_ªu©êÄq³êÄ¢éB
@u51iajÍΩèHvibjÆDµ]ÂÄA¨~ÍGèð¾çèÆOÖº°½ÜÜüÂĽB
@52iajFOYÍÛÆ]½Âàè¾Â½ªAibjºªÜéÅ ¿©È©Â½B
@53iaj¨~ªé ðÍ¢¾èA³ÌáfâòrðÐñ¹½è·éÌÅAibjFOYÍA
@uicj³¤ÀâÈ¢vidjÆ]½B54ªAºª©·êÄ ¨~ÉÍ·«Æêȩ½B55Üp¼è©¯½CªªÕXµÄ½B
@u56ã©çø¢Ä °æ¤©v57¨~Í¢½Íéâ¤ÉµÄwãÉô½B
@u58çuÆRc³ñ©çÌäðÂÄÈv59FOYÍÔ¯éâ¤É]Ðú½B60iaj¨~Íê¡ÙÂÄA
@uibj¨O³ñu°éÌHv
@u61¢¢©çÂÄÈv
@u62ccN«ÄéÈ穢ܫ Åà|¯ÄÈ¿âdlªÈ¢Ë¦v
@u63¢¢©çÂÄ¢Æ]ÓàÌðÂÄ˦©v64ÉᢺÅÍ]ÂÄîéªAáÅs^_µÄéB65¨~ÍmçñçðµÄA©¢Ü« ðoµA°ÌãÉÓ¿ð©¢ÄîéÌÉãë©çHDÂÄâ½B66FOYÍÐèðS®â¤ÉµÄ©¢Ü« ÌÝð?ÞÆ®¢Æ¢Å¹Â½B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| uFOYv | »Ì¼Ìl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||||
| 51 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 51iaj | 51ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 52 | @ | @ | 52ibj | @ | @ | 52iaj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 53 | 53icj | 53ibj idj |
@ | @ | @ | @ | @ | 53iaj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 54 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 54 | @ | @ | @ | @ |
| 55 | @ | @ | @ | @ | 55 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 56 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 56 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 57 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 57 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 58 | 58 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 59 | @ | 59 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 60 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 60ibj | 60iaj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 61 | 61 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 62 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 62 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 63 | 63 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 64 | @ | 64iaj | @ | @ | 64ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 65 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 65 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 66 | @ | 66 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@dðißæ¤ÆN«ãªë¤Æµ½uFOYvðÝÄAu¨~vÍvªf«Cðà樵½Ì©Æ¨á¢·éB»êÉεÄAuFOYvÍAºÉÈçÈ¢ºðã°Äd¹ïðÁÄéæ¤É¾¤ÆAu¨~vª~ªð
éæ¤É£µuFOYvÉ~ªð
¹éªA»êà·®E¢ÅµÜ¤B
@±±ÅÍAuFOYvÆÈÌu¨~vÆÌÓvªÝÁĢȢBdðµæ¤Æ·éuFOYvÉεAu¨~vÍ̲ª«¢ÌÉdð·é͸ªÈ¢Æl¦Ä¢é½ßAvÌÓvªÇÝÆêÈ©Á½ÌÅ éB»êÅàdðµæ¤Æ·éuFOYvÉεAu¨~v͹ßÄ~ªð
ÄÙµ¢Æv¤ªA»ê³¦uFOYvÍE¢ÅµÜ¤B±±ÅͶßÄA̲ª«¢Éà©©íç¸AdðµÈ¯êÎÈçȢƢ¤uêêvÈOÌAFOYÌCªªÕX·é´öª¶ÜêéB»êÍu¨~vÆÌÓvÌêêÅ éB±ÌV½ÈuêêvÉæÁÄAuFOYvÍuÜp¼è©¯½CªªÕXµÄvé±ÆÉÈéB
@±Ìêêðæè¾ÄÉ·é½ßAuFOYvÈOÌl¨ÌàÊÉ_ªu©êÄq³êéB±êÜÅuFOYvÉÌÝuS`ÊvªÝç꽪Au¨~vÌàÊÉà_ªu©êuS`Êv³êéi54¶jB54¶ÍSÅÍÈ¢ªA¾ç©Éu¨~vÌ®oðʵ½´oÌ`ÊÅ éB±Ìæ¤ÉA_ªu©êéÎÛªÏíéÌÍAuFOYvu¨~v¼ÒÌÓvÌá¢ð«¤èÉ·é½ßÅ éƾ¦éB
@±ÌøpÍAuFOYvÆu¨~vÆÌÓvÌᢪÎäIÉq³êÄ¢éÓÅ éB»êƯÉAuFOYvªu¨~vÉεÄ{èðÔ¯ĢéÓÅà éBuFOYvÍ©ª¾Á½±Æð·«æêÈ©Á½u¨~vÉεÄAuÔ¯éâ¤É]Ðúv¿i59¶jAu¢¢©çÂÄ¢Æ]ÓàÌðÂÄ˦©vƾ¤ÅAÕXµ¢CªðA½ÈèÆàðÁ³¹Ä¢éBu¨~v̾®ÍAuFOYvÌÕXÌ´öÅ éƯÉAuFOYvÍgàÅ éÈÉÈç¼Ú»êðÔ¯é±ÆàÅ«éÌÅ éB
@67¨~ÍÙÂļÔÌáqðJ¯éÆyÔÖ~èÄvuÆäðæÂĽB68»µÄçuð©¯éªÈ©Â½ÌųÌÉÜBð¤ÂÄâ½B
@69iajFOYÍÓ¾ñ ųÖCªÌ«¢Í|u°È¢Æ]ÂÄéÌÉAibjMÅèªkÖĽ©çAǤµÄàvÓâ¤Éu°È©Â½B70iaj´ÕXµÄîélqð©ËÄAibj¨~ÍA
@uicj³ñɳ¹ê΢¢ÌÉvidjƽÕà©ßÄ©½ªAiejÔàµÈ¢B71¯êÇàÉäªoÈȽB72\ܪöµÄCàªàs«ÍĽƢÓlqÅÄÑ°Ö¡ÍéÆA¼®¤Æ^_µÄA¢Â©°üÁĹ½B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| uFOYv | »Ì¼Ìl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||||
| 67 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 67 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 68 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 68 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 69 | @ | 69ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 69iaj | @ |
| 70 | @ | 70iej | @ | @ | @ | @ | 70icj | 70ibj idj |
@ | 70iaj | @ | @ | @ | @ |
| 71 | @ | @ | @ | @ | 71 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 72 | @ | 72 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@u¨~vÍd¹ïðæèA³Åuävðu°éæ¤ÉBðÅÁÄâéBµ©µAǤµÄàv¤æ¤Éu°È¢uFOYvÍÄÑQüÁĵܤB
@±±ÅàuFOYvÆu¨~vÌàʪ_ðϦȪçq³êÄ¢éB69¶ÍuMÅèªkÖĽ©çAǤµÄàvÓâ¤Éu°È©Â½vÆ é±Æ©çuFOYvÌàÊÉ_ªu©êÄ¢éBÌ70¶iajÅÍu´ÕXµÄîélqð©ËÄvÆ èAu¨~vÌàÊÉ_ªu©êéB»µÄÄÑ71¶u¯êÇàÉäªoÈȽvÆ èuFOYvÌàÊÉ_ªÏíèq³êéB
@±±ÅàAñlÍ»Ìl¦Ìuêêvð¦µÄ¢éBu³ñɳ¹ê΢¢ÌÉvÆl¦éu¨~vÉεÄAuFOYvÍAuvÓâ¤Éu°Èv¢Éà©©íç¸AǤµÄ੪Åu²¤Æ·éB»µÄâªÄuäoÈÈÂvĵܤÌÅ éB±ÌæÈÈÔxÍA̲ª«¢Éà©©íç¸dð¿¯æ¤Æµ½ÔxƯlÅ éB¦¿Au¨~vÉuYvÉC¹éæ¤É¾íêéÆ©¦ÁÄA©ªÌèÅdðâè°æ¤Æ·éÌÅ éB±Ìµµ½ÔxÍAáÌ¢ElC¿Å é½ßÅ éB
@ܽA69¶uFOYÍ
@73äÍÎÆÚµ AgÌArñÂÄ©½Æ¢ÓRc̪ÂĽB
@74¨~ÍðÏÄu¢½B75iaj»êÌâ¦ÊàÉH׳¹½¢Æv½ªæêØÂÄ°ÂÄîéàÌðNµÄs@É·éÌàÆlÖAibjT¦Ä½B76ª ÉȽB77iaj]èxêéÆòÜŪxêÉÈé©çibjƳÉäèNµ½B78iajFOYàibj»êös@ÅÈicjN«¼ÂÄHðµ½B79³¤µÄ¡ÉÈéƼ®°üÂĹ½B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| uFOYv | »Ì¼Ìl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||||
| 73 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 73 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 74 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 74 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 75 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 75ibj | @ | 75iaj | @ | @ | @ | @ |
| 76 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 76 | @ |
| 77 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 77ibj | @ | 77iaj | @ | @ | @ | @ |
| 78 | @ | 78iaj icj |
@ | @ | 78ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 79 | @ | 79 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@@µÎçuävðu¢¾uFOYvÍA̲̫³Ì½ß°èÉ¢ĵܢAuFOYvªQÄ¢éÔÌu¨~vð`¢½ÓÅ éBu¨~vÍAvÌ̲ÆCªð¤©ª¢ÈªçAvĵ½ãÅò̽ßÉuFOYvðN±·BηéFOYÍA³ÉN±³ê½ªAs@ÅÍÈHðµÄÄÑ°èÉÂB¼ÒÌÔÉΧͶÜêĢȢBdðµÈ¯êÎÈçȢƢ¤uFOYvÌÓ¯ÉA¶IÈ~ªÁÄ¢éÆ¢¤±Æà é½ß©AuFOYvÍs@ÅÍÈ¢BêIÉÅÍ éàÌÌAuFOYvÍ̲̫³ÆAuävðu®Æ¢¤dÆÌuêêv©çðú³êACªÍÀèµÄ¢éÆ¢¦éB
@±±ÅÍAu¨~vÌAvÌ̲ðæêÉl¦æ¤Æ·é^ÈÔxðAu¨~vÌàÊÉ_ªu©ê½qÉæ覵Ģéi75¶iajA77¶iajjBuFOYvÌàÊÉàA_ªu©ê½qi78¶ibjjª éªA¼ÒÌÓvÌÔÉuêêvª¤ÜêĢȢBvwÌÓvÌuêêvÅÍÈAu¨~vÌvÖÌCª\í³êÄ¢éB
@±ÌêÊUÅÍAæÉuFOYvÌÕXªAu¨~vðͶßÆ·éüèÌlXÆÌÓvaʪūȢ±ÆÅàå«ÈÁÄ¢BXÌbɨðX¯½èA°Á½èµÄdðµÈ¯êÎÈçȢƢ¤±ÆðÓ¯¹¸É¢êÎAuFOYvÌCªÍÀè·éB¾ªA¢Á½ñdðµnßéÆA̲̫³ªÓ¯³êA³çÉüèÆÌÓvÌuêêvª¤ÜêĵܤB
@êÊUÉÈÁÄA±Ìu¨~vÆÌÓvÌuêêvª¦³êéªA»êƯÉÞɼڽ·é±ÆÅ»ÌÕXµ½CªÍA éöxÀèµÄ¢éƾ¤±ÆàÅ«éB
yêÊVz
@80\µOAFOYÍòÅN±³ê½B81iaj¡Í½ðlÖéÆàÈibjEg^_ƵÄîéB82MCð½@§ªá̺ÜÅíÂÄîéé ÌÝÉÂÄC«çÉ©©éB83XÌûàÃÜè©ÖÂÄîéB84ÞÍÍÌȢ᷵Š½èð©ôµ½B85ÉÍ^ÈçuªÃ©ÉºªÂÄéB86âvÌõÍCÉÔ©F÷ÂÄA®Ì÷ÅÔÉYûðµÄîé¨~ÌwðÆçµÄ½B87ÞÍ®ªMÅêµñÅéâ¤É´¶½B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| uFOYv | »Ì¼Ìl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||||
| 80 | @ | 80 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 81 | @ | @ | @ | 81ibj | @ | 81iaj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 82 | @ | 82 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 83 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 83 | @ | @ |
| 84 | @ | @ | 84 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 85 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 85 | @ | @ |
| 86 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 86 | @ | @ |
| 87 | @ | @ | @ | 87 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@ÄÑuFOYvÍò̽ßÉN±³êéBÓèð©ñ·uFOYvÍu®ªMÅêµñÅéâ¤É´¶véB
@N±³ê½uFOYvÍAò̽ߩA°CÆÓð´¶éB±ÌÓÍA81¶ÌuS`ÊvðͶßƵÄA·×ÄuFOYvÌàÊÉu©ê½_ÉæÁÄq³êÄ¢éBÕXµ¢CªÍ¿
¢Ä¢éàÌÌAMÉæÁÄu®ªMÅêµñÅéâ¤É´¶½vÆ èA̲ÍËRßÁĢȢB
@u88eû\\eû\\v89yÔ©çÌãèûÅÑöÌId^_µ½ºª·éB
@u90¦¦v91FOYÍé ÌÝÉûðß½ÜÜÖ½B92iaj´âĽâ¤Èmºª·¦Ê©µÄA
@uibjeû\\vicjÆ]½B
@u93½¾æv94¡xÍÍ«èÆs©Â½B
@u95Rc³ñ©çäªÜµ½v
@u96ÊÌ©¢Hv
@u97æÅ·B98¼®gÂÄ©½ªA]ÜèØêÈ¢ªA¾úÌÅ¢¢©çeûªêxgÂÄ©ÄñzµÄº³¢ÂÄv
@u99¨gЪȳéÌ©¢Hv
@u100æÅ·v
@u101iajǤvibjÆFOYÍé ÌãÉèðεÄAÑöªl¢ÉÈÂÄo·äðPCXÌÜÜó¯æ½B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| uFOYv | »Ì¼Ìl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||||
| 88 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 88 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 89 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 89 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 90 | 90 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 91 | @ | 91 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 92 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 92ibj | 92iaj icj |
@ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 93 | 93 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 94 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 94 |
| 95 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 95 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 96 | 96 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 97 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 97 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 98 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 98 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 99 | 99 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 100 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 100 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 101 | 101iaj | 101ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@QÄ¢½uFOYvÉAÄÑu³yÌRcv©ç¯¶uävªßÁÄ«½±ÆðuÑövª°éBuFOYvÍA»Ìuävðó¯æéB½ÌöÊ©AuFOYvÍÄѯ¶uävðu®±ÆÉÈÁĵܤB»µÄAuáÒvðEµÄµÜ¤uävàA±Ì½xàu²¤Æݽ±ÌuØêÈ¢vuävÈÌÅ éB
@88¶Åueû\\eû\\vÆÄÑ©¯éuÑövÉεÄAuFOYvÍ90¶u¦¦vÆÔð·éªAuÑövÉÍ·¦È¢B¼ÒÌÓvaʪ«ÉūĢȢ±Æª¦³êÄ¢éBuFOYvÍAuÑövÉÔðµæ¤ÆµÄàA«Éºðo·±ÆàÅ«È¢óÔÅ èA̲ÆuFOYvÌÓvƪ©Ýí¸Auêêvð¤Ý¾µÄ¢éB
@±±ÅÍAu¨~vÆÌâèÆèi51¶`66¶A70¶jÆÍá¢AuÑövÌàÊð`ʵ½qÍÈ¢BæÌu¨~vÆÌâèÆèÅÍAuFOYvÆu¨~vÆÌl¦Ìᢪ«¤èÉÈéæ¤Éq³êÄ¢½Bêû±ÌuÑövÆÌH¢á¢ÍAïbª¬§Å«È©Á½Æ¢¤öxÌàÌÅ èAuFOYvÆuêêvð¤Ý¾µAÕ§½¹éàÌÅÍÈ¢B»Ì½ßA_ªÏíé±ÆÍÈ¢ÌÅ éBµ©µA±94¶uÍ«èÆs©Â½vÆ éÌÍAºÌs³¾¯ÅÍÈA_oßqÉÈÁÄ¢éuFOYvÌàÊ𤩪í¹éqÆÈÁÄ¢éB
@u102MÅèªkÖéñ¾©çA¢Â» à¬ÌÇì³ñÉÞûªæ©È¢ÌHv
@103©¤]ÂĨ~Í;©Â ½¹ðí¹ÈªçN«Ä½B104FOYÍÙÂÄèðεÄvÌcðã°APCX©ç²«oµÄnðÅ¿©Öµ^_©½B105¨~ͳɿÂÄA»ÂÆFOYÌjÉèðÄÄ©½B106FOYÍÜ墳¤Éó¢½èÅ»êð¥ÐÞ¯½B
@u107ÑöIv
@u108GCv109¼®é ÌÌÅÔðµ½B
@u110uÎðÖÂÄ¢v
@u111GCv
@112uÎÌxxªo½ÅAFOYÍN«ãÂÄAÐGð§ÄÄu¬nß½B113\ªäéÂéB
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| uFOYv | »Ì¼Ìl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||||
| 102 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 102 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 103 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 103 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 104 | @ | 104 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 105 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 105 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 106 | @ | 106 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 107 | 107 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 108 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 108 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 109 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 109 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 110 | 110 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 111 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 111 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 112 | @ | 112 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 113 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 113 | @ | @ | @ |
@N«ãªÁ½uFOYvÍAËRƵÄ̲ª«¢Éà©©íç¸A©ªÅ¤²¤Æ·éBuFOYvÍA©ªÅu¢¾uävÅ é½ß©A¼ÌXÉñÅÍÆ¢¤ÈÌ\µoÉæèíÈ¢BêûAu¨~vÍAvÌ̲ðSzµÄAzÉèðÄæ¤Æ·éBµ©µAuFOYvÍA»êðuÜ墳¤Év¥¢Ì¯éB±±ÅAÄѼÒÌÓvÍH¢á¢ª¾ç©ÆÈéBvÌ̲ðÅDæÉl¦éu¨~vÆAC¹çê½dð®·é±ÆðæêÉl¦éuFOYvÆÍAuêêvªÝçêéÌÅ éB
@uS`ÊvÉæÁļÚÕXµ½Cªª¦³êéí¯ÅÍÈ¢ªAuÜ墳¤ÉvÆ¢¤q©çi106¶jAuFOYvÍÕXðåç¹Ä¢é±Æª¦³êéB
@±±ÅàAuS`ÊvÍÈ¢ªAu¨~vÌ105¶Ìus®`ÊvÍAu¨~vÌàÊÖ_ªu©êÄq³êÄ¢éBâÍèA¼ÒÌÓvªuêêvð¤Ý¾µÄ¢é±Æ𾦷é½ßÌAu©êé_ªÏíé±ÆÉæéÎäIÈqÅ éB
@114iaj¨~Íibj½ð]ÂÄàǤ¹³ÊÆv½©çicjéɿÂÄ©Äî½B
@115buÎÅu¢¾ãA¡xÍçuÖ©¯½B116ºàÌæÇñ¾óCª´ÌL ^_¢Ó¹Åôç©®«oµ½â¤ÈCªµ½B117FOYÍkÖéèð¬ÖA²qð¯Äu¢ÅîéªAǤµÄàCæs©ÊB118´àæ¨~̼ÉŽÜBªsÓɲ¯½B119çuªòñÅN^_Æäɪ«Â¢½B
@u120iaj ÔÈ¢IvibjÆ©ñŨ~Íicj°é^_idjFOYÌçð©½B121FOYÌûªÒèèÆkÖ½B
@122FOYÍçuðÙ®µÄ´ð°o·ÆAäðÂħ¿ãªèAQßêÂÅyÔÖs©¤Æµ½B
@u123¨O³ñ»è⢯Ȣ ccv
@124iaj¨~ͺðoµÄ~ß½ªAibjø©È¢B125FOYÍÙÂÄyÔÖºèĹ½B126¨~à¢ĺè½B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| uFOYv | »Ì¼Ìl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||||
| 114 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 114iaj icj |
@ | 114ibj | @ | @ | @ | @ |
| 115 | @ | 115 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 116 | @ | @ | @ | 116 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 117 | @ | 117 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 118 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 118 | @ | @ | @ |
| 119 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 119 | @ | @ | @ |
| 120 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 120iaj | 120ibj idj |
@ | 120icj | @ | @ | @ | @ |
| 121 | @ | 121 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 122 | @ | 122 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 123 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 123 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 124 | @ | 124ibj | @ | @ | @ | @ | @ | 124iaj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 125 | @ | 125 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 126 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 126 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@ÈɽγêȪçàuFOYvÍAäðu¬nßéBµ©µAâÍè̲ª·®êÈ¢½ßAuCævu°È¢B
@±±ÅÍAuFOYvÌuävðu²¤Æ·éÓvÆA̲ªâÍèuêêvð¤Ý¾µÄ¢éB̲ª«dª¤Ü¢©È¢±ÆðA±êÜÅƯ¶æ¤ÉAuFOYvÌàÊÉ_ªu©êuS`Êv³êéi116¶u´ovjB
@u¨~vÆÌl¦ÌᢪÄѦ³êÄ¢éBvªSzÅd𳹽ȢÆvÁÄ¢éu¨~v¾ªA114¶u½ð]ÂÄàǤ¹³ÊÆv½v½ßÉA©çé±ÆÉ·éBËRçuÌBªOêĵܢAQß¾¯ÅdêÌyÔÉü©¨¤Æ·éuFOYvð124¶uºðoµÄ~ßvæ¤Æ·éBµ©µAuFOYvÍ»Ìæ¤ÈÈÌSzðCÉ©¯é±ÆÍÈA124¶ibjuø©v¸É~èĵܤÌÅ éB±±ÅàA_ª114¶Íu¨~vA116¶A117¶ÍuFOYvÌàÊÉu©êÄ¢éBu©ê_ªÏíé±ÆÉæÁÄA¼ÒÌl¦ÌH¢á¢ª¦³êÄ¢éB
@ܽA±ÌøpÍ»ÌñÂÌuêêv¾¯ÅÍÈAu¢Å¢½uävÆÌuêêvà¤ÜêÄ¢éBu³yÌRcvÌuävðu¢Å¢éÆAçuð~ßÄ¢éBªOêĵܤi118¶jB»µÄA119¶uçuªòñÅN^_ÆäɪvÌÅ éB±êÍAu¨~̼ÉŽÜBvÅ Á½½ßBÌÅ¿Ý Ü©Á½Æ¢¤¨IÈvöÉæÁÄAN±Á½àÌÅ éBµ©µAi©çä̵¢ÉµêÄ¢½uFOYvÉÆÁÄÍAuävðiÌæ¤É©ªÌv¢Êèɵ¤±ÆªÅ«ÈÈÁÄ«Ä¢é»íêÅà éBuävÆAuFOYvƪuêêvðN±µÍ¶ßÄ¢éÌÅ éB
@127qÍêlàȩ½B128Ñöªêl{¾ÌOÉ©¯Ä½B
@u129iaj³ñÍHvibjƨ~ªu¢½B
@u130qð£èÉs«Üµ½v131ÑöÍ^ÊÚÈçðµÄ©¤Ö½B
@u132iajÜ »ñÈð]ÂÄoÄs½ÌHvibjƨ~ÍÎÐoµ½B133RµFOYÍËRÓµ¢çðµÄéB
@134qÆ]ÓÌÍ©çÜZ¬æÌRàpGÝÆ¢ÓÅÂðoµ½ÆÌÈÅ éB135w¶ãªè¾Æ©]ÓA´XÉÍnIAºà©¶©ßÌáÒªêlâñl|¯ÄÈ¢ÍÈ¢B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| uFOYv | »Ì¼Ìl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||||
| 127 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 127 | @ | @ |
| 128 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 128 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 129 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 129iaj | 129ibj | @ | @ | @ | @ | @ |
| 130 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 130 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 131 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 131 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 132 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 132iaj | 132ibj | @ | @ | @ | @ | @ |
| 133 | @ | @ | 133 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 134 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 134 | @ |
| 135 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 135 | @ |
@uFOYvçªdêÉ~èÄ¢«Au¨~vÆuÑövƪb·ÓÅ éB
@u¨~vªuYvÌsæð·ÆAuÑövÍuqvÉï¢É¢Á½Æ¢¤B»êð·¢Äví¸Î¢oµ½u¨~v¾Á½ªAuFOYvÍuËRÓµ¢çðµÄévB±±ÅàAuFOYvÆu¨~vA é¢ÍuÑövâuYvðÜß½OlÆÌÓvÌáªA«¤èÆÈéBu¨~vÉÆÁÄΦébàA̲ª««Édð±È¹È¢uFOYvÉÍΦȢA é¢ÍΤ]TÍÈ¢BܽAueûvÅ éuFOYvªÌ²ðöµÄ¢ÄXªåÏÈóµÅ éÉà©©íç¸Auqv̳ÖsuYvâA»êð©ß²µ½uÑövàA¯lÉuFOYvªl¦Ä¢éóµÆÍ·x·ª éB
@±±ÅÍAÇÌìl¨ÉàuS`ÊvÍÝçêÈ¢B±êÜÅÌæ¤ÉAìl¨ÌàÊðÎäIÉ`¢Ä¢éÌÅÍÈAuFOYvƻ̼Ììl¨ÆÌOÊÌÝðÎ䳹ĢéÌÅ éB
@u136नXðdÓñ¾©ç¨AèÂÄv
@u137ܾ¢æv138iajFOYÍibj³Ó¡Éicj½Îµ½B139¨~ÍÙÂĹ½B
@140FOYÍu¬nß½B141¿ÁĽ©çÍ]öHª¢¢B
@142¨~ÍÈüê̼ZðæÂÄÄAqÅà¾Ü·â¤É]ÂÄAQèðʳ¹AâÂÆÀSµ½Æ¢Óâ¤ÉãèyÉð©¯ÄA궽Éu¢ÅîéFOYÌçð©Ä½B143ÑöÍÌTÌqÌ|Åðøâ¤ÉµÄÑàÈ¢ãøðäèã°½èä躵½èµÄ½B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| uFOYv | »Ì¼Ìl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||||
| 136 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 136 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 137 | 136 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 138 | @ | 138iaj icj |
@ | @ | 138ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 139 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 139 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 140 | @ | 140 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 141 | @ | @ | @ | 141 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 142 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 142 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 143 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 143 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@ÂXªÁÄ¢é½ßAu¨~vÍuYvðÄÑÉsæ¤ÉuÑövɾ¤Bµ©µAuFOYvÍAu³Ó¡É½Îv·éB
@138¶ibjÌu³Ó¡ÉvÍAuFOYvÌàÊÉ_ªu©êÄ¢éBXðà¤ÂßÄࢢÔÑÅ é±ÆÍuFOYv©gà¹ðµÄ¢éÉà©©íç¸A»êðñĵ½u¨~vÉεÄu³Ó¡Év½µÄ¢éB̲̫³ÉÁ¦ÄAüèÌl¨½¿ÆÌêêªAÞðu³Ó¡É½Îv³¹½ÌÅ ë¤B
@±êÉÁ¦ÄA±±Åàu³Ó¡É½Îv·é±ÆÅAÕXµ¢Cªð¢ç©Åà°ç»¤ÆµÄ¢éB±¤µÄA̲ªßèͶßÄ¢é±Æà èAuFOYvÍuHªvæÈéBüèÆÌÓvÌaÊÍ\ªÅÈ¢àÌÌA»ÌÕXµ³ðgàÉÔ¯é±ÆÅuFOYvÍæÉÕXµ¢CªððÁµÄ¢éƾ¦éB
@±êçÌüèÌl¨½¿ÆÌuêêvÍAuFOYvÆuêêvð¤Ý¾µÄ¢éàÌÅ ÁÄàA¼Ú½·é±ÆÅA éöx·®ÉðÁµÄ¢éÆ¢¤±ÆÅ éB
@ܽAiƯ¶æ¤Édêŧ¿ãªÁÄuävðu®±ÆÅAuävðÄÑuFOYv̧äºÉu±ÆªÅ«éæ¤ÉÈÁÄ¢éB®SÉ·×ÄÌuêêvªæè©ê½í¯ÅÍÈ¢ªAuFOYvÌCªÍÀèðæèߵ éB
@êÊVÅÍA¢Á½ñCªªßèͶ߽êÊU©çAuFOYvÍܽÕXªåèͶßÄ¢éB»êÍâÍè̲ª«¢Éà©©íç¸A«Éuävðu®±ÆªÅ«È¢±Æð[ƵÄAuFOYvÆAÞðÆèÜl¨½¿ÆÌÓvÌH¢á¢àAÞÌÕXµ¢CªÌ´öÆÈÁÄ¢éBuävª§äsÂ\É×Áĵܤ±ÆÅàAuêêvª¤ÜêAÕXµ¢Cªðåç¹éBµ©µAêÊVÅÍA»êçÌuêêvªµæè©êé±ÆÉæÁÄAuFOYvÌCªÍÀèðæèߵ éB
yêÊWz
144iajiCæÉqËðJ¯Äibj¹¢Ìá¢ñ\ñOÌicjáÒªü½B145Vµ¢ñ ÀqÌ¿ÉOÚðOÅÑAO@ÌPÉÂܽîºÊðË|¯ÄîéB
@u146UbgÅæ²´ñ¸ªAêÂå}¬Å ½ÂÄ ¨ñȳ¢v147©¤]ÐȪ碫Èè¾ÌOɧÂƺOðñÅèóðËoµAµÖ½wæÅpèÉ´ÓðŽB148áÒÍCLªÂ½ûÌ««â¤¾ª²qÍcÉÒŠ½B149ßê§Â½wâA¢Ê̽¢ç©çAÍr¢JÉ¢ÄîéҾƢӪmçê½B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| uFOYv | »Ì¼Ìl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||||
| 144 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 144iaj icj |
144ibj | @ | @ | @ | @ | @ |
| 145 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 145 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 146 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 146 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 147 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 147 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 148 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 148 | @ |
| 149 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 149 | @ |
@Âßé©ÂßÜ¢©Æ¢¤ÔÌuFOYvÌXÉAuáÒvª»êéB
@±±ÅÍAuqÒ\»vÌuà¾vÌqÉæÁÄAuáÒvÌÁ¥ª¦³êéBãÌqð¥Ü¦Äl¦éÈçAuFOYvÌߢÊuÉ_ªu©ê½uqÒ\»vÆàl¦çêéBµ©µ±±ÅÍAq©çl¦êÎAÁèÌN©©çÌÁ¥ÅÍÈANÉÅàucÉÒvÌuÍr¢JÉ¢ÄîéÒvÅ éÆ¢¤Á¥ðËõ¦½uáÒvÅ éÆ¢¤l¨ÆµÄAuqÒ\»v³êÄ¢éÌÅ éB
@»ÌÁ¥ªuFOYvÉÆÁÄäÈç¢æ¤ÉÈéÌÍA±êÈ~Å éB149¶ÌuáÒvÌÁ¥ÍA¼ÚuFOYvÆuêêvðN±·¶ÝÅÍÈ¢B»êÍuFOYvªDê½ElÅ é±ÆÅà t¯çéBXðC¹çêéÙÇÌl¨Å éuFOYvÍAiÅ êÎAqÌçÉæÁĵCªªQ³êé±ÆÅ質¶Á½èAs@ÉÈÁ½è·éæ¤ÈElÅ éÆÍl¦ª½¢B
@u150iaj³ñÉvibjƨ~ÍáàêÉ©µÄ½¶½B
@u151¨¢ç ªâéæv
@u152¨O³ñÍ¡úÍèªk¦é©çccv
@u153iajâéævibjÆFOYÍs³Ö¬Â½B
@u154iajǤ©µÄéævibjƨ~ͬºÅ]½B
@u155d ¾v
@u156Ǥ¹A ½é ¾¯ÈçÑÉàÈçÈ¢©ç´ÔŨµÈ³¢v157¨~ͼZðEªµ½È©Â½B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| uFOYv | »Ì¼Ìl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||||
| 150 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 150iaj | 150ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 151 | 151 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 152 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 152 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 153 | 153iaj | 153ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 154 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 154iaj | 154icj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 155 | 155 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 156 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 156 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 157 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 157 | @ | @ | @ | @ |
@u¨~vª~ßéOÉAuFOYvªuáÒvÌEðäéƾ¢o·ÓÅ éB
@«Éäàu°È¢uFOYvÉAu¨~vÍEðä繽ȩÁ½½ßuYvðÄÑÉsæ¤É¾¤Bµ©µAuFOYvÍ»êðÕèAd
ðÁÄéæ¤É¾¤BuFOYvÉÆÁÄAucÉÒvÌuáÒvðäéç¢Ì²ª«Æà±È¹éÆl¦éBêûAu¨~vÍAáÌ¢vÌ«iÆ̲Æðl¦A¹ßļZð
¹½ÜÜdð·éæ¤É¾¤B
@±±ÅàA ÜÅdðµæ¤Æ·éuFOYvÆA»êðÈñÆ©~ßæ¤Æ·éuÂ~vƪΧµÄ¢éBܽqàAuêÉ©µÄvu¨~ͼZðEªµ½È©Â½vÆu¨~vÌàÊÉ_ªu©êÄAuFOYvÆÌÓvªÎä·éæ¤É`©êÄ¢éBu¨~vÆuFOYvÆÌl¦ªuêêvð¤Ý¾µÄ¢éB
@158iajÈçðµÄñlð©r×Äî½áÒÍA
@uibjeûAaCÅ·©vicjÆ]ÂĬ³¢ñ¾áðZÑéâ¤ÉV{^_³µ½B
@u159¦¦Aµ×ðТ¿âÂÄccv
@u160«¢×ª¬séÂÄ]ÐÜ·©çApSµÈ¢Æ¢¯Ü¹ñºv
@u161 誽¤v162FOYÍû¾¯Ìçð]½B
@163iajFOYª¢zðñÖ|¯½AibjáÒÍuicjUbgÅ¢¢ñÅ·ævidjƢ½B164iaj»µÄuibjµ}¬Ü·©çlvicjƯÁÖÄÎÐðµ½B165FOYÍÙÁÄrÌ ÅA¡u¢¾nðaç°Ä½B
@u166\¼ÆA\ê¼ÉÍs¯éÈv167±ñÈð]ÓB168½Æ©]ÂÄáн¢B
@169FOYÉÍAj©©ªçÈ¢â¤ÈºðoµÄîé¬Y®Ì«½È¢ª¼®áÉ©ñ¾B170ÅAºi£Â½¬jª¥©ç´Ös̾ÆvÓÆA¹ÌÞ©Ââ¤ÈV[ªã©ç^_ÞÌãµ½ªÉ©ñÅéB171ÞÍâßؽÅV{ð¯Aâ¯ÉSV^_èó©çjÌ ½èðC½B172´ÔàáÒ;ɿçַ驪Ìçð©æ¤Æ·éB173FOYÍvÐؽÅãÅà ѹ©¯Äâ轩½B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| uFOYv | »Ì¼Ìl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||||
| 158 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 158ibj | 158iaj icj |
@ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 159 | 159 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 160 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 160 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 161 | 161 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 162 | @ | 162 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 163 | 163iaj | @ | @ | @ | @ | @ | 163ibj | 163icj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 164 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 164ibj | 164iaj icj |
@ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 165 | @ | 165 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 166 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 166 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 167 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 167 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 168 | @ | @ | @ | @ | @ | 168 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 169 | @ | @ | @ | @ | @ | 169 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 170 | @ | @ | @ | @ | @ | 170 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 171 | @ | 171 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 172 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 172 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 173 | @ | @ | @ | @ | 173 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@̲̫¢uFOYvÍAy¢²qÅbµ©¯ÄéuáÒvÉεÄAÕ§¿ðåç¹Ä¢B
@̲ª«ÆàAdÉεÄèð²¯È¢uFOYvÉεÄAuáÒvÍy¢²qÅbµ©¯ÄéB»Ì½ßAuáÒvÌ160¶Ìu«¢×ª¬séÂÄ]ÐÜ·©çApSµÈ¢Æ¢¯Ü¹ñºvÆ¢¤¾tÉàAuFOYÍû¾¯Ìçv𾤾¯Å¸êtÈÌÅ éi162¶jB³çÉAuáÒvÉÆÁÄEäèÆ¢¤dªy¢àÌÆl¦Ä¢é½ßA163¶icjuUbgÅ¢¢ñÅ·ævA164¶ibjuµ}¬Ü·©çlvÆybµ©¯AuÎÐv³¦©¹éBµ©µAuFOYvÉÆÁÄ©Å èAdÉεÄæð·±ÆªÅ«È¢EäèÆ¢¤dðAuUbgvÏܵ½èA}¢ÅäÁĵܤ±ÆÈÇÅ«È¢BEäèÆ¢¤dÉηéAuáÒvÌÔxªuFOYvÌElC¿Ì«iðtÈÅ·é±ÆÉÈéB
@³çÉA±Ìæ¤ÈuáÒvÌy¢Á¥ðàÆÉAuFOYvªzµÜ·Ü·ÕXµ¢CªÉÈÁÄ¢B̲ª«¢ÌÉà©©íç¸JÉdðµæ¤ÆµÄ¢éuFOYvÆAu¬Y®vÉVÑÉsæ¤ÉzÅ«éuáÒvƪAuêêvÆÈÁÄ¢B ÜÅuFOYvÉÆÁÄÌuáÒvÅ éªAÕXµ¢CªÉ³¹éuêêvð¤Ý¾·àÌÅ é±ÆÉÏíèÍÈ¢B
@¾ªA±ÌuáÒvÍqÅ é½ßA±êÜÅƯ¶æ¤É¼ÚèÉü©ÁÄ«Ôð±ƪūȢB173¶Ìæ¤ÉuvÐؽÅãÅà ѹ©¯Äâ轩½vÆvÁ½ÆµÄàA»êÍuâ轩½vÅ èAÀÛÉÅãðѹ©¯é±ÆÍÅ«È¢B±êÜÅAgàɶåð¾¢ú±ÆÅA¢ç©ðÁÅ«Ä¢½ÕXµ¢CªàAqÅ éuáÒvÉÍ»êàÅ«¸ÉA~ϳêÄ¢ÌÅ éB
@168¶ÍAu½Æ©]ÂÄáн¢BvÆ¢¤uS`ÊvÅ éBµ©µA½¾u½Æ©]ÂÄáн¢BvÆq³êÄ¢éÌÝÅANÌuS`ÊvÅ é©A¾mɦ³êÄ͢ȢB±ÌêÉ¢éÌÍAuÑövu¨~vuáÒv»µÄAuFOYvÅ éBOã̶¬©ç¾¦ÎAuÑövÆu¨~vªu½Æ©]ÂÄáн¢vÆv¤ÌÍs©RÅ éB¦¿A±ÌuS`ÊvÍuáÒv©uFOYvÌàÊð`ʵ½àÌÆ¢¤±ÆÉÈë¤B
@àµAuáÒvÌuS`ÊvÆl¦éÈçÎAÌæ¤ÉÈë¤Bµ«èÉbµ©¯éuáÒvªAÙÁÄ¢éuFOYvɽ©ÔµÄÙµ¢AÆ¢¤Ó¡Åu½Æ©]ÂÄáн¢BvÆv¤ÌÅ éBucÉÒvÅAµ©à±ÌuFOYvÌXɽ̪ßÄÅ éÆl¦çêéuáÒvÉÆÁÄAuFOYv̽¾Èçʵµ¢µÍCðaç°½¢Æl¦½AÆðßÅ«éÌÅ éB
@êûAuFOYvªu½Æ©]ÂÄáн¢BvÆl¦½Æ·êÎAÇÌæ¤Éà¾Å«é¾ë¤©B±ÌêA ÜèÉy¢û²Åbµ©¯ÄéuáÒvÉεAuFOYvªuवÜÆàȱÆð¾ÁÄà碽¢vÆvÁ½ÆðßÅ«éB é¢ÍA±ÌêÉ¢éu¨~v©uÑöv©ÉA±Ìy¢²qÅbµ©¯ÄéuáÒvÉεÄA¶åÌêÂÅà¾ÁÄÙµ¢AÆvÁ½Æ¢¤ðßà¬è§ÂB
@±Ì168¶ÌuS`ÊvÉ¢ÄATäç¾i2003jÅÍA
êèèÌ_Í»ÌwñǪFOYÉu«·¦é±ÆªoéàÌÌA¨~âcÉoÌqÉdÈÁÄ¢é±Æà éB±Ìê³êĢȢêèûðÛèIɨ¦éÌÅÍÈA»¤¢Á½êèûª¦·ÌÍÞµëFOY¾¯ÉìiªÅ_»³êé±ÆÌÈ¢àÌÆ¢¦È¢¾ë¤©B
iºüøpÒB
Täç¾i2003juuê¼Æuäv_\\qA`EÆ߬àr\\v
wbìqåwåw@_W@¶w¶»¤Òxn§j
ÆAu©êé_É¢ÄwEµÄ¢éÓÅAºüÌßƵÄAȺÌæ¤É¾yµÄ¢éB
ïÌIÉÍA¨~Ìu»êÌâ¦ÊàÉH׳¹½¢Æv½ªæêØÂÄ°ÂÄîéàÌðNµÄs@É·éÌàÆlÖAT¦Ä½BvâAqÌu½Æ©]ÂÄáн¢BvÈÇÌÓÅ éB
iTäç¾i2003jj
ÂÜèAu½Æ©]ÂÄáн¢BvÍATäÍuqvÌSA·Èí¿uáÒvÌuS`ÊvÅ éÆl¦Ä¢éB
@¾ªAuáÒvÌuS`ÊvÆl¦çêéàÌÍA±êÈOÌqÉÍÈ¢B±Ìu½Æ©]ÂÄáн¢BvÆ¢¤q¾¯ªuáÒvÌàÊÉu©ê½_©çAuS`Êv³ê½àÌÆÍl¦É¢Bµ©àAu½Æ©]ÂÄáн¢AÆáÒÍvÁ½vÆ¢Á½`ÊÅÍÈAu½Æ©]ÂÄáн¢BvÆ¢¤SÌàe¾¯ª`ʳêÄ¢éÆ¢¤qÅ éB»ÌOãÍuFOYvÌàÊÉu©ê½Í¸Ì_ªA¢«Èè168¶Ìu½Æ©]ÂÄáн¢BvÆ¢¤q¾¯ªuáÒvÌàÊÉÏíéÆ¢¤ÌÍAs©RÅ ë¤B é¢ÍA±Ìu½Æ©]ÂÄáн¢BvÆ¢¤qªAêÂÌqÅuáÒvuFOYv¼ÒÌàʪ¦³ê½àÌÆl¦éÌ೪ éB
@±ÌqÍâÍèuFOYvÌuS`ÊvÆl¦½Ù¤ªÃÅÍÈ¢¾ë¤©BuFOYvª¢çu½Æ©]ÂÄáн¢BvÆl¦ÄàAâÍèqÌuáÒvÉεļÚu½Æ©]v¤±ÆÍÅ«È¢ÌÅ éB±ÌÓÅÍAuáÒvÉÕXµ¢Cªðåç¹Ä¢uFOYvÌàÊÉ_ªu©êAuS`Êv³êéÌÅ éi168`170¶A173¶jB
@174FOYÍäðà¤êxL ^_âÂÄæÃA©çäènß½ªAǤàvÓâÓÉØêÊB175èàkÖéB176»êÉQÄîÄÍ»êöÅàȩ½ªAN«Ä©¤ëüƼ® ¤ªêÄéB177Xäéèð~ßÄ@¯êǼ®@ÌæªY^_µÄÄÍH賤ÉéB
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| uFOYv | »Ì¼Ìl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||||
| 174 | @ | 174 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 175 | @ | 175 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 176 | @ | 176 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 177 | @ | 177 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@»êÅàElC¿ÌuFOYvÍAuáÒvÌEðäë¤Æ·éBµ©µA̲ª·®êÈ¢uFOYvÍAqÌçð̼«±Þ̨ðÆÁ½±ÆÅA³çÉ«»³¹éB±±ÅàAuFOYvÌàÊÉu©ê½_©çÌqÉæÁÄAdðµÈ¯êÎÈçÈ¢óµÅ èȪçA̲ª««É±È¹È¢Æ¢¤uêêvªÄѤÜêéB
@̲ª«ÆàAdÉæð³È¢uFOYvÌv¢ÆÍtÉAuävÆuêêvðN±µnßéB±ÌqÅÍA174¶uǤàvÓâÓÉØêÊvA175¶uèàkÖévƧäs\ÉÈÁ½uävÆ»Ìè³ðqµ½ ÆA176¶u»êÉvu¼®
¤ªêÄévÆA̲̫³ª»êÉYÁ³êé`ÌqÉÈÁÄ¢é±ÆÅ éB̲ª«¢½ßÉuèàkÖévÌÅÍÈAuǤàvÓâ¤ÉØêÊvAuèàkÖévãÉAu»êÉv̲ૢAÆ¢¤ÈÌÅ éB
@±±ÅÌqÌ«Ìt]ÍAdv³êé׫Šë¤BêÊUÌ69¶ÅÍuMÅèªkÖĽ©çAǤµÄàvÓâ¤Éu°È©Â½vÆu°È¢RªuMÅèªkÖév±ÆƵĦ³êÄ¢½ªA±±ÅÍtÉÈÁÄ¢éÌÅ éB±êÍAuFOYvðÆèÜuêêvªA̲ª«¢Éà©©íç¸Adð±È³È¯êÎÈçȢƢ¤uêêv¾¯ÅÍÈÈÁÄ«Ä¢é±Æð¦µÄ¢éBuävðµ¤rðͶßÆ·égÌ´oÆuFOYvÌÓvƪuêêvðN±µÍ¶ßÄ¢é½ßÉAuävð§ä·é±ÆªÅ«ÈÈÁÄ«Ä¢éÆ¢¤±ÆɼÈçÈ¢B
@178ÅÔÌeºªµ½ÌÅA¨~ÍüÂÄs½B
@179ØêÈ¢äÅäçêȪçàáÒͽCÈçðµÄéB180ÉàáyàÈ¢Æ]ÓÅ éB181´³_o³ªFOYÉͳÅÆáÉG½B182iajgЯÌØêéäªÈ¢ÅÍȩ½ªibjÞÍ»êÆXÖâ¤Æ͵ȩ½B183Ǥ¹½Åà©ÜÓàÌ©Æ¢¤CÅ éB184»êÅàÞÍsmJÉȽB185µÅà´ç¯ÎAǤµÄà´É±¾Íç¸ÉÍîçêÈ¢B186±¾Íêα¾ÍéöááªNÂÄéB187©ç¾àiXæêĽB188MàåªoĽâ¤Å éB
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| uFOYv | »Ì¼Ìl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||||
| 178 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 178 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 179 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 179 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 180 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 180 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 181 | @ | @ | @ | @ | 181 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 182 | @ | 182ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 182iaj | @ |
| 183 | @ | @ | @ | @ | @ | 183 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 184 | @ | 184 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 185 | @ | @ | @ | @ | 185 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 186 | @ | @ | @ | @ | 186 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 187 | @ | @ | @ | 187 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 188 | @ | @ | @ | 188 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@̲ª«A«É䪵¦È¢óÔÅ ÁÄàuFOYvÍAuáÒvÌEðäé±ÆðâßÈ¢B«ÉäêĢȢÉà©©íç¸A»êÉÍCé¸É179¶uáÒͽCÈçðµÄvA180¶uÉàáyàÈ¢Æ]ÓvÔxªA³çÉ181¶uFOYÉͳÅÆáÉGvé±ÆÉÈéBuFOYvÌêµÝðmé͸ÌÈ¢uáÒvÌÔxÍAuFOYvÌdÉèð²©È¢l¦ûÆuêêvðN±·ÌÅ éB
@¾ªAuFOYvÍAØêÈ¢uävðèú»¤ÆµÈ¢Bu²¤ÆµÄàCæu°È©Á½u³yÌRcvÌuävðg¢±¯éÌÅ éB»ÌSÍuǤ¹½Åà©ÜÓàÌ©Æ¢¤CÅ évBuFOYvÍAElƵÄÌâÃÈ»fÍð¸¢AdÉεļñ´¢ÈÓ¯ÉÈÁÄ¢B¾ªA»êÅàu±¾Íç¸ÉÍîçêÈ¢vuFOYvÍAÜ·Ü·ááðN±µÄ¢±ÆÉÈéBäêÈ¢uävð©¦æ¤ÆµÈ¢ÌÍAuFOYv©gÌ»fÅ èȪçAäêÈ¢±Æɱ¾í豯AááðN±µÄ¢Æ¢¤«zÂðA©çÉæÁÄø«N±µÄ¢ÌÅ éB
@±±ÅàA187¶u©ç¾àiXæêĽvA188¶uMàåªoĽâ¤Å évÆ̲̫³ªAEª«ÉäêȢƢ¤qÌãÉA¦³êÄ¢éB
@±êçÌÕXµ¢CªâAuáÒvÌáÉGéÔxÍA·×ÄuFOYvÌàÊÉu©ê½_©çq³êÄ¢éB
@189iajŽÌÞÌbµ©¯½áÒÍibjFOYÌs@É°êÄicjÙÂĹ½B190»µÄzðäéªÉÍÌóµ¢J©çéæJŤÂç^_dnß½B191ÑöàÉßÂÄ°ÂÄéB192àÔð¾Ü·ºª~ñÅAлèÆȽB193éÍààOàSÃÜèÔ½B194ä̹¾¯ª·¦éB
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| uFOYv | »Ì¼Ìl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||||
| 189 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 189iaj icj |
@ | 189ibj | @ | @ | @ | @ |
| 190 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 190 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 191 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 191 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 192 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 192 | @ | @ |
| 193 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 193 | @ | @ |
| 194 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 194 | @ | @ |
@uáÒvÌаðäènßĵÎç·éÆAuFOYvÆuáÒvÈO̶Ý𦷹ªÁ¦ÄA ½èÍÃâÉïÜêÄ¢B±¤Èé±ÆÅAuFOYvÍuä̹¾¯vð·±ÆÉÈéBuFOYvÌÓ¯ÍAuáÒvÌEðäé±Æ¾¯ÉWµÄ¢ÌÅ éB
@ ½èªÃÜ試é±ÆÅAuFOYvÉÓ¯³êéi é¢ÍuFOYvªÓ¯Å«éj¹ÍAuä̹¾¯vÉÈÁÄ¢BuFOYvÌÓ¯ÉÍAuävª©ªÌÓvɽµÄäêȢƢ¤´o¾¯ÉÈÁĢƢ¤±ÆÅ éB ½èªÃâÉïÜêé±ÆÉæÁÄA«ÉEðäêÈ¢Aµ©µ»ÌªÉ±¾íç¸ÉÍ¢çêÈ¢AÆ¢¤«zÂÌÉAuFOYvͶßçêĵܤB»µÄAuävÌäêÈ¢¹ÈOÉA¼ÉÓ¯·éÎÛªÈÈÁĵܤÌÅ éB
@195iajÕXµÄ{轩½CªÍ«½¢â¤ÈCªÉÏÂÄibj¡ÍgàCàSæêĽB196áÌÍMÅn¯³¤É¤éñÅîéB
@197ô©çjAèóAzÈÇðä½ãAôÌ_©¢ªªÇ¤µÄà¤Üs©ÊB198±¾Íèsµ½ÞÍ´ªðç²Æí¬æè½¢â¤ÈCªµ½B199iaj§Ìr¢êÂ^_ÌÑÉûªÂÄéâ¤Èçð©ÄéÆibjÞÍ^Ý©ç»ñÈCªµ½ÌÅ éB200áÒ͢©°üÂĹ½B201ªèÆãÖñðཹĽí¢àÈ¢ûðJ¯ÄéB202sµÐÈAæ²ê½ª©¦éB
@203æêؽFOYÍÄàNÁÄàçêÈ©Á½B204ÄÌÖßÉÅÅà³ê½â¤ÈSªµÄîéB205½àÞà°oµÄ´ÜÜ´Ö]°½¢â¤ÈCªÉȽB206à¤æ³¤I@207©¤ÞͽÕv½©mêÈ¢B208RµÄ«IÉËR±¾ÍÂĽB
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| uFOYv | »Ì¼Ìl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||||
| 195 | @ | @ | @ | 195ibj | 195iaj@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 196 | @ | @ | @ | 196 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 197 | @ | 197 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 198 | @ | @ | @ | @ | 198 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 199 | @ | @ | @ | 199iaj | 199ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 200 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 200 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 201 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 201 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 202 | @ | @ | @ | 202 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 203 | @ | @ | @ | @ | 203 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 204 | @ | @ | @ | 204 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 205 | @ | @ | @ | @ | 205 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 206 | @ | @ | @ | @ | @ | 206 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 207 | @ | @ | @ | @ | @ | 207 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 208 | @ | 208 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@uFOYvÍ̲̫³ÉÁ¦ÄAuáÒvÌEð¤Üäé±ÆªÅ«È¢±ÆÅAÕXµ¢Cª©çAu«½¢â¤ÈCªÉvÈéB»µÄAu±¾Íèsµ½ÞÍ´ªðç²Æí¬æè½¢â¤ÈCvÜÅàµÄéB
@uävðÂèÌ´o¾¯ÅÍÈA196¶uáÌÍMÅn¯³¤É¤éñÅvéæ¤ÉAoÜÅàªDíêÄ¢B¾ªA»êÅàäéÌðâßæ¤Æ͹¸ÉA198¶uç²Æí¬æè½¢vÆ¢¤zÜÅ·éæ¤ÉÈéBêûAËRƵÄuáÒvÍ»ÌuFOYvÌص½óµðmç¸ÉA201¶u½í¢àÈ¢ûðJ¯ÄvQÄ¢éÌÅ éB»Ì³_oÈÔxð©ÄàAuFOYvÍqÅ éuáÒvÉεÄA»Ìu«½¢â¤ÈCªvð¼Ú½©¾¤±ÆÍÅ«È¢ÌÅ éB
@âªÄAuFOYvÍuävð§äÅ«ÈÈéΩèÅÍÈA204¶uÄÌÖßÉÅÅà³ê½â¤ÈSªµÄvASgÌgÌ´oð¸ÁÄ¢B
@209ccnª`bÆЩ©éB210áÒÌôªsNbÆ®¢½B211ÞͪÌæ©ç«ÌÜæÜŽ©¢àÌɲ¯çê½â¤É´¶½B212ÅA´¢àÌÍÞ©çÄÓÆæJÆðæÂÄsÂĹ½B
@213ÍÜÐöàÈ¢B214ÞÍü»êð©lßħ½B215íªê½ÕÍÅûFðµÄ½ªAabÆW¢gªÉ¶ÞÆA©é^_ª·èãÂĽB216ÞÍ©lßÄî½B217ª¸ñÅ `É·èãªÂĽB218»êª¸_ÉBµ½É ÍöêÄXCÆêÄØɬê½B219ÞÉÍêíÌrXµ¢´îªN½B
@220¦ÄqÌçð¯½Ìȩ½FOYÉÍA´îªñíȳÅÂĽB222ÄzÍiXZµÈÈéB221ÞÌSgSSÍSÉzÐÜê½â¤É©¦½B223¡ÍǤÉà»êÉſªoÈȽB224ccÞÍäðtèÉ¿©ÖéÆ¢«È订Æôðâ½B225nª·Â©èBêéöÉB226áÒÍgã¦àdȩ½B
@227ê¡Ôðu¢ÄªçµéB228áÒÌçÍ©é^_yFÉϽB
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| uFOYv | »Ì¼Ìl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||||
| 209 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 209 | @ | @ | @ |
| 210 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 210 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 211 | @ | @ | @ | 211 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 212 | @ | @ | @ | 212 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 213 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 213 | @ | @ | @ | @ | @ |
| 214 | @ | 214 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 215 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 215 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 216 | @ | 216 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 217 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 217 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 218 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 218 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 219 | @ | @ | @ | @ | 219 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 220 | @ | @ | @ | @ | 220 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 221 | @ | 221 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 222 | @ | @ | @ | 222 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 223 | @ | @ | @ | @ | 223 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 224 | @ | 224 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 225 | @ | 225 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 226 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 226 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 227 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 227 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 228 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 228 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@uFOYvÍ¢Éð¯ĵܤBµ©µA±±ÅÌqÍÁ¥IÅ éB209¶uccnª`bÆЩ©évÆ èAuЩ¯½vuЩ¯évÅÍÈAuЩ©évÆ èAuävðèÉÁÄ¢é͸ÌuFOYvÌÓvÆͳÖWÉ𯽩Ìæ¤Éq³êéB ½©àunvâuävªÆ©ÌÓuðLµÄ¢é©Ìæ¤ÉuЩ©évÌÅ éBܽAu²¯çê½â¤É´¶½v èA±±ÅàuFOYvÌÓvÆͳÖWÉN±Á½Ï»Ìæ¤Éq³êÄ¢éB
@219¶uêíÌrXµ¢´îªN½vA220¶u´îªñíȳÅÂĽvA221¶uSÉzÐÜê½â¤É©¦½vA223¶uǤÉà»êÉſªoÈȽvÆA ½©àuFOYvÆÍSÖWÌÈ¢ÍÌìpÉæèElɱ©êÄ¢©Ìæ¤ÉAq³êÄ¢éB»µÄAÁÄ¢½uävÅuáÒvðEµÄµÜ¤ÌÅ éB
@±Ìæ¤ÉAuäv𵤱ÆÉ©¯Ä¼l¾Á½uFOYvÍAuävð§äµ«êÈÈèA©çÌÓuÆuêêvðN±µ½ÊAuáÒvðEµÄµÜ¤Bê{ÌuävªAgÌ´oð¸Á½uFOYvÌÓvɽµÄAElɱ©êÄ¢ÌÅ éBuFOYvª©ç«zÂð¤Ý¾µ½±ÆÍm©Å éªA»ÌuFOYvÌÓvÆͳÖWÉuáÒvðEµÄµÜ¤ÌÅ éB»ÌqÍAuFOYvðÁQÒƵÄÅÍÈAElÉ
@uáÒvðEµÄµÜ¤¼ÚÌ«Á©¯ÆÈÁ½ÌÍAͶßÄqð¯ĵÜÁ½Æ¢¤±ÆÅ éBµ©µAElÖ±©êÄ¢´öÍAuFOYvÌÕXðåç¹é±ÆÉÈÁ½lXÈuêêvÌèԵŠéB
@229FOYÍwǸ_µÄ|êéâ¤ÉTÌÖqÉðµ½B230ÄÌÙ£ÍêÉÉÝA¯ÉÉxÌæJªÒÂĽB231áðËÞÂĮ½èƵÄéÞÍlÌlÉ©¦½B232éàlÌlÉÃÜè©Ö½B233ÄÌ^®Íâ~µ½B234Ą̈Í[¢°èÉ×½B235üÆè¾¾¯ªOû©çââ©Éõið߼B
| ¶Ô | Î@Û@\@» | qÒ\» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l@¨@`@Ê | ¨`Ê | ྠ| ðß E ]¿ | |||||||||||
| uFOYv | »Ì¼Ìl¨ | ®Ô`Ê | ÃÔ`Ê | |||||||||||
| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||||
| ´o | Sî | vl | ||||||||||||
| 229 | @ | 229 | @ | @ | @@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 230 | @ | @ | @ | 230 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 231 | @ | @ | 231 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 232 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 232 | @ | @ | @ |
| 233 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 233 | @ | @ | @ |
| 234 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 234 | @ | @ | @ |
| 235 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 235 | @ | @ |
@uáÒvðEµÄµÜÁ½uFOYvÍA|êéæ¤ÉÀèÞÆ¢¤Æ±ëÅwäxÍIíéB
@uáÒvðEµ½uFOYvÍADíê½æJªêCÉuÒÂÄvéB231¶uáðËÞÂĮ½èƵÄéÞÍlÌlÉ©¦½vÆ èA_ÍuFOYvÌàÊ©ç£êAÁèÌìl¨ÅÍÈ¢uqÒvÉßéBÄÑA232¶uéàlÌlÉÃÜè©Ö½vA233¶uÄÌ^®Íâ~µ½vA234¶uĄ̈Í[¢°èÉ×½vÆÃâªu¨`Êvu®Ô`Êv³êéB»µÄA235¶ÅÍuüÆè¾¾¯ªOû©çââ©Éõið߼vÆA_ªl¨ÅÍȨÌÅ éu¾vÉu©êAq³êéB»êÜÅuFOYv©u¨~v©Æ¢¤ìl¨Éu©êÄ¢½_ªA±±ÅÍli³¦àÁĢȢu¾vÉÏíÁÄ¢éÌÅ éB
@±Ìu¾vÉu©ê½_É¢ÄAgìªîi1989juuê¼Æwäxðß®éK\\¶wÖÌðú^¶w©çÌðú\\viwwpxæ461989N3jÅÍAÌæ¤ÉwE³êÄ¢½B
@
»ÌqÏ«ÌgUè̺Åл©É²³êéÌÍAOEÆÚGµ½´o̶Xµ¢®«Å èAgÌ«ð[Öíç¹½´«Ì_È̾BgUèÍgUèÌÜÜÅ èAFOYÌ`ÛàAElÆ¢¤_IÈ`[tà»±ÅÍâèÉÈçÈ¢BÉà©©íç¸ÅIIÉñ¦³êéÌÍA çäé_ðÝèɵÄAElÉÜÅ¢½é±¤µ½SgÌ´oðAlÔÉÍXɵı¤µ½sÈÔªN±éÆ¢ÁÄÜÆßĵܤqqÏ«rÈÌÅ éB»±É éÌÍÕ«Ìçðµ½âλ³ê½åÏɼÈçÈ¢B
iºüÍøpÒBȺ¯¶B
gìªîi1989juuê¼Æwäxðß®éK
\\¶wÖÌðú^¶w©çÌðú\\vwwpxæ46j
uFOYvÌåÏIÈugÌ«ð[Öíç¹½´«Ì_vÉæéElðAu¾vÆ¢¤¨ÌÉ_ªu©êé±ÆÅAulÔÉÍXɵı¤µ½sÈÔªN±éÆ¢ÁÄÜÆßĵܤvÆ¢¤uqÏ«vðwE·éBµ©µA»êÍuqÏvIÅ èȪçAÀÛÉÍuâλ³ê½åÏvÅ éÆ¢¤ÌÅ éB
@µ©µA±Ìu¾vÉ_ªu©êé±ÆÍAuqÏvuåÏvÆ¢¤ñΧÅÆç¦çêéàÌŠ뤩Bu¾vÍPɨÌÅ èAγ·éoð»ÌÜÜfµo·àÌŵ©È¢BuFOYvÉÆÁÄuqÏv©AuFOYvÌuåÏv©Æ¢¤Î§ÅÍAwäxÆ¢¤ìiÍÆç¦çêÈ¢ÌÅÍÈ¢¾ë¤©BÅÍAÅãÌ235¶Å_ªu¾vÉu©êéÓ¡ÍÇ±É é̾뤩B±êÍæTÅAÁ¥IÈqÆÆàÉAl@ð[ßéB
@±Ìæ¤ÉAwäxÅÍAuFOYvªAlXÈuêêvÉæÁÄElÖƱ©êÄ¢SÌßöð`¢½ìiÅ éB»ÌuêêvÉæÁĤÜê½ÕXµ¢CªªA«zÂÌųêAElÆ¢¤ÉéÌÅ éB
@»Ìuêêvð¤Ý¾·uFOYvª`o³êÄ¢qÌÁ¥ÆAu©êé_ÌϻɢÄAÅl@ð[ßé±ÆÆ·éB
@{ÅÍæSÜÅɾçê½wäxÌl@ÊÉÁ¦ÄA³çÉÁ¥IÈqÉ¢ÄÌl@ð¨±È¤BܽAwäxÅÍAu©êé_ªÏ»·é±ÆàAÁ¥ÌêÂÅ éB_ÌzÉ©©íéA±Ìæ¤Èu©êé_ÌϻɢÄàA í¹Äl@·éB»Ìl@ÊÉæèwäxÌåèð¾ç©É·éB
@wäxÅÍA±êÜÅÝÄ«½w½é©xAwÔÜÅxÉÝçêÈ©Á½qÌÁ¥ÌêÂƵÄA¼g\»ª éB¼g\»ÍAwäxɨ¢ÄAdvÈ\»ðÜñ¾qÍwäxÆ¢¤ìiÌåèðl¦é¤¦ÅdvÈÁ¥Å éBȺÉïÌIɼg\»ªp¢çêÄ¢éÓðøpµA»Ìdv«ðl¦é±ÆÉ·éB
@u56ã©çø¢Ä °æ¤©v57¨~Í¢½Íéâ¤ÉµÄwãÉô½B
@u58çuÆRc³ñ©çÌäðÂÄÈv59FOYÍÔ¯éâ¤É]Ðú½B60iaj¨~Íê¡ÙÂÄA
@uibj¨O³ñu°éÌHv
@u61¢¢©çÂÄÈv
@u62ccN«ÄéÈ穢ܫÅà|¯ÄÈ¿âdlªÈ¢Ë¦v
iºüøpÒBȺ¯¶Bj
@ãÌøpÍêÊUAN«ãªÁ½uFOYvªu¨~vÉεÄd¹ïðÁÄéæ¤É¾¢Â¯éÓÅ éB±±Åºü59¶AuÔ¯éâ¤ÉvƼg\»Åq³êÄ¢éBuFOYvÌkbª»ÌÕ§¿Ì½ßÉA¾tðÔ¯éæ¤Éu¨~vÉѹçêéBPÉu]Ðú½vƷ龯ÅÍÈA¸¦Ä¼g\»ÉµÄ¢éƱëªÚ³êéB
@vðSzµÄ¢éu¨~vÉεÄAuFOYvÍAZµ¢úÅ éÉà©©íç¸dÅÍÈ©ªÌ̲ðSzµæ¤ÆµÄ¢é±ÆÉÕ§ÁÄ¢éB¼g\»Åq³êé±ÆÅA»ÌÕXµ³ª¦³êé±ÆÆÈéBuFOYvÌÓvÆuêêvðN±µÄ¢éƱëÅ éB¾ªA»ÌÕXÍAuÔ¯éâ¤É]Ðúv±ÆÉæÁÄAðÁµæ¤ÆµÄ¢éÆ¢¤à¾àÅ«æ¤B
@80\µOAFOYÍòÅN±³ê½B81iaj¡Í½ðlÖéÆàÈibjEg^_ƵÄîéB82MCð½@§ªá̺ÜÅíÂÄîéé ÌÝÉÂÄC«çÉ©©éB83XÌûàÃÜè©ÖÂÄîéB84ÞÍÍÌȢ᷵Š½èð©ôµ½B85ÉÍ^ÈçuªÃ©ÉºªÂÄéB86âvÌõÍCÉÔ©F÷ÂÄA®Ì÷ÅÔÉYûðµÄîé¨~ÌwðÆçµÄ½B87ÞÍ®ªMÅêµñÅéâ¤É´¶½B
@±êÍêÊVÅ éB°ÁÄ¢½uFOYvÍA\OÉò̽ßÉN±³êAQ°©ç®ðßéÆ¢¤ÓÅ éB
@uFOYvÍQÄé®ð©nµAu®ªMÅêµñÅéâ¤É´¶véBºü87¶ÅAuFOYv©g¾¯ªM̽ßÉêµñÅ¢éÌÅÍÈAÞª©Ä¢é͸ÌÎÛÅ é®ÜŪuMÅêµñÅévæ¤É´¶½±ÆªA¼g\»Å¦³êéB±Ì87¶ÍACªÌ«³ðqµ½uS`ÊvÅ é½ßA¼g\»ÌgÆíg\\g¦éàÌÆg¦çêéàÌ\\Æ¢¤ÖWÍÈ¢B»Ì½ßµ§É¾¦Î¢íäéu¼g\»vÅÍÈ¢ªA±±Åͼg\»ÆµÄµ¤±ÆÉ·éB¼g\»ðp¢é±ÆÅAuFOYvÌ̲̫³ð`¢Ä¢éBuFOYvÌ̲ÍAgÌ´oð¸¢Â éÌÅ éB
@115buÎÅu¢¾ãA¡xÍçuÖ©¯½B116ºàÌæÇñ¾óCª´ÌL ^_¢Ó¹Åôç©®«oµ½â¤ÈCªµ½B117FOYÍkÖéèð¬ÖA²qð¯Äu¢ÅîéªAǤµÄàCæs©ÊB118´àæ¨~̼ÉŽÜBªsÓɲ¯½B119çuªòñÅN^_Æäɪ«Â¢½B
@êÊVBØêÈ¢½ßÉÔÁÄ«½uävðAuFOYvªQ°Åu¬nßéÓÅ éB
@uFOYvÍAdðµnßé±ÆÅA̲ª«ÆàA¡½íÁÄ¢½æègÌÌ´oªßè éBuFOYvÍA87¶Åu®ªMÅêµñÅéâ¤É´¶vÄ¢½ªAu¬nßé±ÆÅuºàÌæÇñ¾óCª´ÌL
^_¢Ó¹Åôç©®«oµ½â¤ÈCªv·éBgÌ𮩷±ÆÅ̲̫³ðÓ¯µÈÈèAuFOYvÍØÁÄ¢½óCª®«oµ½æ¤É´¶éÌÅ éB±±ÅàAuFOYvÌàʪ¼g\»Å¦³êéBdðo¸ÉQ°ÅÕX·éÌÅÍÈAiǨèÉdðµÄÌ𮩷±ÆÉæÁÄA±êÜÅÌgÌ´oðæèߵ éÌÅ éB
@142¨~ÍÈüê̼ZðæÂÄÄAqÅà¾Ü·â¤É]ÂÄAQèðʳ¹AâÂÆÀSµ½Æ¢Óâ¤ÉãèyÉð©¯ÄA궽Éu¢ÅîéFOYÌçð©Ä½B143ÑöÍÌTÌqÌ|Åðøâ¤ÉµÄÑàÈ¢ãøðäèã°½èä躵½èµÄ½B
@êÊVBd𵱯éuFOYvÉεÄAu¨~vͼZð
éæ¤É£·B
@»Ìû²ªÜéÅuqÅà¾Ü·â¤É]ÂÄvƼg\»Å¦³êéi142¶ºüjB±±ÅÍuFOYvÌs®AàÊÅÍÈ¢ªAu¨~vÌuFOYvÖÌÔxªuFOYvðtÉÆË·éBgàÅ éu¨~vɽµ½èAs¾¢úÁ½è·é±ÆÅAuFOYvÍA©gÌÕXððÁµæ¤ÆµÄ¢½B»ÌÔxªAÜéÅuqvÌæ¤ÈÌÅ éBu¨~vÍA»¤µ½uFOYvÌssÆࢦéÕXðÔ¯æ¤Æ·éÔxÉεÄA°eÅ èAuFOYvÌ«iðæðµÄ¢éƾ¦éB±ÌøpÌOÉ ½é114¶Åibju½ð]ÂÄàǤ¹³ÊÆv½©çvÆ¢¤qàAuFOYvÌ«iððµÄ¢éu¨~vª¦³ê½ªÅ ë¤B
@195iajÕXµÄ{轩½CªÍ«½¢â¤ÈCªÉÏÂÄibj¡ÍgàCàSæêĽB196áÌÍMÅn¯³¤É¤éñÅîéB
@êÊWBuFOYvÍucÉÒvÅ éuáÒvÌEðäèȪçAæêÊÄĵܤB
@ºü196¶uáÌÍMÅn¯³¤É¤éñÅîévƼg\»ÅuFOYvÌ̲ð¦µÄ¢éB̲ª«¢Éà©©íç¸A_oð¤qÌEäèðµÄ¢é½ßAuFOYvÍܷܷ̲ðöµÄ¢BuáÌÍMÅn¯³¤vÆ éÌÍAEðä龯ÅÍÈu©év±ÆàÜÜÈçÈ¢óµÅ é±ÆÅ ë¤BuFOYvÍàÍâÊíÌdðÅ«éóµÉÍÈ¢ÌÅ éB
@203æêؽFOYÍÄàNÁÄàçêÈ©Á½B204ÄÌÖßÉÅÅà³ê½â¤ÈSªµÄîéB205½àÞà°oµÄ´ÜÜ´Ö]°½¢â¤ÈCªÉȽB206à¤æ³¤I@207©¤ÞͽÕv½©mêÈ¢B208RµÄ«IÉËR±¾ÍÂĽB
@êÊWBuFOYvªuáÒvÌôÉð¯é¼O̪ŠéB
@ºü204¶uÄÌÖßÉÅÅà³ê½â¤ÈSvÆàÍâo¾¯ÅÍÈASgªA̲sÇÆuáÒvÖÌÕ§¿ÆÉæÁÄA©Rð¸¢Â élqª¼g\»Å¦³êéBuÅvÆ¢¤©ªÌÓvÆͳÖWÉͽçà̪gƵÄà¿¢çêÄ¢é±Æ©çàAuFOYvÌSgªÉÀÌóÔÉ é±Æª¦³êÄ¢éB
@êÊUÌIíè©çêÊVÉ©¯ÄAòðùÞÆ¢¤Óª Á½i76`80¶jB±ÌEäèð·éOÉAuFOYvÍòðùñÅ¢éÉà©©íç¸ASgðuÅÅà³ê½â¤ÈSvª·éÌÅ éBuFOYvÍA·×ÄÌàÌÆuêêvðN±µA«zÂÌÉ¢éÌÅ éB
@229FOYÍwǸ_µÄ|êéâ¤ÉTÌÖqÉðµ½B230ÄÌÙ£ÍêÉÉÝA¯ÉÉxÌæJªÒÂĽB231áðËÞÂĮ½èƵÄéÞÍlÌlÉ©¦½B232éàlÌlÉÃÜè©Ö½B233ÄÌ^®Íâ~µ½B234Ą̈Í[¢°èÉ×½B235üÆè¾¾¯ªOû©çââ©Éõið߼B
wäxÌÅã̪ŠéBuáÒvðEµÄµÜÁ½uFOYvÍA229¶uwǸ_µÄ|êéâ¤ÉvÖqÉÀèÝA»µÄA»ÌpÍA231¶ulÌlvÅ éƼg\»Åq³êéBulÌlÉvÈé±ÆÅAuFOYvÍu¶«¨v é¢ÍulÔvƵÄÌli»Ìà̪¸íêĵܤÌÅ éB232¶àuéàlÌlÉÃÜè©Ö½vƧı¯É¼g\»Åq³êÄ¢éB±ÌêÉ¢éSÄÌÒªAulÌlÉvAu¨vÆ»µÄµÜ¤B±ÌÓÅÍA»êÜÅuFOYvÌàÊÉu©êÄ¢½_ÉæéAlÔIÈ»fâAliÆ¢Á½àÌSĪÛè³êÄq³êéÌÅ éB»µÄAu¾vÆ¢¤¨ÌÉ_ªu©êq³êéÅãÌ235¶ÉÂȪéB¼g\»ª½p³êÄ¢é±Æ©çàA±Ìu¾vÆ¢¤¨ÌÉu©êéÆ¢¤_ÌÏ»ÍAìiÌåèâA_ÌzÆ©©íédvÈàÌÅ ë¤B»ÌÏ»ÌÓ¡É¢ÄÍAÌuu©êé_ÌÁ¥vÅ_ð©o·±ÆÉ·éB
@±êç̼g\»ÍA»ÌÙÆñǪuFOYvÌàÊA é¢ÍuFOYvÌàÊð½fµ½àeÉ¢ÄÌàÌÅ éBuFOYvªÕXµÄ¢élqð¼ÚIÉ\»·éÆÆàÉA¼g\»ðp¢Ä»ÌàÊð¦µÄ¢éBܽAuFOYvÌÕXµ½CªÌ½©ÔèÉæèApxªÈÁÄ¢é±ÆÉàÚ³êéBuFOYvÌàÊðÆç¦é¤¦Å³Å«È¢\»Å èAÁ¥IÈ\»ÉÈÁÄ¢éB±êç̼g\»¾¯ÅÍAuFOYvÌàÊðÆ禫é±ÆÍÅ«È¢Bµ©µAuS`ÊvÆ í¹ÄÆç¦é±ÆÅAElÖ±©êÄ¢uFOYvÌàÊÌßöðæè¾ÄÉǤ±ÆªÅ«éÁ¥IÈqÅ éÆ¢¦æ¤B
@±¢ÄAà¤êÂÌÁ¥Å éAu©êé_ÌϻɢÄl@·éB
@æS̪ÍEl@ÉæÁÄAwäxɨ¢ÄADZÉ_ªu©êé©AÆ¢¤u©êé_ªÏ»·é±ÆªAÁ¥IÅ é±ÆªmF³ê½Bµ©µAìiÌŨÌÅ éu¾vÉ_ªu©êé±ÆÉ¢ÄÍAl@ðۯƵī½B»±ÅAwäxɨ¯é±êçÌ_ÌÏ»ÍAåèðl¦é¤¦ÅÇÌæ¤È_ÌzÅ éÌ©Al@·é±ÆÉ·éB_ªu¾vÉu©êéÓ¾¯ÅÍÈAìiSÌÌu©êé_ÌϻɢÄAà¤êxl¦ÈªçAl@µÄ¢B
@wäxɨ¢ÄAu©êé_ͨ¨ÞËuFOYvÉ éƾ¤±ÆªÅ«éBá¦ÎA»êÍ`ªÌÌæ¤ÈuS`ÊvÌqÅmF³êéB
@1zZ{ØÌC°ÌFOYÍ×̽߿µ°ÖA¢½B2»êªxHGcìÕÌOÉ©©ÂÄçºàÌdÉZµ¢·è¾Â½B3ÞÍQȪçê ÄOÉÇÐoµ½¹öÆ¡¾öª½çÆlÖ½B
±Ì3¶ulÖ½BvÆ¢¤uS`ÊvÍAPÉuFOYvÌàÊð`¢½àÌÅÍÈAuFOYvÌàÊÉu©ê½_©çq³êÄ¢éiºüjB»êÍAulÖ½vàeƵÄu¹övEu¡¾övÆAuFOYvÆÌ¢«³ÂªÉ±©çÅ éBuqÒ\»vÌuà¾vEuðßE]¿væÁÄALqIÉq³êéªAuFOYvÌvlàeÅ éBêÊUÌ`ªÅàA
@24ÉßÃÉÂê Äqª½Ä ñŽB25iaj¯½½Üµ¢ÉqËÌJ¯ÂÄâAÑöÌø«¸éÌäéñ¾«ÊÌ£¢½â¤È¿ibjªsȽ_oÉÍs^_GéB
ÆZµÈèͶ߽XÌlqªuFOYvÌuS`Êvu´ovÉæÁÄÆç¦çêÄ¢éB̲̫³ÉÁ¦AXªZµ¢Éà©©íç¸AXɧ±ƪūȢ½ßuFOYvÍAX̪µ¢lqª_oÉus^_GévÌÅ éB
@uFOYvÉu©ê½_ªAÈÅ éu¨~vÉu©êéÌÍAÌÓÅ éiñdºüªu¨~vjB
@u51iajÍΩèHvibjÆDµ]ÂÄA¨~ÍGèð¾çèÆOÖº°½ÜÜüÂĽB
@52iajFOYÍÛÆ]½Âàè¾Â½ªAibjºªÜéÅ ¿©È©Â½B
@53iaj¨~ªé ðÍ¢¾èA³ÌáfâòrðÐñ¹½è·éÌÅAibjFOYÍA
@uicj³¤ÀâÈ¢vidjÆ]½B54ªAºª©·êĨ~ÉÍ·«Æêȩ½B55Üp¼è©¯½CªªÕXµÄ½B
@u56ã©çø¢Ä °æ¤©v57¨~Í¢½Íéâ¤ÉµÄwãÉô½B
@u58çuÆRc³ñ©çÌäðÂÄÈv59FOYÍÔ¯éâ¤É]Ðú½B60iaj¨~Íê¡ÙÂÄA
@uibj¨O³ñu°éÌHv
@u61¢¢©çÂÄÈv
æSÅÌl@ÅàwEµ½æ¤ÉA54¶u¨~ÉÍ·«Æêȩ½vÆ¢¤u¨~vÌuS`ÊvÉæÁÄAuFOYvÌàÊÉu©êÄ¢½_ªAu¨~vÌàÊÖÆÏ»·éB±±ÍAu¨~vÆuFOYvÆÌÓvaʪ¤Ü¢©¸ÉAuFOYvªÕXðåç¹éÓÅ éiêÊUjBu¨~vÆuFOYvÌÓvª©ÝÁĢȢlqªA_ªu©êéìl¨ðϦé±ÆÉæÁÄAæè¾Äɦ³êéBàÊÉ_ªu©êél¨ªÏíéÌÍA»Ìuêêvðæè¾Äɦ·½ßÅ éƾ¦æ¤B
@112uÎÌxxªo½ÅAFOYÍN«ãÂÄAÐGð§ÄÄu¬nß½B113\ªäéÂéB
@114iaj¨~Íibj½ð]ÂÄàǤ¹³ÊÆv½©çicjéɿÂÄ©Äî½B
@115buÎÅu¢¾ãA¡xÍçuÖ©¯½B116ºàÌæÇñ¾óCª´ÌL ^_¢Ó¹Åôç©®«oµ½â¤ÈCªµ½B117FOYÍkÖéèð¬ÖA²qð¯Äu¢ÅîéªAǤµÄàCæs©ÊB118´àæ¨~̼ÉŽÜBªsÓɲ¯½B119çuªòñÅN^_Æäɪ«Â¢½B
@u120iaj ÔÈ¢IvibjÆ©ñŨ~Íicj°é^_idjFOYÌçð©½B121FOYÌûªÒèèÆkÖ½B
@êÊVBØêÈ¢©çÆßÁÄ«½uävðAuFOYvªQ°Åu¬Í¶ßéÓÅ éB±±àAdÈǹ¸ÉxñÅ¢ÄÙµ¢Æv¤u¨~vÆAC³ê½dðÈñÆ©±È»¤Æ¢¤uFOYvÌÓvª©Ýí¸uêêvðN±·ÓÅ éB114¶ibju½ð]ÂÄàǤ¹³ÊÆv½vÆ èAu¨~vÌàÊÉ_ªu©êÄ¢éB116¶ÌuºàÌæÇñ¾óCª´ÌL
^_¢Ó¹Åôç©®«oµ½â¤ÈCªµ½BvÆ¢¤qÍuFOYvÌuS`ÊvÅ èAÄÑuFOYvÌàÊÉ_ªu©êéB³çÉ120¶icju°é^_vÆ èAÌ121¶ªu¨~vª©½Å ë¤uFOYÌûªÒèèÆkÖ½vÆ¢¤`ÊÅ é±Æ©çAu¨~vÌàÊÉ_ªu©êÄq³êÄ¢éB
@±Ì¼ÒÌÎäàAuFOYvÌÓvÆAu¨~vÌC¤C¿ÆªuêêvðN±µÄ¢é±ÆðAæè¾ÄÉ·é½ßÉu©êé_ªÏ»·éÌÅ éB
@u150iaj³ñÉvibjƨ~ÍáàêÉ©µÄ½¶½B
@u151¨¢ç ªâéæv
@u152¨O³ñÍ¡úÍèªk¦é©çccv
@u153iajâéævibjÆFOYÍs³Ö¬Â½B
@u154iajǤ©µÄéævibjƨ~ͬºÅ]½B
@u155d ¾v
@u156Ǥ¹A ½é ¾¯ÈçÑÉàÈçÈ¢©ç´ÔŨµÈ³¢v157¨~ͼZðEªµ½È©Â½B
@êÊWÌAuáÒvªXÉEðäÁÄÙµ¢ÆKêéÓÅ éB
±ÌøpàAu¨~vÌàÊÉ_ªu©êÄq³êÄ¢éB150¶ibjuáàêÉ®©µÄvÆ èAu¨~vÌàÊÉ_ªu©êÄus®`Êv³êÄ¢éB±êÍus®`ÊvƵĪ޳êéªADZÉ_ªu©êÄ¢é©AÆ¢¤âèðÜñ¾qÅ éB»µÄA157¶u¨~ͼZðEªµ½È©Â½vÆ¢¤uS`ÊvàAu¨~vÉ_ªu©êÄq³êÄ¢éB±ÌÓÉ¢ľ¦ÎAuFOYvÌuS`ÊvÍÈAu¨~vÌvðSz·éàʾ¯ª`ʳêÄ¢éB¾ªA±±Åàu¨~vÌÓɽ·és®ðÆë¤Æ·éi̲̫³É©Üí¸dð¿¯æ¤Æ·éjuFOYvÆÌÓvÌÎäA·Èí¿uêêvª¦³êé½ßÌ_ÌϻŠéÆ¢¦æ¤B
@±Ìæ¤É_ÌÏ»ÍAu¨~vÆuFOYvÆÌÓvÌuêêvð«¤èÉ·éAæè¾ÄÉ·é½ßÌàÌÅ éÆ¢¦æ¤B
@¾ªA±Ìæ¤È_ÌÏ»Éæé¼ÒÌuêêvð«¤èÉ·éÈOÉàA¼ÒÌuêêvðæè¾ÄÉ·éqà éB»êÍAåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêÉæéàÌÅ éB_ÌÏ»ÅÍÈ¢ªAuFOYvAu¨~v¼ÒÌl¦Ìuêêvð«¤èÉ·éqƵÄA±±ÅmFµÄ¨B
@åÏIÈ]¿«ðàÁ½PêÉæÁÄAuFOYvÆu¨~vÆÌuêêvð¾ÄɳêéÌÍAåɼÒÌû²ÌÎäÅ éBȺɰé̪»ÌÓÅ éB
| ¶Ô | ]¿³êéÎÛ | ]¿«ðàÁ½Pê | q |
|---|---|---|---|
| 36 | uFOYv | us©Â½v | »êðÕÂÄA uAâéºIvÆFOYÍQ°©ç{½Bs©Â½ªmêĽB |
| 51 | u¨~v | uDµv | @uÍΩèHvÆDµ]ÂÄA¨~ÍGèð¾çèÆOÖº°½ÜÜüÂĽB |
| 57 | u¨~v | u¢½Íéâ¤ÉµÄv | @uã©çø¢Ä °æ¤©v¨~Í¢½Íéâ¤ÉµÄwãÉô½B |
| 64 | uFOYv | uÉᢺv us^_µÄév |
@u¢¢©çÂÄ¢Æ]ÓàÌðÂÄ˦©vÉᢺÅÍ]ÂÄîéªAáÅs^_µÄéB |
| 92 | uFOYv | u´âĽâ¤Èmºv | u¦¦vFOYÍé
ÌÝÉûðß½ÜÜÖ½B´âĽâ¤Èmºª·¦Ê©µÄA @ueû\\vÆ]½B |
| 94 | uFOYv | u¡xÍÍ«èÆs©Â½v | @u½¾æv¡xÍÍ«èÆs©Â½B |
| 105 | u¨~v | u»ÂÆv | @¨~ͳɿÂÄA»ÂÆFOYÌjÉèðÄÄ©½B |
| 106 | uFOYv | uÜ墳¤Év | @FOYÍÜ墳¤Éó¢½èÅ»êð¥ÐÞ¯½B |
| 138 | uFOYv | u³Ó¡Év | @uܾ¢ævFOYͳӡɽε½B |
| 153 | uFOYv | usv | uâéævÆFOYÍs³Ö¬Â½B |
ãÌ\ÍAæQßwÔÜÅxÅl@µ½\ƯlÉAåÏIÈ]¿«Ì éPêÆA»êðÜñ¾qð²«oµ½àÌÅ éBwÔÜÅxÌàÌƯlÉA\̶[©çAu¶ÔvAu]¿³êéÎÛvAu]¿«ðàÁ½PêvAuqvƵĢéBuqvÉÍA»ÌåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêªÝçêéqÌê¶ð²«oµ½B]¿«ðàÁ½êªAukb`ÊvÌû²É©©íéàÌÅ éêÍA»Ìukb`ÊvÌqಫoµÄ¢éBÎäµâ·¢æ¤Éu¨~vÉηéàÌÌÝÔ|¯ðµ½B
@±êçÌSĪu¨~vÆuFOYvÌÎäª`«o³êéàÌÅÍÈ¢BwÔÜÅxÌæ¤ÈujÌqvÆuÌlvÆÌÖWÆAuFOYvÆu¨~vÆÌÖWÆÍᤩçÅ éBwäxÅÍAuFOYvªu¨~vÌl¦âÔxÆÇÌæ¤ÉuêêvðN±µAElÖ±©êÄ¢©AÆ¢¤ßöðæè¾ÄÉ·é½ßÉAãÌæ¤ÈåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêðÜñ¾qÉæÁĦ³êéÌÅ éB
@±Ìæ¤ÉAuFOYvÆu¨~vÆÌÓuÌuêêvðæè¾ÄÉ«¤èÉ·é½ßA_ÌÏ»ÆÆàÉAåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêðÜñ¾qàAÚ³êéÌÅ éB
@ÅÍA_ðu©êé_ÌÏ»Éß·±ÆÉ·éBÌøpÍAìiÅãÌu¾vÉu©êé_ªÏíéÓÅ éB
@229FOYÍwǸ_µÄ|êéâ¤ÉTÌÖqÉðµ½B230ÄÌÙ£ÍêÉÉÝA¯ÉÉxÌæJªÒÂĽB231áðËÞÂĮ½èƵÄéÞÍlÌlÉ©¦½B232éàlÌlÉÃÜè©Ö½B233ÄÌ^®Íâ~µ½B234Ą̈Í[¢°èÉ×½B235üÆè¾¾¯ªOû©çââ©Éõið߼B
@±±ÅA»êÜÅuFOYv©u¨~v©Ììl¨ÌàÊÉu©êÄ¢½_ªAu¾vÆ¢¤¨ÌÖÆÏ»·éBu¾vÉ_ªu©êé±ÆÉæÁÄAuFOYvÌpªAuFOYvÌàÊÆͳÖWÉ`©êé±ÆÉÈéB231¶ulÌlÉ©¦½vÆ éÌÍAuFOYvÌOʪAu¾vÉu©ê½_ÉæÁÄ`©êÄ¢éqÉÙ©ÈçÈ¢B235¶ÍAPɨÌÅ éu¾vÉ_ªu©ê½±Æª¦³êÄ¢éqÅÍÈ¢BuüÆè¾¾¯ªvÆ¢¤qÉ
Ú³êéBuüvuÆèvu¾¯ªvÆOdÉu¾vÌݪ±ÌõiðfµoµÄ¢é±Æª²³êÄ¢éÌÅ éBæÁÄA235¶ÍAPÈé_ÌÏ»ÅÍÈAwäxÌåèÉà©©íéâèÅ éB
@±Ì_ÌÏ»ÉæéêAÌ`ÊÍA¨ÌƵÄA½¾ÀðÀƵÄfµo·u¾vƵÄA`Ê·é±Æª¦³ê½uqÒvÌ_ð½f³¹½qÅÍÈ¢¾ë¤©B¨ÌÅ éu¾vÍAÚÌOÉ éõiðA»ÌÜÜðfµo·àÌÅ éB»±ÉÍA@IÈîàȯêÎAÐïIÈK¥àȯêÎAÏIÈ»fàÈ¢B½¾ÚÌOÌõiðAõiƵÄfµo·BìiÌÅãÅOdɲ³ê½u¾vÖÌ_ÌÏ»ÍAu¾vƵÄÌuqÒvª`«o³êé±ÆÉÈéB
@uFOYvªuáÒvðE·ßöðA³Ü´ÜÈuêêvƻ̫zÂÉæÁÄA`©êÄ¢½B¾ªAÅãÅu¾vÉ_ªu©êé±ÆÅA»êÜÅuFOYv̨êÅ Á½wäxÆ¢¤ìiªAuFOYvÌ»fâAuFOYvÌSÅàÈ¢Õ«Ì é¨êÖÆÏ»·éÌÅ éBuFOYvÌuÂv̨êƵÄÌwäxªAu¾vƵÄÌuqÒvª`«o³êé±ÆÅANÉÅàN±è¤é¨êƵÄ`©êé±ÆÉÈéB»ÌÏ»ÍAuFOYvÌuåÏv©uqÏv©AÆ¢¤ñΧÅÍÈ¢B\»»Ìà̪uåÏvÅ éÀèAuqÏvÍ è¾È¢Bl©ç¨ÌÖÆ¢¤u©êé_ÌÏ»ÍAuÂv©çuÕ«vÖÆ¢¤Ï»ÈÌÅ éB
@áÌ¢«iÅ éuFOYv¾©çN±Á½oÅ èȪçAuFOYvÌàÊÉ_ªu©êÈ¢±ÆªÅãɾ©³êé±ÆÅANÉÅàN±è¤éoÆÈéBÂlÌ»fÉæÁÄElÖü©ÁÄ¢Á½ÌÅÍÈAsÂðIÉElÖ±©êÄ¢ßöƵÄ`©êéÌÅ éB
@æÁÄAwäxÌåèÍAuFOYvªuáÒvðE·Æ¢¤àÊÌßöð`ÆÆàÉAêûÅÍ»êªNÉÅàN±è¤ésÂðIÅÕIÈßöƵÄÌàÊÌϻŠéB
@æUÅÍA±êçÌl@ÉæÁľç©ÆÈÁ½wäxɨ¯é_ÌzÆq@ðÜÆßé±ÆÉ·éB
@{ßæQÍæRßÅÍAwäxɨ¯é_ÌzÆq@ðĪ©èƵÄAwäxÉ¢ĪÍEl@ð··ßÄ«½B{ÅÍA»ÌªÍEl@ÊðÜÆßé±ÆÉ·éBÄÑwäxðÜÆßéÆ·êÎȺÌæ¤ÉÈë¤B
@ä𵤱ÆÉÖèÆ©MðàÁÄ¢½áÌ¢«iÌuFOYvÍA×ÅQñŵܤBXÍZµ¢úÅ èAålÅ éuFOYvªXðxñÅàC¹çêéEl͢ȢBXªZµÈènßéÆAêlÌqªuävðu¢ÅÙµ¢ÆâÁÄéBÁÉålÉu¢Åà碽¢Æ·¢½uFOYvÍAÈu¨~vª~ßéÌà·©¸ÉAd¢gÌÅN«ãªèu²¤Æ·éªA[¾·éæ¤ÉÍu°È¢BâªÄæêÊÄÄ°ÁĵܤBòÅN±³ê½uFOYvÍAu¢¾uävªØêÈ¢ÆXÉßÁÄ«½±Æð°çêéB̲ÍËRƵÄDêÈ¢Éà©©íç¸AuFOYvÍu¬nßéBXÉÍqªNà¨ç¸X¶Ü¢µæ¤Æ¢¤u¨~vÉεÄAuFOYvͽηéB»±ÖAcÉÒÌuáÒvªEðäÁÄêÆKêéB¼ÌElÉC¹æ¤Æ¾¤u¨~vðÕ詪ªäéÆuFOYvªdð¿¯éBy¢²qÌuáÒvÌÔxÉAuFOYvÍÕXµÈªçàAEð»ènßéBµ©µAuävð¤Üµ¤±ÆªÅ«¸A̲àÜ·Ü·«»·éBâªÄAuävÌnªuáÒvÌôÉøÁ©©èAª¬êéBͶßÄqð¯½uFOYvÍA½©É¢çêéæ¤ÉuävÅuáÒvðEµÄµÜ¤BlÌæ¤ÉÈÁ½uFOYvðfµo·ÌÍA¾¾¯Å Á½B
@wäxÌåèÍA±¤µ½uFOYvÌàÊÌßö»ÌàÌÅ éBgÌ´oð¸¢A«Éäð¬êÈÈèA»êÅà[¾·éæ¤Édð®µÈ¯êÎÈçȢƢ¤uFOYvªA¢©ÉµÄuáÒvðEµÄµÜ¤©AÆ¢¤ßö»ÌàÌÅ éB»ÌêûÅAu¾vƵÄÌuqÒvª¦³êé±ÆÅA»ÌßöªuFOYvÂlÉN±Á½oÅÍÈAlÔêÊÉàʸésÂðIÅÕIÈßöƵÄ`©êéÌÅ éBsÂðIÅÕIÈElÖÌßöA±êªwäxÌåèÅ Á½B
@wäxÍAuFOYvðSÆ·éOl̬àÅ éB»ÌàʪAuFOYvÌàÊÉu©ê½_ÉæÁÄ`©êÄ¢éBܽAuFOYvêl¾¯ÅÍÈA¼ÒÆÌÎäÉæÁÄA»ÌH¢á¢ª«¤èɳêéBuFOYvÌ÷Å¡GÈàÊÌElÖÌßöªAuFOYvÌuS`ÊvÆA»ÌÈu¨~vÌuS`ÊvÆÆàɦ³êéÌÅ éB
@ìiÍAuFOYvªA¢©É©gÌ̲AXÌóµAüèÌlXÌÓvÈÇÆuêêvðN±µÄ¢©ª`©êé±ÆÉæÁÄAuáÒvÌElÖƱ©êÄ¢BêÊTÅÍAuFOYvÌElƵÄÌrÌdzAáÌ¢«iAXÉC¹çêéÒª¢ÈÈÁĵÜÁ½Æ¢¤óµªÝè³êéB
@»ÌuFOYv̳Éq©çuäðu¢ÅÙµ¢vƶªüé±ÆÉæÁÄAuFOYvÍdð·é±ÆÉÈéB̲ª«¢ÌÉà©©íç¸Adð·é͸ªÈ¢ÆvÁÄ¢éÈÌu¨~vÍARvÌs®ÌÓ}ððÅ«È¢B»ÌH¢á¢ªV½ÈuêêvƵÄAu¨~vÌàÊÉu©ê½_ÉæèuS`Êv³êéBdðµÈ¯êÎÈçÈ¢ÌÉA̲ª««ÉdªÅ«È¢A»êÉÁ¦ÄüèÆÓvaʪ¤Ü¢©È¢±ÆÉæéuêêvÅAÜ·Ü·ÕXµ½Cªðåç¹Ä¢B
@êÊWÅAuáÒvÌEðäé±ÆÅA»ÌÕXªÅªÉB·éB»êÜÅgàÉÕXµ½CªðÔ¯é±ÆÅ éöxðÁ³¹Ä¢½uFOYvÉÍAqÅ éuáÒvÉεÄÍ»êªÅ«È¢BÜ·Ü·«Èé̲Ay¢²qÌuáÒvÖÌ{èAdª±È¹È¢±ÆÖÌÕXÉæÁÄAuFOYvÍuävÅuáÒvÌôð¯ĵܤB»êð©½uFOYvÍAÓvÆͳÖWÉuáÒvðuävÅEµÄµÜ¤BEµÄµÜÁ½uFOYvÆAÞðæèÍÞSÄÌà̪â~µA¨ÌÅ éu¾vÉu©ê½_ÉæÁÄA»Ìõiªq³êéB
@wäxSÌðʵÄ_ªu©êéÌÍAuFOYvÌàÊÅ éB»ÌàÊÍAÇÌæ¤É´¶é©AÇÌæ¤Év¤©AÇÌæ¤Él¦é©Æ¢Á½¿ÌÙÈéuS`ÊvÉÁ¦AÎÛðuÇÌæ¤ÉÆç¦é©vÆ¢Á½ul¨`Êvu¨`ÊvÉà½f³êÄq³êéBµ©µwäxɨ¢ÄAà¤êÂÌ_ÌzÌÁ¥ÍAuFOYvÌàÊÉu©ê½_ÆÆàÉA»Ì_ªÏ»·é±ÆÅ éBuFOYvÆu¨~vÆÌl¦ªH¢áÁÄ¢é±ÆªAu©êé_ªÏíé±ÆÉæÁĦ³êéB»µÄìiÌÅãɨÌÅ éu¾vÉ_ªu©êé±ÆÉæÁÄAu¾vƵÄÌuqÒvª¦³êéB±êÉæÁÄAáÌ¢«iÌuFOYvÌÂlƵÄÌElªANÉÅàN±è¤éÂ\«ª èANÅ ÁÄà»êðð¯é±ÆÍﵢƢ¤AÕ«ÆsÂð«ÆðàÁ½àÊÌßöƵĦ³êéBu©êé_ÌÏ»ªAìiÌåèÆ©©íédvÈ_ÌzÌÁ¥ÆÈÁÄ¢éÌÅ éB
@wäxɨ¯éq@ÌÁ¥ÌêÂÍAuFOYvÌàÊð`«o·uS`ÊvÉ éBuFOYvÌ̲̫³ÆA»êÉæÁÄgÌ´oð¸¢A¼lÅ Á½Í¸Ì䪵¦ÈÈèAÕXðåç¹Ä¢BáÌ¢«iÅ éuFOYvÍAdªÅ«È¯êÎÅ«È¢ÙÇA©¦ÁijÉÅàdðµæ¤Æ·éB»µÄoÈ¢©ªÉ³çÉ ð§ÄÕX·éÆ¢¤«zÂð¶Ýo·B»ÌSÌßöðAu´ovuSîvuvlvÆ¢Á½¿ÌÙÈéuS`ÊvÉæÁÄA`«o·Bu¨~vÆÌuS`ÊvÌÎäÉæÁÄAuFOYvÌl¦ÆÌuêêvªæè¾ÄÆÈèA³çÉÕXðåç¹Ä¢±ÆÉÈéB
@»µÄAà¤êÂÌÁ¥ÍAäg\»ÆåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêÅ éBäg\»ÉæÁÄAuFOYvÌÕXµ¢àʪ²³êéBܽAuFOYvª©éÎÛA´¶½gÌ´oª¼g\»³êé±ÆŦ³êéB¿ÌÙÈé½lÈuS`ÊvÆÆàÉA¼g\»ÅàʪÔÚIÉA¼ÚIɦ³êé±ÆÅAæè§ÌIÅ÷È̲ÆCªÌNª¦³êéÌÅ éB@ܽAuFOYvÆu¨~vÆÌuS`ÊvÌÎäÌÙ©ÉAuFOYvÆu¨~vÆÌÔxªåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêÉæÁÄàAæè¾ÄÉÎä³êé±ÆÉÈéB
@uFOYvÌû²ÉεÄAus©Â½vAusvÆ¢Á½åÏIÈ]¿ªº³êéB±êÉÁ¦ÄAuÔ¯éâ¤ÉvAuÅÅà³ê½â¤ÈvÆ¢Á½¼g\»ðÜñ¾qÉæÁÄAElÖÆ¢¤C[Wª³êÄ¢±ÆÉÈéB\èªwäxÅ èAùÉ¥íƵÄÌBgªÜÜêÄ¢éBusvÈÁÄ¢uFOYvÌû²ÆAÕXµ¢CªªåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêðÜñ¾qÆA³çÉElðC[W³¹éuÔ¯éâ¤ÉvuÅvÆ¢Á½¼g\»ÌqÍAuFOYvÌElÖÆ¢¤àʾ¯ÅÍÈAqÌÉ é±ÆλÌà̪àÂC[WÉæÁÄàAlðE·Æ¢¤¶Cɱ©êÄ¢±ÆÉÈéB»ÌÓ¡ÅàA¼g\»âåÏIÈ]¿«ðàÁ½qÍAìiÌåèðl¦é¤¦ÅdvÈq@ÌêÂÅ éÆ¢¦æ¤B
@ÈãÌæ¤ÉAæQÍÅÍAúìi̪ÍEl@ð¨±ÈÁÄ«½BæRÍÅÍAæQÍŨ±ÈÁ½ªÍEl@ðàÆÉAuê¼ÆÌúìiɨ¯é_ÌzÆq@̤Ê_Æ·Ù_ðl¦é±ÆÉ·éB
@æRÍÅÍAæQÍŪÍEl@µ½w½é©xAwÔÜÅxAwäxÌ_ÌzÆq@ÌÁ¥É¢ÄAärl@ð¨±È¤BæPßÅÍAæPÅ_ÌzÌÁ¥Ì·Ù_ðl¦½Ì¿AæQÅOÂÌúìiɨ¯é¤Ê_É¢Äl¦é±ÆÉ·éB
@ܸw½é©xɨ¯éAÙ©ÌñìiÉÍÝçêÈ©Á½_ÌzÌÁ¥É¢ÄAÝÄ¢±ÆÉ·éB
@w½é©xÍAuM¾YvªAucvÌ@Ì©ÉN±Á½AucêvÆ̽Æaððo±·é±ÆÉæèA¼ÒÉü©¤©ªÆ¢¤Ó¯ðl¾·éìiÅ Á½Bw½é©xÍOl̬àÅ èA_ÍìiÌSl¨Å éuM¾YvÉInu©êÄ¢½Bw½é©xɨ¢ÄA¼ÌìiÉ©çêÈ¢àÁÆàÁ¥IÈ_ÌzÍA¡«Ì éqÉÝçêéuqÒvÆuM¾YvÆÌdÈèÅ éB
@20Acê̺Åáªoß½B
@u21¼®N«Ü·v22iajÞÍibjCÀßÉAicjXèȪçé ©çñÌrÜÅoµÄAidjÌÑðµÄ©¹½B
@u23¨Ê^Éà¨Ö·é̾©ç¼®N«Ä¨àêv
@24¨Ê^Æ]ÓÌÍ´®Ì°ÌÔÉ|¯Ä éCMæÌÑÅAM¾YªwÌ KÁ½æw̳tÉcÌSȽA`¢Äá½àÌÅ éB
@25iajÙÂÄ¢éÞðibju³ A¼®vicjÆcêÍ£µ½B
@u26åävA¼®N«Ü·B27\\ÞûÖsÂÄľ³¢B28¼®N«é©çv29iaj³¤]ÂÄÞÍibj¡ÉàN«³¤ÈlqðµÄ©¹½B
@30cêÍÄÑoÄs½B31ÞÍ°èɾñÅs½B
iºüøpÒBȺ¯¶j
±ÌøpÍAw½é©xÌêÊUÅAucêvªñxÚÉuM¾YvðN±µÉ®ÉüÁÄéÆ¢¤ÓÅ éBêxN±µÉ½ucêvªAÈ©È©N«æ¤ÆµÈ¢uM¾Yvð©©ËÄN±µÉéBµ©µAuM¾YvÍAOú[éÜŬàðÇñÅ¢½½ß°è½¢Æ¢¤~ÉÄÈ¢BñxÚÉN±µÉé±ÆÅAuM¾YvÍAucêvð[¾³¹é½ßÉA·®ÉÅàN«»¤ÈfUèð·éB
@uM¾YvÍAܾ®SÉoÁµÄ͢ȢBæÁÄAïÌIÈíªÆµÄAucêvðÇ¢Ô·½ßÌuS`ÊvͳêÈ¢Bµ©µA22¶idjuÌÑðµÄ©¹½vA29¶ibju¡ÉàN«³¤ÈlqðµÄ©¹½vÆ¢¤us®`ÊvÉæÁÄA»Ìàʪ`©êéB±êÍAuM¾YvÌOÊÌ®ÔIÈ®ìð`ʵ½us®`ÊvÅ èȪçAuM¾YvÌucêðÈñÆ©Ç¢Ô»¤vÆ¢¤uS`ÊvðàÜñ¾¡«Ì éqÆÈÁÄ¢éB±¤µ½¡«Ì éqª³êéÆ«AuqÒvÍAuM¾YvÌOÊ©àÊ©Æ¢¤ñΧIÈÊuÉÍ_ðu¢Ä¢È¢BuM¾YvÌàÊð©Ê·©½¿ÅAus®`ÊvÆ¢¤uM¾YvÌOÊð`ʵĢéÌÅ éB±¤µ½¡«Ì éqðÂ\É·é_ÌzÍA¼ÌñìiÉÍÝçêÈ¢w½é©xÌÁ¥Å éBÌøpÅÍA»Ì_ÌzªAw½é©xÌåèð©Ñãªç¹éàÌÆÈÁÄ¢éB
@123ÞÍ®ðo½B124ãÌ ÆñÔÚÌ ÌFqƪ×Ì®ÌàxàÉ ½ÂĽB125MO¾¯àxàEÌãÉ˧¼B126iajMOÍÞð©éÆ}ÉñªðµÄVäÌêûð©ã°ÄA
@uibjº¾vicjÆÍñÅ©¹½B127iajãÌ ªA
@uibj³¤]ÖÎMOͪªå«¢©ç{ɼ½³ñÌ⤾ívicjÆ]½B128iajMO;ÓÉÈÂÄA
@uibjÌ¢Èvicjƺð£ÂÄEðÐËé^ðµ½B129iaja¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YªA
@uibj¼½²·ÉEÍÈ¢ævicjÆ]½B130iaj ñlªAibjuí[¢vicjÆÍâµ½B131iajMOÍA
@uibjµÜ½IvÆibj¢âÉܹ½ ûicjð«¢ÄAEðòѺèéÆA¢«ÈèêÂÅñ®èÔµðµÄAidj¨Ç¯½çðiejÌÓÆifjFÌûÖü¯Ä©¹½B
@ucêvÆÌaððʽµ½uM¾YvÍAæ¤â©ªÌQ°ª é®ðoéB»±ÅuM¾YvÍAí
½¿Æïbððí·±ÆÅAw½é©xªIíéB
@ºü131¶ibjÌu¢âÉܹ½ûvÆ¢¤qªA¡«Ì éqÉÈÁÄ¢éB131¶ibjÍAuM¾YvÌíÅ éuMOvÌû²ðqµ½us®`ÊvÌêÅ éB±ÌqàAuMOvÌus®`ÊvÉA»êðÝéuM¾YvÌuS`ÊvªÜÜêÄ¢éB»êÜŮɶ±àÁÄ¢½uM¾YvÉÆÁÄA©çN«Ä¢½uMOvÌpÍAu¢âÉܹvÄ¢éæ¤ÉAålÑÄ´¶çêéÌÅ éB±ÌuMOvÌû²ÍAPÈéus®`ÊvÅÍÈAuM¾YvÌàÊð½f³¹½A¡«Ì éqÈÌÅ éB131¶Ì¡«Ì éqðÆç¦é±ÆÅAucêvÆÌâèÆèÉæé129¶ÌuM¾YvÌÓ¯ÌÏ»ð©Ñãªç¹é±ÆÉÈéB
@êÊVÅÍA©ªÌ®©çOðßéi¨ðX¯éj¾¯Å Á½uM¾YvªAucêvÆÌâèÆèÉæÁÄA©ªªuMOv½¿ÉÇÌæ¤È\îðµÄ¢éÌ©AÆ¢¤¼ÒÉü©¤ua¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄv¢éÆ¢¤©ªÌ\îðÆç¦é±ÆªÅ«éæ¤ÉÈÁ½ÌÅ éBw½é©xɨ¯éA¡«Ì éqÍADZÉ_ªu©êéÌ©AÆ¢Á½âèÆÆàÉAìiÌåèðÆç¦é½ßÌdvÈ_ÌzÌÁ¥Å éB
@wÔÜÅxÍAúí©çDÔÉæé±Æɵê½u©ªvªAkC¹ÌuÔvÜÅsÆ¢¤AñlÌqÇàðAê½uÌlvÉεÄAÖSE¯îðøÆ¢¤ìiÅ Á½BwÔÜÅxÍA{¤ÅªÍÎÛƵ½ìiÅBêÌêl̬àÅ éB_àAInêlÌÌu©ªvÌàÊÉu©êÄq³êéBwÔÜÅxɨ¢ÄAÁ¥IÈ_ÌzÍAu©ªvÌàÊÌ`©êûªÏ»·é±ÆÉæÁÄAÎÛiuÌlvjÉηéu©ªvÌÖSE¯îªå«[Èé±Æª`©êéÆ¢¤±ÆÅ éB»ÌÁ¥ÆÍADZ©çiN©çj`Ì©AÆ¢¤âèÅÍÈAÇÌæ¤É`Ì©Æ¢¤âèÉ©©íé_ÌzÅ éB
@156iajÌlªñ[ð«I½AibjjÌqªA
@uicjê@³ñAµÂ± vidjÆ]Ðoµ½B157qÔÉÍÖª¢ÄîÈ¢B
@u158वäoܹñ©Hv159iajêÍibjfµÄicju¢½B160jÌqÍûªðñ¹Ä¤ÈÃB
@161iajÌlÍAjÌqðøâ¤ÉµÄA ½èð©ôµ½ªibjÊÉlàÈ¢B
@u162iajवAÒÂÄlHvibjÆØèÉȾßéªAicjjÌqÍgÌðä·ÂÄAàçµ³¤¾Æ¢ÓB
øpÍêÊWAu©ªvªñlÌqÇàÌeðzµÄ¢éÆAuÌlvÉujÌqvª¬Ö𵽢ƾ¢o·ÓÅ éB
@ujÌqvEuÔvÌñlÌqÇàÆuÌlvÆÌâèÆèðÏ@µÄ¢½êÊUÍAuÌlvÉ¢ÄÌuS`ÊvªÈ¢¾¯ÅÍÈA_ªu©êÄ¢é͸Ìu©ªvÉ¢ÄÌuS`ÊvàAO¶µ©È©Á½Bµ©µAêÊVÅeðzµAuÌlvÌ«öðz·éÆAuÌlvÉ¢ÄuS`Êv³êéæ¤ÉÈéB
@159¶ibjufµÄvA161¶ibjuÊÉlàÈ¢vÍAuÌlvÉ¢ÄÌuS`ÊvÅ éBµ©µA±ÌàÊÍuÌlvÌàÊÉu©ê½_©ç`©ê½qÅÍÈ¢B_ÍËRƵÄu©ªvÉu©êÄ¢éB±ÌuÌlvÌuS`ÊvÉæÁÄAu©ªvªuÌlvÉηé¯îEÖSªå«ÈÁ½±Æª¦³êÄ¢éÌÅ éBu©ªvÉÆÁÄÌuÌlvÆÌSIÈ£ªßâ½½ßAèÌàÊÜÅÇÝæé±ÆªÂ\ÉÈÁÄ¢éÌÅ éB
@±ÌuÌlvÉ¢ÄÌuS`ÊvÍAÖÌ¢ĢȢԼÅqÇàɬÖ𵽢ƢíêêÎARufv·é±ÆÉÈèA»µÄ½Æ¦»ÌÔ¼ð©ñµ½ÆµÄàAÁÉul¦và
@170iaj¢¾âçÊà©çA
@uibj³^_vicjÆjÌqÍO±²Ýɺ ð¨³Öéâ¤ÉµÄ¢ÓB
@u171³ As«Ü¹¤v172iajêÍGÌÔð|¯ÉºµAçðñ¹ÄAuibj_µÒÂÄĸÕævicjÆ¢ÐAXÉ©ªÉAuidj°êüèÜ·Aê¡©Äĸ«Ü·v
@u173iajæ¤äÀ¢Ü·vibjÆ©ªÍicjõidj]½B
@êÊWuFs{vwÉDÔª
ÆAuÌlvÍu©ªvÉÔñVÌlqð©Ä¨¢ÄÙµ¢ÆÜêéBøpÍAºÔ·é͸Ìu©ªvªA»ÌÝðõø·éÆ¢¤ÓÅ éB
@êÊUÅÍujÌqvÌóÛÉ¢ÄÌuS`Êvªñ¶ÆAuÌlvÆujÌqvÌÚ³ªÄ¢é±ÆÉCâ½Æ¢¤uS`ÊvÌݪu©ªvÌuS`ÊvÅ Á½Bµ©µAñlÌqÇàÌeÉ¢ÄÌzðI¦A»êªu©ªvÉÆÁÄÌêqÌÀÆÈÁ½êÊWÅÍAuÌlvÖ̦ͪuõv¢ÆuS`Êv³êéæ¤ÉÈéB±ÌuS`ÊvàAu©ªvÌAuÌlvÖÌSIÈ£ÌkÜ誦³êÄ¢éB±êÜÅÍAêqÌâèÆèðÏ@·éÒÅ Á½u©ªvªA©çÏÉIÉêqÉÖíë¤Æ·éÒÉA»ÌÔxðÏ»³¹½ çíêÈÌÅ éB±ÌÏ»ÍAêÊVÌeivjÌzªìidvÈÓ¡ðàÂÆÆàÉA»êð«Éµ½u©ªvÌuÌlvÖÌÖSE¯îÌ嫳E[³ÌÏ»Åà éÌÅ éB
@ÈãÌæ¤ÉwÔÜÅxɨ¯é_ÌzÌÁ¥ÍAêlÌÅ é±Æ¾¯ÅÍÈ¢Bu©ªvÌàʪ¼ÚuS`Êv³êé©Û©AÆ¢¤Ï»ªAìiÌåèâ»êÉÂȪéàÊÌßöðl¦é¤¦ÅAwÔÜÅxɨ¯éÅLÌ_ÌzÌ è©½ÈÌÅ éB
@wäxÍADê½ElÅ Á½uFOYvªuáÒvðEµÄµÜ¤Æ¢¤àÊÌßöªAÕ«ÆsÂð«ðàÁÄ`©ê½ìiÅ Á½BwäxÍAw½é©xƯlÉAáÌ¢«iÌuFOYvðSƵ½Ol̬àÅ éBµ©µAwäxɨ¯éA¼ÌñìiÉÝçêÈ¢_ÌzÌÁ¥ÍAu©êé_ªÏ»·éÆ¢¤±ÆÅ éBu©êé_ªÏ»·é±ÆÉæÁÄAuFOYvÆu¨~vÌl¦ÌH¢á¢ª¦³êé±ÆÉÈéB»µÄA»êÍElÖƱ©êÄ¢´öÅ éAuFOYvÆÌuêêvÌvöÌêÂÆÈÁÄ¢éB
@u49¡ÌàÉâÂÄu©¤v50iajÞÍ©¤vÂÄibjd¢©ç¾ ÅcÌãÖN«¼Â½ªAá¿òªµÄbÍÌãÖ˵ĽB
@u51iajÍΩèHvibjÆDµ]ÂÄA¨~ÍGèð¾çèÆOÖº°½ÜÜüÂĽB
@52iajFOYÍÛÆ]½Âàè¾Â½ªAibjºªÜéÅ ¿©È©Â½B
@53iaj¨~ªé ðÍ¢¾èA³ÌáfâòrðÐñ¹½è·éÌÅAibjFOYÍA
@uicj³¤ÀâÈ¢vidjÆ]½B54ªAºª©·êÄ ¨~ÉÍ·«Æêȩ½B55Üp¼è©¯½CªªÕXµÄ½B
@u56ã©çø¢Ä °æ¤©v57¨~Í¢½Íéâ¤ÉµÄwãÉô½B
u58çuÆRc³ñ©çÌäðÂÄÈv59FOYÍÔ¯éâ¤É]Ðú½B
iºüÍ·×ÄøpÒBȺ¯¶Bj
ãÌøpÍAwäxÌêÊUACªªßènß½uFOYvªuävðu²¤Æµæ¤·é±ÆÆA»êð©Ä¢½ÈÌu¨~vªvÌÓ}ªðÅ«È©Á½lqªAu©êé_ðϦȪçAq³êéÓÅ éBºüªuFOYvÌàÊÉu©ê½_©çÌqAñdºüªu¨~vÌàÊÉu©ê½_©çÌqÅ éB
@̲ª«ÆàAXÉC¹çêéElª¢È¢ÈãA©ªÅâ鵩ȢÆuFOYvÍl¦Ä¢éBµ©µAių¦Cªª«¯êÎdðµÈ¢Æ¢¤uFOYvªÌ²ª«QñÅ¢éúÉäðu²¤Æ·éÆÍvÁĢȢu¨~vÍAuFOYvÌÓ}ð·®ÉðÅ«È¢ÌÅ éB»êÉÁ¦AןªoÈ¢uFOYv̱ÆÎÍAu¨~vÉ·¦È¢B»Ì½ß¼ÒÌl¦ÍH¢á¢uêêvð¤Ý¾·±ÆÉÈéB
@»ÌuFOYvAu¨~v¼ÒÌH¢á¢ðæè¾ÄÉ·é½ßÉAu©êé_ªuFOYvi50¶A52¶jAu¨~vi54¶jAuFOYvi55¶jÌàÊÆÏ»µÄq³êé±ÆŦ³êéB
@220¦ÄqÌçð¯½Ìȩ½FOYÉÍA´îªñíȳÅÂĽB222ÄzÍiXZµÈÈéB221ÞÌSgSSÍSÉzÐÜê½â¤É©¦½B223¡ÍǤÉà»êÉſªoÈȽB224ccÞÍäðtèÉ¿©ÖéÆ¢«È订Æôðâ½B225nª·Â©èBêéöÉB226áÒÍgã¦àdȩ½B
@227ê¡Ôðu¢ÄªçµéB228áÒÌçÍ©é^_yFÉϽB
@229FOYÍwǸ_µÄ|êéâ¤ÉTÌÖqÉðµ½B230ÄÌÙ£ÍêÉÉÝA¯ÉÉxÌæJªÒÂĽB231áðËÞÂĮ½èƵÄéÞÍlÌlÉ©¦½B232éàlÌlÉÃÜè©Ö½B233ÄÌ^®Íâ~µ½B234Ą̈Í[¢°èÉ×½B235üÆè¾¾¯ªOû©çââ©Éõið߼B
±ÌøpÍAuáÒvðEµÄµÜÁ½ ÆÌuFOYvÌlqª¦³êéÓÅ éB½©É±©êéæ¤ÉqðEµÄµÜÁ½uFOYvÍAlÌæ¤É|êéæ¤ÉAÖqÉÀèñŵܤB
@±±àA_ÌÏ»ªÝçêéÓÅ éBuFOYvªuáÒvðE·lqªq³ê½ªi220¶`228¶jÆA»Ìlqðu¾vª©Ä¢½Æ`ʳêéªi229¶`235¶jÆÍAu©êé_ªlÔÅ éuFOYv©çA¨ÌÅ éu¾vÖÆ_ªÏ»·éBºüªuFOYvÌàÊÉu©ê½_©çÌqA¾ü̺üªu¾vÉu©ê½_©çÌqÅ éB
@»êÜŨ¨ÞËuFOYvÌàÊÉu©ê½_ÉæÁÄq³êÄ¢½Éà©©íç¸AìiÌÅãŨÌÅ éu¾vÉ_ªu©êé±ÆÉæÁÄAuFOYvƵÄÌ
uqÒvÅÍÈAu¾vƵÄÌuqÒvª¦³êé±ÆÉÈéB±ÌÏ»ÉæÁÄAuFOYvÌÂÌElÖÌßöª`©ê½ìiÅÍÈANàª×éÂ\«Ì éÕIÅAuFOYvÅÍÈÆàNદêé±ÆªÅ«È¢sÂðÌßöÆÈéÌÅ éB
@ÈãÌæ¤Éwäxɨ¢ÄÍAq³êéÛDZÉ_ªu©êéÌ©AÆ¢¤_ªu©êéÊuÌÏ»ªAìiÌåèÉ©©íéÁ¥IÈ_ÌzÌ è©½Å éÆ¢¦éB»êÍAOl̬àw½é©xÉàAêl̬àwÔÜÅxÉàÈ¢wäxÅLÌÁ¥Å éB
@ÈãÌæ¤ÉA»ê¼êÌìiɨ¯é_ÌzÌ·Ù_ðärµÄ«½B±æQÅÍAw½é©xwÔÜÅxwäxɨ¯é¤Ê_É¢Äl@·éB
@w½é©xAwÔÜÅxAwäxÆ¢¤uê¼ÆÌOÂÌúìiɤʷé_ÌzÌÁ¥ÆÍÈñŠ뤩B
@OÂÌìiÌåèðär·êÎA¢¸êàêlÌìl¨ÌSÌßöð½ÇÁ½àÌÆ¢¤¤Ê_ð©o·±ÆªÅ«æ¤Bw½é©xÍAucêvƽµað·éÆ¢¤SÌßöÅ èAwÔÜÅxÍu©ªvªuÌlvÖSIÈ£ðkßĢƢ¤SÌßöª`©êéBwäxÍAuáÒvðEµÄµÜ¤Æ¢¤uFOYvÌSÌßöªìiÌåè»ÌàÌÅ Á½BìiÌAû©_ÍAaðA¯îAElÆ¢¤¿ÌÙÈéàÌÅ ÁÄàA»ÌSÌßöªdvÅ é±ÆͤʵĢéÌÅ éB_Ìz̤Ê_àA±ÌåèÆÌ©©íèÉ©o¹éÆ¢¦æ¤B
@·Èí¿AOÂÌìiÆàAêlÌAOlÌÆ¢¤lÌÌá¢Í éÆÍ¢¦A¨¨ÞËêlÌìl¨ÌàÊÉ_ªu©êéÌÅ éBwäxÅÍAu¨~vÉà_ªu©êé±Æªí©Á½Bµ©µA±êÍ·×ÄuFOYvÆÌl¦ÌH¢á¢ðæè¾ÄÆ·éàÌÅ èASÍAw½é©xÌuM¾YvâAwÔÜÅxÌu©ªvƯ¶æ¤ÉAuFOYvêlÌàÊÉ_ªu©êÄq³êéBêlÌSÌßöð`êAñlÈãÌl¨ÌSÌdÈèâA¡Ìl¨ÌåÌ«ÌÖíèÆ¢Á½_ÌzÅÍÈA»ÌSÆÈél¨êlÉu©ê½_ÉæÁÄAq³êÄ¢B
@ܽAdvȱÆÍA_ªu©êéêlðSÆ·é_ÌzÍAìið\¬·éSÄÌqÉe¿µÄ¢é_Å éB±Ì_É¢ÄÍAïÌIÉìi²ÆÉáð°ÄÝÄ¢±ÆÉ·éB
@1iajcÌOñõÌ@Ì éOÌÓAibjM¾YÍQ°Å¬àðÇñÅéÆAicjÀñÅQÄécêªA
@uidj¾úV³ñ̨¢ÅȳéÌͪ¼Å·¼viejÆ]½B
@2bµ½B3iaj·éÆibj°ÂÄîéÆv½icjcꪯ¶ð]½B4ÞÍ¡xÍÔðµÈ©Â½B
@u5»êɷ©èxxðµÄu̾©çA¡ÓÍà¤Ë½ç¢¢Å¹¤v
@u6í©ÂÄÜ·v
@7iajÔàÈibjcêÍ°ÂĹ½B
@8iajÇ꾯©ibjo½B9M¾Yà°È½B10vð©½B11êªß¬Ä½B12ÞÍvðÁµÄAQÔèðµÄA»µÄé ÌÝÉçðß½B
ÈãÌøpÍw½é©xÌ`ªÅ éBúÌucvÌ@Éõ¦ÄQéæ¤É¤Èª·ucêvÉεÄAuM¾YvÍ\í¸¬àðÇݱ¯éBâªÄ°ÈÁ½uM¾YvàAê߬ɰèÉ
B
@`ª©çuM¾YvÉ_ªu©êÄ¢é±ÆÍAùÉæQÍÌl@ÅݽBïÌIÉÍ3¶ibjÌu°ÂÄîéÆv½vÆ¢¤uS`ÊvâA7¶iajuÔàÈvA8¶iajuÇ꾯©vÆ¢¤uS`ÊvðÜñ¾¡«Ì éqÉæÁÄAuM¾YvÉ_ªu©êÄ¢éÆl¦é±ÆªÅ«æ¤B
@¾ªA±±ÅwEµ½¢ÌÍA±ÌêAÌqÍA·×ÄuM¾YvÌàÊɦµÄq³êÄ¢éÆ¢¤±ÆÅ éBPÉ_ªuM¾YvÉu©êÄ¢éÆ¢¤±Æ¾¯ÅÍÈAuM¾YvÌFmâ´oɦµ½qÅ éB10¶uvð©½BvÆq³êA11¶uêªß¬Ä½Bvƻ̩½àeivÌjªw·jªq³êéB±êÍAuS`ÊvÌL³Æ¢Á½u©êé_Ìâ辯ÅÍÈAuM¾YvÌ»ÌÌFmâ´oɦµÄq³êéÆ¢¤±ÆÅ éBêÊVÅͳçɻꪰŠéB
@50¢ÂàÞɯȢQVÌMOªA¡úÍN«ðµÄA×̮ŠÌFqÆ¢ÅéB
@u51iaj¨èÊBìÊAåÊA¬ÊvibjÆ»ñÈðêÉ©ñÅéB52iaj»µÄêiºð£èã°ÄA
@uibj´àå«¢ÌÍFq¿âñÌáÊvicjÆêlª]ÓÆAêlªidjuMO³ñÌ ½ÜviejÆ{½B53ñlͽÕ௶ðJèԵĽB
±êÍAw½é©xÌêÊVÅAQ°ª é®É¢éuM¾YvªA×Ì®Ìlqð®oÉæÁÄ`ʳêéÓÅ éB
@ucêvªN±µÉé±ÆÅN«ãªé±ÆªÅ«ÈÈÁ½uM¾YvÍAcÉïÜèȪçA×Ìlqðf¤BÚÍoßÄ¢éªA®É¶±àÁ½ÜÜÅ é½ßA×ÌlqÍA·¦ÄébµºÅµ©f¢mé±ÆªÅ«È¢B
@±ÌêAÌ`ÊàAuM¾YvÉu©ê½_ÉæÁÄq³êéBuM¾YvÌàÊ»ÌàÌðuS`ÊvÌ©½¿Å¼Úq³êé±ÆÍÈAuM¾YvÌ®oðàÆɵ½FmÉæéîñÌݪq³êéBâÍèAuM¾YvÌ»ÌÌFmâ´oɦµÄq³êÄ¢éÌÅ éBSÆ·éêlÌl¨ÌàÊÉ_ªu©êéÆ¢¤_ÌzÌÁ¥ÆÆàÉA»Ìl¨ÌFmâ´oÉÜŦµÄq³êéÌÅ éB
@wÔÜÅxà¯lÉAu©ªvÌFmâ´oɦµÄq³êéB
@125jÌqÍÙÂÄñm¢½B126êÍïÌ©çlÜûÌG{ðoµÄâ½B127ÉâobNÈǪL½B128jÌqÍ_µA»êçÌG{ðêÂ^_©nß½B129´©ªÍAãÖßè©©ÂÄAºÚgÐðµÄ{ð©ÄéjÌqÌáÆAî£è¯¶ÚðµÄ[¢ÄéêÌáƪ»Âè¾Æ¢ÓÉS¢½B
@130©ªÍêeɺÍê½qð\\áÖÎdÔÅüнêÈÇÉ©éAæà±êç̽ÌÞàÈ¢jÆÆÌOÊÉ°ê½Â«ª¬³ÈêlÌçÈèAgÌ«ÈèÌàÉAµÂÆèƲa³êAêÂÉÈÂÄéà̾Æ]ÓÉÁ©³êéB131ÅAêÆqÆð©r×ÄAæÄéÆvÓB132ÉÆqÆð©r×Äî£èÄéÆvÓB133³¤µÄAÅãÉÆêÆð©r×ÄSÞÌÈ¢Ìð½ÆÈsvcÉvÓª éB
@134¡AðvÐoµÄA©ªÍêɶê½q©çA»Ìðz¹¸Éçêȩ½B135³¤µÄ´lÌ¡Ì^½ÜÅàz¹¸ÉçêÈ¢B
±êÍAêÊUIíè©çêÊVÌͶßÉ©¯ÄÌÓÅ éB ÜèÉóÛÌá¤uÌlvAujÌqv¼ÒÌÚ³ªÄ¢é±Æð[ƵÄAu©ªvÍñlÌqÇàÌe\\uÌlvÌv\\ðzµnßéB
@±ÌwÔÜÅxÌêêÊɨ¢ÄàAu©ªvÌ»ÌÌFmâ´oÉîâÄq³êÄ¢éBPÉu©ªvÉ_ªu©êÄ¢éÆ¢¤±Æ¾¯ÅÍÈAu©ªv̵ĢéiµÄ¢½jÓðA»ÌÌFmɦµÄq³êé±ÆÅA134¶â135¶Ìæ¤Èàʪ¼Ú`©ê½uS`ÊvÖÆzðcçܹĢ±ÆÉÈéÌÅ éB
@wÔÜÅxɨ¢ÄàA_ÌzÍAPÉu©ªvÉ_ªu©êéÆ¢¤¾¯ÅÍÈA»ÌÌl¨ÌFmâ´oÉîëAq³êÄ¢éB»êÍAwÔÜÅxɨ¢ÄAêl̬àÅ èȪçAuqÒvƵÄÌ´IÈuqÒ\»vªñíÉȢƢ¤±Æ©çàà¾Å«æ¤BuqÒvƵÄÌ»ÝÌ_ÅÍÈADÔÉæéu©ªvÌ_ÅÌFmâ´oÉîâÄq³êéB
@m©ÉA130¶©ç133¶ÍA´IÈuqÒvÉÆÁÄ̻ݩçq³êÄ¢éBµ©µA134¶u¡AðvÐoµÄvÆ·®ÉܽDÔÉæÁÄ¢éu©ªvÌ_Éß³êéÌÅ éB±Ìæ¤ÉµÄAwÔÜÅxÍAìiSÌÅÝêÎInADÔÉæÁÄuÌlvÆü©¢¤u©ªvÌÔɦµÄAq³êé±ÆÉÈéÌÅ éB
@u166\¼ÆA\ê¼ÉÍs¯éÈv167±ñÈð]ÓB168½Æ©]ÂÄáн¢B
@169FOYÉÍAj©©ªçÈ¢â¤ÈºðoµÄîé¬Y®Ì«½È¢ª¼®áÉ©ñ¾B170ÅAºi£Â½¬jª¥©ç´Ös̾ÆvÓÆA¹ÌÞ©Ââ¤ÈV[ªã©ç^_ÞÌãµ½ªÉ©ñÅéB171ÞÍâßؽÅV{ð¯Aâ¯ÉSV^_èó©çjÌ ½èðC½B172´ÔàáÒ;ɿç^_·é©ªÌçð©æ¤Æ·éB173FOYÍvÐؽÅãÅà ѹ©¯Äâ轩½B
ãÌøpÍAwäxÌêÊWAuáÒvÌy¢²qÉA̲̫¢uFOYvªÕXðåç¹éÓÅ éB
@̲ª«ÆàdÉèð²¯È¢uFOYvÍAÕXð}¦ÈªçàAEäèÉü©¤B»êÉεÄAuFOYvÉÆÁÄÌEäèÆ¢¤dÌdÝðmçÈ¢uáÒvÍAy¢²qÅbµ©¯éBµ©µAqÅ éuáÒvÉͼÚuÅãvðѹé±ÆÍÅ«È¢B»ÌÕXµ¢CªðuFOYvÌàÊÉ_ªu©êq³êéB
@¾ªA±ÌêAÌqàuFOYvÌ»ÌÌFmâ´oɦµÄq³êÄ¢éB166¶ÌuáÒvÌukb`Êvu\ê¼ÉÍs¯éÈvÆ¢¤±ÆÎðó¯ÄAuFOYvͱê©çuáÒvªü©¤Å ë¤u¬Y®vÉs̾ë¤ÆzðcçܹéB169¶ÍuFOYvÌuS`ÊvÌuvlvÅ éBµ©µA±êÍPÉuFOYvÌàÊð`ʵ½ÌÅÍÈAOÌuáÒv̱ÆÎðó¯ÄÌuS`ÊvÅ èAFmâ´oÜŦµÄÌàÌÅ éB
@wäxÅÍAæÉݽæ¤ÉuFOYv¾¯ÅÍÈAu¨~vâ¨ÌÅ éu¾vÉu©ê½_ÉæÁÄq³êéÓª éB»êÍåèðÆç¦é¤¦ÅàdvÈÁ¥Å Á½Bµ©µA»ÌÁ¥ÍAuFOYvɨ¨ÞË_ªu©êA»µÄuFOYvÌ»ÌÌFmâ´oɦµÄq³êé±ÆªOñÉÈÁÄ¢éÁ¥Å éBìiÌÙÆñǪAuFOYvÌA»ÌÌFmâ´oɦµÄq³êé©ç±»Au¨~vÌàÊÉ_ªu©ê½Æ«ÍuFOYvÆÌuêêvª«¤èÆÈéÌÅ éB¨ÌÅ éu¾vÉ_ªu©êé±ÆÅAåèªÕIÅsÂðIÈSÌßöÅ é±Æª©Ñ ªéÌàA¯lÅ éBæÁÄA¼ÌñÂÌìiƯlÉAwäxàܽAuFOYvÌ»ÌÌFmâ´oɦµÄq³êé±ÆðSƵ½_ÌzÌÁ¥ðàÁ½ìiÈÌÅ éB
@ÈãÌæ¤ÉAw½é©xAwÔÜÅxAwäxÆ¢¤OÂÌúìiɤʵ½_ÌzÍAlÌðÙɵ½ÆµÄàAêlÌl¨ÌSª`©ê½ìiÅ èA»µÄA»Ìl¨ÌàÊðAFmâ´oÜÅà½fµÄq³êéÆ¢¤_ÌzÌÁ¥ðA¤Ê_ƵÄÁÄ¢éÆ¢¦éB±êÍAq@ÌÁ¥ÅÍÈAÇÌæ¤Éq·éÌ©AÆ¢¤_ÌzÌÁ¥ÈÌÅ éB¾ªAÉl¦éq@ÆÌÖAÍ[¢àÌƾ¦éB
@±¤µ½_ÌzÌÁ¥ð¥Ü¦AæQßÅÍAw½é©xAwÔÜÅxAwäxÌOÂÌúìiɨ¯éq@Ì·Ù_ƤÊ_É¢Äl@·é±ÆÉ·éB
@_ÌzÉÂâÄAOÂÌúìiɨ¯éq@É¢ÄÌ·Ù_A¤Ê_ðl@·éBæPßƯlÉAܸ»ê¼êÌq@ÌÅLÌÁ¥É¢Äl@·éB
@w½é©xɨ¢ÄÌq@ÌÁ¥ÍAuM¾YvÌSÌ`©êû̽l«Å éBuM¾YvªN«ÄAucêvÉ ð§ÄAâªÄaðÉéÆ¢¤êAÌSÌßöÍA¿ÌÙÈÁ½uS`ÊvÉæÁÄA§ÌIÉ`©êéÌÅ éBÅà°ÈÌÍAÌæ¤ÈÓÅ ë¤B
@85ÞÍ©Ìâ¤É©gÌQ°ð½½Ýoµ½B86iajåé ©çÌé A»ê©ç¬é ð½½Ü¤Æ·éAÞÍsÓÉibju¦¦vÆvÂÄAicj¡cꪴÉÍÓ½æ¤É©ªÌ´¬é ðÍÓ½B
@87Þͳɵ¦Ä ½ ¨É ª¦½B
@88 µ½©çê·sðµÄâ礩µçB89zKÖXèÉsÂÄâ礩µçB90zKÈçAÔOlÌw¶ª¿Äñ¾B91cêÍV·Å®¢Äî餾©çA©ªªsÂÄîéÔÆàSz·é¾ç¤B
êÊWAuM¾YvÌucêvð¢©ÉµÄSz³¹æ¤©ÆvÄ·éÓÅ éBucêvð©¹ÄÇ¢oµ½uM¾YvÍAȨà»Ì{èð}¦é±ÆªoÈ¢BN«ãªÁ½uM¾YvÍ
ª¦ÈªçAucêvÉεÄXP[gÉs±ÆÅSz³¹Äâë¤ÆìíðûéÌÅ éB
@±±ÅÍAuM¾YvÍ«ÓÉ¿Ä¢éÆv¦éÙÇAïÌIÉucêvðSz³¹Äâ뤩Æl¦éB89¶uzKÖXèÉsÂÄâç¤vA»¤·êÎ91¶u©ªªsÂÄîéÔÆàSz·évÉá¢È¢AÆl¦éÌÅ éB±êÍuS`ÊvÌÅàAuvlvÆÄ×éÙÇÌïÌ«Æ_«ª éBµ©µAÌÓÅÍA¯¶uM¾YvÌàÊÌuS`ÊvÅ éªA»¤µ½ïÌ«àAÓ¯IÈÓ}àÈ¢B
@112M¾YÍ}ÉÂεȽB113·sàâß ¾Æv½B114ÞÍ΢ȪçA´ÉêXXÉµÄ Â½¬é ðæèã°Ä½½ñ¾B115~zcàB116iaj»ê©çcêÌཽñÅ¢éÆibjÞÉÍÂε¢É½¾©«½¢â¤ÈCªNÂĽB117ܪ©RÉoĽB118¨ª©¦ÈȽB119»êª|^_jֿĽB120iajÞÍibj©¦È¢ÔÉicjüêðJ¯ÄcêÌ੪Ìà³Åɵñ¾B121ÔàÈÜÍ~½B122Þ͹̷ª^_µ³ð´¶½B
@êÊWAucêvÆÌïbÉæÁÄuM¾YvÍSÌí¾©ÜèâA{èðSÄðÁ³¹ÄµÜ¤B»êÜŽµÄ¢½uM¾YvªA±±ÅaðÉé±ÆÅA®ðoé±ÆÉÈéB
@ucêvÆÌâèÆèÌãAuM¾YvÍêlÉÈéÆAsÓÉÜð¬µA·ª·ªµ¢CªÉÈéB±ÌÏ»ªAãÌæ¤ÉuS`Êv³êéBµ©µA±±Åڷ׫ÍA±ÌêAÌSÌÏ»ªAuM¾Yv{lÌÜÁ½Ó}µÈ¢Ï»Å éB»êÍAàe¾¯ÅÍÈAucêvðSz³¹æ¤ÆµÄ¢½Æ«ÌuS`ÊvÆÌ`ÊÌ¿Ìá¢ÉæÁÄ঳êÄ¢éB
@116¶ibjuÞÉÍÂε¢É½¾©«½¢â¤ÈCªNÂĽBvA117¶uܪ©RÉoĽBvA118¶u¨ª©¦ÈȽBvA119¶u»êª|^_jֿĽBvA121¶uÔàÈÜÍ~½BvA122¶AuÞ͹̷ª^_µ³ð´¶½BvÆA»ÌÏ»ªuM¾YvÌÓuÆͳÖWÈus®`ÊvâuS`ÊvÌu´ovAuSîvÌqŦ³êéBæÉøpµ½85¶©çÌÓÅÍAuM¾YvÌuS`ÊvuvlvÅïÌIÉAucêvðSz³¹¢ç¹æ¤Æ¢¤ÚIðàÁĦ³êÄ¢½ÌÉεA»ÌSÌÏ»ÍA¿IÉÙÈÁ½qÅ éƾ¦æ¤B
@±Ìæ¤Éw½é©xÌq@ÌÁ¥ÌêÂÉA¿IɽlÈuS`Êvª°çêéB±êÍwäxÅà¯lÌqªFßçêéBµ©µAêl̬àÅ éwÔÜÅxÉÍFßçêÈ¢Á¥IÈq@Å éB
@uS`Êv̽l«ÆÆàÉA_ÌzÅàÆè °½¡«Ì éqàAw½é©xɨ¯éÅLÌÁ¥IÈq@Å éBuêÊÝèvÌq é¢ÍAus®`ÊvÉÜÜê½uM¾YvÌuS`ÊvÅàAuM¾YvÌàʪ¦³êé±ÆÉÈéB±Ìæ¤È½lÈqÉæÁÄAuM¾YvÌucêvÆ̽©çaðÖÆ¢¤A÷Å¡GÈSÌßöªA§ÌIɦ³êé±ÆÉÈéÌÅ éBw½é©xɨ¯éåèªA±ÌSÌßö»ÌàÌÉ é±ÆðÜßÄl¦éÆA±¤µ½q@ÌÁ¥ÍdvÅ ë¤B
@¼ÌñÂÌìiÉÍ©çêÈ¢AwÔÜÅxɨ¯éq@ÌÁ¥ÍAåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêÉæÁÄu©ªvÌSª`©êéÆ¢¤àÌÅ éBæPßÌ_ÌzÌÁ¥Åàݽæ¤ÉAwÔÜÅxÌêÊUÉÍu©ªvÌuS`ÊvªAí¸©O¶µ©È¢Bµ©µA»ÌàʪÜÁ½í©çÈ¢ÌÅÍÈAÌæ¤ÈåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêÉæÁÄAN¾É¦³êÄ¢éB
@u25iajê³ñAÇ¢ÆêævibjƵÂèÌjÌqªûÌÔɵíðñ¹Ä¢ÓB
@u26iaj±±Í²´ñ·ævibjÆêÍwÌÔðºëµÈªçéÉ]½B
@u27½ÁÄ¢¢æv
@u28úÌ ½éÖéÆA¨ÂÞ ªÉÝÜ·æv
@u29iaj¢¢Â½çvibjÆqÍ°ëµ¢çðµÄêðÉçñ¾B
@u30iajê³ñvibjÆéÉçðñ¹ÄAuicj±ê©çËA¢ÜÅsñÅ·©çËB31áµrÅA¨O³ñ̨ÂÞ ÅàÉÝo·ÆAê³ñÍ{É«½¢Ê¢éñÅ·©çËB32ËA¢¢¾©çê³ñÌ]Óðm¢Ä¸ÕB33»êÉËA¢ÜÉúÌ ½çÈ¢û̪ ©çA³¤µ½ç¼®¢çµâ¢ËB34ðèܵÄHv
@u35iajªÈñÄÉÈèâdȢ½çvibjÆqÍ®P^_µ]У½B36êÍßµ³¤Èçðµ½B
@u37¢éÌ˦v
@êÊUÌͶßAu©ªvªuÌlvÆ»ÌqÇàujÌqvÆÌâèÆèð©Ä¢éÓÅ éBú½èÌ¢¢êµ©Èªó¢Ä¨ç¸AuÌlvÍujÌqvÌ̲ðl¦ÄÀçÈ¢Ù¤ª¢¢Æ¾¤Bµ©µAujÌqvÍǤµÄàÀ轪èêeð¢ç¹éAÆ¢¤êÊÅ éB±ÌãAu©ªvÍuÌlvÌ¢Á½lqð©©ËAujÌqvÉúª½çÈ¢©ªÌÈð÷ÁÄâé±ÆÉÈéB»Ì«Á©¯ÌÓÅ éB
@±ÌÓÅÍA©Ä¢éu©ªvÉηéuS`Êvͨë©Au©ªvÉηé»ÌÙ©Ì`ÊÍêØÈ¢B±±É éÌÍAuÌlvÆujÌqvÆÌâèÆèÌݪ¦³ê½ukb`ÊvAus®`Êvµ©È¢Bµ©µA»êƯɱ±ÉÍA»ÌâèÆèð©Âßéu©ªvÌêqÉηéóÛÌᢪFZ½f³êÄ¢éƾíȯêÎÈçÈ¢B
@ujÌqvÍA29¶ibju°ëµ¢çðµÄvA35¶ibju®P^_µ]У½vÆA·«ª¯ÌÈ¢äÔÈqÇàƵÄAóÛ«q³êéBêûA»ÌêeÅ éuÌlvÍAIn¸â©É26ibjuéÉvA30¶ibjuéÉvÆJÉbµ©¯éB»êÅà[¾µÈ¢ujÌqvÉεÄAußµ³¤Èçðµ½vÆq³êéB±Ì¼ÒÍAêeð¢ç¹éÈóÛÌujÌqvA§qðSzµÄ¢éÉà©©í縢ç³êé©í¢»¤ÈuÌlvÆ¢¤Îäª éB±Ì_ÅÍuÌlvÉεÄ[¢¯îðø¢Ä͢ȢªA»ÌGèͱÌ_ÅùÉ éB±±ÅA»Ì¼ÒÌóÛÌÎÆ«ªA¼ÚIÉu©ªvÌuS`ÊvÉæÁÄA¦³êé±ÆÍÈ¢Bµ©µA»ÌSÍêqñlðÆ禽qÌÉ éÌÅ éB
@w½é©xâwäxÉÍA½lÈuS`Êvª©çê½BêûÌwÔÜÅxÅÍA¸¦Ä»ÌuS`ÊvªÈ¢±ÆÅAu©ªvÌàÂêqÌóÛÌᢪ¦³êȪçàA»êª¢¾[¢¯îÉÍBµÄ¢È¢AÆ¢¤u©ªvÌàÊð¦µÄ¢éB»µÄuÌlvÖÌÖSªå«ÈèA¯îª[ÜÁ½êÊWÅÍAu©ªvÆuÌlvÉ¢ļÚuS`Êv³êé±ÆÉæÁÄA»ÌSÌÏ»ª¦³êéæ¤ÉÈéB
@±¤µ½q@ÍAOÂÌìiÌÅwÔÜÅxÉÌÝ©çêéÁ¥Å éB
@wäxɨ¯éq@ÌÁ¥ÍA¼g\»Ì½pÆAElɱ©êÄ¢uFOYvÆηé©Ìæ¤ÈqÌC[WÌA½Å éBwäxÅÍAuáÒvðEµÄµÜ¤Æ¢¤AªÍÎÛƵ½OÂÌìiÌÅàAÁêÈðàÁ½ìiÅ éBuFOYvÌElÖÌßöðl¦é¤¦ÅA¼g\»ÆAqÌC[WÌA½ÍdvÈq@ÌÁ¥ÆÈÁÄ¢éB
@26Éq˪J¢½B
@u27³yÌRcÅ·ªAUßlª¾úÌÓ©çä·sðVηñÅ·©çA[ûÜűêðu¢Åu¢Äº³¢B28ªæèÉÜ·v29̺¾B
@u30iaj¡úÍ¿ÂÆ½Ä ñÅéñÅ·ªA¾ú̩̤¿Àâ ¢¯Ü¹ñ©HvibjÆY̺ª·éB
@31iajÍê¡a½lq¾Â½ªA
@uibjÀâ ÔáÐÈËv32iaj©¤¢ÂÄÉqËðÂß½ªA¼®J¯ÄA
@uibjäÊ|ÅàeûÉäèеܷæv
@u33 ÌAeûÍccv34Yª¢ÓB35iaj»êðÕÂÄA
@uibjAâéºIvicjÆFOYÍQ°©ç{½B36s©Â½ªmêĽB37iaj»êÉÍÖ¸A
@uibjæ뵤äÀ¢Ü·vicjÆYÌ]Óidj̪·¦éB38ÍÉqËðÂß½lq¾B
wäxÌêÊUA§ÄñÅ«½XÉAuävðu¢ÅÙµ¢Æ¢¤dÌ˪üéB»êðQ°É¢éuFOYvª·¢Ä¢éÆ¢¤ÓÅ éB±±ÅuFOYvÍdð¿¯éƾÁ½±Æ©çAê{Ìuävðu¢¾èA±êÅEðäÁ½è·é±ÆÅAuáÒvðEµÄµÜ¤æ¤ÉÈéÌÅ éB
@Q°É¢éuFOYvÍAdêÆÍʺɢé½ßA®oÉæÁÄAqÆXÌElÌuYvÆÌïbðFm·éBÁÉueûvÉu¢ÅÙµ¢Æ·¦½uFOYvÍA©ªªu®ÆAQ°©çÔð·éBµ©µA»ÌºÍ36¶us©Â½ªmêÄvéB±Ìs³ÍAQ°©çÔðµÄ¢é½ßºð£èã°½±ÆÉæéus³vÅ éBµ©µA»êƯÉ_oÌs³Å éBøpÌOÉ ½éÓÅAMÅ©³êé±ÆÅ_oªsÈÁÄ¢élqª¦³êéB
@³çÉA±ÌqÍAâªÄuáÒvEµÖÆéElÖÌßöðl¦éÆ«AuävÆuFOYvÌSªsÈÁĢƢ¤Aq̱ÆÎÌC[WðàÂus³vÅà éB½x©»Ìus³vªqÌÈ©ÉÜÜêé±ÆÅAìiÌ\èuävÌC[WÆdÈèAqƵÄàElÖ±©êÄ¢ÌÅ éB
@195iajÕXµÄ{轩½CªÍ«½¢â¤ÈCªÉÏÂÄibj¡ÍgàCàSæêĽB196áÌÍMÅn¯³¤É¤éñÅîéB
@197ô©çjAèóAzÈÇðä½ãAôÌ_©¢ªªÇ¤µÄà¤Üs©ÊB198±¾Íèsµ½ÞÍ´ªðç²Æí¬æè½¢â¤ÈCªµ½B199iaj§Ìr¢êÂ^_ÌÑÉûªÂÄéâ¤Èçð©ÄéÆibjÞÍ^Ý©ç»ñÈCªµ½ÌÅ éB200áÒ͢©°üÂĹ½B201ªèÆãÖñðཹĽí¢àÈ¢ûðJ¯ÄéB202sµÐÈAæ²ê½ª©¦éB
@203æêؽFOYÍÄàNÁÄàçêÈ©Á½B204ÄÌÖßÉÅÅà³ê½â¤ÈSªµÄîéB205½àÞà°oµÄ´ÜÜ´Ö]°½¢â¤ÈCªÉȽB206à¤æ³¤I@207©¤ÞͽÕv½©mêÈ¢B208RµÄ«IÉËR±¾ÍÂĽB
@wäxêÊWA¢æ¢æ·µÁ½uM¾YvªuáÒvÌôɯé¼OÌÓÅ éBuävðÂèÉgÌ´oª¸íêAæê«ÁÄ¢uFOYvÌSª¦³êéB
@196¶uáÌÍMÅn¯³¤É¤éñÅîévA204¶uÄÌÖßÉÅÅà³ê½â¤ÈSªµÄîévÆAMªuFOYvÌoÜÅ`µÄ¢lqÆAè³¾¯ÅÍÈSgÌgÌ´oªDíêÄ¢lqª¼g\»Å¦³êéB
@æÉÇ¢ÜêÄ¢uFOYvÌSðÆç¦é½ßÉÍA±êçÌÁ¥Iȼg\»ð³·é±ÆÍÅ«È¢BܽA±Ì¼g\»Éà¿¢çêÄ¢éuÅvÆ¢¤gàAElÖÆ¢¤C[WðAqã̱ÆÎÉæÁijêÄ¢éÆྦæ¤B»ÌOÉuòvðùñÅ¢é͸ÌuFOYvÍASgªáµAuÅvð·çê½æ¤É´¶çêéÌÍAElÖÌC[WÌA½Å éB
@æPÍÅg½ì®¡i1965jÅÍAJèêY̶ÍÆäµÄAuê¼Æ̶Íɨ¢ÄÍA¼ªÙÇ̼g\»µ©È¢±ÆðwEµÄ¢½B»µÄ»êÍuÐï«vÆu¨vÆ¢¤¼Ò̶ÍÌ·Ùð¦·àÌÅ éƵĢ½Bm©Éw½é©xâwÔÜÅxɨ¯é¼g\»ÍAÁM·éÙǽÍÈ¢Bܽ»êƯÉAwäxɨ¯é¼g\»Ìæ¤ÈAåèÆ©©íéàÌÅÍÈ¢Bwäx̱¤µ½q@ÌÁ¥ÍAÅLÌàÌÅ éÆ¢¦æ¤B
@ÈãAOÂÌìiÌq@ɨ¯é·Ùðl@µÄ«½Bw½é©xɨ¢ÄÍA½lÈuS`ÊvÆ¡«Ì éqAwÔÜÅxɨ¢ÄÍA»ÌàÊð¼ÚuS`Êv³êé©Û©ÉæÁÄAàÊÌÏ»ª¦³êéÆ¢¤Á¥ª Á½BwäxÅÍA¼g\»ÆAqÉÜÜê½±ÆΪàÂC[WÌA½ÆÉæÁÄAElÖÌßöª¦³êÄ¢½B
@±¢ÄAw½é©xAwÔÜÅxAwäxÆ¢¤OÂÌúìiɨ¯éq@̤Ê_ðAæQßÅl¦é±ÆÉ·éB
@»êÅÍAw½é©xAwÔÜÅxAwäxɤʵ½q@ÌÁ¥ÍAÇ±É éƾ¦é¾ë¤©B
@_Ìz̤ʫÍAìiÌSl¨ÌA»ÌÌFmâ´oÉîâÄq³êÄ¢éÆ¢¤àÌÅ Á½Bq@ɨ¯é¤Ê«ÍAåÏIÈ]¿«Ì éPêðÜñ¾qªA»ÌSl¨ÌSð©ÞãÅdvÈqÉÈÁÄ¢éÆ¢¤±ÆÅ éB»µÄA»êͤʵ½q@ÌÁ¥Å éÆÆàÉA»ê¼êÌåèðÆç¦é½ßÉÍsÂÈàÌÅ éB
@w½é©xÅÍAïÌIÉÍÌæ¤ÈqÅ éB
@u38{ɵĨàêB39नVàFoÄÜ·¼v
@u40í«ÖÄ»¤®Ã^_]Ó©çA®N«çêÈÈéñ¾v
@u41 Ü̶âIv42iajcêÍibj{ÂÄicjoÄs½B43M¾YàरÍÈȽB44N«Äࢢ̾ªA]èN«ë^_Æ]Íê½ÌÅÀÛN«ÉÈÂĽB45iajÞÍ{Æ°ÌÔÌÑð©ÈªçAibj»êÅàà¤NµÉé©^_Æ¢¤sÀð´¶Ä½B46N«Äâ뤩ÈÆvÓB47Rµà¤µÆvÓB48व±¤µÄÄNµÉȩ½çA»êÉƶÄN«Äâç¤A³¤vÂÄ¢éB49ÞÍå«ÈáðJ¢Ä¢¾¡ÉÈÂĽB
w½é©xÌêÊUAOxucêvÉN±³êé±ÆÅuM¾YvÍA®SÉáªoßĵܤBµ©µAucêvɽxàN±³êé±ÆÅAtÉÚªoßÄàN«ãªèÃçÈéB»±ÅAu¤µ±¤µÄÄNµÉȩ½çA»êÉƶÄN«Äâç¤vÆAQ°ÉµÎç¢Âïé±ÆÉ·éBÈãAucêvð{ç¹A©¹éÜÅuM¾YvÍN«ãªë¤ÆµÈ¢B
@49¶uå«Èávðµ½ÜÜuM¾YvÍQ°Å¡½íéB±Ìuå«ÈvÆ¢¤åÏIÈ]¿«ðàÁ½qªA®SÉáªoßĵÜÁ½uM¾YvÌàÊð çíµÄ¢éBùÉáªoßAN«é©N«Ü¢©Yñ¾åAucêvªN±µÉȯêÎN«æ¤ÆßéB»±ÉÍAucêvÉεÄÌÍÁ«èƵ½Ó¯ª éB»Ì½ßuå«ÈvÆ¢¤åÏIÈ]¿«ðÜñ¾PêÉæÁÄA²³êé±ÆÉÈéB
@qƵÄuM¾YvÌàÊðÜñ¾æ¤ÈA¡«Ì éqÅÍÈ¢Bµ©µAuM¾YvÌàÊ\\oÁÌóÔÆAucêvÉηéN«Ü¢Æ·éÓ¯\\ðÆç¦é½ßÉÍAdvÈqÆÈÁÄ¢éB
@38iaj©ªÍËRA
@uibjÖ¨¢Åȳ¢vicjÆÌðêÚè ¯ÄAuidjÈçúªèܹñæviejÆ]½B
@39jÌqÍ}ÈáÅ©ªð©½B40çFÌ«¢AªÌ«ÌJ¢½AÈq¾Æv½B41©ªÍ¢âÈCªµ½B42qͨÆ@ÆÉÈðÂ߼B
@u43Ü AǤà°êüèÜ·v44iajÌlÍßµ¢çÉÎð©×ÄAuibjê³ñAäçð]ÂÄA »±ðqØȳ¢vicjÆqÌwÉèðâÂÄûÖ·â¤É·éB
@u45¢çµâ¢v46©ªÍjÌqÌèðæÂÄ©ªÌTÉ¿ç¹½B47jÌqÍÈá«ÅX©ªÌçð©Ä½ªA¬µÄQOÌiFÉ©ü½B
@wÔÜÅxÌêÊUA¢Á½lqÌuÌlvð¯æ¤ÆAujÌqvÉu©ªvªÀÁÄ¢½Èð÷ÁÄâéÆ¢¤ÓÅ éB±±ÅujÌqvÉÈð÷Á½±Æ©çAu©ªvÍêqÉÖíÁÄ¢±ÆÉÈéA»Ì«Á©¯ÆÈéÓÅ éB
@wÔÜÅxɨ¢ÄAÁ¥IÈÅLÌq@ÌÁ¥ÆµÄA¼ÚuS`Êv³êéÌÅÍÈAuÌlvÆujÌqvÆÌ`«í¯ÉæÁÄAu©ªvÉÆÁÄÌñlÌóÛÌᢪÔÚIɦ³êé±ÆðmFµ½B»ÌÁ¥ÉÖAµÄA»¤µ½q̽ÍAåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêðÜñ¾qÆÈÁÄ¢éÌÅ éB39¶u}ÈávA40¶uÈqvA41¶u¢âÈCvA44iajußµ¢çvA47¶uÈá«vÆ¢¤qÉAåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêªÝçêéB±êçÍ·×Äu©ªvÉÆÁÄÌAujÌqvÌóÛÌ«³ÆAuÌlvÌóÛÌdzƪÎä³êÄ¢é`ÊÌÌêÅ éB
@±Ìæ¤ÉAwÔÜÅxÌq@ÌÁ¥Å Á½A±¤µ½ÎÆIÈ`ÊÌÈ©ÉAåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêªÜÜêÄ¢éÌÅ éB»µÄA±ÌÁ¥ÍwäxÉà ÄÍÜéOÂÌúìiɤʵ½àÌÅ éB
@189iajŽÌÞÌbµ©¯½áÒÍibjFOYÌs@É°êÄicjÙÂĹ½B190»µÄzðäéªÉÍÌóµ¢J©çéæJŤÂç^_dnß½B191ÑöàÉßÂÄ°ÂÄéB192àÔð¾Ü·ºª~ñÅAлèÆȽB193éÍààOàSÃÜèÔ½B194ä̹¾¯ª·¦éB
wäxÌêÊWAuFOYvªuáÒvÌEðäÁÄ¢éÆAüè©ç¹ªÁ¦Ä¢«AÓèªÃâÉïÜêĢƢ¤ÓÅ éBÃâªuFOYvÉÓ¯³êé±ÆÅAuFOYvÍEðäé±ÆÉW³¹çêA³çÉÕXðåç¹Ä¢±ÆÉÈéB
@uáÒvÍ°ÁĵܢAuÑövà°èu¨~v̺෦ÈÈéB»µÄA193¶uààOàSvA194¶uä̹¾¯ªvÆAÃâªåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêÉæÁÄA²³êĦ³êÄ¢éB²³êé±ÆÅAÃâªæèêw[ÜèAuFOYvð
@ܽwäxÌÁ¥IÈq@ÉA¼g\»ª°çê½BL¾¦ÎA¼g\»àAåÏIÈ]¿«ðàÁ½\»Å éÆ¢¦éB½ðAÇÌæ¤É©é©A·¦é©Æ¢Á½uÆ禩½vÌâèÅ éA¼g\»ÍAåÏIÈ]¿«ðàÁ½\»Å éB»ÌÓ¡ÅàAwäxɨ¢ÄåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêA é¢Í\»ðÜÞqðl¦é±ÆÍAåèðl¦é¤¦ÅsÂÈÌÅ éB
@±Ìæ¤Éuê¼ÆÌúìiɨ¯é¤Êµ½q@ÌÁ¥ÍAåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêÅ èA»êªìiÌåèƧÚÈ©©íèðàÁÄ¢éB±±ÅAæPÍÅݽæs¤ðà¤êxÝĨ«½¢B
@g½ì®¡ÍAJèêY̶ÍÆärµÄAuê¼Æ̶Íðu¦¨I«iv̶ÍÅ èAuu¨vÉü©¤v¶ÍÅ éÆwEµÄ¢½B³çÉAJèêY̶ÍæèàA¼ª½A`eE¼g\»ªÈ¢Æ³êÄ¢½B»µÄA±ÌªÍEl@ÍAî{IÉAêèÊ̶Íɨ¯éiâ\»ÌÊIȽÇÉæéàÌÅ Á½B
@µ©µAåèÆÖA³¹Äl¦éÆAÞµëAtÈÌÅÍÈ¢¾ë¤©BÂÜèAg½ì®¡i1965jÅwE³êÄ¢½È¢iâ\»ªAåèðÆç¦éãÅdvÈPêA\»Å èAsÂÈqÈÌÅ éB¾ªA»êÍA¬Ñpvâg½ì®¡Ì¢¤u¨ÌYvAu¦¨I«iv̶ÍÅ é©ç±»AåèƧÚÉÖíéqÅ éÆ¢¤à¾àÅ«æ¤B¶ÍSÌÅAå¼Å éu¨Éü©¤vqÌÅAåÏIÈ]¿«ðàÁ½Pêâ\»ðÜñ¾qÉæÁÄAåè\\ìl¨ÌSÉÖíéàÌ\\ª©Ñãªéæ¤ÉdgÜêÄ¢éÌÅ éB
@½Í©ÈÌÀ¶É§ µ½ìÒÌuáv̨¦½¢EÍA×ÉĶ«¶«µ½oÌ[À𦷪A»êçÌ`ÊÍÎÛÌPÈéÊ^IÄ»ÅÍÈåÏÌ¢½¶«½ÊÀÅ éB±Ìuê¼ÆÉÆÁÄÍAu©évÆ¢¤oI®ìͦul¦évÆ¢¤vlI®ìÉÂȪéBÂÜ袩Éæu©v½Ûðo¦Ä¢é©A»ÌmÀ³Í»ÌÌSIàeÌm©³Å èA©½àÌÆ»ÌÌSÌóÔƪsªÈàÌƵĶݷéí¯Å éB
iT_´¶B
Jûßqi1977juu½é©vÉݦéuê¶wÌ´^v
wÉì¶xæ11j
@ãÌøpÍAæPÍÅàݽJûßqi1977juu½é©vÉݦéuê¶wÌ´^viwÉì¶xæ11@1977N3jÌAuê¼Æ̶ÍÉ¢ÄÌwEÅ éBuê¼Æ̶ÍÉ¢ÄAuu©évÆ¢¤oI®ìͦul¦évÆ¢¤vlI®ìÉÂȪévÆ¢¤s¢uåÏÌ¢½¶«½ÊÀvÉæéàÌÅ éÆwEµÄ¢éBµ©µæPÍÅA±ÌwEÍA\»êÊA¬àêÊɤʷéàÌÅ é±ÆðmFµ½B\»åÌÉæÁÄA\»Ó}ðB¬·é½ßɵÜê½nìIÈuìivÅ é¬àÍAÇñÈ`ÊiLqjÅàAÇñÈà¾i]ßjÅàA\»åÌÌul¦éÆ¢¤vlI®ìvÉÂȪçÈ¢àÌÍÈ¢BÅÍA±ÌwEªÓ¡·éƱëÍÇ±É é̾뤩B
@»êÍAuê¼ÆÌúÌOìiɤʵÄÝçê½q@ÌÁ¥É éÌÅÍÈ¢¾ë¤©BOÂÌúìiɤʵ½q@ÌÁ¥ÍAåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêªAìl¨ÌSðÆç¦é¤¦Å©¹È¢àÌÅ Á½B»µÄA»êÍåèâ\¬ÆàÖA·édvÈq@ÌÁ¥Å Á½Buu©évÆ¢¤oI®ìͦul¦évÆ¢¤vlI®ìÉÂȪévÆ¢¤Jûßqi1977jÅÌwEªA\»êÊE¬àêÊÉηé¾yÅÍÈAuê¼Æ̶ÍÌÁ¥Éηé»êÅ éÈçÎA»ÌÓ¡Í»Ìq@ÌÁ¥ðwµÄ¢éÌÅÍÈ¢¾ë¤©B
@¾ªA±±ÅdvÈÌÍAuê¼ÆA é¢ÍSÆÈéìl¨ÉÆÁÄÌuåÏv©uqÏv©Æ¢¤ñΧÅl¦ÄÍÈçȢƢ¤±ÆÅ éB©½àÌA·Èí¿`ÊâLqªA¦l¦½±ÆA·Èí¿»ÌàÊâS»ÌàÌÅ éÆ¢¤wEÍA\»êÊÉÂȪéÕIÈÁ¥ÆÈÁĵܤBµ©µA»êªåèðÆç¦é¤¦ÅdvÉÈéAÆÆç¦éÆAuê¼Æ̶Íìiɨ¯éÁ¥ÌêÂƾ¦éÌÅÍÈ¢©B
@·Èí¿Auê¼ÆÌúìiɨ¢ÄAåèÍAêlÌÅ êOlÌÅ êASl¨ÌSÌNâßöª»ÌÜÜåèɼµÄ¢éB·¾·êÎAåèðÆç¦é½ßÉÍ÷Å¡GÈl¨ÌSðÆç¦é±ÆªsÂÅ éB»ÌSÌßöðÆç¦éÉÍAPÉuS`Êv¾¯ðÇÁÄ¢ÄàÆ禫é±ÆÍÅ«È¢Bw½é©xÅÍA¡«Ì éqAwÔÜÅxÅÍÇÌæ¤Éêqª`«ª¯çêÄ¢é©AwäxÅÍA¼g\»ªA»ÌSðÆç¦é½ßÉsÂÈq@ÌÁ¥Å Á½B»êÉÁ¦ÄA±êçOÂÌúìiÉÍAåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêðÜñ¾qªA»ê¼êÌSðÆç¦é¤¦ÅsÂÈqÅ Á½Buê¼ÆÌúìiɨ¢ÄAì¨ÌSÌßö»Ìà̪åèi é¢ÍåèƧÚÉ©©íéàÌjÆÈè¤éêAåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêðÜñ¾qªAìiÌåèðÆç¦é¤¦ÅAĪ©èÆÈéB
@uu©évÆ¢¤oI®ìͦul¦évÆ¢¤vlI®ìÉÂȪévÆ¢¤JûÌwEªdvÉÈéÌÍA±Ì½ßÅ éBàʪ\í³ê½©½oIÈÎÛÍAÈÉðÇÌæ¤É`©êé©Æ¢¤±ÆªA´¶½Al¦½Æ¢¤SâvlIÈàÊÉÑ¢ĢéBu¨`Êvâul¨`ÊvªAÇÌæ¤ÈåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêðÜñÅ¢é©AÆ¢¤±ÆªAìl¨ÌàÊÉÖíèA»êªåèðÆç¦é¤¦ÅdvÈqÉÈÁÄ¢éB¾©ç±»Auu©évÆ¢¤oI®ìͦul¦évÆ¢¤vlI®ìÉÂȪévÆ¢¤wEªAuê¼Æ̶ÍÌÁ¥ÆÈéÌÅ éB
@±Ìq@̤Ê_ÍA_Ìz̤Ê_ƧÚÈ©©íèª éBSÆÈéìl¨Ì»ÌÌFmâ´oÉîâÄq³êé©ç±»AåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêðÜñ¾q@ªA»ÌSðÆç¦é¤¦ÅdvÆÈéÌÅ éB
{eÅÍAuê¼ÆÌúìiAÆÉw½é©xAwÔÜÅxAwäxÆ¢¤OÂÌìiÉ¢ÄA_ÌzÆq@É
ڵȪçAl@ð¨±ÈÁÄ«½BÄÑÜÆßéÆ·êÎA{eÌ_ÍÌæ¤ÉÈë¤B
@w½é©xÍAucvÌ@Ì©AuM¾YvªucêvÉN±³êéÆ¢¤±Æð[ƵÄAuM¾YvªucêvɽµaðÉéÆ¢¤SÌßöª`©ê½ìiÅ Á½BÅIIÉaðÉé±ÆÅAuM¾YvͼÒÉü«¤©ªÉεÄÌÓ¯ðl¾·é¨êÅ Á½B»ÌSÌßöªA¿ÌÙÈÁ½uS`ÊvâAuM¾YvÌuS`ÊvðÜñ¾qÆ¢¤¡«Ì éqÉæÁÄA§ÌIÉ`©êÄ¢éÆ¢¤Á¥ª Á½B»±ÉÍAl¨Ìà©O©AÆ¢¤ñΧIÈ_ÌzÅÍÈAàÊð©Êµ½OÊÌ`ÊðÂ\É·é_Ìzª Á½B
@wÔÜÅxÍA½Ü½Ü¯¶Ô¼ÌêÔÉæèí¹½uÌlvÉεÄAu©ªvªÖSƯîðø«ASIÈ£ðkßĢƢ¤ìiÅ Á½B»êͯÉA ÜżlƵÄuÌlvÆÚ·é½ßA[¢¯îð¦µÈªçàAõ³ê½u[vð©È¢Æ¢¤u©ªvÆuÌlvƪ¾mÉüø«³ê½Æ±ëÅÌÖSE¯îÅ Á½BÖSE¯îðø¢Ä¢»ÌßöªAuÌlvÆA»Ìêð¢ç¹éñlÌqÇàƪul¨`ÊvÉæÁÄóÛª`«ª¯çêéB»µÄqÇàÌeðz·é±ÆÉæÁÄASIÈ£ðkßAuÌlvÉηéuS`ÊvÜųêéÙÇɻ̣ÍßÃB»¤µ½qÌÏ»ÍA»ÌÜÜ_ÌzÌÁ¥Å èAq@ÌÁ¥Å Á½B
@wäxɨ¢ÄÍAáÌ¢ElÅ Á½uFOYvªAlXÈuêêvðN±·±ÆÅAuáÒvðEµÄµÜ¤Æ¢¤SÌßöð`¢½ìiÅ Á½Bµ©àA»ÌSÌßöÍAÕIÅsÂðIÈßöÅ éæ¤ÉAu¾v©çfµo³ê½àÌƵÄ`©êÄ¢½BuFOYvªlXÈàÌE±ÆÆuêêvðN±µÄ¢ßöðA¿Ì½lÈuS`ÊvÆAu©êé_ªÏíé±ÆÉæÁÄA¦³êÄ¢½B»µÄAìiÌÅãÅu¾vÉ_ªu©êé±ÆÅAlÔƵÄÌ»fðº³È¢uqÒvª©ÑãªéB±¤µ½u©êé_ÌÏ»ªwäxÌåèðl¦é¤¦ÅàAdvÈ_ÌzÅ Á½B
@ÈãÌOÂÌìiðªÍEl@µ½Ê©o³ê½¤Ê_ÍÌæ¤ÉÈë¤B
@OÂÌìiɨ¯éA_Ìz̤Ê_ÍAeìiÌÅSÆÈéìl¨ÌA»ÌÌFmâ´oɦµÄq³êéÆ¢¤àÌÅ Á½B±êÍìl¨ÌSÌßöª»ÌÜÜAåè»ÌàÌÅ é±ÆÆàÖWµÄ¢éÁ¥Å Á½B
@êûAOÂÌìiɨ¯éq@̤Ê_ÍA»¤µ½_ÌzÆÌÖAÅA`ÊÉÝçêéåÏIÈ]¿«ðàÁ½PêÉÜñ¾qªAåè\\ìl¨ÌSÌßö»ÌàÌ\\ðl¦é¤¦ÅdvÈqÅ éÆ¢¤±ÆÅ éB
@±Ìæ¤Èl@ÌÊÍAPɶÍ\»_âuê¼Æ¤ÉÆÇÜéàÌÅÍÈ¢B{eÅÎÛƵ½OÂÌìiâA»ÌÙ©Ìúìið³ÞƵÄà¿¢éÎ ¢ÌîbIȤƵÄLøÅ éÆl¦éB
@{eÍAuê¼ÆÌúìiÉ¢ÄAªÍÎÛðOÂÌìiÉièAl@µÄ«½B{¤ÆµÄÌ_É¢ÄÍAIÍÌÊèÅ éB³çɤðißÄ¢É ½ÁÄÌ¡ãÌÛèƵÄÍAÌæ¤È±Æª°çêæ¤B
@ܸA³çɽÌúìiðªÍÎÛÆ·éKvª éBqÐÆÂÐÆÂÉ¢ĪުÍð¨±ÈÁ½ÊA¾ç©ÉÈÁ½±ÆÍuê¼ÆÌúìiðl¦é¤¦Å»Ìê[ÉÈé±ÆÍm©Å ë¤Bµ©µúìiÍAuê¼ÆÌìiÌÅàA½í½lÅÀ±IÈìiª½ éB»êçÌìiðl¦éÉÍAæè½ÌìiðªÍEl@·éKvª ë¤B
@»ÌãÅAúEãúÆÇÌæ¤ÈÖW«ª éÌ©AÆ¢¤ÊIÈÏ»AÏeÆ¢Á½ªÍEl@ªl¦çêéBuê¼ÆÆ¢¤ìÆÉÆÁÄA»Ì\»©çl¦éÎ ¢AÇÌæ¤ÈÏ»ª éÌ©A é¢ÍȢ̩ð¾ç©É·é½ßÉÍA¼ÌúÆÌÎÆEärªsÂÅ ë¤BúEãúÆÌÖAÅl¦ÄͶßÄA^ÌÓ¡ÅÌAúìi̶Í\»Á«ª¾ç©ÉÈéB
@ÈãÌæ¤ÈÛèðl¦éÀèA{¤Å¨±ÈÁÄ«½IÍÜÅÌl@ÍAuê¼ÆÌúìiɨ¯é¶Í\»Á«ðl¦é½ßÌêiKÉ߬ȢÌÅ éB
@@@@@@
@ÅãÉA±ÌCm_¶Ì®¬É ½ÁĽÌl̲w±E²Ú£ÈçÑɲ¾ðÁ½Bw±³õÅ éìQ³²æ¶A¼Úw±µÄ¾³Á½ìAæ¶ðͶßƵÄAåã³çåwÌêuÀÌæ¶ûÉÍA½Ì±Æð³íÁ½BÓÓð\µ½¢BܽA¼åwÅ èȪçAwïE¤ïÅçð í¹é½ÑÉA²w±â²¾ðº³Á½éËRåwÌêTæ¶ÉÍAåϴӵĢéB
@æyAãyA»µÄ¯Ìåw@¶ÉàAɶçêAÉỵ ¢AÉhðó¯ÈªçñNÔwԱƪū½BÅàAêNãÌæyÅA¯¶lV¤Û§³åwogÌöèbü³ñª¢È¯êÎAåw@üwàCm_¶ð« °é±ÆàÅ«È©Á½¾ë¤B èªÆ¤²´¢Üµ½B
¹
½¬17N114ú
@±Ìy[WÍCm_¶i½¬16Nxj®¬EñoÉ ½èA·MÒiûücj©ç쬵½àÌÅ·B
@±Ìy[WÍAEChEETCYÍ700sNZÈãð§Å·BfUCÍAX^CV[gÅKèµÄ¢Ü·BX^CV[gðLøɵĢȢêA³µ\¦³êÈ¢±Æª èÜ·B
@±Ìy[WÉ©©êÄ¢é¶ÍE»Ì¼ÍA·×Ļ̧ìÒÉì ª èÜ·By[WÌàeðøp·éÛÍAì ÌÝð¾L·é±ÆyÑA±Ìy[WÖÌNððƵÄAµܷB
copyright (c) 2005, Takada Hisashi