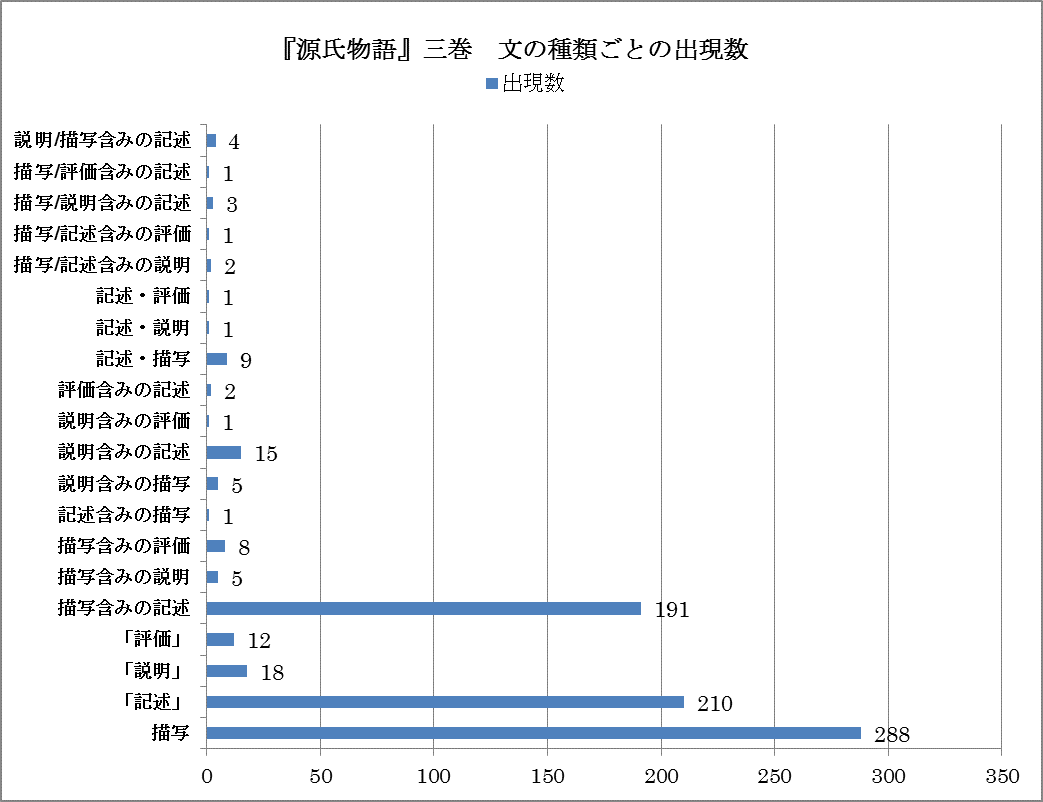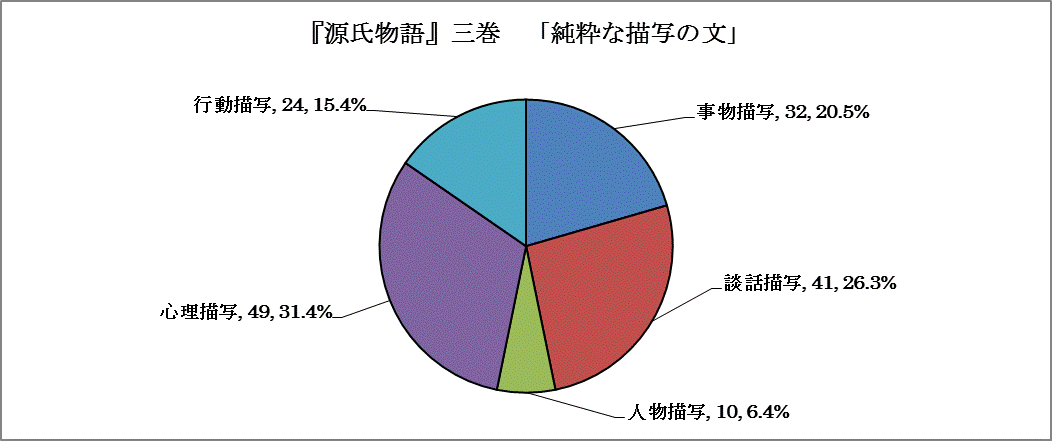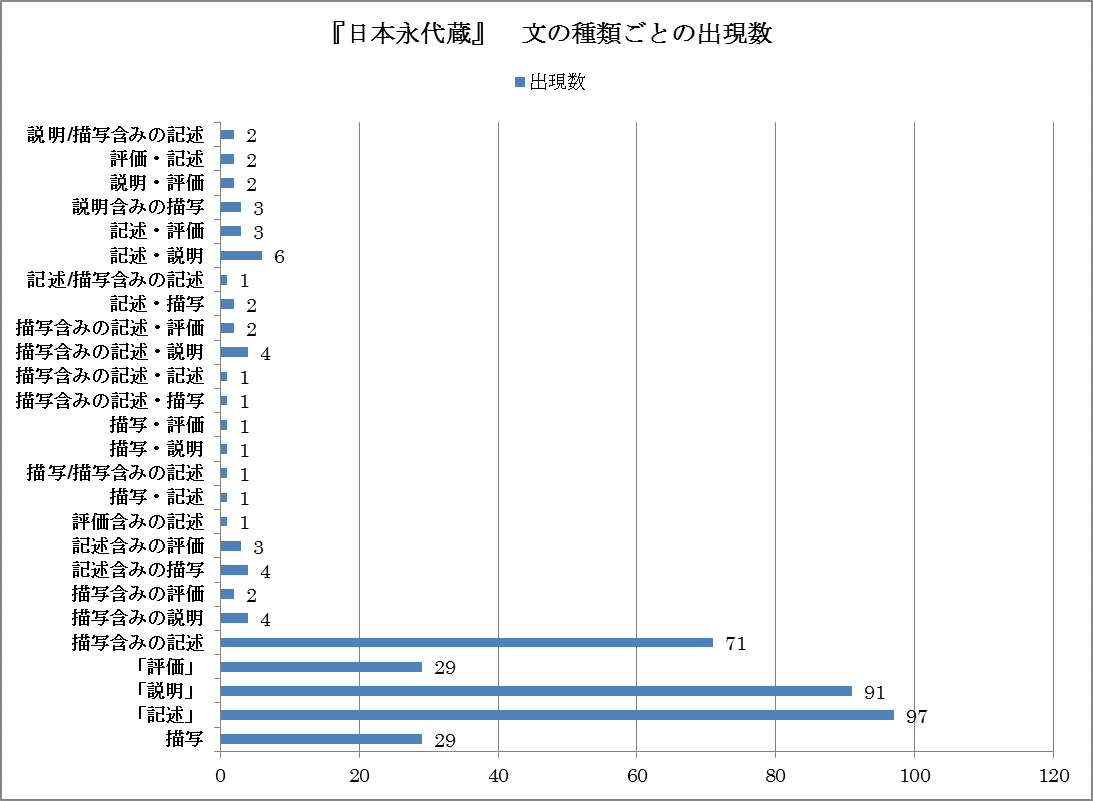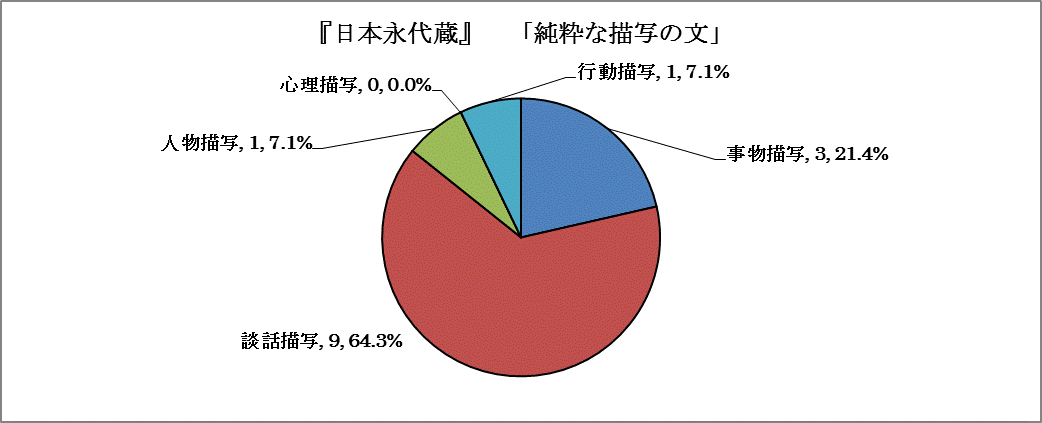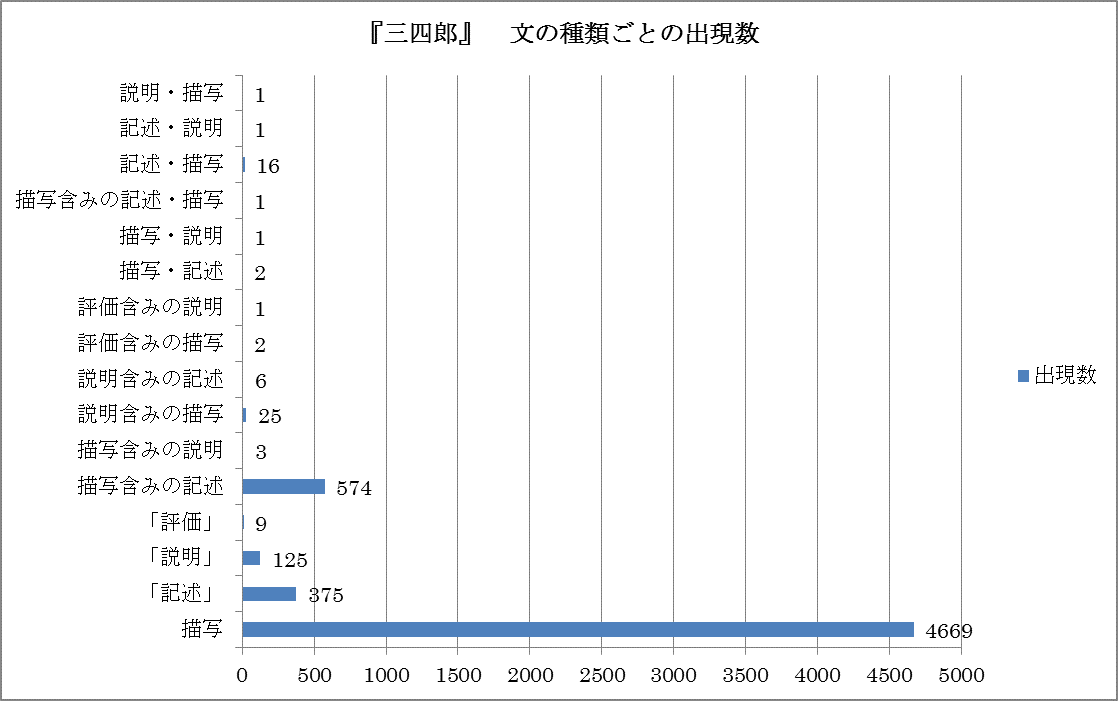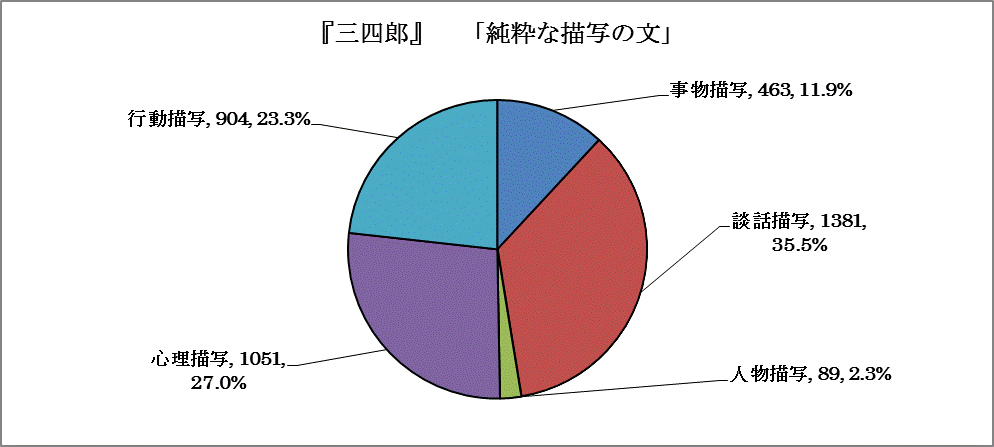本研究は、日本の小説・物語作品において用いられる事物描写の通時的な変遷を明らかにする。分析対象とする作品については一文ごとに分析し、各時代の事物描写の表現特性を示す。
小説・物語は虚構を語る叙述行為であるが、よほど難解な叙述でない限り、読者は作品世界を実感のある存在として享受し、楽しむのが普通である。作品世界に何らかの実感を持たせる表現は、虚構に現実性を与える表現だと言い換えることができる。ところで、我々が現実を認識する際の手立てとして五感が大きな役割を果たしている。であるならば、虚構に現実性を付与する手段として五感に訴えかける表現が用いられるのは当然ともいえる。そのような、表現手法こそが場所や出来事、人物をありありと描き出す描写表現である。ただし、描写表現の文章そのものが五感に訴えかけるわけではない。描写表現の文そのものはあくまでも文字列として視覚的に処理されるにすぎない。描写表現が感覚へ訴えるとは、描写表現によって読者の脳内にその感覚が喚起されることを意味している。描写表現の持つ喚起力が、虚構の作品世界に知覚・感覚性を付与することで、読者は実感を持って作品世界に接することができる。描写表現の持つ喚起力といっても、その喚起の仕方は表現手法によって様々である。それらの手法は、作品の成立した時代や想定される読者、描写をする対象に左右され、各々の要素自体も密接に関連し合っている。
今回の研究では描写対象を事物に限定した事物描写を中心に取り扱う。事物とは登場人物以外のモノやコトを指し、これらは作中人物にとって知覚できる存在である。本研究では登場人物以外の要素がどのようにして作品世界を構築しているのかに注目することになる。また、事物描写に限った場合、作家・作品ごとの研究は充実しているものの、それらを繋げた通時的研究に関してはほとんど見当たらない。本研究は日本文学史における事物描写表現の通時的変遷についての枠組みを提供する。
本研究では、中古・近世・近代と大きな流れの中における事物描写の変遷に焦点を当てて、分析、考察、比較を行なっていく。事物を対象とした表現に注目するということは、人間がどのように事物を認識し、それを表現として具体化させてきたのか、その変化を探ることになる。
研究方法としては、上述した3つの時代から各1作品を選出し、事物描写に関する分析項目を立て、一文ごとに分析する。分析項目は、特に《文の機能》を重視して設定し、描写機能に限定せずに他の機能との関係に注目して分析する。分析結果を基に、いくつかの観点に沿って各作品の表現類型を探し出し、それらを通時的に比較考察していく。そもそも同時代の作品であっても、その表現には差異がある。その差異は通時的にはさらに大きくなると予想できる。日本文学史の大きな流れの中で小説・物語作品の事物描写がどのように変遷してきたのか、その表現に沿った研究を行なうことで、描写表現の通時的研究に多少なりとも寄与することを目指す。
本研究では文学的文章に含まれる小説と物語を研究対象としている。両者に共通するのは、ある程度の長さを持った散文の文学作品であり、そこでは何らかの登場人物や出来事について描かれる。また、作品世界は虚構として、設定された語り手が語ることで出来事は展開していく。登場人物が活躍する舞台が設定されるのが一般的であり、出来事の展開に従って場面も移り変わることもある。重要なのは、両者ともに事物描写表現が用いられているという点である。以上から、両者を類似の文学形式として扱い、本研究ではその差異について問うことはしない。
本研究の研究対象とする小説・物語作品として、中古から『源氏物語』、近世から『日本永代蔵』、近代から『三四郎』の計三作品を選出した。各作品の分析に使用したテクストや分析範囲・作品概要・選出事由は以下に示す。これ以降、分析対象作品の本文引用を行なう場合は全て使用テクストからの引用である。
共通する選出事由は、まず各時代を代表させる物語作品であるので、一定以上の知名度を持った作品が相応しいと考えた。また、通時的な比較・考察を行う際には、各作品における事物描写の広がりを捉えるところから始める。その後、作品ごとの関連性を通時的に比較・考察していく。描写表現の広がりを捉えるためには多数の描写表現が出現することが望ましい。そこで事前の分析から、事物描写が出現しやすいのは舞台説明をする必要がある作品だと判断し、登場人物または読者にとって未知の場所が出てくる作品が相応しいと考えた。視点設定について、中古・近世の作品が基本的に三人称全知視点をとるので、近代の作品も類似した視点設定の作品を選出した。
本研究では一作品の分析を詳細に行なうことを目指しているので、対象作品数を3作品に限定した。ただし、一作者・一作品ごとに描写表現は異なるので、一時代に一作品という選出方法では作品資料が不十分である。また、上代・中世・現代の作品も取り上げていない。本研究で扱えない作品の分析は今後の課題となる。
『源氏物語』
<分析に使用したテクスト>
紫式部(著)、阿部秋生・秋山虔・今井源衛・鈴木日出男(訳・校注)『源氏物語① 新編日本古典文学全集20』小学館、1994年3月、pp.15-50、pp.197-262。
紫式部(著)、阿部秋生・秋山虔・今井源衛・鈴木日出男(訳・校注)『源氏物語② 新編日本古典文学全集21』小学館、1995年1月、pp.221-276。
<分析範囲>
「桐壺」「若紫」「明石」の三巻。
<概要>
著者は紫式部(970年?-1014年?)と目される。成立は長保3年(1001年)から寛弘2年(1005年)までの時期と見られるが正確な時期は不明。一般には全五十四巻、三部構成と見なされているが、これにも諸説ある。1「歌物語」と「作り物語」の流れを融合させ、風情と写実性に富んだ、日本文学史を代表する作り物語作品であり、後世に与えた影響の大きさは計り知れない。
光源氏を中心人物として彼の生涯を描くことを軸に物語が展開していく第一部、第二部、次代の薫らに主軸がおかれる第三部という構成になっている。
<選出事由>
『源氏物語』は中古の物語作品の代表として選出した。研究対象として、「桐壺」「若紫」「明石」の3巻を分析対象とした。「桐壺」は『源氏物語』全体の最初に置かれた巻として、作品世界を立ち上げるときの事物描写に注目するため選出した。「若紫」は源氏の垣間見で視点人物が定まるために事物描写が出現し易いと予想して選出した。「明石」は主人公の源氏が未知の土地に赴くために、新規の舞台を描写する事物描写が出現し易いと予想して選出した。
また、同時代の他作品に与えた影響も大きく、読者意識を探る上でも格好の資料となると考えた。
『日本永代蔵』
<分析に使用したテクスト>
井原西鶴(著)、谷脇理史・神保五彌・暉峻康(訳・校注)『井原西鶴集③ 新編日本古典 文学全集68』小学館、1996年12月、pp.17-205。
<分析範囲>
巻一から巻三までの十五章。
(収録章名)一巻の一「初午は乗って来る仕合せ」・一巻の二「二代目に破る扇の風」・一巻の三「浪風静かに神通丸」・一巻の四「昔は掛算今は当座銀」・一巻の五「世は欲の入札に仕合せ」。
二巻の一「世界の借屋大将」・二巻の二「怪我の冬神馬」・二巻の三「才覚を笠に着る大黒」・二巻の四「天狗は家名風車」・二巻の五「舟人馬方鐙屋の庭」。
三巻の一「煎じやう常とはかはる問薬」・三巻の二「国に移して風呂釜の大臣」・三巻の三「世は抜取りの観音の眼」・三巻の四「高野山借銭塚の施主」・三巻の五「紙子身代の破れ畤」。
<概要>
著者は井原西鶴(1642年-1693年)。副題「大福新長者教」。この副題は、寛永4年(1627年)に刊行され、経済的成功の教訓書としてベストセラーになった『長者教』を踏まえている。発表は貞享5年(1688年)正月。執筆時期には諸説あるが、刊行時期の一年半前から書き始められたと考えられる。全6巻で、1巻につき5章の全30章構成。全6冊が一度に刊行された。『永代蔵』は西鶴の中期?晩年の作品であり、経済小説、モデル小説の先駆けとなった2。町人の生活を生き生きと描出した点や経営手法に関する西鶴の独創的で的確な視点、読者の共感を得易い常識的な感性などによって西鶴の作品の中では特に好評であったようである3。
町人、中でも商人を題材とした短編集といえるが、教訓的色彩が濃く、中には物語の体裁をとっていない章段もある。基本は語り手の視点で語られるが、各章の主人公といえる人物の視点に寄り添うこともある。
<選出事由>
『日本永代蔵』は近世の小説作品の代表として選出した。研究対象として、第1巻から第3巻までの全15章を分析対象とする。短編集であること、日本各地を舞台とすること(特に主要読者層に馴染みのない土地を舞台にする場合)から、舞台描写が多くなると予想した。さらに、商人を題材にした作品であることから、商売で用いる道具(事物)に関しての描写も多いと予想した。
また、西鶴の作品の中でも好評であったことから、同時代の読者意識を探る上でも格好の資料となると考えた。
『三四郎』
<分析に使用したテクスト>
夏目漱石『三四郎』角川書店、1951年10月。
<分析範囲>
全文。
<概要>
著者は夏目漱石(1867年-1916年)。発表は明治41(1908年)年9月1日から12月29日までの期間、朝日新聞紙上において、全170回にわたって掲載された。この時期は漱石が職業作家として活動を始めた時期にあたる。『三四郎』は、『それから』『門』と合わせて漱石の前期三部作に位置づけられる。
熊本の高校を卒業後に上京した三四郎という青年を主人公に据える。様々な人物、学問や新たな女性像との出会いを通して、心動く三四郎を描く。三四郎以外の登場人物の視点から描かれることもあるが、基本的に三四郎に寄り添った三人称限定視点で語られる。
<選出事由>
『三四郎』は近代の小説作品の代表として選出した。漱石の作品として『三四郎』の他に『我が輩は猫である』と『倫敦塔』の分析も試みた。しかし、二作品とも視点設定が一人称となっていることから研究対象として相応しくないと判断した。さらに『我が輩は猫である』は、大半の舞台となる「書斎」が描写されない。舞台の描写が少ないことも、研究対象として相応しくないと判断した理由である。
『三四郎』は主な視点人物の三四郎が新規のモノを見る存在として設定されていることが選出事由である。三四郎は人生で初めて上京する青年として設定されており、その彼が目にするモノの多くは新鮮な感動を持って捉えられると推測できる。新鮮な感動は事物そのものへの関心を呼び起こし、必然的に事物描写も豊富に出てくると予想した。
※以降、研究対象テクスト本文から引用する場合は以下のように示す。
『源氏物語』 『源氏物語』「(巻名)」
『日本永代蔵』 『永代蔵』(巻数)「(章題)」
『三四郎』 『三四郎』章数
以上が、研究対象とする各作品の概要と選出事由である。研究対象とする範囲について数量的な釣り合いがとれていない理由について述べる。現代の描写論に則って分析を行うため、最も現代に近い作品である『三四郎』を実際に分析することで、分析の際に用いる分類項目を定めていった。その際には、可能な限り広い範囲を扱うことを目指したので全文を分析対象としていた。『源氏物語』『日本永代蔵』も全巻を分析対象とすることを目指したが、今回は作業的に困難だと判断して断念した。『源氏物語』『日本永代蔵』の分析が行えなかった範囲については今後の課題としたい。ただし、『三四郎』『日本永代蔵』の場合と比較して、『源氏物語』は長期に渡って執筆されており、執筆者、執筆順序が明らかでない点で研究範囲を慎重に設定する必要がある。
次節では、研究を進めていくための方法について、事物描写の定義と分析項目の設定を中心に論じていく。
本研究では、対象作品の叙述について分類分析を行う。その結果からそれぞれの作品の表現特性を明らかにし、さらに時代ごとの比較考察も行う。分析においては対象テクストの叙述を一文ごとに扱う。これにより、一文ごとの種類・機能について個別的具体的な分析を行える。また、テクスト内での位置や周辺の他の文との関係などテクスト全体における配列や分量に関しても考察する。ただし、分析対象作品が成立した時代背景によって「一文」のとらえ方が異なること、対象とした作品の総文数が異なることから、文数による数量比較の結果は括弧つきで捉える必要がある。
ここで本研究における一文の設定をしておく。文は句点、疑問符、感嘆符、改行を区切りとした文節の集まりのこととし、基本的に、読点・括弧などは区切れとして扱わない。ただし下の例文のように、談話描写を示す鍵括弧のみの文の場合でも、改行など次の文と区切られていることが明らかな場合にはそれぞれを一文とみなす。
7 下線部「板木で押したるやうなこの家の若えびす」について。この叙述は具体的な場面において発言されたと示されているわけではなく談話描写と確定することはできない。ここでは、原文で「と祝ひける」と談話を窺わせている点に考慮し、瞬間を切り出した談話描写と判断している。原文には鍵括弧が用いられていないため、鍵括弧が談話描写を示すという判断自体が成り立たない。これは現代の文章論とかみ合わない部分の一例だといえる。談話描写か否かの判断は基本的には研究対象テクストに依っている。
→ページのトップへ戻る
本章では、事物描写に関する先行研究を概観していく。
実際に分析結果を考察する前に、事物描写に関する先行研究を概観し、考察の観点・仮説を立てる。第1節では小説・物語作品全般、第2節では研究対象とする各作品で事物描写がどのように用いられているかについて論じていく。
描写に関する先行研究には膨大な蓄積があるが、事物描写に限定し、またそれを通時的に取り扱った先行研究はほぼ見当たらなかった。しかし、先行研究の中には事物に関係した描写表現や近世から近代においての描写を通時的に取り扱ったものが見られた。以下では、特にそのような先行研究を中心に取り上げる。
→ページのトップへ戻る
前章で事物描写という表現そのものが持つ特徴についての考察を重ねてきた。本節では小説・物語作品という枠組みの中で事物描写がどのような役割を担っているのかに注目する。
描写の通時的研究
描写という表現技法が小説・物語で果たす役割とはどのようなものか。本稿での事物描写の定義から、描写を「知覚可能な存在を具体的・直接的に描いた叙述表現」と定義する。言い換えれば、「感覚(イメージ)喚起の機能を持った叙述」ということになる。しかし、そもそも日本の描写表現についての通時的研究は可能なのか。この問いについて、本論は当然ながら描写の通時的研究は可能であるという立場である。これについて以下で述べていく。
日本で「描写」という言葉が文学分野において、上で定義したような表現として着目され始めたのは明治期以降と考えられる。これは坪内逍遥の『小説神髄』(1885年-1886年)で描写について触れられることや自然主義における描写論の代表格である田山花袋の存在8から推量されるものである。では、この時期以前の文学作品には描写表現が出現しないかといえば、当然そんなことはない。なぜならば、前章で繰り返してきたように描写は形式ではなく機能だからである。つまり、知覚情報を想起させるような、もしくはそれを狙ったと解される叙述表現が存在していたということである。「描写」という言葉によって意識される以前から、既にその機能を持った叙述があることには何の矛盾もない。機能が先んじて、それが後々名づけられ認識されるようになるのは珍しいことではない。
では、なぜそのような機能が、機能として認識される以前から物語において用いられてきたのか。これは物語が現実の模倣を基礎に始まっていることを考えれば容易に納得できることである。物語に描かれる出来事は、それが虚構であったとしても、私たちの現実認識の枠から外れることはできない。なぜなら、私たちは認識しえないモノを言葉にすることができないからである。たとえ、認識できたとしても言葉にできなければ、その認識は物語という言語芸術には反映されない。そのため、物語は必然的に現実の模倣、現実認識の模倣しかできない。
清水好子氏は「物語の文体」9において物語が文体というものを形成していく過程について論じている。その中で、清水氏は『竹取物語』の文章を例にあげ、以下のように述べている。
事実を文章の上で再現した、いわば文字づら文章づらといったものにおいて、現実の連続をどこで可能にするかが、竹取の場合問題であったのだと思われる。述べられようとする事柄が一連のものであること――事実とはそういうものである――を確かめる必要があったのである。竹取物語はまったくそれを文章の上でやっている。(中略)「見て」「聞きて」という人間同士の素朴な連絡の方法をいつの場合も落とさず文章の上に書き止めたり、または同じ語の繰り返し、重ね合せによって文章にすることのために切れる事柄の切れ目を一面に塗りつぶしている。文が切れることが何を意味しているかに考え到っていない。かかる状態は、いつも述語を持つ整正の姿をくずさぬ会話とともに、文章を操るにあたっての改まった態度、習熟しない態度を思わせる。
(清水好子「物語の文体」『源氏物語の文体と方法』
東京大学出版会、1980年6月、pp.6-7。)
ここで、清水氏は『竹取物語』の文章が、事実を整理せずに書き写していることを指摘している。清水氏はこのような文章を模写的な言語と呼んでいる。物語初期にはこのような露骨な現実模倣が行なわれていた。
物語が現実の模倣であるならば、その中に感覚の模倣を目指した文があってもおかしくはない。物語作者が感覚模倣を目指した結果、物語には初期のころから描写の機能、感覚喚起の機能をもった叙述があったのである。描写表現叙述とは言語による現実の感覚模倣と言い換えることができる。あるいは、現実の感覚模倣を目的とした叙述が描写表現だということもできる。現実の感覚模倣は、歴史記述のように出来事を時系列的に並べる以上により詳細で具体的な現実模倣である。これは描写機能が具体的・直接的な叙述であることから当然のことであるといえる。歴史記述以上の現実再現が、物語の書き手と読み手のどちらの要求によって出現したのかは定かではないが、現実をより正確に再現しようとする発想があることは、現代の生活経験に照らし合わせても特に不思議なことではない。
ここまでをまとめると、描写は機能であり、現実模倣を基礎とした物語作品においては描写機能を持った叙述表現が用いられた。そのため、描写表現の通時的研究は可能である、ということになる。描写表現は「描写」という言葉で意識化されたことで、現実模倣の方法として改めて検討された。ある種の叙述が「描写」という言葉で統一され意識されるようになったことで、現実を単に言葉による模写をしていたときよりも、現実を模写するという行為・方法の考察・分析が重ねられた。その結果が平面描写や写生という表現技法として表れている。
事物描写の役割
ここからは事物描写機能を持った叙述が、小説・物語作品の世界を作り上げる際にどのような役割を担うのか考察していく。ここでの役割は主に事物描写に限定し、人物の行動や談話の描写が担う役割に関してはおいておく。
元来、描写は物語・小説の筋を進行する類の叙述ではなく、むしろその進行をいったん停止させて、作品世界の詳細な説明をする叙述だと考えられていた。筋を進行するのは物語叙述(「記述」)の役目であり、筋が進行する合間に細部を彩ることが描写の役割であった。このような描写表現の用い方は、特に近代以前の小説・物語作品において顕著である10。このような時代的傾向から、この時期の事物描写は作品世界の背景や事物について説明するか、外形的な特色づけといった装飾の役割を担っていたと想定できる。この段階の描写の役割を「背景・事物」「装飾」と呼称し、以下で説明する。
「背景・事物」は《舞台》となる場所、描写対象となる事物の有様を描き出す役割を指している。これは描写対象の知覚・感覚情報の説明と言い換えることもできるので、「背景・事物説明」の方が用語としては適切かもしれないが、本稿ではすでに分析項目として(説明)を設定しているので、それと区別するために「背景・事物」という言葉を用いている。ここでの「背景」は《舞台》とほぼ同義である。「事物」は「背景」には属さないモノやコトを指す。事物描写によっては、《舞台》・事物の視覚情報以外にも、音や臭いなど他の知覚情報も提示される。例えば、「図書館は静かだ」という描写は「背景」の役割を担い、聴覚を喚起する機能をもつ。
また、「背景・事物」の役割を持った描写表現があるときには、知覚・感覚情報以外の説明が付随することも珍しくない。例えば、《舞台》が描写され、それに加えて《舞台》の由来が語られるような場合である。由来はある程度以上の時間を圧縮して語る、つまりは素材の操作・整理がなされているから文の機能としては大抵(記述)になる。
「装飾」は描写対象の説明以上の外形的特色を描き出す役割である。「背景・事物」の説明とは違い、描写によって対象に本質以外の要素を付加する意図がある。例えば、「装飾」によって対象の美しさを付加する役割が見られる。「装飾」はその字義的意味も含めて、本来的には余剰となる部分を付加しているのである。飾らない素材そのものの美を示すのであれば、むしろ「装飾」という役割を持った描写は相応しくない。ところで、「背景・事物」という役割からは敢えて「人物」という描写対象を除外しているが、これは本稿で定義した事物が人間を含まないからである。
「背景・事物」と「装飾」という二つの役割は、どちらも主に対象の外形的な知覚情報を提示しようとしている点で共通している。どちらも描写の根本的な目的である、現実の感覚模倣に沿った役割である。そのため、一つの描写表現が「背景・事物」と「装飾」という二つの役割を同時に担うことがある。というよりも、「装飾」の役割を担った事物描写は、「背景・事物」の役割も兼ねるという方が正確である。なぜなら、「装飾」が余剰の部分を描くためには、そもそも「装飾」の対象となるモノが必要だからである。対象となるモノを示す描写は「背景・事物」の役割とも解することができる。つまり、二つの役割は必ず別箇にあるというわけではない。特に「修飾」の役割を担った描写は、同時に「背景・事物」の役割も担っていると考えられる。
「背景・事物」と「装飾」の最大の違いは、「背景・事物」と比較して「装飾」は読み飛ばしたとしても物語の展開を理解する上では重要でないことが多いという点である。どのような場所で出来事が展開しているかは出来事を理解する上でしばしば重要である。小柴垣がなければ源氏は若紫を垣間見ることができず、汽車でなければ三四郎が女と相席することはなかったかもしれない。対して、すでに述べたように「装飾」はそもそも余剰部分なのである。もちろん「装飾」された対象の美しさが、作中人物の行動原理となり、展開を突き動かしていく場合も考えられる。しかし、「装飾」が必要以上の知覚・感覚情報を提示していることは事実であり、物語の展開を妨げることすらあり得る。
ただし、《舞台》を設定する際に「背景・事物」の役割を担った描写が必須というわけではない。既に描写された場所であれば再度描写する必要はない場合もあるだろうし、また読者が想像しやすいと考えられる場所も描写されないことが多々ある。例えば、『源氏物語』ならば宮中の様子が毎回描かれることはないし、『三四郎』でも汽車の内部が詳しく描かれるわけではない。
また、「背景・事物」と「装飾」の違いはあくまでも比較の問題である。そのため、「背景・事物」の役割を担った事物描写が必ず物語展開に重要な意味を持つわけではない。
「装飾」の役割を担った描写として江戸時代の読み物語に特徴的な描写が挙げられる。磯貝英夫氏による説明を以下に引用する。
人物が姿を現すと、ただちに、その服装、持物、年齢、容貌などを、こまかく紹介するのである。そのやり方は、警察の手配書そっくりである。むかしの作家は、まことに几帳面で、つねにこういうふうにきちんと紹介した上で、その人物を活躍させたのである。
(磯貝英夫「描写のいろいろ」『現代作文講座3 作文の条件』
明治書院、1981年9月、p.138。)
これほどに克明な描写をするためには、当然物語の展開はいったん停止させ、人物をじっくり観察する必要がある。磯貝氏はこの種の描写が持つ問題点を次のように指摘している。
手配書的集中描写、細部描写が徹底すればするほど鮮明な像が現れるにちがいないという一般的な予期とはまったく相反して、網羅的細叙はかえって結像をさまたげやすいことに人々が気づいたとき、排除されたと言ってよい。像は、その特徴的な一部――つまり、その本性と深く結びついた具象部分――の提示、その持続・積み重ねによって、おのずから浮かび上がってくるもので、すべてを羅列する描写は、かえって像を拡散させてしまうのである。
(同上、p.139。)
引用からは磯貝氏の描写形式についての見解(「本性と深く結びついた具象部分の提示」が効果的な描写形式である)が読みとれる。描写対象の提示の仕方が描写機能の効果に影響を及ぼすという点で、描写表現の効果を測る上で重要な指摘である。ただし、ここで「網羅的細叙」が問題になるのは、描写表現の機能よりも形式が優先された結果であることを忘れてはいけない。その形式が機能を果たすために有効であれば、「網羅的細叙」であっても十分に読者の脳内に具体的な像を結ぶ役割を果たすことがあるかもしれない。当然、磯貝氏が批判しているのは、形式が形骸化した江戸時代の一部の作品に対してである。このような描写叙述は対象を装飾するという以上に、特定の形式を用いることによって文そのものを飾りたてる、文飾の役割も担っていたと考えられる。
過度の網羅的描写が形式化していた近世以前の小説や物語(特に戯作調の作品)とは対照的に、近代以降の小説では視点人物の存在が大きくなり、描写の意味づけが変化してくる。再び、磯貝氏の説明を引用する。
これまでの小説であれば、作品の舞台を紹介するとなると、主人公などはさておいて、作中であれば話も中断させて、作者が普遍視点からその風物を描写するのが、普通であった。それにくらべると、この描写は、主人公と不可分につながっていることによって、より有機的であり、また、一つの視点からえがかれることにおいて、より現実的だということができるだろう。
(同上、p.147。)
近代以降の描写は、対象の認識と視点人物(引用においては主人公)が結びついていることを、作者が意識しているのが特徴である。視点人物の存在に意識的であるということは、認識主体が「見ている」ということが強調される。そうなると、読者は「見られる」対象そのものだけではなく、対象を「見ている」主体についても考えざるを得なくなる。ここにおいて描写は単に「装飾」の役割を果たすだけではなく、描写が「見る」人物を規定する役割をもつ。描写はその対象とともに、それを「見る」人物も描き出す役割を担うといえる。ここで描写の役割として新たに「視点人物造型」が想定できる。11
また、磯貝氏は「一つの視点」(一人の視点人物)に限定することが作品世界の現実性を増すとも述べている。これは当然のことで、人が何かを見る際には一つの視点からしか捉えられない。ある物の正面と後姿を同時に捉えることは、日常の生活ではまずありえないことである。ただし、これは瞬時の描写の最中に視点移動がない方がより現実的だというだけである。その移動に整合性があれば視点変化をしても問題はない。例えば、視点人物が対象の周囲を回りながら、描写する場合などはこれに該当するだろう。もしくは、視点人物が変更された場合なども該当するだろう。
「視点人物造型」は既に挙げた「背景・事物」と「装飾」の効果とは全く質が異なる。「視点人物造型」は事物描写の副次的な役割なのである。「視点人物造型」を副次的な役割と判断した理由は、描写の根本的な目的である現実の感覚模倣に沿っていないからである。基本的に描写は「見られる」対象を示す叙述表現である。「視点人物造型」を担った事物描写においても、その基本姿勢が崩れているわけではない。対象を描くことは前提とした上で、「見る」存在やその「見方」に注目しているのである。このような発想の転換は、先にも書いた描写と視点人物の関わりに意識的になったことに起因していると考えられる。「視点人物造型」の役割を担った事物描写が副次的な役割であることから、必ず「背景・事物」の役割も担うと考えられる。
ただし、視点人物が設定されたからといって、当該事物描写が必ず的確な「視点人物造型」の役割を担うわけではない。序章での描写についての考察や磯貝氏の指摘にもあるように、視点人物を決定することは描写性を高めるための一つの方法でもある。つまり、視点人物を造型するために視座を決定したわけではなく、より現実的な描写を狙った事物描写ということもあり得る。視点人物が設定された事物描写は確かに「視点人物造型」の役割を担うが、その事物描写が視点人物を造型しようという狙いで書かれていなければ、人物造型としての効果は低いものになる。
ここから見えてくるのは、例え効果が低くとも、事物描写の視点人物を決定すると、その事物描写は必ず「視点人物造型」の役割を担う点である。これは、「背景・事物」や「装飾」の役割を担っていながらも物語展開には余剰であると判断される事物描写を掬い上げることに繋がる。なぜならば、物語の展開には無関係と思われるような事物描写についても、視点人物が決定していれば「そのような無関係なものにも関心のある視点人物」というような解釈が可能になるからである。もちろん一概にいえることではないが、それでも「視点人物造型」という役割を想定することは余剰と思えるような描写に重要な意味を見出すための手掛かりになる。
ところで、本稿の分析項目で設定した(人物描写)と「視点人物造型」は全く異なるものである。確かに、どちらも人物造型という働きを持っている点は同様である。しかし、(人物描写)が人物を描写対象として「見られる人物」の造型をするのに対して、「視点人物造型」は描写対象を「見る人物」の造型をするのである。つまり、視点人物が決定している(人物描写)の場合には、対象として「見られる人物」と対象を「見る人物」という二者の人物造型がなされる場合もある。
描写の役割としてすでに挙げた3種類の他にもう一種類、「伏線」が想定できる。後の物語の展開に深く関係してくるようなモノやコトを明示的・暗示的に先に描写しておくという場合がこれに当たる。
これは単純に《舞台》やモノを描くための「背景・事物」の役割とは異なる。「背景」の場合、その役割は場面ごとに《舞台》の有様・事物の有様を描写することにあるので、基本的にはその場面においてしか役割を果たさない(同じ場所が《舞台》になる場合は別である)。つまり、「背景」の場合は描写された対象はその場面で読者に強く意識される必要がある。あるいは、後の展開においても描写された時点と同様の意味合いを持つ事物描写と言い換えられる。しかし、「伏線」の場合は必ずしも描写された場面において、描写対象が意識される必要はない。あるいは、後の展開の中で描写された時点とは異なる意味合いを持つ事物描写と言い換えられる。「伏線」については、推理小説を例にすると最も分かりやすい。推理小説ではしばしば、何気なく描写されていた事物や人物の言動が事件の犯人を示す手掛かりになるという手法が用いられる。これは描写された対象が、後の展開の中で、以前描写された時点とは異なる意味を持ったということである。
「伏線」という言葉から察せられるように、この役割を持った描写は物語のプロットに寄与する。これは事物描写として対象を描き出すこととは異なった役割である。つまり「伏線」も事物描写の役割としては副次的だといえる。そのため、「伏線」の役割を担った事物描写も必ず「背景・事物」の役割を担う。
さて、ここまでの考察から事物描写の役割の中で基礎になるのは「背景・事物」だと推定できる。「装飾」は余剰部分も併せ持つため基礎とはいえない。「視点人物造型」「伏線」は副次的な役割と位置付けたので、これも基礎とはいえない。
以上、描写の役割として「背景」「装飾」を想定し、副次的な役割として「人物造型」「伏線」を想定した。
場面と《舞台》
ここで場面と《舞台》という用語について考えてみる。場面と《舞台》は物語・小説作品においてどちらも重要な、構成単位と構成要素である。そして、どちらの成立にも描写は関連が強い。
物語・小説における場面とは、出来事の具体的な展開が描かれている部分のことである。《舞台》は、前章で「作品内の出来事が展開している場所」という定義をした。まとめると場面は出来事そのものであり、《舞台》は場所である。
場面において出来事を具体的に描くためには、描写表現を用いるのが適当なのは明らかであろう。描写は時間・空間・視座・対象を限定することで、具体性を生み出す表現機能である。「彼が学校に行った」は出来事であるが、一般的には場面化されているとは捉えられないと考えられる。これは時間・空間・視座が限定されていないためである。
また、場面が成立するために重要なのは連続性である。場面は出来事の具体的な展開を描くことだと述べた。出来事はそれがどれほど短くても開始と終了があり、開始から終了までは連続している。つまり、文章によってより具体的に出来事を展開させるにはある程度の文量が必要だといえる。「彼は学校に行った」も一つの出来事であり、場面の開始を予感させるかもしれない。それでも、出来事が具体的に展開しているようには捉えられないので、場面が描かれているとまではいえない。
加えて、後続の文は、連続した出来事を描いていると理解できる文でなければならない。「彼は学校に行った。家を出たところで彼女にあった。」という文章ならば、二つの出来事の連続性は理解しやすく、場面としても成立する。後続文もこのように連続性が理解しやすい文であれば、場面はより具体的に成立していく。対して、「彼は学校に行った。彼女が会社に着いた」という文章では、二つの出来事の連続性を理解するために相応の想像力が必要になる。この二つの出来事からは場面が成り立っているとはいえない。場面化のためには出来事の具体化と連続性が重要な条件になる。
ただし、いくら連続性が重要とはいっても出来事を全く断絶なく書くことは不可能であるし、そのような文章が却って描写性を妨げる場合もあることは既に述べた。「彼は学校に行った。家を出たところで彼女にあった。」という文章も、その行間には「彼は靴を履いた」や「彼はドアを開けた」という出来事が想定できる。つまり、書かれた出来事と出来事の合間には別の出来事があることを示している。さらに、この合間の出来事は「彼がドアを開けるために右手を上げた」というように際限なく細分化できる。出来事をいかに厳密に描き出そうとしても、そこには必ず空所が存在する。もちろん、その空所を少しでも埋めるために出来事を細密に書くことも可能である。しかし、例文程度の長さならまだしも、長編物語で毎回このような細密な描写が繰り返されると、物語は一向に進展しない。しかも、私たちは「彼は学校に行った。家を出たところで彼女にあった。」という二文の合間の出来事が描かれていないことに問題を感じたりしない。出来事の省略が読者の想像で十分に補足できる範囲であれば、物語展開の理解において特に問題にならないことが分かる。つまり、場面を成立させるための出来事の連続性とは、読者の納得できる範囲での省略を許すものであるし、またある程度の省略がなければ読者の想像を妨げることすらある。一般的には、後続文との連続性が理解できる文章が「読者の納得できる範囲」に当てはまる文章である。そして、「読者の納得できる範囲」とは、それぞれの時代や社会階層ごとの共通観念の上に成り立っている。
ところで、実際の小説・物語作品においては、必ずしも出来事の開始から終了までが全て示されるわけではない。そもそも、出来事の開始や終了が明確に定まっている場合が稀であるし、開始時点・終了時点の認識は、認識する主体によってまちまちである。また、書き手が出来事全体の一部だけを切り出して提示するという方法を用いることもある。反対に、場面の開始と終了は必ずある。これは小説・物語作品に限りがある以上は当然のことである。時系列に沿って出来事が提示されていくような単純な構成の作品であれば、一つの場面が描かれ、それに続く場面を描くか、場面と場面の間の出来事が「記述」として記されるという方法がとられる。極端な場合、一つの作品が一場面だけを描く場合もある。その場合は作品の開始と終了がそのまま場面の開始時点・終了時点と重なることになる。
ここまで場面について考察してきた。場面が限定を必要とすることから、逆説的に場面化している部分の対象表現は基本的には描写と判断できる。つまり、場面が成立しているか否かは描写表現を見出す一つの基準になる。
《舞台》の設定は出来事が展開している場所が判明すれば成立する。このときの出来事は場面化している必要はない。例えば、「東京の下宿に住んでいる」という文は場面としては成立していないが《舞台》が東京であることは分かる。《舞台》が具体的に描かれる場合は事物描写が用いられる。場所は人物以外の知覚可能な存在であり、本稿の事物の定義を満たしている。
ここで場面と《舞台》を同時に取り上げたのは、《舞台》を具体的に設定することが場面化の一方法になるからである。場面を具体的に描くためには、場所の限定が一つの条件となることは既に述べた。つまり、具体的な《舞台》設定をすることは場面を立ち上げる有効な手段といえる。本研究の対象作品においても《舞台》の設定、言い換えれば場所についての事物描写が場面化に寄与していることが多いと予想した。場面化の際に使われる方法が考察の観点として挙げられる。反対に、《舞台》が設定されずに場面化なされる場合でも必ず《舞台》は存在している。このような場合の《舞台》がどのように限定されているかについて、《舞台判断文》から見出す。
事物描写の効果
次に、事物描写の効果について考察する。描写表現について、「描写性が高い」や「描写の成功」といった表現がなされることがあるが、そもそも描写の効果とはなんだろうか。描写の効果については二つの場合が想定できる。描写表現そのものの効果と一つの表現方法としての効果である。
描写表現そのものの効果とは、描写表現の「感覚(イメージ)喚起の機能」によって引き起こされた読み手の心象感覚である。この効果性については、「描写性の高さ」・「喚起力の強さ」といった言葉で表現される。一般的には、より具体的な感覚を喚起する叙述の方を描写性が高いといわれる。描写性が高い叙述は、読み手に具体的な感覚を思い起こさせる強い喚起力を持っていると判断される。描写性が変化する条件、特に描写性が高くなるための条件については前章に示した。ここでは、具体性を高めるためには限定性を強める必要があると要約しておく。
表現方法としての効果とは、小説や物語の一方法として作品の中に描写があることによって生じる結果である。表現方法としての描写について、どのような叙述が効果的であるかは一概にはいえない。なぜならば、方法は目的と合致してはじめて価値を持つからである。ここでの描写の効果は作品目的に対しての妥当性と言い換えることもできる。この妥当性は作品の目的に応じて変化するので、描写性の高い表現が必ずしも求められるというわけでもない。描写の妥当性を測るためには、必ず具体的な作品を想定しなければならない。また、描写の妥当性については、描写表現叙述のある部分がどのような働きを持っているかという、作品の部分についても同じことが言える。これは描写の妥当性が描写の役割とも関係していることを示している。
本稿では、描写そのもの効果を「描写性」、表現方法としての効果を「描写妥当性」と呼称して区別しておく。
描写性について、前章では描写を形式的に定義するために考察した。ここでは、描写の役割で挙げた網羅的・手配書的描写を例に描写性について考える。
過度な網羅的描写が分かりづらいことは既に述べた。つまり、網羅的描写は描写性が低いといえる。確かに網羅的描写は像を結びづらいということは、自らの読書体験や生活経験から理解できることでもある。過度な網羅的描写の分かりづらさの原因として、言語の表示の仕方と人間の認識の仕方が異なる点が挙げられる。文章が対象を直線的・線条的にしか表し得ないのに対して、人間の対象認識はある程度のまとまりを一度に捉える。一つ一つの要素を段階的に追加していくようにして像を結んでいくというのは、我々の普段の認識方法と異なる。それでも、要素が少なければ処理できないことはないだろうが、過度な網羅的描写はその処理容量を超えるために像が結びづらくなる。
ここから、描写性を高めるためには、磯貝氏が主張したようにより簡潔でありながらも印象の強い言葉、知覚・感覚喚起力の強い言葉を用いることが有効だといえる。では、印象の強い言葉とはどんな言葉だろうか。これについて磯貝氏は「本性と深く結びついた具象部分」を提示することであると述べており、これは対象の本質の提示を求めていると言える。また、事物の印象的に示す言葉といえば、指示対象を喚起するための言葉である事物名称、特に固有物の名称は客観的な描写の手段として有効である。
しかし、いくら印象的な言葉・事物名称を用いようとも、結局は受容する読者ごとに喚起される像には違いが生じる。問題は「印象的」という基準が何によって決定されるのかという点である。ここではその決定要因を書き手と読み手の共通観念に求める。経験や思考を深く共有し、あるモノについての知識理解の度合いが似通っていれば、なにを「印象的」な言葉とするかの判断は容易である。しかし、実際にはこの共通観念も時代や社会階層によって異なる。そのため、最も事物をあらわすはずの事物名称はしばしば知覚・感覚喚起力を失う。
本研究では事物名称のみの場合は事物描写と判断しないことは既に述べた。これは作者による限定の意思が判断できず、描写意図の有無が判定できないからである。また、事物名称全てを事物描写に含めると対象が膨大になり、分析が困難になるというのも理由の一つである。しかし、事物名称が高い描写性を持つ場合があることも事実である。今後は事物名称も加え、各時代や社会階層の共通観念を踏まえた上で、再度その描写性について研究する必要がある。
文字による認識の場合、一度に認識できる情報量の問題とともに情報の配列も問題になる。文字の場合は直線的・線条的にしか情報を提示できないことは既に述べた。情報を一つずつしか提示できない以上、知覚情報の配列が描写性に関係することは予想できる。情報の配列に関しては、現実認識を再現することが困難である。なぜならば、生活経験から考えて、現実では対象の情報を一つずつ順番に認識するようなことはほぼないからである。配列が描写性に与える影響については、更なる考察を要する。
描写妥当性については実際の作品を想定する必要があるので考察が困難である。ここでは、描写の役割と関連したことについてのみ述べる。
一般的には「背景・事物」「装飾」の役割を担う描写の場合は描写性が高いほうが良い。「背景・事物」や「装飾」は、その役割から基本的には知覚・感覚の喚起を目的にしている。つまり、「背景・事物」や「装飾」は、現実の感覚模倣という描写本来の目的と役割が一致しており、描写性が描写妥当性に直結している。対照的に「視点人物造型」や「伏線」の場合は、描写対象を具体的に描き出すことそのものが目的ではない場合もある。あえて描写対象をぼかしたままにしておくことが、後の展開の「伏線」になることもある。
ここでの描写の効果に関する考察は以上にしておく。さらに深めるべき点として、時代ごと階層ごとの共通観念を明らかにすることで、現代ではなくそれが書かれた時代における描写表現の有効性を考えるということが挙げられる。これは描写表現を研究する上で常に問い続けなければならない点である。
描写に関する語句の3タイプ
最後に描写の先行研究について整理し、本研究の位置付けを行なう。
先に記したように事物描写の通時的研究は見当たらないが、描写表現・技法に関連した研究は数多く見受けられた。このような現状は、描写が小説・物語作品において重要な役割を果たす表現技法であることの表れといえる。
「描写」という言葉は、意味範囲が曖昧なことから文学研究において多様な観点から研究されている表現の一つでもある。本研究の参考文献を収集する中でも描写に関する多様な語句があった。今回の参考資料の中から例をあげると、写生12・表現映像13・視覚イメージ・情景描写・自然描写14・容姿描写15などである。これらはそれぞれの語が何に重点を置くかによって名称が異なっている。それぞれの語が重点を置く要素については後述する。
では、今回の研究対象である事物描写はどのような描写表現なのか、他の描写表現に関する語句と比較しながら、説明していく。
まず、上に挙げた研究で用いられる描写に関する語句をその性格ごとに3タイプに区別する。それぞれ、(1)手法に重点を置くもの (2)読者に重点を置くもの(3)対象に重点を置くものの3タイプである。例として挙げた語句をタイプごとに区別して以下に再掲する。ただし、当然ながら重点を置くものを基準にタイプを判断しただけであり、実際はそれぞれ別のタイプの性質も併せ持っている。重要なのは、それぞれの語句を厳密にタイプ分けすることではなく、描写に関連した語句には3つの捉え方があるということである。
(1) 手法に重点を置く――写生
(2) 読者に重点を置く――表現映像・視覚イメージ
(3) 対象に重点を置く――情景描写・自然描写・空間描写
(1)の手法に重点を置くタイプは、作者が当該手法を用いることを重視するタイプである。作品中で描写が果たす役割や、描写を読んだ読者が脳内にどのようなイメージを抱くかではなく、作者の対象への接し方を最も重視しているのである。このタイプの場合、作品とそれを書いた人物の態度は分ち難いものとして捉えられる傾向にある。
(2)の読者に重点を置くタイプは、描写表現が読者に及ぼす影響を重視するタイプである。表現意図や表現形式によって描写を規定するのではなく、読者の脳内にイメージを喚起するという機能に重点を置いたタイプである。このタイプで特徴的なのは、一見描写的ではない表現も描写表現に含まれることがあるという点だろう。神尾暢子氏は「源氏物語の表現映像」16において、「例」という語が同時代の読者にとって共通の映像を脳内に喚起するとして、その働きと特性を論じた。ここでの「例」は、読者の脳内に感覚(イメージ)を喚起する機能を持つという点から描写表現と見做すことが出来る。 (2)のタイプで問われるのは、「作者と読者と素材との力学的均衡関係」17である。これは、作者が想定する読者像とどのように関わり合うかについて、素材の提示の仕方から問うていくことになる。
「表現映像」という用語について補足する。「表現映像」は知覚情報のイメージ喚起力を問題にしている点で、本研究が定義した描写表現と大いに重なることは既に述べた。表現映像という術語の特徴は、その言語が用いられた社会に共通する経験や思考など知覚以外の要素についてより意識的である点である。神尾氏は表現映像を以下のように規定し、その究明意義についても述べている。
ここでいう「表現映像」とは、言語表現によって成立する視覚や聴覚や味覚や嗅覚や触覚といった感覚的映像だけでなく、情感や評価や意志といった観念的な映像をも包括する総合概念である。
(中略)言語表現の現実的な意味とは、素材概念(ナニ)と表現映像(イカニ)との総合であると規定しうる。
そこで、表現映像の究明は、在来の意味研究に欠落しがちであった言語の現実性を追求する営為であるといえる。
(神尾暢子「『王朝国語の表現映像』―自著についての紹介そのほか―」
『表現研究』第36号、表現学会、1982年9月、p.55。太字は本文ママ。)
本研究では、神尾氏が対象としたような「例」という言葉は研究対象の単純化という理由から研究対象に含めていない。しかし、描写表現においてもその描写性を測るためには、「言語の現実的意味」を考慮しなければならないのは明白である。「言語の現実的意味」を探るためには、その描写表現が用いられた時代の書き手と読み手を取り巻く環境や文化を明らかにする必要がある。
(3)の対象に重点を置くタイプは、取りあげる描写対象に重点を置くタイプである。〇〇描写という形式で表され、〇〇の部分に描写対象が入る。このタイプで問われるのは、〇〇の部分に入る描写対象の扱われ方である。それぞれの作者・作品・文種によって、特定の描写対象がどのように具体化されているかが問題になる。
これら3タイプの中で、本研究で扱う事物描写は(3)のタイプに属する。そこで本研究の問いもこのタイプに沿ったものになる。事物という「人間以外の知覚可能な存在」という作品要素が、作品世界を構築する際の働きを検証していくことになる。ただし、前述したように他のタイプの性質が過分に含まれる描写表現も存在する点には注意したい。このタイプ分けは、「虚構の作品世界に事物描写が如何に具体性を付与しているのか」という問いを軸に、分析を進めるという方針を確認するためのものである。
本節では、小説・物語作品全般における事物描写に関する先行研究を概観し、描写表現の果たす役割や効果を想定して考察してきた。ここで想定した役割や効果は仮説段階であり作品分析・考察の結果、変更される可能性もある。
→ページのトップへ戻る
ここからは研究対象とする各作品の先行研究を概観しながら、それぞれの作品で描写がどのように用いられているかについて論じていく。当然ながら各作品に関して数多くの先行研究が存在する。ここではその全てを概観せずに本研究に関わるものに限定して取り上げる。
→ページのトップへ戻る
『源氏物語』の描写に関しては、物語における描写の働き、特に場面の重要性を押さえる。
本項では特に清水好子氏の論に多く依るところがある。清水氏は『源氏物語』が場面設定を取り上げて、その方法について論じている。前節でも述べたように場面化は描写と関連の強い方法であり、清水氏の論には参考にするべき点が多い。
『源氏物語』における場面という方法
『源氏物語』は中古の物語を代表する作品であり、中でも写実性に優れていることは広く認められている。
清水氏は『源氏物語』が虚構の世界を具体的に築く方法を以下のように指摘している。
物語にしろ、小説にしろ、人間への興味から出発するのであるから、源氏物語でも人物が重視されるのは当然である(中略)源氏物語においては、それは、対面し、語り合う人物として描かれる。二人の相対座する中心人物のいる場面、これが、この物語の心象世界を刻みあげてゆく際の原型である。このような場面をいくつか積み重ねることによって(中略)、世界に奥行を持たせようとする。したがって、多くの人間が関係し、主人公の運命を左右するような社会的事件でも、一場面――局部に集中的で、完結性を有し、それゆえ孤立化し断片化しようとする一場面、一情景に寸断されて具象化されていった。
(清水好子「源氏物語の作風」『源氏物語の文体と方法』
東京大学出版会、1980年6月、pp.47-48。))
上記の引用では、中心人物の対話場面によって具体的な世界が築かれることが指摘されている。そして、対話場面の設定については以下のように指摘する。
つねに二人の物語として構成されるために、相手の人物の交替が、話の交替になる。そして、中心になる二人の人物に焦点が合わされたときには、詳しい背景や人物の動きについての描写がある。つまり、源氏物語各巻のいくつかの話は、中心になるような一場面(または数場面)を持っているということができるのである。
(同上、p.49。)
『源氏物語』が対話場面を細密に描き出し、そのような場面を物語展開の中心に据える構成を持っているという指摘である。さらに、『源氏物語』の細密な場描写は特に視覚を喚起するような表現であり、これは当時の物語絵という形式による物語享受形態との関係を指摘している18。
本研究の分析に際しては、中心的場面の設定に注目することが一つの観点として設定できる。また、今回対象とした三巻の内には、場面として成立しているか曖昧なまま、出来事が展開される部分もあった。このような部分の特徴にも注目する。
『源氏物語』では、なぜ対話場面によって具体的に世界を描き出す方法が用いられたのか。これについて、そもそも会話による物語進行が、当時の物語作品の基本であったと清水氏は述べている。以下の引用は、『源氏』以前の『洞物語』や『落窪物語』が会話を基本とした物語進行をしていることを押さえた上での主張である。
物語のもとの形は会話部分が主要構成要素であって、さほど多からぬ、たぶん二人か三人ぐらいの人物が対面してお話しをする、そんな対面の場がいくつか積み重り、繋がって筋が展開してゆくのが、物語の基本型だったのではないか、だからまず会話部分が大切なので、人物がどうしたこうしたというト書き的部分--いわゆる地の文は閑却にされた、そうした部分に注意して、描写やさらに心理描写が入ってくるのは、物語の歴史の上では相当進歩した段階でのことだったのではないかと思うのである。
(清水好子「場面表現の伝統と展開」『源氏物語の文体と方法』
東京大学出版会、1980年6月、p.137。)
『源氏物語』もこの例に漏れず人物の対話を物語の中心に据えた構成を持っている。ただし、既に述べたように、『源氏物語』はそれ以前の作品と比較して、人物の行動や《舞台》が詳細に描写されたのである。そのために、『源氏物語』においては場面化という方法が特徴づけられる。
しかし、場面化という方法は物語展開にとって相応しくない面もある。以下は、その指摘である。
この物語では、いろいろていねいに舞台をしつらえて、人物を登場させ、対座する各人物に語らせることで、話を進めてゆこうとするのであるが、方法として、それは、長篇を語るにもっとも有効なものとは思えない。なぜなら、長く大きい物語を続けるためには、各場面、各段の、本来、孤立化し、断片化しようとする性格はふさわしいものではないからである。
(清水好子「源氏物語の作風」『源氏物語の文体と方法』
東京大学出版会、1980年6月、p.52。)
場面化が描写表現を駆使した手法であることから、描写の弊害と同じく場面化は物語進行を阻害することがある。清水氏は、『源氏物語』が断片化する場面ごとに「凝集された時間があり、それを同心円を描くように時間の歩みが大幅になって、次の濃密な時間、すなわち場面に移ってゆく作り方19」によって、物語を進展させたと述べている。『源氏物語』は、人物に重きを置く点はそれ以前の作品と共通していながら、会話によって人物を描きだす以外の方法として視覚的な場面を重要視し、なおかつ物語進行とも共存させようとした点で画期的である。
最後に、『源氏物語』の描写表現への意識について、「螢」の巻の考察を通して清水氏は以下のように指摘している。
ものの姿をそのまま描写し、そのことによって、おのずから意味を語らせようと意識的に動き出したのはやはり新しいことであって、源氏物語のなかにそれが部分的に見られても、けっして自覚的なものでなかった
(清水好子「螢の巻の場面描写」『源氏物語の文体と方法』
東京大学出版会、1980年6月、p.123。)
『源氏物語』は描写によってものに語らせるということに自覚的ではなかったのである。なぜならば、『源氏物語』は光源氏という主役人物に関わることどもを描くという枠組みが最重要であり、場面・事物・出来事の描写はその一手法でしかなかったからである20。また、この清水氏の指摘は描写表現の通時的変遷にも関連している。物語が人物について語ることを最優先の目的としていた時代には、物語作者は事物によってものごとを語らせる事物描写の働きに自覚的ではなかった。このような事物描写意識は近代以降に大きく変化したと考えられるが、それが作品の上にどのように現れているのか注目する。
ここでは、清水氏の論を参考に『源氏物語』における場面構成・場面設定を見てきた。場面化は、人物の対話を中心に展開する『源氏物語』において有効な方法として用いられたが、あくまでも人物を描くための一手法であった。
後世における『源氏物語』の受容
『源氏物語』が後世の作品に与えた影響は計り知れず、その全てをここに挙げることは不可能であり、また本稿の目的とも異なる。ここでは『源氏物語』の受容について近世と近代に限定して概観する。
近世の『源氏物語』受容について。簡潔にまとめると、近世の文学において『源氏物語』は無視できない存在であった。佐藤悟氏の言葉を以下に引用する。
近世文学は中世以前の文学と切り離して成立することが出来なかった。したがって中世文学がそうであったように、日本古典の白眉である『源氏物語』の影響を直接・間接に受けずにはいられなかったのである。
(佐藤悟「源氏物語と近世文学」『源氏物語講座第八巻源氏物語の本文と受容』
勉誠社、1992年12月、p.380。)
この言葉からは、中古、中世、近代を通して日本文学が西洋の影響にさらされることなくあり続けてきたということが読み取れる。さらに、近代は出版文化が生まれた時代でもあり、それ以前に比べてより簡便に『源氏物語』に触れることのできる状況にあったため、受容の仕方は様々にあった。
近世の『源氏物語』受容の代表例として、西鶴が挙げられる。西鶴の小説処女作として発表された『好色一代男』が、『源氏物語』の翻案であることについては、影響の程度に諸説あるものの既に一般に認められているといえよう21。また、『源氏物語』の物語論が西鶴の文芸意識に影響を与えたという谷脇理史氏の指摘がある。谷脇氏は西鶴の文芸意識について以下のように述べている。
文芸の有用性・有効性を打ち出そうとする姿勢がない。と同時に、自らの主張をいかなる方法で打ち出すかを語ろうともしていない。さらに、自らの文芸に権威を求める必要を認めず、権威など持たぬことに自負を持っているがごとくでもある。
(谷脇理史「仮名草子・浮世草紙と源氏物語」『源氏物語講座第八巻源氏物語の本文と受容』
勉誠社、1992年12月、p.402。)
谷脇氏は『好色一代男』の跋文や他作品から上のような西鶴の文芸意識を見出している。そして、このような西鶴の文芸意識の形成に寄与したのが『源氏物語』であったと指摘している。谷脇氏は『源氏物語』「蛍」の巻において展開された物語論を取り上げ、「世間的に価値なきものという前提を承認した上で、それが『世に経る人のありさま』の諸相を語るものであることを自負し、その方法を語っているということになる22」と要約している。このような物語の方法は「権威づけ」を望まず、また世の人々の姿をありのままに描こうとする西鶴の文芸意識と大いに重なる。谷脇氏は、西鶴当時の『源氏物語』の影響力や西鶴自身の『源氏』の読書経験から、西鶴が「自らの文芸の意味を考えようとする時、意識せざるえないものだった23」と主張している。
さて、以上のような事象からは『源氏物語』に対する西鶴の肯定的受容の態度が読み取れる。しかも、その態度は方法意識とも関係している。特に、両者の世人のありのままの姿を描こうとする態度からは写実的態度の類似が予想される。写実性は描写表現と関連しており、二者の描写表現に共通する部分があることが予想できる。これは比較の際に注意するべき点である。
さらに、西鶴以外にも柳亭種彦作・歌川国貞画の『偽紫田舎源氏』などの存在から『源氏物語』が近世において幅広く、また概ね肯定的に受容されていたといえる。
近代ではこの受容態度が変化する。西洋の思想が持て囃される中で『源氏物語』否定的に捉えられるようになる。近代の『源氏物語』受容状況について、千葉俊二氏の説明を以下に引用する。
馬琴などの勧善懲悪小説を退け、近代小説への新しい道を拓いた坪内逍遥の『小説神髄』は、必ずしも『源氏物語』を無視せず、宣長の「物のあはれ」説を引いて、勧懲的な読みの呪縛から源氏を解き放ち、比較的高い評価をあたえていた。が、以後のわが国の近代文学はいうまでもなく西洋文学の圧倒的な影響下に展開されていったので、明治期の文学界において『源氏物語』は、模写(リアリズム)という西洋伝来の文学理論的な観点から再評価された西鶴ほどにも読まれなかった。
(千葉俊二「源氏物語と近代文学」『源氏物語講座 第九巻 近代の享受と海外との交流』
勉誠社、1992年1月、p.9。)
引用からは『源氏物語』が西洋文学の思想と相容れずに評価されなかったことが読み取れる。近代の『源氏物語』批判の理由としては、『源氏物語』悪文説が挙げられる。この悪文説は漢文/和文・男性/女性という対立の観点から捉えられる24。『源氏物語』が悪文か否かの判断はともかく、当時はそのような評価が一般的であったといえる25。
『源氏物語』の文章について漱石の言葉を挙げておく。
一體に自分は和文のやうな、柔かいだら/\したものは嫌ひで、漢文のやうな?い力のある、?ち雄勁なものが好きだ。また寫生的なものも好きである。(中略)徒にだら/\した『源氏物語』(中略)なども好まない。
(夏目漱石「『余が文章に裨益せし書籍』」『漱石全集 第十六巻 別冊』
岩波書店、1967年4月、p.496。初出は『文章世界』1906年3月15日。)
上記から分かるように、漱石も『源氏物語』の文章については否定的であり、自分の執筆に取り入れようとはしなかった。西洋の影響を受けた日本語は和文と比較するとより論理的だといえる。その現代語と比較すれば、漱石が和文を「柔かいだら/\したもの」と評したのもやむなしといえる。漱石は西洋思想の影響を強く受けており、また写生文という方法との関連が強い。これについては後の項で述べる。漱石の評価に代表されるように、近代において『源氏物語』は概ね否定的に受容されていた。
ここでは、近世と近代の受容に限定して取り上げ、とりわけ本研究の研究対象となる作家である西鶴と漱石に関連させてみてきた。まとめると西鶴の肯定的受容、漱石の否定的受容が指摘できる。このような受容の仕方は、作家個人の特徴は見られるものの概ね時代ごとの受容の仕方をそのまま反映している。
以上、本項では『源氏物語』の事物描写に関して、特に場面という方法と受容に見てきた。『源氏物語』は日本文学を代表する散文作品として多大な影響力を持っている。その影響は肯定・否定、直接・間接と多様にある。
→ページのトップへ戻る
→ページのトップへ戻る
『日本永代蔵』の描写に関して、西鶴の文学史における評価を通じて、その文体を概観するところから始める。特に、西鶴の文体は通時的研究において重要な意味を持つことについて論じていく。
西鶴の文体
西鶴が写実に通じた作家であることは、すでに広く認められているといえる。写実性は描写表現と繋がり、西鶴の作品に事物描写が頻出することを予想させる。しかし、その描写表現は『源氏物語』や『三四郎』とは異なった特徴をみせる。その理由として、西鶴個人の気質は当然ながら、西鶴作品の主要な読者であった貞享・元禄文化期の平民たちの影響が考えられる。
ここでは、西鶴の文体に関する先行研究について、特に描写に関連するところを西鶴個人の気質にも触れながら取り上げる。
西鶴の文体に関しての研究には一定数の蓄積があり、その特徴はある程度明らかになっている。以下に、西鶴文体の特徴を要約したものとして浮橋康彦氏の説明を引用する。
省略が多い。飛躍と連想。連用中止や接続助詞の多用による長文化。文脈上呼応のねじれ。会話と地の文の混融。体言の列挙。並列連文節の多用。描写の即物性・具体性。――以上のことをふまえて尻取文・曲流文・雅俗折衷……等
(浮橋康彦「西鶴文体の一原型―『北条五代記』と『日本永代蔵』―」
『西鶴 日本文学研究資料叢書』有精堂、1969年10月、p.217。
初出は『国文学攷』43号、1967年6月。)
上記のような西鶴文体の特徴については他の文献、例えば『西鶴辞典』においてもほぼ同内容が記載されており26、共通の見解と捉えられる。また、このような文体的特徴の起源は、西鶴が談林派の俳諧師であったという経歴と「はなし」という口語的表現を好んだという性格に求められるのが一般的である27。西鶴は俳諧師として特に矢数俳諧に秀でており、短句の連続によって形作られる文はこのような俳諧の方法の影響を受けていると解される。先に挙げた浮橋氏の論文ではこれらの起源に加え、『北条五代記』のような私軍記の系列に西鶴文体の原型を見ようと試みている。現在のところ、西鶴の方法論に関する発言・文章は見られず、作品本文の表現特性からしか西鶴の表現方法を探ることはできない。繰り返しになるが、『日本永代蔵』に限らず西鶴の小説作品における描写表現は特徴的である。先の引用では「描写の即物性・具体性」という言葉でまとめられている。実際に西鶴の描写表現を例に挙げて説明する。
おの/\五銭・三銭、十銭より内をかりけるに、ここに年のころ二十三四の男、産れ付ふとくたくましく、風俗律儀に、あたまつき跡あがり、信長時代の仕立着物、袖下せはしく、裾まはり短く、うへした共に紬のふとりを無紋の花色染にして、同じ切の半襟をかけて、上田縞の羽織に木綿裏をつけて、中脇指に柄袋をはめて、世間かまはず尻からげして、ここに参りし印の、山椿の枝に野老入れし髭籠取りそへて、下向と見えしが、御宝前に立ち寄りて、「借銭一貫」と云ひけるに、寺役の法師、貫ざしながら相渡して、その国その名をたづねもやらず、かの男行きがたしれずなりにき。
(『日本永代蔵』一巻の一「初午は乗って来る仕合せ」)
『永代蔵』一巻の一は、正月の水間寺で法外な借銭をした男・網屋が、その貸銭を使って大儲けをするという致富譚である。下線部「年のころ二十三四の男~山椿の枝に野老入れし髭籠取りそへて」は、主人公・網屋の人物描写にあたる。容姿や服装の見た目について大仰に粉飾した言葉で描写されているわけではなく、具体的で現実に存在するものを通じてのみ描写されている。「信長時代の」や「世間かまはず」という作者の判断・評価も含まれてはいるが、基本的に対象の目に見える具体的部分に限った描写をしており、「即物性・具体性」という西鶴描写の特徴を顕著に示している。西鶴の描写は描写対象にしろ、描写の叙述にしろ、抽象を避けて具体を求めていることがわかる。具体物に限定した描写をしているということは、文飾を重ねることなく簡潔な文章になっているということも指摘できる。単純に描写が写実的で想起しやすいというだけではなく、「装飾」の役割を担った描写も排除されているのである。また、この文は短句の連続や捩れ文といった西鶴の他の文体的特徴も示している。特に、描写対象を列挙する手法は西鶴描写の特徴である。例文でも、体つき・頭・服装・所持品まで複数の描写対象を列挙している。このような手法は、やはり西鶴の俳諧師としての出自に関連付けて説明される。ここで対象列挙の方法を西鶴描写の特徴として挙げたが、前節で述べたように対象を網羅的に描写する表現は、江戸時代(特に江戸後期)の典型的な描写表現の一つでもあった。そして、これも述べたように網羅的描写は描写効果を妨げる場合もある。西鶴の列挙描写も一歩間違えば、描写としての効果を欠く可能性がある。しかし、西鶴の描写はそのような典型的・形式的な描写とは異なるという評価もなされている。これは特に近代作家によって与えられた評価であり、これについては後述する。
ところで、西鶴小説の欠点として小説構成能力の弱さが指摘される28。既に江戸後期には、滝沢馬琴が西鶴の構成力のなさを批判していたようである29。構成力の弱さといっても様々だが、例えば筆者の主張を優先するあまり小説の筋がおざなりになることがある。『永代蔵』の場合であれば、小説の筋を書くよりもある舞台の経済・生活の様子を紹介することを目的とした章段もある30。このような章段は舞台となる土地柄の紹介こそが目的であろうから、章段の狙いからすれば誤った構成とはいえない。それでも、「怪我の冬神鳴」のように一応主人公といえるような人物が設定され、その人物に関する事件が語られるという点から、土地紹介のような章段であっても小説的体裁を保とうとしていることが読み取れる。しかし、その主要人物に関する事件が章段の一部分でしか扱われない点が、却って小説としてだけでは成り立っていないという、構成の中途半端さを露呈することに繋がっている。構成能力の弱さは、描写表現と直接的に関連するわけではないだろうが、例えば小説的体裁が破綻した場合には描写表現も曖昧なものになることが予想される。
ここで西鶴文体の通時的意義について触れる。
西鶴の小説構成能力の弱さは確かに一般的には欠点として批判される。馬琴の批判があることから、現代の文学的観点に限った批判というわけでもない。しかし、この欠点も含めた西鶴の文学の方法・文体的特徴について、「はなしの方法」や「はなしの姿勢」といった口語表現との関わりにおいて捉えなおすことが指摘されている31。西鶴の「はなしの方法」や「はなしの姿勢」に注目するべきという指摘は、現代の小説観とは異なる視点から西鶴作品を捉えることが求められる。以下に「はなしの方法」に注目する意義について、藤江峰夫氏の言葉を引用する。
西鶴作品を、近代小説の過渡的な形態とみるか、逆に混沌ゆえの豊饒さを有しているとみるか、いずれにせよ西鶴の「はなしの方法」の考察は、近世小説としての西鶴作品の特質やその評価の問題と深く関わっている。
(藤江峰夫「西鶴の方法と文体」『西鶴辞典』おうふう、1996年12月、p.37。)
ここで、「はなし」という言葉は物語を語る行為としての「語り」を想起させ、本研究では取り上げなかった中世の『平家物語』のような「語り」の文学との関連を示唆する。また、西鶴の「はなしの方法」は文学言語の口語化を促がし、「雅俗折衷体」と呼ばれるような文体の誕生と繋がった。後にも触れるが、この「雅俗折衷体」は明治期において一部の作家に評価され、写実主義の一手段として取り入れられた。まとめると、西鶴の文体は西鶴以前の文学作品の影響を示し、近代にも影響を与えた文体ということである。このような時代ごとの繋がりを顕著に示す作家の文体は通時的研究を行う上で注目に値する。西鶴はその文体的特徴から通時的研究において重要な位置を占める作家である。
西鶴と平民読者
ここでは読者としての貞享・元禄期の平民と西鶴作品の関係性を捉えていく。
西鶴の功績の一つとして、文学作品というものを平民階層にも開いたということが挙げられる。これは西鶴と同時期に活躍した他作家にも当てはまるかもしれないが、やはりその中でも西鶴が際立っていると考えられる。ここで「平民」とは武家階層の人間ではなく、町に住み商取引に関係しているような階層、つまりは町民とほぼ同義で用いている。以下の麻生磯次氏の言葉を、西鶴に対する評価の定説として挙げておく。
当時の平民文学は、遊里生活が反映しているだけではなく、さらに広く町人の人生観・生活・思想が流れこんでいる。平民生活の如実の姿が文学に現れたのは、西鶴の町人物に始まるといってよい。その作品はその時代の町人生活の縮図である。身代のやりくり、事業の成功失敗、盛衰興亡の有様などが、広い範囲にわたって述べられており、吝嗇・強欲・気転・才覚などの町人魂から、風俗や生活様式に至るまで精細に描かれている。分限者となるために悪戦苦闘する町人の姿がまざまざと反映しているのである。
(麻生磯次「概説」『増補新版日本文学史4 近世Ⅰ』至文堂、1975年11月、p.12。)
下線部「西鶴の町人物」の代表作として『日本永代蔵』が挙げられる。
西鶴のような町人作家が登場する以前の文学作品は、書き手も読み手も公家や僧侶といった一部の階層に独占された文化であった。江戸時代の半ばになると、平民の書き手が、平民を題材とし、平民の読み手に向けて作品を書き始めたのである。このような平民文化が発展した理由として、日本社会の中における平民の台頭が挙げられるだろう。特に、町人の活躍が目覚ましかった上方は文化の主流となった。
当時の平民思想を一概にまとめるのは危険だが、平民にとって生活をしていくための金銭が重要であったことをふまえれば、概ねの平民思想は理想よりも現実が優先されていたと想像するのは難くない。遊郭や劇場といった民衆の享楽的・現世的な文化も、彼らが「今」という現実を最も求めていたことを示唆している。
平民の生活が実を求めるものであれば、題材自身であり読者でもある平民についての文学作品が写実的に描かれるのは不思議ではない。読者としての平民は、華麗な文飾が施された難解な書物よりも、簡単明瞭な写実的作品を求めていたと考えられる。平民の現世利益追求の気質は、理想や高尚な思索に耽ることよりも、確かにこの世にあるものに目を配ることを求めたのである。写実的な作品においては、平民にとって実生活に関連があると感じられる題材の選択や提示の仕方が求められた。自分と関係のある世界を描いた作品はそのまま自らの生活世界に適用できるからである。
西鶴は特に写実性に優れた作家として貞享・元禄当時も、現代でも評価されている。例えば、今回の研究対象とした『日本永代蔵』は、町人・商人そのものを題材とし、その暮らしぶりや思想といったものをありのままに描き出している。平民自身を題材にすることは、平民にとって最も「実」に即していた。さらに、題材だけではなくその提示の仕方、つまりは文章表現においても西鶴は写実的であったと評価されている。
西鶴の写実性は平民たちの気質に対応したことで評価されたが、読者の評価を受けて作家の表現が変わることもしばしば起こり得る。特に『日本永代蔵』は西鶴晩年の作であり、西鶴は商売作家として当時の読者の求めるものをある程度以上に理解していたと考えられる。平民文化の中で、平民に向けて、平民を題材とした作品を書くという時代背景も西鶴の写実性を形成した大きな要因の一つとして挙げられる。
読者が作家の書きぶりを規定することは珍しくないが、その読者は時代によって異なる。西鶴に限らず各時代の読者は作品に影響を与えているはずであり、読者を見ることは時代を見ることに繋がる。実を求める平民読者が、西鶴の描写表現をどのように規定したのかは注目に値する。西鶴の場合、町人出身ということを含めて、実を求める「町人の言葉」で作品を書いていたと考えられる。しかし、今回の研究では作品本文の分析に重点をおいており、この点についての考察が不十分である。更なる追求が今後の課題となる。
西鶴の再評価
西鶴はその活躍した時代において評価された作家である。更に近代においても西鶴の文体・描写表現は、近代作家に大きな影響を与え、一つの文体モデルとして捉えられていた。ここでは西鶴の再評価について論じる。
西鶴は活動当時には多大な人気を誇ったようであるが、当然その人気が出版当時から維持されているわけではない。特に「幕末維新期から明治一〇年代にかけて、西鶴は時代の厚い儒教的雰囲気や馬琴を北斗視する勧懲主義的文学観に圧されて深く埋もれていた32」ようである。また、平民にとっての西鶴の魅力が具体性・即物性であったとすれば、人気の低下も十分にあり得る。なぜならば、具体性・即物性は分かりやすさという利点で多くの読者を引きつける反面、その具体性・即物性に縛られることになるからである。物や事柄そのものに縛られることによって、時代や階層・文化ごとの共通観念を共有しない読者の参入が困難になる。特に西鶴が現実の出来事を題材に描く場合には、その出来事が起きる状況や時代に縛られる。具体性・即物性は直接的に小説としての評価を下げるわけではないが、常に新鮮さを求める読者に対しての訴求効果を下げる一因となる。西鶴が小説家として活躍した約十年の内に、好色物・武家物・町人物と次々と作風を変えていったことも、当時の平民読者層の目移りが激しかったことの傍証といえる。『日本永代蔵』は教訓譚としての側面を持っているので、その点では出版より後の時代の平民読者にも価値のある本であったかもしれない。しかし、江戸前期を題材・舞台にした致富譚であることから、作中で示される教訓が後の時代には適用できないと読者に捉えられてもおかしくはない。また西鶴の時には物語を破綻させ得る程の構成能力の低さも、娯楽として物語を求める読者に不満を抱かせたと推測できる。馬琴のような長編作家の人気が高かったことがこれを暗示する。
以上のような理由から、西鶴の作品が出版当時から現在まで常に注目され続けてきたとはいえない。完全に忘れ去られるということはなかっただろうが、批判がありながらも一定以上の注目をされ続けてきた『源氏物語』や漱石の作品とは異なる。
このような西鶴作品が明治期以降の近代作家によって、平民読者とは違った観点から再評価された。その理由は作家の立場によって様々であるが、概ね西鶴の文章表現や表現から窺える西鶴の執筆態度について、近代以降の文学作家の観点からの評価であった。西鶴文体を特に評価した作家は、明治二十年代の尾崎紅葉・幸田露伴・樋口一葉、明治四十年ごろの島村抱月・田山花袋・正宗白鳥などである3334。紅葉・露伴・一葉といった作家は写実主義を目指した作家であり、西鶴の具体物を繰り出す文体に写実性を見いだした。抱月・花袋・白鳥は自然主義を目指した作家であり、西鶴を自然主義的作家として取り上げることで、自然主義発展の手掛かりにした。
ただし、ここでの評価は平民読者とは全く異なる近代作家の立場からなされたものだという点には注意する必要がある。二つの立場には、娯楽や情報獲得のため、つまりはただ読むためだけに読む平民読者と自らの作家活動の糧として、つまりは書くために読むという違いがある。明治期の西鶴の再評価は専ら書き手からの評価であり、西鶴作品が明治の一般読者の人気を得たというわけではない。
西鶴が再評価された点に注目する理由はその時期にある。西鶴の再評価の時期は漱石が活躍した時期と近い。
言文一致体を目指す中には、明治二十年代において西鶴の文体が模倣されていた段階と、その後の写生文という文体が用いられた段階が見いだせる。これらの段階は直接に連続しているわけではないが、言文一致という一つの潮流の中に西鶴の文体と漱石と関連の深い写生文が並ぶということである。さらに漱石は自然主義との対比で語られることも多く、その自然主義の手掛かりとされたのが西鶴である。
漱石自身が直接的に西鶴を意識していたことを示す資料は見当たらない。むしろ、漱石は自らの執筆方法について、西鶴の影響を否定し、西洋思想の影響が大きいことを以下で述べている。
一國の歴史は人間の歴史で、人間の歴史はあらゆる能力の活動を含んでゐるのだから政治に軍事に宗教に經濟に各方面もわたつて一望したら何う賴母もしい囘顧が出來ないとも限るまいが、とくに余に密接の關係ある部門、即ち文學丈で云ふと、殆んど過去から得るインスピレーションの乏しきに苦しむと云ふ有様である。人は源氏物語や近松や西鶴を擧げて吾等の過去を飾るに足る天才の發揮と見認めるかも知れないが、余には到底そんな己惚は起せない。
余が現在の頭を支配し余が將来の仕事に影響するものは殘念ながら、わが祖先のもたらした過去でなくつて、却て異人種の海の向ふから持つて來てくれた思想である。
(夏目漱石「東洋美術圖譜」『漱石全集第十一巻評論雑篇』岩波書店、1966年10月、p.228。
初出は『東京朝日新聞』1910年1月5日。)
さらに漱石は西鶴の文章について「『西鶴もの』は讀んで面白いとは思ふが、さて眞似る氣にはなれぬ35」と述べている。このような漱石の言葉を見る限り、漱石自身が西鶴の方法を用いたとは考えられない。西鶴と漱石は近似しながらも直接には交わらないのである。だからこそ両者の文章には比較する価値がある。
伝統的な日本文学に大きく影響を受けながら自らも日本文学の一つのモデルになった西鶴と西洋の方法を取り入れながら現代の文学言語の基礎を築いた漱石を比較することは、近代という時代に起きた大きな転換点を見ることになる。近世と近代における文体の大きな変化を見るには、西鶴と漱石は適切な作者である。もちろん、『日本永代蔵』と『三四郎』という二作品だけでは材料としては不十分であり、同作者の他作品の分析・考察が必要である。また、今後の課題として近代作品の研究対象に一葉や花袋の作品を選出する。両者は近世の西鶴と近代の漱石の間にある空所を埋めるために是非とも研究するべき作家である。
『日本永代蔵』に関する指摘
本項では、描写表現を中心に西鶴文体を取り上げてきたが、最後に研究対象である『日本永代蔵』についての指摘を整理する。
『日本永代蔵』は西鶴の作品の中で、町人物と言われる部類に属すると作品と捉えられる。西鶴は『好色一代男』に代表される好色物、『武道伝来記』に代表される武家物を出版した後にこの町人物に取り組んだ。町人物は町人の生活について特に経済面を軸に書かれた作品群である。町人は町人階級の西鶴にとって身近な存在であり、好色物・武家物よりもより素朴で、関心の深い題材であったと考えられる。身近な題材であることから西鶴は執筆の材料には困らなかっただろうが、反面読者である平民階級に対しても身近な題材であるからこそ興味をひきつけにくかったとも考えられる。しかし、実際には『永代蔵』は西鶴の諸作品の中でも人気のある作品だったようである36。『永代蔵』の工夫の一つとして、「大福新長者教」という副題が示す教訓書的性格が挙げられる。『永代蔵』で西鶴が「元手のない人間には儲けることができない」という旨のことを記しているように、出版当時の庶民経済は停滞気味であった37。このような社会情勢の中、『永代蔵』は出版当時の読者に教訓書として読まれていたようである38。致富についての教訓書的性格が『永代蔵』の人気に繋がったと考えられる。
教訓書的性格の他に、『永代蔵』の魅力として指摘されるのは写実性である。以下は、谷脇理史氏の指摘である。
『永代蔵』全体が、金銭と人間とのかかわりを真正面からとりあげ、これまでの文芸がまともに問題としなかった世界を直視して作品としたことの新しさは指摘するまでもない。しかも、一見読者の興を魅きにくい身近な話題、非文学的とも見られる素材ととりくみ、そこに浮世を生きる現実の町人のありようを具体的に描破して行く方法は、従来の作品に全く存しない新しさを備えていると称してもいい過ぎにはならないであろう。
(谷脇理幸「西鶴と西鶴以後」『岩波講座日本文学史第8巻17・18世紀の文学』
岩波書店、1996年8月、p.67。)
谷脇氏は、『永代蔵』の虚飾を用いずに現実をありのままに見せようとする方法を高く評価している。ここでは谷脇氏の意見だけを取り上げたが、他の先行研究においても『永代蔵』の写実性はしばしば評価される。また実在の人物をモデルにして、それとわかるように暗に示すような書き方も読者を引きつける方法の一つといえる。
まとめると、『永代蔵』では、教訓性・写実性・モデルといった方法が用いられたわけである。特に、写実性・具体性は描写と大いに関わる性質である。『永代蔵』が写実性において高く評価されることは、描写表現の頻出を予想させる。ただし、西鶴の欠点として挙げた構成力の弱さは『永代蔵』でも表れている。一巻の三「浪風静かに神通丸」・二巻の二「怪我の冬神鳴」などがこのような欠点を示している。短編小説的構成が破綻した章段では、舞台の紹介や西鶴の主張についての叙述が多く、一貫した筋がないか、重視されていない。反対に、一巻の二「二代目に破る扇の風」・二巻の一「才覚を笠に着る大黒」などは一貫した筋を持った章段である。このような構成の差異が、事物描写の出現や効果にどのような影響を与えるのかという点が考察の観点となる。
以上、本項では『日本永代蔵』について、西鶴の文体を中心に先行研究を概観してきた。西鶴が通時的研究において重要な位置を占める作家であることを示し、『永代蔵』が写実的と評価されてきたことに触れた。その上で、作品の構成が描写に与える影響という問いを立てた。さらに、西鶴が用いた「町人の言葉」や近世から近代にかけての文体変化についても論じ、考察の観点とした。ただし、これらの問題ついては本研究の資料だけでは不十分であり、今後の課題として挙げられる。
→ページのトップへ戻る
→ページのトップへ戻る
『三四郎』の描写に関して、漱石と関係の深い写生という言葉をおさえるところから始める。次に、『三四郎』に見られる写生的表現、またその他の描写に関することを取り上げる。
『三四郎』は、『源氏物語』『日本永代蔵』と比較して事物描写に限らず描写表現の多様に用いられる作品であると予想される。なぜならば、『三四郎』は、西洋思想の影響を強く受け描写表現に意識的になった時代に執筆された作品だからである。さらに、漱石は自身が西洋思想の影響を受けていることに自覚的な作家であり39、特に写生概念との関連が深い。以下、漱石と写生概念の関わりについて論じていく。
写生
漱石を描写という表現と絡めて論じていく際には、写生という言葉を無視するわけにはいかない。元来、実物を見たままに写し描く西洋の絵画技法であった写生を、絵画を愛好していた正岡子規が客観的な態度で描写する文芸上の概念としての用い、これが言文一致運動において大きな役割を果たしたというのが通説である。本研究で定義した事物描写は、子規の用いた意味での写生と似通う部分がある。客観的態度で描写する点、さらには自らの外界にある対象を描き写すことを目的としている点である。ただし、写生概念を率先して広めた人物が正岡子規であることからもわかるように、写生は俳句と密接に関係しながら成立してきた。この点で描写と写生には差異がある。
明治期において、写生は作者の主観を排する手法として持ちこまれた。成瀬正勝氏の写生の文学史的価値についての提言の中で、氏は写生という技法について以下のように述べている。
小説はいふまでもなく時間芸術である。それを空間芸術である絵画の技法の上でのみ処理しようとしたところに、写生文は自ら否定することになった。すなはち写生文の多くは、絵画的な空間のひろがりのなかで、――文末に現在形を用ゐることによつて――情緒に富むムードの揺曳には成功したけれども、それだけに時間の経過に従つて展開する小説本来の物語性を欠く弊を生じたのである。
(成瀬正勝「写生文の文学史的価値についての一提言―鴎外・漱石と写生文―附 照葉狂言のこと」
『夏目漱石Ⅱ 日本文学研究資料叢書』有精堂、1982年9月、p.5。
初出は「成蹊国文」第三号、1970年3月。)
成瀬氏は空間表現という写生の表現特徴の内に小説技法としての近代的発展の限界を見ているが、本論において写生文の史的価値に関しては触れない。
事物描写と写生が類似していることについては既に述べたが、事物描写も同じような特徴を持っている。すなわち、事物描写がなされるときには物語内時間が停止に近づくという点である。そして、描写によって、特に過度の描写によって時間の進行が緩慢になることで時系列に沿った出来事の進展が阻害されることも既に述べた。物語の中で出来事が展開してゆくことが「小説本来の物語性」であるならば、時間停止は「弊」と捉えられる。しかし、本論ではむしろ物語の進行をいったん停止してまで描かれるもの、その描かれ方に注目する。出来事の進行を停止してまで描かれる事物には、当然それだけの価値があると考えられる。特に注目に値するのは「視点人物造型」の役割を担った事物描写である。なぜならば、『三四郎』は他の研究対象作品と比較して視点人物が明確に設定されているからである。その設定に「視点人物造型」の役割を担った事物描写がどのように影響しているのかは注目するべき点である
ところで、時間停止が「弊」と捉えられるのは過度の網羅的描写のように、その停止が行き過ぎた場合に限ると考えられる。西鶴がその具体的描写で評価されていたように、ある程度の描写は作品世界を具体的にイメージさせるために必須である。事物描写の最も基本的な目的は「背景・事物」の役割による作品世界の具体化である。そのために、物語進行が緩やかになること自体は「弊」とはいえない。しかし、過度な網羅的描写は物語進行を完全に停止させ、これは確かに「弊」といえる。「弊」と捉えられるような状況は、作品中で物語進行と描写の均衡がとれていない、言い換えれば描写妥当性が低い場合である。写生文の場合、この均衡を安定させて物語として成り立たせるよりも、客観的な態度で描くという写生文家としての態度を重視した40ために、このような弊害が起きたのだと推測する。ただし、全ての小説・物語作品において物語進行と描写の均衡が取れていることが望ましいかは不明である。なぜならば、描写妥当性は作品の目的に左右されるからである。本研究では対象作品がこの均衡をどのように扱っているのかに注目したい。
写生文とは簡潔にいえば「見たままのものをそのまま書き写す」という技法であるが、実際は事実の再現を目指した文章というわけではない。というよりも、言葉によってありのままの事実を再現することは不可能である。視覚情報一つをとっても一度に認識できる情報量は文字情報とは比較にならない。また、そのような情報を何の整理もなく並べたとしても、読者はその文章を現実の再現として認識しないというのは既に述べた通りである。つまるところ、写生文とはありのままの事実を再現しているかのように見せかけた文章なのである。ここで着目したいのは視点設定である。事実をそのまま再現しているかのように読者に感じさせるためには、語り手と視点人物が一体となる一人称の視点になることが最も望ましい。なぜならば、認識主体としての視点人物と語り手としての表現主体が一体になることで、事実と表現の間隔は最も近くなるからである。このような視座の限定は、序章で述べた描写の成り立つ条件の一つでもある。さらに、写生の「見たまま」という根本的な性質は、写生対象と認識主体が同一の時空間に存在する必要があることを示している。これは時空間の限定にあたる。つまり、写生文は今回の事物描写として設定した範囲の中でも、よりその条件に当てはまるような表現技法であり、描写性の特に高い表現だといえる。
漱石と写生文
ここからは、漱石が写生をどのように理解し、用いていたかをまとめていく。
子規と関係の深い漱石も写生文に無関心ではなく、これは漱石自身がそのものずばり「寫生文」41という題でその特色について論じていることからもわかる。「寫生文」において漱石は、写生が世間で認められるようになっているが、その特色は未だ明らかではないと述べている。写生について漱石自身が注目する点については以下のように述べている。
寫生文と普通の文章との差異を算へ來ると色々ある。色々あるうちで余の尤も要點だと考へるにも關らず誰も説き及んだ事のないのは作者の心的状態である。他の點は此一源泉より流露するのであるから、此源頭に向つて工夫を下せば他は悉く刃を迎えて向ふから解決を促がす譯である。(太字は原文では傍点)
(同上、p.22。)
ここで漱石は写生文と普通の文との差異を「作者の心的状態」に求めている。その上、この点こそが写生において最も源泉となる部分になるとまで述べている。漱石が「作者の心的状態」を重視したのは人事を描く文章の差異を作者の態度の差異に求めたからである。写生文家の態度について、漱石は「寫生文家の人事に対する態度は(中略)大人が小供を視るの態度である42」と述べている。これは写生文家が「視察対象」とは異なる平面に立つということを表した、漱石なりの比喩である。ここで漱石の述べた写生文家の態度は、写生の根本的な理念である「客観的態度」と通じることが以下の漱石の言葉からも分かる。
彼我の境界を有して、我の見地から彼を描かなければならぬ。是に於いて寫生文家の描寫は多くの場合に於て客観的である。(中略)小兒の喜怒哀楽を寫す場合に勢客観的でなければならぬ。こゝに客観的と云ふは我を寫すにあらず彼を寫すといふ態度を意味するのである。(太字は原文では傍点)
(同上、p.26)
漱石はこのような写生文家の態度が、一般の小説家にはない「餘裕」や「ゆとり」を生むと述べている。さらに、漱石は写生文家の客観的態度を普通の小説家と比較して、「描き出ださるべき一人に同情して理否も、前後も辨へぬ程の熱情を以て文をやる男よりも慥かな所があるかも知れぬ43」と評価している。ただし、写生文家の客観的態度が小説を書く際の「唯一」・「最上等」の態度ではないと付言している。まとめると、漱石は写生文の書き手の態度に注目し、その客観的態度に一定の評価を置いていた。
「寫生文」の執筆意図が文章の最後で述べられている。それによると、「寫生文」は漱石の創作態度を示すというよりは、批評のために写生文というものを扱ったということである。「寫生文」からは、漱石が写生について一定以上の理解を示していたことが読み取れるが、同時に漱石が写生を自らの方法としては用いようとしていないことも読み取れる。しかし、これは漱石の作品に写生概念が影響を与えていなかったことを示す理由にはならない。むしろ、漱石が「寫生文」において写生の肝要な点が技法ではなく態度であると主張した点に注目すると、写生概念は漱石作品に大きな影響していたことがわかる。写生文の要が態度にあるとすれば「写生文家」的な人物を作品の中に再現することが可能だと推測できる。技法はそれを用いる特定の行動と不可分に結びついている。そこである技法を再現するためには、その技法を用いた特定の行動とともに再現する必要がある。写生文が技法によって成り立っているとすれば、「写生文家」を再現するためにはまさに「写生文」を書く人そのものを書かなければならない。この場合の写生文家は作家、もしくはそれに類する人物に限定される。しかし、写生文が書き手の態度によって成り立っているとすれば特定の行動に縛られる必要がなくなる。「写生文」を書く「写生文家」そのものではないとしても、「写生文家」と同様の態度である「写生文家」的な登場人物を描くことができる。そして、実際に漱石はこのような人物を、自らの作品中に描き出していると考えられる。この点については再度触れる。
漱石作品と写生
漱石が写生文と関わりの深いことは、その作品の構造からうかがえるという相馬庸郎氏の指摘がある。
『吾輩は猫である』は写生文であった。(中略)作品の成立事情にからんで言っていることではない。また作品の叙述細部にいわゆる写生技法が巧みにいかされているところが多いから、そう言ってみただけのことでもない。『吾輩は猫である』という長編小説の構造そのものが写生文的であった、と言っているのである。少くとも漱石の理解する「写生文」概念にそのままあてはまっている。
(相馬庸郎「漱石と写生文―もう一つのリアリズム・覚書―」
『夏目漱石Ⅱ日本文学研究資料叢書』有精堂、1982年9月p.10。
初出は「文学」1974年4月。)
相馬氏は、漱石の述べた写生文家の態度(「大人が小供を視るの態度」)を「作者と作中人物の距離・間隔の問題」と解し、この距離間隔が『吾輩は猫である』において二重に構造化されていると述べている。まずは作者自身と語り手として設定された猫、さらに猫と語られる対象となる苦沙弥先生たちという二つの距離間隔である。相馬氏はこの間隔を設定したことが、漱石のいう写生の特徴である「ゆとり」や「客観」性を作品の中に生み出していると考察する。他にも『吾輩は猫である』に作品全体を貫く筋がない点も写生文的特徴として挙げている。相馬氏の指摘は、写生の技法そのものではなく、その概念が漱石の作品に影響を与えたことを示唆する。
また、漱石の造語である低徊趣味も写生文家の態度と類似する。低徊趣味とは漱石の造語で、「『鶏頭』序」という高浜虚子の作品の序文において用いられた語である。以下にその定義を引用する。
文章に低徊趣味と云ふ一種の趣味がある。(中略)一と口に云ふと一事に?し一物に倒して、獨特もしくは連想の興味を起して、左から眺めたり右から眺めたりして容易に去り難いと云ふ風な趣味を指すのである。(中略)此趣味は名前のあらはす如く出来る丈長く一つ所に佇立する趣味であるから一方から云へば容易に進行せぬ趣味である。換言すれば餘裕がある人でなければ出来ない趣味である。(夏目漱石「高浜虚子『鶏頭』序」『漱石全集第十一巻評論雑篇』
岩波書店、1966年10月、p.555。初出は1908年1月。)
下線部「容易に進行せぬ趣味」は写生文家が筋よりも対象への興味を優先させる点と共通し、また下線部「餘裕がある人でなければ出来ない趣味である」は漱石が述べた写生文家の態度そのものである。上記の引用から、低徊趣味の人物が写生文家と相通じるものの見方をしていることが読み取れる。
ここまで、漱石の思想・作品創作に写生概念の影響が大きいことを確認してきた。漱石が一般の写生文家と異なるのは、写生文家としての態度で写生文を書くのみならず、写生文家の態度をした人物を作中に登場させることを選択した点である。漱石は「写生文家」的人物を描いたのである。ただし、漱石の全作品が写生文的特徴を持っているわけではない。子規を含む写生文家の影響の大きかった前期の作品に、このような傾向が強いと推測する。
『三四郎』と写生
ここまで、漱石と漱石作品にとって写生概念の影響が無視できないことについて論じてきた。本研究の対象作品となる『三四郎』についてもこれは同様である。漱石による「『三四郎』豫告」を以下に引用する。
田舎の高等學校を卒業して東京の大學に這入つた三四郎が新しい空氣に觸れる、さうして同輩だの先輩だの若い女だのに接觸して色々に動いて来る、手間は此空氣のうちに是等の人間を放す丈である、あとは人間が勝手に泳いで、自ら波瀾が出来るだろうと思ふ、さふかうしてゐるうちに讀者も作者も此空氣にかぶれて是等の人間を知る様になる事と信ずる、もしかぶれ甲斐のしない空氣で、知り榮のしない人間であつたら御互に不運と諦めるより仕方がない、たゞ尋常である、摩訶不思議は書けない。
(夏目漱石「『三四郎』豫告」『漱石全集第十一巻評論雑篇』岩波書店、1966年10月、p.499。
初出は『東京朝日新聞』1908年8月19日。)
この「豫告」で漱石は、筋よりも三四郎が人と出会うことで自然と生じる事件を描くと予告している。この「豫告」は、筋よりも場面を優先する写生文家的態度の表明と解釈できる。また、下線部「たゞ尋常である、摩訶不思議は書けない」も、見たままの現象を描くという写生文家の根本的理念である客観的態度を表した言葉と捉えられる。既にこの「豫告」から漱石が『三四郎』を写生文家的態度で書こうとしていることが分かる。このような漱石の執筆態度についての表明が、そのまま表現に直接的に表出していると安易に受け取ることはできないが、何らかの影響は与えていると考えられる。特に、事物描写に関して、次に挙げる視点設定との関係が重要である。
『三四郎』は基本的に三人称視点で語られ、作品の大部分では三四郎を視点人物としている。作品世界は三四郎の視点を通して語られていく。語り手ではなく、三四郎という作品世界に存在する人物に視座を置くことで、描写性の高い表現が出現しやすくなると考えられる。
さらに、この三四郎が低徊趣味の持ち主であることが、本文において示されている。
三四郎は勉強家というより寧ろ洲徊家(※注:低徊家と同義)なので、割合書物を読まない。その代りある掬すべき情景に逢うと、何遍もこれを頭の中で新にして喜んでいる。その方が命に奥行がある様な気がする。今日も、何時もなら、神秘的講義の最中に、ぱっと電燈が点く所などを繰返して嬉しがる筈だが、母の手紙があるので、まず、それから片付始めた。
(『三四郎』4、注は引用者。)
低徊家の態度が写生文家の態度と共通していることは既に述べた。つまり、主な視点人物となる三四郎が低徊家≒写生文家ということになる。写生文家の態度を持った人物が作品の大部分で世界認識の視座の役目を果たすということは、事物描写が頻出することを予想させる。引用部では、三四郎が「自らを掬すべき情景」という外界の事物に、低徊家としての興味を引かれることも語られている。つまり、三四郎は外界の事物に興味を抱く人物と設定されている。ただし、三人称視点であるために、語り手が三四郎と距離を置き、語り手自身の視座から語ることもある。「吾輩」の視点で語られる『吾輩は猫である』と比較すると、『三四郎』という作品はその全体が写生文であるとはいえない。
『三四郎』について、三四郎が写生文家的態度の人物であるために、三四郎に視座が置かれたときに描写性の高い表現が出現すると考えられる。また、三四郎が写生文家的態度で事物を見るということは、反対に事物描写の叙述が三四郎を写生文家として造型するということも考えられる。つまり、『三四郎』の事物描写は前節で想定した「人物造型」の役割を担っていると予想できる。
異なる観点の先行研究
ここまで、特に漱石と写生の関係に絞って論を進めてきた。『三四郎』も写生概念との関係が深く、描写表現が頻出すると予想した。最後に写生とは異なる観点の先行研究を押さえる。
ここでは、漱石の描写表現全般について漱石門下の赤木桁平氏の「描寫の傾向及び特質」44を参考に、その表現特性をまとめる。赤木氏は描写を性格描写・心理描写・自然描写に分けてそれぞれの表現特性を考察している。赤木氏の考察から漱石の描写に共通する傾向が読み取れる。
赤木氏は三種類の描写のうち性格描写を特に評価しており、その評価は「人物の個性に具はる少許の性癖なり特質なりを印象的に寫し出45」す点に与えている。心理描写について、赤城氏は前期が分析的・説明的で心理よりも理屈に傾倒しているのに対して、後期には明快さが見られ、その心理描写は完成していると評価している。これは、漱石の心理描写がより印象的な描写へ変遷したとも言い換えられる。事物描写と最も関連のある自然描写についても、「その與へられたる對象の最も著しい部分を捉へて、これを出来るだけ印象的に描き出す46」と分析しており、これも漱石が印象的な描写を目指したことを示唆する。つまり、漱石は描写対象の最も印象的な部分を取り上げることを目指し、網羅的な描写を避けようとしていたと考えられる。描写の効果に関して核となる印象の強い要素のみを取り上げる描写の方が効果的であることは既に論じた。漱石の描写全てがそのような効果を発揮しているとは言えないが、赤城氏の考察からは漱石が描写表現の効果的表現方法まで意識していたことがうかがえる。
以上、本項では写生概念を中心に先行研究を概観してきた。漱石、そして『三四郎』に写生概念が強い影響を与えていることを確認し、『三四郎』には事物描写が頻出するという仮説を立てた。これは本研究の当初から予想されていたことではあるが、先行研究を踏まえることで改めて、説としてより強固になった。さらに描写の「視点人物造型」という役割や物語進行と描写の均衡という描写の効果についても問題として挙げた。
本節では事物描写に関しての先行研究を作品ごとに概観してきた。研究対象の三作品を時系列で並べると次のような関係が見いだせる。
まず、『源氏物語』は当然ながら以後の二作品とは関係なく作られたものである。次に『日本永代蔵』は、『源氏物語』を評価し、その文芸意識への影響も指摘される西鶴によって書かれた作品であり、文学の方法にも共通性が期待される。また、西鶴は近代においても西洋リアリズムの観点から再評価されている。西鶴との共通性が指摘された『源氏物語』は却って否定的に評価されたのとは対照的である。最後に『三四郎』は、『源氏物語』・西鶴とどちらの影響も否定した漱石によって書かれた作品である。そして、現代文学の方法は、この三者でいえば漱石に最も依るところがあるのは明白である。
このように複雑な関係を見せる三作品であるが、一方これらの作品は描写性が高いと評価されている点で共通している。しかし、その描写表現は上の関係性を反映するように一様ではない。
本節では、先行研究の概観と共に分析の足がかりとなる仮説も見出してきた。仮説を踏まえた分析結果は次章で示す。
第1章として、先行研究を基点に描写についてのさらなる考察と仮説の設定を行ってきた。研究対象となる三作品ともが描写表現と関連の強い作品であることも明らかになった。次章では対象作品についての本文の分析とその結果から特に事物描写に関しての考察を行っていく。
<脚注>
46 同上、pp.311-312。
→ページのトップへ戻る
→ページのトップへ戻る
本章では、研究対象となる『源氏物語』『日本永代蔵』『三四郎』について分析項目による分析結果を基に観点に沿った考察を行っていく。観点として、《文の機能》に応じた文の種類、事物描写、場面を設定する。
分析結果の表は全部を掲載することができないので、分析例として一部を巻末に付し、本章には作品資料の本文のみを引用する。
以下、用語について説明する。
(描写)(「記述」)(「説明」)(「評価」)の4種類については、単一の機能を持つという点に注目して《単機能文》という別称も用いる。
《複数の機能を持つ文》(複数の機能が直列に並んだ文) (一方の機能がもう一方の機能に内包されている文)については、それぞれ《複機能文》(直列文)(内包文)と略称で表す。具体的な分析項目を挙げる際には、(直列文)の場合は(描写・記述)や(記述・評価)のように(~・~)で表す。(内包文)の場合は、(描写含みの記述)(説明含みの描写)のように(~含みの~)と表す。この際には「記述」「説明」「評価」の鍵括弧は外して示す。
《複機能文》の中でも分かりづらい項目として(~/~含みの~)や(~含みの~・~)がある。(~/~含みの~) には、例えば(描写/評価含みの記述)があり、これは(描写と評価を内包した記述)を表す。(~含みの~・~) には、例えば(描写含みの記述・描写)があり、これは(描写含みの記述と描写の直列)を表す。以下に整理して示す。
※(描写)(「記述」)(「説明」)(「評価」)の別称
(描写)(「記述」)(「説明」)(「評価」)――――――――《単機能文》と別称
※《複数の機能を持つ文》の呼称
《複数の機能を持つ文》―――――――――――――――《複機能文》と呼称
(複数の機能が直列に並んだ文)――――――――――――(直列文)と呼称……例 (描写・記述)
(一方の機能がもう一方の機能に内包されている文)―――(内包文)と呼称……例 (描写含みの記述)
「記述」「説明」「評価」の鍵括弧は外す
※《複機能文》の中で分かりづらい項目
(~/~含みの~)―――――――――――――――――――例 (描写/評価含みの記述)
(描写と評価を内包した記述)を表す
(~含みの~・~) ――――――――――――――――――例 (描写含みの記述・描写)
(描写含みの記述と描写の直列) を表す
《複機能文》の一つ(描写含みの記述)についての説明を加える。各作品における(描写含みの記述)は、『源氏物語』では24.4% (190文)で第3位の出現割合、『日本永代蔵』では19.5% (71文)で第3位の出現割合、『三四郎』では9.9% (574文)で第2位の出現割合を示した。分析結果から(描写含みの記述)は比較的出現割合の高い機能といえる。ここから、(描写含みの記述)は小説・物語作品の主要機能の一つと判断して、考察を進めていく。(描写含みの記述)についての解説は本章第1節で行う。
→ページのトップへ戻る
本節では『源氏物語』の分析結果から観点に沿った考察を行い、作品の表現特性を明らかにする。以下、『源氏物語』三巻とは「桐壷」「若紫」「明石」をまとめて扱う意味で用いる。
考察の前に分析に関する諸情報を挙げておく。『源氏物語』について、今回の研究で対象とした三巻の総文数は778文であった。各巻の文数は「桐壷」巻183文、「若紫」巻323文、「明石」巻272文であった。
→ページのトップへ戻る
本項では《文の機能》に応じた文の種類について考察していく。
次のグラフは、『源氏物語』三巻における文の種類ごとの出現数である。
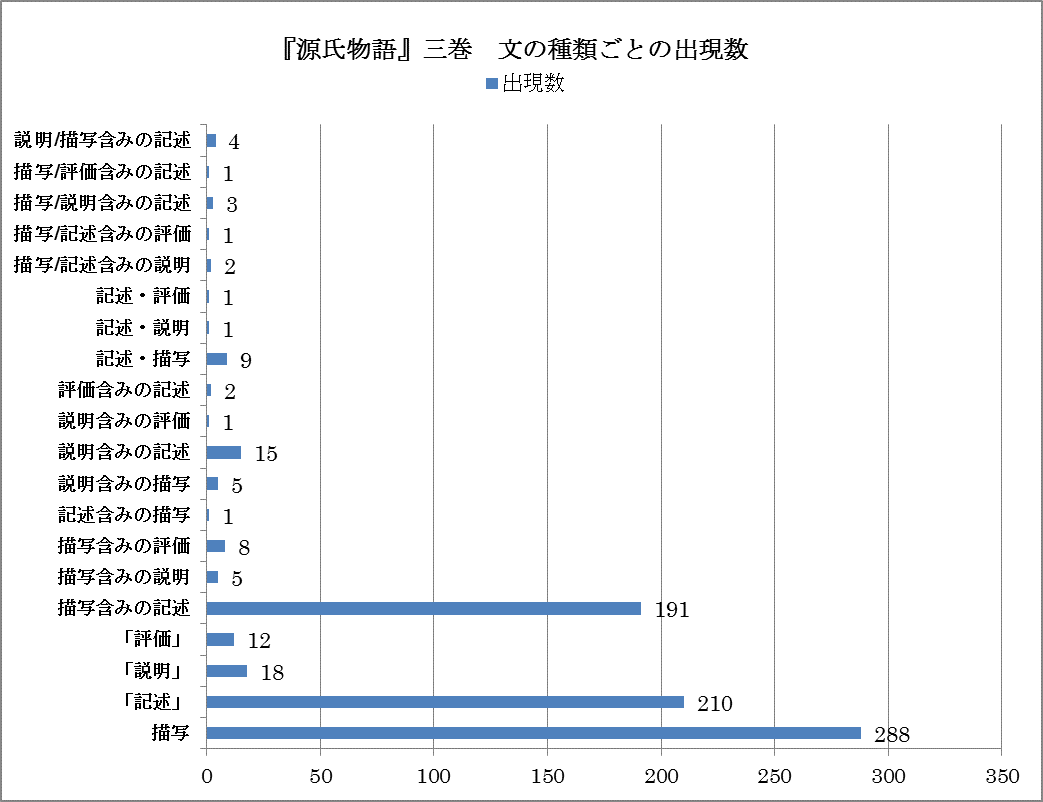
文の種類ごとの出現割合を比較し、その上位の機能に着目することで、その作品においてどの機能が重視されているかが分かる。文の種類の傾向から考えられる、作品ごとの表現特性について論じる。
『源氏物語』三巻に出現した文の種類は計20種類である。出現割合は、(描写)が37.0%(288文)で出現割合第1位、(「記述」)が27.0%(210文)で出現割合第2位、(描写含みの記述)が24.6%(191文)で出現割合第3位である。これら3種の文が『源氏物語』三巻で占める割合は88.6%(689文)である。これら3種は対象表現47である点で共通している。
ここで対象表現に注目する。(説明)(評価)といった叙述者表現48を含まない純粋な対象表現文の全体割合は90.2%(702文)である。つまり、作品世界の事態や事物を示す叙述が全体の9割を占めていることになる。一般的に、小説・物語作品は虚構の世界を言語によって具体的に描き出すことを目的にした言語芸術だといえる。虚構の世界を具体的に描き出すためには作品世界の事態や事物を対象にする必要がある。そうでなければ、虚構の作品世界を描き出すことなどできない。分析結果は、『源氏物語』が作者の思想や心情を伝えるための書き物ではなく、虚構の世界を描き出すための作品として造型されていることを示している。
対象表現に関して(描写)(「記述」)(描写含みの記述)を取り上げて更に考察していく。(描写含みの記述)は部分的に(描写)機能が現れるが、全体としては(「記述」)機能を示している。ゆえに、(描写含みの記述)は(「記述」)に属する文だといえる。これを踏まえて、『源氏物語』三巻における(描写)と(「記述」)系列の出現割合は、(描写)は37.0%(288文)、(「記述」)系列は51.5%(401文)であった。『源氏物語』では(描写)よりも(「記述」)系列の方が約1.4倍多い。また、『源氏物語』では(「記述」)系列の文が全体の半分を占めていることも分かる。この結果は『源氏物語』のどのような特性を示すのか。ここで(「記述」)の役割や効果を押さえておく。
(「記述」)はある一定以上の時間の流れの中における出来事を記す。(描写)が時間の流れを緩やかにして出来事を具体的に描くのに対して、(「記述」)は出来事をまとめて記すにとどめて時間を進行させる。つまり、(「記述」)は物語を進行させる役割を果たし、(「記述」)が多いということは物語がどんどん進展していくことを示している。
以上を踏まえると、『源氏物語』には物語を進展させる叙述が全体の半分近くあるといえる。なぜ、『源氏物語』がこのような特徴を持つのか。この理由を『源氏物語』が持つ光源氏の一代記的側面との関連から考える。
一代記は一人の人物の一生を書く。そのため、一代記では物語の進行と人物の人生の進行は同列に扱われる。一代記においては、対象となる人物にまつわる出来事の中でも特に描く価値があると考えられる部分に焦点をあて場面として(描写)することでその人物を具体的に描き出そうとする。『源氏物語』の場合は、源氏の女性との関係を中心に源氏の一生を記そうしていることが作品から読み取れる。つまり、源氏が女性と関係する場面を中心に一代記が構成されているといえる。そして、この場面とは前章で挙げた清水氏の指摘にあったように人物の対話場面でもある49。
しかし、人の一生を書くからといって、その人にまつわる出来事を全て具体的に描いていてはいくら紙幅があっても足りない。また、前章の清水氏の指摘にもあったように、場面とは本来断片的なものである50。そのため、一つの場面のみを描いていては物語は容易に進行しない。言い換えれば、人の一生を書くためには一つの出来事・一つの場面に拘泥していることはできず、場面と場面をつなぐ役割の叙述が必要になる。そこで時間を進め、物語を進行させるために(「記述」)系列の文が必要になる。つまり、『源氏物語』は光源氏の一生を書く上で、場面を具体的に描くために(描写)の文を用いる一方、物語を進行させるために(「記述」)系列の文が必要なのである。これは『源氏物語』に(「記述」)系列の文が半数近い割合で出現している理由の一つといえる。
ここまで、(「記述」)と(描写含みの記述)を同系列の文と捉えて論を進めてきた。しかし、この二種類の文には異なる部分もある。その差異とは、(描写含みの記述)には(描写)機能が内包されている点にある。以下に例文を挙げる。
その年の夏、御息所、はかなき心地にわづらひて、まかでなんとしたまふを、暇さらにゆるさせたまはず。年ごろ、常のあつしさになりたまへれば、御目馴れて、「なほしばしこころみよ」とのみのたまはするに、日々に重りたまひて、ただ五六日のほどにいと弱うなれば、母君泣く泣く奏してまかでさせたてまつりたまふ。
(『源氏物語』「桐壷」)
これは桐壷の更衣が病に伏せり、宮中を退出する直前の出来事である。一文目が(「記述」)、二文目が(描写含みの記述)である。
一文目では「その年の夏」という以外に時間的な限定はない。この時間的限定からは、源氏が三歳になった年51の夏に起こった出来事であるということが読み取れるだけである。また、「まかでなんとしたまふを、暇さらにゆるさせたまはず」という、帝への退出願いのやり取りもある程度の時間経過の中で起きたと考えられる。一文目は出来事をまとめて記す(「記述」)文といえる。二文目についても、一文の中で「五六日」以上の時間が経過し、その出来事がまとめて記されているので全体としては(「記述」)文といえる。しかし、下線部「『なほしばしこころみよ』とのみのたまはする」の部分だけは帝の具体的な発言が示されている。この発言部分については、帝という人物が実際に話す場面が喚起され得る。つまり、下線部は(描写)機能を持っている。
ここで下線部が(談話描写)であることは像の喚起を容易にしている。なぜならば、(談話描写)によって描かれるのは人物の発話であり、発話行為は、その所要時間を想起しやすいからである。私たちは生活の中で発話行為を繰り返し経験している。そのため、書き文字であってもその言葉を実際に発話した場合にかかるおおよその時間には見当がつき易い。具体的な時間が想起できるのであれば、具体的な行為についても想起しやすくなる。ゆえに、談話描写は像を喚起し易いのである。
ただし、下線部は限定が弱いために、その描写性は低いといえる。確かに、下線部から帝の発言という行為について、特にその行為時間を具体的に想像できる。しかし、逆にいえばこれ以外の限定が加えられておらず、ここで述べた以上の想像は困難である。帝がどのような場所におり、当該発言を誰が認識しているのかは示されない。例文では語り手が出来事を俯瞰的に語っており、視座が作品世界内に置かれていないことも描写性を低くする要因となる。
また、この帝の発言は具体的ではあるが、本当にこの通りの発言をしたとは考え難い。『源氏物語』に限らず、小説・物語作品は虚構世界について書くものであるから表される出来事は全て虚構であるが、ここで指摘したいのはそのような意味ではない。話し言葉をそのまま書き言葉にはできないという意味でもない。より正確にいうならば、帝の発言を「ありのままに描いて」いないように捉えられる、ということである。(描写)はありのままに出来事を描こうとする叙述である。(描写)の積み重ねによって作られた場面の中では、行為や事物がありのままに描き出されている。(「記述」)は出来事の時間を圧縮して記していると述べてきたが、換言すると、これは作者が出来事を操作した上で提示しているといえる。当然、(描写)文も作者が対象を操作して提示している。しかし、「ありのままに描いている」ように見せかけるということは、操作を出来る限り目立たなくしているということである。対して、(「記述」)文ではこの操作を隠すことができない。なぜなら、現実には一瞬で「五六日」経つなどということはないからである。つまり、私たちが(「記述」)文を読むときには、必然的に作者による事象の操作を感じることになる。(描写含みの記述)が(「記述」)系列に属しているということは、(描写含みの記述)も作者の操作を隠すことができないということである。この結果、一部分が「ありのまま」を描こうとしても、文全体がその作為を暴いてしまうのである。そのため、帝の発言は「ありのまま」に感じられず、作者による操作が感じ取れる。その場合には「ありのまま」を描いているとは感じられず、描写性は低くなる。
さらに、現代の私たちの感覚で想起した発言は、本来作者の想定していた発言場面とは異なる可能性の方が高い。これは『源氏物語』当時の帝と現代の私たちとの間に、時代的・社会文化的に大きな隔たりがあるため当然のことである。この指摘は研究対象作品全てについていえる。ただ、この点を考慮すると論が進まないので、本稿ではこの隔たりに関しては無視する。むしろ、現代の私たちが作者の想定したものとは異なる形であったとしても具体的行為を想起し得る、つまりは(描写)機能を発揮するという点に着目する。当時の読者が同じ描写表現によって、どのような像を想起していたかを探るのは今後の課題とする。
ここまでをまとめると、下線部は(描写)機能を発揮しているのだが、(描写)機能として確立しているというには疑問を抱く部分もある。それでも、(「記述」)文の中に(描写)機能が含まれていることは明らかである。(描写含みの記述)に含まれる(描写)機能に疑問を覚える要因は、(「記述」)文の中に含まれていることによって生まれていると考えられる。つまり、(「記述」)文に含まれている限り、部分的に(描写)機能を発揮しても、その機能・限定が持続することはない。これを踏まえると、(描写含みの記述)の積み重ねでは場面を作ることはできないといえる。
では、このように(「記述」)文が(描写)機能を内包することで、(描写含みの記述)は何を果たそうとしているのか。この問いについて最も単純な答えを挙げておく。(描写含みの記述)は(「記述」)文に(描写)機能を内包することで、作品世界を描くことと物語を進展させること、つまりは(描写)と(「記述」)の両機能の両立を狙っているのである。
描写が物語の進行を阻害することは繰り返し述べてきた。物語を進行させるために作者は(「記述」)を用いる必要がある。しかし、(「記述」)も対象表現ではあるものの、出来事をまとめて記すだけであり具体物は描かれない。作品世界を具体的に描き出すことが物語作者の一つの目的であるとすれば、(「記述」)によって物語を進行させている間にも具体性を求めても不思議ではない。そこで(描写)機能を含んだ(「記述」)文が書かれるようになったと考えられる。ただし、中古・近代の作者がこのような執筆意識を持っていたかどうか、そもそも文章の機能というものを意識していたかどうかについて、今回の作品資料や参考文献からは結論をだせない。ここでは、物語作者の根本な目的が(描写含みの記述)を志向するという推測を述べたに過ぎない。
(描写含みの記述)の狙いが果たされ難いことは上で述べた通りである。(描写含みの記述)に内包される(描写)機能は基本的に描写性が低く、(描写)として確立した機能を持っていない。それでも、(描写含みの記述)には作品世界を具体的に描くという効果があることも確かに認められる。また、物語の進展と具体化を同時に行う(描写含みの記述)は、物語作者にとっても使い勝手の良い叙述だと考えられる。研究対象作品全てにおいて、(描写含みの記述)の出現割合が必ず3位以内に入っていることもこれを示唆する。これらを踏まえて、(描写含みの記述)を小説・物語作品の主要機能の一つと判断した。
さて、ここまでを踏まえて『源氏物語』の対象表現三種(描写)(「記述」)(描写含みの記述)について、再度考察する。(「記述」)系列が半数近いのは確かである。しかし、(描写含みの記述)の(描写)機能に着目すると、(描写)と(描写含みの記述)を合わせた出現割合は61.6%(479文)であり、これは(「記述」)系列の文の出現割合よりも高い。(「記述」)系列の文についても、内訳は(「記述」)が27.0%(210文)、(描写含みの記述)が24.6%(191文)と大きな差は見られない。『源氏物語』に出現する全ての文の種類の中で(描写)の出現割合が一位であることも合わせて、文の種類から指摘できる『源氏物語』の表現特性をまとめておく。
『源氏物語』は、(描写)(「記述」)(描写含みの記述)を含む対象表現によって、主に作品世界の事物・事態を書いている。『源氏物語』は一代記的性格を持ち、(描写)によって描かれる場面と場面を、 (「記述」)系列の文がつなげることで物語が進行していく。ただし、その(「記述」)系列の文においても具体性を志向するために半数近くに(描写)機能が含まれ、(描写)と(描写含みの記述)を合わせると六割近い出現割合を占める。これらのことから、『源氏物語』は描写表現が多用される作品だといえる。
本項では『源氏物語』三巻に出現する事物描写を取り上げて、考察していく。
まず、事物描写の出現割合を示す。今回は事物描写を(事物描写)と(風景描写)の二項目で分析した。(事物描写)と(風景描写)を合わせた事物描写の『源氏物語』三巻における出現割合は16.6%(129文)であった。
次に、この129文の中から「純粋な事物描写の文」を取り上げる。「純粋な事物描写の文」とは事物を描写する機能のみを持った文である。分析項目に当てはめると、《単機能文》(描写)に属して(事物描写)もしくは(風景描写)の働きのみを持つ文のことである。以下に例文を挙げて説明する。
明けゆく空はいといたう霞みて、山の鳥どもそこはかとなう囀りあひたり。名も知らぬ木草の花どもいろいろに散りまじり、錦を敷けると見ゆるに、鹿のたたずみ歩くも、めづらしく見たまふに、悩ましさも紛れ果てぬ。
(『源氏物語』「若紫」)
源氏が尼君に紫の上を所望して断られた後、勤行を終えて戻ってきた僧都と明け方に対座している場面である。一文目が(描写)―(風景描写)、二文目が(描写)―(風景描写/心理描写)である。どちらも(描写)である点は共通しているが、一文目は「純粋な事物描写の文」で、二文目はそうではない。
この例では書かれていないが、源氏は僧都に招かれてその坊を訪れており、《舞台》は《北山の僧都の坊》として既に設定されている。また、例文の直前に「暁方になりにければ」という時間の設定もされている。ここでは源氏と僧都の対座が場面化されていると考える。一文目、二文目共に下線部が北山の風景描写である。一文目「明けゆく空は~囀りあひたり」では、明けゆく北山の風景が空の霞む様子と山鳥たちの鳴き声によって視覚的・聴覚的に描写されている。二文目の下線部「名も知らぬ~たたずみ歩くも」も、同様に北山の風景をそこに生きる動植物たちの姿から描き出している。また、二文目の「見たまふ」という知覚動詞が、この風景を捉える視座が源氏にあることを示して、描写性を高めている。例文に挙げた内、一文目と二文目の下線部までは風景描写の機能を持っている。しかし、二文目の下線部以降「めづらしく見たまふに、悩ましさも紛れ果てぬ」の部分は、北山の風景を見ることで心洗われる源氏の心理を描いている。つまり、二文目は風景と心理の両方を描写している。
一文目のように風景描写(あるいは事物描写)の機能だけを持った文を、本稿では「純粋な事物描写の文」と呼称している。「純粋な事物描写の文」を取り上げるのは、事物描写の機能だけを持つ文が文中でどのように用いられているのかを見出すためである。『源氏物語』三巻における「純粋な事物描写の文」の出現割合は、(事物描写)3.5%(27文)、(風景描写)0.6%(5文)、合計で4.1%(32文)であった。
また、「純粋な事物描写の文」の他にも、行動・心理・談話・人物をそれぞれのみを描写した、「純粋な描写の文」が存在する。これら「純粋な描写の文」の合計は156文であった。次のグラフは、『源氏物語』三巻における「純粋な描写の文」全体における各描写の出現割合である。
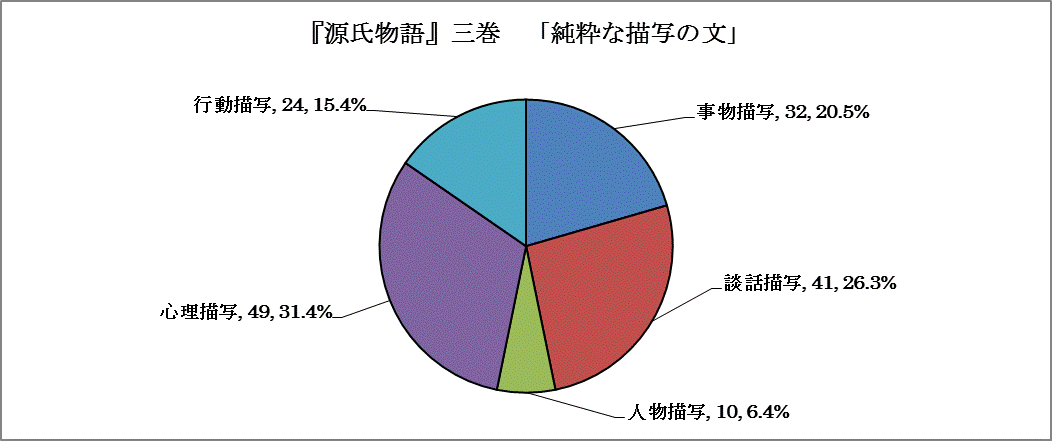
この中での「純粋な事物描写の文」の出現割合も挙げる。出現割合は(事物描写)が17.3%、(風景描写)が3.2%、合計で20.5%であった。「純粋な事物描写の文」は「純粋な描写の文」の中で第3位の出現割合であった。「純粋な描写の文」の内、出現割合が最も多いのは「純粋な心理描写の文」の31.4%(49文)、続いて「純粋な談話描写の文」の26.3%(41文)であった。
『源氏物語』三巻における「純粋な事物描写の文」には二種類の描写対象に集中していた。一つは《舞台》設定のための描写、もう一つは書き文字の描写である。この二種類に含まれない事物描写についてはここでは措いておく。
まず、《舞台》設定のための描写について述べる。《舞台》設定の事物描写として、以下の例が挙げられる。以下の例(1)~(3)では「純粋な事物描写の文」にのみ下線を付ける。
(1)おはします殿の東の廂、東向きに倚子立てて、冠者の御座、引入れの大臣の御座御前にあり。
(『源氏物語』「桐壷」)
「桐壷」巻で源氏の元服の儀を記した部分。儀式の行われる《舞台》が設定されている。(宮中)は《舞台》になるときでも描写されないが、例では珍しく(宮中)の様子が描かれる。ここで《舞台》の設定は儀式の説明になっている。元服の儀という日常とは異なる出来事が行なわれるので、普段は描かれない場所でも改めて《舞台》として設定されたと考えられる。儀式に関係する事物の位置以外の《舞台》の描写がないことからも、日常とは異なる部分のみを描いていることがわかる。
(2)げに、いと心ことによしありて同じ木草をも植ゑなしたまへり。月もなきころなれば、遣水に篝火ともし、灯籠などもまゐりたり。南面いと清げにしつらひたまへり。そらだきもの心にくくかをり出で、名香の香など匂ひ満ちたるに、君の御追風いとことなれば、内の人々も心づかひすべかめり。
(『源氏物語』「若紫」)
「若紫」巻で僧都に招待された源氏が(僧都の坊)を訪れる場面。《舞台》となる(僧都の坊)が事物描写によって設定されている。闇夜の中で「篝火」が「遣水」に映える視覚的な情景と迎え入れられた部屋の「名香のかをり」といった嗅覚による《舞台》設定がなされている。
(3)造れるさま木深く、いたき所まさりて見どころある住まひなり。海のつらはいかめしうおもしろく、これは心細く住みたるさま、ここにゐて思ひのこすことはあらじとすらむと思しやらるるにものあはれなり。三昧堂近くて、鐘の声松風に響きあひてもの悲しう、巌に生ひたる松の根ざしも心ばへあるさまなり。前栽どもに虫の声を尽くしたり。ここかしこのありさまなど御覧ず。むすめ住ませたる方は心ことに磨きて、月入れたる真木の戸口けしきことにおし開けたり。
(『源氏物語』「明石」)
『明石』巻で、源氏が明石の君のもとを初めて訪れる場面、明石の君が住まう(岡辺の宿)が《舞台》として描写される。「造れるさま~住まひなり」と岡辺の宿全体の描写がされ、「鐘の声」や「虫の声」といった聴覚による《舞台》設定も行なわれる。
また、(2)と(3)の《舞台》設定に共通する点として、源氏の行動に沿って《舞台》設定の事物が描かれている点が挙げられる。(2)では、坊の外から「南面」に入るまでが、順番に描写されている。(3)でも、まずは岡辺の宿の全体の印象から描かれ、源氏が「ここかしこのありさまなど」を見回した後に「むすめ住まわせたる方」が描写され、源氏がそこへ入っていくことがわかる。(2)と(3)では《舞台》設定がそのまま源氏の行動と繋がっている。このような《舞台》設定がなされると源氏の行動を一々描く必要がなく、《舞台》設定からそのまま屋内の対話場面に移ることができる。特に、事物描写と心理描写のみで屋内に入って行く(2)の《舞台》設定にはこの特徴が顕著に表れている。このような《舞台》設定がなされた理由として、作者が人物の行動描写を避けた、あるいは『源氏物語』当時の読者層にとっては《舞台》設定のみで人物の行動までが読み取れたという仮説が成り立つ。この仮説の検証は今後の課題となる。
《舞台》の設定が事物描写によってなされる例を挙げて、考察した。『源氏物語』における《舞台》と場面の関係については次項で触れる。
次に、書き文字の描写について述べていく。以下は、北山での加持から帰京した源氏が、帰京翌日に北山の尼君と紫の上に送った手紙の文面である。
尼上には、
もて離れたりし御気色のつつましさに、思ひたまふるさまをもえあらはしはてはべらずなりにしをなむ。かぽかり聞こゆるにても、おしなべたらぬ志のほどを御覧じ知らば、いかにうれしう。
などあり。中に小さくひき結びて、
「面影は身をも離れず山桜心のかぎりとめて来しかど
夜の間の風もうしろめたくなむ」とあり。
(『源氏物語』「若紫」)
文字によって書かれた手紙や和歌は文字によって書き写すことができるので、描写の容易な題材である。さらに、書き写すということは描写対象の再現度も高く、描写性は高い。ここでも源氏が尼君に宛てた手紙の文面と紫の上に宛てた和歌の言葉が再現されている。『源氏物語』における書き文字の代表が手紙や和歌である。そのため、手紙や和歌が事物対象として繰り返し現れたと考えられる。ただし、手紙や和歌が「純粋な事物描写の文」として現れた理由については今回の分析結果からは判明しなかった。
以上、本項で考察してきたことをまとめる。『源氏物語』三巻における事物描写の出現割合は16.6%、「純粋な事物描写の文」の出現割合は4.1%である。「純粋な事物描写の文」は、《舞台》と書き文字の描写の二種類に集中していた。
本項では『源氏物語』三巻において、どのように場面が設定されているのか考察していく。
まず、『源氏物語』三巻において場面が設定されたと判断した部分を挙げていく。
「桐壺」巻では、野分の後に桐壺の更衣の死を悼む場面が大きく一つの場面を成していると考えられる。さらに、この大きな場面は靭負の命婦が桐壺の母を弔問する場面とその直後帰参した命婦と帝が語らう場面とに分けられる。「桐壺」巻はこの野分の段を除いて、出来事は主に(「記述」)系列の文によって書かれる傾向にある。
「桐壺」巻では、光源氏の出生以前から婿入り後まで、実時間にして15年以上に及ぶ長期間について記している。このような長期間を書くためには、(「記述」)系列の文が相応しいことは既に述べた。もしも、作中の出来事を(描写)によって描くならば、源氏の子供時代を描くだけでも数巻を要すると考えられる。このような書き方からは、『源氏物語』において光源氏の生い立ちに関する情報は必須であっても、その子供時代を詳細に描くことには主眼が置かれていないという指摘ができる。
「若紫」巻では大まかに三場面が見出せる。北山で若紫と邂逅する場面、北山から帰京した尼君ら訪ねる場面、尼君死去を知った後から若紫を二条邸に迎える場面である。これらの大きな場面の合間に藤壺との密通や尼君との手紙のやり取りが記されている。この三場面の中でも、北山の場面と尼君死去後の場面については、いくつかの小さな場面に分けることができる。
「明石」巻でも大まかに三場面を見いだせる。明石に移ってから入道と語る場面、明石の君と初めて対面する場面、明石の君と別れを惜しむ場面である。これらの大きな場面の前後に、須磨での嵐や桐壷院との夢での再会、明石を去る部分などが記されている。
さて、『源氏物語』三巻からは以上のような場面が見出されるが、この場面はどのようにして設定されているのか。その設定の方法として、場面を立ち上げるときには事物描写による《舞台》設定が用いられる。《舞台》設定の事物描写については、前項に例(1)~(3)を挙げているのでここには再掲しない。《舞台》設定が場面の立ち上げに用いられる際に共通する点として、場面展開部の前に描かれることと新規の場所のみが描かれることの二点が挙げられる。ここで、新規の場所とは作中で初めて登場した場所で、かつ『源氏物語』当時の読者にとっても馴染みの薄い場所のことである。
まず、共通点のうち一点目について述べる。上に挙げた三巻の場面の内、《舞台》設定がある上で場面が展開する例として、「桐壷」巻の靫負の命婦弔問の場面、「若紫」巻の僧都の坊を訪れる場面と京都の紫の上の邸を訪れる場面、「明石」巻の明石の君を初めて訪れる場面が挙げられる。これらの場面での《舞台》は、場面の中心となる人物の対話の前に設定されている。そして、基本的には人物が対話する場面の途中で《舞台》設定が追加されることはない。
もちろん、場面展開部の合間にも事物描写はある。そのような事物描写の例を以下に挙げる。
波の声、秋の風にはなほ響きことなり。塩焼く煙かすかにたなびきて、とり集めたる所のさまなり。
このたびは立ちわかるとも藻塩やく煙は同じかたになびかむ
とのたまへば、
かきつめて海人のたく藻の思ひにもいまはかひなきうらみだにせじ
あはれにうち泣きて、言少ななるものから、さるべきふしの御答へなど浅からず聞こゆ。
(『源氏物語』「明石」)
源氏が明石の君と別れを惜しむ場面である。下線部の事物描写は、岡辺の宿から捉えられる風景を描いており、これが続く歌に取り入れられる。
霰降り荒れて、すごき夜のさまなり。「いかで、かう人少なに心細うて、過ぐしたまふらむ」とうち泣いたまひて、いと見棄てがたきほどなれば、「御格子まゐりね。もの恐ろしき夜のさまなめるを。宿直人にてはべらむ。人々近うさぶらはれよかし」とて、いと馴れ顔に御帳の内に入りたまへば、あやしう思ひの外にもとあきれて、誰も誰もゐたり。乳母は、うしろめたなうわりなしと思へど、荒ましう聞こえ騷ぐべきほどならねば、うち嘆きつつゐたり。若君は、いと恐ろしう、いかならんとわななかれて、いとうつくしき御肌つきも、そぞろ寒げに思したるを、らうたくおぼえて、単衣ばかりを押しくくみて、わが御心地も、かつはうたておぼえたまへど、あはれにうち語らひたまひて、「いざたまへよ。をかしき絵など多く、雛遊びなどする所に」と、心につくべきことをのたまふけはひのいとなつかしきを、幼き心地にも、いといたうも怖ぢず、さすがにむつかしう寝も入らずおぼえて、身じろき臥したまへり。
夜一夜風吹き荒るるに、「げにかうおはせざらましかば、いかに心細からまし。同じくはよろしきほどにおはしまさましかば」とささめきあへり。乳母は、うしろめたさに、いと近うさぶらふ。風すこし吹きやみたるに、夜深う出でたまふも事あり顔なりや。
(『源氏物語』「若紫」。太字は引用者。)
尼君死去の後、源氏が紫の上の邸を弔問し、一夜を明かす場面である。下線部の事物描写は、荒れる天気が次第に収まる様子を描くことで時間の進行を示している。場面の合間にある事物描写を二例挙げたが、どちらも《舞台》そのものの描写ではなく、別の働きを持っていることが分かる。
共通点のうちの二点目として、《舞台》は新規の場所のみが描かれるということを挙げた。これは《舞台》設定のない場面が、作中で既に《舞台》設定がされている場合か、あるいは読者にとって馴染み深い《舞台》である場合に限られることからわかる。上に挙げた場面例でも、源氏が入道と対座した海辺の家は、源氏が明石に移動した際に描かれるため《舞台》設定なく場面が展開する。また、宮中など当時の読者に馴染みの深いと考えられる《舞台》も設定されることなく場面が展開する。
先に、源氏の元服の儀に関しての《舞台》設定も、日常とは異なる儀式の位置取りだけが描写されていることを挙げた。これも《舞台》設定において新規性が重視されていることを示している。
では、《舞台》設定がない場合にはどのような基準によって《舞台》が判定できるのか。『源氏物語』三巻では、そこに住む人物が《舞台》を判定する基準になる。例えば、「明石」巻であれば明石の君が登場すれば《舞台》は(岡辺の家)であることが判明する。人物が舞台判定の基準になる理由は、『源氏物語』で描かれるような人物、特に女性は自分の住処から移動するということが通常なかったからである。そのため、その人物が住む場所を一度指定すれば、移動がない限り再度《舞台》を指定する必要はない。源氏と対座する人物が判明すれば、その《舞台》が判明するのである。
《舞台》設定を特に場面構成と絡めて見てきたが、『源氏物語』三巻の《舞台》設定には描写対象について特徴的な点がある。『源氏物語』三巻において《舞台》設定の描写対象となるのは屋外だけであり、基本的に屋内の様子や調度品については描写されない。前項に挙げた例(1)~(3)にしても、主に庭や屋敷の雰囲気といったものが描写されているだけである。そして、この後の場面展開において《舞台》設定の描写がないことは既に述べた。もちろん、御簾・格子・几帳といった調度品の存在は場面の展開部でも示される。例えば、先に挙げた例の太字部分「『御格子まゐりね。もの恐ろしき夜のさまなめるを。宿直人にてはべらむ。人々近うさぶらはれよかし』とて、いと馴れ顔に御帳の内に入りたまへば」からは、「御格子」や「御帳」といった調度品の存在が読み取れる。しかし、ここではその存在が分かる程度の書き方しかされておらず、描写意識が働いているとはいい難い。ここでは、屋内の様子や調度品が存在を示す程度の書き方しかされない理由として、上でも述べた新規性を挙げる。例文の「御格子」や「御帳」は《舞台》ごとに大きく異なるような類の事物ではなく、当時の読者にとっても日常的なものであったと考えられる。そのために描写の必要性が薄かったといえる。
あるいは、場面展開の重点は人物同士の対話にあって、室内の様子を描くということは特に意識されていなかったとも考えられる。これは、《舞台》設定は場面の雰囲気を作り上げるために重要な役割を果たすが、場面展開部に至れば人物の対話を描くことに集中するということである。つまり、『源氏物語』では事物よりも人物の対話が優先されていたということである。ただし、《舞台》設定が場面展開部の前にあることと室内・調度品の描写がないことだけでは、このように断言することはできない。人物の対話が重要視されていたことを示す資料が必要になる。
ここまで、『源氏物語』三巻における《舞台》設定の特徴について述べてきた。最後に場面として確立していないが、限定化がなされている部分について述べておく。このような部分は、(「記述」)的に出来事を進展させていく中に時間や場所を限定できる部分がある。そして、その部分によって場面化しているように捉えることもできる。しかし、それぞれの限定に連続性が見られないために、場面として確立しているとはいい難いのである。このような限定性を付与する描写として最も大きな効果があるのは(談話描写)だと考えられる。何度も述べている通り、談話は描写対象の中で最も現実の時間の流れを想定し易い。対して、例えば心理の描写は時間概念との関わりが薄く、心理の動きに要した時間は想定し難い。
以上、本項で考察してきたことをまとめる。『源氏物語』三巻において、場面展開に事物描写を用いた《舞台》設定が必ずあるわけではなない。《舞台》が描写されるときには新規性が重視され、また《舞台》設定は場面展開部の前になされる。また、《舞台》として描かれるのは屋外だけであり、屋内や調度品が描写されることない。
ここまで『源氏物語』三巻について、分析結果から観点に沿った考察を行い、特に事物描写に関した表現特性を見いだしてきた。各観点で見出した表現特性については各項にまとめた。『源氏物語』三巻では「純粋な事物描写の文」が《舞台》設定と手紙に集中していたが、今後はそこに含まれない「純粋な事物描写の文」が描き出すものを取り上げて、考察する。
→ページのトップへ戻る
本節では『日本永代蔵』の分析結果から観点に沿った考察を行い、作品の表現特性を明らかにする。『日本永代蔵』三巻とは『永代蔵』の一巻から三巻をまとめて扱う意味で用いる。
考察の前に分析に関する諸情報を挙げておく。『日本永代蔵』について、今回の研究で対象とした三巻の総文数は362文であった。各巻の文数は第一巻125文、第二巻127文、第三巻110文であった。各章の文数は一巻の一「初午は乗って来る仕合せ」33文、一巻の二「二代目に破る扇の風」10文、一巻の三「浪風静かに神通丸」31文、一巻の四「昔は掛算今は当座銀」22文、一巻の五「世は欲の入札に仕合せ」29文、二巻の一「世界の借屋大将」40文、二巻の二「怪我の冬神馬」26文、二巻の三「才覚を笠に着る大黒」20文、二巻の四「天狗は家名風車」12文、二巻の五「舟人馬方鐙屋の庭」29文、三巻の一「煎じやう常とはかはる問薬」14文、三巻の二「国に移して風呂釜の大臣」17文、三巻の三「世は抜取りの観音の眼」32文、三巻の四「高野山借銭塚の施主」21文、三巻の五「紙子身代の破れ畤」26文であった。
→ページのトップへ戻る
本項では《文の機能》に応じた文の種類について考察していく。
次ページのグラフは、『日本永代蔵』三巻における文の種類ごとの出現数である。
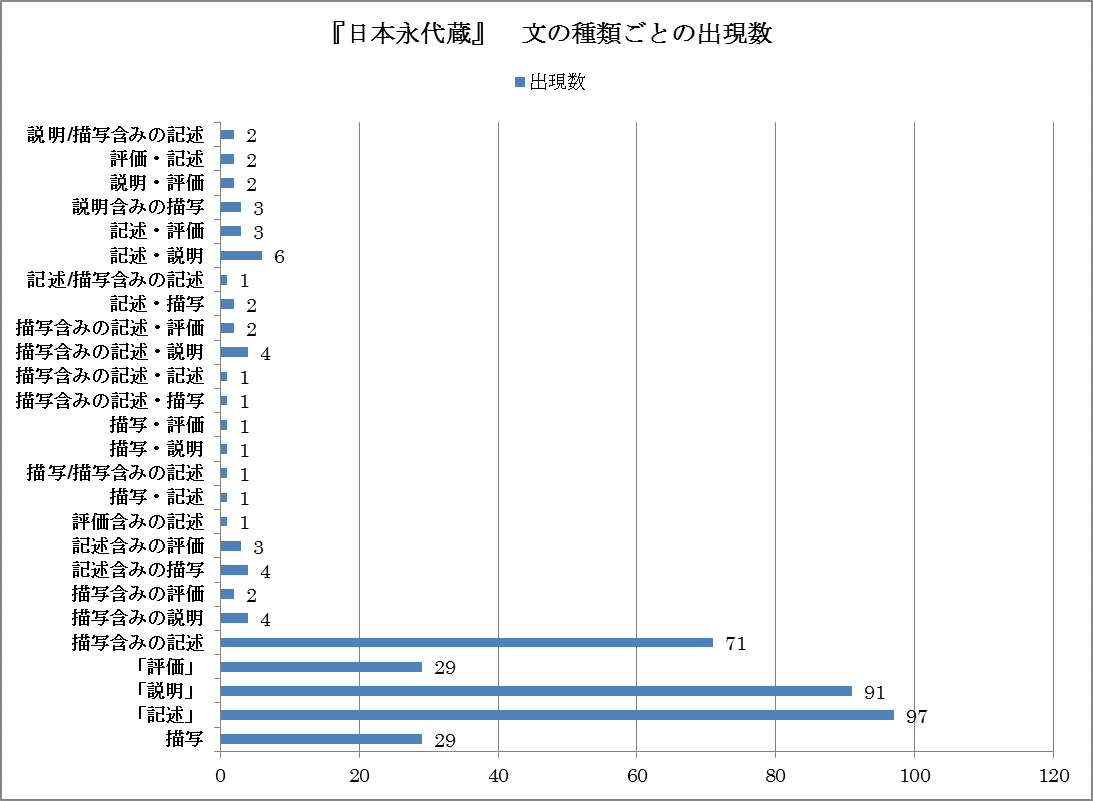
『日本永代蔵』三巻に出現した文の種類は計26種類である。出現割合は、(記述)が26.6%(97文)で出現割合第1位、(「説明」)が25.0%(91文)で出現割合第2位、(描写含みの記述)が19.5%(71文)で出現割合第3位である。これら3種の文が『日本永代蔵』三巻で占める割合は71.2%(259文)である。
対象表現に注目すると、純粋な対象表現文の全体割合は57.5%(208文)で、全体の六割を超えている。しかし、同じ純粋な対象表現文について『源氏物語』90.2%(702文)、『三四郎』97.0%(5637文)と、二作品とも全体の九割以上である。『永代蔵』の対象表現の割合は、他の二作品と比較して三分の二以下である。
また、(説明)が出現割合第2位、(評価)が8.0%(29文)で、出現割合は(描写)と同列の第4位というように、叙述者表現の出現割合が他の二作品と比較して高いことも特徴である。叙述者表現では語り手が作品世界の外側に身を置き、しかも語り手自身の思考・価値判断について述べる。『永代蔵』の叙述者表現とは以下のようなものである。
美目は果報のひとつと、これを聞きつたへて、随分女子を大事に生育てけれども、安倍川の遊女はしらず、つひに好き女見た事なし。とかく美形はないものに極まれり。これを思ふに、唐土?居士が娘の霊照女は、悪女なるべし。美形ならば、よもや箙は売らせてはおかじ。
(『永代蔵』三巻の五「紙子身代の破れ畤」。下線部が「説明」。)
ここでは、主人公・忠助が孝行娘の美貌によって没落生活から抜け出したという結末を受けて、語り手が皮肉交じりの結論を述べている。注目したいのは、語り手が作品世界の出来事を発想の起点にしてはいるものの、内容自体は自分の思考に限定して語っている点である。視座だけではなく内容からも、既に語り手が作品世界と距離をおいていることが読み取れる。視座と内容、二つの面で作品世界から距離を置くような『永代蔵』の語りはより客観的に作品世界を捉えているといえる。
『永代蔵』の叙述者表現と『三四郎』の叙述者表現を比較すると、その差異はより明確になる。
すると今度は与次郎の方から、三四郎に向って、
「どうも妙な顔だな。如何にも生活に疲れている様な顔だ。世紀末の顔だ」と批評し出した。三四郎は、この批評に対しても依然として、
「そう云う訳でもないが……」を繰返していた。三四郎は世紀末などと云う言葉を聞いて嬉しがる程に、まだ人工的の空気に触れていなかった。またこれを興味ある玩具として使用し得る程に、ある社会の消息に通じていなかった。ただ生活に疲れているという句が少し気に入った。成程疲れ出した様でもある。三四郎は下痢の為めばかりとは思わなかった。けれども大いに疲れた顔を標榜するほど、人生観のハイカラでもなかった。
(『三四郎』4。下線部が「説明」。)
ここでは、大学の授業に嫌気がさし始めた三四郎を、与次郎が「世紀末」という言葉を用いて評している。『三四郎』の場合は語り手が自身の思考を語る部分においても、作品世界の出来事に沿った内容に収まっている。この場合は、三四郎の煮え切らない態度について彼の性格を基に説明している。この時点では確かに視座は語り手にあり、語り手自身の思考について語っているものの、内容は三四郎の人となりの説明であって作品世界と距離を置いているとは捉え難い。『永代蔵』と『三四郎』の叙述者表現を比較すると、『永代蔵』の方がより客観的であることが分かる。『永代蔵』の叙述者表現は、『永代蔵』の客観性を強める働きをしているといえる。
さて、叙述者表現の出現割合が高いということは、従来から指摘される『永代蔵』の教訓書的性格を表している。教訓書において筆者の思想や信条を語る部分は必須である。教訓書では筆者が的確な教訓を述べることが作品の中心的要素だからである。『永代蔵』も、西鶴が題材となった出来事に的確な指摘を付けることで教訓書としての性格を持った。筆者が教訓を垂れる部分は叙述者表現となって、作品世界と距離を置かざるを得ない。『永代蔵』が教訓書的性格を持つことは、副題やその受容のされ方からも分かるが、文の種類からもその性格が読み取れる。ただし、『永代蔵』三巻の中には、一見西鶴による教訓が書かれていないように見える章段もある。しかし、そもそも致富譚や没落譚を語ること自体が、致富への方法や没落回避の心がけを示しているともとれる。そのため、必ずしも西鶴自身の指摘を入れる必要もない。また、西鶴が『永代蔵』において敢えて物語形式を用いていることを考えれば、物語の完成度を優先して、直接的に教訓を垂れない場合も考えられる。一巻の二「二代目に破る扇の風」はまさにこのような章段である。この章段には叙述者表現がなく、ただ始末物の一代目が築いた財産を、二代目が茶屋遊びによって食いつぶしてしまうことが語られる。たった一度、遊郭を訪れたことで没落してしまう急転直下の様は、それだけで読者に教訓めいたものを感じ取らせる。
さて、『永代蔵』が確かに教訓書的性格を持つことを押さえた上で、しかし、最も出現割合が高いのは(「記述」)の26.6%(97文)である。さらに、(描写含みの記述)と合わせて(「記述」)系列の割合を見た場合には、46.2%(168文)とおよそ半数近い出現割合である。対して、同じ対象表現である(描写)の出現割合は(「評価」)と同列の第4位であるものの、実際には十五章段に分散して出現するため、中には全く(描写)が出現しない章段もある。純粋な対象表現文が六割近いことも併せて考えると、『永代蔵』は作品世界を書くという意識を持ち、特に出来事の進行に重きをおいていると指摘できる。この理由を次のように考えた。
『永代蔵』では主に一人の人物の致富か没落の様が書かれる。一般的に、致富や没落は一定の期間を必要とする出来事である。必然的に(「記述」)系列の文との相性が良くなる。特に没落譚では、一代目の成功を踏まえて、二代目の没落の様が記されることもあり、その場合は物語内の期間がより長くなる。例えば、一巻の二「二代目に破る扇の風」はこの二代目没落譚に該当する。『永代蔵』は一定の物語内期間が必要な題材を選択していながら、その形式として短編といえる長さを採用している。短い文量で一定の期間を記すには、(「記述」)系列の文が適している。また、『永代蔵』にも『源氏物語』と同様に一代記があることも(「記述」)系列の割合が高くなることの一因である。一代記に(「記述」)系列の文が適していることは前節で述べた。
以上、文の種類から指摘できる『日本永代蔵』の表現特性をまとめておく。『永代蔵』は叙述者表現の割合が他の対象作品よりも高く、これは『永代蔵』の客観性を強める働きをしている。また『永代蔵』の教訓書的性格も表している。しかし、対象表現も六割近く、作品世界を書くという意識も認められる。対象表現のほとんどが(「記述」)系列の文であることから、特に出来事を進行させていくことが重視されていると理解できる。これは短い文量の中で一定以上の期間を記すためには、(「記述」)系列の文が適しているからであった。
ただし、『永代蔵』の場合、各章段ごとに一代記であったり、舞台紹介であったりと特色があるので全体傾向として指摘できることは少ない。描写表現も各章段において必ずしも出現するわけではなく、各章段の特色とあわせて考察する必要がある。
本項では、『日本永代蔵』三巻に出現する事物描写を取り上げて、考察していく。
まず、事物描写の出現割合を示す。 (事物描写)と(風景描写)を合わせた事物描写の、『日本永代蔵』三巻における出現割合は17.1%(62文)であった。
次に、この62文の中から「純粋な事物描写の文」を取り上げる。『日本永代蔵』三巻における「純粋な事物描写の文」の出現割合は、(事物描写)は0.6%(2文)、(風景描写)は0.3%(1文)、合計で0.8%(3文)であった。
また、「純粋な描写の文」の合計は14文であった。次のグラフは、『日本永代蔵』三巻における「純粋な描写の文」全体における各描写の出現割合である。
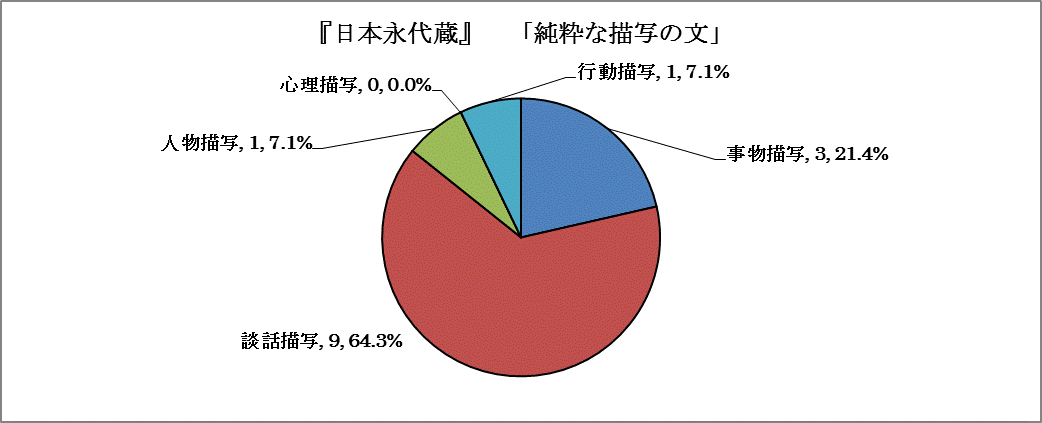
「純粋な事物描写の文」は(事物描写)が14.3%、(風景描写)が7.1%、合計で21.4%であった。「純粋な事物描写の文」は、「純粋な描写の文」の中で第2位の出現割合であった。「純粋な描写の文」の内、出現割合が最も多いのは「純粋な談話描写の文」の64.3%(9文)、第3位は同率で「純粋な行動描写の文」「純粋な人物描写の文」の7.1%(1文)であった。
『日本永代蔵』三巻において「純粋な心理描写の文」が一つも出現しなかったのは、作品の特徴として挙げられる。「純粋な心理描写の文」が出現しないということは、登場人物の思考や感情だけを描くことがないということである。つまり、登場人物の心理が描かれていても、それは必ず行動・談話・事物・人物といった具体的対象物とともに描かれるということである。ここから、『日本永代蔵』の抽象的対象物を描こうとしない表現特性が指摘できる。
さらに『源氏物語』では「純粋な心理描写の文」の出現割合が最も高かったことや『日本永代蔵』が現実の利益を追求する平民階層に向けて書かれたことを踏まえると、この表現特性は書き手や読み手の性質の違いを表した部分ともいえる。ただし、ここでは資料が不足しているのでこれ以上の考察はできない。書き手や読み手の性質差が文章表現に与える影響については今後の課題とする。
『永代蔵』三巻における「純粋な事物描写の文」は3文なので、ここにその全てを挙げる。以下の例(1)~(3)では「純粋な事物描写の文」にのみ下線を付ける。
(1)十二月二十八日の曙、いそぎて荷ひつれ、藤屋見世にならべ、「うけ取り給へ」といふ。餅は搗きたての好もしく、春めきて見えける。那は聞かぬ顔して十露盤置きしに、餅屋は時分柄にひまを惜しみ、幾度か断りて、才覚らしき若い者、杜斤の目りんと請け取つてかへしぬ。
(『永代蔵』二巻の一「世界の借屋大将」)
ここでは主人公・藤一が正月の餅を餅屋につかせて配達させた時の出来事が記されている。下線部が(描写)―(事物描写)である。下線部は餅屋が持ってきた餅の好ましげな様子を描写している。餅だけを取り上げて描写することは餅の存在を強調する。しかし、藤一はこの餅をすぐには受け取らずに、時間を置くことで目方を減らして料金を安くしようと目論んでいた。描写による餅の強調が、却って餅を無視する藤一の行為を際立たせ、彼の始末ぶりを描き出すことに繋がっている。描写妥当性のある効果的な事物描写といえる。
下線部の視点設定について述べる。下線部末の「見えける」は知覚動詞であり、下線部の事物描写の視点人物として藤一が設定されている可能性も考えられる。しかし、前後の文は「記述」の文で、語り手の視点から客観的に語られている。さらに、下線部後続の文で「那は聞かぬ顔して」と藤一を見られる側の人物として書いていることから、この時点の視点人物が語り手であることが分かる。これを踏まえると、下線部の描写文のみ藤一を視点人物として設定しているとは考え難く、下線部も語り手による客観視点からの描写だと判断できる。
(2)諸人浪の声をそろへ、笛・太鼓・鉦の拍子をとつて、大綱つけて轆轤にまきて礒に引きあげけるに、その丈三十三尋二尺六寸、千味といへる大鯨、前代の見はじめ、七郷の賑ひ、竃の煙立ちつづき、油をしぼりて千樽のかぎりもなく、その身・その皮・ひれまで捨る所なく、長者になるはこれなり。切り重ねし有様は、山なき浦に珍しく、雪の富士、紅葉の高雄ここにうつしぬ。いつとても捨て置く骨を源内もらひ置きて、これをはたかせ、又油をとりけるに、思ひの外なる徳より分限になり、すゑ/゛\の人のため大分の事なるを、今まで気のつかぬこそおろかなれ。
(『永代蔵』二巻の四「天狗は家名風車」)
ここでは主人公・源内を中心に大鯨を捕獲した出来事が記されている。下線部が(描写)―(風景描写)である。下線部は、引き上げた大鯨を切り重ねた磯の様子を比喩を用いて描写している。前文の「その丈三十三尋二尺六寸~ひれまで捨る所なく」で鯨の規格外の大きさが示される。その規格外の大きさは切り身になっても同様であり、切り身が置かれた磯の風景を描写することによってそれを強調する。
(3)そののち菊屋申すは、「この古き戸帳を申しうけ、京の三十三所の観音へかけたき」といへば、「安き事」とてつかはしけるを、残らず取りてかへる。この唐織、申すもおろか、時代わたりの柿地の小釣、浅黄地の花兎、紺地の雲鳳、その外も模様かはりぬ。これみな大事の茶入れの袋、表具切に売りける程に、大分の金銀とりて家栄え、五百貫目と脇から指図違ひなし。
(『永代蔵』三巻の三「世は抜取りの観音の眼」)
ここでは主人公・善蔵が長谷寺の仏前に掛かっていた戸帳を騙し取り、それを商売品として売り払ったことが記されている。下線部が(描写)―(事物描写)である。下線部は長谷寺から騙し取った戸帳の模様を描写し、その価値を示している。戸帳の価値を示すことでそれを商品にする妥当性を示している。また、この描写の「時代わたりの柿地の小釣、浅黄地の花兎、紺地の雲鳳」の部分は前章で挙げた西鶴文体の特徴の一つである列挙の方法に当たる。
上に挙げた例では、事物描写は全て語り手の客観的な視点から描かれている。これは『永代蔵』三巻における「純粋な事物描写の文」には「視点人物造型」の役割を担った事物描写がないことを意味する。また、『永代蔵』が客観性の強い作品であることを前項で示した。ここで挙げた「純粋な事物描写の文」は客観視点に立った描写をすることで、『永代蔵』の客観性の強さを補強する一因となっている。
以上、本項で考察してきたことをまとめる。『永代蔵』三巻において、事物描写は全体の17.1%で、「純粋な事物描写の文」は全体の0.8%である。例に挙げた「純粋な事物描写の文」各々は様々な働きを示し、また『永代蔵』の客観性を補強する一因となっている。ただし、全体における出現割合が極端に低いために『永代蔵』の表現特性を示すとまではいえない。また、「純粋な心理描写の文」が出現しないことは『永代蔵』の表現特性の一つとして挙げられる。
本項では、『日本永代蔵』三巻において、どのように場面が設定されているのか考察していく。
まず、『永代蔵』三巻において場面が設定されたと判断した部分を挙げる。ただし、『永代蔵』は短編小説集であること、先にも挙げように(描写)の出現割合が低いことからも分かるように、場面が設定され難い作品である。また、場面として設定されていると判断できても連続性がなく、他の二作品ほど場面が確立しているとはいい難い。これらを踏まえた上で『永代蔵』三巻で場面と判断した部分を挙げる。
一巻の二「二代目に破る扇の風」で扇屋が島原遊郭を訪れる場面、二巻の一「世界の借屋大将」で藤一が若者たちに教えを授ける場面、二巻の三「才覚を笠に着る大黒」で新六が東海寺で一夜を過ごした場面、三巻の五「紙子身代の破れ畤」で忠助が年の暮れに近所の者と年齢の穿鑿をする場面が挙げられる。
これらの場面には必ず人物同士の対話があるが、それを中心に場面が構成されているとまではいえない。しかし、やはり談話が場面を構成する上で重要な役割を持っている。例えば、二巻の一で藤一が三人の若者と祝儀ものの謂れをこじつけるところや三巻の五で忠助が自分の年齢を現在の困窮した状況に絡めて嘘をつくところなどは、対座する人物の問いによって場面が成り立っている。
『永代蔵』三巻の場面設定の特徴として《舞台》設定の事物描写がほぼなく、その場所の地名が直接示されるという点が挙げられる。『永代蔵』三巻における《舞台》判定は基本的に地名の提示によるといえる。
《舞台》設定の事物描写がない理由として、そもそも事物描写自体が少ないことが挙げられる。また、『永代蔵』が短編小説的形式を用いながら、出来事の展開を優先して一つの場面に固執しないことを第1項で述べた。場面に固執しない以上、場面展開の《舞台》が判明しさえすれば、その《舞台》を具体的に描く必要性は低い。
では、『永代蔵』三巻における詳細な《舞台》設定はどのようになされるのか。以下に例を挙げる。
北国の雪竿、毎年一丈三尺降らぬと云ふ事なし。神無月の初めより山道を埋み、人馬の通ひ絶えて、明けの年の涅槃の頃まではおのづからの精進して、塩鯖売の声をも聞かず、茎桶の用意、焼火をたのしみ、隣むかひも音信不通になりて、半年は何もせずに明暮煎じ茶にしておくりぬ。諸事をかね/゛\たくはへ置きし故に、渇命に及ばざりき。かかる浦山へ馬の背ばかりにて荷物をとらば、万高直にして迷惑すべし。世に船ほど重宝なる物はなし。
ここに坂田の町に、鐙屋といへる大問屋住みけるが、昔は纔かなる人宿せしに、その身才覚にて近年次第に家栄え、諸国の客を引き請け、北の国一番の米の買入れ、惣左衛門といふ名を知らざるはなし。表口三十間・裏行六十五間を家蔵に立てつづけ、台所の有様目を覚ましける。米・味噌出し入れの役人、焼木の請け取り、肴奉行、料理人、椀家具の部屋を預り、菓子の捌き・莨?の役、茶の間の役・湯殿役、又は使ひ番の者も極め、商手代・内証手代、金銀の渡し役・入帳の付け手、諸事一人に一役づつ渡して、物の自由を調へける。亭主、年中桍を着てすこしも腰をのさず、内儀はかるい衣装をして居間をはなれず、朝から晩まで笑ひ顔して、なかなか上方の問屋とは格別、人の機嫌をとり、身過を大事に掛けける。座敷数かぎりもなく、客一人に一間づつ渡しける。都にて蓮葉女といふを、所詞にて杓といへる女三十六七人、下に絹物、上に木綿の立縞を着て、大かた今織の後帯、これにも女頭ありて指図をして、客に一人づつ寝道具あげおろしのために付け置きける。
(『永代蔵』二巻の五「舟人馬方鐙屋の庭」)
二巻の五において北国の生活を記す序説と坂田の町で栄える鐙屋という大問屋の繁盛を記す部分。これはそれぞれ北国と鐙屋の《舞台》設定と捉えられるが、一見して分かる通りに (「記述」)系列の文を用いて書かれている。事物描写は下線部「表口三十間・裏行六十五間を家蔵に立てつづけ、台所の有様目を覚ましける」のみである。つまり、この《舞台》設定でも事物を描くことよりは、その場所における人々の生活や商売の様子を書くことが重視されているのである。二巻の五は、鐙屋の繁盛を起点として西鶴の手代論や問屋論を語る章段である。鐙屋の繁盛する《舞台》の設定は後の手代論や問屋論に繋がる。
また、雪国の生活を記す序説は『永代蔵』当時の主要読者層に対しての《舞台》紹介的な意味合いを持つ。ここから『永代蔵』でも『源氏物語』と同じく、読者に馴染みの深い場所は《舞台》として設定されず、新規性を持った場所のみが書かれると考えられる。これを踏まえると、例えば二巻の一の藤一の家とは、つまりは商人の家であり、その内装をわざわざ描写せずとも当時の読者には想起できたと考えられる。そのために、読者に馴染みの深い場所は短編小説の量的制約から考えても《舞台》を描く必要性がない。対して、北国や二巻の二で記される大津、二巻の四で記される紀の国の大湊は、上方に住む読者にとっては日常的な場所とはいい難く、《舞台》を紹介する必要性がある。また。このように主要読者層と馴染みの薄い場所を《舞台》にすることは、読者の興味を引きつける工夫ともいえる。まとめると、『永代蔵』三巻においても《舞台》設定において新規性が重視されていたといえる。
先に『永代蔵』では場面が確立し難いことを述べた。場面として成立していないが限定化がなされている部分については、前節でも述べたように一部分だけの限定で連続性がないことが原因である。しかし、より具体的に描かれながらも場面と判断しなかった部分もある。以下に、その部分を挙げて考察する。
「物には時節、花の咲き散り、人問の生死、なげくべき事にあらず。しかれども、命は養生の一大事なるに、毒魚と知りながら鰒汁、これに風味かはらずして藻魚といふもの、何の気遣ひなかりき。女房は縁組のはじめより祖母になるまで手池にせしを、無分別に水をへらしぬ。この貧取りかへす事なく、一生損にたつなれば、人たしなむべきはこれ、長命はその心にあり」と、堅作りの親仁、若い者どもに異見を申せし。「むかし難波の今橋筋に、しわき名をとりて分限なる人、その身一代独り暮して、始末からの食養生、残る所なし。この人も男ざかりに、うき世を何の面白い事もなく果てられ、その跡の金銀御寺へのあがり物、四十八夜を申してから役に立たぬ事なり。されども、年久しく内蔵に隠れ、世間見なんだ銀が、人手にまはりて、九軒の二日払ひの用にも立ち、道頓堀の座払ひのたよりともなる。宝といふ字の消ゆる程、今は世のすれ者となりける」と、大笑ひせし。「このしわき人は五十七癸の辰にてありしが、又癸の辰の年辰の日の辰の刻に相果てられし」といへば、これも不思議の宏才なる人ありて、三世相命鑑を繰りけるに、「この男先生は、鎌倉の将軍頼朝公より西行法師に給はりし鏐の描、値遇の縁にひかれてたま/\人界に生を受け、その身は金ながらつかふ事もならず、人の子の物になりける。このはずなり。その金猫は、西行しばし手にふれて、里の童子にとらせける。その猫ほしや」と、見もせぬむかしの物語にもまづ掻きつき、欲をまろめて今の世の人間とはなりぬ。
(『永代蔵』三巻の四「高野山借銭塚の施主」)
これは三巻の四の冒頭部である。頑固老人から若者への教訓話という体裁をとり、具体的な談話と行動の描写から場面として捉えられなくもない。しかし、ここで設定された場は全く抽象的な場であり、具体的な場面を描いたとはいえない。抽象的な場とは、叙述者表現の一種として捉えられるということである。そのように判断する理由は、この挿話がこの章段での語り手の思想を引き出すためだけの役割しか持っていないからである。この挿話に登場した「堅作りの親仁」や「若い者ども」は、この章段の後の部分では全く登場せず、またどのような人物であるか限定されることもない。さらに、この挿話の時期や場所の限定も全くない。特に、この挿話の最後に示される「見もせぬむかしの物語にもまづ掻きつき、欲をまろめて今の世の人間とはなりぬ」は語り手によるまとめの部分であり、ここまでの話が「欲をまろめて今の世の人間とはなりぬ」という結論を導くためのものであることが分かる。これらの理由から、この挿話がある具体的な場面を抜き出したのではなく、語り手の想像によって作られたものだと判断できる。
では、なぜこのような場面ともとれるような書き方がなされたのか。これも西鶴の工夫の一つだと考えられる。この章段は一つの筋を持たず、様々な挿話を紹介して西鶴の思想を述べるという構成になっている。その導入に「いかにも」あり得そうな具体的な挿話を置くことは、その後の西鶴の主張を受け入れやすくさせる働きがある。また、いきなり具体的な談話から章段が展開していくことが『永代蔵』では珍しく、読者を引きつけるための工夫になったと考えられる。
以上、『永代蔵』三巻の場面に関して考察してきたことをまとめる。『日本永代蔵』三巻において、場面は成立し難い。場面が成立した場合には人物の対話が重視される。また、《舞台》設定の事物描写がほぼなく、《舞台》は地名によって示される。さらに、《舞台》について書かれる基準として新規性が重要である。
ここまで『日本永代蔵』三巻について、分析結果から観点に沿った考察を行い、特に事物描写に関した表現特性を見出してきた。各観点で見出した表現特性については各項にまとめた。本稿での考察を踏まえて仮説に答えると、短編小説的章段や土地紹介的章段といった構成によって、《舞台》設定の事物描写の出現割合は大きく変わらないと結論できる。ただし、事物描写は《舞台》設定以外にも用いられており、これらの表現に着目することで西鶴の表現特性はより明らかになると考えられる。本研究で扱えなかったものとして各章段ごとの挿絵がある。これは描写性の低い部分を想起する一助になっていると考えられ、本文と挿絵の関連についての分析を今後の課題とする。
→ページのトップへ戻る
本節では『三四郎』の分析結果から観点に沿った考察を行い、作品の表現特性を明らかにする。考察の前に分析に関する諸情報を挙げておく。『三四郎』の総文数は5811文であった。
→ページのトップへ戻る
本項では《文の機能》に応じた文の種類について考察していく。
次のグラフは、『三四郎』における文の種類ごとの出現数である。
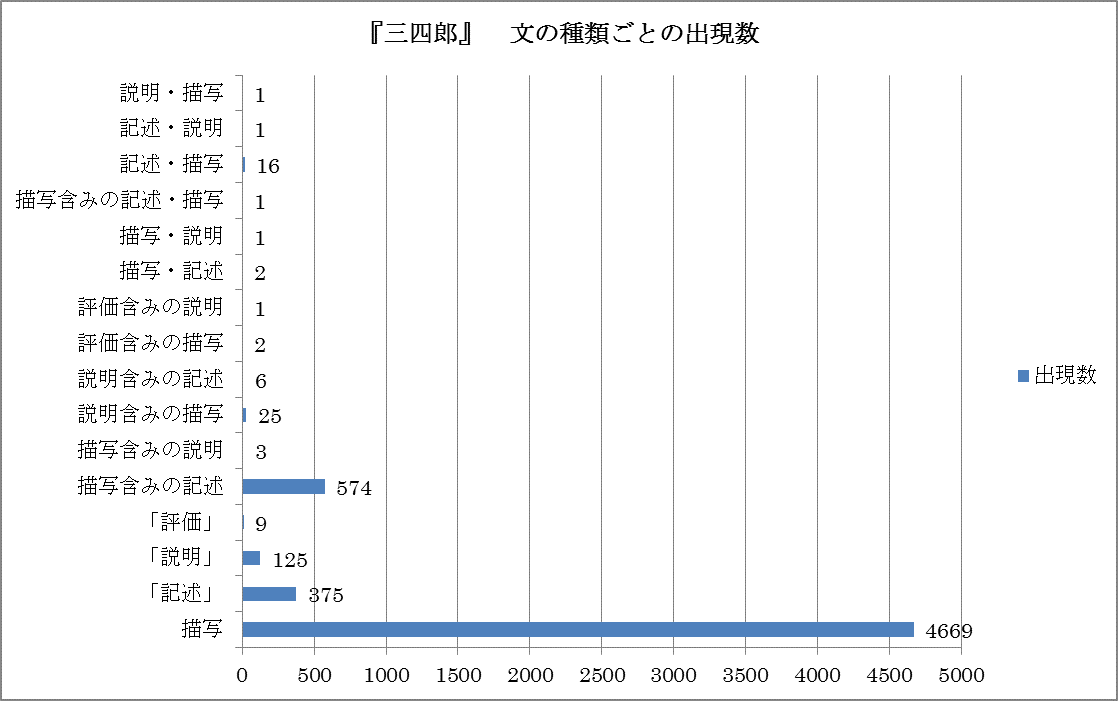
出現した文の種類は計16種類である。出現割合は、(描写)が80.3%(4669文)で出現割合第1位、(描写含みの記述)が9.9%(574文)で出現割合第2位、(「記述」)が6.5% (375文)で出現割合第3位である。これら3種の文が『三四郎』で占める割合は96.7%(5618文)である。また、これら3種は対象表現である。対象表現に注目すると、(説明)(評価)といった叙述者表現を含まない純粋な対象表現文の全体割合は97.0%(5637文)である。つまり、作品世界の事態や事物を示す叙述が全体の9割強を占めていることになる。対象表現と小説・物語作品の関係については本章第1節で論じたのでここでは繰り返さない。分析結果は、『三四郎』が作者の思想や心情を伝えるための書き物ではなく、虚構の世界を描き出すための作品として造型されていることを示している。
対象表現に関して(描写)(「記述」)(描写含みの記述)を取り上げて更に考察していく。『三四郎』における(描写)と(「記述」)系列の割合を比較すると、(描写)が80.3%(4669文)、(「記述」)系列が16.3%(949文)であった。『三四郎』では(「記述」)系列よりも(描写)の方が約5倍多い。『三四郎』では(描写)の文が全体の8割を占めていることもあわせて、『三四郎』には描写表現が頻出するといえる。各文の描写性についてひとまず置いておけば、『三四郎』の表現特性として描写性の高さが指摘できる。
描写表現が頻出する原因について、「『三四郎』豫告」52を基に次のように推測した。「豫告」で、漱石は『三四郎』において物語の筋よりも出来事を描くことを重視していると、前章で述べた。これは『源氏物語』や『日本永代蔵』と異なる点である。『源氏物語』には光源氏という人物の一生を記すという筋がある。『日本永代蔵』も致富譚・没落譚というよう筋のある展開を持つ章段がいくつかある。筋がある物語作品は、その筋を追うために(「記述」)系列の文を用いて物語を進行していく必要があることを既に述べた。『三四郎』ではこの筋を追うことが重視されていない。つまり、物語を進行させずに一つの場面を描き続けることが問題にならないのである。(記述)系列の出現割合が他の二作品と比較して、極端に低い結果もこれが原因だと考えられる。
さらに(描写含みの記述)が『三四郎』で第2位の出現割合であることも併せて、文の種類から指摘できる『三四郎』の表現特性をまとめる。『三四郎』は対象表現文によって、作品世界内の事物や物事を書き出そうとしている。しかも、(描写)の頻出から筋の進行よりも作品世界を具体的に描く叙述が重視されている。
ただし、『三四郎』に筋の進行がないわけではない。『三四郎』で最も目立つ筋として認められるのは、三四郎と美禰子の関係であろう。では、この筋はどのように進行されるのか。ここで『三四郎』の視点人物が三四郎に集約されていること53に注目すると、筋を進行する方法が分かる。結論を述べると、『三四郎』において筋の進行は三四郎が認識しない場所で行われているのである。これを最も顕著に示す出来事は美禰子の結婚である。以下は三四郎が美禰子の結婚を知った場面である。
しばらくしてから、三四郎が与次郎に聞いた。
「君、この間美禰子さんの事を知ってるかと僕に尋ねたね」
「美禰子さんの事を? 何処で?」
「学校で」
「学校で? 何時」
与次郎はまだ思出せない様子である。三四郎は已を得ず、その前後の当時を詳しく説明した。与次郎は、
「なるほどそんな事が有ったかも知れない」と云っている。
三四郎は随分無責任だと思った。与次郎も少し気の毒になって、考え出そうとした。やがてこう云った。
「じゃ、何じゃないか。美禰子さんが嫁に行くと云う話じゃないか」
「極ったのか」
「極った様に聞いたが、能く分らない」
「野々宮さんの所か」
「いや、野々宮さんじゃない」
「じゃ……」と云い掛けて已めた。
「君、知ってるのか」
「知らない」と云い切った。
(『三四郎』12)
例からはこの時点まで三四郎は美禰子が結婚したという事実を全く知らなかったことが読み取れる。美禰子の結婚は、美禰子に惹かれていた三四郎にとって重大な出来事である。三四郎と美禰子の関係について書くという『三四郎』の筋にも大きく絡む出来事である。しかし、この出来事は三四郎が認識するまで、事実として作品内に書かれることはない。美禰子の結婚という重大事件は、既に起きた出来事として提示されるのみである。そして、この後の展開では三四郎がこの出来事に対応する場面を描く。ここで再び筋の進行は停滞することになる。つまり、『三四郎』では、場面が描かれることで書かれた部分では筋の進行が停滞するが、書かれていない部分で出来事を進行させていくことで物語全体の筋を進行させている。
また、このような筋の進行のさせ方は『三四郎』における限定視点の生成に大きく関与している。限定視点においては視点人物が認識するものが作中に示され、反対に認識されないものは示されることがない。限定視点の生成には、視点人物の視座から認識できるものだけを描くという方法があるが、反対に認識できないものは徹底して書かないという方法もある。三四郎の知らぬところで、出来事が起こり、三四郎がその出来事に全く関与できないというのは後者の方法にあてはまる。『三四郎』では三四郎という視点人物が明確に設定される。その設定には、筋の進行方法も大きく関与しているのである。
本項では『三四郎』に出現する事物描写を取り上げて、考察していく。
まず、事物描写の出現割合を示す。(事物描写)と(風景描写)を合わせた事物描写の、『三四郎』における出現割合は13.7%(799文)であった。
次に、この799文の中から「純粋な事物描写の文」を取り上げる。『三四郎』における「純粋な事物描写の文」の出現割合は、(事物描写)は5.9%(343文)、(風景描写)は2.1%(120文)、合計で8.0%(463文)であった。
また、「純粋な描写の文」の合計は3888文であった。次のグラフは、『三四郎』における「純粋な描写の文」全体における各描写の出現割合である。
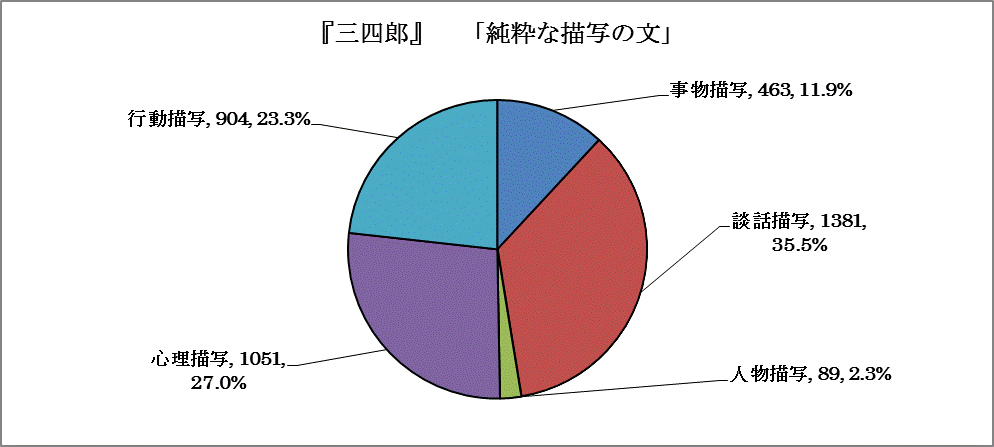
「純粋な事物描写の文」は(事物描写)が8.8%、(風景描写)が3.1%、合計で11.9%であった。「純粋な事物描写の文」は、「純粋な描写の文」の中の第4位の出現割合であった。「純粋な描写の文」の内、出現割合が最も多いのは「純粋な談話描写の文」の35.5%(1381文)、続いて「純粋な心理描写の文」の27.0%(1051文)である。
ここで注目するべきは、「純粋な描写の文」そのもの出現割合である。「純粋な描写の文」は3888文であり全体で66.9%、(描写)の中だけならば83.3%の出現割合を示す。つまり、『三四郎』の文章の半分以上が「純粋な描写の文」によって成り立っていることになる。この結果から、改めて『三四郎』の描写性の高さが指摘できる。また、他の二作品においても「純粋な談話描写の文」は出現割合が比較的高く、人物の談話が持つ描写性の高さが読み取れる。
『三四郎』の「純粋な事物描写の文」は(463文)あり、その全てをここに挙げることは出来ない。ここでは、第1章で『三四郎』が写生文家的態度の人物として造型されていることを指摘したことを踏まえ、その造型に関与した事物描写に注目する。
第1章で写生文家的態度と共通する考え方として、低徊趣味という漱石の造語を挙げた。低徊趣味とは、「一と口に云ふと一事に?し一物に倒して、獨特もしくは連想の興味を起して、左から眺めたり右から眺めたりして容易に去り難いと云ふ風な趣味を指す54」。そして、三四郎はこの低徊趣味の持ち主であることが本文で示されている。
ここでは三四郎の低徊趣味を事物描写の連続から見て取る。以下に挙げるのは、風景の描写が連続して表れている部分である。
(1)坂の上から見ると、坂は曲っている。刀の切先の様である。幅は無論狭い。右側の二階建が左側の高い小屋の前を半分遮っている。その後には又高い幟が何本となく立ててある。人は急に谷底へ落ち込む様に思われる。その落ち込むものが、這い上がるものと入り乱れて、路一杯に塞がっているから、谷の底にあたる所は幅をつくして異様に動く。見ていると眼が疲れるほど不規則に蠢いている。
(『三四郎』5)
三四郎が広田や美禰子たちと菊人形を見物にいく道中、団子坂の上から見た坂の風景である。ここで一文目に「坂の上から見ると」とあって、視座が三四郎に置かれていることがわかる。三四郎の視点から、坂の形状や賑わいといった風景が描かれている。三四郎はこの風景を「見ていると眼がつかれる程に」集中して見ている。注意として、ここでは人の入り乱れる様子も描かれておりこれは(行動描写)と捉えられるかもしれない。しかし、ここでは人物の行動が坂の様子を構成する背景の一部と判断したので、全て(風景描写)と取っている。
(2)子供の葬式が来た。羽織を着た男がたった二人着いている。小さい棺は真白な布で巻いてある。その傍に奇麗な風車を結い付けた。車がしきりに回る。車の羽弁が五色に塗ってある。それが一色になって回る。白い棺は奇麗な風車を断間なく揺かして、三四郎の横を通り越した。三四郎は美しい葬だと思った。
(『三四郎』10)
三四郎が広田の家から原口の家へ向かう道中に子どもの葬列と出くわす場面。子どもの入った棺が描写されている。三四郎の目が棺の全体から、棺に結い付けられた風車に移って行く様子が分かる。ここでも、風車の羽弁の色が五色であることを見て取る程には対象を集中して見ている。
描写表現が連続するのは、例えば『永代蔵』での人物の網羅的な描写などでもあった。しかし、そのような描写は基本的には語り手の視座からの描写であって、『三四郎』のように登場人物が対象を凝視するわけではない。また、(1)や(2)のように「純粋な事物描写の文」が連続して出現することは他の二作品ではほぼない。
ところで、(1)や(2)のような事物描写の連続は「視点人物造型」の役割を担っている。一つの対象をじっと見つめるというのはまさに低徊趣味の表れであり、三四郎が興味を抱いた事物を矯めつ眇めつする人物として描き出されている。
『三四郎』では、事物描写の直前に知覚動詞を頻繁に用いることも特徴として挙げられる。次に挙げるのは『三四郎』第2章の知覚動詞が事物描写の前に置かれた例である。
見ると色々書いてある。まず今年は豊作で目出度いと云う所から始まって、身体を大事にしなくっては不可ないと云う注意があって、東京のものはみんな利口で人が悪いから用心しろと書いて、学資は毎月月末に届く様にするから安心しろとあって、勝田の政さんの従弟に当る人が大学校を卒業して、理科大学とかに出ているそうだから、尋ねて行って、万事よろしく頼むがいいで結んである。
(『三四郎』2。太字が知覚動詞。)
三四郎が東京で初めて受け取った母からの手紙を読んでいる。太字部「見ると」という知覚動詞が用いられているため、手紙を見る視座が三四郎にあると分かる。
部屋の中を見廻すと真中に大きな長い樫の机が置いてある。その上には何だか込入った、太い針線だらけの器械が乗っかって、その傍に大きな硝子の鉢に水が入れてある。その外にやすりと小刀と襟飾が一つ落ちている。最後に向うの隅を見ると、三尺位の花崗石の台の上に、福神漬の缶程な複雑な器械が乗せてある。
(『三四郎』2。太字が知覚動詞。)
三四郎が野々宮の部屋を初めて訪れた場面である。太字部「部屋の中を見廻すと」「最後に向うの隅を見ると」と二度も知覚動詞が置かれており、三四郎の視座から野々宮の部屋を描いていることが強調される。
上記二例のように知覚動詞によって対象を認識していることが明示される場合もあれば、次のように三四郎が認識していることが示され、その後に事物描写があるという場合もある。これも知覚動詞を用いるのと同じ働きを担っており、三四郎に視座があることを示している。
炎天で眼が眩んだ時の様であったが少時すると瞳が漸く落付いて、四辺が見える様になった。穴倉だから比較的涼しい。左の方に戸があって、その戸が明け放してある。
(『三四郎』2。太字が知覚動詞。)
太字部「四辺が見える様になった」と書かれることで、この後に続く「左の方に戸があって、その戸が明け放してある」という認識の視座が三四郎にあることが分かる。
不図眼を上げると、左手の岡の上に女が二人立っている。女のすぐ下が池で、池の向う側が高い崖の木立で、その後が派手な赤煉瓦のゴシック風の建築である。そうして落ちかかった日が、凡ての向うから横に光を透してくる。
(『三四郎』2。太字が知覚動詞。)
三四郎が「不図眼を上げ」たことで岡の上の様子を認識する。太字部には三四郎が認識の視座にあることを示すと同時に、その認識の結果が三四郎には思いがけないものであることも示している。
このように、知覚動詞、またはそれに類する表現で三四郎に視座があることを強調することは、『三四郎』における限定視点をより強固なものにしている。他の二作品が基本的に三人称客観視点にあるのに対して、『三四郎』では強固な限定視点の生成がなされている。さらに、客観視点の所謂「神の視座」からではなく、作品内に存在する人物の限定された視座から作品世界を描くことはより現実的な認識の方法に近く、描写性を強めている。『三四郎』の描写性が高いことは、描写表現が多用されることだけではなくこの限定視点によっても説明できる。
以上、本稿で考察してきたことをまとめる。『三四郎』において、事物描写は全体の13.7%で、「純粋な事物描写の文」は全体の11.9%である。(描写)の内で「純粋な事物描写の文」が半数を超える出現割合を示すことから、改めて描写性が高い作品だといえる。事物描写の特徴としては、三四郎の低徊趣味を表す事物描写の連続と限定視点を強固にする知覚動詞の頻出を挙げた。
本項では『三四郎』において、どのように場面が設定されているのか考察していく。
前々節『源氏物語』、前節『日本永代蔵』では、場面が設定されたと判断した部分を全て挙げてきた。しかし、『三四郎』では作品の大部分が場面として設定されているので、ここではその全てを挙げることはしない。
『三四郎』の場面では、基本的に人物の対話か三四郎の行動が描かれる。三四郎が誰か他の人物といる場合は対話が中心に描かれ、三四郎が一人の場合は三四郎の行動に沿って見たものや考えたことが中心に描かれる。では、『三四郎』の場面はどのように設定されていくのか。『三四郎』の場面設定の特徴をよく表していると判断した場面を例に、その特徴を述べていく。
曙町へ曲ると大きな松がある。この松を目標に来いと教わった。松の下へ来ると、家が違っている。向うを見ると又松がある。その先にも松がある。松が沢山ある。三四郎は好い所だと思った。多くの松を通り越して左へ折れると、生垣に奇麗な門がある。果して原口という標札が出ていた。その標札は木理の込んだ黒っぽい板に、緑の油で名前を派手に書いたものである。字だか模様だか分らない位凝っている。門から玄関まではからりとして何にもない。左右に芝が植えてある。
玄関には美禰子の下駄が揃えてあった。鼻緒の二本が右左で色が違う。それで能く覚えている。今仕事中だが、可ければ上がれと云う小女の取次に尾いて、画室へ這入った。広い部屋である。細長く南北に延びた床の上は、画家らしく、取り乱れている。先ず一部分には絨毯が敷いてある。それが部屋の大きさに較べると、まるで釣り合が取れないから、敷物として敷いたというよりは、色の好い、模様の雅な織物として放りだした様に見える。離れて向うに置いた大きな虎の皮もその通り、坐る為の、設けの座とは受け取れない。絨毯とは不調和な位置に筋違に尾を長く曳いている。砂を錬り固めた様な大きな甕がある。その中から矢が二本出ている。鼠色の羽根と羽根の間が金箔で強く光る。その傍に鎧もあった。三四郎は卯の花縅しと云うのだろうと思った。向う側の隅にぱっと眼を射るものがある。紫の裾模様の小袖に金糸の刺繍が見える。袖から袖へ幔幕の綱を通して、虫干の時の様に釣るした。袖は丸くて短い。これが元禄かと三四郎も気が付いた。その外には画が沢山ある。壁に掛けたのばかりでも大小合せると余程になる。額縁を附けない下画という様なものは、重ねて巻いた端が、巻き崩れて、小口をしだらなく露わした。
描かれつつある人の肖像は、この彩色の眼を乱す間にある。描かれつつある人は、突き当りの正面に団扇を翳して立った。描く男は丸い脊をぐるりと返して、調色板を持ったまま、三四郎に向った。口に太い烟管を啣えている。
「遣って来たね」と云って烟管を口から取って、小さい丸卓の上に置いた。燐寸と灰皿が載っている。椅子もある。
「掛け給え。――あれだ」と云って、描き掛けた画布の方を見た。長さは六尺もある。三四郎はただ、
「なるほど大きなものですな」と云った。原口さんは、耳にも留めない風で、
「うん、中々」と独言の様に、髪の毛と、背景の境の所を塗り始めた。三四郎はこの時漸く美禰子の方を見た。すると女の翳した団扇の陰で、白い歯がかすかに光った。
(『三四郎』10)
三四郎の第10章において、三四郎が美禰子に会うために原口の家を初めて訪れる場面である。《舞台》は(原口の仕事場)である。場面展開部は原口が美禰子の絵を描く傍ら、三四郎や美禰子と話すという形で進行していく。同時に三四郎は原口と話しながらも美禰子に対しての思いを廻らしている。
上に挙げた例は展開部に至るまでの部分であり、《舞台》設定の事物描写がある。場面展開の前に事物描写による《舞台》設定がある点は、『源氏物語』三巻と共通している。描写対象を提示する順番が、屋外から屋内へという三四郎の行動に沿っている点も共通点として挙げられる。しかし、『三四郎』では屋内に入ってからも三四郎の行動に沿った事物描写がある。屋内に入るとすぐさま人物の対話が展開していく『源氏物語』とは異なる点である。これは限定視点という視点設定によって、三四郎という視点人物の動きにより忠実に沿った描写を行なう必要があったからである。
この限定視点を踏まえると、この《舞台》設定の事物描写は三四郎の心理状態を表していると解される。三四郎の心理を表しているのは、《舞台》設定の事物描写の連続と多量さである。特に(原口の仕事場)については熱心過ぎる事物描写がなされている。ここに三四郎の低徊趣味を見ると同時に、美禰子への心の迷いも見ることができる。
三四郎がこの《舞台》で最も興味のある対象は当然美禰子で間違いない。これは作品の展開上明らかなことであり、原口の家を訪ねた理由が「美禰子に会うため」であることからも分かる。しかし、三四郎が美禰子を認識するのは、《舞台》についての熱心な事物描写の後である。上に挙げた例文の最後の部分である。例文末の「三四郎はこの時漸く美禰子の方を見た」という一文は、三四郎が敢えて美禰子を見なかったことを示唆している。また、(原口の仕事場)についての事物描写が終わった直後、「描かれつつある人は、突き当りの正面に団扇を翳して立った」と一度美禰子に視線が行きかけるが、すぐさま「描く男は丸い脊をぐるりと返して」と原口の方に視線を移している。三四郎は一度見かけた美禰子からわざわざ目を逸らしている。『三四郎』では、全体を通して美禰子に対する三四郎の気持ちが整理されない。その気持ちの迷いが、ここでの執拗な《舞台》設定・事物描写に表れていると考えられる。三四郎は整理のつかない気持ちのまま美禰子に会うことに戸惑いを覚えており、少しでも美禰子との接触を先延ばしにしようとしているのである。
《舞台》設定の方法から『三四郎』の限定視点性が強固なものであることに触れ、事物描写の役割について述べてきた。
ところで、(原口の仕事場)についての描写は網羅的な描写ということもできる。網羅的な描写が却って像を結びづらいことは前章で述べた。しかし、ここでの網羅的描写には上に述べたような理由から描写妥当性を認めることができる。網羅的描写によって三四郎が美禰子へ抱いている戸惑いの気持ちが描き出されているからである。つまり、『三四郎』では限定視点が生成されることで、網羅的描写にも描写妥当性を与えている。もちろん、『三四郎』の全ての網羅的描写が描写妥当性を有するというわけではない。
ここまで、『三四郎』の場面設定には《舞台》設定の構成上の位置と限定視点との関わりについて述べてきた。事物描写とは異なるが、限定視点を生成する場面設定として『三四郎』の冒頭部が挙げられる。
うとうととして眼が覚めると女は何時の間にか、隣の爺さんと話を始めている。この爺さんは慥かに前の前の駅から乗った田舎者である。発車間際に頓狂な声を出して、馳け込んで来て、いきなり肌を抜いだと思ったら脊中に御灸の痕が一杯あったので、三四郎の記憶に残っている。爺さんが汗を拭いて、肌を入れて、女の隣りに腰を懸けたまでよく注意して見ていた位である。
(『三四郎』1)
『三四郎』の冒頭部、三四郎が名古屋行きの汽車に乗っている場面である。冒頭第一文「うとうととして眼が覚めると女は何時の間にか、隣の爺さんと話を始めている」で、既に三四郎の視座から物語が始められている。例えば、「女は何時の間にか」という部分は、物語開始以前に三四郎だけが遭遇した出来事があったことを示しており、読者は三四郎の理解に沿ってしか作品世界に入ることができない。『三四郎』の冒頭部から既に限定視点が生成されていることが分かる。
『三四郎』では、場面化していながら《舞台》設定がされない場合もある。その基準は『源氏物語』三巻や『日本永代蔵』三巻と同じく、既に作中で《舞台》として設定されているか読者にも馴染みの深い場所の場合である。これは、例えば第1章の汽車の中が描写されないことから分かる。
さらに、ここでも限定視点の影響を考えると、汽車や下宿は三四郎にとって特に興味を引き起こす対象ではなかったと考えることができる。汽車や下宿は三四郎にとってありふれた場所であるから、三四郎が興味を抱かなくとも不思議ではない。つまり、三四郎にとっての新規性がない場所であるから《舞台》設定の事物描写がなかったとも考えられる。どちらの場合でも、『三四郎』で《舞台》設定の事物描写がなされる基準として新規性が重視されているということには変わりがない。
『三四郎』での《舞台》判定の方法は主に二種類に分けられる。《舞台》が場所の名称や事物描写によって設定される場合はそれらによって判定できる。《舞台》の設定がない場合はその場所と関係の深い人物や事物が示されることで判定できる。この人物や事物はそれぞれの《舞台》による。例えば、広田の家であればお手伝いの婆さんがいることや、その婆さんが与次郎について話していることから《舞台》が判定できる。
以上、本項で『三四郎』の場面設定に関して考察してきたことをまとめる。『三四郎』において事物描写を用いた《舞台》設定がなされる場合、《舞台》は場面展開部の前に描かれる。《舞台》の描写に関しては新規性が重視され、その新規性は三四郎という登場人物にも左右される。さらに、場面設定も限定視点を生成しており、限定視点の影響下では視点人物の行動に沿った事物描写がなされる。
ここまで『三四郎』について、分析結果から観点に沿った考察を行い、特に事物描写に関した表現特性を見いだしてきた。各観点で見出した表現特性については各項にまとめた。本項で考察してきたことを踏まえると、『三四郎』において限定視点という視点設定は一つの表現特性だといえる。限定視点は事物描写にも影響を与えており、特に「視点人物造型」の役割を担う。ここでは、『三四郎』に登場した事物描写の内、一部しか扱えておらず、他にも取り上げるべき事物描写がある。
第2章として、研究対象三作品の分析結果とその考察から各作品の事物描写に関した表現特性を見出してきた。
各作品の表現特性を簡単にまとめておく。『源氏物語』と『日本永代蔵』は(「記述」)系列の文によって、物語を進行させることが重視される。ただし、両作品ともに(描写含みの記述)を用いることで、物語の進行とともに作品世界の具体化を両立させようとしている。『三四郎』は(描写)の文を多く用いることで、作品世界での出来事を具体的に描くことが重視されている。
場面設定に関しては、三作品ともが《舞台》設定において新規性を重視するという共通点が見られた。しかし、『三四郎』が限定視点に設定されていることが他の作品との差異を生んでいる。
次章では、本章で明らかになったことを踏まえて、観点ごとに対象作品を比較考察し、事物描写の通時的変遷を明らかにしていく。
54 夏目漱石「高浜虚子『鶏頭』序」『漱石全集第十一巻評論雑篇』岩波書店、1966年10月、pp.550-560。初出は1908年1月。
→ページのトップへ戻る
本章では対象作品の分析結果を比較考察することで、日本文学における事物描写の通時的変遷の様相を明らかにする。
→ページのトップへ戻る
本節では《文の機能》に着目し、その通時的な変遷について述べる。
結論を先に述べる。『源氏物語』三巻・『日本永代蔵』三巻・『三四郎』を分析した限りにおいて、日本の小説・物語作品で用いられる文は、近代において機能が整理されて用いられるようになっている。ただし、この《文の機能》の整理は事物描写の出現割合には影響を及ぼしていない。
以下で、研究対象作品の分析結果を比較しながら説明していく。
《文の機能》の整理
まず、《単機能文》の出現割合に注目する。《単機能文》は一文一機能であり、《文の機能》が最も単純な状態だといえる。《複機能文》はそれぞれの機能どうしの配列や内包の仕方によって単純さの度合いに差があるが、一文に複数の機能がある点で《単機能文》よりは複雑である。当然、《単機能文》の出現割合が高ければ、より多く単純な文を用いていることになる。
各作品における《単機能文》の出現割合は、『源氏物語』三巻で67.9%(528文)、『日本永代蔵』三巻で67.6%(246文)、『三四郎』で89.1%(5178文)であった。『源氏物語』『日本永代蔵』と比較して、『三四郎』では《単機能文》の割合が20%以上増加し、その分《複機能文》が減少している。この結果から、『三四郎』では、それ以前の作品よりも単純な文が用いられていることが示された。
次に、作中に出現した文の種類数に注目する。作中に出現した文の種類数は、『源氏物語』三巻が20種類、『日本永代蔵』三巻が26種類、『三四郎』が16種類であった。《単機能文》4種は各作品に必ず出現したため、種類数の増減とは即ち《複機能文》の増減を意味している。『三四郎』は他の二作品と比較すると、《複機能文》が最も少ない。《単機能文》が一文内の機能数が最小であることによって単純な状態だといえるように、文章もまた用いられる文の種類が少ない方がより単純な状態だといえる。これを踏まえると、『三四郎』の文章は他の二作品よりも《複機能文》が少なく、比較的単純であることが示された。
さらに、「純粋な描写の文」にも注目する。(描写)も、事物・風景・行動・談話など、描写対象に応じて種類を分けていた。研究対象の各作品には、これらの描写対象を一度に描くような(描写)があった。(描写)についても、描写対象が一文につき一つであるほうがより単純な描写表現だといえる。つまり、「純粋な描写の文」の出現割合が多い方が、より単純な描写表現を多く用いているといえる。各作品における「純粋な描写の文」の出現割合は、『源氏物語』で三巻20.1%(156文)、『日本永代蔵』で三巻3.9%(14文)、『三四郎』で66.9%(3888文)であった。ここでも、『三四郎』は他の二作品と比較して単純な描写表現を多く用いていることが示された。
以上、分析結果の比較から、近代の作品である『三四郎』は、中古の『源氏物語』と近世の『日本永代蔵』と比較して、文・文章・描写表現においてより単純な表現を多く用いていることが明らかになった。この結果から、日本の小説・物語作品の《文の機能》は近代において整理されたと結論する。一文の《文の機能》が少ないことが文として整理された状態であるというよりは、《文の機能》一つが一つの形式単位、つまりは一文単位で別個にあるということを指して整理と呼んでいる。
日本の小説・物語作品の《文の機能》が近代において整理されたのは、当時の日本に西洋思想が流入したことが原因だと考えられる。近代、特に明治期において日本が西洋の文化・思想を取り入れて近代化を推し進めたことは広く認められている。特に、『三四郎』の作者・漱石が西洋思想に影響を受けて、それを作品に反映していることは漱石自身の言葉にもある55。また、特に漱石と関係が深い小説技法である写生についても、もともとは西洋の絵画技法であった。
特に、この写生技法が《文の機能》の整理と関連が強いと考える。写生技法の見たままに書くという方法は《文の機能》でいえば(描写)にあたる。そして、『三四郎』には《単機能文》(描写)が全体の80.3%(4669文)の出現割合を示している。さらに、「純粋な描写の文」に限定しても66.9%(3888文)と半数以上を占めている。「純粋な描写の文」は《単機能文》であるだけではなく、(描写)としてもより単純化された状態の文である。このような(描写)や「純粋な描写の文」の頻出は見たままに書くという写生技法の表れだといえ、《文の機能》の整理に写生技法が関連していることを示唆する。
また、一文の平均文字数が少ないことも、この《文の機能》の整理と関連すると考えられる。実際、各作品における一文の平均文字数は『源氏物語』三巻で約68文字、『永代蔵』三巻で約78文字、『三四郎』で約28文字と、『三四郎』は他の二作品の半分以下の文字数である。今回は一文の文字数については措いていたが、文字数の差は各時代の文の捉え方の違いを反映していると考えられるので、今後は文字数にも考慮する必要がある。
ところで、《文の機能》が整理されることは、文章の整理に直結しない。あくまでも一文内において《文の機能》が単純化されて用いられるようになっているというだけであり、文の配列によって形作られる文章の単純化とは別の問題である。さらに、《文の機能》が整理されることは、文の「分かり易さ」とも直結しない。「分かり易い文」の定義は曖昧であるが、その指標の一つとして情報量が挙げられる。一般的には一文の情報量が多いよりも少ないほうが分かり易いと考えられる。その意味で《文の機能》の整理が文の「分かり易さ」に関係しているとはいえる。しかし、上でも述べたように本研究では一文の文字数については考慮していない。たとえ《単機能文》であっても、文字数が多ければ情報量は多くなり、一概に「分かり易く」なるとはいえない。
今回は(直列文)と(内包文)はどちらも《複機能文》として区別せずに扱ってきた。しかし、《文の機能》の整理ということを問題にすると、この二種類の文の間にはその整理の度合いに差がある。例えば、以下の例文の下線部は《複機能文》(描写・説明)である。
三四郎は懐に三十円入れている。この三十円が二人の間にある、説明しにくいものを代表している。――と三四郎は信じた。返そうと思って、返さなかったのもこれが為である。思い切って、今返そうとするのもこれが為である。返すと用がなくなって、遠ざかるか、用がなくなっても、一層近付いて来るか、――普通の人から見ると、三四郎は少し迷信家の調子を帯びている。
(『三四郎』10。下線部が(描写・説明))
三四郎が美禰子に借りた三十円の扱いに悩む場面である。下線部の前半部「返すと用がなくなって~一層近付いて来るか」までは三四郎の(心理描写)であるが、後半部「普通の人から見ると~帯びている」は語り手による三四郎の心理に対する意味づけである。ここで、一文の中には二種類の機能があるが、二種類の機能が分かれている部分が明確であり、配列の方法に整理が見いだせる。このような(直列文)の場合は《単機能文》二文相当と見做すこともでき、その整理の度合いは(内包文)よりも高いと考えられる。文の種類による、整理の度合いの差異を明らかにすることは今後の課題である。
ここで、上記の結論から出た新たな問題について述べておく。《文の機能》の整理という観点から捉えると『日本永代蔵』三巻は研究対象の内で最も《文の機能》が整理されていない作品だといえる。《単機能文》の出現割合については『源氏物語』とほぼ同じであるが、出現した文の種類が最も多いのが『永代蔵』三巻である。この理由は西鶴の文体的特徴と関連していると考えられる。例えば、西鶴の文体的特徴として飛躍・連想が挙げられるが、これは一文の途中で機能の種類が変化することの理由になる。
新たな問題というのは、《文の機能》が整理されていることが文の発展とどのように関連しているのかということである。近代で《文の機能》が整理されたことは既に示したとおりであるが、これが文の発展を示しているというわけではない。なぜならば、その整理の大きな理由が西洋思想の流入が原因だと考えられるからである。つまり、純粋に日本の文が発展した結果、《文の機能》の整理が起きたとはいい難い。
『源氏物語』にあるような和文は、漱石から「柔かいだら/\したもの56」と指摘され、実際に明治期の享受態度は否定的なものが大部分であった。対して、西鶴の文体はその写実性から明治期に再評価されている。しかし、この二作について、『永代蔵』の教訓書的性格を代表する叙述機能を除けば、《文の機能》の類似も見いだせる。特に《単機能文》の出現割合がほぼ同じというのは注目すべきである。二つの作品の文体は全く異なるものである。しかし、少なくとも《文の機能》に関しては類似する点を見出すこともでき、二作からは日本における文の発展の一端が窺える。これを踏まえて、西鶴の文体について考えてみたとき、そこに《文の機能》の発展の筋道を見ることができるのではないだろうか。『日本永代蔵』が《複機能文》の種類が最も多く、整理されていない状態なのは確かである。しかし、ここから西鶴が一文に複数の機能を持たせることを可能にしたという仮説も成り立つ。一文一機能ではなく、一文複機能でありながら、なおかつ写実性も併せ持つ西鶴の文体が純粋な日本の文の発展形としてあるといえるのではないだろうか。
これは当然仮説の域を出ず、今回の分析結果からはこれ以上のことを述べることはできない。ただ、西鶴の作品は「近代小説の過渡的な形態とみるか、逆に混沌ゆえの豊饒さを有しているとみるか57」でその評価が異なる。その文体に着目した場合には、まさに「混沌ゆえの豊饒さ」を示すことができると考える。
今後の研究の方向性として他の時代・他の作品の分析を行うことは必須である。また、西鶴に関しては『日本永代蔵』のように教訓書的性格の強い作品ではなく、『好色一代男』といったより小説的性格の強いといわれる作品を取り上げることが重要である。
事物描写の出現割合
さて、ここまで中古・近世と比較して近代では《文の機能》が整理されたということについて、文の種類の出現割合から説明してきた。では、本研究の中心課題である事物描写の出現割合には通時的な変遷が見られるのか。結論として、事物描写の出現割合ついて通時的に大きな変化は見られないといえる。以下で説明する。
まず、(描写)の出現割合は、『源氏物語』三巻で37.0%(288文)、『永代蔵』三巻で8.0%(29文)、『三四郎』で80.3%(4669文)である。この結果から(描写)の出現割合は近代で極端に増えていることがわかる。この理由について、『源氏物語』と『永代蔵』は筋を追うことを重視しているが、『三四郎』は場面を描くことを重視していると前章で述べた。(描写)表現は、近代作品において極端に増えているのである。
しかし、事物描写の出現割合に限定してみると、『源氏物語』三巻で16.6%(129文)、『永代蔵』三巻で17.1% (62文)、『三四郎』で13.7% (799文)とその差があまり見られないことが分かった。「純粋な事物描写の文」に限定した場合の出現割合は、『源氏物語』三巻で4.1%(32文)、『永代蔵』三巻で0.8%(3文)、『三四郎』で8.0%(463文)と若干『三四郎』で増加しているものの、その差は大きいとはいえない。分析結果からは事物描写の出現割合が通時的に大きく変化したとはいえない。
では、『三四郎』で極端に増えている(描写)は何を描いているのか。これは人物の談話と心理といえる。『三四郎』では「純粋な談話描写の文」の出現割合は23.8%(1381文)で、「純粋な心理描写の文」の出現割合は18.1%(1051文)である。つまり、『三四郎』では作品世界に現れる事物を描くよりも、人物の談話と心理を描くことを重視していたといえる。
これは《文の機能》の整理が事物描写の出現割合に影響を及ぼしていない理由にもなる。『三四郎』で《文の機能》が整理された理由の一つは、《単機能文》(描写)の極端な増加にある。この増加の原因が(談話描写)と(心理描写)の増加に多くを依っているならば、事物描写が増加しなかったことの説明となる。ここで『三四郎』になぜ(談話描写)と(心理描写)が増加したのかという新たな問題が挙げられるが、この問いについて今回の分析から指摘できることはない。今後の課題とする。
ここまでのまとめとして、再度結論を述べる。
近代を境に、日本の小説・物語作品に用いられる文は、その機能が整理されて用いられている。ただし、この《文の機能》の整理は事物描写の出現割合には影響を及ぼしていない。
本研究では文を機能によって分類するということを土台として研究対象作品を分析してきた。結果として、事物描写の通時的な変遷について、その様相の一端が明らかになった。
→ページのトップへ戻る
→ページのトップへ戻る
本節では場面設定に着目し、その通時的な変遷について述べる。
前章の各作品の場面に関しての考察を踏まえて、その共通点と差異点を挙げることで、通時的な変化を見出す。
場面設定の共通点
まず、場面設定の共通点から挙げていく。根本的な共通点として、どの時代の作品にも場面と判断できる部分があったことが挙げられる。この事実は日本の小説・物語作品が、少なくとも中古の時代から出来事をただ記すだけではなく、出来事を描くことも目指してきたことを意味している。ただし、『永代蔵』三巻では短編小説的構成の量的制約によって、場面が確立し難いという表現特性があった。それでも、場面と捉え得る部分があったことは確かである。
次の共通点として、場面で描かれる出来事として人物の対話が選ばれるということが挙げられる。『源氏物語』三巻では場面化されるときには必ず二人以上の人物が対話をしていた。『永代蔵』三巻や『三四郎』においても、人物の対話は頻繁に場面で描かれた。この理由と関係すると考えられる清水氏の主張を再掲しておく。
物語のもとの形は会話部分が主要構成要素であって、さほど多からぬ、たぶん二人か三人ぐらいの人物が対面してお話しをする、そんな対面の場がいくつか積み重り、繋がって筋が展開してゆくのが、物語の基本型だったのではないか、だからまず会話部分が大切なので、人物がどうしたこうしたというト書き的部分--いわゆる地の文は閑却にされた、そうした部分に注意して、描写やさらに心理描写が入ってくるのは、物語の歴史の上では相当進歩した段階でのことだったのではないかと思うのである。
(清水好子「場面表現の伝統と展開」『源氏物語の文体と方法』東京大学出版会、1980年6月、p.137。)
清水氏は物語の基本が会話にあり、それを書くことが物語の「もとの形」であったと主張している。対話は物語を作るための基本であり、だからこそ場面においてもまず人物の対話が選ばれたと考えられる。また、場面の中で人物の対話が描かれるのは、対話が(談話描写)によって描かれることとも関係している。(談話描写)はその所要時間を想像し易く、具体的な感覚の喚起が容易である。したがって、(談話描写)は他の描写表現と比較すると容易に具体的な場面を設定することができる。現実の出来事を模倣するために、まず最も身近で容易な対話によって場面を設定するという方法が選択されても不思議ではない。もしくは、他の描写表現でも、作品当時には十分な描写性をもって場面を設定していたと考えることもできる。これについては、資料が不足しているため、今後の課題となる。場面で描かれる出来事として対話が選ばれるという事実からは、(談話描写)が通時的に高い描写性を持ち続けていることが読み取れる。
ここまで、直接的に事物描写とは関係のない共通点を挙げてきた。場面と事物描写の関わりを考えたとき、最も関係しているのは《舞台》の設定である。事物描写を用いた《舞台》設定は全ての作品に見られた。ただし、『永代蔵』三巻では場面の中で事物描写を用いた《舞台》設定は行なわれていない。『源氏物語』三巻と『三四郎』に共通する点として、場面の中で事物描写を用いた《舞台》設定が行なわれる場合、その設定は必ず場面展開部の前になされる点が挙げられる。これは場面構成に通時的な共通点があるということである。また、場面展開の前に《舞台》設定がなされるということから、展開部では《舞台》が判明していることが場面設定の基本だといえる。
《舞台》設定で三作品全てに共通する点として、事物描写で描かれる対象の新規性が重視される点が挙げられる。ここでの新規性は、登場人物と読者どちらに対しての新規性であっても良い。新規性の重視は、通時的に描写の際に何を描くかという意識が通底していることを意味する。なぜ、新規性が重視されるのか。一つの理由として読者に対する作者の配慮が考えられる。読者が全く知らない場所の説明や紹介をすることで、読者が作品世界を理解する援助をしている。しかし、これだけでは新規性を持った事物が描写対象として選ばれることの説明としては不十分である。描写対象の新規性という点については、他の事物描写も取り上げて考察する必要がある。
ここまで、場面設定の共通点を挙げてきた。以上に挙げた点は、各作品の特色によって完全に一致するわけではないが、通時的に変化していないといえる。
場面設定の差異点
次に、場面設定の差異点を挙げていく。場面設定の差異点として、《舞台》設定の事物描写がより視点人物に沿った表現に変化している点が挙げられる。そして、その結果より描写性の高い事物描写が用いられている。この差異は、次のような場面設定の違いから分かる。
造れるさま木深く、いたき所まさりて見どころある住まひなり。海のつらはいかめしうおもしろく、これは心細く住みたるさま、ここにゐて思ひのこすことはあらじとすらむと思しやらるるにものあはれなり。三昧堂近くて、鐘の声松風に響きあひてもの悲しう、巌に生ひたる松の根ざしも心ばへあるさまなり。前栽どもに虫の声を尽くしたり。ここかしこのありさまなど御覧ず。むすめ住ませたる方は心ことに磨きて、月入れたる真木の戸口けしきことにおし開けたり。
(『源氏物語』「明石」)
『源氏物語』三巻の事物描写を用いた《舞台》設定は、人物の対話を描くという展開部が優先されたことで屋外に限定されている。
曙町へ曲ると大きな松がある。この松を目標に来いと教わった。松の下へ来ると、家が違っている。向うを見ると又松がある。その先にも松がある。松が沢山ある。三四郎は好い所だと思った。多くの松を通り越して左へ折れると、生垣に奇麗な門がある。果して原口という標札が出ていた。その標札は木理の込んだ黒っぽい板に、緑の油で名前を派手に書いたものである。字だか模様だか分らない位凝っている。門から玄関まではからりとして何にもない。左右に芝が植えてある。
玄関には美禰子の下駄が揃えてあった。鼻緒の二本が右左で色が違う。それで能く覚えている。今仕事中だが、可ければ上がれと云う小女の取次に尾いて、画室へ這入った。広い部屋である。細長く南北に延びた床の上は、画家らしく、取り乱れている。先ず一部分には絨毯が敷いてある。それが部屋の大きさに較べると、まるで釣り合が取れないから、敷物として敷いたというよりは、色の好い、模様の雅な織物として放りだした様に見える。離れて向うに置いた大きな虎の皮もその通り、坐る為の、設けの座とは受け取れない。絨毯とは不調和な位置に筋違に尾を長く曳いている。砂を錬り固めた様な大きな甕がある。その中から矢が二本出ている。鼠色の羽根と羽根の間が金箔で強く光る。その傍に鎧もあった。三四郎は卯の花縅しと云うのだろうと思った。向う側の隅にぱっと眼を射るものがある。紫の裾模様の小袖に金糸の刺繍が見える。袖から袖へ幔幕の綱を通して、虫干の時の様に釣るした。袖は丸くて短い。これが元禄かと三四郎も気が付いた。その外には画が沢山ある。壁に掛けたのばかりでも大小合せると余程になる。額縁を附けない下画という様なものは、重ねて巻いた端が、巻き崩れて、小口をしだらなく露わした。
描かれつつある人の肖像は、この彩色の眼を乱す間にある。描かれつつある人は、突き当りの正面に団扇を翳して立った。描く男は丸い脊をぐるりと返して、調色板を持ったまま、三四郎に向った。口に太い烟管を啣えている。
(『三四郎』10)
対して、『三四郎』三巻の事物描写を用いた《舞台》設定では、視点人物の動きに沿って屋内でも描写が続く。
ここで挙げた差異点は、『源氏物語』三巻・『日本永代蔵』三巻が客観視点に設定されているのに対して、『三四郎』が限定視点に設定されていることによって生じている。《舞台》設定の比較からは、近世以前の作品で客観視点が一般的であるのに対して、近代では限定視点が徹底されて用いられているという、視点設定についての意識変化が見出せる。また、『三四郎』では限定視点が強固に設定されることで、《舞台》設定の事物描写が「視点人物造型」の役割を担っている。
以上から、事物描写の通時的変遷の様相として、近代で限定視点設定が徹底されたことで、より視点人物の動きに忠実な事物描写がなされるように変化し、描写性も高くなったことが明らかになった。
ただし、このような《舞台》設定は、作品ごとのジャンル特性にも影響を受けていると考えられる。『源氏物語』や『永代蔵』は、比較的長期の出来事を書くような一代記や致富譚といったジャンルに属している。対して、『三四郎』は写生文的な書かれ方がなされている。それぞれのジャンル特性に注目すると、『源氏物語』や『永代蔵』の描写性が低くなるのは当然ともいえる。今後の課題として、共通したジャンルの作品の通時的変遷を研究することで、より細密な変化が見出せると考えられる。ただし、写生文というジャンル自体は近代になってから現れたものである。中古からあるジャンルと近代を代表するジャンルとの比較は、通時的な変遷を見る資料として申し分ないものである。
ここまでのまとめとして、再度結論を述べる。
場面設定に関して、中古から近代まで一貫して場面化という方法が用いられ、そこでは基本的に人物の対話が描かれた。事物描写を用いた《舞台》設定は場面展開部の前に行われ、その場合対象となる事物は何らかの新規性を有する点が共通している。しかし、近代において限定視点が徹底されたことで、《舞台》設定はより視点人物の動きに忠実に沿った表現に変化し、その描写性も高くなった。
以上、第3章として、対象作品の表現特性を基に事物描写の通時的な変遷について論じてきた。本章では、「《文の機能》の整理と事物描写の出現割合」と「場面設定に関する限定視点の影響」という二つの観点から、事物描写の通時的変遷の様相を明らかにした。しかし、ここで明らかになったことはその変遷の一端である。終章では、本研究の結論を提示するとともに、今後の課題についてもまとめていく。