「21歳」
石川香代子
私は飛行機に乗っていた。それは宮崎行き午後の便だった。私は実家に帰ろうとしていた。それは母に会うためだった。10月にはいり、空は高く澄んで飛行機からの眺めは気持ち良かった。日ごろの忙しさから離れたくて、自分を見失いそうで、帰りたかったのかもしれない。別に悲しいことがあったのではない。次の正月に帰ればそれでいいのだが、私は母に会いたかった。とにかく、母と話をしたいと。私は誕生日を向かえ21歳になったばかりだった。母は21歳に父と結婚した。今、私は結婚を考えている人がいる。そう思ったら帰りたくなったのだ。盆に帰らなかったせいもあり、祖父母は喜ぶに違いないが、母は無理して帰らなくても、といっていた。機内のイヤホンからは、流行のJ−POPが流れている。宇多田ヒカルの声が心地よかった。「飛行機はまもなく宮崎空港に到着します。皆様座席ベルトをしっかりと締め……。」アナウンスと共に飛行機は着陸体制に入った。太平洋沿いのシーガイヤは、屋根が開いていて、上から見えそうだった。
飛行場につき、荷物を受け取り、そこから到着ロビーに出る。そこには待ち人が沢山いて、出ると一番に多くの視線を浴びなければならず、私はそれがいつも苦手だった。その中には母の姿もあった。背の低い母は周りにうもれていたが、すぐに見つけることができた。私も背が低いからだ。
「おかえり。」
母はそう言ったまま少し笑った。
「ただいま。」
と私も少し笑った。それで会話は終わるのだが、二人にいろんなことばは要らなかった。道沿いのフェニックスが秋風にゆれていた。うちに帰ると、変わらない家と変わらない家族がいた。帰った来たんだと、少し力が抜けた。一人暮しには必ずついてくる、無意識に張っていた緊張が緩んでいった。そこで、たった3日間の帰省だが、帰ってきて良かったと思えた。父は相変わらず頑固で堅物だし、弟は野球に熱中していた。私が好き勝手やれているのもこの家族がいるからなのだと、素直に思えた。口には出せないが、本当にそう思った。
夜になり、父も弟も寝入った時間、私はまだ眠れずにいた。どうしても、一人で暮らしていると夜更かしになるので、癖が抜けない。台所に行くと、母は洗い物をしていた。うちは専業農家だから、小さい頃学校から帰っても母親はいない環境で育った。朝が早いので、仕事から帰ってもバタバタと風呂に入り、晩飯を食べて寝る。その中で、私がゆっくり母と話せるのは、寝る前のほんのちょっとした時間だけだった。のどが乾いたと言って、洗い物をしている母の後姿を見ていた。「もうねらんね。」と言われて「うん。」と言っても私はずっとそこに座っていた。その時のように私は座った。母と話がしたくって帰ってきた。電話ではなくこんな風に。
「お母さん?」
「なに?」
私は何を話そうか分からなくなった。
「なんね?」
聞きなおす母。
「うん。」
私は麦茶をコップに入れた。
「なんかあったとね?」
何もない、けど私は話したいことがあった。
「今ね、付き合ってる人がおるとよ。」
母は振り返り、
「あんたにね?」
「そう。」
今まで、一度も母とこんな話をしたことがなかった。実家にいるときも、それから一人暮しから帰省したときも、「彼氏はおらんとや?」と聞かれても「うんにゃ。」と言いつづけていた。恥ずかしかったのもある。でもずっと思っていた。彼ができたら母に紹介したい、そうできるような付き合い方をしたい。母は手を止めとなりに座った。
「ええ、そうね。」
静かにつぶやいた。驚いている様子はなかった。
「初めてね。」
「いや?」
「えっ。」
それから二人はクスクス笑いあった。
「でも、この人やったらお母さんに言える人やって思ったから……。」
「うん。」
「言ってみた。」
「そうね……。」
母と娘の会話を久しぶりにしていた。
「お父さんにはいわんでね。」
母は黙っていた。当たり前よって言うように。
「でも気づいちょるかもね。」
「なんで?」
「指輪、ほらそんなとこにはめちゅっから。」
母は、左手の薬指を見て言った。
「いいやろ。」
「いくら?」
また二人は笑いあった。
「お母さんもほしいわ。」
「今度言っとく。」
「もっとそれよりよかとが。」
――良かった。母に言ってみて正解だった。私はなんとなく聞いた。
「お母さん、21で結婚したっちゃがね。」
「そうよ。」
「その前におらんかったと?」
「なにがね?」
「彼氏。」
言った後、まずかったかなとは思ったが、聞いてどうなるもないことだ。母はしばらく黙ったが、
「お母さんはあなたくらいのときは東京にいてね……。」
と、私の隣に座り話し始めた。
1974年、恵子は集団就職で東京で暮らしていた。狭いが寮の生活は快適で、友達と休みの日には新宿に遊びに行ったりしていた。毎週火曜日と金曜日には、歌声喫茶に行き、いろんな歌謡曲をピアノに合わせ歌った。時には有名人を見にスタジオにも行くほど、恵子は東京生活を満喫していた。
「ねえ、今度のお休みの日、私の友達と遊ぶ約束があるの。来ない?」
山形から来た信子が誘った。
「いいの? 行きたいわ。」
それが彼と出会うきっかけだった。
当日、待ち合わせした場所に来たその友達は男連れ二人だった。恵子はびっくりして「何? 男の人なの?」
と信子に聞いた。
「あら、女って言った?」
そう言い残して彼女は車に乗りこんだ。仕方なく、恵子も乗った。車は北へ北へと進む。男は二人とも東京の人だった。田舎から出てきた恵子は、東京の男の人と話すのがあまり好きではなかった。
「名前は?」
運転しながら一人が話しかけてきた。助手席には信子が座っている。そうか、この人が狙いなのか。恵子は、遊ぶために自分がうまく使われたと思い黙っていた。
「あれ? 聞こえない?」
運転手はルームミラーを覗いた。
「恵子って言うのよ。」
代わりに信子が答えた。
「よろしく、恵子ちゃん。おれ伸二。」
「この人すごいのよ。将来デザイナーになるんだって。ねっ」
聞いてもないのに信子は付け加えた。
「君、静かだね。一言もまだしゃべってない。」
伸二は車を飛ばす。どこへ行くか知らされないまま、のんきにしゃべるなんてできない。恵子は不機嫌のままだった。すると、
「どうしたの? 具合でも悪い?」
隣に座っているもう一人の男が話しかけた。恵子は黙って首を振る。もうすべての人がうっとうしかった。
「俺、亮って言うんだ。何か飲むかい?」
そう言って亮は缶ジュースを何本か出す。すると、
「おれコーヒー。」
「私オレンジがいいわ。」
伸二と信子が口を挟む。
「君は?」
覗きこまれ、機嫌のなおらない恵子は少し体をそらした。
「じゃあ……麦茶で。」
亮は、缶の周りの水滴をふき取り、
「はい。」
と笑って差し出した。
「……ありがとう。」
恵子はそこではじめて相手の顔を見た。色は白く、鼻筋のとおった男性だった。少し釣り目で、薄い唇。恵子は一瞬息を飲んだ。
「格好いいでしょう。」
すかさず信子が代弁するかのように言った。
「亮君もデザイナーを目指してるのよね。」
「いや、おれは伸二と違って建築のほうだけど。」
亮は恵子へ向かって
「やっぱ服のデザイナーのほうがうけるんだ。」
と苦笑いして見せた。恵子は
「そんなことないわ。」
と言いたかったが、もう目は合わせられなかった。さっきまでの怒りも消え、いやまだ僅かにはあるが、隣にいる青年を意識してしまい何もしゃべれずにいた。
「いや、亮のほうがもてるんだ。」
伸二はこちらに聞こえるように大声で話す。車の中はグループサウンズが流れていた。タイガースは恵子も好きなグループだった。
「いや、もてるのは伸二のほうさ。」
「そっかー? そうだな。」
二人は笑った。ただ、信子は面白くない顔をしていた。
「なんだよ。」
伸二は窓の外を見つめ黙っている信子を見て言う。
「なんでも。」
「急に黙り込んで、馬鹿だな。」
「もう! 馬鹿って何よ、馬鹿って。」
伸二はやきもちに気付いているのだろうか。信子はふくれている。亮はうけていた。
「もう……。」
恵子も終いには笑っていた。7月、空は青く晴れ渡っていた。都会の雑踏から離れていくほど、車はスムーズに走っていった。4人は日が暮れるまでドライブを楽しんだ。
「車で旅行でもしたいなぁ」
伸二は車を走らせつぶやいた。
「え? これから行く?」
信子は、目をきらきらさせていった。
「今度、固まって休みができたらな。」
伸二は信子を優しい目で見た。
「いきたいなあ……。」
甘えて見せる。恵子ははじめて信子のこんなところを見てしまい。自分のほうが恥ずかしくなった。田舎の男にはない、軽い感じの話し方や親しみやすさが二人にはあった。信子も田舎から出てきている。この二人とどう知り合ったかは分からないが、同じようなところに引かれていったのだろう。
ドライブは、寮の門限と共に終了し、信子と恵子は車を出た。
「ありがとうね。また行こうよ、伸ちゃん。」
信子は手を振った。恵子も
「ありがとう。」
それだけ言って、チラッと目を亮の方へやった。亮はこちらを見ていたので慌てて顔を伏せたが、彼の
「またね。」
ということばに、素直にうなづいてしまった。車は走り去る。信子はまだ手を振っている。うっとりした目で、彼の車を見送っていた。
「……いっちゃったわ。」
不意に淋しそうな顔。信子は本気に好きなんだと、恵子はこのとき思った。恵子も、二人といる時間とても楽しかった。寮に戻って、永遠伸二の話を聞かされるまでは。
部屋に帰ると、母から電話があったと知らされた。かけ直そうとしたが、内容はわかっていた。――帰ってきなさい。早く帰ってきなさい――それだけだった。恵子に父親はいなかった。弟は大学に行くため家を出ていた。家には母一人だった。恵子はやっと都会の暮らしを楽しめるようになって、また宮崎の田舎の暮らしに戻るのが嫌だった。でも、母は一人で自分を待っているのは分かっていた。
恵子は東京でウエイトレスをしていた。東京の人はおしゃれで、芸能人もたまに来るときがあり、店内はいつも華やいでいた。しかし、テレビで見る芸能人より、もっとうれしくて緊張して待ち望む客がいた。亮だった。あれから二人は店に来るようになり、今では亮一人でも来てくれる。
 「いらっしゃいませ。」
「いらっしゃいませ。」
決まって恵子がオーダーを取りにいった。
「げんき?」
「うん。」
「そう。じゃあ、コーヒー。」
「はい、かしこまりました。」
他の客に見つからないようにことばをかわす。知らず知らず恵子の心は亮に傾き、こんな風にでも会える日をいつも楽しみにしていた。
「ああ、ちょっと。」
亮が後姿に声をかけた。
「はい……。」
恵子はもう一度亮のそばへ寄る。
「あの……。その君の仕事が終わる時間、何時かな?」
「え?」
恵子はなんだかどきどきしながら
「6時……、でおわるけど。」
メニューをぐっと抱きしめていった。
「じゃあ、7時、寮の前で待ってるから。いい?」
「え? うん。」
なぜかも聞けずただうなづいた。ただうれしくてうなづいた。
7時、恵子は他の友達に何も言わず出かけた。外には車が止まっていて、亮が中から手を振った。車に乗る。今日は亮の車だ。
「親父のなんだけど、かっこいいだろ?」
「うん。」
緊張してしゃべれない。
「いこうか。」
「うん。」
しかし、それから、この緊張は少しづつ緩んでいった。何度もこうやって会って行くうちに、一年が過ぎ、亮はどんどん恵子にとって大切な存在になっていった。21歳の誕生日、恵子は初めて亮の部屋につれられた。設計士になる勉強の道具が部屋を占領していた。
「見せたいものがあるんだ。」
そう行って彼は一枚の設計図を広げた。
「俺まだまだだけど、自分で書いてみたんだ。自分の家の設計。」
そこには、直線や曲線で描かれた図があった。数値などが、細かく記されてある。
「将来、きっと成功して、このうちに住みたいんだ。」
「へえ……。」
恵子はうれしそうな目で設計系図を眺めた。
「……、君と。」
一瞬、沈黙が流れた。
「君と住みたい。この家に。」
もう一度亮は言った。恵子は驚いて彼の顔を見つめた。それと同時に大粒の涙がこぼれた。恵子の心は、喜びと同時に深い悲しみで溢れた。自分はすぐにでも田舎に帰らなければいけない。しかし、この人を連れてはいけない。
「ありがとう。」
そう答えるのが精一杯だった。部屋に帰ると、葉書が一枚届いていた。母からだった。母からの葉書なんて初めてだった。恵子からは何度も出したことはあるが、字が汚いことを恥じていた母は筆不精で、決して手紙を書こうとはしなかった。(なんだろう。)恵子は葉書を裏返した。葉書にはこう書かれてあった。
――恵子さん、誕生日おめでとう。東京の暮らしはつらくはないですか。体は壊していませんか? 仕事頑張ってくださいね。お元気で――
短いその文章は、震えた細い字で書かれていた。良く見ると、葉書には蝋がぬってあり、まだ梅雨が開けない季節、雨で濡れないようにしてあった。
「おかあさん。」
恵子は座り込んだ。さっきとは違う涙がほほを伝い止まなかった。帰ろう、母の元へ帰ろう。そう決心した。
「信子。」
恵子は部屋を尋ねた。彼女は一緒の部屋の友達と話していた。
「なあに?」
信子は笑顔で顔を向けた。部屋を出ると、恵子がいつもと違うことに気づき、
「どうしたの? 何かあったの?」
と顔を覗いた。
「うん、あのね。」
恵子はうつむいたまま答えた。
「私、田舎に帰るね。」
明るく打ち明けようと無理に笑って見せた。
「どうして。どうしてなの? 恵子。」
信子は急に言われて動揺している。
「嫌だよ。私、恵子とはなれるなんて嫌だよ。」
恵子も帰りたくない気持ちは十分にあった。
「ごめんね、ごめんね信子。」
二人とも泣いていた。
「もう、決めたから。帰らなきゃ。」
恵子は母親のこと、手紙のことを話した。
「そう……。でも、亮君は? どうするの?」
そのことについては何も言えなかった。
「今日、プロポーズされたの。」
「返事はしたの?」
恵子は首を振った。
「恵子ぉ。結婚しなよ。そしてここに残ろうよ。ずっといようよぉ。幸せになってよ。」
信子は恵子の肩をつかみ、大きく揺らした。こんなに引き止めてくれる友達がいて、愛してくれる人がいて、恵子は自分を幸せだと思った。田舎から出てきて、悲しかったり、淋しかったり、つらいこともあった。なれない都会で働いて、家に仕送りをして、恵子は強くなっていった。他の友達もこのことを聞き、まわりで泣いている。今では、こんなに温かい人たちに囲まれ生きている。楽しいことばかり思い出されてくる。しかし、もうこれ以上母を一人にしておけなかった。
「みんな、ありがと。今まで、ありがとう。」
恵子はもう十分だった。十分幸せだと思った。21歳の誕生日、その日は恵子にとって決して忘れられない日となった。
宮崎行きのフェリー乗り場では、沢山の友達に見送られた。
「恵子、元気でね。」
信子はまた泣いていた。
「また、会おうね。いつかきっと。」
恵子はそう約束して、信子と抱きしめ合った。そこには伸二もいたが、亮の姿はなかった。恵子は、結婚できないと言う返事の手紙を送り、田舎に帰ることも知らせた。それからは、もう店でも会うことはなかった。
「亮のやつ、来ないな。どうしたんだろう。」
伸二は時計を気にした。
「いいの。私がいけないから、来ないのは当たり前よ。」
恵子は笑ってみせた。
「結婚……。してほしかったな。」
信子はポツリとつぶやいた。
「もう、いいのよ。それよりあなたたち、頑張ってね。」
恵子は伸二に
「信子をお願いね。」
と言った。
「恵子ぉ。」
信子はまた泣き出した。
「もう、そんなに泣かないで。もう、船が出ちゃうから行くね。」
恵子は笑って別れようと決めていたから、泣いている信子を慰めてばかりだった。
「じゃあね、バイバイ。みんな、元気でね。」
大きくてを振る。汽笛が鳴った。船はだんだん港から遠のいていった。だんだん、みんなが小さくなっていった。東京ともバイバイか……。と思ったそのとき、港沿いを走る車を見つけた。まさかと思い、身を乗り出して見ると、それは亮の車だった。猛スピードで走っている。涙があふれてきた。
「亮、亮ごめんなさい。ごめんなさい。」
聞こえはしないが、恵子は何度も声に出していた。車から降りてこちらを見ている。両手をふっている。恵子が出した答えに、亮は怒ってしまったんだろうと思っていた。もう会えないのも仕方がないと諦めていた。でも、今亮はいつまでも手を振ってくれている。見えなくなりそう。恵子は海に飛び込んででも戻りたかった。
「亮……亮……。」
恵子も、いつまでも手を振った。母の葉書を握り締めて。
「それで、帰ったらお父さんがおったと。見合いでね。」
昔をうれしそうに思い出して話す母。普段、働く時には見せない顔に、私は母に初めて女らしさを感じた。
「信子と伸二さんは結婚したかい、よかったとよ。」
今でも東京にいるらしい。夏に届いた、暑中見舞いの葉書を見せてくれた。
「ねえ、おかあさん?」
「ん?」
「その人と……、亮さんと結婚できれば良かったとにね。」
「ううん。そげなことないが。」
母は私の肩を抱いた。
「あんたが生まれたがね。そいでお母さん幸せよ。」
「……、うん。」
私は母のほうにもたれたまま、涙が込み上げてきた。泣きそうになった。
「おかあさん、ありがとう。生んでくれて、ありがとう。」
やっとの思いで言うことができた。
「うん、うん。」
母は私の頭をなぜ、何度もうなずいた。この人が私の母で、本当に良かったと思った。
「あんた、結婚するとね?」
「ううん。まだ分からん。」
私の中で、結婚の意味や幸せの意味が少し変わろうとしていた。 「ゆっくり考えなさい。」
「ゆっくり考えなさい。」
「うん、わかった。」
「そのひとかっこいい?」
「えー? どうかな、普通。」
そう、母が恋した人はどんな顔だったのだろう。母はつづけた。
「顔はまあいいから。お金持ちね?」
「えー!?」
二人は顔を見合わせまたクスクス笑い合った。私がおなかにいるとき、男の子だったら亮とつけたかったと母から聞いたことを思い出した。寝る前、母はそっと
「お父さんには言わんでね。」
とささやいた。
終
「茜色の空」
土屋 千紗
火事が起こると、空が一面真っ赤な色に染まるのだという。
その話を聞いたとき、漆黒の空を鏡のようにして、そこに茜色の光がぼんやりと映っている情景を、ちひろは思い浮かべていた。
「見てみたいなー」と言うと、母は怖い顔で、「火事を見た晩はおねしょするんだよ」と言った。
もう十年も前のことだ。
母が倒れたのはその直後だった。そのまま言葉を交わすことなく、母は逝ってしまった。そしてその四年後に父は再婚した。
今、ちひろには十六歳年下の妹がいる。
その長くて厳しい坂道を上りきると、目の前には広々とした緑地公園と、さらにその向こうに、最近開発されたばかりの新興住宅地が一望することができる。
ちひろはそこでふっと一息つくと、自転車を倒して、草地に座り込んだ。
五分くらい休憩しても大丈夫だろう。そう思いながらも、義母の心配そうな顔が目に浮かぶ。
ちひろを送り出す時も、義母は苦い顔で、「ほんとに大丈夫?帰りはちあきもいるんだよ?重いよ?」と、何度も訊いてくるので、その度に「大丈夫」を繰り返さなくてはならなかった。
ちあきの幼稚園は、家から自転車で十五分ぐらいのところある。いつもなら義母が朝夕送り迎えをするところだが、今朝、彼女が足の骨を折って帰ってきたために、ちひろが代わりをしなければならなくなった。石か何かにつまずいて、こけたひょうしに溝にはまってしまったのだという。全治三ヶ月の怪我だった。ちょうどその頃、ちひろの大学は九月の末まで夏休みだったのである。
木陰に座ると、涼しい風がさあっと吹いてきて、とても気持ちがいい。
通りはすでに緑道に入っており、誰も通らず、静かでのんびりとした雰囲気だった。
このまま眠ってしまいたかったが、心配顔の義母が家で待っていることを思うと、そうそう油を売ってもいられない。
住宅地と緑地公園の狭間には、鮮やかな青い屋根が見える。あれがちあきの幼稚園のはずだ。かすかに子どもの声が聞こえてきた。
「よいしょっと」
 おばさんくさく気合いを入れて眠気を追い払うと、自転車にまたがって勢いよく坂を駆け下りた。ぴゅーぴゅー耳元で風が鳴って、胸がどきどきしてきた。顔をあげると空しか見えなくて、まるで上空を駆け抜けているような気持ちになった。
おばさんくさく気合いを入れて眠気を追い払うと、自転車にまたがって勢いよく坂を駆け下りた。ぴゅーぴゅー耳元で風が鳴って、胸がどきどきしてきた。顔をあげると空しか見えなくて、まるで上空を駆け抜けているような気持ちになった。
すでに日は傾き、雲は淡いオレンジ色になって、ピンクからブルーにグラデーションした空を漂っている。
「きれーなそらー」
ちひろが思わずつぶやいたその時、雲の色がかずかに濃くなったように見えた。
前方に視線を移すと、ちょうど幼稚園の青屋根の向こうに、細く煙の立ち上っているのが見える。
ちひろは不安に駆られて、自転車のスピードを一気に加速させた。
息をきらして幼稚園に到着すると、そこはたくさんの人だかりで騒然としていた。ちひろの見た煙はもう消えており、ただ隣の民家の壁が黒く焼け跡を残している。どうやらボヤ程度の火事だったらしい。
とりあえず怪我人も出なかったみたいだ、と胸をなでおろしたとき、人混みの中に見覚えのある後ろ姿を見つけた。
彼はちひろと同じように自転車に乗りながら、火事のほうを気にしている。ちひろの視線を感じてか、はっとこちらを振り返った。
ああ、やっぱり。また会った。
それは最近よく近所をうろついている少年だった。いつも自転車で、ちひろの家の前を通り、家の中を窺っているようなそぶりを見せるのだ。
一般的な高校生のようだが、ストーカーじゃないかしらとちひろは思っていた。
気持ち悪い!なんでこんなとこにいるの?
うんざりして幼稚園のほうに方向転換すると、正面にちあきがぼんやり無言で突っ立っている。火事のせいか、彼に出会ったせいかはわからないが、ちひろはちょっと大げさなほどにびっくりしてしまった。
「あー、びっくりしたー。あんたまたぼんやりしてー。先生にちゃんとさよならしてきた?」
また無言で頷くちあき。
「じゃ、帰ろうか」
うんともすんとも言わず、ただぼーっとした表情でちひろの後をついてくる。いつものことながら、ちあきの無口さにはとまどってしまう。
「火事、見たの?」
さっき急いで駆け下りた坂を、今はゆっくりと重い自転車を押しながら上っていく。
ちあきはうつむいたまま首を横に振った。
行きの爽快感とはうってかわって、疲労感がどっと押し寄せてくる。
ちあきは産まれた時からこんなにしゃべらない子だったろうか。よく考えてみると、ちあきと「おしゃべり」らしいことをした覚えが、ちひろにはない。
ちひろは、火事を見たらおねしょするんだよ、と言いかけて、こんな話ちあきに話しても、無言で返されるだけだろうと思ってやめた。
それから数日間、朝は父親が通勤のついでにちあきを送り、夕方はちひろが迎えに行くという生活が続いた。
あいかわらずちあきは一言も口をきかない。そういえば、ちあきと二人きりになるというのは、これまでめったになかったことだったので、幼稚園の行き帰り、数十分でも一緒にいると、今まで気が付かなかったちあきの性格なんかが見えてくる。
無口な子なので、人見知りするのかというとそうでもない。おとなしいが、他人にも自然にとけ込んでいくようなところがある。
それに、何にでも興味を持つ。ぼんやりしているのかと思っていたが、そうではなく、自分の興味のあるものに気を取られているのである。しかもそれは一見なんでもないものなのだが、よく見ると、どうしてこんなことに気がつくのだろう、というようなもので、ちひろはその度に驚かされていた。
例えばちあきは、公園で新聞を読んでくつろいでいる男性を、なぜだかじっと見ていたりする。別に何ということもない老人の、どこにそんなに興味を覚えるのかよくわからない。でも、よく見ると、その人の目がほとんど見えていないことに気づく。新聞は広げてあるだけで、その目は何も見えていないのである。
そういうことが毎日のようにあった。ちひろはあえて、どうしてそんなことに気が付くのかということは訊かなかった。ただ、ちあきには自分の理解できない部分があるのだろうと、漠然とそんなふうに考えていた。
その日、ちあきが興味を示したのは、犬を散歩させている主婦のようだった。いつも見かける人で、やはりちひろには何がそんなに珍しいのかよくわからなかった。
それよりも、ちひろには今気になっていることがある。
この間起こった火事のことだ。
被害事態はたいしたことはなかったが、後で聞いたところによると、ここのところ、あの時のようなボヤ騒ぎがよく起こるというのだ。しかも、それは放火の可能性が高い、という噂だった。
数年前にも、こんな不審火の続いたことがあった。
ちひろの母が死んですぐのことだ。
それはいつも辺りが薄暗くなるころで、起こるのは必ず新興住宅地の建物でだった。あの時も放火魔の仕業だろうと言われていた。
火事が起きた時、「空が真っ赤になる」という母の言葉を思い出したちひろは、二階の窓から空を見た。遠くの空が真っ赤に染まって、暗闇に朱い光が灯っているみたいに見えた。
そのとき、ちひろの胸に初めて、母親の死が真実だという実感が迫ってきたのだ。
結局、犯人は近所の少年で、「悪質ないたずら」であることがわかった。
それにしても、今回の不審火も放火ならば、怪しいのは「あいつ」じゃないだろうか。
あの高校生。全然知らないのに疑うのは悪いけれど、何となくあの不自然な行動が気にかかる。夕方のあんな時間に自転車でふらふらして、ちょっとおかしいとしか思えない。
幼稚園でボヤ騒ぎがあった時からも、彼はしょっちゅう家の前を通った。一日に二度も三度も。ちあきを迎えに行く直前に、はかったように現れるので、怖くてしかたがないのだった。そのくせちひろが家から出ると、すごいスピードで逃げていってしまう。
本当に怪しすぎて、何度か義母に言おうかと思ったが、気をつかわれてしまうのも嫌で言い出せなかった。
幼稚園の往復をするようになって十日余りが経った。
ちあきが、あまりにもいろんなものに気を取られるので、どうしても家に帰るのが遅れる。
特に最近は、緑地公園にさしかかると急に落ち着きがなくなって、必ず足止めされるので、最後には公園の広場で十分程ぼんやり過ごすのが習慣のようになってしまった。
ちあきと二人っきりでいることにも慣れた。この頃では、その時間が一日で一番くつろいでいるような気さえする。
雲がいくつも流れていく。太陽を覆う度に、白く鈍い光を放ちながら。
ちひろは、ここのところ全く雨に降られなかったことを思い出して、降ったら歩いて送り迎えするのかなあ、と考えたりしているうちに、うとうとと眠り込んでしまった。
夢を見ていた。
七つぐらいの少年がいる。こっちを見てる。手にはマッチを持って、今にも火をつけようとしている。ちひろには、それが火事を起こそうとしているんだとわかっていた。
危ないよ、と言いかけて、ちひろは口をつぐんだ。
母親の面影が浮かんだ。
振り返ると、自転車に乗った少年が走り去って行くのが見える。それは、七つの少年ではなく、あの高校生だった。
はっとすると、目の前が真っ赤だった。空が変に赤黒く染まっている。
「ちあき?」
あわてて周囲を見渡すと、ちあきが誰かと二人でいるのが遠くに見えた。
ふたつの影は、朱色の光に照らされて、ゆらゆら揺れている。
目を凝らすと、ちあきと向かい合っているのが、あの少年だとわかった。恐ろしくなってちひろが駆け寄って行こうとすると、いきなり向こうからめらめら燃える炎が襲いかかってきた。
たちまち二人は炎にのまれていく。
ちひろは悲鳴にも似た声をあげて、ちあきの名前を呼んでいた。
 そこで目が覚めた。自分の声で起きたらしい。
そこで目が覚めた。自分の声で起きたらしい。
辺りはすっかり薄暗くなっていた。
「ちあき!?」
ちあきはすぐ側に立っていた。ちひろに背を向けて、上を見上げている。
鰯雲が、夕日のまわりに流れて、茜色に染まっている。それはだんだん色を失って、やがて淡い闇がかぶさっていくのがわかった。
すっかり日が落ちてしまうのを待っていたように、ちあきはこちらを振り向いた。
「誰にも会わなかった?」
ちひろがそうきくと、一言、
「犬が来た」と答えた。
そして、じっとちひろの顔をみつめながら、小さな手で頬に触れてきた。
涙が流れていたのだ。
「ありがと・・」
ちあきの頭を抱えるようにしながら、ちひろはまた泣いていた。
それっきり、あの少年には会わない。
十年前、確かにちひろは少年の放火現場を見た。おそらくいたずら心でやったことだろうが、民家の垣根に放った火が、たちまち燃え上がったときのその目は、不気味に輝いていた。
ちひろはやめるように言おうとしたが、ふと、火事を見てみたい、という気持ちが起こって、それを黙認してしまったのだ。
そして自分の家の二階にかけあがり、火事の光景を眺めていた。
火を放たれた家には幸い人がおらず、怪我人もでなかったものの、後になってちひろは、自分のしたことの恐ろしさを思った。
もしかしたら、捕まった少年が自分のことを警察に言うかもしれない。そんな恐怖がこみ上げてきたのだ。
しかし、何事もなかったように時は経ち、その放火事件は忘れられていった。
ちひろ自身もまた、日々の小さな出来事に気をとられているうち、あの時のことは記憶からすっかり抜け落ちてしまっていたのだ。
どうして今まで忘れていられたのか。そして、あの高校生は一体誰だったのか。
あの夢を見た日、ちひろは思い切って、家の前をうろついていた少年のことを義母にきいてみた。だが、そんな少年は見た事がないと言う。逆に心配されて、しつこくちあきのお迎えをやめるかと言われて困った。
義母が心配するのも無理はないのだ。
放火魔の犯人が、実はあの犬を散歩させていた主婦だとわかったのである。
ちあきが「犬が来た」と言った、あの犬は、その主婦の犬だった。
どういう事情でそうなったかはわからないが、何かが鬱屈していたのだろう。彼女は人通りの少ない通りを狙って、犬が他に気をとられているすきに火を放っていたのだ。
しかしあの日、いつもはおとなしくしているはずの犬が、突如吠えだしたのである。
驚いて彼女が手をゆるめると、犬は狂ったように近所中を走り、吠えまくった。
そうして放火の現場は通行人の目に止まり、主婦はとりおさえられた。
それにしても、ちひろは、ちあきがその主婦に注目していたことを思い出すのだ。どこをどう見て何を思っていたのかは不明だが、あの子には本当に驚かされる。
だがそれは、以前のような、自分と異質なものを持っているように感じた不気味な思いではなかった。
あの時、ちあきが炎にのまれそうになったとき、身をきられるかのような悲しみが、ちひろを襲ったのは確かだった。そして、さしのべられた小さな手からは、暖かいものが流れこんできた。
今思うと、あの自転車の少年は、ちひろの記憶から生まれた幻だったのかもしれない。しかし、本当にいたのかもしれないと思わせるような存在感が彼にはあった。
けれど不思議と、何度も会っていたのにもかかわらず、ちひろは少年の顔が思い出せなかった。
ただ、あの生々しい存在感だけが、母との想い出のように、古びているが懐かしく、ちひろの記憶の抽出の奥へと、そっとしまわれたのだった。
「line」
佐野陽子
梅雨の空気はまだ七月の空を埋め尽くして、電線や窓や道路に覆いかぶさり、頑固なまでに夏が来るのを拒絶していた。外側に向けられて血管をうっすらと浮かばせた手はぼんやりと熱く、意識も窓の外へ一方的に向けられたきり返ってこない。まだ触れていない床の冷たさを求めながら、静子はそこに最高の眠りを求める。この狭い居間も、昼の静寂の中では急におとなしく自身を律して、この空間に水を差すようなことはせず、静子は自分も「もの」なんだなあと、彼らとの共存を快く思った。そして、次第に瞼が閉じられていくと、扇風機の音が少し煩わしく感じられて、しかし、それもまた眠りを深めるように静子の周波数は奪われていった。
静子は、その浮遊感の中で、ひとつの黒い塊をみていた。それは、不安、孤独、焦り、悲しみ、憧憬といったものを内包しており、コツコツ、コツコツ、と音を立てて時折、おしよせてくる塊だった。
 静子の父が遺書を残して家を出ていったのは一週間前のことだった。
静子の父が遺書を残して家を出ていったのは一週間前のことだった。
その日、父はいつものように、自分で作った目玉焼きをトーストにのせたのと、きちんと豆を挽いて淹れたコーヒーを朝食に食べ、そして、なんということもなく「いってきます」と言って、靴を履いて、家を出た。静子もまた、いつものように、父より少し遅く起きて、コーヒーだけ温めて飲み、父の「いってきます」に、顔も見ずに「いってらっしゃい」と答えて送り出した。それがあまりにも日常だったので、後で警察の人に最後の状況を訊かれても、ほんとうに、「いつも通り」としか言いようがなかった。けれど、その日、10時を過ぎた頃に会社の上司から父が出勤していないと電話で知らされ、夜になっても何の連絡もないまま、次の日も父は帰ってこなかった。そして、静子は居間の、貴重品を入れる引き出しの中に、父の手紙を見つけたのだった。それは、茶封筒で、黒いボールペンで、きっちりとした字で、「静子へ」と書いてあった。
封筒は開けなかった。静子は、何か確信のようなものに動かされて、警察に電話をして、また、たった一人の親戚であり父の姉にあたる、千葉に住む叔母に電話をした。
それから、警察に出向いて、捜索願を出した。その後、静子は小さな部屋に入るよう言われ、しばらくしてそこに入って来たのは女の警官だった。その女の警官は、最初家出人の捜索だと思っていたらしく、それなりに同情を見せていたがどこか慣れた手つきで、静子は、時折、彼女が発する簡潔な質問にゆっくりと答えながら、癖毛を黒いゴムで縛ったその婦人警官の手から次々と生まれる大きな字が、薄い紙をどんどん埋めていくのをただ見ているだけだった。そして、静子がその手紙を手渡すと、彼女は開けても良いか断ってから、大きなハサミでざくっとその茶封筒を切って中を確かめた。そしてその時、初めてそれが遺書だとわかったのである。
静子は、しかし、驚かなかった。なんとなくそんな気がしていた。その手紙を最後に、父がどこか知らないところへ行って、二度と帰ってこないという気がしていた。人がある感情を持ちながら書いた字には、その人の気持ちが痛いほど表れているものだ。それが長年見慣れてきた父の字であればなおさらだ。だから、その手紙を開けることはなかった。そして、読む気もしなかった。たとえ死んでも、生きていても、傍にいなければ同じである。
そんな静子とは逆に、その手紙の内容を見たとたん、はっと顔色の変わったその警官は、内線でここ一・二日であがった身元の分からない自殺者を調べてくれ、静子の父がどの死体にも当てはまらないことを喜んでくれた。
「死ぬと言って家出をした方でも、結局踏み切れずに帰ってくる方はたくさんいるから、それを信じて、お父さんが見つかるまで、落ち込まないでがんばって探しましょう。」
そう言って、静子の手を握った。三十代半ばといったかんじの彼女の手は冷たく、少しごわごわしていて、静子の少しほてった若い手にはなんとなく異質だった。その後、もう一人、今度は男の警官が部屋に入ってきて、一通り、状況や親類のことを静子に尋ね、調書を取って、警察はできる限りのことをすると言って、そして静子は家に帰された。
そのことを、家に帰ってからまた、例の親戚へ電話をした。するとその叔母は家に駆けつけてきてくれ、そして静子の前で少し泣いた。叔母は、静子が小さいときからいろいろと面倒を見てくれた、明るくて優しい、思いやりのある人で、どことなく父に似ていた。もし自分に母親がいたら、こんなかんじだろうか、と静子はよく考えたことがある。
ガラスのコップに入れた、つめたい麦茶を飲んで叔母は少し落ち着いた。それからしばらく静子と話したあと、父の知り合いや仕事関係に電話をしたり、その他経済面のことなどを調べてくれると言った。遺書には、それらのことが一切書かれていなかったのだそうだ。叔母は帰り際に、静子も一緒に来るか、と訊いたが、静子はそれを断った。叔母がその夫の母親の介護で忙しいのを知っていたし、また、それよりも、しばらく独りになりたかった。全身が疲れていて、何も考えることができなくなっていた。
静子はそのまま、ジーンズを脱いで、ソファにたおれた。
遠くの方から、何か音がしている。
それが電話のベルの輪郭を持つまでそう時間はかからなかったけれど、静子は、今、電話が鳴ると言うことの重大さがまだ分からず、それによって感じたのは、フローリングに長時間接していた肩や腰がしびれていることと、少し汗ばんだ首が気持ちわるい、ということぐらいだった。しかし、ベルの音がとぎれ、留守を知らせるアナウンスに変わった瞬間、静子は全身の血が逆流したようになった。うずくまったまま体がこわばって動けなかった。そしてそのまま発信音の後を待った。
「…えー、杉本です。今日の時点では、お父さんとみられる死体は見つかっていません。何か連絡があれば、また電話します。」
一週間前調書を取った、女の警察官の声だった。彼女はほぼ毎日こうして電話をくれていた。彼女の声を聞いて静子はほっとし、「親切な人だ」と思った。
今、何時だろう。その前目が覚めていたのはお昼頃だった。扇風機のタイマーはもう止まっていて、部屋は、夜の静けさにつつまれ、無音だった。
プルルッ……
また電話が鳴った。静子は、今度はちゃんと、地球の引力に逆らって体を起こし、少し緊張しながら電話に出た。
「もしもし…」
「あ、藤村です。今、いい?」
静子はその声を聞いてほっとした。父ではない。
静子は、父の赴任先である大阪の大学に通っていた。藤村とは、大学の同じクラブを引退してから、しばらく会っていなかったが、関西弁の、少しハスキーな低い声は、以前と変わらなかった。
「うん、いいよ。あ、ねえ、今何時?」
「え?今…夜の八時。何、寝てたん。ごめん、起こしてしまった?」
相変わらず、優しいイントネーションで話すなぁ。静子は、受話器から、一気に流れ込んできた暖かいエネルギーに、ちょっと泣きそうな感じがした。
「うん。でも、たくさん寝たから大丈夫。」
「そうか、…いや、ちゃうねん、今、部屋の掃除をしとってんけどな、おまえのCDが三枚も出て来てなー。なんちゅーか、あれや、思い出の品々や。」
藤村は一年前まで、静子の彼氏だった人だ。
「…何のCD?」
「うーんとなあ、シェリル・クロウと、STINGと…なんや、BASIAか。」
「何、藤村が持ってたの?それ。さがしてたんだよー。」
父が家出をして一週間経ち、しかも死ぬかも知れないという状況で、自分は藤村との会話を、暖かいと思い、楽しんでいる。私って、どこかおかしい、と静子は思う。
「だから、返したいんやけど…、おまえ、もうあんまり学校来てへんやろ?そやから、暇な日あったら、会わへん?」
「…あー、うん、でも、今家がちょっと大変なの」
何が大変だ、今だってあんまり悲しんだりしてないじゃないか。
「どうしたん、何かあったんかー? …うーん、じゃあ郵便で送ってもいいけど。」
人を心配させることを言ってしまう、そういう自分を静子は好きではなかった。藤村も、多分そのことは知っていて、それを考えると静子は少し苦しくなった。
「ううん、いーよ、ごめん。大したことじゃないんだ。私なら、今からずーっとあいてるよ。バイトも、今休んでるから。」
次の日の午後、大学の近くの喫茶店で、二人は会う約束をした。
静子が五分遅れて店に入ると、藤村はもうコーヒーを飲んでしばらく、という感じだった。その喫茶店はパン屋の中に少しお茶を飲むスペースをとってある、大学やクラブの帰りに二人でよく立ち寄った店だった。
「ごめん、待った? 早くに来てたんだねえ。」
静子がそう言うと、藤村は「相変わらず五分遅れるなぁ」と、楽しそうに、読んでいた本を閉じた。しばらく会っていなかったが、雰囲気や、着ている服の趣味が少し落ち着いてはいたものの、藤村の優しくて無邪気な目は健在だったので、静子はほっとし、自分の目の前にいるその人を少し眩しく思った。
「私も何か買ってくるね。藤村、何か食べる?」
「うーん、俺も一緒に行こうかな」
藤村は席を立って、静子と一緒に、セルフ・サービスのシュークリームやサンドイッチを買った。
外は、梅雨もこれで最後だ、と言わんばかりにはげしく雨が降っている。パン屋の窓やガラス戸は、道路の植木の黄緑色を水滴でにじませて、クーラーで涼しく乾いた室内を明るくてらしていた。二人は、しばらくの間、クラブのこと、音楽のことなどを話し、静子は紅茶をもう一杯飲んだ。
「なんか、人とこんなにしゃべったの、久しぶりっていう感じがする。このごろ寝てばっかりで、私。へんなかんじ。」
「なんでバイト休んでるん」
「うん、ちょっと、嫌なことがあってね。」
静子は、美術科ということもあり、三回生の春ごろから、学科のOBの紹介で絵画モデルのアルバイトをしていた。絵画モデルと言っても、もちろんヌードモデルのことで、カルチャーセンターの絵画教室や、大学の美術の授業で、デッサンの被写体になるのである。静子は、普通の女性より背が高く、あまり美人ではないけれども、色白で髪が少し茶色がかっていて、外を歩いていても自然と人目をひいてしまうような女性だった。そんな体なので脱いでもあまりいやらしくなく、かえってそれが人気であった。だから、かなり仕事は回って来るし、給料もいいので、そのお金でギターを買って、家で曲を作って歌ったりしていた。静子は、そんな生活に満足していたし、当時の藤村も、自分の下宿によく寝泊まりしていた静子と、二人ですごす時間を大切に思い、楽しんでいた。
藤村と別れたのは、静子が事務所の人を好きになってしまったからだった。しかしそれは、よくある一時の思いこみで、静子は藤村と別れたことを後悔して落ち込んだ時期もあったが、それもまた経験、と考えた。しばらくして藤村には、静子も知っている後輩の彼女ができたと聞いて、あきらめもついた。それでも、そのアルバイトは続けていた、そんな時に起こったことだった。担当先の教師に襲われかけたのである。静子が、このことを人に話したのは初めてだった。
「それ、大丈夫やったんか」
「うん、でもしばらくやりたくなくて休んでる。やっぱり、駄目なのかなあ、ああいうのは」
「まあね、ギリギリだめだったのかもしれんね。」
藤村はしばらく煙草を持ったままだったので、灰が長くなって今にも落ちそうだったのを一度だけ深く吸って、火を消した。
「ほな……そろそろ行こか。家まで送るわ」
藤村の目が急に遠くなってしまったような気がして、静子は何故かとても悲しくなった。バイトのことは言わなければ良かったのかもしれない。そうしたらもう少し、この心地良い空間で藤村と話すことができただろう。外はあんなに蒸し暑そうで、雨まで降っているというのに、出ていかなければならないのがいやだった。
店のドアを開けると、アスファルトと土と草が蒸発した雨のにおいに包まれて、二人はぬれて色が濃くなった風景のなかを走って駐車場へ行き、車に乗った。
静子は車の中で、話すことを一生懸命さがした。しかし、感情も記憶も蓋をとしたようになっていて何も見つからなかった。そうして、ワイパーの動きだけを目で追っているうちに、助手席で静子は眠ってしまった。
「着いたで。起きーや。」
藤村の手が頭に触れたとき、静子は夢を見ていた。よく憶えていないけれどとても淋しい気持ちが強く残る夢だった。
「夢…見てた。」
空はもう青黒くなって、雨は止んでいた。ワイパーも止まっている。
「寝過ぎやろ、それ。そこまで寝る奴もあんまりおらんな。…でも、なんか懐かしい顔やったわ。かわいかったで。うん。」
「藤村、お茶でも飲んでいく?」
静子は、何故かとても藤村と離れたくなくなり、車のドアを開ける前にそう聞いた。へんに誘っているような、少し後ろめたい感じもしたけれど、実際、静子が自分の感情を本当に素直に出せるのは、いつもこういう瞬間だった。
「いや、やめとくわ。」
藤村は、しかし、あっさりとそう言った。
静子の頭は急に冷たくなった。「そう、じゃあまたね。」と、急いでドアを開け、できるだけきれいに車を降りたはずなのに、ミュールが脱げてシートの下に残ってしまった。
「どうしたん、落ち着きや」
笑いながら、藤村はそれを拾って静子に渡した。静子はそれを受け取ると、照れ隠しがバレバレの自分が恥ずかしくなった。早く立ち去りたい。
「じゃあ、また」
もう一度言ってから、静子は、藤村のワゴンが走り出すのを見送らないで走った。マンションのドアを開けるまで、もう、無酸素運動だった。
家に入っても、誰もいない。部屋の居間には、出ていったままのコーヒーカップと着古したワンピースがあるだけだ。父の不在が、部屋中に日毎にどんどん浸食してくる。その圧倒的な淋しさに、静子は訳が分からなくなった。泣けばいいのに、涙や、具体的な感情が遠くて、ただ息が詰まる。それを紛らわそうと、いつものように横になった。しかし、眠ろうとしても、さっきみた夢の淋しい感覚が蘇り、却って苦しさは増していく。
静子は、父が大切にしていたバランタインを出してきた。昔から、たまに眠れないときそうしていたように、グラスに氷を入れて、それを注いだ。少しずつ喉に通すと、その飴色のウィスキーはさすように冷たくて、胃に熱くとどく感覚は静子を落ち着かせた。
突然、玄関のベルが部屋に響いた。それはあまりにも久しぶりの音だった。静子がドアの穴をのぞくと、外には叔母が立っていた。
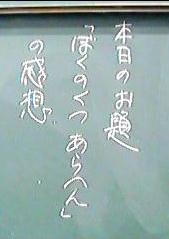 「ひさしぶり。しっかりやってる?」
「ひさしぶり。しっかりやってる?」
叔母もウィスキーを飲んで、以前来たときよりも冷静な目で静子を見た。叔母は父の残した預金などについて調べてくれたらしい。そして、父の年収から考えると信じられないほどの預金があり、また、名義は全て静子になっていたと、報告した。叔母は、静子が一人でも生活できるように前から準備していたのだろうと言った。
「私が大人になるのを待っていたみたい。」
「そうかもしれないね。」
しばらくの間、二人は何も言わずに黙って飲んだ。
「カマンベールチーズとクラッカーがあるから、何か作ろうか。」
今日は飲もう、という勢いで、静子は言った。藤村の下宿でそうだったように、二人だけでじっくり過ごす夜は、いつも温かい何かが心のなかに溢れてくる。静子がクラッカーを出しているあいだに、叔母は冷蔵庫をあけて、軽く食べられるものを探した。
「何にもないねぇ。」叔母はそう言って笑った。
その時、電話が鳴った。
静子は、すぐに受話器を取った。例の女性の警察官だった。
三日前に、父を見かけた人がいるらしいのだ。父が出張でよく行っていた舞鶴のラーメン屋に、父が来ていたという。そこの店長と父は仲が良かったらしく、間違いはないということだった。静子は急いでメモをとった。
彼女は静子よりもずっと現実的に、父のことを探して行動してくれていた。静子は罪悪感のようなものを感じ、この気持ちは何だろうと考えていた。
「すぐ行こう。」
叔母は言った。
「舞鶴って、京都だよね。ここは大阪だから、車で行けばすぐね。タクシーでもいいけど、誰か車出せる人、いる?」
叔母は明らかに藤村のことを言っていた。静子は彼のことをよく叔母に話していたから覚えていたのだろう。しかし、今日の静子にとってそれは痛いことばだった。
「ううん、いないから。タクシーで行くわ。でも、私一人で行くから叔母さん帰っていいよ。ごめんね、大阪まで来させて。」
さっきの警官や叔母をみていると、本当にそんな気持ちになった。
「何言ってるの、叔母さんも一緒に行くわよ。」
「ちがうよ、私、もっと責任をもって行動しないといけないような気がするの。今、一人で考えないと、これから先も私はこのままだと思う。」
静子は、自分がこんなことを言うなんて、口に出るまで思っていなかったが、口に出したことによって、自分の気持ちが現実味を帯びてきた。さっき感じた絶対的な淋しさと、叔母や警官の暖かさというものの間に、静子はひとつの答を見つけたような気がしたのだ。
叔母を説得して、静子は一人で舞鶴に行くことにした。何かあったらいつでも呼びなさい、と言って叔母は帰っていった。静子は部屋で一人になったが、さっきのように、沈黙や淋しさに圧倒されることはなかった。どちらかというと、大きなエネルギーが暖かく身体を動かしてくれるのを快く感じて、手早く準備を済ませると、急いで家を出ようとした。
また電話が鳴った。
「おう。今からドライブ行こうや」
藤村だった。
「ごめん、今から出かけるの。また今度ね」
静子はなぜかとても幸せな気分になった。今なら藤村と素直に話せるだろう。
「じゃあ、送るからさ。ていうか、おまえの家までもう来てんねん。」
「え」
「ごめんな、あつかましいな俺は。そやけど、どこでも行くで」
「ふふ、じゃあ、舞鶴まで行ってくれる?」
夜の高速道路はすいていて、藤村の車はエンジンの静かな低音を立てながら、STINGの声と共鳴するように滑らかなカーブを描いている。それが二人の時空間を弛緩させ、精神が、身体よりもフロントガラスやメーターの光にその実態を映しているようだった。その中で、静子は藤村に父の失踪や、死んだ母のことを話した。藤村は、ただ前を見てその声を聞き、たまに「うん」と低い声で返事をした。車は100キロを越したスピードで走っているのに、その中はまるで時間がゆったりと浮遊しているようだった。静子は、話しつづけた。
そうしているうちに、車は料金所を抜け、高速道路よりも空いている一般道路におりた。時計を見ると、午前2時だった。
「もう、海の近くやで。」
藤村はそう言った。こどものころ枕元で絵本を読んでくれた父の声みたいに。
静子は急に緊張してきた。父の消息を知る者に会う。その実感は、ざくざくと押し寄せてきた。父がいなくなって十日も経っていないのに、もう随分会っていない気がした。
「『母を訪ねて三千里』のマルコって、こんな気持ちかな」
藤村は、かもなぁ、というふうに首をかしげた。
そのラーメン屋は、舞鶴の旅館街の少し奥まったところにあった。深夜営業をしていて、よくある黄色い看板のネオンが光っていた。路肩に車を止め、二人は車を降りた。まだ海は見えなかったけれど、海の確かな存在感に包まれている町だった。「お腹減ったし、先にラーメン食べようよ。」
そう言って、二人はラーメンを食べた。
「美味しいとは言えんなぁ、これは。」
「そうだね…」
こんなにお腹がすいて、しかも深夜に食べているのにこの程度では、普通の時ならまず食べようとは思わないだろう。父は、このラーメンを何回食べたんだろうか。その店は、店長らしい五十歳くらいのおじさんと、その奥さんらしい人でやっていた。静子は、その美味しいとは言えないラーメンを食べてから、カウンターごしに、茹でためんの湯気に顔をしかめているそのおじさんに、父の写真を見せ、話を聞いてみた。するとおじさんは、はじめ湯気の中でけげんな顔をしていたが、すぐに父のことを話してくれた。
「かんじのいいおじさんやったな。」
藤村は、コンクリートの上を歩きながら言った。
「そうだね」
舞鶴の港は、若狭湾から出航するであろう巨大なフェリーと、妙にライトアップされたターミナルが、ばかでかい駐車場と海に線を引いていた。夜明けが迫った港には、また小雨が降り始めていた。藤村と静子は、それらに比べるととても小さな歩幅で、夜明けの海に近づいていった。海辺で降る雨はまた違った匂いを孕んでいて、肌寒い早朝の空気とよくあっている。
「お父さん、あのフェリーに乗って北海道へ行ったのかな。」
空と海が同じ青い色をして二人を包み込んでいた。その深すぎる青のなかでは、静子や藤村の声は響いてもすぐ消えてしまうのだった。
そのラーメン屋のおじさんの話によると、静子の父が失踪した原因は、静子だった。年々母に似てくる静子を、父は娘として愛せなくなっていた。静子と離れなければ、自分の全てが壊れてしまうと言っていたらしい。死ぬつもりで家を出たが、それも違うと考え、しかし自分の存在を消したい。そううち明けた父に、おじさんは北海道の農場を経営する友人を紹介したらしい。そして、父は今、そこで暮らし始めているそうだ。
静子は、父の気持ちには気づいていなかった。家にいるときはいつも何も考えずに過ごしていたし、よく外泊をしたし、食事と寝るために家があるようなものだった。今はそれを、少し後悔する。もっと父と話す時間を持てばよかったと、思う。
永遠に取り戻せないであろう、親と子の、時間。
父は、どんな人だったのだろう。
「静子、もういっかい、僕と一緒に暮らせへん?」
藤村がそう言った。その声が、あまりにも空と海の境界線に向かって響いていって、それに小雨と波の音で世界がもう十分すぎるほど満ちていたので、静子は返事ができなかった。
そのかわりに、涙がでてきた。
人は、絶対的な何かに直接触れたとき、涙が出るものなのかもしれない。
静子はその手触りを、確実に感じていた。大人になっていくというのは、優しくなるということなのだ。大切な人が一人ずつ増えて、その優しさに応えること。
「いつか、北海道へ、このフェリーに乗っていこうね。」
気づくと目の前の海がオレンジ色に縁取られていた。夏の匂いのする朝だった。
「そろそろ帰りますか。」
藤村は、静子の手をとって、朝日に起こされた山並みのほうへ向きなおした。だだっ広い駐車場の端で藤村の車が、ぽつんと二人を待っていた。