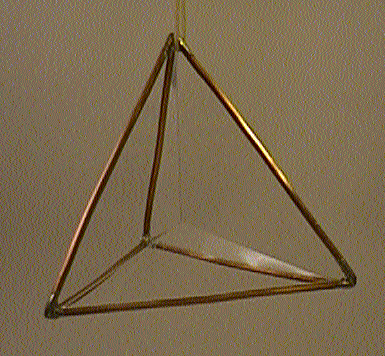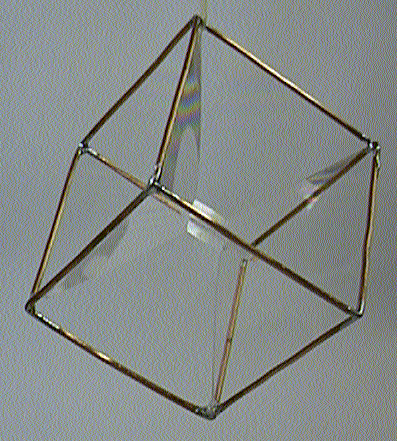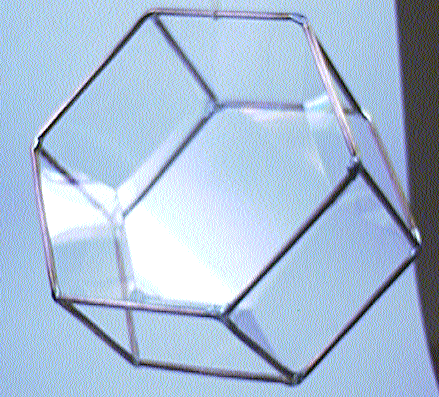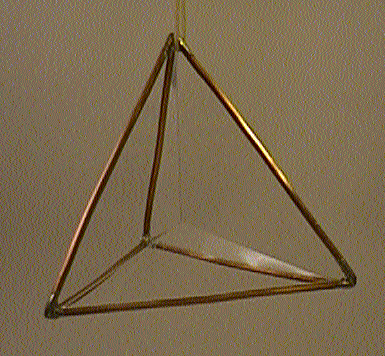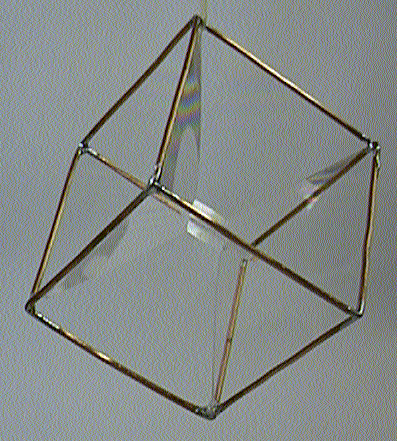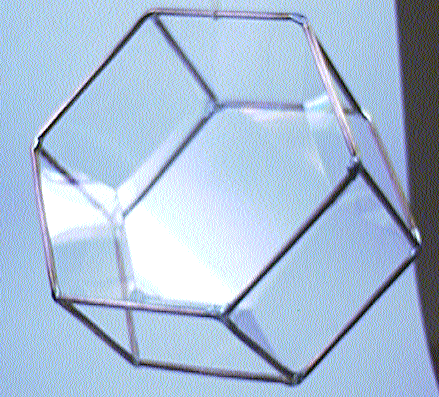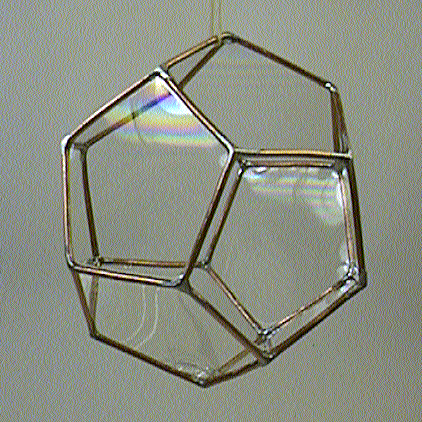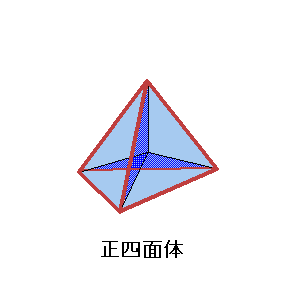膜の「意志」!?の解説
- Q9:銅線をきれいに磨くのはのはなぜ?
- A9:表面張力は微妙な変化でも,その力に大きな影響を与える。
- 今回の実験は,銅線で出来た立体に膜を張らせるものでありその膜がなるべく割れにくくなるように磨くのです。
Q10:立体にはどんな膜ができるの?
- 銅線で出来た様々な立体をゆっくりと石けん液の入った容器から取り出すと次のような膜が出来たはず。もし,写真と異なる膜が出来ていたのならば,おそらくその立体のすべての辺,頂点を含んでいない膜になっているはずです。
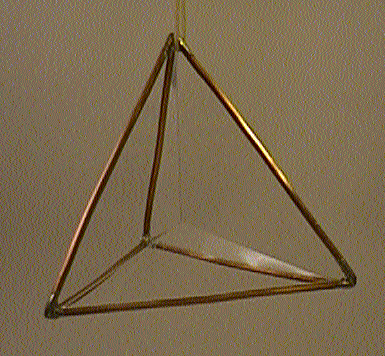
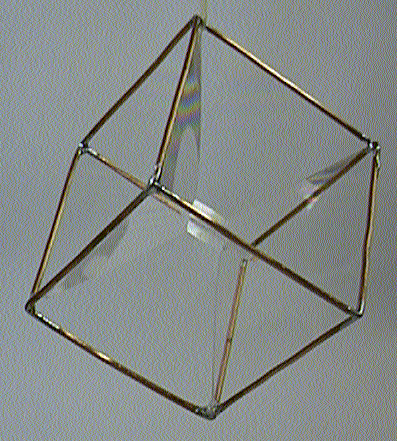
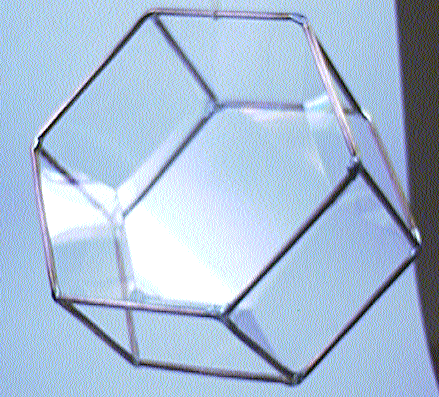
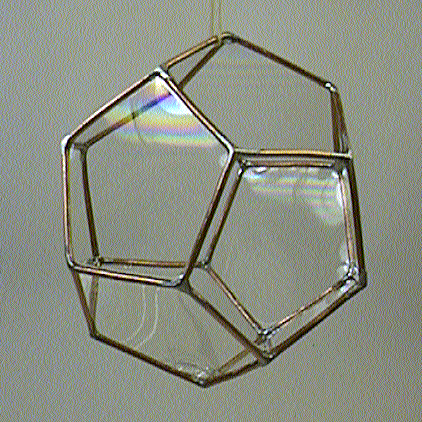
このような膜が出来るのは,立体に出来る膜には表面張力が働いており,膜が出来るだけ小さな面積で済むようにしようとしているからなのです。
写真だけでは,膜の形状がわかりにくいので図で描いてみました。
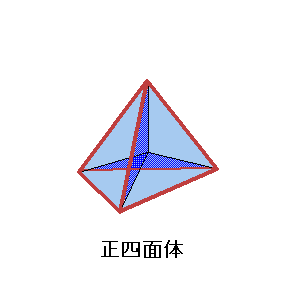



この立体に出来る膜の問題を「プラトーの問題」という。この問題に関しては,
こちら
を見て下さい。
もとに戻る
「表面張力を科学しよう」に戻る
参考文献
小暮陽三 著:身近な教養物理,森北出版
内藤卯三郎 水野国太郎 池本義夫 著:物理学実験法講義(上巻),培風館
立花太郎 著:シャボン玉(その黒い膜の秘密),中央公論社