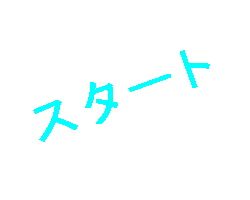| 沸とうするとは? 「沸とう」という言葉を辞書で引くと、「液体がその内部で気化する現象」と書いてある。沸点(沸とうが起こるときの温度)に達することで、液体の表面だけでなく(表面で気化するのを蒸発という。)、内部でも液体から気体に変わろうとする現象が起こるのを沸とうというのです。 | ||
|---|---|---|
| どういう時に沸とうは起こるのか? 一言で言えば、外気圧=蒸気圧になった時に沸とうは始まります。 これでは何のことだか分からないのでもう少し詳しく説明します。 まず、蒸気圧についてですが、蒸気圧とは同じ物質の気体と液体(または固体)が共存しているときの気体が押す圧力のことです。温度が高くなるにつれて、気体に変わろうとする分子が増えるので蒸気圧は大きくなります。 そこで水について考えてみましょう。水の蒸気圧と温度の関係は下の表のとおりです。 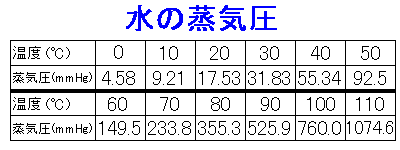 水は1気圧(760.0mmHg)の状況下において100℃以下では蒸気圧が外気圧よりも小さいために沸とうすることができません。水が内部から気化しようとするのを外気圧がおさえているのです。しかし、100℃に達すると外気圧と蒸気圧が等しくなって、内部でも蒸発が起こるのです。これが沸とうという現象なのです。 では、実験で起こった現象はどういうことなのでしょう? | ||
フラスコ内部で何が起こったのか?
| ||
| ちょこっとメモ 高い山の上で地上で炊くのと同じようにご飯を炊くとうまく炊けません。なぜかというと、山の上では地上よりも気圧が低いので、上で説明したように水の沸点が100℃以下になってしまいます。そのために沸とうしていてもお米にうまく火が入らないのです。 それとは逆に圧力鍋を使って調理をすると、鍋の中の圧力が上がることで、沸点が100℃よりも高くなり、短時間で調理ができるのです。短時間で肉とかも柔らかくなるので、煮込み料理などに圧力鍋をよく使います。 |