��㋳���w ����w���_�Q ��u���ɂ�� �����K��W
| �v�����[�O | 22109 |
| �l�͗������� | 22108 |
| ���~�i���G | 22110 |
| It's a wonderful world ! | 22107 |
| �͂��� | 22101 |
�u�E�E�E���ɂ����v
�@����͌��ɏo�����Ƃ͂��납�A�v�����Ƃ���������Ȃ��������t�̂͂��������B�����Ď��̍ł������Ȍ��t�B
�@�ł����̂Ƃ�����͉���������Ă����B���ɂ����Ƃ��Ɏ��˂Ȃ��Ƃ������Ƃ��ł��s�K�Ȃ��Ƃ̂悤�Ɏv��ꂽ�B
�@�܂Ԃ����B����ɉ������������B�ׂɒN������H�N�H����E�E�E�����͂ǂ��H�������A�v���o�����I�ǂ��������B�ǂ����œ|�ꍞ�̂��Ǝv������B���āA�S�R�ǂ��Ȃ�ĂȂ��I�悭�m������Ȃ��j�̕����ł��ɒ����}���Ă��܂����̂��B
�@�q�b�ׂ̗Ŕ���Ȃقǂɂ���₩�Ȓ��̌����炢���ς��ɗ��тȂ���Q�������ĂĂ���͖̂k��W�ꂾ�B�q�b�Ɠ����o�C�g��œ�N��̂m�吶�B������ӂł͖��̒ʂ��������̂m��ɒʂ��W��͊m���ɓ��̂����l���B�L�c�q�b�͂r�吶�B���������ł��������x���͉��������B�q�b����l�Ŏ��Ԃ����Ă��܂��Ă���ƁA�悤�₭�W����ڂ��o�܂����B
�u���͂悤�B�����ˁB�v
�������Ȑ��B����Ȑ��o���B
�u���A���͂悤�������܂��B�Ȃ��������ł��ˁB�܂��Q�ĂĂ����ł���B�v
�u����A���v�B�����N�����B�����͉����\��Ȃ��́H�v
�u���A�͂��B�v
�u����A����������Ƃ�����肵�Ă����H���A�тł��H���ɍs�������B�v
���H���̏�܂��U�������Ă����́H
�u�����A�����A��܂��B���ז����Ă��݂܂���B�v
�낭�ɉ��ς����Ȃ��ŏo�ė��Ă��܂����B����قǍQ�ĂĂ������낤���H����A�����ł��Ȃ��B�����ȂƂ���A���܂�悭�o���Ă��Ȃ��B�q�b�̖ڂ̑O�𑋉z���ɕ����������Ō�����Ȃ��X�����߂������Ă����B�Ƃ͂������̂́A�ق�̐����ԑO�͔��ɗ���Ă����̂����B�����i�F�ł��i�s�������Ⴆ����ȂɌ��������ς����̂��낤���H����A�����͂��ꂾ���ł͂Ȃ��͂����B�q�b�̐g���̂������A�������߂݂̒�v�ɂ��̐g���ς˂Ȃ���A�q�b�͈ꍏ�������m��Ȃ��X���甲���o���ĉƂɋA�肽���Ɗ肤�����Ȃ������B
�@�Z���\�O���y�j���B�y�j���͈�T�Ԃ̂����Œq�b�ƍW�ꂪ�B��o�C�g��Ŋ�����킹����������B���̓��̃o�C�g������A�W��͎����̃o�C�N�ʼnƂ܂ő���ƒq�b��U���Ă����B���͒q�b���o�C�N�̖Ƌ��������Ă���B�o�C�N�D���Ȃ̂��B�����b�ł͂Ȃ��B�o�C�g�悩��Ƃ܂ł͂��������Ȃ����A�y���C�����ő����Ă��炤���Ƃɂ����B
�@������������q�b�ɂ͒j�F�B�����������B�Ƃ��������A�q�b���g���F�B�Ƃ�������j�F�B�Ƃ���ق����C���y�������̂��B���������̍W��̂��Ƃ��g�j���h�Ƃ��Ă͌��Ă��Ȃ������B�����炱�������ɗU���ɂ̂��Ă��܂����̂��B
�@�o�C�N�͑O�ɏ���Ă����ɏ���Ă��y�����B�o�C�g�悩��q�b����l��炵�����Ă���}���V�����܂ł̂ق�̐����A�q�b�͖����������B�����^�]�҂��N���Ȃ�Ė��ł͂Ȃ������B���낻�돋���Ȃ��Ă����Ƃ���ɕ����S�n�悭�q�b�̖j�łĂ͋����Ă������B
�u���肪�Ƃ��������܂����B�v
�u����A������B���o�C�N�ő���̍D�������B�v
�u�����͂����l�ł����B�C�����ċA���Ă��������ˁB�v
�u����B����܂����x�B���A���̓y�j�o�C�g���I�������ɔтł��H���ɍs������B�����邩��B�v
�u���A������ł����H���肪�Ƃ��������܂��B�y���݂ɂ��Ă܂��B�v
�܂�����q�b�͊ȒP�ɕԎ������Ă��܂����B
�@�Z����\���y�j���B�o�C�g���I���ƁA�W��͒q�b���o�C�g��Ɏc�����܂܈�x�ƂɋA�����B�Ăђq�b�̑O�Ɍ��ꂽ�W��͕��i�����Ȃ����t�Ȋi�D�ŎԂ̃n���h���������Ă����B
�u����āB�v
���������ĉ^�]�Ȃɍ������܂���Ȃ̃h�A���J����B
�u���肢���܂��B�v
�u�K���ɔтł��H���āA���̌㉴�̒m���Ă邢�������̃o�[�ɍs�����B�v
�u���A�͂��B�v
��l���悹�����������y���ɑ���o���B�ǂꂭ�炢���������낤���B�������łɒq�b�̒m��Ȃ��y�n�ł��邱�Ƃ͊m���������B�����ē�l�̓X�p�Q�b�e�B���X�̒��ԏ�ɍ~�藧�����B
�@�ԓ��ł��X���ł��s�v�c�Ɠ�l�̉�b���r��邱�Ƃ͂Ȃ������B�T�Ɉ��A�������o�C�g��ł������Ȃ���������A����Ȃɉ�b���e�ނƂ��v���Ȃ��������B�W��͂���܂Œq�b�������Ă��������Ŗ����z�ȃC���[�W�Ƃ͈قȂ�A�悭�b�����Ă��ꂽ�B�������ƂĂ��y�������ɁB������v�킸�����������Ă��܂��B�s�v�c�ȗ͂������Ă���l���Ǝv�����B�ł��q�b�ɂƂ��Ă͂�͂肻��ȏ�̑��݂ł͂Ȃ������B�{���͂悭�b���l�������B�Ƃ������z���������Ȃ������B
�@��x�ڂɎԂ��~�肽�Ƃ��A�q�b�̖ڂɍW�ꂪ���������͋C�̂����V���b�g�o�[���f���Ă����B���ɓ���₢�Ȃ⊵�ꂽ�����Œ���������W��B�Ȃɂ��Ȃ艌�����ӂ����W��B����ł��V���b�g�o�[�̕��͋C�Ƃ͗����ɁA�q�b�̖ڂɂ̓o�C�g��̐�y�Ƃ������݈ȏ�ɉf�邱�Ƃ��Ȃ��W�ꂪ�����B
�@�q�b�͂���قǂ������D���Ƃ�����ł͂Ȃ������B���������߂Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B���̓��������ɂ������Ƃ͈قȂ�F�N�₩�ȃJ�N�e����ڂ̑O�ɂ��Ă����B�ӂƍW��̃O���X������Ɛ�قǂ��炠�܂�ω����Ȃ��B
�u���A�^�]���邩�炳�B�v
�u���A�������B����A�����E�E�E�E�E�E�B�v
�u���ŁH����������������ǂ�ǂ����ł�B���̂��Ƃ͋C�ɂ��Ȃ��Ă�������B�v
����Ȃ��Ƃ�����ꂽ���Ĉ�l�ŃK�u�K�u���߂Ȃ����E�E�E�B�Ƃ͌����Ȃ��炿�������O�t�ڂ̒����͏I���Ă���̂��B�o�C�g�ł̔�����`���āA�q�b�͂����ɋC�����悭�Ȃ��Ă����B�C�t���Θb��͉ߋ��̗����o���ɕς���Ă����B���ȓW�J���Ǝv���Ȃ������y��ڂ̑O�ɂ���Ƙb���Ȃ�������Ȃ��C�������B
�u�O�̔ގ��͓�ゾ������ł���B����������l��炵�ŁB�ŏ��͂悩������ł����ǂˁA�����Ⴄ�Ȃ��Ďv�����u�ԋ}�Ɍ��ɂȂ��Ă��܂��āB���ǂ����ɏI������Ⴂ�܂����B�v
�u�ւ��B�Ȃ��̐l���킢�������ˁB�Ȃ�āB�ł��D����������ł���H�v
�u���ꂪ�A����������Ȃ���ł��B���܂�D������Ȃ������̂����B����ꂽ����I�b�P�[�������Ċ������������B�ł��L�X�͍D���ł�����B�v
���������Ă�낤�B���������Ď������Ă�H�����A�ł������x���B
�u�L�X�H�L�X�D���ȂB�v
���������A�肽���B�ڂ̑O�Ŋy�������ɘb���W��B�ł����͊y�����Ȃ��B���̊Ԃɂ����z���𑱂��Ă��鎩���������B
�u���������H����A���낻��A������B�v
�u�͂��B�����������܂ł��B�v
�����A���ĐQ�悤�B���̂Ƃ��q�b�͋~���̏��_���͂�����Ƒ������悤�Ɏv�����B
�@�łɕ����Ԕ������B���̑т������c���Č���Ă͏�����r���̐��X�B���̊Ԃɂ���l���悹���������͒q�b�ƕt�������̒������i�̒��𑖂��Ă����B����ƋA���ė��ꂽ�Ƃ������g������C�ɒq�b����芪�����B
�u���肪�Ƃ��������܂����B���₷�݂Ȃ����B�v
�ԓ�����o�悤�Ƃ������̂Ƃ��A�q�b�͂��̐����͂Řr�����܂ꂽ�B
�u���H�v
���������ĐU��Ԃ����u�ԁA�~���̏��_�ł͂Ȃ��A�W��̐O���q�b�̂����߂炦�Ă����B

�@�Z����\������j���B�L�����p�X����F�����ƕ����Ă����q�b�̌g�т��k�����B
�u�E�E�E�B�v
�u�ǂ������́H�v
���ʂ����鎿�₪�q�b�̒��̖ʓ|�������v�����ő���Ɉ����o�����C�������B
�u����ꂽ�B�v
�u���H�N�H���ꂥ�H�v
����ς�ʓ|�������B
�u�o�C�g��̐�y�B�v
�u�����Ȃ��B�ǂ�Ȑl�H�t�������́H�v
�u�債���l����Ȃ���B�����ڕ|�����A�����z�ł݂�Ȃɂ͂��܂�D����ĂȂ������B�E�E�E�ӊO�Ƃ���Ȃ�Ȃ��������ǁB�ł��D���ł͂Ȃ��ȁB���Ǖʂɂ��������Ċ���������B�_����������ʂ��������B�v
�u�܂�����Ȃ��ƌ����Ă�B�v
�����ȏΊ�𑗂��Ă����F�����B�ł����͏�肭�Ί�����Ȃ��ł���B�������Ȃ��B�����W��̉Ƃ����w�ɗ����Ȃ�āB
�@�������킸�ɍW��̉Ƃ���o�āA�d�Ԃɔ�я�����B����Ⴀ�W��͋C�ɂȂ��ˁB�o�C�N�ɂ���H���ɂ���A�ȒP�ɗU���ɏ���Ă����N���̏��B�C�P��Ǝv���ē��R����ˁB
<�I�����b�e�h�E�C�E�J���P�C�H>
<�T�@�H�i���f�V���E�l�B>
<�T�@�b�e�B�c�L�A���i�C�H>
<�E�E�E�C�C�f�X���B>
���`���A�܂��ςȎn�܂肾�B��w�ɓ����Ă��炱��Ȃ̂�����B�܂������I������Ⴄ��B��w�ɂȂ������l�̗������悤�Ȃ�Ė������`���Ă����͂ǂ��ɂ������낤�H�F��������Ƃ��Ȃ�Ƃ������Ēf������̂ɂ���Ȃ��Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�āB�ǂ����ɂƂ��Ă��ň�����E�E�E�B
�@���E�E�E�H�����������������ł����܂ŗ����Ǝv�����̂ɁB�������킸�ɉƂ��o�čs�����܂ܘA������������B�U���ɂ͂�������Ă��邵�A�Ȃ��Ȃ��b���e��ł����A���\�C�P�Ă�Ǝv���Ă��̂ɁB�����悻��B�ł��������Ă��ꂽ�є����������Ȃ��B�Ȃ��A�C�c�A���N�o�C�g��ɏ��߂ė������������Ȃ��Ă������B��������A���߂ăo�C�g��Ɍ��ꂽ�Ƃ��͒j���Ǝv������B
�u�������āI�k��I�����Ă�̂��H�v
�u�����B���܂�B���H�v
�u���O�A���l���Ă�B�������^�������Ȋ炵�āB�v
�u�������͗]�v����B���Ƃ������B����A�ޏ��ł��邩�����ĂˁB�v
�u�́H�����悻��B���O���̊ԕʂꂽ���������B�������H�v
�u����B�܂�������Ȃ����ǁA���ƈꉟ�����Ċ������ȁB�v
�u�ւ��B���O���悭����ȁB�ŁA���̎q�����H�v
�u����B�v
�u�m��H�v
�u�r��B�v
�u����̂r�吶�Ȃ�Ăǂ��Œm�荇������H�v
�u�o�C�g��B�v
�u�ւ��B�ŁA�@�F�����̘b���������ɐ^�ʖڂɍŌ�́g�����h���l���Ă���ĖB�v
�u�܁A����ȂƂ��납�ȁB�v
<�I�����b�e�h�E�C�E�J���P�C�H>
<�T�@�H�i���f�V���E�l�B>
<�T�A�b�e�B�c�L�A���i�C�H>
<�E�E�E�C�C�f�X���B>
���ꂪ�^�ʖڂɍl������������E�E�E�B�����ł����������ʂ��B<�C�C�f�X��>���āB����ɂ��Ă��ςȃ��c�B���܂ł���ȃ^�C�v���Ȃ��������B�O�̔ޏ��Ƃ̒Z���t���������I����������Ȃ̂ɁA�܂������ɏI����Ă��܂������ȁE�E�E�B�܂��������B�����傤�Ǒދ��Ȏ������������B
�u�͂��B�v
�u������H�v
�u���̊Ԃ̃N���X�}�X�̂��Ԃ��B�v
�u�ق�ƁH���肪�Ƃ��B�Ă������H�v
�u�ǂ����B�C�ɓ����Ă��炦��Ƃ������ǁE�E�E�B�v
���ς�炸�W��̓��}���`�b�N�j����B�ł�����ȕ�����₷���Ƃ��낪�q�ǂ��݂����ł��킢�������B�ԂŁ~�~�R�ɍs�����Ȃ�Ė�i���o�b�N�Ƀv���[���g�̂��Ԃ��n���܂����ė\�����Ă�悤�Ȃ���Ȃ��B
�u�킠�B�Ȃ����������B���肪�Ƃ��B�v
�u���Ă݂Ă�B���A�������Ă�����B�v
�u�ǂ��H�v
�u����B���������B�v
�u�ق�ƁH���肪�Ƃ��B�v
�{���͗��肢���ς��ɂ����������Ȗ�i�̂����ʼn����悭������Ȃ������B�����A���͂�����ł��ł���̂ɁA�����ɂȂ�Ƌ}�ɐl���ς�����悤�ɂ������Ȃ铪�ŕK���ɍl���Ă��ꂽ���Ƃ������������B
�@�Ȃ������čW��̐Q������߂Č���������������N���o���Ă���B�����ɏI��邾�낤�Ɨ\�z���Ă����t���������Ȃ��Ȃ��������̂ł͂Ȃ��B���݂������̕s���͂��邯�ǁA���ł��b�����������Č��߂����A������v����邱�Ƃɂ���ĉ�������Ă��镔��������̂ł͂Ȃ����Ǝv������ɂȂ��Ă����B
�u����A�������N���t�������Ă�ˁB�v
��i��ڂ̑O�ɂ��Ă��邩�炩�A�ڂ��P�����čW�ꂪ�Âɘb���n�߂��B
�u����B����������Ȃɑ����Ƃ͎v���ĂȂ�������B�v
�u���H�܂��ŁH���͉����B��w�����Ă��牽�l���ƕt�������Ă������ǁA�ǂ���Z���Ă��A�����O�����A���낻��^�ʖڂɕt��������l���������ȂƎv���Ă���ˁB�v
�o���I���ӂ̂����炳�܂ȑ䎌�B�W��̕\��Ί炩�ǂ��������ʂł��Ȃ��قnj��ƈł̈ꌩ�ΏƓI�Ɍ�����R���r�����̖ڂ𑨂��ė����Ȃ��B�ł����ɂ͕�����B�W��̕\��B���N���o�����B���ɂƂ��Ă��v���Ԃ�̒����t�������B�����Ɠ��Ƃ������Ƃ�Y�ꂳ���邢���̏Ί�ł����������Ă���B
�u���A�q�b�Ƃ������炱�̐撷���t�������Ă����������Ďv���B����ŁA���݂��ɑ�w�𑲋Ƃ��āA�����҂���悤�ɂȂ�����ꌬ�Ƃ��ďZ�݂����ȁB�q�b�͂����v��Ȃ��H�v
����n�̎��⍢���ˁB�m���ɍW��̂��Ƃ͂������D�������ǁA���܂ŕt�������Ă��邩�Ȃ�ĕ�����Ȃ����A���̐�܂��܂���肽���������邵�B�������������Ȃ�Ă܂��܂��l�������ƂȂ���B
�u�����ˁE�E�E�B�v
�u����B���ꂩ�����낵���ˁB�v
����Ȏ��̍W��̏Ί�ɂ����������ˁE�E�E�B
�u�k��N�H���v���H�v
�u�����B���߂�B������炿����ƕ��ׂ��ۂ��āB���H�v
�u����̎����̃��|�[�g�Ȃ��ǂ��A��ǂ����Ă�������Ȃ��Ƃ��낪����́B�����Ă����H�v
���ς�炸�����Ƃ肵���b�������ȁB�q�b�Ƃ͑�Ⴂ���B
�u����B������B�ǂ��H�v
�u�����B���̐��l���������ʂƂǂ����Ă�����Ȃ��́B�v
���ꂢ�ɓh��ꂽ�܂��ڗ��w�ŕK���ɍ����Ă͂��邪����ł͓���W��̖ڂɂƂǂ��Ȃ��B
�u�E�E�E�B����A�����Ԉ���Ă��B�v
�u���H�ق�Ƃ��H�v
���������Ȃ��璷���s�A�X���Ԃ牺���Đ^���͍W��Ɋ���߂Â��Ă����B
�u�E�E�E�B���H�ǂ����H�v
�ӂ�����Ɣ����������Đ^���͊�������ߑ����Ă���B
�u���I���������B�Ȃ��B���������B���߂�A���߂�B�r�b�N���������B�v
�}�W����B�o�J���Ă������A�Ԕ������Ă������E�E�E�ł�������Ɖ��������B�q�b�ɂ͐�ɂȂ��Ƃ��낾�ȁB��ׂ��A������������q�b�Ɠ�����ׂĂ��B
�u�������I�v
�u�ɂ��I�Ȃ�H�v
�u�����˂��A���������l�́B���̎q�ƋC�y�ɘb���邵�B�v
�u�Ȃ���B����悩�A���т܂��H�H���ɍs������B�v
�u���ꂥ�H�^�������ƍs���Ȃ��̂��H����͎₵���j�����ł��������܂����B�v
�u�E�E�E�B�v
������˂��B�m���ɏ������������Ƃ��v�������ǁA����Ȃ�Ȃ����B���ɂ͒q�b������B
�u�����A�҂Ă�I�v
�u�����̔ӂ��т͉��������H�v
�u�������ȁE�E�E�n���o�[�O�B�v
�u�܂��H�ق�ƂɃn���o�[�O�D�����ˁB�O�̓`�[�Y���̂�������A�����͘a���ɂ���H�v
�u�a���H�����������B���������y���݁B�v
�u����A�A�蔃�������ċA�낤�B�v
�u����B�v
�W��̍D���ȐH�ו��C�R�[���q�ǂ����D���ȐH�ו��B�O�H����Ƃ��͑��[��������]���i�B�������Ƃ��̓n���o�[�O�𒆐S�ɁA�قƂ�ǂ̏ꍇ�����������N�G�X�g�����B�g�}�g�����B�傫�Ȏq�ǂ����B�ł����̎q�͂�����������������ʂ݂̏Ƌ��Ɏc�����H�ׂĂ����B���̎p���������āA���Ƃ��ƋC�ɂ��Ă����̏d��]�v�ɋC�ɂ��Ȃ����������j���鎄������B
�@�����˂��B��������ăe���r���đ�����Ă��珟��ɂ��т��o�Ă������ˁB���͂��Ȃ��̉��H���g�H�W��ƌ����H��k����Ȃ��B�������āB���ꂵ�Ă����āB���ꂪ�H�ׂ����B�����ɍs�������B�������Ȃ��B���͂��Ȃ��̉��H�������㉺�^�����J��Ԃ������ЂƂ܂����ӂ��܂����傫���w�������X���炵���Ȃ�B�ŋߑ����Ă��������B�W��ɑ����s�B�����ĉ��ɕ\����Ȃ���s�B�ł�������ɂ����o���ˁB�����W��̋�s���o���܂��Ɛ���Ă��鎞���܂��čW��͓��ӂ̊Â������Ŏ��ɋ߂Â��A�L�X�����Ă����B����Ŏ��̋@��������Ǝv���Ă���̂��B�܂����ے���Ƃ͌���Ȃ��܂ł������悭�͂Ȃ邯�ǁB
�u�W��I���̏�Еt���āI�v
�w�����Z�ރ������[���}���V�����Ȃ̂ɃL�b�`���ɗ��Ǝ��R�Ɛ����傫���Ȃ��Ă��܂��B�܂�ŃG�v�����������V�Ȃ����肪�ӂ������Ă��鎞�v�ɏ��������߂�݂������B
�u�q�b�A�ł�����B�v
����ȕ����������ɗ��Ȃ��Ă��������āB
�u�͂����B����A����Ƃ�����^��ŁB�v
�����̂��Ă��܂��B���܂ł���ȋC�����Ƃ͗����Ȍ��t��f��������悢�̂��낤�B�Ȃ��ŋߖ{���ɔ��Ă��������B
�w�E�E�E�B�x
���̂����������B���̓d�b�̓��e�B��b��̌������ōW�ꂪ�����Ƃ��Ă��邱�ƁB�����čW��̕\��B
�w���̑O�̃o�����^�C���A�����������ɖZ�����Ĉꏏ�ɉ߂����Ȃ��Ă��߂�B�������Z�����Ă��A�̗͓I�ɂ����_�I�ɂ����Ă��ˁB����Ȃ��ƌ����Ă�̂͏��m�̏�Ȃ��ǁA���������������Ȃ��H�x
���H���̌�����B
�w�͂����茾���Ă�����B�x
�w�����H�x
�m�����B�m�����B
�w�^������D���Ȃ�ł���H�x
�܂��B�܂������Ȃ��B���̓d�b���I���܂ł́B
�w�E�E�E�B�x
���̊ԍW��̕����Ō������B��ɂȂ����`���R���[�g�̓��ꕨ�B
�w������B�ʂ�悤�B�x
�w�҂��āA�ʂꂽ����Ȃ��B�������������������ȂƁE�E�E�B�x
��������Ď����X�g�b�N���Ă�������ȂB����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B���͂���Ȃɓs���̂���������Ȃ��B
�w����A�ʂ�悤�B�x
�w���������B���߂�B�{���ɂ��߂�B�x
�������B���̏��ɕ������B������j�̓o�J�ȂB����ȃo�J�ȏ��������Ȃ�āB
�w����B�x
�u�`�b�I
���������炱��������d�b����Ă�����B
�����B���x�W��ɂ͕��������Ă����Ƃ��낾�������B���Ƃ͗����Ɏ����玟�ւƗ܂��j��`���Ă͏��ɗ����Ă䂭�B������̂悤�ɂ��Č����̂��ȁH����Ȏ��ɁE�E�E�B����A�ꂵ���Ȃ��Ă����B���߁E�E�E�}�ɏZ�݊��ꂽ���̕������ƂĂ��Ȃ������Ɏv���Ă����B�܂�ł��������ӂ�ꂽ����̎���ǂ��o�����Ƃ��Ă��邩�̂悤���B�������B�ЂƑ��肵�Ă��悤�B�j�ɓ˂��h����悤�ȕ��������ς��āA�܂����������~�߂Ă��܂����B
�@��D���ȃG���W�������������Ȃ��B�������Ă���͎̂�b���ʂ��ď������Ȃ����W��̐��B�w�S�����B�z���g�E�j�S�����x�ӂ邭�炢�Ȃ瑼�̏��Ȃ�čD���ɂȂ�Ȃ��Ⴂ������Ȃ��B�C�Â��Ă��Ȃ���ł͂Ȃ������B�W��͂����炩�^�������̘b���悭����悤�ɂȂ��Ă����B�C�ɓ����Ă���ȂƂ��v�����B�ł�����ȏ�͓��ɉ��������Ȃ������B�Â������B
�@�����ꂽ���i������ɋ삯�čs���B�����B�炪�₽���B�肪�₽���B�����Ȃ���B�^�钆�̍����͎Ԃ̒ʂ肪���ɏ��Ȃ��B���܂���Ⴄ���̉^�]��Ɋ�������Ă͂��܂����Ƒ����s���ɂȂ�B�������A�Ԃɂ͂˂��Ď��˂����B���ɂ����E�E�E�B���ɂ����E�E�E�B
�@
������킸�ɖ߂��Ă��Ă��܂����B�����̔��h��̕ǁB�����̃x�b�h�B�����Ă����̎p���ɉf�邢���ƂȂ��ς��Ȃ����B�ς���Ă���͖̂ڂ̎��肪�Ԃ����Ă��邱�ƁA�M���ۂ����ƁA�E�E�E�ގ������������ƁB
�@������\�O���B�����قǏ����������N�̉Ă̐����͂ǂ���琊����m��Ȃ��炵���B�ˑR�`���C�������������ς��ɖ�Ђт����B�����͒���������Č����Ă������H�����̊���ɏd���ȃh�A�������J����Ƃ����ɂ͑傫�Ȏq�ǂ��������Ă����B��܃����Ԃ�̍ĉ�B����Ă��܂����B�����̒��������Ȃ����������B
�u�����Ƀh�A���J����̂͊�Ȃ���B�ςȊ��U�Ƃ����邩������Ȃ����A��x�̂���������N�������̂��m�F��������������B�v
�u���������H�v
���������Ă���́A���̐l�́H
�u�O�s�����B�v
�u�N�����Ă�́H�v
�u������B�v
���ĂȂ��Ă��A����Ȃ��Ȃ��ɂ͓���Ȃ��B
�u������Ƒ҂��āB�v
�����̌���߂Ă������ƕ����o���B�W��͂����炭����߂����߂ɗ����B�^�������Ə�肭�����Ȃ��āE�E�E�B���ł������ʂ�����B�ʂ�Ă����Ԍo�̂ɔ���ɂ��܂��������悤�Ƃ��Ă�̂��A���������Ƃ��Ă�̂����͂�����ƕ������B�ł��W��͋C�Â��Ă���͂��B������x�ƌ��ɂ͖߂�Ȃ��Ƃ������Ƃ��B����߂鎄�̎d������������B����߂鎄�̍���̖�w�Ɍ��郊���O����������B
�@�l�͗��������B�S�������ɂށB�������e�������ŁA�ł����S�ɂ͒e���邱�Ƃ��Ȃ��B�y�����悤�łƂĂ��ꂵ���C�����B��͂�l�͗��������B�ӂƂԂ₭�B�u���N���T�N�������ꂢ�ɍ炢���ȁE�E�E�v
�@�T�N�������J�̋G�߁B�w�Z�ւ̒ʊw�H�𑫑��ɋ}���B�V�w���B�l�͂��̓����N�Ԗ��������Ă���B���͂����܂������ɂ̂т�B�������A���X�̕\����݂��A�t�͍����ؓ��A�Ă͂��݂̏h���A�H�͉��F����q������A�~�͔���̐��E�����o���B�l�͈��������݂��߂Ȃ���w�Z�ւƌ������B�����ɓ���Ɖ����ς��Ȃ������̌��i������B�l�͂Ȃ����������������߂��B
�u�������A���͂�I�v
�u���`�a��A�������I�v
�F�B�̗ւ̒��ɓ����Ă����B���C�Ȃ��A���̈Ӗ��������Ȃ���b���l���ށB
�u�����̎����̐��w�T�A�܂�����˂ǁE�E�����Ӗ��s���₵�v�u����Ȃ�����āB��l�Őԓ_�Ƃ낤��v
�u������Ȃ��A�c���́B���O���w�ł�����B�v
�u�܂��`�ˁA�v
�u���̌��������炵�����������C�ɐH����v
�����̉�b�B�����Ă����̗F�B�B�����ς��Ȃ��B�ł��l�͂������ł����S�n�������ꏊ���Ǝv���B�����Ėl�ɂƂ��Ă��������̂Ȃ����E�Ȃ̂�������Ȃ��B�F��ȂǂƂ������̂�l�͐M���Ȃ������B�F��͉����̂��̂��A���Ƃ��Y�݂𑊒k�����Ƃ��Ă��A��܂���Ԃ߂͂��Ă���邯�ǁA�{���ɐS�ꌾ���Ă���邱�ƂȂ�ĂȂ��B�݂�Ȏ�������ŁA�����Đ�Ȃ̂��B�F��͕\�ʓI�Ȑl�ԊW���Ȃ��������ł����Ȃ��̂��B�l�͂��������Ă����B�ł��A������͈Ⴄ�B���C�Ȃ���k�̒��ɂ������������{���̌��t�Ƃ������̂�������B�����Ď����ɂƂ��ĐM�����Ă��������Ȃ��Ǝv���邻��ȓz��Ȃ̂�������Ȃ��B
�u�������A�������ŏI�����I�����炲�ѐH�ׂɍs������v
�u���`�������B�ρ`���ƍs������I�݂�Ȃ��s�����H�v
�u�����A�s���s���v
�l�����ɂƂ��Ď����Ȃ�Ă��̂͂����傫�ȈӖ��͎����Ȃ������B�����̌�ɖl��̒��Ԃ̈Öق̗����Ƃ��Ă̒�����V�ԂƂ������Ƃɑ傫�ȈӖ��������Ă����B��͂莎���͖l�ɂƂ��đ傫�ȈӖ��������Ȃ������B�l�͕��l�����肬��ł��̗L���i�w�������Z�ɓ��w�ł����B�������A�l��҂��Ă����̂́u�������ڂ�v�Ƃ������b�e���������B�u�������ڂ�v�͑���ɂ���Ȃ��B�l�͋������������Ă����B�N��l�Ƃ��Ď�����F�߂Ă͂���Ȃ������B������A�����𒅏���A�����āu�������Ȃ�Ăǂ��ł������˂�v�Ƃ������Z���t�Ŏ������g��[�������Ă����B�������ǓƂŁA�������݂��߂ŁA�����������łȂ��悤�Ȋ����������B�����ĒN���l������Ă���Ȃ��ƁB�I��̃`���C���ƂƂ��Ɉ�ڎU�ɌC���Ɍ������B�f�����C�ɗ����ւ��A�ܐl�͂��������ɍZ����яo���B�Z��ɐm�������ɂȂ��Ă��鐶�k�w���̋��t�̐����l��̔w�ɓ˂��h����B
�u�����I�X�q�����Ԃ�A�V���c�𒆂ɓ���āA�z�b�N���������Ƃ��߂�I�I�v
�����Ƃ������܂����^�ɂ͂ߍ��܂ꂽ�l�����B���̌^����͂ݏo�����Ƃ͐�ɋ�����Ȃ��B���X�����Ԃ�A�����̃z�b�N����ԏ�܂ł�����ƕ��A�V���c�͒��ɓ����B�����čZ��̋��t�ɓ���������B���ꂪ�ǂ��q�Ȃ̂�������Ȃ��B�����āA���ꂪ�����]�������̂��낤�B�l��͂���Ȑ��k�ɂ͂Ȃ肽���Ȃ������B����A�ނ���Ȃ�Ȃ������̂�������Ȃ��B�Љ�̒��ŏ�肭�����������@��m��Ȃ������B��͂�l��́u�������ڂ�v�Ȃ̂�������Ȃ��B�w���ɓ˂��h���鐺�������Ȃ�������ؓ����삯������B�߂��̃R���b�P���̗g�����ē������̖l���U���B�����ɂ܂��䂭�X�[�c�p�̃T�����[�}���B��������A�ƘH�ɂނ�����w�B���Ԃ̂��������ȂЂƂƂ����߂����V�v�w�B����ȓ�������Ȃ���l�͉����̂ɂ������邱�Ƃ̂Ȃ��������g��������B�D�G�ȍ��Z���������邱�Ƃ��A�ł̐��E���������Z���ɂ��Ȃ�Ȃ��������B���x�̏����ȐH���ő吷��̃J�c���𒍕�����B�w�������ő吷��T�[�r�X�Ȃ̂��B���̂Ƃ�����͍��Z���ł悩�����Ǝv���B�H�����̘b��͐�璋����̗V�ԃ��j���[�\�z�ɐs����B�ܐl�ܐF�A�F�X�Ȃ������낢�v�Ă���ь����B�Ɠ����ɖl��̋������X�ɏ����Ȕg����傫�Ȕg�ւƕω�����B�F�X�ȋ���炷�Ă��o���̂����A���ǂ����̃R�[�X�ɗ����������B�����̃R�[�X�ƃ{�[�����O�����āA�t�@�[�X�g�t�[�h�X�ŋx�e����B�����čŌ�̓J���I�P�Ƃ������̂��B��͂肱�̃R�[�X�ɗ��������Ƃ����̂������ɂ��l��炵���B���Z���̖l��ɂƂ��Ă����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������������ɖ��������܂ŗV�ԕ��@��l�����͍l���������B���Z���Ƃ����������ő���Ɋ������A�������g���̂��B�����͍��Z���ł��邱�Ƃɋ^��������A�Ӗ������o���Ȃ������̂����A���̂Ƃ�����͍ő�Ɋ��p����B�������ĈӖ��̂Ȃ����ƂȂ̂����B�d�Ԃɏ��A���S�X�ɌJ��o���B���Ԃ͕��ʂ̕����̒��ԁB���̕��ʂȓ���̒��ɓ��قȖl��͉��l�����o���B�����N�ɂ��ł��Ȃ����Ƃ����Ă��鉽�Ƃ������Ȃ��悤�Ȗ������ɐZ��̂��B�{�[�����O�����I���A��ꂽ�̂��x�߂邽�߂Ƀt�@�[�X�g�t�[�h�X�Ɉړ�����B�����č������̂͐H�ׂȂ��B�P�Q�O�~����̃W���[�X�������Ă���łS���ԁA�T���Ԃ����b��������̂��B���v���A��������Ȃɘb�����邱�Ƃ��������̂��Ƌ^��Ɋ����Ďd�����Ȃ��̂����B���̎��Ԃ͖��@�̂悤�ɂ����Ƃ����Ԃɉ߂��������B��K�Œ������A�g���C�������ĎO�K�ɏオ��B�����āA�S�n�悢�������̂����鑋�ۂ�I��Ōܐl������B�t�̗z�C�ɖl�����̐S����w�x�炳�ꂽ�B

�X�S�N�P�Q���̂�����̕��ی�A�m���͂����̂悤�ɒҌN�ƋA��̓r�ɂ��Ă����B�����̃z�[�����[���ŌÐ�搶����A���̘A�̃T�b�J�[���̘b�������߁A��l�͂��̘b�Ő���オ���Ă����B���w�Z�̍��w�N�ɂȂ�ƁA�N�ɂP�A�Q��s���铯����̏��w�Z�R�̃X�|�[�c���ɎQ�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�B�m���̏��w�Z�ł́A���̃X�|�[�c���̂��ď��̘A�ƌĂ�ł����B�����ė����ɍs���鏬�̘A�̎�ڂ��A�T�b�J�[�Ɍ��肵���̂ł���B�m���͎���������ł���ꂾ�Ɗ����āA�S���e��ł����B
�u���炪�o����D���ԈႢ�Ȃ��ȁB�v
�u�ق�܂�ȁB�ł����̃����o�[��������ƐS�z�₩��A�^���_�o�����z�U���ƂȁB�v
����ȉ�b�����킵�Ȃ���A��l�͗[���̒ʊw�H������Ă����B�m���ƒҌN�͂��ꂼ��ʂ̃T�b�J�[�`�[���ɏ������Ă������A�����ʼn��x���ΐ킵�����Ƃ�����A�ҌN�̎��͂͗m�����F�߂Ă����B�܂��ꉞ�̓T�b�J�[�`�[���ɏ������Ă��邾���͂����āA�m�������̐��k���́A��͂肤�܂������B��l�͑��������[�_�[�C���ŁA�|�W�V��������ɂ��Đ^���ɘb���������B�₪�ĒҌN�̉Ƃɒ������̂ŁA�m���͂���Ȃ�������ƁA�����Ŏ���������l�q����z���Ȃ���A��l�A�蓹��������B
�����̕��ی�A���̘A�̃T�b�J�[���̎Q����]�҂͂T�N�Q�g�̋����ɏW�܂邱�ƂɂȂ��Ă����B�m���ƒҌN���|�����I���ċ����֓���ƁA���łɂ�������̒j�����W�܂��Ă����B��l�͂����ɒj�q�����o�[�́g�`�F�b�N�h���n�߂��B���ꂩ��T�b���o���Ȃ������ɁA��l�͊�������킹�ăj�����Ă����B
�u�j�b�|���ɃT���R���A���Y�ɓc��A���N��������B����͂�����ȁB�v
�u�ق�܂�ȁB���̓z���F�^���_�o�ǂ����B�D���ԈႢ�Ȃ���ȁB�v
�m���ɏ��̘A�ɎQ������]����̂́A����قڑS�����^���Ɏ��g�̂���҂ł���B����ɍ���̓T�b�J�[�Ƃ����l�C�̎�ڂł��邱�Ƃ�����A�T�N���̃X�|�[�c�����B�������낢����`�ɂȂ����B�m���͋����`�[�����ł������ߊ��ł������A���������܂�ڗ����Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ɠ��S�ł͏����S�z�ɂȂ����B�����Đ搶����X�P�W���[�����̘b������A�^����ɏo�Ă��������獇�킹�����˂��Q�[�����s�����ƂɂȂ����B���߂̈�ۂ��̐S�Ƃ����v����A���q�����Ă���Ƃ������Ƃ������ėm���͒�����ăQ�[���ɗՂB
�������I�����U������A�q�ǂ��B�͂��ꂼ�ꓯ�������ɋA��ғ��m�ŋA����B���̎��m���͒ҌN�ƁA����N�ƈꏏ�ɋA�����B����N�Ƃ͓����N���X�ŁA�b���������Ƃ͉�������������A�ꏏ�ɗV�肷����͒��ǂ��ł͂Ȃ������B�������������߂ē���N���A�m���̉Ƃ̋ߏ��ɏZ��ł��邱�Ƃ��킩��A���ꂩ��Ƃ������̂́A�������ی�Ɉꏏ�ɃT�b�J�[�̗��K�����A���̌�ꏏ�ɋA��Ƃ������Ƃ��������B�������邤���ɁA�m���ƒҌN�Ɠ���N�̒��͂�������[�܂��Ă������B�~�x�݂ɓ����Ă��O�l�́A�ꏏ�ɗV�Ԃ��Ƃ����������B�ҌN�̉ƂŃe���r�Q�[����������A�����ŗV��A�������T�b�J�[�̗��K���������Ȃ������B�~�x�݂��������炷���ɁA���̘A�̂P�����ڂ����邩��ł���B�m���́A�������҂��������Ďd���Ȃ��������A��������Y�݂��������B�T�N���ɂȂ��Ă��炷���ɁA�m���͏������Ă��鏭�N�T�b�J�[�`�[���̃X�^��������A�O����邱�Ƃ������Ȃ��Ă����B���̂��Ƃ́A������������^���Ɋւ��Ă͉���s���R�������Ƃ��Ȃ������m���ɂƂ��āA�ƂĂ��V���b�N�Ȃ��Ƃ������B����ł��������ɃT�b�J�[�𑱂��Ă������A�P�O���ɂȂ�ƌÐ�搶�̉e���ŁA�x�ݎ��Ԃɂ���Ă����o�X�P�b�g�{�[�����{�i�I�ɂ��邱�Ƃɂ����B�����Ēn��̃~�j�o�X�P�b�g�{�[���`�[���̗��K�ɁA���ɉ��Q������悤�ɂȂ����B�o�X�P�b�g�{�[���͗m���ɂƂ��āA�ƂĂ��������낭�A�T�b�J�[�ȏ�ɖ��͓I�ł������B�P�Q���ɂȂ鍠�ɂ́A�T�b�J�[������B���Ă����B�o�X�P�b�g�����܂��Ȃ�ɂ�A���N�T�b�J�[�̗��K�ɍs�����Ƃ����ɂȂ��Ă����B���e��������r���[�Ȃ��Ƃ͂����ɁA�ǂ�������Ɍ��߂Ȃ����ƌ����Ă����B�����ėm���́A���̘A�̎����ƁA����ɂ��̌�ɂ��鏭�N�T�b�J�[�̎������Ō�ɁA�o�X�P�b�g�{�[���ɐ�O���悤�ƌ��S�����B�{���Ɏ������D���Ȃ̂̓o�X�P�b�g�{�[�����ƍl�����܂Ƃ܂�����́A��������₩�ȋC���ɂȂ�A���̘A�����łȂ�����܂ł��܂���C�̏o�Ȃ��������N�T�b�J�[�̎������A����낤�Ƃ����C���N���Ă����B���̐Â��Ȗ�A�m���͏m�̏h������邽�߂Ɋ��Ɍ������Ȃ�����A���̒��ŃT�b�J�[�̃C���[�W�g���[�j���O�����Ă����B
�R�w�����n�܂�Ƃ����ɁA���̘A�̃T�b�J�[���̂P��킪�n�܂����B�m���̒ʂ����w�Z�̉^����͂ƂĂ��������߁A�����͑���̏��w�Z�ōs����B�o�X�Ŏ������ɒ����Ƃ��łɁA���̏��w�Z�����������Ă����B�������Ă��̎����̏��҂ƁA���T����������炵���B�E�H�[�~���O�A�b�v�����Ȃ�����A�N�������ڂŋC�ɂ����ɂ͂����Ȃ������B�������n�܂�Ɨ\�z�ʂ�A�I�n�D���������B�m���𒆐S�ɑ���̍U����h���A�ҌN�𒆐S�ɍU�߂�B���̂ǂ̊w�Z�������K�����Ƃ������g���A�ނ�ɂ͂������B�P�_�Q�_�Ǝ��X�ɒҌN���S�[�������߂Ă������B�m���͎���Ŏ��������Ă��鏗�̎q�̔������A�C�ɂ���]�T���炠�����B�Ƃ����̂����w�ɂقƂ�ǃ{�[�������Ȃ�����ł���B�����̗m���ɂ́A�����ދ��Ȏ����ł������B�����������B
���̓��́A������������̎����̘b�Ŏ������肾�����B
�u�ҌN�S�_�����߂������āH�v
�u�ҌN�����������ΗD���ԈႢ�Ȃ��ȁB�v
�m���͂������ɂ����₩�ȋC���ł͂Ȃ������B�T�b�J�[�ɂ����ẮA�U�����d���ł���t�H���[�h���肪���ڂ���A�_�߂���ƈȑO����s���Ɏv���Ă�������ł���B�ł��邱�ƂȂ玩�����t�H���[�h�ɂȂ��āA���_�����߂��������B���������̊肢�͌��ǁA���N�T�b�J�[�ł����̘A�ł��������Ƃ͂Ȃ������B�m���͐�������ł������B����͗m���̂��܂�ω����D�܂Ȃ��ێ�I�ȋC���ɂ̓}�b�`���Ă������A�������g�ł���邱�Ƃ͓��ӂł������B����ł���͂�A�U���̒��S�ɂȂ��Ē��ڂ��W�߂����Ƃ����v���������邱�Ƃ͖��������B
���ꂩ�琔����A�����̂R�l�Ŋw�Z����A���Ă���ƁA����N���ӂƐ^���ȕ\��Řb���������B
�u�ŋ߂�����������q�����̕����Ă�������������A�莆���肵�Ă�˂��B���̑O�Ȃ����߂Â�����莆�݂����Ȃ�ĂĉB���Ă����B�߂���C�ɂȂ�˂�B�����m��ւ�H�v
�m���B�́A�S���m��Ȃ��������ƂȂ̂ŕԓ��ɍ����Ă��܂����B�܂�������N�ɁA����ȔY�݂��������Ȃ�Ďv�������Ȃ��������Ƃł���B
�u�݂������̋C�̂������Ⴄ�H������Ȃ����Ƃ������������������ǁE�E�E�v
�u�ł������ق�܂�����狖����ւ�Ȃ��B���x���q�̒N���ɕ����Ă݂����B�v
��l�͕K���ɍl���o�����Z���t�������ɒ������B����N�́A
�u���₠��܂葼�̐l�ɂ͌����Ƃ��āB�I�N�B���m��ւ�̂�����炢����B�܂����̂��������Ȃ邩������ւB�v
�ƌ�������͂��ނ����܂ܖق��Ă��܂����B���͂�������������Ă��܂��Ă����B����N�ƕʂꂽ��A�m���ƒҌN�͘A�x�����̉Ηj���ɁA�������菗�q��₢�l�߂邱�Ƃɂ����B�܂����܂����킯�ł͂Ȃ����A�F�B�������߂��Ă��Ėق��Ă���킯�ɂ͂����Ȃ��Ƃ����ӔC������l�ɂ͂������B
���j���͏j���ł������B���̓��m���͂�����Ƃ������Ƃŕ�e��{�点�Ă��܂����B��e���ĎO���C�ɓ��ꌾ���Ă���̂ɁA�m���̓e���r�ɖ����ɂȂ茾�������Ȃ���������ł���B�����ĂƂ��Ƃ��m���͂��̓��A���C�ɓ��邱�Ƃ��ւ����Ă��܂����B�v�t���ɓ��낤���Ƃ����N���ɂƂ��āA���C�ɓ��炸�Ɏ��̓��w�Z�֍s���Ƃ������Ƃ͑ς����Ȃ������B�w�Z�ŃN���X���[�g�ɁA�L���ƌ����悤���̂Ȃ��ςł���B�����ŗm���͂��̓��̖�A�Q���ӂ�����Ƒ����Q�Â܂�̂�҂����B���x�����̐��E�z�����܂ꂻ���ɂȂ�̂��䖝���Ȃ���A�R���Ԉȏ���z�c�̒��ł����Ƒς��Ă����B�����Ă悤�₭�S�����Q���̂��m�F���Ă���A�m���͂������蕗�C����������B�������ɓ��D�̓��́A�������łɗ�߂Ă����B���߂ē������ł����ƃV�����v�[����ɂƂ�A�V�����[�������̂ʼnƑ����N���Ȃ��悤�ɐÂ��ɂ����ɂ������B���̌��͂蓒�ɂ͐Z���肽�������̂ŁA�䖝���ē��D�ɓ������B���炭���D�̒��Ń{�[�b�Ƃ��Ă���ƁA�}�ɋߏ��Ŏ����Ă��錢����Ăɖ��������B��C���������āA����ɔ��������̂ł͂Ȃ��A���������̉Ƃ̌�����Ăɂł���B�����������ɋ����邩�̂悤�ȁA�s�C���Ȑ��������̂ŗm���͉������|���Ȃ�A�������ƕ��C����オ��z�c�ɐ��荞�B���v�͌ߑO�P�������w���Ă����B
�h�[���Ƃ����傫�ȉ��ƁA�L���[�Ƃ�����̔ߖŗm���͖ڂ��o�܂����B�����N���Ă���̂��S���킩��Ȃ��A�������Ƃ������Ă���悤���B�m���͉��b���\��Ă���A�����A�Ǝv�������A���́u�n�k��v�Ƃ������t�Ō����ƔF�������B�Ƃɂ��������������킩��Ȃ��B�d�C�������^���Èł̒��A�S�S�S�S�Ƃ������ƌ������h�ꂾ����������ꂽ�B�m���͂��������ƁA�z�c�����Ԃ��Ėڂ���Đk���Ă����B
�悤�₭�h�ꂪ�����܂��āA���ƕ�͗m���̖������m�F����ƁA�ׂ�̕����ŐQ�Ă����Z�ɐ����������B�Z�̕����ɂ͑傫�ȃ^���X������A���ꂪ�Z�̕z�c�߂����ē|��Ă������A���܂��Ƃ��K�����A�����Ɉ����������ČZ�̑̂ɒB���邱�ƂȂ��~�܂��Ă����B���njZ�͈�x������O�ɏo�āA�悤�₭�Ƒ��S�����W�܂����B���̌�]�k�����x�ƂȂ��P���Ă��āA�m���̐S�͋��|�S�ň�ꂩ�����Ă����B���͔��H�̊m�ۂ�A���ꂽ�H��̌�Еt�������A��͋M�d�i���W�߂���A�h����̏��������Ă����B�������m���̓V���b�N�ʼn������邱�Ƃ��ł����A�����ق��ĕz�c�̏�ɉ�������Ă����B�O�̗l�q�����ɍs�����ƃh�A���J�����ꂪ�A�k��������
�u��������B�������̃A�p�[�g�̈�K���Ԃ�Ă�E�E�E�v
�ƕ��Ɍ������B��K���Ԃ��Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂��A�m���ɂ͑z�������Ȃ������B����ƒǂ��ł���������悤�ɁA���̐l�̋��ѐ����������Ă����B
�u�������ɂ����ł��B�N�������āB�v
�m���͉��̂���Ȃ��Ƃ��N�����̂��A������Ȃ��̂��Ǝv�����B������������w�Z�֍s���āA�T�b�J�[�̗��K������͂��������̂ɁA��̉����N�����Ă���̂��킩��Ȃ������B�K���Ɍ������~�߂悤�Ƃ������A�P�P�̐S�ɂ͂��܂�ɂ��d���h�����̂������B���̌�́A�e�͂Ȃ����x���P���Ă���]�k�ɐk���Ȃ���A�������ɂ��������z�c�ɐ����Ă����B
���߂��ɂȂ�ƁA�߂��̌x�@���ɔ��悤�ƕ����������B�����Ă݂�Ƌߏ��̐l����������W�܂��Ă����B�������炵�炭����ȏ��Ő�������̂��Ǝv���Ă���̂����̊ԁA���q���̗Վ��h�ɂɂȂ�Ƃ������R�ŁA�S���x�@���̑̈�ق���ǂ��o����Ă��܂����B�r���ɕ��Ă���ƁA�c��ƍb�q���ɏZ��ł����̌Z�����]�Ԃł͂��Ƃ܂ŗ��Ă��ꂽ�B�������m�F����ƃz�b�Ƃ����\����ׁA�b�q���͔�Q�͑傫���Ȃ����炱�����ɗ����Ƃ����Ă��ꂽ�B�����ėm����Ƃ͂��������b�q���̑c���ցA�ԂŌ��������ƂɂȂ����B�m���̉Ƃ̋ߏ��́A��������c�ł������B�������̃A�p�[�g�����łȂ��A�F�B�̈ꌬ�Ƃ��߂ɌX���Ă����B�^����ɉ�ꂻ���ȗm�����Z�ރI���{���A�p�[�g���A�قƂ�ǖ����Ȃ̂͋�����葼�Ȃ������B���ɂ͂������̃w���R�v�^�[�����ł���B�~�����Ɨm���͎v�������A�ǂ�����ނ̂悤���B
�����͍b�q���܂ŎԂłR�O�����Œ����B�����������͑S���Ⴄ�B���͎Ԃł��ӂ�A����ɐi�܂Ȃ��B����ɓ��H�����ꂽ��˂��o���肵�Ă��邱�Ƃɉ����āA�M�����|��@�\���Ă��Ȃ����߂��Ȃ荬����Ԃł������B����I�Ɍ�ʐ��������Ă���j���̎p���A�ƂĂ���ۓI�ł���B�m���͑����b�q���ɒ����ė~�����Ǝv���Ă����B�K���X�z���ɁA�ߎS�Ȍ��i���ۉ��Ȃ��ɖڂɔ�э���ł��邩��ł���B���H�ɖ����|���ɂȂ��Ă���B�Ƃ��Ռ`���Ȃ�����Ă���B���ƍ������H�����|���ɂȂ��Ă���B�Ԃ̒��̃��W�I�ŁA����̒n�k���u���Ɍ��암�n�k�v�Ɩ��Â���ꂽ���Ƃ�m�����B�k���n�͒W�H�����Ƃ����B�������m���ɂ́A����Ȃ��Ƃ͂����ǂ��ł��悩�����B
�ǂꂭ�炢���������낤���A�Ԃ͂悤�₭�c��̉Ƃɒ������B�c��͗m����Ƃ��������}������Ă��ꂽ�B����b�����邪�A�܂��ӌ�т�H�ׂ邱�ƂɂȂ����B�J���[���C�X�ł��������A�H��ɂ̓T�������b�v��������Ă����B�m���͈ȑO�H�~���킩�Ȃ��������A������肩�����B�e���r�ɂ͒��c��̑�Ђ̗l�q���f���o����Ă���B�e���r��ʂ��Ēn�k�̗l�q�����āA��ςȂ��Ƃ��N���Ă���Ɖ��߂Ď�������̂�����s�v�c�Ȃ��̂ł���B���̓�����m���́A��l�łӂ������ނ��Ƃ������Ȃ����B�]�k�ɋ����A�Ԃ̑��鉹��]�k�Ɗ��Ⴂ���A���������̏ꂩ�瓮���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��������B�O�ɏo�邱�Ƃ͏��Ȃ��Ȃ�A�e���r��}���K�ɖv�������B�����ł��������痣�ꂽ�������̂�������Ȃ��B�Ƃɂ������̐k�Ђ��@�ɁA�m���̍l��������͔����ɕω������B
�c��̉Ƃɗ��Ă��琔����A��F�Ńe���r�̃j���[�X�ԑg�����Ă���ƁA����̐k�ЂŖS���Ȃ�������s���s���̕��̖��O�����\����Ă����B�m���͂����{�[���ƃe���r�߂Ă����B����ǂ����ƂɁA���̐l���͑��������ł���B�����̓������R�b�v����ɂƂ�A���ɋ߂Â������̎��A�e���r�̉�ʂɌ��o���̂��閼�O���������B
�u����Ȃ���P�P�@�_�ˎs�����E�E�E�v
�m���͋A��̓d�Ԃɗh���Ă����B�d�ԓ��ɂ̓��~�i���G�̍L�����A��������݂��Ă���B���N�͂P�O��ڂ̊J�Â��������B���ł͂�������f�[�g�X�|�b�g�ɂȂ��Ă��āA�m���͉������₵���v���������B���N�͏��߂ă��~�i���G�ɍs������ł���B�����Ă��������k�Ђ���P�O�N���o�Ƃ��Ƃ��Ă���B�P�O�N�O�A�]�Z���͂��߂Čo�����A�F�B��S�����Ƃ����o���������B���̍��͖������Ƃɂ����g�̉��̂��ƂŐ���t�ŁA�߂��މɂȂǖ��������B�������������̂��Ƃ��v���o���ƁA���ɂ������̂����ݏグ�Ă���B�P�O�N�Ƃ����Ό�������A���̔ߌ��̋L���͏��X�ɕ���������悤�Ɋ�������B�m���͐k�Ђɂ���Đ��������A�����ɏ����������B���܂�ɂ��傫�ȁA�\�����ʕω��ɉ����Ԃ��ꂻ���ɂȂ������Ƃ��������B�����A�v���o���̂����������k�Ђ̂��Ƃ��A���ł͂������茩�ߒ������Ƃ��ł���B�w���Ƃ͐�����Ȃ��B�m���͂��ꂩ����A�����������ɐ����Ă����B�w�ɒ����A�����̋A�蓹������Ȃ���ꂢ���B
�u���~�i���G�y���݂�ȁB�v

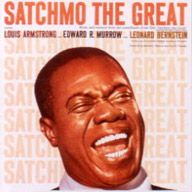
I see trees of green , redroses too �D
I see them bloom for me and you .
And I think to myself , " What a wonderful world ! "
I see sky of blue , and clouds of white ,
The bright blessed day , the dark sacred night .
And I think to myself , " What a wonderful world ! "
The colors of the rainbow ,
so pretty in the sky ,
are also on the faces of people going by .
I need friends shaking hands , saying , " how do you do ? "
They are really saying , " I love you . "
I hear babies cry. I watch them grow .
They'll learn much more than I'll ever know .
And I think to myself , " What a wonderful world ! "
Yes , I think to myself , " What a wonderful world ! "
�܂����������Đl���͂��炵���I
�������炪�l�ƕ�Ƃ̐V�����������̂悤���B
�u�͂��H�v
�v�������Ȃ��ꌾ�ɁA�����r�����B�T���̊y���݂ł���A���݉��ł̌�y�Ƃ̈�t�B�ŋ߂͎d���������A�����̊Ԃɓo�ꂷ��@��������Ȃ����B���A���̕��A�ǂ�������������܂ł̂悤�Ȏ��R����������Ă����B
�@���̎d�������悤�Ǝv�����̂́A��w�̃N���u�̐V�������}�p�[�e�B�[�ŗF�B�ƃl�^����炳�ꂽ�̂����������������B�����͂��Ƃ��Ɗ��̏o�g�ł͂Ȃ��A�c���̍�����g�{�V�쌀�����Ă����킯�ł͂Ȃ��B�u�����v�̖����Ȃɂ��킩��Ȃ��B����܂ł̓e���r�Ō|�l�����̃l�^�����āA�Ђ����甚���鑤�������B�������A���������Ńl�^������Ă݂�ƁA�Ȃ��Ȃ��v���������A�u�l���킹��v�Ƃ������Ƃ̓����Ɋ�������ꂽ�B�ƁA�����ɂ����l�O�Ńl�^���I����ƁA�����̃l�^�Ől������S�n�悳�ɉ������o����̂ł������B
�@���ꂩ��Ƃ������́A�����|�l������ڂ��ς�����B����Ȃɂ��ȒP�ɐl���킹�邱�Ƃ��ł���ނ�ɑ��āA���h�̔O������悤�ɂȂ����B�������u����v�̂ł͂Ȃ��A�l���u�킹��v�Ƃ������ƁB�������������l���u�킹��v���ɂȂ肽���Ǝv���悤�ɂȂ����B�����̃C�x���g�Ńl�^�����@�����A���悵�ėF�B�ɐ��������A�݂Ȃ̑O�Ńl�^��������B���X�ɃR�c�����݂��������Ƃ�����A����̕]���͏�X�������B���̂܂܂����Ń��V��H���Ă������炢���ȂƎv���悤�ɂȂ�A��w�ɒʂ��Ȃ���A�����|�l�{���w�Z�ɂ�����o���悤�ɂȂ����B
���炭���āA�����{���w�Z�̒j�ƃR���r��g�ނ��ƂƂȂ����B�������g�A�m�ł���v���C�h�������Ă���������Ă���B���r���[�Ȃ�Ȃ�R���r�͑g�ނ܂��Ƃ����v���Ă����B����ꂽ�Ƃ���̕����ɒʂ����ƁA�����ł��łɑ����炵���l�����҂��Ă����B�����͒j�O�̎��|�l���������Ȃ��A���̂��߂������ɂ����ɐl�C�̂���E�Ƃ��������A�������R���r��g�ނȂ�A�����ɂ��u�����v�Ƃ������͋C���Y���Ă���悤�Ȍ��I�ȃ��b�N�X�����Ă����������A�Ǝv���Ă����B�Ƃ��낪�A�������U��������Ƃ��̑���ۂ́u���i�v�������B���������߂Ă����悤�Ȍ��I�ȗv�f�͉���Ȃ��A���邩��ɍ����́A���ʂ̎�҂ł������B�����̒��łЂƂ��ߑ������āA���݂��̎��ȏЉ���n�߂��B�����Ƃ���ɂ��ƁA�ȑO�ɃR���r��g��ł������Ƃ�����炵���B�����ȃR���r��g��Ŋ����������Ƃ��Ȃ����������A�����Ȃ�u��y�v�ł���B�����̑����Ƃ��������Ō�����������t���Ă������Ƃ��������Ȃ����B�R���r���́u�S���U���X�v�B���܂ł��肻���łȂ��������O���B�����̓c�b�R�~��S�����A�l�^���������ƂɂȂ����B�ȑO����l�Ԋώ@�ɂ͎��M���������B�Ɠ��̎��_�Ől�Ԃ����Ă���ƁA���ɖʔ����B���C�Ȃ�����̈�ł��A�����Ɏ��������A�K���u���v�ɂȂ�B�l�^�̍����͂���ł������A�ƐS�Ɍ��߂Ă����B�����͂������Ɍo���L�x�Ȃ��������āA����ۂƂ͑ł��ĕς���āu���i�v�������B�����e���|�A�Ԃ̎����͐▭�������B�o��������Ƃ����̂ł�����x�͂��Ăɂ��Ă������A�\�z�ȏ�ɋZ�p�̂���A�D�G�ȑ����Ɍb�܂�邱�ƂƂȂ����B
�@�����̃l�^�Ɏ��M�������Ă����������A�����܂łɂ����������Ԃ͂�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���悤�ɂȂ����B�����A����ő��̗L�]�Ȏ��|�l�����̃l�^�����āA����ł�������������Ԃ������낢�A�Ƃ͂Ȃ��Ȃ������Ȃ������B��������ɂ���S�����A�����ɏ�M�������A�������g�̌ւ�������Ĉꌂ�K�̃l�^�����̂ł���B�������瓪������o�邽�߂ɂ́A�܂��܂����������ɂ́A����Ȃ�����������悤�Ɏv��ꂽ�B
��w���ƌ���A���͓I�Ɋ����𑱂����B�����|�l�{���w�Z�������ɑ��Ƃ��A����Ď������ɏ������邱�ƂɂȂ����B�������|�l�ł���B�����͂قƂ�ǂȂ��A����܂ő����Ă����A���o�C�g�͑��ς�炸���Ȃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�ЂƂނ����O�Ȃ�A����������������u���ς݁v���オ���������A�ق�̈ꈬ��̌|�l�������A���̓��Ő��v�𗧂ĂĂ��������̂ł���B�������g�A�����Ċy�ȓ��ł͂Ȃ����Ƃ����m�őI���ł���B�n���ɃA���o�C�g�����Ȃ���̊����͊o������Ă����B
�������A�������Ȃ��u���ς݁v����͖������낵���̂ł���B��O�́u�����u�[���v�̓����B�e���r�ԑg���o���G�e�B�[�������A����ɔ����āA�����̎��|�l�������A�|�\�E�ւƑ��ݓ���Ă������B�S�[���f���ɂ������Ԃ�Ƃ����|�l����������o���悤�ɂȂ����B�u�����v�͒��ڂ𗁂сA���Ԃ̂����|�l�ɑ���F�m���ς���Ă����B�ȑO�̂悤�Ɍ��w��������邱�Ƃ͂Ȃ��A�����ɂ���l�C�̐E�ƂƂȂ��Ă������̂ł���B
���������D�i�C�̔g�ɏ�邱�Ƃ��ł��A���X�ɑ傫�ȕ���ɏo���Ă��炦��悤�ɂȂ�A�e���r�o���������Ă������B��������ƈႢ�A�X�Ő����������邱�Ƃ������Ȃ����B����ق₳���̂͌����Č����ł͂Ȃ����A�t�@���̒��Ō|�l�̃v���C�x�[�g���l������_�l�̂悤�Ȑl�͂߂����ɂ������̂ł͂Ȃ��B�ȑO�̂悤�Ɏ��R�ɉ߂����Ȃ��Ȃ����͔̂ς킵�������B�������Ă��邤���ɂ��A�e���r�ԑg�̃��M�����[�o���Ȃǂ̎d���͑����Ă����A�X�P�W���[�����͓��ɓ��ɍ������߂��Ă����悤�ɂȂ����B�D���Ŏn�߂����Ƃł͂��邪�A����I�t�̉߂��������l����̂������̊y���݂ƂȂ��Ă��܂��Ă���B
�@����Ȑ܂̂��̊Ԃ̋x���ł���B�̂�т�ƉH���x�߂���肾�����B�����̍s�����̈��݉��Ɍ�y���Q�`�R�l�A��čs�����B
�u�����B��������Ⴂ�B�v
���������Ȃ��݂̑叫�������������o�}���Ă��ꂽ�B�������������Č�y��A��Ă��Ă���悤�ɁA��w���ォ���y�ɂ�Ă��Ă�����Ă�������X�ł���B�����X���ɂ́A�܂��^�V���������̃T�C���������Ă���B�X���ɂ̓J�E���^�[�ȂɃT�����[�}�����̒j���Q�l�����Ă��邾���ŁA���ɋq�̎p�͂Ȃ��B�����̍��~�Ȃɂǂ�����ƍ��������B�v�킸�o�Ă��܂��������u�����������v�ƌ�y�ɓ˂����܂��B
�u�������������\�����������B�v
�u�قȖl�͂߂���߂��Ⴈ������Ȃ��������B�v
���������N��̌�y�|�l������������Ԃ��B
�u����B�߂���߂��Ⴈ�������B�v
�����|�l�̈�s�炵���A���̓���Ȃ����������b���e��ł���B
���������A�����̐��E�̏㉺�W�͔��Ɍ������B�N�����т����A�|�������ׂĂȂ̂ł���B�Ⴆ�R�O�̂�������ƂP�R�̒��w���ł����Ă��A�|���̒����ق����u��y�v�ł���A�Z���ق����u��y�v�Ȃ̂ł���B�w�����ォ��̈��n�̏㉺�W���o�����Ă������A�̂���㉺�W�͋��ł���B�����ł������ȏ㉺�W���A�����̐��E�̂���͂���������₱�����B�������������Ȃ���y�������A���Ƃ��A�v���C�x�[�g�̑ł���������ł����Ă������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
 �u���܂��ǂ�����B�v
�u���܂��ǂ�����B�v
����ł������r�[�����^��Ă����B���ɂ����ӂꂻ���Ȃӂ�����Ƃ����A���H�~��������B
�u�Ƃ肠�������t���܂��傩�B�v
�������炵�Ă����͎̂��������ł͂Ȃ��炵���B�R�c���A�Ƃ����y�����ƂƂ��ɁA��ĂɃr�[���𗬂����B
�^��Ă��闿����H�ׂȂ���A��y�����̎������̘b���Ă����B�����Ō�y�̈�l���瑊�k������������ꂽ�B�s�v�c�ƁA���̏�͂��Y�ݑ��k���ɂȂ�₷���̂ł���B
�u���͂ˁA�l�A�������悤�Ǝv�Ă��ł���B�v
�\�z���Ȃ��������k���e�Ɉ�u�������~�܂����B���̌�y�͂܂��܂�����o�����ŁA�\���ȉ҂�������킯�ł͂Ȃ������B���R�A�A���o�C�g�����Ȃ���̐����ł���B���ʁA�����|�l�̌����Ƃ����́A�d�����O���ɏ��n�߂Ă��炷����̂ł���B���������肵�Ȃ������́A�܂�����������邱�Ƃ��l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�u�q�ǂ����ł��Ă�������ł���B�v
�Ȃ�قǁA���Ɍ����u�ł�������������v�ł���B�ӔC���Ƃ��āA������ƌ�������Ƃ������������������B�����������A���̎����Ɍ����͂������Ȃ��̂��B�����̊��o�ł͂��肦�Ȃ����Ƃł���B
�u���₯�ǂ��O�A�d���͂ǂȂ�����˂�B�v
�v�킸�A�������ďo�Ă��܂����B
�u����A�����܂���B�����A�����o�C�g�����Ȃ����܂��ǂˁB�v
�o�債���悤�ɒW�X�ƌ����Ă̂����B���͂����|�l�ɂƂ��āA���S�ɍD�i�C�ł���B���A���܂ő������͂킩��Ȃ��B��x�u���C�N�����|�l���O�����Ď��Ƃ���Ƃ����̂́A�悭����b�ł���B���̂��߂ɂ��A�`�����X�̍L�����Ă��邱�̎����ɁA���͓I�Ɋ������A�m�ł���n�ʂ�z���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B�A���o�C�g�ŕ��S�������Ă��܂��ẮA�|�l�Ƃ��Ă̊����͋K�͂��k������������Ȃ��B����Ȃ炢�����̂��ƁE�E�E�ƍl���Ă��܂��̂����ʂł���B
�ӂƂ��̌�y�̂ق��ւƖڂ����ƁA���������̒��ōl���Ă���悤�ȕs���͕\��ɂ͈�ؕ\��Ă��Ȃ��B����ǂ��납�܂�ŕ�����̂悤�ɉ��₩�ȕ\������Ă���B��y���g�̒��ł͊��S�ɉ�������Ă�����̂悤�Ɏv��ꂽ�B
�u����͂ǂ�Ȑl�Ȃ�H�v
�����́A���ʁA�߂ł������Ƃł���B�h�C�L����Y�킹�Ă�����̋�C���O���C�������B
�u����A���ʂ̂n�k�ł���B�v
�u�ʐ^�Ƃ��Ȃ��́H�v
���܂ɂ������Ĉꏏ�Ɉ��݂ɍs���ԕ��ł͂��������A�����W�ɂ��Ă͏ڂ����m��Ȃ������B�����Ă�������ʐ^�ɂ́A��y�ɂ͕s���������Ǝv����قǂ̔��l�̎p���f���Ă����B�傫�ȃs�[�X����́A���N�Ȑl�����ǂݎ�ꂽ�B���̂����|�l�����₱��Ȕ��l�̉ł����炦��悤�ɂȂ����̂ł���B�����D�i�C�͂������ȁA�Ǝv���m�炳�ꂽ�B
�u�������Ȃ��āB���O�ɂ́B�v
�u�悤�����܂��B�v
�����炭�����̂ق��ɂ����낢��Ȑl�Ɍ����Ă����̂��낤�B���ꂵ�����ȕ\���́A�������̏[���Ԃ肪�`����Ă���B
�u���储�A���x���̎q�Ȃ���ŃR���p���悤��B�v
������l�̌�y���ڂ��P�����Ȃ���K���̂����ڂ��_���Ă���B
�u������āB���O�ȂƃR���p�����牴�̂��݂���F�B�����悤�ɂȂ�B�v
���ł�˂�A�Ƃ�������Ƀ`���[�N�X���[�p�[�����܂��Ă���B�S�̂���������Ă���C������B�ŋ߂͂����������Ԃ̂ق����u�����Ă���v�Ƃ�������������B���ɂ����O���X�̒��g���Ȃ��Ȃ������ƂɋC�Â��A��y���C�������Ă��ꂽ�B�������肢���C���ɂȂ��Ă��Ă���̂ŁA��D���ȁu���ہv�̃��b�N�𒍕������B�����͒��܂łƂ��Ƃ����A�Ǝv�������̂��Ƃł���B
�u�����A�����S���U���X�̕Њ�����H�v
���t�����ɂނ��Ƃ��āA���̕����Ɍ�������ƁA�����ɂ��K���̈������ȑ�w�����̃O���[�v�������ɗ����Ă����B�|�l�̃v���C�x�[�g���l������_�l�͂��Ȃ������ɁA���������������̂悤�ȃt�@���͂��������Ƃ���̂ł���B��قǂ܂ł̉~���ȍ��~�͓ˑR�̊��g�Ɍ�����ꂽ�B�����u�[�����������A�����|�l�̎Љ�I�n�ʂ����サ���Ƃ͂����A�ˑR�Ƃ��Ă��������y�͓r�₦�Ȃ��B���������Ă����炵���w�̒Ⴂ�j��������B
�u�Ȃʔ������Ƃ�����B�v
�ŒႾ�B�����|�l�Ƃ����̂́A���������Ďd�����ɔ��ɂ�������̃G�l���M�[������Ă���B���ł��{�P����悤�ɏ������Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����A�ԑg���ł̎����̖����A�܂�L�����Ƃ������̂����ɂł������Ȃ���Ȃ�Ȃ������������B���l����Ƃ��A�����|�l�̃v���C�x�[�g�ɓ��ݍ��ތ����͎����Ă��Ȃ��͂��ł���B�܂��Ă�A���������̑������ɂ����̎d�������߂��Ă͂��܂������̂ł͂Ȃ��B
�u���O��Ȃ��B�v
�������܂Ń`���[�N�X���[�p�[�����Ă������̋C�̑�����y�̍s���ɁA�t�ɓ����₳�ꂽ�B���������A���ɂ������Ă��ẮA�̂����������Ă�����Ȃ��B�䖝���Ă��߂����A�|�l�炵���e���r�ԑg�Ńl�^�ɂ��Ĕ����������������Ă������B
�u��߂�߁B�v
�u�������̓v���C�x�[�g�ł��Ă�˂�A���ق��Ă����B�v
���łɓ{��͎��܂��Ă����B�����̂悤�ɁA��l�̑Ή����ł����B��y��A��Ă����y�Ƃ��āA�͔͓I�ȍs�����ł������Ƃɂ������z�b�Ƃ����B
�u�Ȃ��A���炯��Ȃ��B�v
����̈��������ɁA��y���s�N���Ƃ������A�ڂł���������������B���Ԃ��o���Ă������Ƃ�����A�X��ς��邱�Ƃɂ����B�叫�͂܂�Ŏ����ɔ��邩�̂悤�ɏa��������ĉ��x���u���߂�ˁv�̃W�F�X�`���[�������B���x���f���������̓��̊���͖������ɔ��z�ɂ�����ꂽ�B
�u���ݒ������B�v
�u�������ˁB�v
���������Ă݂����̂́A���������͋C�͂��Ƃɂ͖߂�Ȃ��B�킩���Ă͂������̂́A���̂܂܂ł́A���E�����Ȃ��B�Ƃ肠�����A�������Ǝ������߂����ȓX��T���ĕ������Ƃɂ����B�������ȋ�C�����U�����Ƃ������قǁA�܂��܂��������ȋ�C�ɕ�܂�Ă����B�����ŁA��C�Ɍ����Ɉ����߂���Ă����C�������B�����قǂ܂ł́A�[�����ň�t��������y���A��������Ɖe�����Ƃ��Ă���B���̓X�ł́A�������̓X�ł͕����Ȃ������悤�Ȗ{���́u���Y�ݑ��k���v�ɂȂ邩������Ȃ��B��قǂ̎������u�����Ă���v�Ɗ�����ꂽ�̂��R�̂悤���B�u���v�����퉻�������Ă��܂������߂̐E�ƕa���낤���B�R�l���������������Ă���悤�ŁA���ɕ����Ă���C������B
�u���[�����B�v
�₽�����Ɏv�킸����������߂��B�܂��܂��A���̓X�͌����肻���ɂȂ��B