一月上旬
教え子の
つんつんと指で書く文字路地焚火
瀬戸内の浜から上がる凧の数
蹴る玉の滞空時間冬の原
足下に来た白球の匂い
少年の一群過ぎて冬夕焼
灯を消して机上に残る冬の月
校門に手を触れている老紳士
持ち替える


一月中旬
お
風止んでぽたりと落ちる紅椿
どんど焼き見つめる頬の赤さかな
笹藪が雪を落として腰伸ばす
地下二尺ほぼ球体に蛇眠る
老齢の女教師の手にゆきうさぎ
「も」の多き論文を読む寒の夜
枯れ枝の百の雀は飛び立ちぬ
寒風を受けて
凧糸は若き父親の手から伸び


一月下旬
採点の赤鉛筆が静止する
失敗のたこ焼き口が開いており
数えられるほどの粉雪飛んでいる
わが内にある石英はやや緑
手袋の中指にある歯形かな
外套の雨粒に街一つずつ
金剛の一つにはかに発火する
冬晴れや卒業論文提出日
冬の江に色を見つけて立ち上がる
首伸して青鷺が行く寒の川


二月上旬
日曜のライオン冬の空を見て
遠山に時に瞬く鏡あり
冬西日試験問題できあがる
バスを待つ背後に冬が来て触る
虎の視線外套の背に受けている
塾の子を待つ足踏みの五六人
五年女子五人集いて春近し
受験子の寝顔に少し笑みありて
横雲の上辺燃やしいる夕陽
抜き取りし奥歯の穴の自己主張


二月中旬
目を覚ます朝の車内や寒緩む
手袋を脱げば手のひら湿りおり
終鈴の受験生の頬白し
外れ玉の闇に猫の目光りたり
土はねて躍り上がるやハサミムシ
春雨の命そのまま小魚へ
早朝のプラットホーム出汁香る
春雨の道は蛇の目を写しおり
見送りて婆は駅舎に座りけり
春雨や龍の鼻毛ののびる頃


二月下旬
遠山をけものの如き雲の影
白鷺が水から脚を抜くかたち
昼遅き雛の準備はゆるゆると
いかなごの釘煮の香り路地に満つ
鴨橙白鷺檸檬水温む
春の宵小鼠檻を囓りおり
丑三のテレビの軋み二月尽
合鍵を二つ減らして卒業す
早帰り列車が夕日を追いかけて
発表会のピアノに映る桃の花


三月上旬
枯椿撃たれたボスの高笑い
春が来る競歩の尻の動きにて
生返事木洩れ日背なに踊りけり
なにごとか叫んで割れるシャボン玉
欠伸する猫は門番従えて
黄昏の父の帰還や桃香る
受験生やや俯きて歩きたり
昼寝する又八郎の裸足かな
かぐや姫帰らず博士の妻になり
水噴かぬ噴水にある希望かな


三月中旬
散り散りに車窓をよぎる終い雪
残月や後期試験は終わりけり
頭頂を風通り過ぎ卒業す
冬越しの蕾に緑現れて
への字から力を入れて伸びる猫
早春の緑のスカート揺れる駅
水澄みて日矢の一条白砂に
ゆっくりとガラス彫刻解け続け
公園の子らの歓声暮遅し
合格発表悲鳴のごとき日本晴れ


三月下旬
春の陽や足指の間に湿りあり
春潮は魔法が利かぬ裸馬逃げよ
卒業式追いかけてくるピアノの音
合格後校歌をさらう姉妹
好きな方へ伸びて行きますユキヤナギ
鈍行の老爺の大きな喉仏
春の日を透かして赤き猫の耳
春風や昼寝の猫のひげ光る
鴨去りし川辺の土の暖かさ
春の暮れ人は踊りて木となるか


四月上旬
美しき数式があり新年度
あれとこれ負の相関なり雪柳
夙川に家族四人の花筏
空中にありて蜜柑は老いにけり
川沿いの桜描く人並びいて
街灯が花を照らした道を行く
生返事カンコンカンコン明滅す
春風や干したるシャツのほの紅き
入学式三分前のベル響く
叢を白く変えたる落花かな


四月中旬
保護者らの拍手の長さ離任式
ナルニアのライオンにない臭いかな
ビッグバンドジャズで行く帰路電車
拳骨が転ぶ翁の身から出て
しがみつく花ちらほらと投票日
白墨の粉の香りや新学期
黒板を背負いてバラの静かなる
ぼんやりと開く弁当豆ご飯
ホトトギス鳴きつる方は高圧線
人が来て女児立ち上がる春の海


四月下旬
ふりむけばどすんとたこ焼き落ちており
春蝶のおのれを運ぶ重さかな
社交辞令重なる先の熱帯魚
迷路から化粧の匂いひとを吐く
病床に少女ら白く微笑める
人の中人ひた急ぐ背を曲げて
女高生指で書く文字輝けり
よく笑ふ雨天決行バスが行く
ヒキガエル客として見る授業かな
中空に浮かぶ淋しさここへ来い


五月上旬
飛び出した白桃赤のサツキかな
電柱の烏こっそり鵜を見てる
噴水に一人の女蹲る
快晴や白煙上げる煙突群
ランナーは通り過ぎたり遊撃手
すぐそこに傾いている飛行船
風光る空中静止フリスビー
初夏の風とまらんとする黒揚羽
帰路遙かきらと光りぬ夜の雨


五月中旬
もろもろのしつぽのとれてゐる立夏
小説の子を産む場面苺食ふ
キャンパスをそろそろと行く子猫かな
一塊の海の匂いや蛸を切る
雨粒の波紋をくぐる燕かな
麦秋を特急列車薙いで行き
起し絵の街をまっすぐ歩きけり
水に入る直線泡を連れている
埋め立て地午後三時半揚げ雲雀
葉の陰で黒ずんでいく桜んぼ
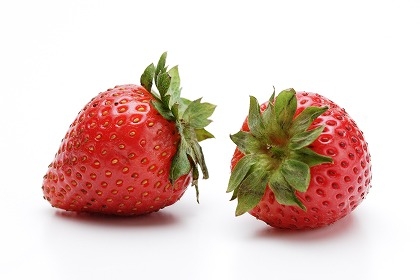

五月下旬
見飽きてもなおそこにある夜景かな
光堂つかみて離すいなびかり
ラグビーの試合終わりて揚げ雲雀
黒猫の兄弟の目みな薄緑
涼風の月下を満たす花水木
麦の秋実習生の顔の汗
葉と葉とがもみ合う夜の香りかな
子鼠が回す車の止まりがち
錆おいて伸びる線路や風光る
蝶墜ちてまだ人中に動くかな


六月上旬
青鷺が植え終わりたる田に映る
関東平野市松模様に麦の秋
青空に腕挙げてみる衣替え
緑陰を抜ける自転車白き風
吊革と聞いてる曲がシンクロす
蛇いちご木漏れ日を吸い赤くなる
着布団を替えて広がる夏の夢
大鯉のたましひ黒き泡となる
泡光る氷を入れた麦茶かな
堤防に逆立一人みなみかぜ


六月中旬
少年の肩にアカシヤ散りかかり
でで虫が薄薔薇色の殻負いて
石垣についと飛び込む親雀
紫陽花や実習生の手の動き
モンスーン山懐に雨の虎
刃向かいし大きな蜂を踏み潰す
階上より僅かに届く咳止まず
夏の雲同じ事務服同じ席
沖までの光は波を白く見せ
折り畳み開いて閉じて雨の街


六月下旬
子鼠の瞳に写る蛍光灯
かたつむりページをめくるたびに見る
木漏れ日は地中の蝉の夢の中
平日を修学旅行の列車過ぐ
ときをりは命小さく透きとほる
つま先を2センチあげて歩く梅雨
梅雨の午後眠るランゲルハンス島
すれ違う牛の睫の長さかな
初蝉や捕虫網がぴくと揺れ
プール開き光の中を昇る泡


七月上旬
子の寝相蛙の如し風涼し
冷蔵庫唯今の夏詰まりおり
骨模型明るき部屋で口開けて
向日葵が少し俯く夕べかな
蛤にうまれて白い風を受け
曇天に吸い込まれていくコンチキチン
クーラーが寝ても良いよと呟いて
それなりの勢いで飛ぶ水たまり
湯気の中卵カステラ降りしきる
薔薇一枝振り回している塾帰り



七月中旬
夜店の灯映して鈍き虫の
前期試験声なき「あ」がひろがりて
ベランダの蝉を雨中に投げてやる
ガラス窓をウスバカゲロウ染めており
丸虫の前でビーダマとまりけり
サイダーの泡のごと
濃き汗の
終業式子等の手にあり夏の雲
手花火が瞳の中で


七月下旬
夏の恋袋を掛けぬ林檎の木
雨を知る道を行く傘見下ろして
木漏れ日を上昇していく蝶一頭
垂れ下がる赤き鉄鎖の熱さかな
八月や娘が鳩を分けてゆく
生きるのが好きな女の夕かな
夏草や人形の顔だけのぞく
ヒマワリの畑に時折風の道
黒犬のごとき雨雲近づきぬ
自転車をこぐ炎天の風受けて


八月上旬
丑三つの街灯に沸く蝉の声
たまねぎの憂鬱すこしうすみどり
ざわめくは俯角八十度の花火かな
八方の小さき墓にも団子置き
山国の闇を十九は見あきたり
意志受けて白球強く跳ねていく
台風にミッキーマウス手を振って
十二支みな小声で言ひて夏祭
送り火の混雑予告地下の駅
腹痛の子と歯痛の子が夏休み

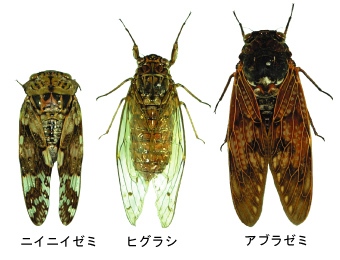
八月中旬
蝉の声何もしない日過ぎていく
提灯が赤き墓前の盆踊り
家々に話し声あり盆の村
船虫がざわめいている防波堤
合宿から帰った夜のカレーかな
手花火で手花火を燃す姉妹
油照り言葉少なき檻の猿
引き上げて一本の糸水中花
夏の朝あんパン一つ籠の中
板の間に電車残りし夏の宵


八月下旬
水球に世を写しおり苔の花
子どもより老女の多き地蔵盆
喪の家の水兵ひとり生きてをり
台風来ジャンプシュートに網揺れて
氷解けた上澄みを飲む冷コーヒー
行く夏や天井見つめる眠れぬ子
一瞬がちょっぴり解るしやぼん玉
自転車のペットボトルに夏少し
青空に銀行のある大都会
初サンマ骨だけにして自慢する


九月上旬
いつまでも恋の猫名はブラッキー
子供らが早く出ていく休暇明け
無花果を裂く病室の白さかな
雨粒を湯気に弾くや鬼瓦
こほろぎの子等の眸ひかる幸せか
両眼に念珠つめたくよこたはる
小さき葉が腰かけている波止の秋
浅き川持ちあげている鯔の群
ミーンミンミンと八回鳴いて一休み
ヤッケ着てサンバイザーする案山子かな


九月中旬
秋風が撫でる昼寝の土不蹈
雷が光るラピュタの如き雲
羅や奥の鈴虫皆哀し
帽子振る客は緑の浪の上
秋冷やフロントガラスの虫の跡
老犬の遅き歩みや天高し
葡萄の実色濃くどれにしようかな
雲燃えて優勝カップ差し上げる
天高し倒立練習続きたる
鯵刺しがあと三メートルで銛に成り


九月下旬
猫の眼の俯きがちや秋の暮れ
巣に誇る獲物の球や女郎蜘蛛
休日の図書館の庭落ち葉鳴る
高層から歩く人見る川柳忌
赤とんぼもう秋なのかと首傾げ
前日の白線薄きグラウンド
放課後の机の下に夕日差す
ドングリがぐりぐりぐりと手の外に
返却日過ぎている本天高し
三度目でできた人間ピラミッド


十月上旬
秋の陽を窓辺のコップ虹にして
喉の筋立てて大綱引いており
揺れている石榴は空に続きおり
少女等に撫でられている夜の猫
せせらぎの石に戻りし鳥の声
銀杏をタイヤが潰す帰り道
秋深し川面をすべる鷺の白
おーいおーいと声出してみる城の秋
秋雨を飲み干して木々赤くなり
鵜が羽を陽にあてている秋の川


十月中旬
水鳥の水の中にて日向ぼこ
参観日白粉花が群れており
鯔の子の黒き塊覗く鷺
外灯を浴びて吹き出す芒かな
来年のどんぐり小さく枝にあり
校門の裏の石榴は割れており
天高く少女鼓隊はピンク色
秋風やトスしたコイン芝の上
帰路電車いつもの席で文庫読む
やわらかな跳躍猫が逃げていく


十月下旬
翳り来るサンシュユの実の赤さかな
風吹いて光りが走る花薄
虫の声明るき校舎とりまいて
雄鹿に追われた家族に秋の風
空白の記憶の如し秋の雲
留鳥の二羽の航跡重なりて
小春日や白鳥のごと歩む人
秋の陽に仁王の乳首くっきりと
小鼠の揃えた手の甲薄桃色
鞦韆の頂点の足秋陽蹴る


十一月上旬
秋の暮れスパイダソリティアきりもなし
手を止めて四時間目の空秋の色
切り干しが光り吐き出す膳の上
黒猫の伸びする形秋深し
幸せは綺麗に張れた蜘蛛の糸
夕凪を縫い取っていく秋の鯔
ドアチャイム押す鼻先をおでんの香
小春日や松葉相撲の切りがなく
幼稚園の鯉悠々と投票日
悪玉が散るは美し曼珠沙華


十一月中旬
七五三下され物の紙風船
よき娘きて白い椿を通り過ぐ
夕陽うけ京都タワーが白さ増し
日を浴びる日光写真を待つ間
黒猫の瞳が光る椅子の下
雲が行く秋のパルケエスパーニャ
指先に木洩れ日赤く届きけり
勇気持ち本日をもち炬燵出す
胸像は秋の陽浴びて無風なり
久々にくんと呼ばれる同窓会


十一月下旬
いづかたも雲燃え終わり波静か
秋の暮吾が手に育つ二三の句
先を行く猫の裸足や秋の風
見物の人去ればまた落葉掃く
雨の午後じっくりじっくり大根炊く
冬の田の案山子静かに倒れおり
冬蜘蛛の命小さく燃えており
道端に少女の命隠れけり
我が影を追いかけてくる小竜巻
終列車前の座席の独り言


十二月上旬
ほの白しライトアップの先の空
ドア開いて七番線の寒さなり
買ってきた年賀葉書の白さかな
若鹿が覗く魔界の水たまり
業終へて夜霧の中を降りていく
冬月の光が包む小学校
廃品回収表紙のとれた俳誌あり
水母より忽ち君を見に出づる
冬電車瞼で受ける日の光
青空に柿の木柿を差し上げる


十二月中旬
図書館で子どもの声が遠ざかる
落椿ふみて
冬天のあちこちにある来世かな
石枕新聞全紙昼餉時
重ね着を静かに開く
六甲は雪を
寒烏電信柱に一羽ずつ
先端の小さな
裏山の我一人知る


十二月下旬
BB弾枯葉の陰で光りおり
年の暮れすべてのレジが音立てて
魂に魂五六個詰めておき
冬の道命小さくついてくる
冬の陽の声が聞こえる糸電話
夜の闇にはなやいでゐる寒さかな
満月を望む岬で鵜に変わる
老婦人レンズの奥に冬眠す
しやぼん玉冬の獣を
あかあかと胸の谷間が光りをり

