| ここでは、熱の研究に貢献した人々について簡単に説明しましょう。 |
|---|
| ガリレオ・ガリレイ | アモントン | ||
| ファーレンハイト | セルシウス | ||
| ケルヴィン | ジョセフ・ブラック | ||
| ボイル | シャルル | ||
| ラヴォアジェ | ラムフォード |
ちょこっとメモ ラヴォアジェとラムフォード
ガリレオ・ガリレイ(1564-1642)
 ガリレオはイタリア北部のピザで音楽教師の長男として生まれました。物理学や天文学の分野で多
くの発見や発明をした彼は、「近代科学の父」といわれています。彼は温度計、望遠鏡、偽(にせ
金発見器など、多くの機器を開発しました。
ガリレオはイタリア北部のピザで音楽教師の長男として生まれました。物理学や天文学の分野で多
くの発見や発明をした彼は、「近代科学の父」といわれています。彼は温度計、望遠鏡、偽(にせ
金発見器など、多くの機器を開発しました。その他、彼は地動説を唱えたことでも有名な人物です。1583年,彼は寺院のランプが振れる のを見て振子の等時性を発見しました。 1609年に真空では重さに関係なく、落ちる速さは、同じであるという法則落体の法則を発見 しました。コペルニクスの地動説を支持したガリレオは裁判によって活動をおさえられたが新し い科学をうちたてました。そして、1642年に亡くなりました。 その年、イギリスで万有引力の法則によって地動説を理論的に裏づけたニュ-トンが生まれました。 |
|---|
アモントン(1663-1705)
|
彼は、ガリレオが作った空気温度計を改良した。ガリレオは水を使って温度計を作ったのに対して、アモントンは細い水銀柱を用いることにした。 また、彼は作った温度計をどんどん冷やしていくことで内部の空気の圧力が低下していくことに気づいた。そして、圧力が零になる温度があるのではないかと考えた。いわゆる絶対零度の存在を推定したのです。 |
|---|
ファーレンハイト(1686-1736)
|
1686年ダンチッヒに生まれた彼は商人としてオランダに行った。そこは昔から学術用のガラス器具を製作する技術が栄えていたところで、彼はその技術を身につけて、気象学器械の製作を仕事としていた。 気圧計の水銀柱の高さが温度に左右されていることを知っていた彼は、水銀を温度計に利用した。そして、作った温度計に、「水と氷と塩化アンモニウムの混合物からえられる、もっともきびしい寒冷」の温度を0度、氷の融解点を32度、人の体温を96度とする目盛りをつけた。この目盛りが華氏目盛(°F)である。 また彼は、水の沸騰点をその温度計で212度と測りましたが、大気の重さが変化すれば、沸騰点も上下することを認めていました。(気圧が変われば、沸点も変わることに関する実験を、熱の実験コーナーでやっています。見たい時はここをクリック) |
|---|
セルシウス(1701-1744)
|
私たちが普段目にする摂氏温度(℃)は、このセルシウスさんが導入しました。 彼は、1701年、天文学教授の子どもとして生まれ、数学、実験物理学、天文学を学びました。1730年には、父の後を継いで天文学教授になりました。 1742年、彼は、作った温度計をとけかけの雪の中に入れたときの水銀の高さと沸騰しているお湯に入れたときの水銀の高さに印をつけ、その間の距離を100等分する温度目盛を考えました。最初、氷点を100度、沸点を0度としていましたが、後に1気圧下の水の氷点を0度、沸点を100度に改められた。 |
|---|
ケルヴィン(1824-1907)
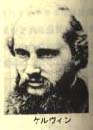 イギリスの物理学者である彼は、北アイルランドで大学の工学教授の子どもとして生まれた。10歳でグラスゴー大学に入学した。15歳のときのヨーロッパ大陸旅行で熱伝導論や天体力学などを学んだ。ケンブッリジ大学で教育を受けたり、パリ留学などを経験した後グラスゴーに戻る。グラスゴーに戻った彼は1846年からグラスゴー大学の自然哲学教授となり、1904年には同大学の学長になった。
イギリスの物理学者である彼は、北アイルランドで大学の工学教授の子どもとして生まれた。10歳でグラスゴー大学に入学した。15歳のときのヨーロッパ大陸旅行で熱伝導論や天体力学などを学んだ。ケンブッリジ大学で教育を受けたり、パリ留学などを経験した後グラスゴーに戻る。グラスゴーに戻った彼は1846年からグラスゴー大学の自然哲学教授となり、1904年には同大学の学長になった。 |
|---|
華氏と摂氏
| 華氏と摂氏の表現はそれぞれ、ファーレンハイトの中国語表記である華倫海と、セルシウスの中国語表記である摂爾修に由来している。 |
|---|
ジョセフ・ブラック(1728-1799)
 石灰石を強く熱し、発生する気体を調べ二酸化炭素を独立した1つの物質と認めた。研究を行うとき、重量の変化を測定し、化学変化を定量的に扱う方法を開発した。熱現象に関心を持ち、氷を溶かすのに大量の熱が必要で、解けても温度が変わらないことから氷の融解熱を測定し潜熱の考えを実験的に確立した(1761)。また水蒸気の潜熱のおおよそを測定した(1767)。
石灰石を強く熱し、発生する気体を調べ二酸化炭素を独立した1つの物質と認めた。研究を行うとき、重量の変化を測定し、化学変化を定量的に扱う方法を開発した。熱現象に関心を持ち、氷を溶かすのに大量の熱が必要で、解けても温度が変わらないことから氷の融解熱を測定し潜熱の考えを実験的に確立した(1761)。また水蒸気の潜熱のおおよそを測定した(1767)。また、熱学上の研究を講義の形で発表しワットに大きな影響を与えた。 その他、熱平衡の研究から温度と熱の区別を明確にし、潜熱の存在を説明した。氷熱量計を作り(1762)、熱量、熱容量、比熱を定義した。 熱の物質説に立っていたが熱量の保存を認めていた。 |
|---|
ボイル(1627-1691)
 イギリスの物理学者、化学者である彼は、1627年、裕福な貴族の子どもとして生まれました。ジュネーブ、フィレンツェで学び、しだいに化学に興味を抱いた彼は、1656年からオックスフォードで科学者集団に加わり、1668年ロンドンに定住しました。熱の研究のみならず、光や音に関しても研究し、1691年に亡くなりました。
イギリスの物理学者、化学者である彼は、1627年、裕福な貴族の子どもとして生まれました。ジュネーブ、フィレンツェで学び、しだいに化学に興味を抱いた彼は、1656年からオックスフォードで科学者集団に加わり、1668年ロンドンに定住しました。熱の研究のみならず、光や音に関しても研究し、1691年に亡くなりました。1660年に「容器に閉じ込められた気体の圧力は一定の温度の下で体積に反比例する。」というボイルの法則を発見しました。 |
|---|
シャルル(1746-1823)
|
フランスの実験物理学者。生い立ちや家系は不詳である。若い頃パリに行き、役場に勤めるものの、緊縮政策で職を失い、実験物理学を学び始める。驚くことに、わずか18ヶ月の学習だけで公開講座を開設。しゃべりの上手さと説明実験の上手さで多くの人々を魅了した。 この頃(フランス革命前)のパリでは、気球の研究が盛んだった。彼も水素気球の実験を行い、1783年夏には無人飛行を、その年の冬には有人飛行を成功させた。この実験を通して、1787年に彼は「圧力が一定なら気体の熱膨張は気体の種類によらず温度上昇に比例する。」というシャルルの法則を見いだした。 |
|---|
ラヴォアジェ(1743-1794)
 彼はフランス・パリで生まれました。幼いころ母を失い、叔母のもとで成長し、法科大学を卒業しましたが、気象・天文などに熱中していきました。
彼はフランス・パリで生まれました。幼いころ母を失い、叔母のもとで成長し、法科大学を卒業しましたが、気象・天文などに熱中していきました。彼は金属など燃焼することで質量が増大することを知り、燃焼は酸素との結合であり、燃素などというものは存在しないことを明らかにして、今まで燃焼は燃素(フロギストン)が抜け出すことであるとされていた燃素説を否定しました。 また、彼は元素とみなせる物質を33種挙げて元素表を作りました。その中には熱素もあり、熱素説の先駆けとなりました。 |
|---|
ラムフォード(1753-1814)
 1753年北アメリカ生まれの応用物理学者。生地マサチューセッツ州ウォンバーンでは正規の学校教育は受けなかった。独立戦争の時にイギリス側について、1776年アメリカからイギリスへ亡命しました。彼はイギリスで火薬や火器の研究をし、ミュンヘンで軍需工場を起こしました。1793年神聖ローマ帝国の伯爵位を受けて、ラムフォード伯と名乗りました。1800年ロンドンに王立研究所を創設しました。1814年パリで亡くなりました。
1753年北アメリカ生まれの応用物理学者。生地マサチューセッツ州ウォンバーンでは正規の学校教育は受けなかった。独立戦争の時にイギリス側について、1776年アメリカからイギリスへ亡命しました。彼はイギリスで火薬や火器の研究をし、ミュンヘンで軍需工場を起こしました。1793年神聖ローマ帝国の伯爵位を受けて、ラムフォード伯と名乗りました。1800年ロンドンに王立研究所を創設しました。1814年パリで亡くなりました。彼は火薬研究のとき、弾を込めずに発砲すると、弾を込めたときより砲身がずっと熱くなるのに気付き、「火薬は弾丸の代わりに砲身の金属粒子に激しい運動を与えたのではないか。」と考え、熱が生じる原因は今まで熱素の移動であると考えられていたが、本当は運動によるのではないかと考えるようになった。ミュンヘンの工場では、大砲の中ぐり作業中に大量に熱が発生するのに気付き、中ぐり装置全体を水中に入れ、作業中にどれだけ熱が発生するのかを測った。すると熱は装置を動かしつづける限り出てくるように思われて、その熱は熱素という物質であるならどこからきているのかと考えるようになった。化学変化も他の熱の供給もないから、熱発生の原因は運動しかないと考えるようになり、熱の運動説を深めていった。 |
|---|
ラヴォアジェとラムフォード
| 熱素説の先駆けとなったラヴォアジェと、その熱素説を否定して熱の運動説を見いだしたラムフォード。この二人は私生活においても因縁深いようである。ラヴォアジェがフランス革命で処刑された後、ラヴォアジェ未亡人はなんとラムフォードの奥さんになるのです。4年後には離婚するのですが、時代の流れを感じさせるエピソードです。 |
|---|
|
《参考文献》 『歴史をたどる物理学』 我孫子誠也著 【東京教学社】 『新訳 ダンネマン大自然科学史6』 安田徳太郎訳・編 【三省堂】 『新訳 ダンネマン大自然科学史7』 安田徳太郎訳・編 【三省堂】 『物理学辞典 改訂版』 物理学辞典編集委員会編 【培風館】 |
|---|
