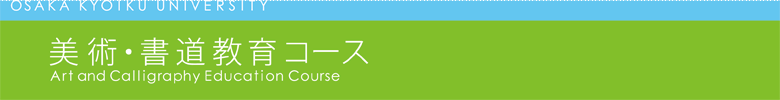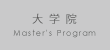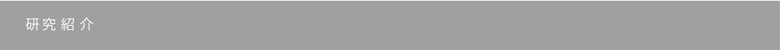令和3年度
| 学生氏名 | 修士論文題目 |
| 吉田 弥生 | 「保育」における「遊び」の重要性と保育者によるこどもへの共感的かかわりについて |
令和2年度
| 学生氏名 | 修士論文題目 |
| 井上 盛太朗 | 色覚多様性に配慮した図画工作題材の提案-色を扱う題材について- |
令和元年度
| 学生氏名 | 修士論文題目 |
| 梅山 菜帆 | 遊びの空間としての図画工作の授業の再評価 |
| 香月 欣浩 | 支援者の態度が造形表現に与える影響 |
| 中村 幹史 | 粘土や土の特性を活かした絵画表現についての研究 |
| 樊 穎 | ロリータファッションに関する一考察 |
| 平井 里奈 | 陶芸の掻き落とし技法を用いた作品制作の変遷 |
| 平松 範子 | つくる視点から捉えた「しかけ絵本」の研究〜題材展開への考察〜 |
| 向井 優馬 | 二人称の美術制作論ー美術家と作品の関係性を探るー |
平成30年度
| 学生氏名 | 修士論文題目 |
| 荒西 伸吾 | 「線の集積による絵画」についての考察 |
| 汪 夢瑤 | 小学校図画工作科における絵本を用いた鑑賞授業に実践に関する研究ー美的経験の認知発達論にもとづく絵本の分類と,日本,中国,台湾での授業実践からー |
| 高瀬 麻佑 | 造形活動の題材における「飾る」ことの創造的意味についての一考察 |
| 張 銀迪 | 絵本の制作体験についての考察ー参加型空間絵本の制作を通してー |
平成29年度
| 学生氏名 | 修士論文題目 |
| 岡本 悠里 | 紙を素材とした作品制作研究ー<方法>を繰り返す制作の視点と課題ー |
| 清家 颯 | 意味生成の行為としての造形行為の研究ー「造形の思考」「造形の意志」の働きに着目してー |
| 谷口 愛実 | 法楽寺所蔵不動明王二童子像について |
| 丁 超 | 集団で行う造形活動の指導方法についての一考察ー「全員の行為を生かす絵画」の実践からー |
| 中村 朋子 | 現代におけるキャラクターの研究―キャラクターの自律と社会的役割を考えるー |
平成28年度
| 学生氏名 | 修士論文題目 |
| 岡本 弘美 | 近代デザインの課題と思考力を養うデザイン教育〜デザインの社会的責任の再考と中学校におけるデザイン思考教育の実践を通して〜 |
| 藤原 まい | ストップモーション・アニメーションを用いた映像表現に関する考察 |
平成27年度
| 学生氏名 | 修士論文題目 |
| 新井 馨 | 「美術」の構造とアール・ブリュット概念の再考ー美術教育の「美術」を考えるためにー |
| 太田 菜津子 | 藤原俊成の私家集書写活動について―伝西行筆「中務集」を中心にー |
| 下井 めぐみ | 自ら考える書写教育ー知識構成型ジグゾー法を用いてー |
| 田中 温子 | 自己肯定感を育む美術科授業の一考察 |
| 羽田 智美 | 図画工作科における「工作に表す活動」の課題の考察と映像教材の提案 |
| 松下 昇平 | 「共通感覚」と「感覚の統合」ー美術教育研究における「感覚」の解釈についての一考察ー |
| 和泉 采花 | 特別な支援が必要な生徒に対する書教育ー自己肯定感を高めるためにー |
| カク 爽 | 陶芸における色彩を用いた「顔」の表現研究ー陶芸表現における顔のメイクアップー |
| 川西 莉夏子 | 箱を用いた題材の美術教育における意義をさぐる〜自他との橋渡しの役割を持つ物としての箱の意味〜 |
| 櫻井 佑美 | 和歌懐紙の書式にみられる性差についてー平安時代における唐と和の役割の違いからー |
| 天花寺 弘隼 | 陶芸における「影」の研究及びその作品制作ー影を再認識する表現の試みー |
| 西尾 明奈 | ペンで描くことの意味 植物をモチーフとした制作の考察から |
| 三木 千代 | 絵画表現における「にじみ」についての一考察 |
| 山本 翔真 | 絵画制作における素材と造形行為の関係についての一考察ー子どもの絵画制作における「主題」を探るための試みとしてー |
平成26年度
| 学生氏名 | 修士論文題目 |
| 趙 倩 | 日中の吉祥文様に見られる同異と応用についての考察 |
| 福壽 亮太 | 黄庭堅の書法に関する一考察―草書作品の書法の特質についてー |
| 小山 茉莉 | サウンドスケープとサウンドマップの研究;サウンドマップづくりのためのフィールドワークとフィールドノートの提案 |
平成25年度
| 学生氏名 | 修士論文題目 |
| 岸本 直子 | 小学校中学年を対象とした対話の充実を図る美術鑑賞指導についての一考察 |
| 北村 由里子 | 舞踏表現と美術表現 −身体と表現のあいだにあるもの− |
| 杉本 千明 | 八大山人の書法についての一考察 |
| 大長 めぐみ | 写生についての一考察 −描く人と描かれるものとの関係に着目して− |
| 武市 香奈子 | 陶芸制作における造形思考の考察 −「粘土・顔料・釉薬」の重なりから生まれる造形表現の展開− |
| 松尾 勇哉 | 映像メディアを用いた美術教育実践についての一考察 −映像と音を関連させる映像編集技術の指導に着目して− |
| 森治 健太 | 顔を描く −線の表現の観点から− |
| 城野 知佐 | 図画工作科における子どもの学びと教師のまなざしについての一考察 |
| 田中 麻美 | いわさきちひろの世界観について 〜子どもとの関わりを通して〜 |
平成24年度
| 学生氏名 | 修士論文題目 |
| 大久保 成 | タイポグラフィ・デザインの研究とデザイン制作 −主に中学校美術科での副読本的活用を想定したアートブックの提案− |
| 高稲 悠 | 美術と数学の相互関係 −シンメトリーにおける一考察− |
| 中屋 萌梨 | 中学校美術科の教科書に掲載された生徒作品の分析 〜写実性に着目して〜 |
| 路 飛 | 美術とジェンダー −ジェンダーの視点から見る「源氏物語絵巻」− |
平成23年度
| 学生氏名 | 修士論文題目 |
| 乾 圭恵 | 美術教育における支援と評価に関する一考察 −造形活動における「学び」の生成に着目して− |
| 今津 道恵 | 陶芸制作における造形思考の変化 −私自身の素材感の変化を踏まえた作品制作− |
| 漆原 良美 | 子どもの造形行為の非分化性に関する一考察 −子どもの造形行為の円環構造と、学習指導要領の内容の検討から− |
| 田中 文子 | 「かわいい」イラストレーション表現の探求 |
| 根来 孝明 | 良寛の書法に関する一考察 |
| 林 知美 | ヘレン・フランケンサーラーの木版画制作における思考過程の一考察 −日本との関わりに着目して− |
| 松野 真知子 | ジョージア・オキーフの花シリーズについての一考察 −濃淡による画面構成を中心に− |
| 峯本 さおり | 図画工作科における共感的支援 |
| 渡邊 優香 | 透明についての一考察 〜ダニエル・ビュレンヌの作品をめぐって〜 |
| 藤岡 優太 | 自画像に関する一考察 −自分の姿かたちにこめる制作者の想いや表現の工夫について− |
平成22年度
| 学生氏名 | 修士論文題目 |
| 勝木 恵莉 | 美術館での鑑賞をより豊かにする鑑賞ツールの研究 〜鑑賞の行為を促すデザインを考慮した新しいセルフガイドの提案〜 |
| 河本 実久 | 書鑑賞導入法の一考察 |
| 島谷 絵理 | 「寸松庵色紙」に学ぶ作品制作 −『源氏物語』を手がかりに− |
| 張 洪涛 | 絵画制作における制作者の観察と描き方の結び付きについての一考察 −写実の解釈とその変遷に着目して− |
| 富川 展行 | 平安時代における「散らし書き」誕生についての一考察 −寸松庵色紙にみられる「上下(左右)分割式」の構成法をめぐって− |
| 長嶋 祥平 | 映像制作におけるリズムの扱いについての一考察 −エイゼンシュタインの理論を手掛かりに− |
| 中村 香央里 | 芸術科「書道」における書の学習についての一考察 −黄庭堅の書を基にして− |
| 前田 有紀子 | 取り組みやすさと発想の広がりを意図した描画方法の研究 −制作、ワークショップの実践、およびクロード・ヴィアラの作品分析を通した<かたち>を<反復>する描画方法の考察− |
| 李 淑君 | ディック・ブルーナの線を取り入れた中国画の変化 −親しみやすさを求めて− |
平成21年度
| 学生氏名 | 修士論文題目 |
| 入口 卓也 | 粘土の素材研究における意識変化の考察 |
| 木戸 千紗子 | 日比野五鳳の古典観 −日比野五鳳の言葉から読み解く古筆の重要性− |
| 小林 佳代 | 造形基礎理論構築のための分析方法についての一考察 −近代デザイン理論の再考察を通して− |
| 篠原 祐 | 絵画を「つくる」行為に関する一考察 |
| 神保 悠 | 図画工作科的「生きる力」を育むために必要な授業方法論についての一考察〜<選択する行為>を起点とし展開する授業モデルの提案〜 |
| 竹内 太平 | 現代美術における作品認識と判断についての一考察 〜感性による作品判断について〜 |
| 張 林 | 平面デザインにおける漢字を用いた表現についての考察 −漢字のもつ生命力を生かす表現− |
| 土居 由布子 | 陶芸制作における造形思考の考察 −制作プロセスと「粘土の薄さ」「粘土の表面」から生まれる形− |
| 古田 雄貴 | 青白磁についての考察 −青白磁釉を用いた大皿の制作− |
| 溝口 俊太郎 | 中等美術教育における表現と「抵抗感」についての一考察 −「内なる他者」の発見を通して− |
| 森岡 輝次 | 美術教育の場面に必要な「痕跡として見る視点」の一考察 −絵画作品の鑑賞と制作について− |