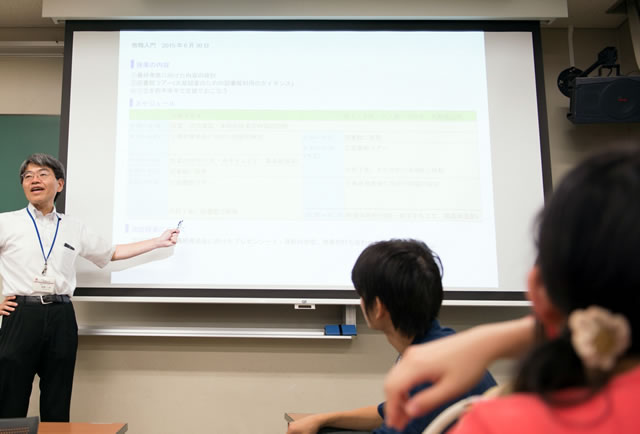著作情報(撮影:後神勇樹)
著作情報(撮影:後神勇樹)
卒論作成過程にあたっては、指導教員から研究方法や論文内容についての定期的な指導が得られると同時に、中間発表会の実施などで多くの教員の助言を得られるような支援体制がつくられています。4回生は原書講読やフィールドワークなど、自らが定めた方法での調査を積極的に行っています(卒業論文の指導教員の選択では、学生の希望が最大限尊重されます)。
2023年度
- 個別化・個性化カリキュラムにおける評価と調整 ―愛知県東浦町立緒川小学校の実践を手がかりに―
- 学び続ける教師像についての一考察 ―中教審答申等を手掛かりとして―
- 「対話的な学び」を実現する授業づくり ―こども哲学の実践分析を通して―
- 自閉スペクトラム症の子どもの得意を生かした通常学級の授業づくり ―赤木和重の理論を手がかりに―
- 自己肯定感を高めていくための自己評価の方法 ―自閉スペクトラム症の子どもに焦点を当てて―
- ポスト・コロナにおける子どもたちの人間関係を形成する特別活動の実践方法 ―コロナ禍前とコロナ禍の特別活動の実践比較を手がかりに―
- 小学校教育における発達障害のある子どもへの合理的配慮 ―当事者研究を手がかりに―
- 資質・能力ベースの時代に求められる基礎学力の形成 ―岸本裕史における「読み書き計算」の習熟を手がかりに―
- 生活現実に即した授業における教材研究の視点 ―すべての子どもたちが能動的に学ぶ授業を目指して―
- 学習障害のある子どもへの支援方法のあり方 ―窪島務の「教えない」指導を手がかりに―
- 日本社会におけるマスク文化についての考察 ―新型コロナウイルス感染症を経て―
- すべての子どもの学びを保障する授業の構造 ―愛知県東浦町立緒川小学校の個性化教育を手がかりに―
- 「自ら学ぶ」子どもを育む授業づくり ―「学び方」学習における「学習の行為化」を手がかりにして―
- 安彦忠彦の自己評価論 ―内村鑑三の修養と比較して―
- 教育委員会が行う教員養成事業の今日的な在り方 ―東京教師養成塾と奈良県次世代教員養成塾を手がかりとして―
- 教育愛に関する一考察 ―教師と子どもの友愛的かかわりに焦点を合わせて―
- 私立学校における建学の精神の実際的機能 ―百合学院中学高等学校を支えてきた教師による語りからの考察―
- 個別最適な学びの実現に向けた授業づくり ―学びのユニバーサルデザインを手がかりに―
- 分離教育からインクルーシブ教育への移行に関する検討 ―「共に学ぶ集団づくり」の視点から捉える交流及び共同学習―
2022年度
- 学びの意味の発見を導く教育方法に関する研究 ―宿題と授業の関連に着目して―
- いじめの認知についての一考察 ―「大津市中2いじめ自殺事件」を手がかりにして―
- ICT教育時代に求められる教師の指導のあり方 ―大村はまの「教えるということ」を手がかりに―
- 小学校の通常学級における発達障害のある子どもの学力保障 ―湯浅恭正のインクルーシブ授業論の検討を通して―
- 学校教育における自己肯定感の研究 ―「存在理解」の「自己肯定感」について―
- 批判的リテラシーを形成する授業づくり ―パウロ・フレイレの教育思想を手がかりに―
- インクルーシブ教育を目指す社会の現状と課題 ―障がい者のセクシュアリティの認識に着目して―
- セクシュアル・マイノリティの生徒の視点から見た校則の改善を目指す教師の働きかけ ―高等学校を中心に―
- 発達障害児に求められる個別の指導計画・個別の教育支援計画の作成と活用 ―アメリカの個別教育計画(IEP)を手がかりに―
- 差異を理解しあえる集団づくりに関する一考察 ―「文化的に応答性のある教育」を手がかりに―
- 学級集団づくりにおける規律 ―ケアと子どもの居場所づくりを手がかりとして―
- 男女間の理工系進学格差に関する考察 ―格差の実態とそれをもたらす要因の分析―
- 民主主義社会を実現するための公教育の在り方について ―デューイを手がかりに―
- 日本におけるイエナプラン教育の可能性 ―子どもの幸福度から見て―
- 学級づくりにおける受容的な場の形成 ―宮坂哲文の教科外活動の構想を手がかりとして―
2021年度
- 日本の教員養成制度の課題に関する一考察 ―開放制教員養成制度に着目して―
- 授業づくりの型と教師の指導性との関係 ―発問に焦点をあてて―
- 教育の専門家と法の専門家の連携の意義と在り方 ―学校の法化現象の観点から―
- 子どもの食育における担い手の検討 ―学校と子ども食堂の「食育力」と課題に着目して―
- 特別支援学校高等部における発達障害児のキャリア教育に関する研究 ―浦河べてるの家の当事者研究を手がかりに―
- 外国にルーツのある幼児を支援する保育環境の在り方 ―日本と外国のしつけや子育て観の違いに着目して―
- 政治的リテラシーを育むための政治的中立性の在り方に関する一考察 ―政治的中立の方針を国が示しているイングランドとの比較検討を通して―
- 就学義務制度における不登校支援の教育の質の確保の課題 ―デンマークの教育義務制度を手がかりに―
- 食品ロスと食料不足の併発を無くす方法に関する一考察 ―消費者ニーズと購買行動の観点から―
- SNSの普及と多様化が教育に及ぼす影響について
- 教育における競争に関する一考察 ―学校における「序列化」と「画一化」の視点からの分析―
- 「笑い」を学校教育に取り入れる意義と方法 ―対人関係を円滑にするための「笑い」の観点から―
- 小学校における主権者教育のあり方の検討 ―ドイツの「政治教育」の事例を手がかりに―
- 授業における視覚的支援の新たな方法に関する一考察 ―マンガの技法である「コマ割り」「吹き出し」「つかみ」に着目して―
- 教育政策文書における曖昧性と恣意性に関する一考察 ―中央[臨時]教育審議会答申の文言に着目して―
- 子ども主体の授業における教師の力量 ―M教師の国語科の授業分析と聞き取り調査に基づいて―
- 「オタク」の変遷に関する言説研究 ―消費者行動の観点から―
2020年度
- 高等学校における居場所づくりの視点と方法
- 主体性をもった子どもを育成するための検討-今泉博の授業論をてがかりに-
- 「真正の学習」を通した非認知的能力の形成
- 体罰を用いない指導を身につける教師教育の在り方
- ストレスのない幼児期の子育て環境-フィンランドに移住した日本人の親の考え方の変化に着目して-
- 非行・問題行動が見られる子どもへの指導に関する研究-少年院での矯正教育を手がかりに-
- 「真正な学び」の構造と授業づくりの視点
- 子どもの意見表明権を保障する子ども参加の在り方-メアリー・ジョンの「参加の橋づくり」モデルを中心に-
- 学校と家庭における「学び」の接続に関する一考察-小学校におけるICTを用いた反転授業の導入に着目して-
- 「つながり格差」を乗り越える教育実践に関する研究
- 教師が用いる非言語的指導の種類と役割-小学校教諭の事例に基づく非言語的指導に込められた期待の観点から-
- 「ブラック校則」の再検討-「他律」と「自律」の視点からの分析-
- なぜ人は学ぶのか-生涯学習から考える学びの在り方-
- 現代の学校教育における死の授業のあり方について
- 日本におけるEBEの構造に関する検討-日本のPDCAサイクルとのつながりを手掛かりに-
- 授業における批判的リテラシーの形成-P.フレイレの「意識化」と「対話」を手がかりに-
- 教師と子どもの信頼関係に関する研究-「他者」としての教師の在り方に着目して-
- 個人的運動領域における学習集団の指導に関する研究-個人思考と集団思考に着目して-
- 人工妊娠中絶に対する日本とベトナムの意識の違い-妊娠・出産に関する権利の主体性と性教育の観点から-
- 教員の職務負担感の軽減につながる同僚性の検討-現職教員に対する聞き取り調査に基づいて-
- 「自由」と「規律」を併せ持つ人格形成のあり方に関する研究
- 若者の生きづらさの社会学-高野悦子と現代の若者に着目して-
- オンライン授業の導入による教育観のゆらぎ-対面授業を前提とした教育の捉えなおし-